![]()
北海道:五稜郭、松前城、舘城、花沢館、勝山館、松前大館、茂別館、松前藩戸切地陣屋、四稜郭、志苔館、白老陣屋、シベチャリチャシ、浜益毛陣屋、鶴ヶ岱チャランケチャシ、モシリヤチャシ、チャルコロミオチャシ、根室半島チャシ跡群(オンネモトチャシ)、エクエピラチャシ、桂ケ岡チャシ
東北:弘前城、根城、久保田城、盛岡城、角野館、多賀城、仙台城、二本松城、会津若松城、白河小峰城、山形城、米沢城、三春城、白石城、童城、寒河江城、畑谷城、長谷堂城、上山城、中山城、館山城、延沢城、小国城、新庄城、鮭延城、清水城、尻八館、中里城、福島城、唐川城、種里城、深浦城、田城・出羽柵、湊城、脇本城、檜山城、十狐城、大湯館、小枝指館、石鳥谷館、大里館、松山城、新田目城、平形舘、尾浦城、丸岡城、小国城、二子城、岩谷堂城、柳の御所、大槌城、鍋倉城、土沢城、花巻城、豊島館、山根館、西馬音内城、八口内城、稲庭城、横手城、大森城、本堂城、角館城、岩切城、若林城、川崎城、船岡城、角田城、金山城、亘理城、小浜城、桑拙西山城、梁川城、黒木城、中村城、駒ヶ嶺城、小高城、平城、須賀川城、長沼城、七尾城、寺池城、佐沼城、岩ケ崎城、岩手山城、宮崎城、名生城、涌谷城、九戸城、一戸城、姉帯城、浄法寺城、昼沢城、高水寺城、安部館、雫石城、座主城、猪苗代城、神指城、向羽黒山城、鴨山城、久川城、棚倉城、赤館城、七戸城、芦名沢館、八戸城、三戸城、堀越城、大光寺城、黒石陣屋、大浦城、湯口茶臼館、浪岡城
関東:水戸城、佐倉城、江戸城、川越城、小田原城、八王子城、足利氏城、金山城、鉢形城、箕輪城、品川台場、白金長者屋敷、世田谷城、深大寺城、沢山城、小野路城、片倉城、初沢城、松竹城、高月城、滝山城、平塚城、稲付城、志村城、赤塚城、石神井城、勝沼城、戸倉城、檜原城、那珂西城、石神城、太田城、助川海防城、龍子山城、笠間城、宍戸城、難台山城、真壁城、小幡城、赤山城、岩槻城、伊奈氏陣屋、足利政氏館、源経基館、松山城、大築城、河越氏館、難波田城、山口城、衣笠城、新井城、鎌倉城、玉縄城、大庭城、深見城、桝形山城、茅ヶ崎城、小机城、神奈川台場、関宿城、臼井城、師戸城、本佐倉城、飯高城、坂田城、御茶屋御殿、小弓城、千葉城、高崎城、倉賀野城、平井城、根小屋城、国峯城、松井田城、安中城、前橋城、大胡城、山上城、桐生城、佐野城、唐沢山城、皆川城、多気城、石那田城、宇都宮城、飛山城、児山城、祇園城、鷲城、佐貫城、館山城、稲村城、勝浦城、万喜城、大多喜城、久留里城、真里谷城、土生城、大椎城、国府台城、菅谷城、小倉城、杉山城、山田城、忍城、深谷城、花園城、天神山城、千馬山城、守谷城、牛久城、木原城、島崎城、鹿島城、土浦城、小田城、久下田城、結城城、古河城、荻野山中藩陣屋、小沢城、津久井城、岡崎城、今井陣場、石垣山城、土肥城、鷹ノ巣城、足柄城、河村城、小泉城、館林城、白井城、岩櫃城、長井坂城、沼田城、名胡桃城、宮野城、西明城、茂木城、村上城、烏山城、那須神田城、武茂城、黒羽城、芦野城、大田原城、御前原城
甲信越:新発田城、村上城、鶴ヶ岡城、松代城、小諸城、上田城、松本城、甲府城、高遠城、高田城、春日山城、湯村山城、白山城、新府城、若神子城、獅子吼城、旭山砦、深草城、谷戸城真、篠城、大島城、飯田城、松尾城、鈴岡城、妻籠城、高島城、桑原城、上原城、根知城、勝山城、上杉城、鮫ケ尾城、直峰城、箕冠城、荒戸城、樺沢城、坂戸城、勝山城、躑躅ヶ崎館、要害城、於曾屋敷、連方屋敷、勝沼氏館、岩殿城、駒宮城、谷村陣屋、御坂城、金山城、鳥坂城、江上城、平林城、大葉沢城、津川城、本与板城、与板城、長岡城、栖吉城、栃尾城、下倉山城、大井田城、福島城、柿崎城、北条城、井上城、飯山城、霞城、鷲尾城、葛尾城、戸石城、真田館、平賀城、龍岡城、葛山城、旭山城、牧之島城、木舟城、青柳城、平瀬城、林城、桐原城、山家城、埴原城
北陸:七尾城、高岡城、富山城、金沢城、丸岡城、一乗谷城、福井城、越前大野城、小浜城、後瀬山城、国吉城、敦賀城、金ヶ崎城、玄蕃尾城、杣山城、府中城、小丸城、東郷槇山城、勝山城、丸岡藩砲台跡、朝倉山城、黒丸城、北庄城、宮崎城、魚津城、松倉城、弓庄城、猿倉城、安田城、白鳥城、穴水城、小丸山城、石動山城、末森城、津幡城、朝日山城、松根城、鷹巣城、高尾城、守山城、阿尾城、森寺城、木舟城、一条寺城、瑞泉寺城、増山城、大聖寺城、波佐谷城、御幸塚城、小松城、和田山城、岩倉城、二曲城、鳥越城、舟岡城、高尾城
東海:岐阜城、名古屋城、犬山城、岡崎城、岩村城、掛川城、駿府城、大垣城、吉田城、郡上八幡城、高山城、長篠城、武田氏館、山中城、小牧山城、楽田城、清洲城、勝幡城、小幡城、那古野城、末森城、岩崎城、沓掛城、鳴海城、丸根砦、大高城、刈谷城、西尾城、桜井城、安祥城、苗木城、明智城、小里城山城、妻木城、長山明智城、金山城、小倉山城、大桑城、三岳城、二俣城、高根城、久野城、横須賀城、高天神城、諏訪原城、小山城、丸子城、久能山城、赤木城、五ヶ所城、波切城、鳥羽城、田丸城、大河内城、阿坂城、高須城、墨俣城、革手城、加納城、鷺山城、北方城、曽根城、揖斐城、菩提山城、竹中氏陣屋、西高木家陣屋、深沢城、葛山城、山中城、興国寺城、沼津城、韮山城、長浜城、下田城、田原城、野田城、宇利城、古宮城、田峯城、足助城、飯森城、松平城、大給城、篠脇城、小鷹利城、蛤城、増島城、小島城、高原諏訪城、鍋山城、高山城、松倉城、萩原諏訪城,丸山城、名張城、霧山城、松ヶ島城,木造城、上野城、神戸城、峯城、長嶋城
近畿:桑名城、津城、松坂城、亀山城、上野城、彦根城、長浜城、二条城、大阪城、和歌山城、竹田城、津山城、明石城、篠山城、郡山城、岸和田城、小浜城、田辺城、福知山城、出石城、龍野城、赤穂城、伏見城飯盛山城・交野城・津田城・守口城・茨木城・高槻城・芥川城・地黄陣屋・池田城・真田丸出城・若江城・恩智城・八尾城・高屋城・丹南陣屋・狭山陣屋・上赤坂城・根福寺城、多聞城、柳生城、福住井之市城、椿尾上城、豊田城、龍王山城、宇陀松山城、沢城、十市城、高田城、二上山城、片岡城、信貴山城、小泉城、筒井城、稗田環濠、千早城、高取城、竹田城、安土城、観音寺城、小谷城、鹿背山城、笠置城、槇島城、淀城、勝龍寺城、山崎城、山科本願寺、御土居、聚楽第、静原城、亀山城、八木城、周山城、園部城、建部山城、宮津城、弓木城
、膳所城、大津城、宇佐山城、坂本城、大溝城、朽木城、清水山城、賤ヶ岳砦、山本山城、佐和山城、鎌刃城、弥高寺跡、上平寺城、横山城、虎御前山城、東野山城、白旗城、上月城、利神城、置塩城、八木城、此隅山城、有子山城、黒井城、岩尾城、手取城、亀山城、入山城、鹿ヶ瀬城、鳥屋城、大野、雑賀城、太田城、中野城、太田城、根来城、平須賀城、田辺城、龍松山城、八幡山城、安宅本城、勝山城、新宮城、大石城、小川城、新宮城、水口城、日野城、長光寺城、岡山城、八幡山城、浅小井城、山崎山城、伊丹城、尼崎城、鷹尾城、洲本城,三木城
中国:津山城、鳥取城、松江城、月山富田城、郡山城、津和野城、萩城、岩国城、広島城、福山城、鬼ノ城、備中松山城、岡山城、若桜城、景石城、山崎城、太閤ケ平砦、二上山城、桐山城、道竹城、天神山城、防己尾城、鹿野城、羽衣石城、打吹城、岩倉城、由良台城、船上山城、尾高城、米子城、江美城、三石城、天神山城、金川城、徳倉城、足守陣屋、備中高松城、富山城、撫川城、庭瀬城、常山城、下津井城、猿掛城、成羽城、楪城、高田城、岩屋城、神辺城、桜山城、相方城、鞆城、鷲羽山城、三原城、高山城、新高山城、頭崎城、鏡山城、府中出張城、銀山城、桜尾城、亀居城、築山城、大内氏館、山口藩庁、高嶺城、荒滝城、清末陣屋、勝山城、勝山御殿、串崎城、霜降城、七尾城、益田氏城館、浜田城、二ツ山城、福光城、鵜の丸城、山吹城、高瀬城、三刀屋城、福山城、甲山城、蔀山城、五龍城、猿掛城、鈴尾城、今田城、吉川元春館、日野山城、小倉山城、駿河丸城、三入高松城、満願寺城、白鹿城、新山城、十神山城、勝山城、熊野城,三笠城、三沢城、徳山城、鞍掛城、東郷山城、上関城、若山城、敷山城、
四国:徳島城、高知城、宇和島城、大洲城、松山城、今治城、丸亀城、高松城、湯築城、荏原城、港山城、恵良城、鷺森城、西条藩陣屋、川之江城、新谷藩陣屋、安芸城、香宗我部城、山田城、大津城、岡豊城、本山城、泰泉寺城、撫養城、木津城、勝瑞城、西条城、一宮城、上桜城、川島城、秋月城、岩倉城、重清城、東山城、大西城、白地城、浦戸城、朝倉城、吉良城、蓮池城、戸波城、波川城、姫野々城、久礼城、中村城、宿毛城、平島館、牛岐城、日和佐城、海部城、河後森城、大森城、吉田藩陣屋、黒瀬城、松葉城、三滝城、甘崎城、能島城、来島城、引田城、虎丸城、雨滝城、十河城、喜岡城、屋島城、勝賀城、聖通寺城、多度津陣屋、宅間城、天霧城、城山城、由佐城
九州:小倉城、福岡城、佐賀城、吉野ケ里、唐津城、名護屋城、平戸城、島原城、熊本城、大野城、大分府内城、岡城、人吉城、鹿児島城、飫肥城、中津城、杵築城、臼杵城、秋月城、柳川城、佐伯城、名島城、立花城、元寇防塁、柑子ヶ岳城、高祖山城、岩屋城、水城城、久留米城、発心城、猫尾城、益富城、門司城、松山城、馬ヶ岳城、城井谷城、岩石城、香春岳城、障子ヶ岳城、長野城、花尾城、山鹿城、八代城、古麓城・鷹峰城、鍋城、御船城、岩尾城 、高崎城、大友館、栂牟礼城、森陣屋、角牟礼城、日隈城、月隈城、長岩城、光岡城、立石陣屋、日出城、清武城、穆佐城、綾城、宮崎城、南郷城、目井城、櫛間城、都城城、祝吉館、梶山城、勝岡城、加久藤城、都於郡城、佐土原城、高鍋城、高城、松山塁、日の岳城、梶谷城、直谷城、三城城、玖島城、俵石城、諫早城、鶴亀城、深江城、原城、日野江城、獅子城、岸岳城、徳川家康陣、住吉城、塚崎城、須古城、潮見城、鹿島城、山城、志布志城、恒吉城、富隈城、加治木城、長尾城、栗野城、出水城、平佐城、清色城、安岐城、富来城、田原城、高田城、真玉城、千葉城、高木城、姉川城、蓮池城、綾部城、勝尾城、基肄城、三瀬城、佐敷城、水俣城、宇土城、宇土古城、本渡城、富岡城、久玉城、菊の池城、守山城、鞠智城、隈部館、田中城、筒ケ嶽城
沖縄:首里城、名護城、中城城、勝連城、座喜味城、今帰仁城、伊波城、安慶名城、伊祖城、浦添城、大里城、大城、糸数城、知念城、垣花城、玉城、南山城、具志川城、福寺城、清水城、指宿城、頴娃城、知覧城、加世田城、伊作城、一宇治城、加治木城、建昌城、蒲生城、延岡城、松尾城
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百五十八弾:兵庫県お城・城下町巡り&小京都重要伝統的建造物群保存地区観光 2018年12月8-9日 摂津・播磨・丹波・但馬・淡路と、それぞれ異なる魅力に溢れる5つのエリアがあります。北は日本海、南は瀬戸内海に接し、変化に富んだ美しい景観を楽しめるのも魅力。世界遺産「姫路城」、雲海に浮かぶ「竹田城」、異国情緒漂う「神戸」、伝説と花の島「淡路島」等、人気観光スポットが数多くある兵庫県に足を運び、兵庫県に点在する比較的マイナーなお城5か所、小京都重要伝統的建造物群保存地区9か所を訪れました。 8日12:30車で出発、阪神高速経由して神戸に向かう。 お城・小京都重要伝統的建造物群保存地区巡り。 伊丹城:築城年代は定かではないが南北朝時代には伊丹氏の居城であった。 南北朝時代には数々の戦が摂津国で行われ、伊丹城でも数々の功城戦が行われ、時には落城している。 天正2年(1574年)織田信長は茨木城主荒木村重に命じて、池田城主池田氏と伊丹城主伊丹氏を攻め滅ぼし、荒木村重を摂津国守護として伊丹城へ置いた。 村重は伊丹城を有岡城と改名して城の大改修を行った。 天正6年(1578年)播磨国三木城主の別所長治が織田信長に叛くと、つづいて村重も織田信長に叛き有岡城に籠城した。この時、黒田孝高が村重を説得するために赴いたが、そのまま捕えられて幽閉された。信長は池田・塚口・食満・加茂・倉橋・原田・刀根山に軍勢を配して有岡城を包囲し、長期戦にはいった。天正7年(1579年)村重は近習を連れて夜陰に紛れて有岡城を脱し、尼崎城へ逃れた。城主が存在しないまま籠城を続けていたが遂に裏切り者が出て、周囲を固める砦が破られ天正7年(1579年)末に落城した。 その後、信長は池田之助を城主に置いたが、天正11年(1583年)美濃国へ転封となり羽柴秀吉の直轄領となって廃城となった。 尼崎城:元和3年(1617年)戸田氏鉄によって築かれた。 古来より近畿と西国を結ぶ要所である尼崎には、戦国時代には細川氏によって城郭が築かれていたという。 豊臣時代からの尼崎郡代である建部氏は、元和元年(1615年)大坂夏の陣の戦功により一万石の加増をうけ尼崎藩を立藩するが、元和3年(1617年)播磨国林田へ転封となった。 代わって近江国膳所より五万石で入部した戸田氏鉄は、幕命により尼崎城を築き、以後譜代大名が続いて明治に至る。 鷹尾城:山城部分を「鷹尾城山城」平城部分を「芦屋城」と区別していうこともある。阿波の細川澄元の畿内進出の防衛最前線基地として、細川高国が「鷹尾山の天険を利用して、早急に山城を築け」と瓦林正頼に命じたと言われている。 鷹尾城は築城後よりすぐに芦屋河原の合戦の中心となり、赤松義村軍の猛攻にあい瓦林正頼らは鷹尾城からおちのびたが、船岡山合戦より赤松義村軍が兵をひいたのを見計らい、瓦林正頼は鷹尾城を改修するとともに越水城を築城しこれを本城とし、鷹尾城は家臣の鈴木与次郎に守らせ越水城の支城とした。その後記録が残っていないので、越水城が廃城となった同時期に鷹尾城も廃城になったと思われる。( 神戸北野:北野・山本地区は明治以来、雑居地として発展してきたことから、異人館と呼ばれる洋風建築と和風建築が混在し、独特の町並みを形成してきました。 エキゾチックで個性的な景観を保全・育成するために、神戸市では明治・大正・昭和初期の33件の洋風建築物と7件の和風建築物を伝統的建造物として認定していますが、これら以外にも異人館をはじめとする伝統的遺産が現存しています。 洲本城:築城年代は諸説あり定かではないが室町時代後期に安宅氏によって築かれた。 天正9年(1581年)安宅氏は羽柴秀吉に破れ降伏する。 天正10年(1582年)仙石秀久が城主となるが天正13年(1585年)脇坂安治が城主となり大改修した。 大坂夏の陣後はその功により阿波徳島の蜂須賀氏に加増され重臣の稲田氏が城代となった。 17:00姫路方面に向かう。 18:30姫路市内のホテル到着後?華街を散策し食事を済ませて就寝。 9日7:30車で出発。 室津:江戸時代、参勤交代時に諸大名の乗船、下船地として賑わったとか。最盛期には、一ツ屋・薩摩屋・筑前屋・肥前屋・肥後屋・紀伊国屋と呼ばれる六つの本陣があったそうです。通常は一つの宿場町に一つの本陣がほとんどだったと言うので、当時の賑わいはすごいものだったのでしょう。残念ながら今は、本陣跡として「本陣 薩摩屋跡」などの石碑が残っているだけでした。 室津に残る江戸期の建物は回漕問屋「島屋」を資料館にした室津海駅館と海産物問屋「魚屋」を改装した室津民俗館で、これら2軒の商家以外には昔ながらの町並みは残っていませんでした。それでも町屋のほとんどが和瓦の屋根で統一されていてノスタルジックでとても良い雰囲気でした。 坂越:江戸時代から廻船業で栄えた港町。国指定記念物の原生林が茂る生島が目の前に見える。旧坂越浦会所から、国道250号方面へ行く道の両脇に古い街並みが残る。造り酒屋・奥藤家の堂々たる建物や坂越まち並み館(などをゆっくり見学したい。 龍野:播磨の小京都ともいわれる脇坂藩5万3000石の城下町。うすくち醤油に代表される産業の町でもある。鳥かごを伏せたような鶏籠山のふもとに脇坂安政が城を構えたのが寛文12年(1672年)。清流揖保川のほとりには、今も家老門や武家屋敷、醤油蔵がたたずみ、しっとりとした情緒を感じさせる。龍野城跡など見どころが集まる旧市街は道が細いので徒歩が便利。童謡「赤とんぼ」を作詞した三木露風や哲学者の三木清など、龍野ゆかりの文化人の資料館も見ごたえがある。 平福:400年前の景観が今なお残る街並。 街道沿いに建つ家々の格子やウダツといった意匠、佐用川沿いに連なる川座敷や土蔵群など、因幡街道の宿場町として栄えた名残が多く残る街並が魅力の佐用町を代表する観光スポット。また、江戸時代から続く醤油醸造元"たつ乃屋"や、宮本武蔵初決闘の地など、長い歴史を持つ平福ならではの魅力もたくさんある、 竹田:城下町は初代藩主中川秀成(ひでしげ)(1570~1612年)が整備。碁盤の目のように広がる区画は岡藩繁栄の象徴とされ、殿町の武家屋敷通り(歴史の道)は土塀と石垣がある江戸時代の屋敷13軒が並び、築200年の建造物もある。 市は1979年に旧市街地の町並み保存を目的に「市史跡等環境保存条例」を制定。2016年に「市景観条例」に移行し▽入り母屋・切り妻の和風瓦屋根の推奨▽高さ15メートル以内▽原色は使わない近隣のバランスに配慮した色彩―を定めた。江戸時代~戦前の日本家屋29棟が国や県、市の文化財として登録、指定を受けた。 市はさらに20棟を登録文化財候補として挙げ、所有者に対して「竹田の財産を残しませんか」と提案、交渉を進める。空き家の場合は、空き家バンクを通じて利用希望者を探している。2年前に地域おこし協力隊として東京都から移住した小笠原順子さん(37)は、殿町にある築88年の木造住宅を購入した。「竹田で子育てをして、趣がある町並みを守りたい」と話す。 重伝建は城下町や宿場町など建造物群と環境が保存された地区。市町村が都市計画や条例で区域を定め、文部科学大臣が市町村の申し出により、価値が高いものを選ぶ。 城下町は江戸時代の商家や武家屋敷、明治~昭和の建造物が混在し、建造物群として認められていない。 出石:豊岡市は兵庫県の北東部に位置しています。市域の南東部にある出石は、出石川と東の山塊から流れ出る谷山川との合流部付近に位置し、有子山を背にして北に広がっています。現在の出石は、慶長9年(1604)頃、小出吉英が出石城を築城するとともに城下町を整備したことにはじまると考えられています。 保存地区は、出石城跡をはじめとして、近世後期における城下町の町割や敷地の間口割をよく残すとともに、近世から近代に建てられた町家や寺社建築、武家屋敷など、但馬地方における城下町の歴史的風致を今日に良く伝えています。 丹波篠山篠山城下:城下町における保存地区の範囲は、国指定史跡篠山城跡とその周囲に町割りされた旧武家町、旧商家町からなり、東西約1,500メートル、南北約600メートル、面積約40.2ヘクタールに及びます。旧武家町は篠山城の外堀に面して上級武士の長屋門を残し、城の西に位置する南北の通り-御徒士町通りには天保元(1830)年の大火直後に建てられたとされる茅葺入母屋造りの武家屋敷を残し、通りに面して土塀と棟門を配します。旧商家町は、江戸時代末期から大正期に建てられた町家を連たんして残します。篠山市篠山伝統的建造物群保存地区は、天下普請による篠山城跡を核とし、武家町や商家町の町割りを残すなど、近世の城下町の基本的構造を良く残すと共に、武家屋敷や近世から近代にかけて建てられた商家及び寺院など、城下町の要素を全体としてよく残し、その歴史的風致を良く今日に伝え、全国でも価値が高い町並みであると評価され、平成16(2004)年12月10日付けで国の重要伝統的建造物群保存地区(重伝建地区)に選定され、平成19(2007)年2月には城下町篠山の町並みが美しい日本の歴史的風土100選に選ばれました。 丹波篠山福住:篠山城下から京都に向かう宿場町、福住地区。平成24年12月に国の重要伝統的建造物保存地区に選定されました。丹波地方独特の商家の建物が多くみられ、宿場町の面影が色濃く残る町並み。素朴な雰囲気がお散歩にぴったりです。 三木城:築城年代は定かではないが別所氏によって築かれたと云われる。 別所氏の系図については定かではないが、赤松則村(円心)の弟敦光が別所五郎左衛門を名乗ったのが始まりと云う説や、赤松季則の次男である頼清が、永暦元年(1160年)に加西郡在田荘別所村に移り、別所城を築いて居城とし別所氏を称した説などがある。 史料に登場するのは6代別所則治で、文明15年(1483年)守護赤松政則が山名氏に大敗し国人層の信頼を失い堺に逃亡、翌年には浦上則政に家督を廃された。 この時、別所則治が前将軍足利義政にとりなして家督を安堵させ、文明17年政則に従軍して播磨に入国した。 戦国時代に入ると守護赤松氏の勢力は衰退し、別所氏はしだいに自立することとなり、天文7年(1538年)と翌8年には尼子氏の侵攻にあったが、これを撃退した。 天文23年(1554年)三好氏が有馬重則を助けて播磨に入国し別所氏の諸城を落とすと、別所氏は三好に属した。 しかし三好氏が織田氏によって勢力を削がれると、別所氏は織田氏に通じ三好と対立、天正6年(1578年)には毛利氏に付き、織田軍の羽柴秀吉と対立する。秀吉は三木城を完全に包囲し周辺の諸城を落とした後、別所長治以下一族が自害し落城した。 その後は天正13年(1585年)摂津国茨木より中川秀政が入城するが、朝鮮の役で没した。弟秀成が継いだものの禄高は半減となり、文禄3年(1594年)豊後国岡に転封となった。 慶長5年(1600年)池田輝政が姫路に入部すると、三木城には伊木忠次が三万石で在城したが、元和の一国一城令によって廃城となった。 17:00終了、帰路に向かう。 今回の旅行、兵庫県に足を運び、兵庫県に点在する比較的マイナーなお城5か所、小京都重要伝統的建造物群保存地区9か所を訪れ楽しみました。 今回も地味なお城が多いが洲本城は立派な石垣がしっかり残っており感動しました。 小京都重要伝統的建造物群保存地区は何回も訪れたことがあり再確認しました。 今回で全国のお城1000箇所を訪れ制覇し無事終了しました。 |
                   |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百五十七弾:三重県お城・城下町巡り&小京都重要伝統的建造物群保存地区観光 2018年12月1-2日 観光資源が豊富で、F1が開催される鈴鹿サーキットをはじめ忍者発祥の地と言われる伊賀エリアなど魅力あるスポットが数多く存在する。お伊勢参りで有名な伊勢神宮には国内外から多くの参拝者が足を運び、横丁ではグルメも楽しむことができ、複合リゾート施設志摩スペイン村やナガシマスパーランドなどレジャースポットも豊富な三重県に足を運び、三重県に点在する比較的マイナーなお城9か所、小京都重要伝統的建造物群保存地区4か所を訪れました。 1日12:30車で伊賀方面に向かう。 伊賀上野:伊賀エリアのおすすめご当地情報をご紹介。伊賀エリアには薬師寺、上野公園、赤目四十八滝などの観光スポット、上野天神祭、伊賀焼陶器まつり、名張川納涼花火大会などの観光イベント、赤福、いちご大福、てこね寿司などのご当地グルメがあります。 伊賀上野は、三重北西部に位置し、忍者の里として知られ、奈良街道と伊賀街道の要所であり、宿場町として栄えました。上野城の城下町としても栄えました。東京にも似た名があるため、伊賀上野と呼ばれています 丸山城:丸山城は「天正伊賀の乱」の要因となった城です。北畠氏の養子となった織田信雄(北畠信意)は1578年(天正6年)、伊賀の領国化を図るために重臣の滝川雄利に命じて丸山城を築かせましたが、これに反発した伊賀の国人たちによって攻められ、一揆軍に占領されました。その後、第一次、第二次と二度にわたる伊賀侵攻の末、伊賀を完全に領国とし、雄利を再び城主としました。雄利が松ヶ島城に移った頃に廃城となったと思われます。城址は伊賀随一と評されるほどの規模で、削平した曲輪跡をはじめ、土塁や堀切などの遺構が良好に保存されています。また本丸跡にある天守台上には、大正時代に建立された丸山城址の石碑があります。 名張城:天正13年(1585年)松倉勝重によって築かれた名張城が始まりとされる。 上野に転封となった筒井定次は家臣松倉勝重に八千石を与え名張城を築かせた。 天正15年(1587年)松倉重政は家禄を捨て定次との主従関係を切り奈良興福寺成自院に入った。これは酒食に溺れる定次を勝重・重政が父子が諌言したが聞き入れられなかった為ともいわれるが定かではない。 重政は後に豊臣秀吉、徳川家康に仕え肥前国島原六万石を得た。 寛永12年(1635年)伊予国今治から藤堂高吉が領地替えで名張に入り陣屋を築いた。 名張藤堂家は独立した大名とはなれず、伊勢国津の藩内領主という位置付けであった。 霧山城:康永元年・興国3年(1342年)北畠顕能によって築かれたと云われる。 北畠氏は村上源氏で京の北畠に居住した公家であったが、建部3年・延元元年(1336年)後醍醐天皇が吉野山に遷幸の時に北畠親房が南伊勢に下向し、玉丸城を拠点として勢力をのばした。 足利氏はこれに対して幾度となく玉丸城を攻撃し康永元年に落城、顕能は多気郡に逃れた。その後、南北朝の合体や後小松天皇譲位による南北決裂などもあったが、南朝方は次第に勢力を削がれ北畠氏も一守護大名となっていった。 永禄12年(1569年)織田信長が南伊勢に侵攻すると、北畠具教は大河内城に籠城し抵抗したが、やがて信長の次男信雄を北畠の養子として家督を譲ることで和解した。具教は三瀬館に潜み信雄に対抗しようとしたが天正4年(1576年)信雄の命によって暗殺された。 18:00多気市内のホテル到着後?華街を散策し食事を済ませて就寝。 2日7:30車で出発。 伊勢:古くから「日本人の心のふるさと」として親しまれてきた伊勢神宮。広大な森林の澄んだ空気に心が洗われます。昔町めぐりも魅力的。敷地の広い伊勢神宮は、時間をかけてゆっくりとめぐりましょう。古くからの習わしでは、外宮を参拝してから内宮を参拝します。両宮ともに「御正宮(ごしょうぐう)」→「別宮(べつぐう)」の順にお参りを。 参拝後は、お伊勢さんの門前町「おはらい町」散策へ。川沿いの石畳にレトロなお店が軒を連ね、昔懐かしい町並みを楽しめます。そして賑やかなのが「おかげ横丁」。老舗和菓子店や、名物・伊勢うどんを食べられる店、和風の可愛い雑貨屋さんなど、入ってみたいお店がいっぱい! 松坂:江戸時代に商業の町として栄え、豪商のまちとなった松阪。今も城跡や武家屋敷が残り、レトロな風情が町並みに漂います。 松阪もめんの粋な着物姿で散策してみるのもおすすめ。本場の松阪牛は逃せません。 松ヶ島城:永禄10年(1567年)頃、北畠具教が築いた細首城が始まりと云われる。 具教は織田信長の侵攻に備え家臣日置大膳亮に守らせた。 永禄12年(1569年)の織田軍の侵攻では日置大膳亮は細首城を焼いて大河内城に籠城した。 信長の次男信雄が北畠氏の養子になり家督を継ぐことで和議が成立すると信雄は田丸城を築きこれを本拠とした。 しかし田丸城が焼失すると細首城を改修し松ヶ島城と改名した。 本能寺の変の後は羽柴秀吉によって蒲生氏郷が入城したが氏郷は新たに松坂城を築いて本拠を移したため廃城となった。 木造城:貞治5年・正平21年(1366年)木造顕俊によって築かれた。 顕俊は北畠顕能の次男で木造城を築き木造氏を名乗った。 二代目の俊康は京都に住み足利将軍と親しかった為、本家北畠氏の南朝と対立した。 永禄12年(1569年)織田信長の南伊勢侵攻によってそれに従い信長の次男信雄が北畠氏の養子となり家督を嗣ぐことで和解した後は、それに従った。 上野城:織田信長の弟、信包が、津城の仮城として1570年に改修築城した伊勢上野城。お市にとっては兄である信長に攻められ、浅井長政(お市の夫、三姉妹の父)が自害した後、信長の計らいにより、お市と三姉妹が移り住んだお城です。江は0歳から7歳までを過ごしました。その後、廃城となり、後に津藩主、藤堂高虎により取り壊され、現在は城郭の跡のみ残っています。 標高38mの伊勢街道沿いの台地に造られたこの城からは、伊勢湾や鈴鹿連峰が一望でき、展望台となった今でも当時の景色が偲ばれます。 神戸城:築城年代は定かではないが天文19年(1550年)頃に神戸具盛によって築かれたと云われる。 神戸氏は伊勢平氏関氏の一族で、関盛政の長子関盛澄が鈴鹿郡と河曲郡内二十四郷を領し、沢城を築いて神戸氏の祖となったと云われる。 永禄10年(1567年)神戸友盛のとき、織田信長の家臣滝川一益の侵攻を受けたが、高岡城に籠もった山路弾正がこれを凌いだ。翌11年(1578年)にも織田氏が攻め込み、神戸友盛は信長の三男信孝を養子として迎えることで和睦となった。 元亀2年(1571年)信長は神戸友盛を沢城に隠居させ、信孝を神戸城主に据えた。その後、友盛は近江の蒲生氏に預けられたが、これに反発した山路弾正らは神戸城奪還のために高岡城で挙兵しようと画策したが、計画が発覚して弾正は切腹となり、高岡城には小島兵部が置かれた。 正8年(1580年)神戸信孝は神戸城を拡張して五重の天守を設けた。 天正10年(1582年)信孝は四国攻めの総大将として堺にて渡航の準備をしていたが、本能寺の変が勃発して中止となり、秀吉に合流して明智光秀を討った。その後、信孝は岐阜城に移り神戸城には小島兵部が入った。信孝はその後、賎ヶ岳合戦に際して柴田勝家と結んで岐阜城で挙兵したが、羽柴秀吉によって岐阜城が攻められ降伏して開城し、知多の野間大坊で自刃した。 天正15年(1587年)水野忠重が三河国刈谷より移ったが、文禄元年(1592年)再び三河国刈谷に移り、滝川雄利が城主となった。 関:関宿は、古代から交通の要衝で、日本三関の一つ「鈴鹿関」が置かれ、江戸時代には東海道五十三次47番目の宿場町として、参勤交代や伊勢参りの人々で大変賑わいました。そして現在、旧東海道の宿場町のほとんどが旧態をとどめない中にあって、江戸時代から明治時代に建てられた古い町家が200軒あまり残っており、往時の姿を色濃く残していることから昭和59年に東海道の宿場町としては唯一国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。 峯城:築城年代は定かではないが正平年間(1346年~1370年)に関盛忠の五男峯政実によって築かれたと云われる。 峯氏は政実以降六代続いたが、天正2年(1574年)峯八郎四郎盛祐が伊勢長島の合戦で討死すると弟与八郎が幼小であったため、岡本下野守が峯城主となった。 天正11年(1583年)滝川一益の家臣滝川儀太夫益重によって攻められ峯城は落城するが、羽柴秀吉が大軍を率いて峯城を包囲し、数ヶ月の籠城の末に兵糧が尽きて儀大夫は開城した。この戦いの後、織田信雄の家臣佐久間正勝が入城した。 天正12年(1584年)秀吉と信雄が対立すると、小牧・長久手合戦の前哨戦として秀吉は蒲生氏郷、関長門守などに命じて峯城を攻めさせ、わずか数日で落城した。 長嶋城:寛元3年(1245年)藤原道家によって築かれたのが始まりとされる。 文明年間(1469年~1487年)伊藤重晴が再び築城した。 元亀元年(1570年)一向宗願証寺の門徒が長島城を攻めて伊藤氏を滅ぼした。 更に一向宗は矢田城の滝川一益を追って、織田信長の弟興長を自刃される。 元亀2年(1571年)織田信長は大軍をもって長島城を攻めるが落とせず、退陣で殿を勤めた氏家卜全が討死した。 天正2年(1574年)三度目の長島城攻略によって落とすと、滝川一益を城主として北伊勢を領した。 天正11年(1583年)滝川一益は柴田勝家に味方して羽柴秀吉に敵対するが、勝家が秀吉によって滅ぼされると一益もまた攻められ、所領を没収された。その後は、天野景俊、原胤房、福島正頼が城主となる。 ・慶長6年(1601年)福島正頼は大和国宇陀に転封。 ・慶長6年(1601年)上野国阿保より菅沼定仍が二万石で入封、元和7年(1621年)定芳の時、近江国膳所に転封。 ・慶安2年(1649年)下野国那須より(久松)松平康尚が一万石で入封、元禄15年(1702年)忠充の時、除封。 ・元禄15年(1702年)常陸国下館より増山正弥が入封、以後明治に至る。 16:00帰路に向かう。 今回の旅行、三重県に足を運び三重県に点在する比較的マイナーなお城9か所、小京都重要伝統的建造物群保存地区4か所をおとずれ楽しみました。 比較的地味な城跡、何回か訪れたことのある小京都重要伝統的建造物群保存地区(伊賀上野、伊勢、松坂、関)訪れ今回で兵庫の城跡のみとなりました。 |
    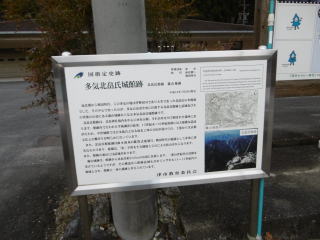            |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百五十六弾:山口県お城・城下町巡り&小京都重要伝統的建造物群保存地区観光 2018年11月24-25日 角島、秋吉台、錦帯橋などの観光スポット、関門海峡花火大会、萩焼まつり、七夕ちょうちんまつりなどの観光イベント、ういろう、瓦そば、夏みかん菓子などのご当地グルメがあり、山陽地方の県で、かつて周防国と長門国であった土地は毛利家に支配されていました。江戸時代には長州藩と称して幕末の動乱を主導している山口県に足を運び、山口県内に点在する比較的マイナーなお城6か所、小京都山口重要伝統的建造物群保存地区2か所を訪れました。 24日16:05新幹線のぞみで新大阪駅出発 18:34徳山駅到達、駅前のホテル到着後繫華街を散策し食事を済ませて就寝。 25日8:00レンタカーで出発、お城、小京都伝統的建造物群保存地区巡る。 徳山城:慶安元年(1687年)毛利就隆によって築かれた。 就隆は毛利輝元の二男で元和3年(1617年)周防国都農郡を中心に三万石を分地されたことに始まる。 就隆は寛永2年(1625年)に下松に陣屋を構え、寛永11年(1634年)四万五千石の大名として正式に諸侯に列した。慶安元年(1648年)に野上村に居館を移し、慶安3年(1650年)に地名を徳山と改め徳山藩となった。 正徳5年(1715年)三代元次のとき、宗家である萩藩との境界にある松の木を巡って騒動となり、幕府から「本家に対する非礼」を理由に元次は改易、出羽国新庄藩へお預けとなって徳山藩領は萩藩に還付された。 享保4年(1719)領民の藩再興運動もあり、元次が家督を次男の元堯に譲って新たに三万石が与えられ徳山藩が再興となった。天保7年(1836年)就馴のとき幕府より城主格を賜り、石高も四万石に改められた。これによって「御館」と呼ばれていた居館は「御城」や「御殿」と呼ばれるようになった。 鞍掛城:築城年代は定かではない。 大内氏の重臣杉隆泰は鞍掛三万石を与えられ鞍掛山城を居城とした。 弘治元年(1555年)厳島合戦によって陶晴賢が毛利元就に破れると一度は毛利氏に降った。 しかし再び大内氏に従うべく内通したが密書を奪われると毛利氏によって攻めら落城、隆泰は千数百名の城兵と供に討ち死にした。 岩国:豊かな自然に恵まれ、山口県最大の河川である錦川が美しい景観をかたちづくりながら瀬戸内海に注いでいます。市の中心地域には、都市機能が集積し、南部の玖珂盆地では、交通の利便性を生かした工業団地が形成されています。観光都市としての一面も持ち、岩国城跡や錦川に架かる錦帯橋など、多くの観光資源に恵まれ、市域中央から山代地域には、温泉や自然景勝地などを生かした観光、交流施設があります。 東郷山城:詳細不明、東郷峠付近 柳井:柳井は、瀬戸内海交易の要衝として中世の時代から商業都市として栄えました。江戸時代には、岩国藩の御納戸と称され、その商圏は、近隣の各藩領だけでなく、九州一円から瀬戸内海の各地に及んでいました。 その商家の家並みが残る同地区は、柳井津でも最も早く開かれた旧町の西半分にあたり、東西方向の本町通りの両側に続く約200メートルの家並みと、 このほぼ中央から南側の柳井川に通じる掛屋小路からなります。 明治以降もこの地域は中心街として栄え、現在もなお江戸・明治期の商人の家系を継ぐ者が所有し、一部は現在も営業されています。 柳井市のもっとも重要な観光資源であり、年間多くの観光客が訪れます。 上関城:築城年代は定かではないが室町時代に村上吉敏によって築かれたと云われる。能島村上氏の村上義顕の子村上吉敏によって築かれ、代々村上氏によって上関を通行する船舶から通行税を徴収するための拠点となった。 天文20年(1551年)大内義長から将軍家への進納の米二千石を積んだ船は、宇賀島水軍の警護を受け通行税を払わずに航行すると、三島村上水軍はこれを安芸国蒲刈にて迎撃した。大内義長は上関より村上氏を追い出して宇賀島水軍に守らせたが、間もなく村上氏が奪還して再び村上氏の所領となった。 若山城:築城年代は定かではないが文明2年(1470年)に陶弘護が吉見氏に備えて築城されたものと考えられている。天文19年(1550年)には陶晴賢が大内義隆を攻撃する前に大改修したという。厳島の合戦後、晴賢の子長房が守衛していたが、晴賢によって殺された杉氏の一党杉重輔が挙兵して押し寄せ、味方と間違えて城門を開いたところ攻められ落城した。 敷山城:敷山城跡は矢筈ケ岳の8合目あたりに位置する。ここはもともと敷山験観寺という山寺である。南北朝時代に足利尊氏が九州から反転して湊川の戦いで楠正成に勝利し上京、天皇が逃げた比叡山攻略に取り掛かった。そのとき周防国衙の役人清尊、教乗、大内弘道、小笠原長光などが挙兵しここに籠城する。しかし、尊氏によって派兵された大軍によりわずか10日あまりで落城する。 山口:山口市は、豊富な緑や清澄な水を有する自然に満ちた都市となっています。また、大内氏時代や明治維新関連の歴史や文化資源が今に残されており、湯田温泉などを含めて、観光地としての魅力も備えた都市となっています。 17:00帰路に向かう。 18:00徳山駅到達。 18:34徳山駅新幹線のぞみで出発 20:18新大阪駅到達。 今回の旅行、山口県に足を運び、比較的マイナーなお城6か所、小京都山口、重要伝統的建造物群保存地区2か所をおとずれ楽しみました。 今回もお城は地味で案内板も少なくたどり着くのに苦労を要しました。中には城址公園に変貌し整備されていた城跡もあり散策を楽しめました。 小京都山口、伝統的建造物群保存地区、岩国、柳井は何度か足を運んだことがあり、再確認できました。 |
                        |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百五十五弾:滋賀県お城・城下町巡り&小京都大津観光 2018年11月22-23日 日本のほぼ真ん中に位置し、その中央に県土の約6分の1を占める日本最大の湖・琵琶湖を抱え、周囲には緑豊かな山々や田園風景が広がる、水と緑の豊かな自然にふれ合うことができるところです。悠々と水をたたえる琵琶湖と周囲が織りなす美しい風景は、季節の移ろいに応じた折々の景観として楽しむことができます。びわ湖の雄大さと変化に富んだ風景は、「琵琶湖八景」や「近江八景」として風光明媚な景色を紹介しています。また、交通の要衝の地でもあり、古くから文化・経済の先進地として栄えたこの地には、古刹・名刹の歴史ある寺社や戦国時代をはじめとする英傑たちの足跡、歴史情緒が残る町並みなど、奥深い歴史文化があり、国内有数を誇る歴史文化資産は、今もなお県内のそれぞれの地域で大切に守り伝えられています滋賀県に足を運び滋賀県に点在する比較的マイナーなお城10か所と小京都と承認されている大津を訪れました。 22日12:30車で第二京阪,京滋バイパス経由して南郷インター下車、お城巡り 大石城:大石城は舌状尾根の先端部に築かれ、細い道を挟み両側一帯が城域で群郭式の構造であったと推測される。 主郭は、東西52m×南北35mの方形で周囲に土塁を、東背後に見張り台を兼ねた巨大な土塁と堀切を配し、西前面に一段低い副郭(東西22m×南北24m)を備えている。虎口は平虎口で西と南東隅に開いている。北側は断崖となっているが、南側が茶畑で高低差がほとんどなく土塁と空堀で画す程度で、防御が弱く思われる。 小川城:築城年代については諸説あり定かではないが、一般的には鎌倉時代末期に前関白近衛家基に従って設楽庄に入部した鶴見長実が嘉元3年(1305年)に築城したのが始まりと云われる。 鶴見長実の子、鶴見道宗が城主となり、弟行俊は小川氏を称して代々続いたが、長享元年(1487年)に多羅尾和泉守に敗れた小川成俊は山城国和束庄へ逃れ、以降は多羅尾氏の所領となった。 天正10年(1582年)本能寺の変によって織田信長が倒れた際、堺見物をしていた徳川家康が伊賀越えで所領に戻る際に設楽で一夜を明かしたのが、この小川城と伝えられる。 文禄4年(1595年)に多羅尾光太の娘が豊臣秀次に嫁いでいたことから、秀次に連座して改易されたが、その後に徳川家康に召し出されて旗本となり、江戸時代には多羅尾代官陣屋を構えている。これは多羅尾光俊・光太父子が守護した恩に報いたものといわれる。 新宮城:甲賀郡中惣遺跡群(寺前城,村雨城,新宮城,新宮支城,竹中城)の一つとして国指定史跡となっている。 新宮城は磯尾川の西岸にあり、北東へ伸びた尾根に築かれている。谷を挟んで南には新宮支城がある。 新宮城は南西端の最高所に主郭を置き、北東へ伸びた尾根に曲輪を展開する。 主郭は方形で高土塁が巡り、南西側は深い空堀で遮断し土橋が架かる。虎口は北と東にあり、北虎口は北下の堀切に出る。東虎口は二郭へ通じ、二郭は鈎状に屈折した虎口が付き、さらに北東下の段へと続く。二郭の北下には両側から土塁状の伸びた空間があり、池なのか虎口なのかよくわからない地形がある。麓付近には大きな平段がいくつか展開している。 水口城:寛文11年(1634年)徳川家光の上洛の宿館として小堀遠州によって築かれた。 築城に際しては水口岡山城の石垣を転用してたという。 天和2年(1682年)加藤明友が石見国吉永より二万石で水口城主となり水口藩を立藩した。 日野城:築城年代は定かではないが大永年間に蒲生定秀によって築かれたと云われる。 永禄11年(1568年)織田信長による観音寺城攻めで、蒲生賢秀は中野城に籠城したが伊勢国神戸友盛の仲介により人質をだして信長に降った。この時人質として出されたのが後の蒲生氏郷である。 本能寺の変で信長が討たれた時、蒲生賢秀は安土城二の丸を預かっていたが、その悲報を聞いた賢秀と氏郷は信長の妻子を中野城へ移し光秀の誘いに応じなかった。 天正12年(1584年)蒲生氏郷は伊勢国松坂へ転封となり、その後は田中吉政、長束正家が城代となり、慶長8年(1603年)廃城となった。 長光寺城:築城年代は定かではないが鎌倉時代中期に佐々木政尭によって築かれたと云われる。 元亀元年(1570年)南近江に侵攻した織田信長は長光寺城を攻め落とし柴田勝家を配置した。 六角氏は城を奪還するために攻め寄せ勝家は籠城して耐える。 意を決した勝家は味方を鼓舞するため兵に水を飲ませた後に水瓶を割って討って出た。これが「瓶割り柴田」の異名となって後世に語られている。 17:00近江八幡方面に向かう。 17:30近江八幡駅前のホテル到着後繫華街を散策し食事を済ませて就寝。 23日7:30車で出発、お城巡り 岡山城:南北朝期に佐々木氏の支城として築城され、永正五年(1508年)に足利十一代将軍義澄が六角氏の重臣伊庭氏と伊庭氏の家臣九里氏を頼って都より落ち延びて来て岡山城に入った頃より本格的な改修がされたものとの事です。この事態は六角氏と伊庭・九里両氏との間を悪くし、義澄が永正六年(1509年)に当城で病死して以後、永正十七年(1520年)、ついに六角定頼はこの城を攻め開城させました。後、大永五年(1525年)に伊庭氏・九里氏が再び籠りましたが、六角氏に破れ城も廃城になりました。 八幡山城:天正13年(1585年)豊臣秀次によって築かれた。 近江国四十三万石の領主となった豊臣秀次によって築かれ、城下町は安土より移されて発展、近江商人発祥の地としても知られる。 天正18年(1590年)秀次は尾張国清州へ転封となり、かわって大溝より京極高次が二万八千石で城主となった。しかし永禄4年(1595年)関白豊臣秀次が太閤によって自害させられると、京極高次は大津へ六万石で転封となり、聚楽第とともに八幡山城も廃城となった。 浅小井城:大古、沙々木神社豊浦冠者行実の息浅小井次郎盛実の後裔深尾氏第十代加賀守元泰が足利将軍義政の幕下にあって当地を領有後、十一代元範は佐々木(六角)高頼の命により文亀元年(1501年)に築城しました。十二代元秀、十三代元忠と続き、永禄年間にこの城を伊庭氏が領有を画策したが、六角承禎義賢はそれを避け、甲賀武士の山中大和守俊好に与えますが、永禄十一年(1568年)に織田信長の侵攻で落城しました。その後の安土城築城後、城はこの地の豪族の伊佐志摩守に預けられ、信長の鷹狩の際は伊佐氏別邸に立ち寄り休息したと伝えられます。天正十二年(1584年)秀吉は池田秀氏<池田氏は近江源氏佐々木氏の流れで甲賀池田を発祥と六角氏に属していたが観音寺騒動の際六角氏を離れ、信長の近江侵攻時は織田氏に属しました>にこの城を与えますが、池田氏が文禄四年(1595年)に伊予大洲に転封し当城は破却されました。 山崎山城:詳細不明。城主は山崎氏が伝えられる。 大津に向かう。 小京都大津巡る。 大津:今から約1350年前、天智天皇により遷都された歴史の街、大津。日本最大の湖である、びわ湖に寄り添うように南北に広がるこの土地には、世界文化遺産・比叡山延暦寺や日本遺産である石山寺、かるたの聖地としてアニメや映画の舞台にもなった近江神宮をはじめとする多くの観光スポットに溢れています。また、「美肌の湯」として知られるおごと温泉や、夏はウォータースポーツ、冬はスキーなどのアクティブリゾートなど、おすすめスポットや1年を通じてのイベントも盛り沢山!もちろん、日本三大和牛のひとつである近江牛や、様々な湖魚料理など、お楽しみグルメもいっぱい。 石山寺:良弁開山の東寺真言宗大本山で西国三十三霊場第13番の観音霊場。諸堂宇は景勝地の自然と調和している。境内は巨大な硅灰石(天然記念物)の上に建てられており、寺名の由来となっている。 瀬田の唐橋:近江八景「瀬田の夕照」(せたのせきしょう)の主題である「瀬田唐橋」は、別名「瀬田橋」や「長橋」とも呼ばれ「唐橋を制するものは天下を制する」と言われ、古来より京都ののど元を握る交通・軍事の要衝として重視され、瀬田橋が戦の歴史舞台になって千八百年になりますが、特に有名なものは、古くは、大津京が幻の都となった大友皇子と大海人皇子(おおあまのおうじ)の『壬申(じんしん)の乱』をはじめ、『寿永の乱』、『承久の乱』『建武の乱』など幾多の戦乱の舞台ともなりました。織田信長の瀬田橋の架け替えは、比叡山焼き討ちの4年後、天正三年(1575)に諸国の道路修理を命じ関税を免除するとともに、瀬田城主、山岡景隆と木村次郎左ヱ右衛門を奉行に任命し、近江の朽木などから木材を調達し、長さ百八十間(約350m)、幅四間(約7m)の一本橋をわずか3ヶ月という突貫工事で架け替えさせたといわれています。 三井寺:天台宗寺門派の総本山で、観音堂は西国三十三所観音霊場第十四番札所。大友皇子の皇子・大友与多王が父の霊を弔うために寺を創建し、天武天皇に「園城寺」という勅額を賜ったことが名前の由来。また、境内には天智・天武・持統の三帝の産湯に用いられたという霊泉があり、「御井の寺」と称されたことから「三井寺」と呼ばれるようになった。金堂をはじめ、国宝や重要文化財の数は圧巻で、近江八景「三井の晩鏡」でも知られている。春は1000本の桜とライトアップ、秋は紅葉とみどころが多い。 坂本:比叡山延暦寺、日吉大社の門前町として栄え、穴大衆と呼ばれる石工集団の手による「穴大衆積み」という石積が特色づけている町並みは国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。約50ヵ寺も残る延暦寺の高僧の隠居所「里坊」には、借景や自然石を利用した見事な庭園があり、普段は非公開の庭園などが拝観できる社寺・庭園めぐりも開催されています。春の桜と秋の紅葉の時季は特に見ごたえがあり、多くの観光客で賑わいます。 浮御堂:近江八景「堅田の落雁」で名高い浮御堂は、寺名を海門山満月寺という。平安時代、恵心僧都が湖上安全と衆生済度を祈願して建立したという。現在の建物は昭和12年の再建によるもので、昭和57年にも修理が行われ、昔の情緒をそのまま残している。境内の観音堂には、重要文化財である聖観音座像が安置されている。 光徳寺:真宗大谷派の寺院で創建は1361年(康安元年)覚忍により開創されたと伝えられています。 浄土真宗中興の祖である蓮如のために、自らの首を差し出すよう父源右兵衛を説得し、切らせて差し出したという漁師親子の殉教物語があります。 本堂前には「堅田源兵衛父子殉教之像」があります。 延暦寺:伝教大師最澄が比叡山に草庵を結んだことに始まる天台宗総本山。標高848mの比叡山全域を境内とする寺院で、日本仏教の母山と言われている。広大な寺域は100余りの建造物があり、延暦寺の総本堂である根本中堂(国宝)や大講堂などがある「東塔」、最澄作の釈迦如来を本尊とする釈迦堂やにない堂などがある「西塔」、横川中堂や元三大師堂などがあり、静寂に包まれた「横川」の三つのエリアに分かれている。戦国時代に織田信長の焼き討ちにあいましたが、豊臣秀吉や徳川家康などにより復興され、平成6年に世界文化遺産に登録された。 16:00終了、帰路に向かう。 今回の旅行、滋賀県に足を運び、滋賀県に点在する比較的マイナーなお城10か所、小京都に承認されている大津を訪れ楽しみました。 今回のお城、かなり地味で案内板もなく見つけるのが苦労したお城が多く、大変でした。 小京都の大津にある歴史的建造物、石山寺、瀬田の唐橋、三井寺、坂本、浮御堂、光徳寺、延暦寺何回も訪れたことがあり再確認しました。 |
   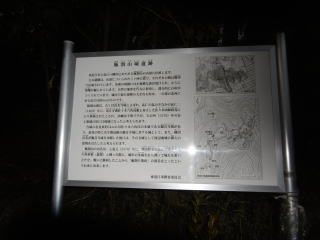          |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百五十四弾:岐阜県中部四十九薬師霊場&お城・城下町巡り観光 2018年11月17-18日 長野県と岐阜県を中心に、山梨・愛知県にまたがりアルプスの山懐にいだかれ、温泉地にも恵まれた大自然の中の巡拝コース中部四十九薬師霊場で岐阜県に点在する霊場10か所、お城11か所を訪れました。 17日12:30車で出発、第二京阪、京滋バイパス、名神経由して小牧インター下車、霊場巡り。 願興寺:縁起 人皇五十二代嵯峨天皇の弘仁六年(815年)天台宗宗祖伝教大師が比叡山より東国巡錫の砌り、御嵩の地にお宿りになりますと、遠近の人々が忽ち集まり仏教信者となり、大師は布施屋(無料宿泊所)を作らしめ、薬師瑠璃光如来の尊像を彫刻して安置された。その後、正暦四年(993年)一条天皇の御代に、皇女が剃髪して行智尼と称し、この地に正宝庵を結んで住まわれ、朝夕本尊薬師如来を礼拝せられたところ長徳二年二月七日(996年)、寺の西南にあたる尼ケ池より金色の御光が四方に輝き亘り一寸八分の御尊像が蟹の背に乗って池の面に浮かばれましたので、行智尼は、この尊像を迎え奉って本尊の腹中に納められました。このこと畏くも天聴に達し勅命により、七堂伽藍を建立し、大寺山願興寺の寺号を賜りました。俗名「蟹薬師可児大寺」はこの因縁によるものです。その後、幾多の兵火あって堂宇は炎上したものの、本尊をはじめ御尊像24体は恙がなくお移し大正三年(1914年)に国宝に指定され、今は国の重要文化財となっている。 真光寺:縁起 何時の頃か当地の里人達は、行基菩薩作の薬師如来像を招来してきて、形ばかりの小堂を建立して日夜尊崇怠りなく、このこと次第に近隣に伝わり、皆共々に相携えて参詣日毎に多し、やがて堂宇の狭小を感ずるや、人々相議して堂宇を拡張再建して一寺とした。 信徒等は、加治田村の龍福寺第四世陽南大和尚を、懇請して開山第一世となす。爾来、順栄、順林、恵珀、道仙、師順、恵湛、玄苗、萬密、文青、穆洲と十世を経て現在第十二代となる。この間、第八代玄苗師の頃、火難に遭い、諸堂全焼、その後間もなく再建されて現在の伽藍とはなったが、そのために創建の年次も不明となった。 洞雲寺:縁起 当山は嘉吉三年(1443)将軍足利義勝公の寄付地により却庵寂永禅師の開基であり、文明十八年以降、瑞浪市開元院より交互性特派遣、慶長九年(1604)開元院十世梵的和尚中興開山となり慶長十三年(1608)西尾丹後守、寺領を寄進、殿宇を再建し永風を唱え大龍峯窟を全備した。 通称田代山寺と呼ばれ山上にあったのを昭和三十三年に現在地に移転新築した。 本尊 聖観世音菩薩。 脇仏 地蔵菩薩・昆沙門天 別仏 東方薬師如来・阿弥陀如来・文珠菩薩・大黒尊天 弁財尊天・水子地蔵菩薩・稲荷大明神・金比羅大権現 当山薬師如来は寛永十七年(1640)殿宇と共に建立し今日に至る。又、町内4ケ所に薬師堂あり。 病苦に悩むものには回春の光明を与え、貪苦に苦しむものには福徳を施与し、身体健全と家門隆昌の薬師如来様であります。 17:00関方面に向かう。 17:30関市内のホテル到着後繫華街を散策し食事を済ませて就寝。 18日7:30車で出発。 霊場、お城巡り 篠脇城:築城年代は定かではないが南北朝時代に東氏村によって築かれたと云われる。 東氏は下総国千葉氏の支族で、承久の乱(1221年)の功により郡上郡山田荘の新補地頭職を得て東胤行が下向して阿千葉城を築いたことに始まる。 四代東氏村は当時勢力を誇っていた鷲見城主鷲見氏との距離が近すぎることと、南朝方の拠点である越前からの来襲に備えるために、篠脇城を築いて居城を移したといわれる。 東氏は代々文武両道で続後撰集、続拾遺集、新続古今集などに入っていた。 応仁の乱が勃発すると東氏は東軍の細川氏に味方したが、美濃国守護の土岐は西軍の山名氏に味方した。この結果、応仁2年(1468年)守護代斎藤妙椿の攻撃を受け、激戦の末落城した。このとき関東に下向していた東常縁は「あるが内に斯かる世ーしも見たりけり、人の昔の猶も恋しき」と詠んだ。人づてに聞いた妙椿は自分に詠を贈ってくれたら所領を返そうと約束すると、「吾世経むしるへと今も頼む哉、みののお山の松の千歳を」をはじめ十首の和歌を贈ったという。これを受けた妙椿は約束通り所領を全て返還したという。 その後、十二代常慶の時、天文9年(1540年)と翌年の天文10年に越前国朝倉氏の攻撃を受け、この時はかろうじて撃退するが、東殿山に赤谷山城を築いて居城を移した。 小鷹利城:築城年代は定かではない。姉小路氏の庶流向氏(小鷹利氏)累代の居城とも云われるが、それを直接示す史料は残っていない。 天正11年(1583年)(あるいは10年)に向家の幼君右近を後見していた牛丸又太郎重親が、逆心を起こして横領を企てた。重臣後藤重元はこれを察知して右近を伴って城を脱し、角川へ逃れたが、重親が差し向けた追っ手に角川村で追いつかれ、重元は防戦して戦死、右近は逃げ延びて母方の縁を頼り常陸の佐竹氏に仕え、向右近宣政と名乗ったという。 蛤城:築城年代は定かではない。 応永年間末期に藤原師言が築いたとの伝承もあるが、天文年間に古川二郎による築城とも云われる。 その後は塩屋筑前守の城となり筑前守は上杉謙信、後は織田信長に従ったが天正11年に討死したという。 その後は一時三木氏の勢力にあったが、三木自綱が金森長近によって討たれると金森氏の城となり、金森可重が入城したが、増島城を築いて居城を移し廃城となった。 この城は「蛤城(はまぐりじょう)」とも呼ばれるが、これは飛騨へ入国した金森氏がこの城へきたとき、城内に蛤石があったため、以後蛤城と呼ばれるようになったのだという。 増島城:築城年代は定かではないが天正15年(1587年)に金森長近によって築かれた。 越前国大野城の金森長近が飛騨国の三木氏を滅ぼして飛騨に入部すると、増島城を築いて蛤城の金森可重を城主とした。 長近が没すると可重は金森氏を継いで高山城へ入り、増島城には長子金森重近を置いた。しかし可重が没した後に金森氏を継いだのは重近ではなく四男の重頼で、この結果重近が京都へ出て茶道に生きた。 元和5年(1619年)一国一城令によって廃城となり、その後は古川旅館として金森氏の別邸として存続されたが、元禄5年(1692年)金森氏は出羽国上山へ転封となり、その領地が天領となって破却された。 小島城:築城年代は定かではないが南北朝時代に姉小路氏によって築かれたと云われる。 姉小路氏は公家で三条実房の子公宣が京の姉小路に住んで姉小路氏を名乗った事に始まる。飛騨の姉小路氏は姉小路家綱が建武新政の際に飛騨国司となり、信包城(向小島城と推定されている)を居城としたことに始まるという。 姉小路家綱は南朝方によって国司に任命されたことから、おもに南朝方として戦っていた。その後、姉小路氏は小島氏・古川氏・向氏の三家にわかれる。 戦国時代になると京極氏の被官であった三木氏が台頭し、小島氏はそれに属していたが、天正13年(1585年)羽柴秀吉の命によって飛騨国に侵攻した越前国大野城の金森長近によって攻められ、小島城は落城した。 江馬下館:築城年代は定かではないが江馬氏によって築かれたと云われる。 江馬氏の出自は定かではないが、鎌倉北条一門または伊豆の江間氏の一族といわれる。 江馬氏下館は南東にある高原諏訪城を詰城とした館である。 江馬氏は高原諏訪城を本城として北飛騨一円に城を築き、北飛騨の雄として勢力を誇っていた。しかし戦国時代には越後国上杉氏、甲斐国武田氏に翻弄される。 江馬時盛ははじめ甲斐の武田氏に通じ、南下して姉小路氏を攻め勢力を延ばしたが、越後の上杉氏が飛騨に侵攻して降伏した。しかし永禄7年(1564年)武田信玄は山県昌景に命じて飛騨に侵攻すると、再び時盛は武田氏に通じ、翌年には武田氏とともに越中へ侵攻した。 武田氏よりの時盛に対して、嫡子輝盛は上杉氏に好意を寄せ父子の関係は悪化、時盛は三男信盛に家督を譲ろうとするが信盛は輝盛にはばかってそれを受けず、時盛は従弟の洞城主麻生野直盛の子慶盛を養子にしようとした。天正元年(1573年)ついに輝盛は父時盛を暗殺し、洞城を攻めて麻生野慶盛を自害させ、弟信盛・貞盛を追放して江馬氏の家督を継ぐ事となった。 天正10年(1582年)三木氏の後ろ盾であった織田信長が本能寺の変で死んだことを機に、輝盛は南飛騨の三木氏を攻めるべく出陣する。しかし吉城郡荒城川において大将江馬輝盛は三木氏の将牛丸又太郎によって討ち取られ、江馬軍は総崩れとなり、本城である高原諏訪城も落城した。 その後、江馬時政という人物が再興し、天正13年(1585年)飛騨に侵攻した金森長近に協力して姉小路氏(三木氏)を滅ぼすが、同年金森氏に反抗して一揆を起こし、金森氏に滅ぼされた。 高原諏訪城:築城年代は定かではないが江馬氏によって築かれたと云われる。 寿楽寺:縁起 創建は不祥だが所蔵する写本大般若経や祈祷札の墨書から推察するに、応永五年(1399)三月、記載の祈祷札(県指定文化財)に宮谷寺末寿楽寺とある。室町時代すでに寿楽寺が存在したことは確かであろう。元禄二年(1689)高山の素玄寺八世古林道宣和尚が中興開山して以来、曹洞宗を継承して現在に至る。本堂は宝暦五年(1756)六世和和尚の代に再建した。単層入母屋造り、間口七間の見事な構えである。 本尊の薬師如来は、厨子入り秘仏である。資料によると天保十一年(1840)春三月に御開帳されている。脇間の十六羅漢像も威厳ある像である。棟続きの観音堂は明治十二年(1879)本田家が寄進した。鐘楼は昭和五十九年に建立された。 安国寺:縁起 建武の中興を成した足利尊氏直義は、禅僧、夢窓疎石の薦めで後醍醐天皇と元冠以来幾多の戦乱に露と消えた兵達の霊を弔う為、一国一寺一塔の大願を発し、六十六国二島に安国寺が設立された。 飛騨の安国寺はその一つとして貞和三年(1347)少林寺を母胎として創設された。当時は七堂伽藍と九ケ寺の塔頭を備え、繁栄していたが、天文・永禄の頃、飛騨戦乱のため兵火にかかり、そのほとんどを焼失した。その後飛騨平定され、寛文の頃、南叟和尚の尽力で再建され今日に至っている。 当山の薬師如来、日光・月光菩薩は、もと本町半田の山腹にあった横河山安寧寺の御本尊であった。安寧寺は安国寺と同時期に兵火にかかり、御本尊のみ難を逃れ、一時は民家に御座されていたが、安国寺再建の折、当所に移入し、堂宇を新たに建立して安置されたものである。行基菩薩の作と伝えられている。御像は寄木造りで永い間風雪に曝された為か彩色が殆ど剥落し、木地が露わになり、処々に胡粉の跡が伺える。このことが却って当山薬師如来の信仰を深めている趣がある。古来より十七年毎に大開帳を行っている。他に国宝経蔵、重文開山像等がある。 飛騨国分寺:縁起 聖武天皇の勅願により全国六十余州に建立された「金光明四天王護国之寺」は、国分寺と称せられる鎮護国家の祈願道場です。 当山は、飛騨の国の国分寺として、天平十八年(746)に行基菩薩が開創された当国第一の古刹です。境内には、樹齢一千二百年の大いちょう(天然記念物)が繁っており、創建当初にそぴえていた七重大塔の礎石(国史跡)と共に寺歴を物語っております。 市内最古の建造物である本堂(国重文)には、行基菩薩御作と伝えられる本尊薬師如来(国重文)をはじめ、旧国分尼寺本尊の聖観音(国重文)、恵心僧都御作と伝えられる阿弥陀如来(県重文)等が安置されており拝観することが出来ます。 毎月八日の縁日には「薬師如来供祈願会」が巌修され心願成就祈願の信者さんが沢山参詣されます。 また、当地方の女性は、安産腹帯を本尊薬師如来より授かる習わしが古来より伝えられており、更に母乳の出にくい母親は薬師如来よりいただけると御本尊へ祈願されます。 境内の三重塔(県重文)は当国唯一の塔建築で、文政四年 (1821)に再建されており、内陣には真言宗の御本尊大日如来が安置されている。 相応院:縁起 当院は明治以前までは隣にある桜山八幡宮の別当寺で長久寺と称しておりましたか、明治初年の排仏毀釈によって廃寺となりました。当時の住職兼神職でありました桜山識雄和尚は、代官所(高山陣屋)へお願い状を出して必死に仏教を守られました。 その結果高野山での飛騨の大名金森家の菩提寺であった相応院が飛騨の国との御縁でその寺号と金森可長近公寄進の雲上阿弥陀三尊・涅槃図・不動尊図等を譲り受け、現在地に本堂を建立致しました。長久寺は高山の裏鬼門に当るので不動尊像をお祀りして鬼門除けと住民の安全等を祈願する神仏混淆のお寺でしたので、その不動尊像・弘法大師像・歓喜天像・聖観音像・十一面千手観音像・弥勒菩薩像等をお祀りしております。又、当院には円空仏が二体あります。一体は稲荷さんで、もう一体は薬師如来です。高山市史に長久寺は山伏寺とも書いてありますので、円空さんも飛騨へ来られた折に立ち寄られ、何体か刻まれた事と思いますが前述のとおり排仏毀釈で古文書等はなく、縁起は代々伝わっている話のみです。 円空薬師如来は本堂左側にお祀りしてあり、裏山には修行大師像がお祀りしてあります。 清傅寺:縁起 当山は、清寧天皇(480)までさかのぼると記されていますが、富山での大火で一部が焼失し、詳しいことは解りません。 又、白山開山と伝えられる泰澄和尚が創設したお寺とも言われております。天平年間 聖武天皇のころ、皇帝健康にすぐれなく、ある時、泰澄和尚が、白山の麓に一堂を創設し、皇帝の病気平癒、国家泰平、万民安穏、五穀豊穣を祈念し、日々白山を見奉り、供養したところ、元気になられた。その後も泰澄和尚は御堂に籠り祈願を続けたと言うことです。堂守六代まで焼きましたが、八十二代後鳥羽帝の時、国乱が起り堂守中絶していたのを、永享五年三月、無量寿院賢興大僧正の高弟子、成伝律師が再興しました。 その後加賀の守、前田家の祈願所となり、次男利次が富山藩として分家した時、富山へ移り、代々領主の祈願所となっておりました。しかし明治の改正により寺録を失い、同十三年の大火で殆ど焼失、その後、当山第19世下切弘道和尚により飛騨に移され現在に至っております。 白山の仏の本地は十一面観音菩薩で当山も本尊は十一面観音です。脇仏に薬師如来が祀られています。飛騨仏師「信二良」作です。形像は、鉢を持する薬師様で、法隆寺の薬師様によく似た面長の美しい面であります。寺伝によれば姫薬師と呼ばれ女性に信仰があります。 鍋山城:築城年代は諸説あり定かではないが、一般的には天文年間に平野豊後守安室によって築かれたと云われる。 平野氏は安室の父右衛門尉の時に信濃国より飛騨国へ入国し三仏寺城主となり、安室の時代に鍋山城を築城(または修築)してここに移り、鍋山氏を名乗ったと云う。 安室は家の安泰をはかるため、実子の左近大夫を差し置いて三木氏より三木自綱の弟顕綱を養子に迎えたが、顕綱は安室を毒殺して左近大夫をも追放した。 追放された左近大夫は越前国大野城の金森長近を頼って落ち、天正13年(1585年)羽柴秀吉の命によって飛騨国へ侵攻した金森長近に加わって三木氏を攻め、再び飛騨へ復帰することとなった。しかし金森氏の飛騨入封後、その処遇に不満があり広瀬氏・江馬氏などと呼応して一揆を起こすが、金森可重によって鎮圧された。 飛騨国を制圧した金森長近はこの鍋山城へ入って政務を行ったが、高山城を築いて居城を移し廃城となった。 高山城:築城年代は定かではないが永正年間(1504~1521年)に高山外記によって築かれた天神山城が前身である。高山氏は飛騨国守護京極氏の家臣で守護代をつとめた多賀出雲守の一族という。 永禄元年(1558年)桜洞城主三木自綱と高堂城主広瀬宗城によって高山氏は滅ぼされると、自綱は叔父の三木久綱を天神山城主とし、天正7年(1575年)松倉城を築いて居城とした。 天正13年(1585年)三木自綱は越中の佐々成政と結んで羽柴秀吉と対立すると、羽柴秀吉の命によって越前国大野城主金森長近が飛騨国へ侵攻し、自綱は高堂城と広瀬城が落城すると降伏、最後に残った三木秀綱の籠る松倉城も落城して三木氏は没落した。 飛騨へ入部した金森長近ははじめ鍋山城を居城としていたが、天正16年(1588年)天神山城を改修して高山城と改称し居城とした。 元禄5年(1692年)金森氏六代金森頼時は出羽国上山へ転封となり、以後飛騨国は江戸幕府直轄領となって高山陣屋によって治められ、高山城は廃城となった。 松倉城:築城年代は定かではないが天正7年(1579年)頃に三木自綱によって築かれたと云われる。また一説に永禄年間(1558年~1570年)に自綱の父良頼の頃に築かれたとも云われる。 三木氏は応永18年(1411年)京極高員の代官として三木正頼が益田郡竹原郷に下向したことに始まると云われる。四代三木直頼のときに益田郡の大半を横領して桜洞城を築いて居城とした。五代良頼の時代になると大野郡へ進出して飛騨国司の姉小路家を滅ぼし、六代自綱のときには高原諏訪城主の江馬氏などを降して飛騨大半を平定した。 天正13年(1585年)三木氏は秀吉と対立する越中の佐々成政と結んだことから、秀吉の命を受けた越前国大野城主金森長近の侵攻を受けた。このとき自綱は広瀬城におり、松倉城には秀綱が籠城して金森軍と戦ったが内応者が現れ落城し、秀綱は城を脱して信濃へ逃れる途中に土民に襲われ死んだという。 三木氏の後に飛騨に入封した金森氏は高山城を居城として築き、松倉城は廃城となったと云われるが、現在残る主郭部の石垣などの遺構は、他の三木氏に関係する城から高石垣などの遺構が確認できないこともあり、金森氏など織豊系の武将によって改修されたものとも考えられている。 萩原諏訪城:天正13年(1585年)佐藤秀方によって築かれた。 天正13年(1585年)越前国大野城主金森長近は羽柴秀吉に命によって飛騨へ侵攻し、三木自綱を敗って飛騨を平定した。これによって金森氏は飛騨を与えられ高山城を築城して居城とし、姉婿の佐藤秀方に命じて桜洞城を廃して諏訪城を築かせこの地方を治めさせた。 元和の一国一城令によって廃城となったが、その後も金森旅館として存続する。しかし、元禄5年(1692年)金森氏が出羽国上山へ転封となると破却された。 禅昌寺:平安時代の創設と言われる臨済宗妙心寺派の禅寺。中国宋朝の様式を伝える建築物は「天下の名刹」として威容を誇っている。境内には金森宗和が造園した名勝指定の庭園「萬歳洞(ばんざいどう)」や茶室、雪舟筆の大達磨像等多くの寺宝の他、樹齢1200年を超える国指定天然記念物の大杉や勅使手植えのゆかりの梅など見どころ満載。予約をすれば座禅体験もできる。 温泉禅寺:縁起 文永二年(1265)湯ガ峰からの温泉の湧出が突然止まってしまう。その翌年、毎日のように飛騨川の河原に舞い降りる一羽の白鷺に村人が気づく。不思義に思った村人がその場へ行ってみると、温泉が湧いていた。空高く舞い上がつた白鷺は、中根山の中腹の松に止まり、その松の下には光輝く一体の薬師如来が鎮座していた・・・。これが下呂に伝わる白鷺伝説であり温泉寺開創の縁起である。 白鷺に化身し、温泉の湧出を知らせたこの薬師如来を本尊とするのが、瞥王霊山温泉寺である。下呂富士と呼ばれる中根山の中腹に建ち、創建は寛文十一年(1671)。江戸元禄期以降、北海道開拓に尽力したことで知られる初代飛騨屋久兵衛の父、武川久右衛門倍良が、萩原・禅昌寺八世剛山和尚を開山に迎え、建立した寺である。下呂温泉を、草津・有馬とともに天下三名泉として初めて全国に紹介したのが、室町時代の五山僧・万里集九である。(「梅花無尽蔵」より)以来、下呂温泉にはたくさんの湯治客が訪れるようになり、江戸中期には年間三万人を数えた。温泉寺にも、花柳病などの湯治客がお籠りし、朝夕薬師如来を拝みつつ、湯治の未、無事病気平癒した人達の残した絵馬が、今でも本堂に数多く残されている。また、願い叶わずこの地で命絶えた人達の過去帳も残っている。 17:00終了、帰路に向かう。 今回の旅行、岐阜県に点在する中部四十九薬師霊場10か所、お城11か所を訪れ楽しみました。 霊場は立派なものが多く、城跡は案内が十分でなく、たどり着くのに時間がかかりました。 帰りの高速道路、紅葉帰りの車が多く渋滞に巻き込まれ時間がかかりました。 |
           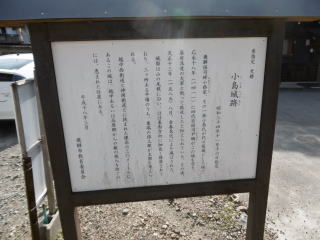          |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百五十一弾:栃木県お城・城下町巡り観光 2018年10月27-28日 今回は北関東地方に位置し、県庁所在地は宇都宮市、県内には日光国立公園が立地し、日光・那須などの観光地・リゾート地を有する栃木県に足を運び、栃木県に点在する比較的マイナーなお城10か所を訪れました。 27日13:50新大阪新幹線のぞみで出発 16:25東京駅到達 16:35東京駅新幹線やばびこで出発 17:26宇都宮駅到達、駅前のホテル到着後友人と食事を済せる。 23:00就寝。 28日8:00レンタカーで出発、城めぐり。 西明城:築城年代は定かではないが益子氏によって築かれたと云われる。 益子氏(ましこ)は「下野国誌」によれば「康平年間(1058年~1065年)に紀正隆が益子那流山の山麓に益子城を築き、のち山上に住した」とある。つまり始め益子城を築き、その後に西明寺城を築いて住んだと解釈されているが定かではない。 益子氏は紀伊姓で、同じく宇都宮氏の家臣の清原姓芳賀氏とともに、紀清両党と呼ばれ鎌倉時代から南北朝時代にかけて宇都宮氏の重臣として活躍した。 天正17年(1589年)益子氏は笠間氏を攻めるなど主家宇都宮氏に叛いたとされ、宇都宮国綱は芳賀高定らと謀って益子氏を誅伐して所領は没収され、益子氏は滅亡したという。 茂木城:築城年代は定かではないが建久年間(1190年~1199年)に茂木三郎知基によって築かれたと云われる。 茂木氏は八田知家が源頼朝より得た下野国茂木保の地頭職を三男知基に譲り、茂木氏を名乗ったことに始まる。 建武3年(1336年)茂木知貞・知世父子は北朝方として各地を転戦するが、留守中に南朝方の北畠顕家に攻められた。 天正13年(1585年)北条氏政によって茂木城は一時奪われたが、佐竹義重によって奪い返された。文禄3年(1594年)茂木治良は佐竹義重の命によって常陸国小川城に転封となり、代わって佐竹家臣の須田盛秀が茂木城代となったが、慶長7年(1602年)佐竹義宣が秋田へ転封となり廃城となった。 村上城:永和4年(1378年)村上新助良藤によって築かれたと云われる。 村上氏は益子氏の一族で、良藤が築城したのち村上丹波守則光、村上丹波守光義と三代にわたる居城であったと伝えられる。 烏山城:築城年代は定かではないが那須氏によって築かれた。築城に関しては応永24年(1417年)那須資重が烏山城を築いて稲積城より移った説と、明応年間(1492年~1501年)に那須資実が築いたとする説がある。 那須資氏の二男資重は沢村城主沢村氏の家督を継いで八代沢村五郎資重と名乗ったが、福原城の本家を継いだ兄那須資之との不和により応永21年(1414年)沢村城を攻められ、資重は烏山に逃れた。 資重は当初興野氏の館に住み、その後稲積城を修築して移り、応永25年(1418年)には烏山城を築いて居城とした。(烏山築城は資重の孫資実との説もある)資重の子資持が那須に復姓して下那須家となり、那須家は本家上那須家と下那須家に分かれて争うようになった。その後、那須家は下那須房資の代に上那須家が滅亡して(亀山城を参照。)下那須家が本流となっている。 天正18年(1590年)豊臣秀吉の小田原征伐で那須資晴は参陣せず、小田原城落城後にようやく秀吉に参謁したが遅参により所領を没収された。那須氏はその後、資晴の子資景が五千石を賜り福原要害城を居城として再興している。また晴資自身も所領が与えられ文禄元年(1592年)には肥前国名護屋に二百五十の兵を引き連れて参陣している。 那須氏が改易されると天正18年(1590年)尾張国清洲から織田信雄が二万石で転封となるが、二ヶ月程で天正19年(1591年)秋田へ転封となった。 那須神田城:天治2年(1125年)須藤権守貞信によって築かれたと云われる。 須藤権守貞信は那須氏の祖とされる人物であるが、その出自については山内首藤氏や那須国造後裔など諸説あって定かではない。 那須資高の十一男は、かの有名な那須与一宗隆で、元暦2年(1185年)源平合戦では源義経に従い、屋島合戦で舟の先端の竿に付けられた日の丸の扇を馬上より弓で見事に射落としその名を轟かせた。その後、源頼朝より那須家の惣領を継ぐよう命じられている。この時、与一は兄弟に所領を分知し那須十氏となった。 ・長男太郎光隆は森田の地を与えられ森田城主森田氏を称す。 ・二男次郎乗隆は佐久山の地を与えられ、佐久山城主作山氏を称す。 ・三男三郎朝隆は芋渕の地を与えられ芋渕氏、その後裔は梁瀬に移り梁瀬氏を称す。 ・四男久隆 ・五男五郎之隆は福原の地を与えられ福原城主福原氏を称すが、与一宗隆の跡を継いで宗家となり、那須氏が上下に分かれた時は上那須氏となった。 ・六男六郎真隆は滝田の地を与えられ滝田城主滝田氏を称す。 ・七男七郎満隆は沢村の地を与えられ沢村城主沢村氏と称す。那須家が上下に分かれた時には下那須家となり烏山城を居城とした。 ・八男八郎義隆は堅田の地を与えられ山田城主堅田氏と称す。その後、片平へ移り片平城主片平氏を名乗った。 ・九男九郎幹隆は稗田の地を与えられ稗田氏を称す。 ・十男十郎為隆は千本の地を与えられ千本城主戸福寺氏を称す。後に千本氏を名乗る。 武茂城:築城年代は定かではないが正応・永仁年間(1288年~1299年)頃に武茂泰宗によって築かれたと云われる。武茂氏は宇都宮城主宇都宮景綱の三男泰宗が武茂郷を領して武茂氏を称したことに始まる。 応永14年(1407年)武茂綱家は子の持綱を宗家宇都宮満綱の養子とし、宗家の家督を継がせた。応永30年(1423年)宇都宮持綱は、持綱が宗家を継いだことに不満を持っていた川崎城主塩谷教綱によって梨木坂で討たれた。持綱の遺児等綱はわずか四歳で、家臣に添われて佐竹を頼って逃れたが、永享10年(1438年)祖父武茂綱家が後見人となって等綱は宇都宮の家督を継いでいる。 持綱が宇都宮宗家の家督を継いだため武茂氏は断絶していたが、寛正3年(1463年)持綱の曾孫にあたる芳賀兵衛成高の子正綱が、武茂太郎を称して武茂氏を再興した。しかしこの正綱も宇都宮明綱(等綱の子)が嫡子なく没した為に、宇都宮氏の家督を継ぎ武茂氏は再び断絶した。 永正3年(1506年)正綱の子兼綱が武茂氏を再興した。この兼綱は武茂右衛門五郎と称して武茂郷一万石を領した。 その後、武茂氏は佐竹氏と那須氏の対抗の狭間にたち、永禄3年(1560年)頃に佐竹氏に属した。文禄4年(1595年)武茂豊綱・堅綱は久慈郡大賀村に八百石を与えられて所替えとなり、代わって佐竹家臣太田五郎左衛門資景が武茂城主となった。 関ヶ原合戦後、佐竹氏は秋田へ転封となり、武茂堅綱もそれに従って秋田へ移った。 黒羽城:天文12年(1543年)大田原資清によって築かれた。 大田原氏は那須七騎の一つに数えられ、資清のときに水口館から大田原城を築いて居城を移しており、それまでの「大俵」から「大田原」氏へと名を改めた。 天正18年(1590年)大田原晴清は、豊臣秀吉の小田原征伐に際して、大田原氏は主家那須氏に先んじて小田原に参陣し、沼津の陣営で豊臣秀吉に謁見、本領七千石余を安堵された。 慶長5年(1600年)関ヶ原合戦においては、上杉氏の動向を探り、また上杉氏に対する備えとして徳川氏の支援を受けて城を拡張した。慶長7年(1602年)には四千五百石余を加増され、併せて一万二千石余となって大名に列した。 大田原藩は寛文元年(1661年)三代大田原高清が家督相続したとき、弟為清に一千石を分与して一万一千石余となり、以後代々続いて明治に至る。 芦野城:築城年代は定かではないが芦野氏によって築かれた。 築城に関しては二つの説があり、一般的に前者の方が有力とされている。 天文年間(1532年~1555年)に芦野資興が太田道潅に兵法を学び芦野城を築いたという説と、天正18年(1590年)に芦野盛泰が築いた説である。 芦野氏は正平年間(1346年~1370年)に那須資忠の三男(あるいは二男)資方(あるいは資宗)が芦野家を継いだことがわかっているが、それ以前については詳らかではない。しかし、吾妻鏡の建長元年(1256年)6月2日の条に「奥の大道を警固するべき路次の地頭」として芦野地頭があり、芦野館を居城とした人物がいたことは確かなようである。 天正18年(1590年)那須七騎の一人芦野盛泰は、主家烏山城主那須資晴には従わず、那須衆として豊臣秀吉の小田原城攻めに参陣し本領を安堵された。 慶長5年(1600年)関ヶ原合戦では徳川家康に属して上杉景勝の南下に備え、その功によって加増され約三千石を領して交代寄合の旗本となった。この時、芦野城の二の丸に陣屋が構えられ芦野陣屋として代々芦野氏が続き明治に至る。 大田原城:天文12年(1543年)大田原資清によって築かれた。 大田原氏は那須七騎の一つに数えられ、資清のときに水口館から大田原城を築いて居城を移しており、それまでの「大俵」から「大田原」氏へと名を改めた。 天正18年(1590年)大田原晴清は、豊臣秀吉の小田原征伐に際して、大田原氏は主家那須氏に先んじて小田原に参陣し、沼津の陣営で豊臣秀吉に謁見、本領七千石余を安堵された。 慶長5年(1600年)関ヶ原合戦においては、上杉氏の動向を探り、また上杉氏に対する備えとして徳川氏の支援を受けて城を拡張した。慶長7年(1602年)には四千五百石余を加増され、併せて一万二千石余となって大名に列した。 大田原藩は寛文元年(1661年)三代大田原高清が家督相続したとき、弟為清に一千石を分与して一万一千石余となり、以後代々続いて明治に至る。 御前原城:築城年代は定かではないが、伝承によれば治承・寿永年間(1177年~1185年)頃に堀江左衛門尉頼純によって築かれたと云われる。 堀江氏は源姓塩谷氏(しおのや)ともいい、八幡太郎義家の後裔で頼純が祖という。 五代塩谷朝義は宇都宮頼綱の弟朝業を養子に迎えて家督を譲った。塩谷朝業は正治・建仁年間(1199年~1204年)頃に川崎城を築いて居城を移したという。その後も塩谷氏の支城となっていたようで、四郎左衛門尉泰朝が城主となっている。 17:00終了。宇都宮駅に向かう。 17:30宇都宮駅到達。 17:58宇都宮駅新幹線やまびこで出発 18:48東京駅到達 19:00東京駅新幹線のぞみで出発 21:37新大阪駅到達。 今回の旅行、北関東に位置する栃木県に足を運び、栃木県に点在する比較的マイナーなお城10か所をおとずれ楽しみました。 各城跡は、遺残物は少なかったが、案内板がしっかりあり、たどり着くのが容易でした。ほとんどが城址公園に変貌しており整備され散策が気持ちよくできました。 今回で東日本の城跡、ほぼ制覇しました。残るは西日本の5都道府県の城跡を残すのみとなり、年内に制覇予定です。 |
        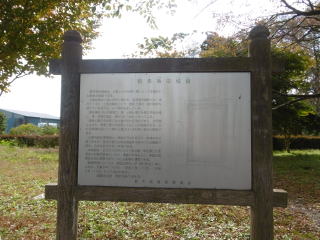  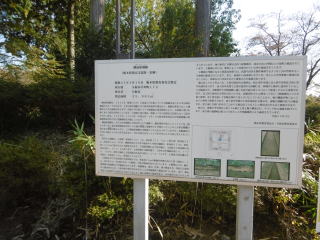      |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百五十弾:石川県お城・城下町巡り観光 2018年10月20-21日 北陸地方に位置し加賀百万石の城下町・金沢市には、季節を問わず、常に美しい景色が見られるよう設計された「兼六園」をはじめ「金沢城」「ひがし茶屋街」「近江町市場」など、加賀藩の栄華を今に伝えるスポットが点在。能登半島ならではの日本海の美しさを堪能するなら「千里浜なぎさドライブウェイ」や「聖域の岬(珠洲岬)」「巌門」ヘ足を伸ばすのもおすすめです。「鶴仙渓」や白山神社の総本山「白山比咩神社」など、内陸の見どころも見逃せません石川県に足を運び、石川県に点在する比較的マイナーなお城11か所を訪れました。 20日13:20大阪駅サンダーバードで出発 16:35金沢駅到達、レンタカーで小松方面にむかう。 お城巡り 松任城:築城年代は定かではないが鏑木氏によって築かれたと云われる。 天正5年(1577年)上杉謙信が侵攻したが落城せず、和議となった。 天正8年(1580年)若林長門守が加賀に侵攻した織田軍と交戦し謀殺され落城した。 天正11年(1583年)前田利長が四万石で越前府中から移ったが、天正15年(1587年)豊臣秀吉の直轄領となった。 その後、丹羽長重が城主となるが、関ヶ原合戦後に再び前田利長に加増され赤座吉家が城代となり、慶長19年(1614年)廃城となった。 17:40粟津市内のホテル到着後繫華街を散策し食事を済ませて就寝。 21日7:30レンタカーで出発、お城巡り。 大聖寺城:築城年代は定かではないが鎌倉時代に築かれた。 現在の縄張になったのは、天正11年(1583年)に四万四千石で入封した溝口秀勝の頃という。 慶長3年(1598年)秀勝は越後国新発田に移封となり、替わって小早川秀秋の家臣山口玄蕃が入封した。 関ヶ原合戦で豊臣方に付いた玄蕃は徳川方の前田利長に二万五千もの大軍で攻められ、一日にして落城した。 その後、一度修復されたものの元和の一国一城令で廃城となった。 寛永16年(1639年)3代加賀藩主前田利常の子利治に七万石を分地して、大聖寺藩が興された。 大聖寺藩は大聖寺城を使用せず、東麓に館を構えた。 波佐谷城:築城時期は定かではないようですが、一向一揆方の宇津呂(打尾)丹波という人物が築城したと伝えられます。天正八年(1580年)の柴田勝家の攻撃で落城しました。その後、小松城に入った村上勝頼が支城として波佐谷城に村上勝左衛門を入れたとされます。慶長三年(1598年)に村上氏は越後の本庄に転封され、この頃に波佐谷城は廃城になったと考えられます。 波佐谷には加賀一向宗の有力寺院の松岡寺がありました。この寺は蓮如の三男の蓮綱が建て、子の蓮慶がこの地に移したとされます。しかし、松岡寺は享禄四年(1531年)に一向宗の内紛で攻められて廃寺になったと伝えられます。 御幸塚城:築城年代は定かではない。 加賀南部の半国守護富樫泰高の居城とも云われ、天正4年(1576年)一向一揆方が、この城から出陣して織田軍を攻めたという。 織田信長は佐久間盛政を将として攻め、盛政配下の徳山則秀の策略で内応者を出し落とした。 慶長5年(1600年)関ヶ原合戦では東軍の前田利家の家臣が布陣し、西軍の丹羽長重と浅井畷で戦った。 小松城:築城年代は定かではないが天正年間初期(1573年~1592年)に若林長門守によって築かれたと云われる。 若林長門守は一向一揆の部将で天正7年(1579年)柴田勝家によって攻撃され落城した。 織田信長は六万六千石で村上頼勝を城主としたが、慶長3年(1598年)越後国本庄に移封となり、丹羽長重が十二万石で松任城から移った。 関ヶ原合戦では豊臣方に属し、徳川方の前田利長と交戦したが敗れて利長に降った。 関ヶ原合戦後、長重は改易となったが慶長8年(1603年)常陸国古渡に一万石で大名に復帰した。 それ以後、前田氏の持城であったが元和の一国一城令により廃城となる。しかし、寛永16年(1639年)加賀藩3代前田利常の隠居城として再び整備された。 和田山城:永正3年(1506年)和田坊超勝寺によって築かれたと云われる。 天正年間に越前一向一揆を破り加賀国に侵攻した織田軍により平定され、北庄城の柴田勝家の部将安井家清(左近)が城主となった。 岩倉城:築城年代は定かではないが享禄年間に一向一揆によって築かれたと云われる。 加賀国守護富樫氏を降した一向一揆に対抗して加賀に侵攻した朝倉氏に対する備えとして築かれたという。 織田軍による加賀侵攻では、鳥越城の前衛として攻防が繰り広げられ落城。織田氏方の拠点として改修されたといわれる。 二曲城:築城年代は定かではないが二曲右京進によって築かれたと云われる。 二曲氏は二曲村の土豪で代々この地に勢力を持っていたという。 織田信長が加賀一向一揆に侵攻すると、鈴木出羽守が白山麓山内衆の総大将として派遣され、鳥越城を築城して拠点を移し二曲城は三坂峠を押える支城となった。 天正8年(1580年)柴田勝家によって攻められ鳥越城とともに落城、鈴木一族は滅亡した。 勝家は鳥越城に吉原次郎兵衛、二曲城に毛利九郎兵衛を置き固めたが、白山麓一向一揆の抵抗は続き天正9年(1581年)に奪還された。 しかし、天正10年(1582年)織田信長によって一向一揆の掃討作戦が行われ、佐久間盛政によって鎮圧、門徒ら300人が磔に処せられた。 鳥越城:築城年代は定かではないが鈴木出羽守によって築かれた。 鈴木出羽守は加賀一向一揆白山麓山内衆の総大将として築城し、織田信長による加賀侵攻に対抗した。 天正8年(1580年)柴田勝家によって攻められ二曲城とともに落城、鈴木一族は滅亡した。 勝家は鳥越城に吉原次郎兵衛、二曲城に毛利九郎兵衛を置き固めたが、白山麓一向一揆の抵抗は続き天正9年(1581年)に奪還された。 しかし、天正10年(1582年)織田信長によって一向一揆の掃討作戦が行われ、佐久間盛政によって鎮圧、門徒ら300人が磔に処せられた。 舟岡城:築城年代は定かではない。 織田信長の加賀に侵攻に対応して、白山麓山内衆の大将鈴木出羽守の守る鳥越城への入口を固める為に修築されたといわれる。 天正8年(1580年)織田軍の加賀平定作戦で鳥越城とともに落城したという。 その後は丹羽長秀の家臣早谷五左衛門、前田利家の家臣高鼻石見守が城主となった。 高尾城:築城年代は定かではないが長享2年(1488年)以前に富樫氏によって築かれたと云われる。 富樫政親は加賀国守護であったが、次第に強力になる一向一揆に危機感を募らせ、将軍足利義尚に支援を要請して一向一揆に対抗しようとした。一向一揆方は政親の家老山川三河守を介して和睦を伝えたが、政親はこれを固持し高尾城を修築して備えた。 一揆方は越前・越中からの政親方の援軍に対する備えを行い、富樫泰高を大将として大乗寺に本陣を据えて高尾城を大軍で包囲した。政親は城内より討って出て一揆勢と戦ったが打開することはできず、頼みの援軍も加賀国境で一揆軍に退けられ政親は城内で自刃して果てたという。一説に高尾城から脱出して鞍ヶ嶽城に入ったが、そこで敗れて討死したとも伝えられる。 16:20終了、金沢駅に向かう。 17:30金沢駅到達 18:07金沢駅サンダーバードで出発 20:54大阪駅到達。 今回の旅行、北陸に位置する石川県に足を運び石川県に点在する比較的マイナーなお城11か所をおとずれ楽しみました。。 歴史的建造物が多く風情のある石川県、観光名所も多く、交通の便もよくなり、多くの観光客でにぎわっていました。マイナーなお城も比較的整備され案内板もしっかりあり、城址公園に変貌しているところが多く、整備され楽しく巡ることができました。 |
                |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百四十九弾:北海道八十八ヶ所三十三観音&お城観光 2018年10月13-14日 北の北海道に足を運び、富良野、帯広、網走、旭川のエリアに点在する北海道八十八ヶ所、三十三観音、お城8か所を訪れました。 13日15:30伊丹空港出発 16:40羽田空港到達 17:55羽田空港出発 19:35旭川空港到達、レンタカーで旭川市内のホテルに向かう。 20:50旭川市内のホテル到着後繫華街を散策し食事を済ませて就寝。 14日5:15レンタカーで出発富良野方面に向かう。 春宮寺:明治38年6月、炭屋実雄が京都から来道し、当現在地に説教所を開設したが、何か理由があったのか、2年後には後任者を決めて、説教所を去ることになる。 炭屋実雄が後任者の谷澤正道に宛てた手紙が何通が残っており、北海道行きをためらう谷澤正道を説得する苦心の跡がうかがわれる文面である。説教所は神楽岡の高台の続きにあり、離宮造営地として設定されただけあり、上川盆地と大雪山を一望に収める風光明媚の地だった。 明治44年、辛苦の中で「春宮寺」寺号公称の許可を得た。 春宮寺のいわれは、この辺一帯が御料地であったので、皇族の安泰を祈る気持ちから、皇太子を意味する春宮とした。 本堂は大正6年の建立。寺近くのアオダモの原生林を払い下げてもらい、用材とした。建築には金釘は1本も使わず、大木を上手に用い、木組みで造られている。 弘照寺: 明治34年頃、開拓で入植した大師信者が当時の上富良野村東中に大師堂を建立し、大師講を組織したのが当寺の前身であり、その後、明治38年富山県出身の岩田實乘が晋住し、真言宗説教所としたのが弘照寺の開創である。その後、寄進のあった現在地に堂宇を建立し、大正8年に移転をした。昭和6年寺号公称が許され、また、岩田實乘が目白僧園にて修行の折、師事をした釋雲照和上から山号を賜り、「慈雲山弘照寺」と称して現在に至る。 富良野寺:富良野寺の開基は前住職宮田戒応師の祖父宮田俊人で佐賀蓮池藩の下級武士宮田儀満の子である。 俊人がどんな理由で渡道を決意したかは不明だが、古丹別の説教所に空きのあることを高野山普賢院住職から知らされ、そのすすめもあってのことと想像されている。天塩国古丹別は日本海も稚内近くの海岸線から、数キロ山すそに入った小村だった。俊人が「北海道天塩国古丹別説教所担当依(ママ)嘱候事」なる辞令をたずさえ来道したのは明治三十九年、四十歳の夏である。しかし当時の古丹別が辺境の地でありすぎたことや、この土地の将来性などを考え早々に見切りをつけ、開教の適地を上川地方にもとめた。 上川地方の中心地旭川は軍都景気に沸き立ち人口が急増し、それが近郊にまでおよび各宗の説教所が布教を開始、教線がみごとに拡張されているのをみた。そこで俊人は情報を得るため現金峰寺の前身、真言宗布教所に秋山亮範を訪ね、富良野地方の開教の可能性を知らされた。 富良野駅に降り立つや俊人は托鉢をしながら市街を一巡すると、一夜の宿のお接待を受ける。 一介の托鉢の僧に温かくその日の宿をお接待したのは、倉前惣太だった。倉前惣太はしばらく俊人を自宅において面倒をみ、八月盆になると徳島や淡路出身の真言宗徒の家を教えて棚経に歩かせ、それが縁となって開創の気運が高まるのである。 俊人はここに布教所開創の決意をかため、秋に北海道をいったん離れ翌四十年五月家族と共に再渡道、ただちに仮り住まいの借家で布教活動を開始した。そのとき高野山から下付された弘法大師像は現在脇士として祭られている。大師像の台座の裏には「元文五庚申」(一七四〇)の記録がある。 帯広方面に向かう。 エクエピラチャシ:ユクエピラチャシは道内でも最大級のチャシ跡です。「ユク・エ・ピラ」とはアイヌ語で「シカ・食べる・崖」という意味です。陸別に伝わる英傑でリクンベツ(陸別)の首長、カネランにちなんで「カネランチャシ」とも呼ばれていますが、詳細はわかっていません。また、火山灰で覆われているため、まるで夏でも雪が残っているような白いチャシとしても知られています。 網走方面に向かう。 桂ケ岡チャシ:北海道網走市郊外のニクル丘陵にある北海道の先住民アイヌの築いた砦跡。「桂ヶ岡砦跡」が正式名称。国指定史跡。北海道内にはアイヌ民族が築いたチャシと呼ばれる砦の跡が700以上確認されているが、ニクル丘陵に残る桂ヶ岡チャシは大小2つのチャシからなる北筒式土器などを出土する集落跡をともなった大規模な砦跡で、大小2つの長円形、鏡餅状の郭跡や竪穴住居跡、貝塚などが残っている。アイヌ民族はかつて、この丘の上のチャシでチャランケ(談判)をしたことから「チャランケチャシ」などともよばれる。桜の名所として知られる桂ヶ岡公園内にある。同公園内には網走市立郷土博物館もある。 弘道寺:明治二十七年説教所として開設。以来六代の住職により大師の法燈が受け継がれてきております。 境内地の四脚門をくぐると右手に鐘楼堂・オホーツク曼茶羅(新四国八十八ヶ所)つつじ・石楠花の花園を巡り坂を上りきると修業大師がお迎えを致します。 旭川に向かう。 大照寺:明治28年讃岐(香川県)・伊予(愛媛県)の2団体が開拓に入植すると共に、郷里の雲風山国祐寺(現香川県三豊市)本尊のご分霊である聖観音を祀る小庵を結び、覚動和尚が錫を留め開創。以来、大師信仰を育む寺として信仰を集め、また、不動明王、弘法大師、十一面観音像は、何れも高野山より勧請した霊尊であります。 昭和62年には現本堂の建立、平成元年には、北海道三十六不動尊霊場第4番札所として、その法灯を輝かせ、1月17日の初本尊大護摩供には老若男女が所願成就を祈念し、多数の檀信徒の参詣があり、厄除招福宝剣加持により、その法縁に浴しています。 当山はオンコ(一位)の寺としても知られ、希望者には種を分けています。 大聖寺: 15:10旭川空港到達 16:20 旭川空港出発 18:10羽田空港到達 19:20羽田空港出発 20:35伊丹空港到達 今回の旅行、北の北海道に足を運び、富良野、帯広、網走、旭川に点在する、霊場、お城8か所を訪れ楽しみました。 走行距離600kmでドライブ観光、自然の中、渋滞なく、真っ直ぐな広い道、広大な敷地、平野の走行、ストレスなく、何回来ても最高の北海道のドライブ観光、満喫しました。 |
         |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百四十五弾:長野県お城城下町巡り観光 2018年9月8-9日 本州の中心部に位置し、今話題の真田家ゆかりの地であること、避暑地の定番としてあまりにも有名な軽井沢や、上高地などの大自然の絶景スポットがあることで知られています。近年では細田守監督のアニメ映画「サマーウォーズ」の舞台でもあります。日本一が多い県としても有名です。日本一長い川、日本一長い浮橋、温泉数、隣接する県の数などな。何よりスゴイのは長寿全国第1位の県。その秘訣は澄み切った空気や、綺麗な水、ヘルシーで美味しいグルメのおかげではないでしょうか?全国的に知られている「信州そば」や「信州みそ」、リンゴのサンふじ、シナノゴールドなどの名産品がもりだくさん、様々な温泉や、家族で楽しめるレジャー施設、松本城などの国宝もあり、見所も満載の地であるため、毎年訪れる人が絶えない長野県に足を運び長野県に足を運び長野県に点在する比較的マイナーなお城10か所を訪れました。 8日15:03新大阪新幹線のぞみで出発 15:53名古屋駅到達 16:00名古屋駅ワイドビューしなので出発 18:58長野駅到達、駅前のホテル到着後繫華街を散策し食事を済ませて就寝。 9日8:00レンタカーでお城巡り、松本方面に向かう。 葛山城:弘治元年(1555年)上杉謙信によって築かれた。 弘治元年7月善光寺平に出陣した上杉謙信は横山城に着陣した後、葛山城を築いて武田氏方の善光寺別当栗山氏の籠もる旭山城と対峙した。 上杉氏と武田氏の対峙は長期にわたり今川義元の仲裁によって和議となり、旭山城は破却された。 弘治3年(1557年)2月落合備中守ら葛山衆の籠もる葛山城を武田の家臣馬場信春が急襲して落城した。これに対して上杉謙信は旭山城を修復して拠点として葛山城を攻略するが、永禄4年(1561年)の川中島合戦の後、上杉氏らは善光寺平から退き、葛山城は武田氏の属城として長沼城の葛山衆が在番していた。 旭山城:築城年代は定かではない。史料による初見は天文24年(1555年)で、武田信玄が善光寺の別当栗田鶴寿を味方に引き入れると、上杉謙信が葛山城を拠点とし、信玄は旭山城に兵三千と弓八百張、鉄砲三百挺を送り込んで対応した。このときは長期戦となり、今川義元の仲介により和睦、その条件として旭山城の破却が盛り込まれていた。 弘治3年(1557年)武田信玄は葛山城を急襲して攻め落とすと、今度は上杉謙信が旭山城を修築して拠点とし武田氏と対峙した。 永禄4年(1561年)の川中島合戦の後、上杉方の守将小柴見宮内を討った武田氏が旭山城を占拠した。その後は海津城や長沼城が重要拠点となっていった。 牧之島城:築城年代は定かではないが香坂氏によって築かれたと云われる。 滋野系香坂氏代々の居城であったが、川中島合戦で上杉氏に通じたため、永禄4年(1561年)武田信玄によって香坂氏は誅され、その名跡は娘婿の春日弾正虎綱が継いだ。 その後、深志城主馬場信房によって牧之島城は改修され城代となる。天正3年(1575年)長篠合戦で馬場信房が討死すると、翌年にはその子馬場昌房が城将となり、上尾城主の平林正恒も在城した。天正10年(1582年)武田氏が滅亡すると、上杉景勝が牧之島城を奪い芋川親正を置いた守らせたが、慶長3年(1598年)上杉氏の会津転封により移っていった。 慶長8年(1603)松平忠輝が松代城主となると家老を置いて守られせたが、元和元年の一国一城令によって廃城となった。 木舟城:詳細不明。仁科氏の初期の居館である館之内館の背後のあることなどから、比較的早い時期の仁科氏の詰城とみられている。 青柳城:築城年代は定かではないが建暦年間(1211年~1213年)頃に青柳氏によって築かれたと云われる。 青柳氏は伊勢神宮の麻績御厨預職としてこの地に根付いた一族と云われる。 青柳氏は信濃守護小笠原氏に従っていたが、天文22年(1553年)武田氏が苅谷原城を攻略し、川中島方面に侵攻したとき、青柳氏は武田氏に降ったが、その後、上杉氏によって攻められ放火された。 青柳氏は武田氏に属した後、麻績城主となって麻績氏を称していたが、天正10年(1582年)武田氏が滅亡し織田信長が本能寺の変で倒れると、一時越後の上杉景勝に従った。しかし、徳川家康の援助を受けた小笠原貞慶が松本に復帰すると、青柳氏は再び小笠原氏に従った。 天正11年(1583年)上杉景勝が青柳に侵攻すると、小笠原貞慶とともに上杉軍と戦ったが大敗し青柳城は落城した。しかし、景勝は急遽陣払いをして越後へ戻ったため、再び青柳氏が再び青柳城主となった。ところが、天正15年(1587年)青柳頼長は小笠原貞慶によって松本城で謀殺され、青柳氏は滅亡してしまう。青柳氏滅亡後は小笠原氏家臣の松林氏が在城した。 平瀬城:築城年代は定かではないが平瀬氏によって築かれたと云われる。 平瀬氏は犬甘氏の一族で犬甘氏とともに小笠原氏に従っていた。 天文20年(1551年)武田氏によって攻め落とされ城兵二百四人が討ち取られた。 その後、武田氏は栗原左衛門に命じて城割(破却)し、鍬立て(築城)が行われ原美濃守が在城した。 林城:長禄3年(1459年)小笠原清宗によって築かれたとも云われるが定かではない。 信濃国守護職を代々務めていた小笠原氏の本城である。小笠原氏は井川城を本城として長く続いたが、戦国時代に入って平城である井川城から山城である林城を築いて移ったものとみられている。 甲斐を統一した武田信玄は信濃へ侵攻をはじめ、天文17年(1548年)塩尻峠の合戦で小笠原長時は武田軍に敗れた。武田氏は松本平の拠点として村井城を築き林城攻めの拠点とした。 天文19年(1550年)武田氏がイヌイの城を落とすと、小笠原氏の大城・深志・岡田・桐原・山家の五か所の城は自落したという。このとき小笠原長時は北信濃の村上義清を頼って落ちのびた。 桐原城:寛正元年(1460年)桐原真智によって築かれたと云われる。 天文19年(1550年)武田氏がイヌイの城を落とすと、小笠原氏の大城・深志・岡田・桐原・山家の五か所の城は自落したという。 山家城:築城年代は定かではないが鎌倉時代末期に山家氏によって築かれたと云われる。 最初に築城した山家氏は諏訪氏系の一族で、元弘元年(1331年)に徳雲寺を創建した神為頼の末裔が山家氏を称した。 諏訪系山家氏は、文明12年(1480年)小笠原長朝に叛いて攻められ、翌13年に諏訪氏の援護を受けたが敗れて滅亡した。その後、永正2年(1505年)頃に播磨国姫路より小笠原氏と同流の折野薩摩守昌治が来住し、小笠原貞朝に属して山家城を居城とし山辺氏を称した。 折野山辺(山家)氏は昌治の後、越前守昌寛、源十郎昌実、藤九郎昌矩と四代続く。 天文19年(1550年)に武田信玄が小笠原氏を攻めたとき、イヌイの城が落城すると、この山家城も自落し武田氏に降っている。 埴原城:築城年代は定かではないが村井氏(埴原氏)によって築かれたと云われる。村井館に住んで村井氏を称した埴原氏によって築かれたと云われる。小笠原氏が信濃守護職となって府中に入るとそれに属した。 天文19年(1550年)武田氏がイヌイの城を落とすと、小笠原氏の大城・深志・岡田・桐原・山家の五か所の城は自落したという。この「イヌイの城」が埴原城ではないかと考えられている。 18:30松本駅到達。 19:07松本駅ワイドビューしなので出発 21:21名古屋駅到達 21:30名古屋駅新幹線のぞみで出発 22:20新大阪到達。 今回の旅行、本州の中心に位置する長野県に足を運び、長野県に点在する比較的マイナーなお城10か所を訪れ楽しみました。今回も地味な城跡でしたが、比較的道路は山城に向かうには険しくなく容易にたどり通ことができました。 城跡、残すはあと100を切りました。今年中に達成予定です。 |
       |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百四十四弾:北海道八十八ヶ所霊場&三十三観音&お城城下町巡り観光 2018年9月1-2日 日本の北端、北海道道東地方に足を運び、道東地方に点在する北海道八十八ヶ所霊場、三十三観音、お城7か所を訪れました。 1日15:30伊丹空港出発。 16:40羽田空港到達。 17:45羽田空港出発。 19:20釧路空港到達、レンタカーで釧路市内に向かう。 18:00釧路市内のホテル到着後?華街を散策し食事を済ませて就寝。 2日5:00レンタカーで出発、霊場、OK城めぐり。 チャシ:アイヌ語で「柵囲い」を意味し、砦、祭祀の場、見張り場など多目的な用途で使われていたとされます。 |
            |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百四十二弾:長野県お城・城下町巡り観光 2018年8月4-5日 本州の中心部に位置し、日本アルプスの山岳に囲まれ「神が降りる地」と呼ばれるほど美しい上高地に代表される自然の宝庫。槍ヶ岳や霧ヶ峰など四季折々の表情を見せる名峰に加え、山々に抱かれた温泉地も多く、白骨温泉、湯田中温泉、渋温泉、野沢温泉といった名高い温泉地が点在しています。また、長野市には「一生に一度は善光寺詣り」とうたわれた善光寺があり、松本市には国宝松本城が鎮座しています。おやき、そばといった素朴な郷土料理が多いのも特徴的な長野県に足を運び長野県に点在する比較的マイナーなお城9か所を訪れました。 4日13:53新大阪駅新幹線のぞみで出発 14:50名古屋駅到達 15:00特急しなので出発 18:05長野駅到達、駅前のホテル到着後?華街を散策し食事を済ませて就寝。 5日8:00レンタカーで出発。お城巡り。 井上城:築城年代は定かではないが井上氏によって築かれたと云われる。 井上氏は鎌倉時代に清和源氏頼信の子頼季がこの地に来住して井上氏を称したのが始まりとされる。 鎌倉時代から南北朝時代にかけての活動は詳らかではない。室町時代に入ると井上十六郷の井上政家、小柳・亘理の井上政満、長池郷の井上為信などが登場する。戦国時代には井上氏は衰退しており、綿内井上氏が須田信正に属していたといわれる。 飯山城:築城年代は定かではないが泉氏によって築かれたと云われる。 泉氏は鎌倉時代に泉小次郎親衡が鎌倉より飯山へ逃れて土着し、泉氏の祖となったと伝えられる。 永禄7年(1564年)頃、上杉謙信は飯山城を改修して武田氏の侵攻に備えた。 その後、武田信玄は長沼城を拠点として飯山城攻略を目指したが、飯山城が落城することはなかった。 その後、武田勝頼の時代に武田氏の属城となったが、天正10年(1582年)武田氏が滅亡した後は織田氏が占拠した。しかし、本能寺の変により織田勢が退くと上杉景勝の所領となり、家臣岩井信能が城主となった。慶長3年(1598年)上杉景勝の会津転封に従い岩井氏は会津に移った。 霞城:築城年代は定かではないが大室氏によって築かれたと云われる。 天正10年(1582年)武田氏滅亡後、織田信長の武将森長可に従ったのもつかの間、信長も本能寺の変に倒れ、越後の上杉景勝にに従った。 慶長3年(1598年)上杉景勝が会津へ転封となると大室氏もこれに従って移り千五十石を領した。 鷲尾城:鷲尾城は倉科の石杭地区の北背後に聳える標高520m程の山に築かれている。 主郭は板状の石を高く積み上げた石積がほぼ全周しており、南端に虎口を開く。主郭の西から南に犬走があり、それが虎口へと繋がっている。主郭から北東へ伸びた尾根は自然地形に近い曲輪があり、二箇所を二重堀切で遮断している。また、主郭から北西に降りる尾根にも堀切、さらに下方に小さな平段が連なっている。 主郭から少し登った所に前方後円墳である倉科将軍塚古墳があるが、この古墳を曲輪として東背後の尾根に二箇所大堀切を設けている。 葛尾城:築城年代は定かではないが南北朝時代末期頃に村上氏によって築かれたと云われる。 村上氏は清和源氏頼信流で嘉保元年(1094年)に源盛清が信濃国更級郡村上郷に流罪となり、その子為国が村上氏を称したことに始まるといわれる。 戦国時代の村上義清の頃には北信濃一帯に勢力を拡げ、天文17年(1548年)の上田原合戦、天文19年(1550年)の戸石城合戦と甲斐の武田信玄を二度敗っている。しかし、天文20年(1551年)戸石城が武田信玄に与していた真田幸隆によって落城し、天文22年(1553年)には一族の屋代氏などが武田氏方に寝返るなど圧迫され、村上義清は越後の上杉謙信を頼って落ち、葛尾城は自落した。その後、義清は越後の援軍を得て葛尾城を攻め落とし、塩田城に入って再帰を計ったが武田氏に敗れ再び越後へ落ちていった。 戸石城:本城、桝形城、米山城の総称。 真田館:築城年代は定かではない。伝承によれば真田信綱の居館とされる。 真田氏累代の居館と考えられており、天正11年(1583年)真田昌幸が上田城を築いて居城を移すまでの居館であった。 昌幸が上田城に移ったあとに屋敷跡に勧請したのが皇太神社と伝えられる。 平賀城:築城年代は定かではないが平賀義信によって築かれたと云われる。 平賀氏は新羅三郎義光の子義盛が平賀に館を構えて平賀冠者を名乗り、その子義信によって平賀城が築かれたと伝えられている。 義信の長男惟義は伊賀国守護を務めて大内冠者と呼ばれ、二男平賀朝雅は北条時政の娘を娶り京都守護職を務めるなど、源頼朝に従って要職を務めた。 応永7年(1400年)大塔合戦では佐久郡の他の国人領主とともに、守護小笠原長秀と戦っている。その後、小笠原氏系の大井氏と争うようになり文安3年(1446年)大井氏によって滅ぼされたと云う。 龍岡城:文久3年(1863年)(大給)松平乗謨によって築かれた。 乗謨は三河国奥殿藩八代藩主で三河国に四千石、信濃国佐久郡に一万二千石の合わせて一万六千石を領していた。飛領地である佐久郡の所領を管轄する陣屋ははじめ三塚村に置かれていたが、宝永6年(1709年)以降に田野口村に移されていた。 文久3年(1863年)領地が手狭で大半の所領が佐久郡にあることを理由に居城を移す事を許され築いたのが龍岡城で、日本ではここと北海道にしか存在しない稜堡式五稜郭として縄張された。慶応3年(1867年)完成し田野口藩となったが、明治維新直前に龍岡藩と改称され、財政困窮を理由に廃藩置県前に廃藩となった。 16:30終了。 17:00長野駅特急しなので出発。 20:50名古屋駅到達。 21:05名古屋駅新幹線のぞみで出発。 21:55新大阪駅到達。 今回の旅行、本州の中央に位置し、日本アルプスに囲ませ、自然の宝庫、長野県に足を運び長野県に点在する比較的マイナーなお城9か所をおとずれ楽しみました。 山城が多く、一部は公園に変貌していました。今回も比較的地味なお城巡りでした。 |
               |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百四十一弾:富山県お城・城下町巡り観光 2018年7月21日-22日 北陸地方の南北にのびる日本列島の中心、本州の中央北部に位置し、東は新潟県と長野県、南は岐阜県、西は石川県に隣接しています。三方を急峻な山々にかこまれ、深い湾を抱くように平野が広がっており、富山市を中心に半径50kmというまとまりのよい地形が特徴です。 また、日本海側の中央に位置する本県では、アジア大陸や朝鮮半島など対岸諸国との古くの交流の積み重ねを活かし、環日本海地域の中央拠点として活発な取組みを展開しています富山県に足を運び、、富山県に点在する比較的マイナーなお城7か所を訪れました。 21日15:42大阪駅サンダーバードで出発 18:26金沢駅到達。 18:40金沢駅新幹線つるぎで出発。 18:53新高岡駅到達、駅前のホテル到着後周辺を散策し食事を済ませて就寝。 22日8:00レンタカーで出発、城めぐり。 守山城:築城年代は定かではないが南北朝時代に桃井直常によって築かれたと云われる。 室町時代には守護畠山氏の守護代神保氏の居城放生津城の詰城としての役割があり、永正16年(1519年)越後の長尾為景が越中に侵攻した際に、神保慶宗はこの城に籠って対抗した。神保氏は天正年間(1573年~1592年)に神保氏張が上杉謙信に降り、謙信没後は佐々成政に従った。 天正13年(1585年)佐々成政が羽柴秀吉に降ると、前田利長が入城し慶長2年(1597年)富山城に居城を移すまで在城した。 阿尾城:築城年代は定かではない。 天正年間(1573年~1592年)の城主は菊池右衛門入道武勝・十六郎父子であった。菊池氏は肥後国の菊池氏の末葉という。 上杉謙信没後、菊池氏は織田信長の家臣佐々成政に従っていたが、成政が前田利家と対立するようになると利家の勧誘を受けて前田氏に通じた。これに対して成政の家臣で守山城主の神保氏張は阿尾城に攻め寄せたが、前田軍と菊池軍でこれを撃退した。 菊池氏は一万石を安堵され前田氏に従い、その末裔は一千五百石で加賀藩に仕えた。 森寺城:築城年代は定かではないが永正年間(1504年~1521年)に能登国守護畠山氏によって築かれたと云われる。 元亀年間(1570年~1573年)から天正年間(1573年~1592年)はじめ頃の城主は長沢(長曾)光国と伝えられ、天正5年(1577年)には上杉謙信に属して能登国穴水城の守将となっていたが、翌年討死している。 天正5年(1577年)上杉謙信は有坂備中に湯山城を攻略させたが、このときの城主は湯山左衛門続甚という。謙信はその後河田主膳を城主としたが、天正7年(1579年)長連龍によって攻められ落城した。 佐々成政が越中に入部した後は、湯山城主として斎藤氏が城主であったが、豊臣秀吉に降伏した後は前田利家の所領となり、廃城となったと見られている。 木舟城:築城年代は定かではない。 石黒荘を本拠とした石黒氏が南北朝時代以前に進出して木舟城を築いて居城とし、木舟石黒氏となったと云われる。 本流福光石黒氏が文明13年(1481年)山田川で一向一揆との戦いで滅亡したのに対し、木舟石黒氏は戦国時代まで続き、石黒左近蔵人の時代には一大勢力を築いていた。 石黒氏は上杉氏に属していたが上杉謙信が急死した後は織田信長に通じ、天正9年(1581年)上杉氏によって攻められ落城した。石黒氏は織田信長に呼び寄せられ近江国長浜にて討たれた。木舟城を手に入れた上杉氏は吉江宗信を城将として守らせていたが、後に織田信長に奪われ佐々成政の支城となった。 天正13年(1585年)羽柴秀吉による越中平定で佐々成政が降伏すると、前田利家の弟前田秀継が入城したが、同年十一月の大地震によって秀継夫妻は没し、子の利秀は翌天正14年に今石動城に居城を移し廃城となった。 一条寺城:築城年代は定かではない。応安2年・正平24年(1369年)室町幕府に反抗した桃井直常方の軍勢が立て籠もっていた一乗之城を、幕府方の吉見氏が攻め落としたことが知られている。 天正12年(1584年)佐々成政が加賀の前田利家を攻めたときには、佐々成政の家臣杉山小助が城主であった。 瑞泉寺城:築城年代は定かではないが文明年間(1469年~1487年)に瑞泉寺によって築かれた。 文明13年(1481年)福光城主石黒右近光義は、医王山惣海寺と組み井波瑞泉寺と山田川にて戦ったが敗れて滅亡した。これにより山田川の東は瑞泉寺領、西は安養寺領(勝興寺)となった。これにより勢力を拡大した瑞泉寺は要害を構えこれが井波城の前身となった。 天正9年(1581年)佐々成政は越中の一向宗の二大勢力となっていた瑞泉寺を攻め、これを攻略した。その後井波城には成政の家臣前野小兵衛が城主となったが、天正13年(1585年)前田利家によって攻略された。 増山城:築城年代は定かではないが戦国時代に神保長職によって築かれたと云われる。 南北朝時代に築かれたとされる和田城は、この増山城の北方にある亀山城と見られている。 天文12年(1543年)頃に神保長職は富山城を築き新川郡の椎名氏を圧迫するようになった。椎名氏を支援する越後の上杉謙信は永禄3年(1560年)富山城を攻め落とし、居城であった富崎城を攻め落とされ、長職は増山城に逃れた。上杉氏はなおも追撃して長職は再び城を捨てて逃れた。 永禄5年(1562年)頃に神保長職は上杉氏に降伏し、後に増山城に居城を移したが、元亀3年(1572年)頃に没した。 長職没後、増山城には一向一揆が籠ったが、天正4年(1576年)上杉謙信が攻め落とした。 謙信は家臣吉江宗信を増山城に置いて拠点とした。 天正6年(1578年)上杉謙信没後、織田信長に仕えていた神保長住が織田軍を率いて越中に入国し、天正9年(1581年)には佐々成政の軍勢が増山城下を焼き払い増山城は落城した。 天正13年(1585年)羽柴秀吉の越中征伐によって佐々成政は秀吉に降った。成政は新川一郡に減封となり、砺波・婦負・射水三郡が前田利家に加増され、増山城には利家の娘婿中川光重が入った 16:00終了、新高岡駅に向かう。 16:30新高岡駅到達。 17:07新高岡駅新幹線はくたかで出発。 17:20金沢駅到達。 17:31金沢駅サンダーバードで出発。 20:09大阪駅到達。 今回の旅行、北陸地方の日本海に面した富山県に足を運び、富山県に点在する比較的マイナーなお城7か所をおとずれ楽しみました。 案内板がしっかりあり、山城が多かったですが、すんなり訪れることができました。 道も広く、渋滞もなく、ストレスを感じないドライブお城巡りでした。 |
                |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百三十九弾:島根県お城・城下町巡り&小京都重要伝統的建造物群保存地区観光 2018年6月30日-7月1日 中国地方の日本海に東西細長く位置し、日本の中国地方の日本海側である山陰地方の西部をなす県。県庁所在地は松江市。離島の隠岐島、竹島なども島根県の領域に含まれる。旧国名は出雲国・石見国・隠岐国であり、現在でも出雲地方・石見地方・隠岐地方の3つの地域に区分されることが多い。全国では鳥取県に次いで2番目に人口が少ない島根県に足を運び島根県に点在する比較的マイナーなお城8か所、小京都重要伝統的建造物群保存4か所を訪れました。 6月30日18:15伊丹空港出発。 19:05出雲空港到達、レンタカーで松江市内に向かう。 19:40松江市内のホテル到着後繫華街を散策し食事を済ませて就寝。 7月1日7:30レンタカーで出発、お城、小京都重要伝統的建造物群保存を巡る。 松江:宍道湖に面した松江の風景はここにしかないものだ。特に松江城の天守閣に立って眺めると湖が海のように見えるためその感が強い。日本を代表する平城である「松江城」を築いたのは堀尾吉晴で、その後は松平家が十代に渡って松江を治めている。特に七代藩主の松平治郷(不昧公)は茶人としても有名で、当時の茶室の明明庵も保存公開されている。お堀に沿って武家屋敷の塀が並ぶ通りを、家老の塩見家の屋敷があったことから塩見縄手と呼んでいる。 後に「知られざる日本の面影」など数々の作品で日本を紹介した小泉八雲ことラフカディオ・ハーンは、松江で英語の教鞭を取っていたころに過ごした家(元々は武家屋敷)が記念館と隣り合わせて立っている。 小泉八雲は日本では、怪談の作者として有名だが、国際的には日本の研究家として知られていた。 市内から少しだけ離れたところにある松江しんじ湖温泉は人気の温泉。 また、松江は古代出雲文化圏の中心地でもあったため、市内には山代二子塚、神魂神社などの古墳古社がある。律令時代の出雲国庁もこの地にあった。 満願寺城:満願寺城は宍道湖と日本海を繋ぐ佐蛇川の入口に面した標高27m程の丘陵に築かれている。 東麓にある満願寺の裏山が城山で、遺構は丘陵全体に拡がっていたようであるが、現在は墓地や警察学校の敷地になっている。 遺構が良好に残るのは満願寺の裏にある墓地の南、宍道湖に面した丘陵部分で高い切岸に囲まれた曲輪の北西下を横堀が巡り、そこから二条の短い竪堀が落ちている。 白鹿城:築城年代は定かではないが永禄年間(1558年~1569年)に松田氏によって築かれたと云われる。 尼子十旗の一つで、毛利氏侵攻のときの城主松田誠保の父満久は尼子晴久の姉婿である。満久は備前国松田一族の松田満重の次男である。 永禄6年(1563年)に毛利元就による侵攻では吉川元春が真山城を向城として築き攻めたて、まず小白鹿が陥落、月山富田城の尼子義久からの援軍も撃退され落城した。 このとき、毛利元就は大森銀山の坑夫を使い地下道を掘らせて井戸を抜いたという。 誠保は落城後隠岐へ逃れ、元亀元年(1570年)布部山合戦に参加している。 新山城:平安時代に平忠度が築いたとの伝承があるが定かではない。 永禄6年(1563年)毛利元就による出雲侵攻で尼子氏の居城月山富田城の重要な支城である白鹿城を攻略するための向城として吉川元春が築いて陣を置いた。 白鹿城攻略後は真山城をこの地方の拠点とし、多賀元信を城主とした。 永禄12年(1569年)毛利氏が兵力の大半を率いて豊後大友氏との戦いに向かうと、再興をはかった尼子勝久は隠岐を経由して忠山城に入り、勝久は各地に激を飛ばして将兵を集め、真山城を落としここを本拠として出雲回復を狙う。 尼子方は月山富田城を囲んだが、天野隆重の謀略により落とすことができず、毛利方が九州から帰国すると次第におされ、元亀2年(1571年)真山城も吉川元春の攻撃により落城し、尼子勝久は織田信長を頼って落ちた。 十神山城:築城年代は定かではない。城主は松田備前守で安来荘の荘官であった。 応仁の乱では山名氏に属し月山富田城の尼子清定を攻めたが撃退され逆に十神山城は清定に攻められ落城した。 尼子氏の持城となった十神山城は尼子十砦の一つに数えられ、松尾遠江守が在城した。 毛利氏によって月山富田城が攻められ落城する頃には毛利氏部将の安芸国草津城主児玉就忠によって落城した。 勝山城:築城年代は定かではない。 古くは滝山城と呼ばれ尼子十砦の一つとして数えられ、城主は田中三良左衛門といわれる。 現在残る遺構は永禄年間(1558年~1570年)に出雲に侵攻した毛利氏によって築かれたもので、 京羅木山城砦群とも呼ばれるように尼子氏の本城月山富田城を見下ろす京羅木山にはいくつかの陣城が築かれ、勝山城もその一つであった。 広瀬:この町は佐々木義清が雲隠の守護となって富田城に入城してから山陰地方の中心へとなっていった。1607年(慶長12年)、堀尾吉晴が移城のために松江城の築城に着手してから富田は急速に荒廃したが、1666年(寛文6年)、松平近栄によって広瀬藩が創設、再び城下町の面影を取り戻した。しかし、同年の秋、大洪水によってこれまでの富田の市街地は流されてしまう。その後、新たに富田川の西部に広瀬町の中心街となる町が建設され、名前も広瀬と改められ、現在に至る。 熊野城:熊野城は標高280mの要害山山頂に築かれている。 要害山は山頂から南と東に尾根が展開しており、熊野城もこの尾根に階段状に曲輪を展開している。東麓には「土居成」と呼ばれる屋敷地があり熊野氏の居館があった所とされている。また西麓にも「城屋敷」という地があり天野氏の屋敷跡と伝えられる。 現在山は中腹から上が酷く荒れており、密集した竹藪をかき分け何とか山頂の主郭に至ったものの、城の遺構を詳しく見て回るような状況ではなかった。東尾根から登ったので、こちらからは階段状になった曲輪群を確認できたが、南尾根に展開する曲輪群は確認していない。東側の中腹から麓近くまで非常に細かな階段状の段が展開している。 三笠城:築城年代は定かではないが牛尾氏によって築かれたと云われる。 牛尾氏は信濃国の神氏の支流中沢真直が大原郡牛尾荘を領して牛尾氏を名乗った事に始まる。尼子十旗の一つ。 その後、出雲国守護京極氏に従い、戦国時代には尼子氏の重臣となったが、尼子義久が毛利氏に降ると毛利氏に属した。 尼子勝久を大将に尼子再興軍が興ると三笠城主牛尾弾正忠は尼子方として五百騎を率いて参陣する。再興軍は出雲国へ上陸すると破竹の勢いで出雲を制圧するも、富田城を落とす事ができず、急を知って九州より毛利軍の主力が引き返してくると、それを迎え撃つべく布部山に陣を置いたが支えきれずに敗走する。牛尾弾正忠は一旦三笠城へ退き、毛利方に属していた高平城の牛尾大蔵を攻めるも、毛利氏の援軍によって逆に三笠城は落城した。 三沢城:嘉元2年(1304年)に三沢為長によって築かれたと云われる。 三沢氏は信濃豪族で木曾義仲の後裔あるいは片切氏(片桐)の分流飯島氏とする説がある。 本丸の東屋にある三沢氏の歴代当主では、後者の飯島氏を採用している。 信濃国飯島城主飯島為光は承久3年(1221年)の承久の乱で戦功を挙げ、出雲国三沢郷の新補地頭を賜った。その後、為長がはじめて三沢に来住し、三沢氏を名乗り三沢城を築いたという。 三沢氏はタタラ製鉄などで地盤を固め、為時のときに布広城を築き、信濃守為忠は横田荘へ進出、永正6年(1509年)遠江守為忠のときに藤ヶ瀬城を築いて居城を三沢から移した。しかし、享禄4年(1531年)三沢為国のとき尼子氏が背後の「桶ヶ嶺」から攻められ藤ヶ瀬城は落城、三沢氏は尼子氏に降った。 天文8年(1539年)尼子晴久が安芸国吉田郡山の毛利氏を攻めた際には、三沢為幸が従軍し、首級十三首をあげる活躍をしたが元就の馬廻から射出された矢を七本受け、元就家臣井上七郎に討ち取られた。 為幸が討死したとき嫡子為清はわずか四歳であったが、天文10年(1541年)大内義隆が尼子の富田城を攻めたときには他の出雲の国人衆と同様に大内氏に従った。しかし、富田城攻城戦のさなか、三沢氏は大内氏に降っていた出雲の国人衆と大内氏を裏切って再び尼子方となり、大内軍は敗走した。 大内義隆が陶晴賢に討たれ、その陶晴賢も毛利元就に討たれ大内氏が滅亡すると、毛利元就は尼子領へ侵攻した。三沢為清・為虎父子は毛利氏に降り、尼子氏が滅んだ後に尼子再興軍が蜂起した際も毛利氏に従って各地を転戦した。 天正17年(1589年)三沢為虎は三沢領を没収され毛利輝元に幽閉された。その後、釈放されて長門国厚狭郡に一万石の所領が与えられた。関ヶ原合戦後も毛利氏に属し、毛利秀元を当主とする長府藩が立藩されると付家老として二千七百石が与えられ、三沢氏は家老として代々続いた。 大森: 大田市大森銀山伝統的建造物群保存地区は,幕府 直轄地約4万8千石,約150か村の中心の町で あった。銀山は14世紀初めに発見されたと伝えら れ,産銀量は17世紀初頭にピークをむかえ海外に も輸出された。町並みは銀山川沿いの谷間に延び る約2.8キロの範囲で,代官所跡や郷宿,武家屋 敷,商家などが現存し,背後の山裾には社寺や墓地, 石切り場なども残され,鉱山町の歴史的景観を良 好に伝えている。 温泉津: 大田市温泉津伝統的建造物群保存地区は,天然の 温泉が湧き出る港町で,中世より石見銀山の外港 として発展してきた。狭隘な谷を切り開いた約 80 0メートルの町並みは,近世の地割をよく残している。 江戸末期から昭和初期にかけて建てられた町屋を 中心に,旅館や社寺などの多様な建造物が並んで いる。それらが周囲の海や山とともに,港町・温泉 町の景観を形成している。 7月1日19:35出雲空港出発 20:25伊丹空港到達。 今回の旅行中国地方の日本海に東西細長く位置する島根県に足を運び比較的マイナーなお城8か所、小京都重要伝統的建造物群保存4か所をおとずれ楽しみました。 今回のお城は山城が多く、かなり地味で案内板のみで遺残はほとんどが見受けられませんでした。 一方小京都重要伝統的建造物群保存巡りは、何回も訪れたことのある松江、松江城、小泉八雲の屋敷、武家屋敷、昔を忍ばせ感動でした。 他の重要伝統的建造物群保存巡りは中世の街並みの散策癒されました。 |
    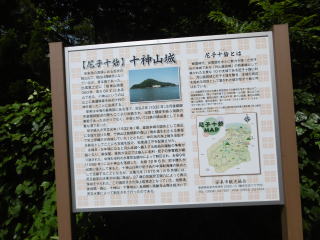           |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百三十八弾:群馬県お城・城下町巡り観光 2018年6月23日-24日 関東地方の北部、源義重を祖とする新田氏が、上野国で勢力を持つが、やがて南朝方として敗戦にまみれる。南北朝の内乱が収束しても、各地で戦いが発生し、幕府は関東管領として上杉氏憲を立てたが、混乱の時代が長く続いた群馬県に足を運び群馬県に点在する比較的マイナーなお城8か所を訪れました。 23日15:50新大阪駅新幹線のぞみで出発 18:23東京駅到達。 18:40東京駅新幹線あさまで出発。 19:33高崎駅到達、駅前のホテル到着後?華街を散策し食事を済ませて就寝。 24日8:00レンタカーで出発、お城巡り。 小泉城:延徳元年(1489年)富岡直光によって築かれた。 直光は足利成氏が鎌倉公方になったとき、邑楽郡に所領を得て館を構えた。 富岡氏は古河公方に属していたが、後に越後国上杉氏、小田原北条氏に従った。 館林城:弘治2年(1556年)赤井照康によって築かれたと云われるが定かではない。 越後上杉氏が関東に進出すると足利長尾氏が城主となるが後に北条氏の支配するところとなり北条氏規が城主となった。 小田原の役では石田三成が攻め寄せるが落城せず後に開城する。 北条氏滅亡後に関東に入部した徳川家康は榊原康政を十万石で入れた。 榊原氏は3代続いた後、陸奥国小峰に転封となり替わって大給松平氏が入封する。 寛文元年(1661年)3代将軍徳川家光の四男綱吉が二十五万石で入封する。 綱吉が将軍となるとその子徳松が城主となるが徳松の死によって館林城は破却された。 宝永4年(1707年)6代将軍家宣の弟松平清武が二万四千石で入封し築城し直した。 のち太田氏、松平氏、井上氏、秋元氏と入れ替わり明治を迎えた。 白井城:築城年代は定かではないが永享年間(1429年~1441年)山内上杉氏の被官である長尾景仲によって築かれたと云われる。 景仲の孫景春は関東管領上杉顕定に叛いて古河公方に付き、武蔵国鉢形城に籠った。 顕定は鉢形城を包囲するが、古河公方の援軍もあり、和議となる。 その後も景春は顕定に対抗するが永正2年(1505年)白井城に復帰した。 越後の長尾為景が上杉房能(顕定の弟)を自害に追い込んだ為、永正6年(1509年)顕定と嗣子憲房は為景を討つべく侵攻、景春は為景に応じて白井城で顕定を迎え撃ったが憲房に破れ、柏原城へと退いた。 顕定は一時為景を越中に追いやったが、翌年長森ヶ原合戦で為景に破れ討死、憲房は白井城へと退いたが、さらに景春に破れ平井城に退いた。 天正18年(1590年)豊臣秀吉が北条氏を攻めた小田原の役の時は、北条氏に属していたが、松井田城を攻略した前田利家、上杉景勝の軍勢に攻撃され開城した。 岩櫃城:築城年代は定かではない。建久年間(1190年~1198年)頃には岩櫃城主として吾妻太郎助亮が登場している。 その後、下河辺行重の孫という行盛が貞和5年・正平4年(1349年)碓氷の里見義時と戦って敗れて自刃し、その子憲行が叔父の安中の斎藤梢基の養子となり、延文2年・正平12年(1357年)上杉憲顕の属して里見義時を討ち、岩櫃城を回復したという。 永禄4年(1561年)頃より武田信玄は西上野に侵攻し、永禄6年(1563年)真田幸隆によって岩櫃城は攻略され、斎藤憲広・憲宗父子は越後の上杉謙信を頼って落ちた。永禄8年(1565年)斎藤憲宗は上杉氏の援軍を得て岩櫃城の奪還を目指したが武田信玄が箕輪城へ着陣した報を受け嵩山城に退いた。その後嵩山城は真田幸隆によって攻略され斎藤氏は滅亡した。 天正2年(1574年)真田隆幸が没し、天正3年(1575年)長篠の合戦で幸隆の長男信綱と次男昌輝が討死すると、武藤氏を継いでいた三男昌幸が真田に復姓した。 天正10年(1582)武田勝頼が甲斐国新府城を捨てて体制を立て直そうとした際に、昌幸は岩櫃城へ勝頼を迎えようとしたが実現せず、勝頼は小山田氏を頼ったが途中天目山にて自刃、武田氏は滅亡した。 関ヶ原合戦の後、真田信之の持城となったが、元和の一国一城令により廃城となった。 長井坂城:長井坂城の築城年代は定かではありませんが、上杉謙信が沼田城の沼田顕泰を攻めた際にこの地に着陣したのが起源とされています。その後、度重なる謙信の関東出陣の際には、沼田城から厩橋城の間を繋ぐ拠点として整備されました。1580(天正8年)年8月には武田勝頼配下の真田昌幸により攻略され、さらに武田氏滅亡後の1582年(天正10年)年10月には鉢形城主・北条氏邦によって攻め落とされました。このとき長井坂城には猪俣邦憲が入り、沼田城攻略の最前線となりました。現在、城址の大半は農地化していますが、沼田街道を取り込んだ縄張り、土塁や堀切などの遺構を確認することができます。 沼田城:天文元年(1531年)沼田顕泰によって築かれた。 天文20年(1551年)関東管領上杉憲政の越後国亡命を追って、小田原北条氏が侵攻し、顕泰はこれに降った。 しかし、永禄3年(1560年)上杉政虎の関東進出により、北条勢は沼田より退去して顕泰は上杉氏に降った。 永禄12年(1569年)顕泰は末子景義に相続させるため、嫡子朝憲を殺したが、沼田衆の攻撃により景義とともに会津に落ち延びた。 上杉謙信没後に勃発した「御館の乱」で景虎が敗れると沼田に残った藤田信吉は武田氏に通じ、城を真田昌幸に渡し、昌幸は叔父矢沢頼綱を城代とした。 天正10年(1582年)武田氏が滅びると、滝川一益は滝川益氏を城主としたが、本能寺の変により退去し再び真田氏の持城となり、嫡子信幸を矢沢頼綱後見のもと城主とした。 天正17年(1589年)昌幸は、北条氏が上洛して羽柴秀吉に面することの条件として、沼田領を北条氏に割譲する条件をのみ、北条方の猪俣邦憲が城代となった。 しかし、邦憲は真田領として残された名胡桃城を奪取、それをきっかけに秀吉は北条氏を討伐することとなった。 小田原の役の後、沼田領は真田信幸に渡された。 関ヶ原合戦では、父昌幸は西軍、信幸は東軍に属し、合戦後信幸は昌幸の旧領を与えられた。 元和8年(1622)年信幸は信濃国松代に移り、後に二男信政に信濃国松代十万石、信利に沼田三万石とした。 沼田真田氏は天和元年(1681年)改易となり、元禄16年(1703年)本多正永が下総国内より入封、享保15年(1730年)駿河国田中に移封となる。 享保17年(1732年)常陸国下館より黒田直邦が入封、寛保2年(1742年)直純の時、上総国久留里に移封となり、替わって駿河国田中より土岐頼稔が入封、以後明治に至る。 名胡桃城:築城年代は定かではないが明応年間(1492年~1501年)に沼田景冬によって築かれたと云われる。景冬は沼田城主沼田景久の三男で名胡桃氏を称した。 天正7年(1579年)真田昌幸は沼田城攻略のため名胡桃城に入り、翌8年に沼田城を攻略した。その後は真田家の重臣鈴木主水重則が城主となった。 天正17年(1589年)豊臣秀吉の裁定により沼田は北条領となったが、名胡桃城は真田氏の持城として維持することとなった。しかし、沼田城代であった猪俣邦憲が名胡桃城を攻略して奪ったため、秀吉の怒りを買い、小田原征伐の発端となった。 宮野城:築城年代は定かではない。上杉謙信が越山して関東に入るとき、度々この宮野城に入っている。 上杉謙信が没した後は、北条氏や滝川氏そして真田氏などの管理下に置かれた。 16:30終了高崎駅に向かう。 18:15高崎駅到達。 18:39高崎駅新幹線あさまで出発 19:32東京駅到達。 24日19:47東京駅新幹線のぞみで出発。 22:20新大阪駅到達。 今回の旅行関東地方の北部に位置する群馬県に足を運び群馬県にt冤罪する比較的マイナーなお城8か所をおとずれ楽しみました。 各城跡は公園に変貌しているところが多く遺残が少なく案内板のみで地味な城跡でした。 |
          |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百三十七弾:新潟県お城・城下町巡り観光 2018年6月16日-17日 甲信越地方の日本海に東西に細長く位置し、南北朝の内乱で、南朝の軍勢が力を持っていたが、足利尊氏は上杉謙顕を越後守護に投入し、南朝方を破った、やがて上杉謙信の登場で越後は統一され、関東や川中島など、各地へ勢力を広げようとする新潟県に足を運び、新潟県に点在する比較的マイナーなお城16か所 をお城10か所訪れました。 16日17:30伊丹空港出発。 18:35新潟空港到達、レンタカーで新発田方に向かう。 19:20新発田駅前のホテル到達後?華街を散策し食事を済ませて就寝。 17日5:00レンタカーで出発。お城巡り。 金山城:金山城館遺跡は、奥山荘城館遺跡〔江上館跡・鳥坂城跡・倉田城跡・野中石塔婆群 ・小鷹宮境内地・韋駄天山遺跡・蔵王権現遺跡・黒川城跡・臭水遺跡・金山城館遺跡・坊城 館跡・古舘館跡の12地点〕の1つで、「願文山城跡」「館ノ内跡」「高館跡〔下ノ館跡〕 」「蝸牛山城跡」からなる城館遺跡である。奥山荘は現在の胎内市、新発田市に所在した近 衛家の中世荘園を云う。平安末期は城一族、鎌倉期以降は三浦和田一族〔中条氏、黒川氏、 金山氏ら〕が在地領主として支配した。大治年間(1126~1131年)、城氏の一族金 山氏〔前金山氏〕によって築かれたと云われる。建久年間(1190~1199年)、金山 氏が追放となり、代わって奥山荘地頭の三浦和田氏が入り、城郭の拡張整備を行い、南北朝 時代、中条政綱の分家金山氏〔本金山氏〕が整備完成させたと云う。1221年「承久の乱 」では、藤原信成の家人酒匂家賢らが願文山城に立て籠もったが、幕府軍の圧勝に終わった 。これを期に勃発したと伝わるが定かではない。その後、戦国末期まで金山氏が続き、15 98年上杉景勝会津移封に伴い、金山氏も移り、廃城になったとされる。 鳥坂城:吾妻鏡に登場する城氏が最後に籠った「鳥坂」に比定されている。 城氏は桓武平氏で秋田城介となった平繁成を祖とする。 その後、中条氏の所領となり、鳥坂城もこの中条氏の時代の遺構が残っている。 中条氏は相模国三浦和田一族で木曽義仲追討で功をあげ、奥山荘の地頭となり、中条氏を名乗った。 中条藤資は永正の乱で守護代長尾為景に属して、上杉方の本庄氏、色部氏と対立した。藤資の娘を娶り中条家を嗣いだ中条景泰は越中国魚津城の城番となり、織田氏に対抗したが柴田勝家に攻められ落城、討死した。 慶長3年(1598年)上杉景勝の会津移封に伴い、中条氏も会津に移り廃城となった。 江上城:建仁元年(1201年)越後の城氏が滅亡した後、治承・寿永の乱で功のあった和田義茂が奥山荘地頭となったのが始まりで、その惣領家である中条氏の館がこの江上館と考えられている。 中条氏は鳥坂城を詰城とし宝治元年(1247年)に鎌倉の三浦和田氏が滅亡した後も越後で勢力を持ち、建治3年(1277年)に中条、南条、黒川氏に分かれた。 中条氏は戦国時代には揚北衆の一員として上杉氏に従い、上杉氏の会津の転封によりこの地を後にした。 平林城:築城年代は定かではないが色部氏によって築かれた。 色部氏は桓武平氏秩父氏の支流で、富士川合戦で功をあげ小泉荘の地頭となり、越後国岩船郡色部条から色部氏を名乗った。 永正の乱では守護方につき、守護代長尾為景に対抗するが敗れ、後にそれに従った。 慶長3年(1598年)上杉景勝の会津移封に伴い、色部氏も金山城に移り廃城となった。 大葉沢城:築城年代は定かではないが鮎川氏によって築かれたと云われる。 鮎川氏は本庄城主本庄氏の庶流である。 天文8年(1539年)鮎川清長は、同族の小川長資とともに本庄城の本庄房長を攻めて出羽国へ追い落とすなど、その地位を高めたが、平林城主色部氏の仲介により和平となった。 永禄11年(1568年)房長の子、本庄繁長は甲斐の武田信玄と通じて上杉謙信に叛き挙兵した。鮎川清長は上杉謙信の要請を受けて本庄氏を攻めたが、本庄繁長もまた大葉沢城を攻めるなど激しく抵抗した。結局本庄氏は葦名盛氏の仲介で嫡子を人質として差し出すことで和議となった。 その後も鮎川氏が続いたが、慶長3年(1598年)上杉景勝の会津移封にともない、鮎川氏も会津に移り廃城となった。 津川城:築城年代は定かではない。建長4年(1252年)蘆名一門で金上氏の祖となる金上館主藤倉盛弘が築いたのが始まりとも云われるが定かではない。越後ではあるが、会津を拠点とした蘆名一門の金上氏が代々居城としており、江戸時代に入ってからも会津領と密接な関係が続いた。 応永26年(1419年)蘆名氏と一門で会津新宮城主新宮盛俊が対立して小河城で合戦しており、これが津川城とみられている。 永正7年(1510年)には越後守護代長尾為景が蘆名家臣松本源蔵の手引きで狐戻城を攻めたが、城主の金上盛信は城に籠もってこれを撃退している。 天正6年(1578年)御館の乱で、金上盛備は上杉三郎景虎を支援し、景勝方の水原氏や下条氏らを攻めた。また新発田重家の乱でも重家を支援している。金上盛備は蘆名氏の重臣として活躍したが、天正17年(1589年)摺上原の戦いで討死、蘆名氏もまた滅亡した。 天正18年(1590年)蒲生氏郷が会津に入部すると、その家臣北川平左衛門が城主となった。蒲生氏に代わって上杉景勝が会津に転封となると藤田信吉が津川城代となって一万五千石を領したが、後に出奔して徳川家康の元に逃れたため、鮎川帯刀が入った。 関ヶ原合戦の後、上杉景勝は会津から米沢へ転封となり、会津に蒲生秀行が入ると、その家臣岡重政が入った。寛永4年(1627年)蒲生氏が断絶となって加藤嘉明が会津に入部すると、幕府の命によって津川城は廃城、その後は津川代官所によって管理された。 本与板城:築城年代は定かではない。 越後守護上杉氏の家臣飯沼氏の代々の居城である。 永正11年(1514年)飯沼頼清は上杉房能と守護代長尾為景が対立すると、房能方に付き敗れて没落した。 その後、直江実綱が入部し後に与板城を築城し居城とした。 与板城:築城年代は定かではないが天正年間に直江氏によって築かれたと云われる。 本与板城飯沼氏が没落した後に入封した直江氏は、本与板城に入城したが後に与板城を築き居城とした。 上杉景勝が会津に移封となると、直江氏もそれに従い廃城となった。 長岡城:慶長10年(1605年)堀直寄によって築城がはじめられたが、完成したのは元和4年(1618年)で牧野忠成によるものである。 坂戸城主堀直寄は、蔵王堂城主鶴千代の後見人となって長岡城の築城をはじめたが、福島城主堀氏の家督相続に纏わる内紛で堀忠俊は改易となり、一族である堀直寄もその影響で信濃国飯山へ転封となった。 堀氏に代わって福島城に松平忠輝が入封すると家臣山田勝重が長岡城主となったが、元和2年(1616年)に忠輝もまた改易となる。再び堀直寄が入封するが、元和4年(1618年)直寄は越後国村上へ転封となった。 元和4年(1618年)越後国長峰より牧野忠成が入封し城を完成させた。 寛永11年(1634年)忠成の二男康成に一万石を分封して与板藩を立藩させ、以後代々牧野氏が続いた。 慶応4年(1868年)戊辰戦争が起こり、家老河井継之助はカトリング砲二門など大量の武器弾薬を購入して帰藩し、5月2日小千谷に陣を張った新政府軍の岩村精一郎と最後の談判が行われたが交渉は決裂し開戦となった。5月19日に長岡城は落城、その後一時長岡城を奪還したものの再び落城して、藩主は会津へ逃れた。 栖吉城:築城年代は定かではないが戦国時代に古志長尾氏によって築かれたと云われる。 古志長尾氏は越後国守護となった上杉房顕に従って越後に入部した長尾景恒が祖で、その子長尾景春が蔵王堂城を居城としていたが、後に栖吉城を築いて居城を移した。 古志長尾氏は長尾景信の時に全盛となり、永録2年(1599年)上杉謙信が上洛して帰国したことを祝う「侍衆御太刀之次第」に一門筆頭として名が記されている。この上洛の際に謙信は河田長親を見出して古志長尾氏を継承させて栖吉城となり、景信は上杉を名乗った。 天正6年(1578年)上杉謙信没後に起こった御館の乱では、上杉景信は上杉三郎景虎方となり府中の戦いで討死、天正8年(1580年)栖吉城は上杉景勝に攻められ落城した。 栃尾城:築城年代は定かではないが南北朝時代に芳賀氏によって築かれたと云われる。 芳賀禅可は宇都宮氏綱の後見として北朝方として戦い、宇都宮氏綱は上野国・越後国の守護職を得た。禅可の子高貞と高家は越後国守護代として越後に入部したが、貞治元年(1362年)に上杉房顕が関東管領となると、足利基氏は宇都宮氏綱から越後守護職を奪って上杉房顕に与える。これによって芳賀高貞・高家兄弟は上杉房顕と戦ったが敗れた。 天文12年(1543年)後に上杉謙信となる長尾景虎が中越地方の国人を統制するために、城主本庄実乃に迎えられた。中越を平定した景虎は天文19年(1550年)兄の晴景に代わって春日山城へ迎えられ長尾家の家督を相続した。 天正6年(1578年)上杉謙信没後に起こった御館の乱では、栃尾城主本庄秀綱は上杉三郎景虎方となり、上杉景勝に攻められ落城した。 慶長3年(1598年)上杉景勝が会津へ転封となると代わって入封した堀秀治の家臣神子田政友が一万石で城主となったが、慶長15年(1610年)堀氏が改易となると廃城となったという。 下倉山城:築城年代は定かではないが戦国時代に築かれたと云われる。 天文年間(1532年~1555年)頃の城主は福王寺氏が城主で、上条定憲が乱を起こした時には長尾為景方として戦った。 天正6年(1598年)上杉謙信没後に起こった御館の乱では、城主佐藤平左衛門は上杉景勝方となり、三郎景虎方の栃尾城主本庄秀綱らに攻められたが撃退した。 慶長3年(1598年)上杉景勝が会津へ転封となり、かわって堀秀治が入封すると小倉主膳正煕が八千石を領して城代となった。慶長5年(1600年)上杉景勝が越後の旧臣を扇動して一揆を起こすと一揆軍は下倉城に攻め寄せ、これに立ち向かった小倉正煕は討死したが、救援に駆けつけた堀直寄によって鎮圧された。 大井田城:築城年代は定かではないが南北朝時代に大井田氏によって築かれたと云われる。 大井田氏は新田氏の一族里見氏の流れを汲む一族で、南北朝時代は南朝方として活躍した。 大井田氏とその一族とされる中条氏は戦国時代も上杉氏の家臣として名前が残るという。 福島城:慶長12年(1607年)堀秀治によって築かれた。 慶長3年(1598年)上杉景勝が会津に移封となり替わって堀秀治が越前国北庄から四十五万石で入封した。 秀治は越後国一揆を鎮圧した後、新たに福島城を築城し春日山城を廃した。堀氏は秀治亡き後、僅か12歳の忠俊が継いだが後見人の堀賢物直政が亡くなると内紛が起こり、家康によって領地を没収され忠俊は鳥居忠政にお預けとなった。この後、越後国には松平忠輝が入封し忠輝は福島城を廃して高田城を築いた。 柿崎城:築城年代は定かではない。発掘調査によって鎌倉時代末期から室町時代前期までの遺物が確認されている。室町時代後期には上杉謙信の重臣として知られる柿崎和泉守景家の居館であったと考えられ、猿毛城が詰城であったと云われる。 北条城:築城年代は定かではないが室町時代に北条氏によって築かれた。 北条氏(きたじょう)は大江広元を祖とする毛利氏一族で安芸国毛利氏と同族である。 天文23年(1554年)北条高広は武田信玄に内応したがそれを知った上杉謙信によって攻撃され降伏し許された。 謙信亡き後の御館の乱では景虎方に付き坂戸城を攻撃した。 北条景広は御館で景勝方の攻撃を受け討死するが高広は後に武田勝頼の斡旋で上杉家に復属した。 16:00終了、新潟空港に向かう。 17:40新潟空港到達。 19:05新潟空港出発。 20:20伊丹空港到達。 今回の旅行、甲信越地方の日本海に東西に細長く位置する新潟県に足を運び新潟県に点在する比較的マイナーなお城16か所お訪れ楽しめました。 比較的案内板がしっかりしており、城跡は史跡公園に変貌しているところも多く、又車が少なく、信号も少ない、真っ直ぐな広い道、田園風景を見ながらドライブ観光、渋滞なくストレス感じなく楽しめました。 |
    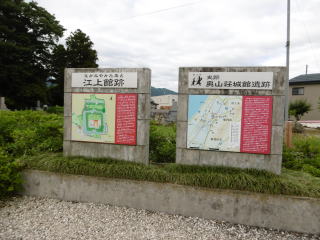                |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百三十六弾:神奈川県お城・城下町巡り観光 2018年6月9日-10日 関東地方に位置し相模国と武蔵国という歴史的に極めて重要な土地を含み、鎌倉幕府はもとより、戦国時代も小田原の北条氏が強烈な存在感を示し、古都鎌倉、小田原城など、歴史散策の見どころが多数ある神奈川県に足を運び、神奈川県に点在する比較的マイナーなお城10か所を訪れました。 9日 13:50新大阪新幹線のぞみで出発 16:35東京駅到達、タクシーで東京プリンスホテルに向かう。 16:50東京プリンスホテル到達。 17:00講演会出席。 19:30懇親会。 21:30就寝。 10日7:00タクシーで東京駅向かう。 7:15東京駅レンタカーで出発、お城巡り。 荻野山中藩陣屋:天明3年(1783年)大久保教翅によって築かれた。 荻野山中藩は小田原藩大久保氏の分家で、大久保忠朝の子教寛が徳川綱吉の小姓組番頭に取り立てられ、そこから出世して一万一千石となって駿河国松長藩として大名に列したことに始まる。 松長藩大久保氏の五代が教翅で、この教翅によって相模国愛甲郡中荻野へ陣屋が移され荻野山中藩となり、一万三千石を領した。荻野山中藩は以降、教孝、教義と続いて明治に至る。 小沢城:築城年代は定かではないが金子掃部助によって築かれたと云われる。 金子掃部助は文明9年(1477年)長尾景春の乱に呼応して小沢城に立て籠もった。刻を同じく蜂起した溝呂木城と小磯城は三浦氏らの相模勢が押し寄せるとすぐに自落したが、この小沢城は容易に落城せず二ヶ月ほど持ちこたえ、一度は落城して逃亡したものの再び立て籠もり、翌年小机城が落城するまで持ちこたえたという。 津久井城:築城年代は定かではない。鎌倉時代に筑井太郎次郎義胤が宝ヶ城に築いたのが始まりとの伝承がある。文献に登場するのは戦国時代からで、大永5年(1525年)に武田氏と小田原北条氏が戦っている。 戦国時代には内藤氏が城主で山内上杉氏の家臣であったが、後に小田原北条氏に属して「津久井衆」と呼ばれた。天正18年(1590年)豊臣秀吉による小田原征伐では、徳川家康の家臣本田忠勝、平岩近吉らによって攻め落とされた。 岡崎城:築城年代は定かではない。 悪四郎と称される岡崎義実が岡崎城を築き居城としたと云われるが、現地の案内板を読むと、それは日本城郭体系に載る「岡崎南部方形囲郭群」を指しているようである。 無量寺周辺を縄張とする岡崎城は三浦道寸で、伊勢宗瑞と長年に渡って争ったが、永正9年(1512年)伊勢宗瑞の猛攻にあって落城した。 今井陣場:天正18年(1590年)豊臣秀吉の小田原攻めで徳川家康が布陣した場所である。 石垣山城:天正18年(1590年)豊臣秀吉によって築かれた。 天正18年(1590年)秀吉は小田原北条氏の討伐を開始し、伊豆国山中城などを抜いて早雲寺に本陣を構えた。秀吉は石垣山へ登って検分を済ませると築城を開始した。突貫工事で築城が行われ、完成すると小田原城側の樹木を伐採して、さも一夜にして城が築かれたように見せ、北条方の度肝を抜いた。これが一夜城と呼ばれる由縁である。 北条氏は一夜城が完成すると間もなく降伏し、北条氏政・氏照らは切腹、北条氏直・氏規らは高野山へと送られた。 土肥城:平安時代末期に土肥氏の城と伝えられる。 現在の遺構は戦国時代に小田原北条氏によるものと推測されている。 鷹ノ巣城:関東へ行くには、足柄峠を越える道と箱根を越える道が存在し足柄峠への道には足柄城をそして箱根には鷹之巣城をおいた。 海抜800メートル以上の所にある。箱根などの城は番城(本城の直属の城で城主をおかないこと)であり、鷹之巣城もその一つだった。 天正18年(1590年)の小田原征伐においては徳川家康に攻められ3月29日に落城しその後家康は本陣としたが、今井陣屋に移ったことで廃城になった。 足柄城:足柄城(あしがらじょう)は、静岡県と神奈川県の県境である「足柄峠」付近にある北条家が築城した城です。 最初は小田原城主・北条氏綱が1536年に足柄城を築城したようですが、1555年には北条氏康が、三田郷(厚木市)の百姓に命じて、足柄城改修の普請人足を命じた古文書も発見されています。 更に、甲斐の武田信玄と手切れとなると、足柄古道の防衛が重要となり、1569年から1571年に掛けても石切衆十人を動員して大規模な改修を行っています。 1571年、武田勢によって駿河・深沢城が陥落すると北条綱成が足柄城へ退却したのち、玉縄城まで撤退しました。 河村城:築城年代は定かではないが南北朝時代に河村秀高によって築かれたと云われる。 文和元年・正平7年(1352年)南朝方の河村一族は、新田義興等の軍勢とともに河村城に籠城して、北朝方の畠山国清等と対峙した。城は難攻不落であったが、翌年南原の戦いで南朝方は惨敗を喫して河村一族の多くが討死し、新田義興は越後国へ逃れた。 戦国時代末期には小田原北条氏の属城となっていたが、小田原征伐によって北条氏が滅亡すると廃城となった。 16:00終了、東京駅に向かう。 17:30東京駅到達。 18:00東京駅新幹線のぞみで出発 20:37新大阪駅到達。 今回の旅行関東地方の神奈川県に足を運び、神奈川県に点在する比較的マイナーなお城10か所を訪れ楽しみました。 平城は城址公園に変貌、山城は案内板のみで地味でした。 今回も地味な城跡巡りでした。 |
              |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百三十五弾:茨城県お城・城下町巡り観光 2018年6月2日-3日 関東地方の北東部に位置し、南北朝の内乱で、常陸国も2つの勢力に分かれ、激しく火花を散らし、この争乱で北朝方の佐竹氏が発展し、文禄4年の常陸統一につながって行く、関ケ原後、石田三成に協力した佐竹氏は、秋田に国替となった茨城県に足を運び茨城県に点在する比較的マイナーなお城10か所を訪れました。 2日13:50新大阪駅新幹線のぞみで出発 16:30東京駅到達、タクシーで東京タワーの近くのホテルに向かう。 16:45ホテル到達。 17:00講演会出席。 19:30講演会終了。 20:00懇親会。 21:30懇親会終了、就寝。 3日7:30タクシーで東京駅八重洲口に向かう。 8:00八重洲口でレンタカーで出発、城めぐり。 守谷城:築城年代は定かではないが相馬氏によって築かれたと云われる。 相馬氏は千葉氏の一族で千葉常胤の子師常が相馬御厨を治めて相馬氏を称した事に始まる。江戸時代に陸奥相馬中村藩となった相馬氏もこの一族である。 相馬氏は大永5年(1525年)には相馬因幡守が守谷城を居城としていたことが確認されている。戦国時代には古河公方に従い梁田氏の配下となっていたが、小田原北条氏の勢力が伸びてくると梁田氏は北条氏に降り、このとき守谷城は北条氏によって接収された。北条氏は永禄11年(1568年)に守谷城を改修している。当初は古河公方足利義氏の御座所となるような話もあったようであるが、結局実現しなかった。天正18年(1590年)北条氏は豊臣秀吉によって滅ぼされ相馬氏もまた没落した。 北条氏に変わって徳川家康が関東に入部するとその家臣菅沼(土岐)定政が一万石を領して守谷城主となった。元和3年(1617年)土岐定義のとき摂津国高槻城に転封となり、一時幕府直轄領となったが、元和5年(1619年)定義が没して土岐頼行が家督を継ぐと幼小であったことから一万石に減封され守谷藩へと移された。寛永5年(1628年)土岐頼行は出羽国上山へ転封となり廃城となった。 牛久城:築城年代は定かではないが戦国時代に岡見氏によって築かれたと云われる。 岡見氏は小田氏の一族で常陸国河内郡岡見郷発祥とされ、南北朝時代頃に分流したと考えられている。 岡見氏は代々小田氏に従っており、永禄12年(1569年)手這坂の合戦では岡見山城守も出陣して討死してる。手這坂の合戦で大敗した小田氏は、天正元年(1573年)頃には佐竹氏に臣従したが、岡見氏はその後も独立した勢力を維持している。 小田氏の勢力が衰退し、佐竹氏側の下妻城主多賀谷重経が勢力を拡大してくると、岡見氏はこれに対抗することとなるが、元亀元年(1570年)には谷田部城が落城、天正8年(1580年)には一時谷田部城を取り戻すが、再び攻め取られ、天正15年(1587年)には牛久城主岡見治家の兄宗治の居城である足高城も落城した。こうした情勢のなか、岡見氏は小田原北条氏に支援を要請し、次第にその支配下に属していくようになる。 小田原北条氏は佐竹領に隣接する牛久城を重要視し、天正15年(1587年)頃から下総国小金城主高城氏、下総国布川城主豊島氏、上総国坂田城主井田氏など近隣の国人たちに交代で牛久城を守るよう命じており、牛久番と呼ばれていた。 天正18年(1590年)秀吉による小田原征伐により岡見氏は北条氏とともに滅亡した。 その後は、由良国繁が上野国桐生城から五千四百石余りで牛久城に入った。関ヶ原合戦で国繁は江戸城の守備を命ぜられ、その恩賞として千六百石が加増され七千石の大身旗本となった。しかし、元和7(1621年)由良貞繁が嗣子なく没すると、弟忠繁が家督相続を許されたものの、家禄は千石に減封された。この元和7年(1621年)に廃城になったとされる。 木原城:築城年代は定かではない。 永禄5年(1562年)には江戸崎城主土岐氏の家臣近藤薩摩守が木原の地に取り立てられており、この頃には木原城が築かれていたといわれる。 軍記物などでは天正2年(1574年)に小田氏の家臣江戸崎監物が佐竹氏に寝返り、木原城は攻められて落城、天正11年(1583年)には葦名盛重など佐竹軍によって攻められ落城、天正18年(1590年)豊臣秀吉による小田原征伐で木原城主は江戸崎城とともに北条方となり落城と三度落城しているが、「図説 茨城の城郭」によれば、発掘調査では焼土や土塁の作り直しなど激しい戦闘の痕跡は確認されていないという。また同書では、土岐氏あるいはその家臣である近藤氏といった小勢力が、現状のような巨大な城郭を築いた背景として、永禄6年(1563年)に土岐氏と小田原北条氏が同盟関係となり、天正元年(1573年)に佐竹氏が小田氏の支城である宍倉城や戸崎城を攻め落とし、土岐氏の勢力範囲と隣接するにあたって北条氏が土岐氏を支援した結果ではないかと推測している。 島崎城:築城年代は定かではないが島崎氏によって築かれた。 島崎氏は大掾氏の庶流行方氏の一族で、行方景幹の次男高幹二郎が行方郡嶋崎に住んで島崎氏を称した事に始まる。 大永2年(1522年)島崎利幹は同族の長山城主長山幹綱を攻めて自刃させ、天文5年(1536年)にも玉造宗幹を攻め、天正12年(1584年)には麻生城主麻生之幹を攻めてこれを滅ぼすなど、南方三十三館と称された諸豪族の筆頭となった。 天正19年(1591年)佐竹義宣の命によって、島崎安定など南方三十三館の城主は謀殺され島崎氏は滅亡した。 鹿島城:養和元年(1181年)鹿島政幹によって築かれたと云われる。 鹿島氏は常陸大掾氏一族の吉田氏庶流で、吉田清幹の子が鹿島三郎成幹を名乗り粟生城に居たが、その子政幹が吉岡城を築いて移ったという。以後代々鹿島氏の居城となったが、天正19年(1591年)佐竹義宣の「南方三十三館の仕置」によって鹿島晴房は常陸太田城にて謀殺され鹿島氏は滅亡した。 土浦城:築城年代は定かではないが永享年間(1429年~1441年)に(今泉)若泉三郎によって築かれたと云われる。また、平安時代に平将門によって砦が築かれたとの伝承も残る。 永正13年(1516年)若泉五郎左衛門が城主の時、小田氏の家臣菅谷勝貞によって攻められ、この後は小田氏の家臣菅谷氏の居城となった。 小田氏は小田氏治の頃、佐竹氏に小田城を奪われ、土浦城へ逃れて勢力の回復をはかるが、天正11年(1583年)佐竹氏の軍門に降った。 天正18年(1590年)豊臣秀吉による小田原征伐の後に関東に入部した徳川家康は、結城城に結城秀を置き、土浦を支配された。慶長6年(1601年)結城秀康は越前国北庄に転封となった。 慶長6年(1601年)下総国布川より(藤井)松平信一が三万五千石で入封、元和3年(1617年)信吉の時、上野国高崎へ転封。 ・元和4年(1618年)上野国白井より西尾忠永が二万石で入封、慶安2年(1649年)忠昭の時、駿河国田中へ転封。 ・慶安2年(1649年)下野国鹿沼より朽木稙綱が三万石で入封、寛文9年(1669年)稙昌の時、丹波国福知山へ転封。 ・寛文9年(1669年)常陸国宍戸より土屋数直が四万五千石で入封、天和元年(1681年)政直の時、駿河国田中へ転封。 ・天和2年(1682年)武蔵国より(大河内)松平信興が二万二千石で入封、貞享4年(1687年)大坂城代として転封。 ・貞享4年(1687年)駿河国田中より土屋政直が六万五千石で入封、以後明治に至る。 小田城:築城年代は定かではないが鎌倉時代末期に八田知家によって築かれたと云われる。 八田氏は常陸国久慈郡八田発祥で宇都宮宗綱の子知家が八田氏を名乗ったことに始まるが、八田知家は小田氏の祖となり、小田城は小田氏累代の居城となった。 南北朝時代の城主は小田治久で、暦応元年・延元3年(1338年)北畠親房は吉野から海路常陸国へ入り神宮寺城に籠ったが、佐竹氏に追われ、阿波崎城に逃れるも再び佐竹氏に追われ小田城に入った。 暦応4年・興国2年(1341年)足利尊氏が派遣した高師冬は小田城を攻めたてるが容易に落城しなかった。しかし、小田治久は高師冬の和平交渉に応じて小田城を開城し、北畠親房は関城へ逃れた。 戦国時代末期の城主小田氏治は、拡大する小田原北条氏と越後上杉氏、またそれに対抗する佐竹・多賀谷・結城などの狭間にたたされ、幾度と無く小田城を奪われては、土浦城へ退き、また小田城を奪い返しては奪われることを繰り返していた。永禄12年(1569年)手這坂の合戦で大敗を喫し、さらに真壁軍に小田城へ先回りされ奪われた為、氏治は土浦城へ退き、以後小田城へ帰参することはなかった。 久下田城:天慶3年(940年)藤原秀郷が築いたのが始まりとされる。 藤原秀郷は平将門がおこした承平天慶の乱を討伐するために、上館(久下田城)・中館(伊佐城)・下館(下館城)を築いたという。 戦国時代になり下館城主水谷正村が宇都宮氏に対する備えとして久下田城を築いた。元亀元年(1570年)正村は家督を弟勝俊に譲り、隠居城としてこの久下田城へ移った。元和の一国一城令により廃城となった。 結城城:治承年間(1177年~1180年)に結城朝光によって築かれたと云われるが定かではない。 結城氏は小山政光の四男で母は源頼朝の乳母寒河尼という。十四歳の時に武蔵隅田宿で陣を張っていた源頼朝に参見してその場で元服し、「朝」の字を賜わり朝光と名乗った。その後、下総国結城郡の地頭職を得て築いたのが結城城の始まりとされる。 16代結城政勝の時には下妻・下館・長沼・小山などに勢力を広げて戦国大名化する。天正18年(1590年)豊臣秀吉による小田原征伐には結城晴朝がいち早く参陣し、十万石の安堵を得るとともに、秀吉の養子となっていた徳川家康の二男秀康を養子に迎え、18代結城秀康となった。 慶長6年(1601年)結城秀康は越前国福井六十七万石に転封となって結城城は廃城となり、その後は天領となった。元禄13年(1700年)水野勝長が能登国西谷より一万石で入封。元禄16年(1703年)廃城となっていた結城城を再築して居城とし、以後明治に至る。 古河城:築城年代は定かではないか鎌倉時代に下河部行平によって築かれたと云われる。 下河部氏は小山政光の弟行義が下河部氏を名乗った事に始まり、その子行平が城を築いたという。 関東公方足利成氏が関東管領上杉憲忠を謀殺したことがきっかけとなって享徳の乱が勃発すると、室町幕府も上杉方を指示し、駿河守護今川氏によって鎌倉は占拠され、成氏は古河公方館へ身を寄せる。これによって古河公方と呼ばれることとなり、成氏は後に修築した古河城へと入り、代々の御座所となった。 今回の旅行、関東地方の茨城県に足を運び、茨城県に点在する比較的マイナーなお城10か所を訪れ楽しみました。 お城が城址公園に変貌しているところが多く、散策できました。 今回ほとんどが平城でしたが地味な城跡が多いが場所の確認は容易でした。 |
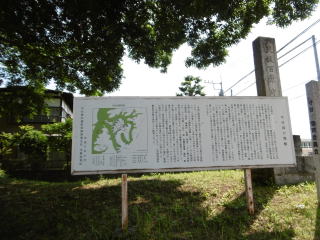     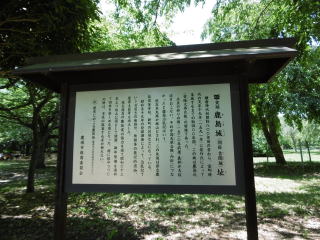       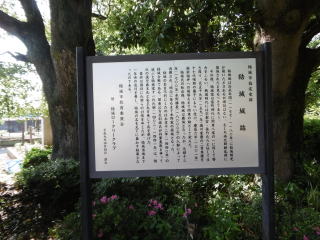  |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百三十四弾:埼玉県お城・城下町巡り観光 2018年5月26日-27日 関東地方の武蔵野国、古くから武士団の力が強く、平安後期以降の館が多く残り、鎌倉幕府の成立に尽力した武士たちは、館からより強固な城に拠点を移したが、やがて関東に転封された徳川家康によって多くが廃城となった埼玉県に足を運び埼玉県に点在する比較的マイナーなお城9か所を訪れました。 26日16:20新幹線のぞみで出発 18:53東京駅到達、地下鉄丸ノ内線で池袋経由、東武東上線で川越下車。 20:20川越駅付近のホテル到着後、?華街を散策し食事を済ませて就寝。 27日8:00レンタカーで出発、お城巡り。 菅谷城:築城年代は定かではないが鎌倉時代に畠山重忠によって築かれたと云われる。 畠山氏は秩父重弘の子畠山重能が武蔵国男衾郡畠山郷に住んで畠山氏を称した事に始まり、重能の二男が畠山重忠である。 畠山重綱は源頼朝が挙兵したときは平家方として三浦氏を攻めたが、やがて源頼朝に従い頼朝の鎌倉入りや富士川の戦い、奥州合戦などで先陣を務め重用された。しかし、頼朝没後の元久2年(1205年)「鎌倉に異変あり」との急報でわずかな手勢を率いて菅谷館を出発した重忠は、鎌倉幕府の実権を握った北条氏によって武蔵国二俣川で大軍に囲まれ討死した。 長享2年(1488年)には扇谷上杉氏と山内上杉氏によって、近くの須賀谷原で合戦が行われ、このときには菅谷城が築かれていたと考えられている。 その後の動向は定かではないが、太田氏が岩槻城へ移ったあとに、小泉掃部助が居城したと伝えられるのみである。 小倉城:詳細不明。 長享4年(1488年)には扇谷上杉氏と山内上杉氏によって近くの須賀谷原で合戦が行われており、近くの平沢寺に山内上杉方の陣が置かれていたが、このときに小倉城が築かれていたかどうかは定かではない。 城主は詳らかではないが、北条氏重の家臣遠山光景、松山城主の上田氏が城主として伝えられている。居館があったとされる東麓の大福寺には「遠山衛門大夫藤原光景室葦園位牌」があり、城主遠山氏室の位牌と伝えられている。 杉山城:築城年代は定かではない。一説に松山城主上田氏の家臣杉山(庄)主水が城主であったと伝えられる。 歴史については詳らかではないが、近年の発掘調査で出土遺物は十五世紀末から十六世紀前葉の年代で、長享年間(1487年~1489年)の扇谷上杉氏と山内上杉氏の長享の大乱のあと、山内上杉氏が扇谷上杉氏に対抗するために築いたものと考えられている 。 山田城:山田城跡は、城跡についての史料は全く無く、江戸時代終り頃に編纂された地誌『新記』の比企郡山川村の条にも見い出すことはできない。地元の伝承では、忍城(現行田市所在)主の成田氏の臣、贄田氏の居城であるとか松山城の出城であるとか伝えられているがはっきりしたことはわかっていない。 忍城:延徳2年(1490年)成田親泰によって築かれた。 天文22年(1555年)北条氏康によって攻められたが、これを退けた。 永禄2年(1559年)長尾景虎が関東に進出、景虎は容易に落城しないことを察知し城下を焼き払った。 これに対して成田長泰は末子を人質として景虎に差し出し、その配下に降った。 翌永禄3年(1560年)再び長尾景虎が関東に進出、鶴岡八幡宮にて上杉憲政から関東管領を譲り受け、上杉政虎と名乗った。 この席で成田長泰は、政虎に辱めを受け忍城に引き上げ、上杉氏に叛き北条氏に身を寄せた。 天正18年(1590年)豊臣秀吉による小田原征伐では、石田三成等が押し寄せたが攻めあぐねた。 三成は羽柴秀吉の備中国高松城の水攻めに倣い、堤防を築いて水攻めを決行した。しかし、堤防は崩れ忍城は落城せず、開城したのは小田原城が降った後であった。 徳川家康が関東に入部すると、松平家忠が一万石、その後四男忠吉が十万石で入部した。 ・慶長5年(1600年)松平忠吉は尾張国清州に五十二万石で転封 ・寛永3年(1626年)深谷より酒井忠勝が五万石で入封、寛永4年(1627年)川越へ転封。 ・寛永10年(1633年)相模より松平信綱が三万石で入封。 ・寛永16年(1639年)下野国壬生より阿部忠秋が五万石で入封、元禄7年(1694年)正武の時、加増され十万石となるが、文政6年(1823年)陸奥国白河へ転封。 ・文政6年(1823年)伊勢国桑名より(奥平)松平忠堯がから十万石で入封、以後4代続き明治に至る。 深谷城:康正2年(1456年)に上杉房憲によって築かれたと云われるが定かではない。 深谷上杉氏は庁鼻和城を居城としていたが、憲国の時に深谷城に居城を移した。 深谷上杉氏は関東に勢力をのばす小田原北条氏と敵対したが、天正元年(1573年)上杉憲盛の時、北条氏に降った。 天正18年(1590年)豊臣秀吉の小田原征伐では城主上杉氏憲は小田原城に詰めていたため不在で、重臣秋元長朝・杉田因幡が守備していたが落城寸前となり開城した。 徳川家康が関東に入部すると(長沢)松平康直が三河国長沢から一万石で入封する。康直が没すると家康の子松千代が長沢松平氏を継いだが夭折し、忠輝が継いだ。 ・慶長7年(1602年)忠輝が下総国佐倉に転封 ・慶長15年(1610年)(桜井)松平忠重が八千石で入封するが、元和8年(1622年)上総国佐貫へ転封 ・元和8年(1622年)酒井忠勝が下総国から一万石に加増され入封、その後三万石、寛永3年(1626年)更に五万石に加増となり忍城へ移封となり廃城となった。 花園城:築城年代は定かではないが平安時代末期に藤田政行によって築かれたと云われる。藤田氏代々の居城で、藤田氏は武蔵七党の一つ猪俣党で武蔵国榛沢郡藤田郷を発祥とする。 室町時代は山内上杉氏に属していたが、小田原北条氏が勢力をのばすとそれに従い、北条氏康の三男氏邦を養子に向かえ用土城に隠棲し用土氏を名乗った。 天正18年(1590年)豊臣秀吉による小田原征伐軍によって攻められ落城した。 天神山城:築城年代は定かではないが藤田康邦によって築かれたと云われる。 藤田氏は武蔵七党の一つ猪俣党で武蔵国榛沢郡藤田郷を発祥とする。 室町時代は山内上杉氏に属していたが、小田原北条氏が勢力をのばすとそれに従い、北条氏康の三男氏邦を養子に向かえ隠棲した。氏邦は天神山城を居城としていたが、後に鉢形城に居城を移す。 天正18年(1590年)豊臣秀吉による小田原征伐軍が鉢形城を落とすと開城した。 千馬山城:築城年代は定かではないが用土新左衛門によって築かれたと云われる。 用土氏は天文15年(1546年)藤田康邦は小田原北条氏に降って四男氏邦を養子に迎えて家督を譲った。この康邦が用土氏と名乗りを変えているが、千馬山城の用土新左衛門は藤田氏の分家筋の用土氏と推測されているようである。 上杉謙信に呼応して高松城に籠城していた秩父衆が北条氏に降ると、北条氏邦は千馬山城の用土業国と相談して人質を出すように指示している。 16:20終了。 17:00川越駅東武東上線で出発、池袋で地下鉄丸ノ内線で東京に向かう。 18:10東京駅到達。 18:20東京駅新幹線のぞみで出発 20:50新大阪駅到達。 今回の旅行、関東地方の埼玉県に足を運び埼玉県に点在する比較的マイナーなお城9か所を訪れ楽しみました。平城はほとんどが城址公園に変貌し整備されていましたが、山城は確認が難しく、時間がかかり、案内板のみの城跡も多かったです。 |
         |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百三十三弾:山梨県お城・城下町巡り観光 2018年5月19日-20日 南アルプスをはじめ、多くの山々が自然の障壁となり、他国と交戦することは珍しく、安定した時代が長く続いたが、武田氏滅亡後に起きた天正壬午の乱では、甲斐も大規模な戦闘舞台となった山梨県に足を運び山梨県に点在する比較的マイナーなお城10か所を訪れました。 19日15:43新大阪新幹線ひかりで出発 17:55三島駅到達、レンタカーで甲府方面に向かう。 20:30甲府市内のホテル到着後周辺を散策し食事を済ませて就寝。 20日7:30レンタカーで出発、お城巡り。 勝山城:築城年代は定かではない。 永正年間(1504年~1521年)に武田信繩の異母弟油川彦八郎信忠が籠もり、武田氏の家督を巡って信繩と争った。 永正5年(1508年)武田信虎のときに油川氏が滅亡して信虎が甲斐を平定するが、永正12年(1515年)には大井信達が反乱を起こし、これに呼応した駿河の今川氏の軍勢が勝山城に入っている。 大永元年(1521年)今川氏の武将福島正成が一万五千の軍勢を率いて甲斐へ侵攻、勝山城へ移り布陣したが、信虎はこの軍勢を撃退した。 天正10年(1582年)天正壬午の乱では徳川家康の軍勢が右左口から侵攻して勝山城を占拠し、修築している。 躑躅ヶ崎館:永正16年(1519年)武田信虎によって築かれた。信虎の時代に石和から躑躅ヶ崎に館を移し、甲斐守護の館として政治の中心地となった。 武田氏は武田信玄の時代に甲斐・信濃を中心に勢力を拡げたが、武田勝頼の時代に織田信長・徳川家康連合軍と長篠で戦って大敗北を喫し、天正9年(1581年)に新府城を築いて居城を移したものの、天正10年(1582年)には織田信長の軍勢によって攻められ滅亡した。 武田氏が滅亡すると甲斐には信長の武将川尻秀隆が入部したが、本能寺の変が起こると蜂起した甲斐国人一揆によって討たれてしまう。空白となった旧武田領を巡り、徳川氏と北条氏が戦った(天正壬午の乱)。この戦いで甲斐は徳川家康の所領となり、平岩親吉が入った。しかし、徳川家康もまた関東へ移封となり、豊臣秀吉の家臣羽柴秀勝、加藤光泰、浅野長政と次々と領主が代わっていく。この間に甲府城が築かれ、政治の中心も躑躅ヶ崎から甲府城へと移り躑躅ヶ崎は廃城となった。 要害城:永正17年(1520年)武田信虎によって築かれたと云われる。 信虎は永正16年(1519年)石和から躑躅ヶ崎館に居城を移し、翌年詰の城として要害山城を築いた。 大永元年(1521年)今川氏の部将福島正成が甲斐国に侵攻する。このとき信虎の正室大井の方は懐妊中で、躑躅ヶ崎館を離れ要害山城に籠った。この時生まれたのが武田晴信で後の信玄である。 天正3年(1575年)長篠合戦で大敗した武田勝頼は、翌年要害山城の修築を開始する。 しかし、天正9年(1580年)方針を転換して新たに新府城を築いた。 武田氏滅亡後も改修し維持されたが慶長5年(1600年)廃城となった。 於曾屋敷:逐次幼年代は定かでは内が於曾氏によって築かれたと云われる。 於曾氏は古代の豪族三枝氏の支族であったが、応保2年(1162年)の八代荘を巡る争いで没落し、その後は加賀美遠光の四男と五男が於曾に入って加賀美氏系の於曾氏が出てくる。 於曾氏は武田信玄の時代には於曾左京亮信安が一族の板垣氏の名跡を継いでいる。 連方屋敷:連方屋敷は東山梨駅の東にあり、一辺約100m程のやや不整形な方形の区画となっている。現在は県指定史跡となっているが、内部は畑や民家もある。 ほぼ全周を土塁が巡っているが、北東や南の一部は土塁が欠損している。堀は北から西に掛けて良く残っている。入口は南の道路に面して案内板がある。 勝沼氏館:築城年代は定かではないが勝沼氏によって築かれた。 勝沼氏は甲斐国山梨郡勝沼郷発祥で、武田信縄の子で武田信虎の弟である次郎五郎信友が勝沼に住んで勝沼氏を名乗ったことに始まる。 天文4年(1535年)勝沼信友は北条氏綱との合戦で敗北して討死した。 跡を継いだ嫡男信元は永禄3年(1560年)逆心の企ありとされ、武田信玄によって成敗された。 岩殿城:築城年代は定かではない。 また、築城者に関しても武田氏とも小山田氏ともいわれているが定かではない。 天正10年(1582年)新府城にいた武田勝頼は、織田氏の進軍に対して、小山田信茂の進言により新府城に火をかけ、岩殿城を目指して退去した。 しかし、小山田信茂は勝頼を受け入れず、勝頼は天目山で自刃、甲斐国武田氏の嫡流は滅亡した。 駒宮城:駒宮城はさして大きな城郭ではないが、急峻な山上にあり、明瞭な堀切と城塁を有しているので、そこそこの要害であったと思われる。岩殿山城の有力支城の1つだったと見るべき城郭である。 谷村陣屋:元禄17年(1704年)谷村藩主秋元喬知(朝)が武蔵国川越に転封となり、谷村藩は廃藩となって宝永2年(1705年)天領となった。 この都留郡の幕府直轄地を管轄したのが谷村陣屋である。 御坂城:天正10年(1582年)北条氏によって築かれたと云われる。ただし、これ以前に武田氏によって烽火台のような施設があったとも云われる。 天正10年(1582年)武田氏は織田信長によって攻め滅ぼされ、織田の武将河尻秀隆が甲斐の大半を統治した。しかしそれもわずかな期間で、織田信長が本能寺の変で倒れると国一揆が起こり河尻秀隆は討死して甲斐は空白地となった。この武田氏の旧領を巡って徳川氏と北条氏が争うこととなる。北条方は北条左衛門が御坂城に陣取りると、徳川方の鳥居彦左衛門が小山城に陣取って対峙し、御坂の黒駒で合戦となると徳川が勝利して北条は御坂城へ退いた。その後、北条氏と徳川氏は和睦となり、御坂城も廃城となった。 16:00終了、三島駅に向かう。 17:30三島駅到達。 17:48三島駅新幹線ひかりで出発。 20:00新大阪駅到達。 今回の旅行、山梨県に点在する比較的マイナーなお城10か所をおとずれ楽しみました。 館と名の付く城跡は公園等で整備されていましたが、山城は今回も地味で探すのが一苦労でした。 |
             |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百三十二弾:広島県お城・城下町巡り観光 2018年5月12日-13日 中国地方に位置し毛利元就が厳島の戦いで陶晴賢を破ったことをきっかけに、中国地方に巨大な勢力が展開され、山陰を抑えた吉川元春、山陽を治めた小早川隆景による毛利両川体制が支配力の拡大に大きく寄与した広島県に足を運び、広島県に点在する比較的マイナーなお城12か所を訪れました。 12日19:08新大阪新幹線さくらで出発 20:14福島駅到達、駅前のホテル到着後?華街を散策し食事を済ませて就寝。 13日8:00レンタカーで出発、お城巡り。 福山城:築城年代は定かではないが柚谷新三郎元家(湯谷又八郎久豊)によって築かれたと云われる。 萩原城の支城として築いたもので、元家の子である湯谷又左衛門実義に守らせた。 永禄12年(1569年)毛利隆元を毒殺した疑いで和智誠春と柚谷元家は厳島に幽閉され、誅殺された。これによって毛利の追討軍が和智氏の城へと向かうとの知らせを受け、福山城では湯谷実義が家臣二十八名とともに自刃して一戦も交えることなく落城したという。 甲山城:築城年代は定かではないが元享年間(1321年~1324年)頃に山内通資によって築かれたと云われる。 山内氏は始め蔀山城を居城としていたがこれを弟通俊に譲って新たに甲山城を築いて移った。 山内氏は始め比叡尾山城の三吉氏、南天山城の和智氏、大富山城の久代宮氏らと所領の争奪を繰り広げていた。周防国大内氏の勢力が備後に及ぶと大内氏に従ったが、出雲の尼子氏の勢力が増すと尼子氏に属するようになった。 天文9年(1540年)尼子氏が毛利元就の郡山城を攻めると、山内氏はこれに参戦したが尼子氏は敗れた。天文11年(1542年)には逆に大内義隆が尼子氏の月山富田城を攻めたが、このときは大内方として参戦するも、尼子方に寝返り大内氏の大敗となった。 その後、山内氏は毛利に従うようになり、関ヶ原合戦の後は防長二カ国に減封となった毛利氏に従い長門へ移り廃城となった。 蔀山城:正和5年(1316年)山内通資によって築かれたと云われる。 山内氏は相模国鎌倉郡山内荘発祥で源頼朝に従って功を挙げ備後国比婆郡地毘荘の地頭職を得た。 正和5年(1316年)山内首藤家の惣領通資が備後に下向して蔀山城を築き本拠とした。元享年間(1321年~1324年)に通資は甲山城へ居城を移し、蔀山城は弟の五郎通俊に譲られた。通俊は多賀山氏を称し、多賀山内首藤家として代々蔀山城を居城とする。 大永6年(1526年)多賀山通続のとき、尼子氏から大内氏に鞍替えしたことから尼子氏によって攻められ、享禄2年(1529年)落城した。その後、安芸の毛利元就に従っていたが、天正19年(1591年)多賀山通信のとき毛利輝元によって改易となり、児玉与三郎が城主となった。 五龍城:築城時期に関しては諸説あるが南北町時代に宍戸朝家によって築かれたと云われる。 宍戸氏は源頼朝に仕えた八田知家を祖とする。八田宗綱の女八田局は源義朝の妾となって知家を産んだが、平治の乱によって義朝が誅せられると知家は八田局に抱かれて八田宗綱の元に走り宗綱の猶子として育った。 八田知家の四男家政が常陸国宍戸を領して宍戸氏を名乗り、安芸国高田郡も領した。元弘3年(1333年)知時の子朝家は足利尊氏に従って六波羅を攻め、その功によって安芸国甲立荘を賜わり、建武元年(1334年)甲立に下向し、はじめ柳ヶ城を居城としたが、後に五龍城を築いて移った。 宍戸氏は五龍城を本拠として次第に勢力を広げ郡山城の毛利氏とも争ったが、毛利元就の長女五龍姫が宍戸隆家と婚姻することで和睦した。以後、宍戸氏は毛利一門の筆頭として毛利氏の勢力拡大に貢献し、関ヶ原合戦後に防長二ヶ国に減封となった後は、周防国佐波郡右田へ移り、後に熊毛郡三丘で一万千三百石余りを領した。 猿掛城:築城年代は定かではないが南北朝時代に高橋氏によって築かれたと云われる。 高橋氏は石見国を本拠とした一族で、その勢力は石見のみならず安芸へも及んでおり、その一族が居城した。 大永5年(1525年)高橋大九郎統種の代に内訌が起こると、五龍城主宍戸元源によって攻められ猪掛城は落城した。 鈴尾城:永徳元年・弘和元年(1381年)福原広世によって築かれたと云われる。 福原氏(ふくばら)は大江広元の次男長井時広を祖とする。応安元年(1371年)長井貞広は毛利元春の五男広世を養子に迎えた。広世が家督を継いだ後、実父である毛利元春より福原村を譲られ鈴尾城を築き居城とした。 福原貞俊の妹は毛利弘元に嫁ぎ、毛利興元・毛利元就の生母となった。江戸時代には萩藩の永代家老となった。 今田城:築城年代は定かではない。 永享年間(1429年~1441年)に山県満政が今田に築城し今田氏を称した。 今田氏は安芸国守護武田氏に属していたが、武田氏の衰退とともに没落し、 後に吉川経高、経忠父子が今田氏を称して吉川氏に属した。 吉川元春館:天正11年(1583年)吉川元春によって築かれた。 天正10年(1582年)嫡男元長に家督を譲った元春が隠居所として築いたのが吉川元春館である。 天正14年(1586年)吉川元春は元長とともに秀吉による九州征伐に従軍していたが、豊前国小倉城で没し、元長も翌15年(1587年)に日向国都於郡で没した。家督は三男広家が継いだが、吉川元春館はこの広家の時代に完成したようである。 天正19年(1591年)吉川広家は出雲国富田城へ転封となり、慶長5年(1600年)関ヶ原合戦で敗れた後は周防国岩国へと移り、安芸国から去っていった。 日野山城:築城年代は定かではないが吉川氏によって築かれた。 毛利元就の次男元春が安芸吉川家に養子に入り家督を継ぐと、天文19年(1550年)に小倉山城から居城を移した。 元春が居城を移す前にも何らかの要害施設があったものと考えられているが、本郭的な城郭整備は元春入城以後も続けられ、元長・広家と三代の居城であった。天正19年(1591年)吉川広家の時に出雲国富田城に居城を移し廃城となった。 小倉山城:築城年代は定かではないが南北朝時代末期に吉川経見によって築かれたと云われる。 駿河国入江荘吉川邑発祥の吉川氏は、経高が安芸国大朝荘に下向したのが始まりで、当初は駿河丸城を居城としたと云われる。その後、経見のとき小倉山城を築いて居城を移した。 その後、代々吉川氏の居城として続いたが、天文19年(1550年)養子に迎えた毛利元就の二男元春のとき、日野山城を築いて居城を移し、小倉山城は廃城となった。 駿河丸城:正和2年(1313年)吉川経高によって築かれたと云われる。 吉川氏は駿河国入江荘吉川邑発祥で、正和2年(1313年)吉川経高が安芸国大朝荘に移り住んだことから安芸吉川氏が始まる。このとき経高は八十歳であったといい、文保3年・元応元年(1319年)に八十六歳で没している。 安芸へ下向した吉川氏が最初に居城としたのがこの駿河丸城とされ、以後四代経見の頃に小倉山城に本城を移すまでの居城であった。 三入高松城:築城年代は定かではない。熊谷氏が居城とする以前に二階堂是藤が居たと云われ、熊谷直時によって追い出されたと云われる。 熊谷氏が伊勢が坪城からこの高松山城に居城を移した時期は詳らかではないが、熊谷信直の頃と考えられている。熊谷氏は安芸国守護職武田氏に従って各地を転戦し、その所領を増やしたが、永正14年(1517年)武田元繁に従って出陣した熊谷元直は有田合戦で毛利・吉川の軍勢に敗れて討死、このとき武田元繁はじめ、八木城主香川行景、己斐城主己斐宗瑞なども討死し、やがて安芸武田氏は滅亡する。 その後、熊谷信直の時に毛利氏に従い、信直の娘は毛利元就の二男吉川元春に嫁いでいる。 18:00終了、広島駅に向かう。 18:30広島駅到達 19;01広島駅、新幹線みずほで出発 20:24新大阪駅到達。 今回の旅行、中国地方の広島県に足を運び、広島県に点在する比較的マイナーなお城12か所を訪れ楽しみました。 生憎雨、雨の中をしっかり12か所の城跡を探し訪れました。 ほとんどが地味な城跡で案内板しかない城跡もありました。 |
      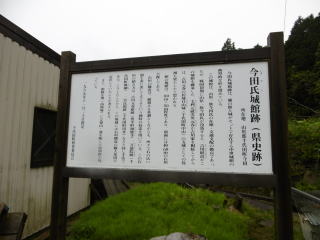        |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百三十弾:愛知健お城・城下町巡り観光 2018年4月14日-15日 中部地方の室町時代に尾張の守護・斯波氏に変わり、織田氏が権力を掌握する。三河では今川氏が駿河、遠江から勢力を拡大してきたが」、桶狭間の戦いで今川義元が織田信長に返り討ちに遭うと、急激に衰退した愛知県に足を運び、愛知県に点在する比較的マイナーなお城10か所を訪れました。 14日17:00車で出発、第二京阪、京滋バイパス、名神、新名神経由して豊川インター下車 19:30豊川インター付近のホテル到着後周辺を散策し食事を済ませて就寝。 15日7:00車で出発、お城巡り。 田原城:築城年代は定かではなく諸説あるが、文明12年(1480年)戸田宗光によって築かれたと云われる。 宗光は渥美半島を掌握すべく田原へ移り、駿河の今川氏の庇護のもとその支配を広げる。 しかし、今川義忠が塩買坂で討死し今川家中が内乱状態となると宗光は田原城を子の憲光に譲り、宗光自身は二連木城を築いて移った。 二連木城に移った宗光が今川方の舟形山城を落とすなど、戸田氏は今川氏に対抗したが、宗光が没した後は再び今川氏に属した。 戸田氏は今川家へ人質として送られる松平竹千代(徳川家康)を強奪して、織田家へ送ったため、天文16年(1547年)今川氏に攻められ田原城は落ち、一族は没落した。 ・天正18年(1590年)池田輝政が入封。 ・慶長5年(1600年)輝政は播磨国姫路へ転封。 ・慶長6年(1601年)伊豆国下田より戸田尊次が一万石で入封。 ・寛文4年(1664年)忠治の時、肥後国富岡へ転封。 ・寛文4年(1664年)三河国拳母より三宅康勝が一万二千石で入封。 以後、三宅氏が明治まで続く。 野田城:永正5年(1508年)菅沼定則によって築かれたと云われるが定かではない。 田峯菅沼氏の定忠の三男定則が富永荘の地頭富永直郷の後継となり、野田菅沼氏の祖となった。 天正元年(1573年)武田信玄が東三河に侵攻、野田城に攻め寄せたが思うように落とせず、金山衆を用いて井戸水を抜き落城させたという。 武田信玄の死因の一つとして、村松芳休の笛の音に聞き惚れた信玄が、本陣を抜け出して城に近付いた所を鳥居三左衛門の鉄砲に討たれ、重傷を負って甲斐国に引き上げる途中で亡くなったと云う伝説は、この野田城合戦でのことである。 宇利城:築城年代は定かではないが熊谷氏によって築かれたと云われる。 熊谷氏は熊谷直実の後裔で、熊谷兵庫頭重実の頃に宇利城を築いたと考えられている。 享禄3年(1530年)熊谷実長のとに松平清康によって攻められ落城し熊谷氏は離散した。この後、宇利城は清康から菅沼定則に与えられ、さらに近藤康用が城主となった。 近藤氏は後に柿本城へ移り、その後の宇利城の動向は定かではない。 古宮城:元亀2年(1571年)頃に武田氏の家臣馬場美濃守信春によって築かれたと云われる。 三河に侵攻して作手の亀山城主奥平氏を降した武田氏が、この地における拠点として築かれたのがこの古宮城で馬場信春の縄張りによるものと伝えられる。 この古宮城には小幡又兵衛、甘利左右衛門、大熊備前守らが城将として駐屯したという。 天正元年(1573年)奥平貞能・貞昌(後の信昌)父子は武田氏を離反して徳川氏に帰属した。このとき古宮城も徳川・奥平氏によって攻められ落城した。 田峯城:文明2年(1470年)菅沼定信によって築かれたと云われる。 菅沼氏は清和源氏で三河国額田郡菅沼郷発祥、定成の時に田峯に移り住んだ。その後、奥三河の地に勢力を広げ、長篠・野田・島田菅沼氏の宗家として田峯菅沼氏と呼ばれた。 天正3年(1575年)長篠合戦で菅沼定忠は武田方として参陣するが大敗、勝頼とともに田峯城へ戻ったものの留守居の叔父定直等の謀反によって入城できず、武節城へ引き上げた。その後奥平氏によって武節城をも追われ信濃国伊那郡へ落ちていたが、天正4年(1576年)定忠は田峯城を急襲してこれを落とし、謀反の一族96人を惨殺した。 足助城:築城年代は定かではない。 南北朝時代に飯盛城主足助氏が築いたとも云われ足助七屋敷の一つとされるが、発掘調査で出土した遺物ではこの時代のものは発見されていない。 明確な最初の城主は足助鈴木氏で三河鈴木氏の支族である。 足助鈴木氏は鈴木忠親・重政・重直・信重・康重と続いた。 鈴木重政は大永5年(1525年)松平清康によって攻められ降ったが、それ以降も離反・従属を繰り返している。元亀2年(1571年)武田信玄の西三河侵攻により真弓山城は落城し、城主鈴木重直は岡崎へ逃れた。これにより一時的に武田方の持城となったが武田信玄が病没すると徳川家康の軍勢が武田氏の軍勢を追い払い、再び鈴木重直が城主となった。 天正18年(1590年)小田原討伐の後、徳川家康が関東へ移封となると鈴木康重は家康に従って関東に移った。しかし、康重は関東での待遇に不満を抱いて直ぐに出奔したという。 飯森城:築城年代は定かではないが鎌倉時代に足助重秀によって築かれたと云われる。 足助氏は源満政の後裔で山田重直の子重長が足助の地に住み足助を名乗った事に始まるとされる。足助重長は黍生城を築いて居城とし、飯盛城は重長の子足助重秀の時代に築かれたとされる。 治承4年(1180年)足助重行は兄山田重満とともに源行家に加担して美濃国墨俣で平重衡と戦って討死した。 元弘元年(1331年)七代足助重範は元弘の乱で後醍醐天皇の要請に応じて笠置山に籠ったが落城、捕らわれた重範は京の六条河原で斬首された。 松平城:築城年代は定かではないが応永年間(1394年~1428年)に松平親氏によって築かれたと云われる。 松平氏の祖と云われる親氏が松平氏館の詰めの城として築いたもので、親氏が信光とともに岩津城へ移ってからは、信広の居城となった。 大給城:築城年代は定かではないが長坂新左衛門によって築かれたと云われる。 やがて岩津へ進出した松平信光が攻略し、岩津城と共に親忠に譲り、親忠は子の乗元へ譲った。 乗元は岩津城主松平親忠の二男で大給城を居城とする大給松平氏の祖となった。 天正3年(1575年)には滝脇の松平乗高に攻められ落城したという。 天正18年(1590年)6代家乗の時に、徳川家康の関東移封に伴い上野国那波へ一万石で転封となり、廃城となった。 17:00終了、帰路に向かう。 今回の旅行、愛知県に点在する比較的マイナーなお城10か所をおとずれ楽しみました。 今回も史跡公園、立派な石垣等目立った城跡も見かけましたが、大半は地味な城跡でした。 |
            |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百二十八弾:静岡県お城・城下町巡り観光 2018年3月31日-4月1日 中部地方の太平洋に東西に広く位置し、駿河、遠江の守護職となった今川氏の影響力が、南北朝時代から大きかったエリア、残る伊豆は北条氏が治め、今川氏真が徳川家康の攻撃を受け困窮すると、駿河、遠江の支配をあきらめて北条氏を頼った静岡県に足を運び静岡県伊豆半島に点在する比較的マイナーなお城8か所を訪れました。 31日18:03新大阪新幹線のぞみで出発、名古屋にこだまに乗り換え 20:43新富士駅到達、駅前のホテル到着後繫華街を散策し食事を済ませて就寝。 1日8:00レンタカーで出発、伊豆半島のお城巡り 深沢城:築城年代は定かではないが今川氏によって築かれたと云われる。 その後、小田原北条氏の所領となり、北条綱成が在城していたが、元亀元年(1570年)武田氏が侵攻し城を取り囲んだ。武田氏は金山衆を使って攻めたて「深沢城矢文」として有名な矢文を送ると、綱成は開城して相模国玉縄城へ引き上げた。 武田氏は駒井昌直を置いて城を改修したが、天正10年(1582年)武田氏が没落すると昌直は城を焼いて退いた。 天正12年(1584年)徳川家康が三宅康貞を置いて小田原北条氏に備えたが、小田原北条氏が滅亡すると廃城となった。 葛山城:築城年代は定かではないが葛山氏によって築かれた。 葛山氏は藤原北家大森氏の支流で、大森惟康の次男惟兼が駿東郡葛山に住んで、葛山氏を名乗ったことに始まる。 伊勢宗瑞が伊豆の堀越御所を急襲して足利茶々丸を討った時、今川氏から援軍として駆けつけたのが葛山氏で、その後、伊勢宗瑞の次男氏時を養子に向かえた。 今川氏が没落すると武田氏に属し、武田信玄の六男が葛山氏の名跡を継いで葛山信貞となのった。しかし、武田氏も滅亡すると葛山氏も没落した。 山中城:築城年代は定かではないが永禄年間(1558年~1570年)頃に小田原北条氏によって築かれたと云われる。 その後、豊臣秀吉による小田原征伐軍を迎え撃つ為に急ピッチで城の改修が行われる。天正18年(1590年)3月29日北条氏勝を主将とする山中城に、豊臣軍が押し寄せ美濃国軽海西城主一柳直末が討死するなど激戦となったが、圧倒的な兵力によって次々と新手を繰り出し袋崎砦が陥落、それを足掛かりに三の丸、二の丸も陥落し、北条氏勝は城を脱して松田康長が最後まで抵抗したが討死した。落城まで僅か数時間であったという。 興国寺城:築城年代は定かではない。 伊勢宗瑞(北条早雲)は、妹婿今川義忠が文明8年(1476年)戦死した後、家督相続争いをまとめた功によって、はじめて城主となった。 宗瑞は堀越御所の内乱に付け込み、堀越公方足利茶々丸を滅ぼして伊豆の領主になると、伊豆国韮山城を築いて居城を移した。 天文18年(1549年)に今川義元によって、小規模な城郭から改修され、武田、北条、今川によって度々争われた。今川義元が桶狭間合戦によって織田信長に討たれた後、武田氏は駿河国に侵攻すると、それに対して北条氏も駿河国に侵攻し興国寺城を落としたが、元亀2年(1571年)武田氏と北条氏は和を結び、武田氏一門の穴山梅雪の家臣保坂掃部介が城主となった。 武田氏が織田氏に滅ぼされると徳川家康の所領となり、関ヶ原合戦後は天野康景が一万石で城主となったが、康景は百姓を殺害した家臣の引渡しを拒んで西念寺に蟄居し改易となり、興国寺城は廃城となった。 沼津城:築城年代は諸説あり定かではない。 天正7年(1579年)武田勝頼が城を修築して小田原北条氏に備え、香坂昌信を城主としたが、この頃は三枚橋城と呼ばれていた。 天正10年(1582年)武田氏が滅亡すると徳川家康は松平康親を派遣して守備させた。 江戸時代になると大久保忠佐が二万石で三枚橋城に入封したが、慶長18年(1613年)忠佐が嗣子なく没すると大久保家は断絶となり、三枚橋城は廃城となった。 その後は天領となっていたが、安永6年(1777年)水野忠友が三河国大浜一万三千石に七千石を加増され、三枚橋城跡に沼津城を築いた。水野氏は以後八代続き明治に至り、明治元年(1868年)徳川家達が駿河国に入国すると、上総国菊間に転封となった。 韮山城:延徳3年(1491年)伊勢宗瑞(北条早雲)によって築かれた。 小田原北条氏の祖、駿河国興国寺城主伊勢宗瑞は、堀越御所の内乱に付け込み堀越公方足利茶々丸を滅ぼして伊豆の領主になると韮山城を築いて居城を移した。 宗瑞は明応4年(1495年)相模国小田原城を奪い、小田原北条氏の祖となり、永正16年(1519年)韮山で没した。 天正18年(1590年)小田原北条氏は豊臣秀吉の小田原征伐を迎え討つ為、山中城と韮山城を最前線として兵を集めた。 韮山城には北条氏政の弟氏規が城主となり兵三千余で豊臣勢四万余を迎え討った。 豊臣方の軍勢は上山田城、本立寺付城など周囲に付城を築いて包囲する。北条氏も天ヶ岳砦などに支城を築いて守りを固めこれに対抗した。山中城をはじめ、関東の諸城が攻略されるなか韮山城は落城せず、朝比奈泰勝を使者として開城を促し、氏規は開城し退去した。 この氏規の家系が江戸時代に河内国狭山に大名として続いた。 氏規が城を退くと徳川家康の家臣甲斐国浄古寺城主であった内藤信成が城主となったが、関ヶ原合戦の後、駿河国府中へ移封となり韮山城は廃城となった。 長浜城:築城年代は定かではないが室町時代に小田原北条氏によって築かれたと云われる。 天正7年(1579年)北条氏はこの長浜城を普請して駿河湾の水軍の拠点とし、武田氏に備えて梶原景宗が長浜城に派遣された。天正17年(1589年)頃には大川兵庫が城番となっていたが、天正18年(1590年)豊臣秀吉による小田原征伐で、北条氏は水軍を下田城や小田原城に集めたため、長浜城の機能は低下していたようである。 下田城:築城年代は定かではないが北条氏によって築かれたと云われる。 天正16年(1588年)には豊臣秀吉に備えて大改修され、伊豆衆の一人清水上野介康英を城主とした。 天正18年(1590年)豊臣水軍は長宗我部元親・脇坂安治らを大将とする一万余りの軍勢で城を囲んだ。対する北条方は清水康英を大将としてわずか六百余名の兵力であった。 五十日余りに及ぶ籠城の末、開城勧告を受け入れ降伏した。清水康英は当初林際寺に謹慎し、のちに三養院へ移り隠棲し、翌天正19年に没した。 17:30終了。 18:20新富士駅到達。 18:39新富士駅新幹線こだまで出発、名古屋でのぞみに乗り換え 21:05新大阪駅到達。 今回の旅行、中部地方の太平洋に東西に広く位置する静岡県に足を運び静岡県の伊豆半島に点在する比較的マイナーなお城8か所をおとずれ楽しみました。 生憎桜の花見時期に当たり観光の車が多く、帰りの下田から 新富士に向かう道路は大渋滞、かなりの時間を要しました。 お城はマイナーだけあって遺跡遺残も地味で訪れるのに時間を要しました。今回もですが観光名所の多い県はマイナーなお城の案内板も少なですね。 |
              |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百二十七弾:千葉県お城・城下町巡り観光 2018年3月17日-18日 関東地方の安房、上総、下総の房総三国で乱を起こした平忠常の後裔・千葉氏が基盤を築いたあと、里見氏が台頭し、戦国時代には安房国を支配した。天下統一後は、江戸に近い将軍のお膝元として有力大名が配された千葉県に足を運び、比較的マイナーなお城11か所を訪れました。 17日13:50新大阪新幹線のぞみで出発 16:23東京駅到達、レンタカーで千葉県市原方面に向かう。 16:00市原市内のホテル到着後周辺を散策し食事を済ませて就寝。 18日6:30レンタカーで出発、房総半島に点在するお城巡り 佐貫城:築城年代は定かではないが応仁年間(1467年~1469年)に武田義広によって築かれたのが始まりとされる。 天文6年(1537年)家督相続争いで武田信隆が峰上城、佐貫城、海造城を拠点とし、小田原北条氏を頼って武田信応に対抗したが、信応方の足利義明、里見義堯によって落城することとなる。 その後は里見氏の城となり、里見義弘の頃には本城ともなったが、里見義弘が没するとその子梅王丸に家督を継がせた加藤信景が佐貫城に入って安房の里見義頼と敵対する。天正8年(1580年)里見義頼は上総へ侵攻し、佐貫城を攻めたてたため、加藤信景は梅王丸の助命を求め開城した。 天正18年(1582年)豊臣秀吉による小田原征伐の後に関東に入部した徳川家康は内藤家長に二万石を与え佐貫城主とした。 館山城:築城年代は定かではないが里見氏によって築かれた。 天正10年(1582年)頃には岡本城の支城として存在していたようである。 天正18年(1590年)豊臣秀吉による小田原征伐で里見氏は豊臣方として参陣するが、里見氏が保護していた御弓公方足利氏の遺児頼淳のために鎌倉を回復しようと企て、また、惣無事令に違反した咎もあって里見氏領の上総領は没収され、安房国一国を安堵された。 これによって上総領の家臣は安房国へ引き上げることを余儀なくされる。これが居城を岡本城から館山城へ移す要因の一つとされ、天正19年(1591年)以降里見氏は館山城に居城を移した。 慶長19年(1614年)里見忠義は大久保忠隣の罪に連座する形で安房国を没収され、伯耆国倉吉に三万石で転封となり、元和8年(1622年)忠義が没すると嗣子なく里見家は断絶となった。里見氏の後、館山城は完全に破却された。 稲村城:築城年代は定かではないが里見氏によって築かれた。 里見氏は上野国碓氷郡里見郷の発祥で、新田義重の子義俊が里見郷に住んで里見を名乗ったことに始まる。 相模国に逃れた里見義実は三浦氏の援助を受けて、安房国白浜を拠点に勢力をひろげ、房総里見氏の祖となる。里見氏の嫡流は義豊の代で途切れ(前期里見氏)、それ以後は庶流の義尭の系統となる。この義尭以後、稲村城は破棄された。 一般的には義通の子義豊が幼少であった為、後見人として弟実尭が義豊が元服した後も義豊に譲らず、義豊は実尭を自刃させ、実尭の子義尭が父の仇として義豊を討ち、里見氏が庶流の血筋へと替わっていく。 しかし、「さとみ物語」(館山市立博物館)によれば、義豊は既に家督を譲られて成人していたということである。義豊は実尭を殺害し、正木通綱をも滅ぼすと、実尭の子義尭は上総国百首城にたて籠って小田原北条氏の支援を得て義豊を安房から追放、翌年には義豊の軍勢を犬掛けの合戦で討ち取った。 勝浦城:勝浦城は、天文十一年(1541)の頃、勝浦正木氏の初代、正木時忠が入城。それ以前は、真里谷武田氏の砦のようなものであったろうと言われています。その後、二代時通、三代頼忠の居城となります。しかし、天文十八年(1590)、豊臣秀吉により安房里見氏が領地の一部を没収されると、里見氏と親交のあった勝浦城主正木頼忠も城を明け渡し、安房に逃れます。なお、頼忠の娘は、後に徳川家康の側室(お万の方)となり、紀州徳川頼宣と水戸徳川頼房をもうけます。高名な水戸光圀(黄門)は、お万の方の孫にあたります。また、絶壁を布を伝わって下りたという「お万布ざらし」伝説は、神社裏の断崖絶壁が舞台です。 万喜城:万喜城は、三方を夷隅川に面した丘陵(城山)山頂部に築かれている。 城山全山が城塞化されていると云っていいほどの堅固な城だ。 現在は山頂部の二段の曲輪と物見台(展望台がある)が主郭部を構成し、主郭南側は侵食谷によって隔てられた痩せ尾根が幾筋もあり、この支尾根を削平して曲輪を置き、更に堀切を随所に設けて防衛ラインを構築している。 北麓から山頂の公園までの車道の両側には民家敷地ともなっている曲輪群が幾段にも構築されて、比較的緩やかな登りとなるこのルートの防備を固めている。 これらの縄張りを見て、かつ実際の遺構を見ると、この城が里見氏からの幾度も続いた来攻を凌いだ「要害の城」であると肌で感じることが出来る。 大多喜城:天正18年(1590年)本多忠勝によって築城された。 徳川家康が関東に入部すると、家康は里見氏への押えとして本多忠勝を根古屋城に十万石で配置する。忠勝は根古屋城が防備に適さないとして、新たに大喜多城の築城を家康に願い出て許された。 ・慶長6年(1601年)本多忠勝は伊勢国桑名に転封。 ・慶長6年(1601年)忠勝の次男忠朝が五万石で残り、元和元年(1615年)大坂夏の陣で戦死。 ・元和元年(1615年)甥の本多政朝が遺領を継ぎ、元和3年(1617年)播磨国龍野へ転封。 ・元和3年(1617年)武蔵国鳩谷より阿部正次が三万石で入封、元和5年(1619年)相模国小田原へ転封。 ・元和9年(1623年)武蔵国岩槻より青山忠俊が二万石で入封、寛永2年(1625年)改易となる。 ・寛永15年(1638年)阿部正能が一万石で入封、寛文11年(1671年)正能は武蔵国忍の養子ととなる。 ・寛文11年(1671年)武蔵国岩槻より阿部正春が一万六千石で入封、元禄15年(1702年)三河国刈谷へ転封。 ・元禄15年(1702年)三河国刈谷より稲垣重富が二万五千石で入封、同年下野国烏山に転封。 ・元禄16年(1703年)相模国玉縄より(大河内)松平正久が二万石で入封、以後明治に至る。 久留里城:築城年代は定かではない。城の創築は定かではないが真里谷武田氏の支城として築かれたとも云われる。 本格的な築城は里見義尭によるもので、義尭は久留里城を居城として小田原北条氏の攻撃にさらされ、永禄7年(1564年)には北条氏康によって攻められ落城する。しかし、永禄10年(1567年)には三舟山で北条氏を敗り、久留里城を奪還した。 天正6年(1578年)里見義弘が没すると、安房国岡本城の里見義頼と梅王丸との間で家督相続を巡る内乱が勃発し、天正8年(1580年)義頼は久留里城を攻略して、後に梅王丸を捕える。以後里見氏の居城は安房国岡本城へと移り、天正18年(1590年)頃には城代として山本越前守が在城した。 天正18年(1590年)豊臣秀吉による小田原征伐で里見氏は豊臣方に属するものの上総国の所領を没収され、上総国は関東に入部した徳川家康の所領となる。 家康は榊原康政の子大須賀忠政を遠江国横須賀より三万石で入部させた。 ・慶長6年(1601年)大須賀忠政は遠江国横須賀へ転封。 ・慶長6年(1601年)相模国より土屋忠直が二万石で入封、延宝7年(1679年)頼直の時、改易となり廃城。 ・寛保2年(1742年)上野国沼田より黒田直純が三万石で入封、以後明治に至る。 真里谷城:康正2年(1456年)武田信長によって築かれたと云われる。 上総国武田氏の武田信長は康正2年(1456年)下総国市河合戦のときに庁南城と真里谷城を築き、真里谷城には信長の嫡男信高の二男清嗣(信興)が城主となり真里谷武田氏の祖となった。 天文6年(1537年)真里谷武田信隆・信応兄弟による内訌で、一時は小弓公方足利義明の支援を受けた信応が家督を継いだが、天文7年(1538年)の国府台合戦によって義明が没した後は、北条氏の支援を受けた信隆が家督に復した。しかし、天文12年(1543年)再び真里谷一族に内紛が勃発し真里谷武田氏の勢力は没落した。 土生城:神亀年間(767年~770年)に鎮府将軍大野東人が蝦夷に対する備えとして「金城」あるいは「貴船城」と呼ばれる城砦を築いたのがその始まりとされるが定かではない。 長享2年(1488年)小弓公方足利氏の家臣中野城主酒井定隆が土気城を築いて土気酒井氏の居城となった。 酒井氏の出自は土岐氏の庶流、あるいは藤原秀郷流波多野松田氏の後裔など諸説あって定かではない。 天文7年(1538年)小弓公方足利義明が没すると、後に土気酒井氏は東金酒井氏らとともに北条氏に属した。永禄4年(1561年)上杉政虎(謙信)が越山して関東に出陣すると、北条氏を離反して上杉氏に属したが、政虎が越後に戻ると再び北条氏に属した。 永禄7年(1564年)国府台合戦で酒井胤治は北条氏を離反して里見氏に付いた。しかし翌年北条氏政の軍勢によって土気城は包囲され、酒井氏は里見氏に援軍を要請したが援軍を得ることはできなかった。天正4年(1576年)酒井氏は再び北条氏に属し、天正18年(1590年)豊臣秀吉による小田原征伐で北条氏とともに滅亡した。 大椎城:大椎(おおじ)城は平安時代中期、上総・下総に強大な権力を持っていた平忠常が築城し、長元の乱(1027~1031)を起こした根拠地と云われている。この忠常は平将門の叔父であった良文の孫にあたり、当時不当な貢税を課した受領(国司)の暴政や貴族権力に反抗した。 この乱の後、忠常の子・常将が初めて「千葉氏」を名乗り、常長・常兼と続き、その子・常重は大治元年(1126)、この城から千葉城(猪鼻城・湯の花城)に移り廃城になったと考えられている。 しかし、「図説・房総の城郭・(千葉城郭研究会編)」によると、「この地はもともと源頼朝に滅ぼされた上総氏の領するところでもあり、千葉氏がここから興ったというのは史実ではなく伝承の域を出ない。」としている。 戦国期には、土気城主酒井氏が村田川流域を押さえる支城として大規模な改修をしたと考えられる。 尚、千葉氏系流は戦国末期の重胤を経て更に現代の千葉胤雄・勝胤までほぼ1千年40代に亘って続いており、千葉県で各地に多く繁栄している。 国府台城:千葉県市川市国府台にある里見公園は、花見の名所になっているが、ここはかつて国府台城だった。1479年、太田道灌の弟・ 太田資忠が臼井城を攻めるために築城したのが国府台城とされる。その臼井城合戦で太田資忠は討ち死にしている。(鎌倉大草紙によれば、下総国 境根原合戦を前に太田道灌が仮の陣城を構えたとあり、これが国府台城であるという説もあり) 特に有名なのが「北条軍 VS 小弓公方および里見軍」で行われた、第一次/二次国府台合戦の古戦場跡であること。戦国時代、下総国支配の決定戦だったと言える。戦後、国府台城は北条氏によってさらに規模が拡張強化されたと考えられる。当時は、真間山(弘法寺)から松戸駅東側(相模台城)までを国府台と呼んでいた。 17:00終了東京駅に向かう。 18:00東京駅到達 18:40東京駅新幹線のぞみで出発 21:10新大阪駅到達 今回の旅行、関東地方の千葉県に足を運び、房総半島に点在する比較的マイナーなお城11か所を訪れ楽しみました。 今回のお城は再建した天守閣等、立派な城跡が多く、城マニアの方だけでなく楽しむことができた城めぐりでした。 千葉県の房総半島、車も少なく、信号も少なく、渋滞のストレスもなくドライブできました。大都会東京から少し離れるとまだまだ田園風景がいっぱいですね。 |
           |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百二十五弾:熊本県お城・城下町巡り&九州四十九院薬師霊場観光 2018年2月24日-25日 九州の西に位置し、室町時代に、古くから同地で力を持っていた菊池氏が守護になり、阿蘇氏、名和氏、相良氏などが各地を支配するが、争乱で絶えなかった、やがて大友氏が肥後に進出し、龍造寺氏、島津氏と対立することになった熊本県に足を運び熊本県に点在するお城6か所、熊本県にに点在する九州四十九院薬師霊場5か所を訪れました。 24日17:30伊丹空港出発。 18:40熊本空港到達、レンタカーで熊本インター下車、インター付近のホテル到着後繫華街を散策し食事を済ませて就寝。 25日8:00レンタカーで出発、霊場お城巡り。 光厳禅寺: 法泉寺:法泉寺のご本尊は、聖観世音菩薩、脇本尊として薬師瑠璃光如来をお祭りしています。 法泉寺の開創は、1293年(永仁元年)鎌倉時代です。今年から遡ること715年前です。 鐘楼堂は古くなっていたものを終戦50年の平成7年に改修して、戦争の為に供出してなくなっていたものを50年ぶりに「平和祈念梵鐘」として造りました。 午前6時と午後6時に世界中で戦火の犠牲になられた方々のご冥福をと恒久平和を願って鳴り響いています。 西厳殿寺: 菊の池城:築城年代は定かではないが延久年間(1069年~1074年)に菊地則隆によって築かれたと伝わる。 十六代菊池武政のとき菊池城に居城を移した後は菊池十八外城の一つとして利用された。 守山城:築城年代は定かではないが正平年間(1346年~1370年)に菊池氏によって築かれたと云われる。 菊池氏は太宰府官藤原政則の子孫とされ、藤原則隆のときに肥後に下向し菊の池城を築いたという。十六代菊池武政のとき、菊の池城から隈部城へと居城を移した。 南北朝時代には南朝の有として肥後国を中心に九州全土にその勢力をのばしたが、北朝方の今川了俊が九州に下向してくるとその勢力は衰退した。 兼朝の時、肥後国守護職を回復し戦国時代に続くが大友氏に破れ嫡流が途絶えた。 菊池氏が滅亡すると赤星氏の勢力下になるが、隈部氏によって追い出され、隈部館から隈部氏が移り居城となる。 隈部氏は北侵する島津氏に降伏したが、豊臣秀吉による九州征伐で秀吉に降伏し本領を安堵された。しかし熊本に入封した佐々成政が検地を行うとこれに反発して挙兵し、成政が菊池城に押し寄せると城村城に籠もってこれに対抗した。これがきっかけとなって肥後国衆一揆が広まり、成政は謹慎の後に切腹、隈部氏もまた嫡流は断絶した。 鞠智城:築城年代は定かではないが7世紀後半に大和朝廷によって築かれた。 天智2年(663年)朝鮮半島白村江の戦いで唐・新羅連合軍に敗れた大和朝廷は九州・中国・四国地方に山城を築いて唐・新羅連合軍の来襲に備えた。 九州では大宰府を中心に基肄城や大野城を築いて防衛線としており、鞠智城は前衛である大野城などへの武器・食糧の供給基地として築かれたと考えられている。 結局大陸から日本への侵攻はなく、その後は役所として利用され10世紀半ばまで存続していたようである。 隈部館:築城年代は定かではないが隈部氏によって築かれた。 隈部氏は大和源氏宇野氏の末裔で菊地氏に仕え隈部の名字を与えられたと云われる。 隈部氏は菊池家臣団において城氏や赤星氏らと並び重要な地位にあった。菊池氏が没落すると大友氏や龍造寺らと結んで勢力を拡大し、天正6年(1578年)には赤星氏を隈府城から追放し、隈府城を本城として移った。 隈部氏はその後、肥後に入封した佐々成政に従ったが、隈部親永は成政の検地に反発して挙兵する。これが肥後国人一揆の発端となったが豊臣秀吉が派遣した援軍に降り、隈部氏は滅亡した。 相良寺: 金剛乗寺: 田中城:築城年代は定かではない。古代豪族和邇氏の末裔といわれる和仁氏累代の居城である。 天正15年(1587年)佐々成政の検地に対して隈部城の隈部親永が反発して国人一揆が発生すると、和仁氏と坂本城主辺春親行などが田中城に籠城して成政に抵抗した。佐々成政は国人一揆を押さえ込もうとしたが、逆に隈本城に攻め込まれたため撤退し、豊臣秀吉に援軍を求めた。秀吉は小早川・立花・鍋島などの諸将に命じて田中城を攻撃させ、安国寺恵瓊の謀略によって辺春氏が寝返り落城した。 筒ケ嶽城:築城年代は定かではない小代氏によって築かれたのが始まりとされる。 小代氏(しょうだい)は武蔵国入間郡小代郷発祥で武蔵七党の一つ児玉党に属していた御家人で武蔵国小代館に住んでいた。 宝治合戦の功により小代重俊が肥後国野原荘の地頭職に任ぜられ、文永8年(1271年)には鎌倉幕府より蒙古襲来に備えて野原荘へ下向するよう命ぜられ、 小代重泰(重康)らの兄弟が下向したことに始まる。 小代氏は以降、肥後国北部の有力国人として代々続き、はじめ大友氏、ついで龍造寺氏、島津氏に属し、豊臣秀吉の九州征伐では秀吉に従って所領を安堵され、肥後に入国した佐々成政、加藤清正そして細川氏の家臣となって近世まで続いた。 17:00終了、熊本空港に向かう。 17:30熊本空港到達。 19:10熊本空港出発。 20:25伊丹空港到達。 今回の旅行、九州の熊本県に足を運び、熊本県に点在するお城を6か所、九州四十九院薬師霊場5か所を訪れ癒されました。 山の頂、畑の中、公園の中に位置する、様々な城跡、楽しめました。 |
                |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百二十四弾:和歌山県お城・城下町巡り観光 2018年2月17日-18日 僧兵集団が力を持ったエリアで、戦国時代に入っても、織田信長、豊臣秀吉に反発した。やがて秀吉の奇襲征伐によって、有力な拠点が相次いで陥落、秀吉は和歌山城を築城し、紀州での支配力を強化した和歌山県に足を運び、御坊から南に点在するお城7か所を訪れました. 17日17:00車で出発、御坊に向かう。 18:30御坊駅前のホテル到着後繫華街を散策し食事を済ませて就寝。 18日7:30車で出発、お城巡り。 平須賀城:築城年代は定かではないが室町時代に野辺弾正忠忠房によって築かれたと云われる。 野辺氏は源経基の子満快の後裔という。 野辺氏は高田土居城を居館として忠房の頃に平須賀城を築いたという。 野辺氏は畠山氏の被官で、湯川氏に属していた野辺光房は永禄5年(1562年)に河内国若江で三好氏と戦い討死した。その子、野辺春弘のとき幡山要害城を築いて居城を移したという。 田辺城:元和5年(1619年)安藤直次によって築かれた。 安藤直次は和歌山に入部した徳川頼宣の付家老で、田辺三万石を賜り田辺城を築いた。これ以前に紀州を領していた浅野氏の家臣浅野氏重が在城した湊城があったが、浅野氏が安芸国広島に転封となると氏重もまた備後国三次へ移った。田辺城の普請は天保年間まで続いた。 龍松山城:築城年代は定かではないが天文年間(1532年~1555年)山本忠行によって築かれたと云われる。 山本氏は清和源氏の子孫ともいわれるが、忠行が紀伊国櫟原荘の地頭として入部したことに始まる。 天正13年(1585年)羽柴秀吉の紀州攻めでは三ヶ月に及んで対峙し和睦となった。しかし、翌年和睦の為に、大和郡山城の羽柴秀長を訪れた山本康長ら13人はその帰路藤堂高虎の館にて謀殺された。 八幡山城:築城年代は定かではないが安宅氏によって築かれたと云われる。 享禄3年(1530年)に安宅氏の跡目相続争いがあり、安宅嫡家大炊頭実俊の弟治部大輔が籠もったという。 安宅本城:築城年代は定かではないが享禄年間(1528年~1532年)安宅河内守によって築かれたと云われる。 安宅氏は橘姓で足利尊氏の命により淡路国沼島の海賊を退治するため、淡路国由良に居城していたという。 天正13年(1585年)羽柴秀吉による紀州攻めで帰参し羽柴秀長に仕えた。 勝山城:安宅勝山城は安宅本城の南に聳える標高212.4mの山頂に築かれている。 主郭は山頂にあり南北二段で土塁が巡る。北が高く南が低い。南の曲輪は西に虎口を開き土塁の内側に石積を残す。東側の土塁には雁木のような石段が見えている。 山頂の主郭から東、西、南の三方に伸びた尾根を堀切で遮断しているが、東の尾根は岩盤を削った圧巻の五重堀切で一番内側の部分は石積を伴っている。また、この堀切に面した曲輪の側面にも石積がある。 南尾根は長く竪堀を伸ばした三重堀切で、主郭の南東下に土塁囲みの小さな腰曲輪が備わっており、この外側に畝状竪堀群がある。 西尾根は主郭南の西虎口から降りると帯曲輪があり、その北端から竪堀、その先に堀切が一条あり遮断しているが、この部分はだいぶ埋まっているようである。 新宮城:元和4年(1618年)浅野忠吉によって築かれた。 関ヶ原合戦後、浅野幸長が和歌山城主となると、家老の浅野忠吉に二万八千石を与え新宮に置いた。この忠吉によって新宮城の築城が始まったが、元和の一国一城令によって一旦は廃城となる。しかし、元和4年(1618年)に築城は再開された。 元和5年(1629年)浅野長晟が安芸国広島に転封となると忠吉は備後国三原へと移った。 浅野氏に代わって徳川家康の十男頼宣が入封するとその付家老として遠江国浜松から水野重仲が三万五千石で入封、この水野氏の時代に完成したという。 16:00終了、帰路に向かう。 今回の旅行、和歌山県のお城巡り、第二弾、御坊から南に点在するお城を巡り楽しみました。 城跡が公園に整備さてていたところが多かった。 |
             |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百十六弾:熊本県お城・城下町巡り観光 2017年12月2日-3日 九州の西に位置し、室町時代に、古くから同地で力を持っていた菊池氏が守護になり、阿蘇氏、名和氏、相良氏などが各地を支配するが、争乱で絶えなかった、やがて大友氏が肥後に進出し、龍造寺氏、島津氏と対立することになった熊本県に足を運び、熊本県に点在する比較的マイナーなお城7か所を訪れました。 2日17:30伊丹空港出発 18:40熊本空港到達、レンタカーで八代方面に向かう。 20:00八代市内のホテル到着後周辺を散策し食事を済ませて就寝。 3日7:00レンタカーで出発、お城巡り。 佐敷城:築城年代は定かではない。現在残る遺構は肥後に入国した加藤清正によって築かれたもので、加藤重次が城代であった。 南北朝時代に築かれた佐敷城は、現在の佐敷城から佐敷川を越えた東側にある佐敷東の城とも考えられているが詳らかではない。 永禄5年(1562年)島津家臣梅北宮内左衛門が佐敷城を攻めたときの城主は佐敷重家であった。天正9年(1581年)島津義久が水俣で相良義陽を敗ると、芦北郡は島津氏に割譲され、島津家臣の宮原景種が地頭として佐敷城主となった。 天正15年(1587年)豊臣秀吉による九州征伐によって島津氏は敗北すると、秀吉の家臣佐々成政、継いで加藤清正と小西行長が肥後に入封し、佐敷は加藤清正に与えられた。 佐敷城を築いた加藤清正は、家臣加藤重次を城代として佐敷城に置いたが、 文禄元年(1592年)の文禄の役に城代の加藤重次が従軍して留守のとき、島津家臣梅北国兼が佐敷城を占拠して挙兵(梅北一揆)した。しかし、一揆は間もなく加藤氏の家臣井上氏・安田氏・坂井氏などによって鎮圧され、梅北国兼は討死した。 慶長5年(1600年)関ヶ原合戦では、加藤清正は東軍、小西行長と島津氏は西軍と分かれた結果、飛領地であった佐敷城は孤立し、島津氏によって攻められた。このとき西軍の敗報が伝わるまでの約30日余り籠城して持ちこたえたという。 元和元年(1615年)一国一城令により廃城となり破却されたが、寛永15年(1638年)島原の乱後に破却不十分として、再び徹底的な破却が行われた。 水俣城:築城年代は定かではないが南北朝時代に水俣氏によって築かれた。 南北朝時代後期には相良氏の支配するところとなったが天正9年(1581年)島津氏が侵攻し落城した。 宇土城:天正17年(1589年)小西行長によって築かれた。 佐々成政が失政により摂津尼崎で自刃すると肥後の南3郡二十四万石で小西行長が入封し、宇土古城の東に新城を築いた。 関ヶ原合戦で西軍に付いた行長は家康に捕らえられ斬首となる。 関ヶ原合戦後熊本の加藤清正によって宇土城は落城、肥後一国に加増された清正は元和2年(1616年)幕命により廃城とする。 宇土古城:永承3年(1048年)に菊池一族によって築かれたと云われるが定かではない。 鎌倉時代末期頃には宇土庄地頭職の宇土道光の居城であった。 文亀4年(1504年)八代の古麓城主であった名和顕忠は相良氏によって追われ、木原城を経て宇土城へと移り、以後、名和氏が代々宇土城主として続いた。 天正15年(1587年)豊臣秀吉による九州征伐で名和顕孝は降伏し所領は安堵された。 その後、肥後に入封した佐々成政に対して勃発した肥後国人一揆では、名和氏は中立の立場であったが、鎮圧後に佐々氏に協力しなかったことを陳謝するため、名和顕孝は弟名和顕輝を城代して上洛した。翌天正16年(1588年)一揆を鎮圧した秀吉の軍勢が、宇土城明け渡しを要求したが、顕輝はこれを拒否して籠城、落城して顕輝は討たれた。 本渡城:築城年代は定かではないが永禄年間(1558年~1569年)に天草鎮種によって築かれたと云われる。 天草氏は筑前国高祖山城を居城とした原田氏の一族とされ、鎮種の時、河内浦城より本渡城を築いて居城を移したという。 豊臣秀吉の九州征伐以後も所領を安堵されたが、南肥後に入部した小西行長の宇土城普請を天草衆は拒否して天正17年(1589年)小西行長と加藤清正によって攻められた。 この戦では本渡城に客将として迎えられていた赤井城主木山弾正が、五百の兵を率いて志岐城へ向かい仏木峠にて加藤清正と戦い、弾正は清正を求めて単騎敵中に乗り込み清正を組み伏せたが、主君あやうしと駆けつけた弾正の家臣に誤って槍にかかり討死したという。 富岡城:慶長10年(1605年)寺沢広高によって築かれた。 天草一帯は宇土城主の小西行長の所領であったが、関ヶ原合戦によって改易となり、肥前国唐津に入部した寺沢広高の所領となった。 広高は慶長8年(1603年)より富岡城の築城を開始し慶長10年(1605年)に完成させた。 寛永14(1637年)島原の乱が勃発、天草でも一揆が蜂起する。富岡城代であった三宅藤兵衛は一揆勢と本戸合戦で戦って敗れ討死する。勢いに乗じた一揆勢は富岡城に攻め寄せ、落城寸前まで攻め込まれたがなんとか持ちこたえ、江戸幕府が派遣した援軍が来るとの知らせによって一揆勢は囲みを解いて島原半島へ渡り原城に籠城した。島原の乱は鎮圧されたが、寺沢氏は天草の所領を失った。 寛永15年(1638年)備中国成羽より山崎家治が入封すると、百間土手を設けて袋池を作るなど城は改修され規模も大きくなったが、寛永18年(1641年)改修が終ると家治は讃岐国丸亀へ転封となった。 寛永18年(1641年)からは天領となり初代代官を鈴木重成が務めた。重成は四万二千石という石高は過大で、それが一揆の一因であったことを痛感、幕府に石高半減の陳情を続けた。重成は承応2年(1653年)江戸で没しているが、一説に幕府への講義のために自刃したとも伝えられる。天草の石高は重成の子重辰の時代に二万一千石へと半減された。 寛文4年(1664年)三河国田原より戸田忠昌が入封すると、忠昌は城の修築費用が領民の負担となるとして寛文10年(1670年)本丸と二の丸を破却して、三の丸に陣屋を築いた。寛文11年(1671年)戸田忠昌は関東へ転封となり、天草は再び天領となると、陣屋がそのまま代官所となって明治まで続いた。 久玉城:築城年代は定かではないが久玉氏によって築かれたと云われる。 久玉氏は天草氏の支族とされ、明応10(1501年)に天草一揆の一人として久玉氏が出てくるのが初見で、この頃には久玉城が築かれていたものと推測されている。 永禄12年(1569年)には河内浦城の天草氏の支城となっていたが、キリスト教の布教に反対する天草氏一族がこれを占拠し、島津薩衆家の島津義虎や肥後の相良氏の支援を受けて天草尚種に対抗した。しかし、天正2年(1574年)頃には落城し天草氏の支城としてキリスト教の司祭館なども築かれた。 慶長6年(1601年)関ヶ原合戦の後に肥前国唐津へ入封した寺沢氏の所領となり、現在の遺構は寺沢氏によって改修されたものと推測されている。 15:00熊本空港に向かう。 17:00熊本空港到達。 19:10熊本空港出発。 20:25伊丹空港到達。 今回の旅行、熊本県に足を運び、八代、水俣、天草に点在する比較的マイナーなお城7か所をおとずれ楽しみました。 今回も立派な城跡が多く、感激、堪能しました。 立派な石垣、城址公園見るべきものがたくさんあり満足でした。 |
  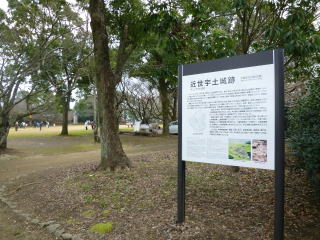           |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百十五弾:岐阜県お城・城下町巡り観光 2017年11月25日-26日 今回は中部地方に位置し、下剋上を体験したかのような斎藤道三、義龍親子が美濃の権力を握ったが、龍興の代になって、織田信長に滅ぼされ、一方、飛騨は織田信長が没した後、豊臣秀吉が金森長近を送り込んで支配した岐阜に足を運び、岐阜県に点在する比較的マイナーなお城11か所を訪れました。 25日18:00車で出発、第二京阪京滋バイパス名神高速道路を経由して岐阜羽島インター下車 20:20岐阜羽島駅前のホテル到着後繫華街を散策し食事を済ませて就寝。 26日7:00出発、お城巡り。 高須城:築城年代は定かではない。暦応元年(1338年)美濃国石津郡に地頭職を賜った氏家重国が館を構え、これを高須城の前身とする説がある。 大永2年(1522年)大橋重一が築き、以降、信重、重長と続く。大橋氏は後に勝幡城の織田信秀に属し、天文年間(1532年~1555年)以降は高津直幸、平野長治、秋山信純など多くの城主が入れ替わった。 関ヶ原合戦後、松ノ木城から徳永寿昌が五万七百石で高須城に入り高須藩となったが、二代徳永昌重は寛永4年(1627年)大坂城改修工事で監督不行届があり、改易され、出羽国鶴岡藩酒井忠勝、さらに出羽国新庄藩戸沢政盛にお預けとなった。同じく嫡男徳永昌勝もお預けの身となっていたが慶安元年(1648年)に赦され、子孫は二千二百石の旗本として速続している。 寛永17年(1640年)下総国関宿から小笠原貞信が二万二千七百石で高須へ移ってきたが、度重なる洪水などに悩まされ、自ら領地替えを幕府に願い出て、元禄4年(1691年)に越前国勝山へ転封となった。 その後は天領となっていたが、元禄13年(1700年)尾張藩主徳川光友の次男で信濃国高井藩主松平義行が高須藩へ転封となり、以降、高須藩三万石として代々続いた。 墨俣城:永録9年(1566年)木下藤吉郎によって築かれた。 稲葉山城攻略のため織田信長は墨俣の地に築城を試みるが、墨俣は当時美濃斎藤領であり稲葉山城と大垣城に挟まれており苦難を強いる。 最初に築城を命ぜられたのは佐久間信盛、続いて柴田勝家が命ぜられるがともに斎藤軍の攻撃により失敗した。 3回目に築城を命ぜられた木下藤吉郎は、建築用材を木曾川上流で加工し河川を利用して運搬し築城に着手する。 始めに柵を造り敵の攻撃に備え、外堀を掘りその土で土台を固め櫓などを組み立てていった。築城完成まで数日であったことから墨俣一夜城とも呼ばれる。 革手城:築城年代は定かではないが正平年間(1346年~1370年)土岐頼康によって築かれたと云われる。 頼康が将軍家の命によって土岐総領家の当主となり、美濃守護となり、続いて尾張守護を兼ね、仁木義長と争って伊勢守護となると永森城から革手城を築いて拠点とした。 加納城:文安2年(1445年)革手城の支城として斎藤利長が築いたのが始まりとされる。この城は天文7年(1538年)頃に一旦廃城となった。 慶長6年(1601年)徳川家康は岐阜城を廃城とし再び加納城の築城を命じ、天下普請によって築かれた。 この時岐阜城の天守や櫓、石垣等を移築転用している。 最初奥平信昌が上野国宮崎から十万石で入城するが寛永9年(1632年)忠隆が没すると嫡子なく断絶する。続いて武蔵国騎西城から大久保忠職が五万石で入封するが寛永16年(1639年)播磨国明石城に七万石で転封となる。 入れ替わりで戸田光重が播磨国明石城から七万石で入封、戸田光煕の時、山城国淀城に転封となり、備中国松山城から安藤信友が六万五千石で入封する。安藤信成の時、陸奥国磐城平城へ転封となり、武蔵国岩槻城より永井直陳が三万二千石で入封、以後永井氏が六代続いて明治に至る。 鷺山城:鷺山城が最初に築かれたのは文治の頃(1185-90)と言われるから源頼朝の奥州攻めの頃のことになる。そして佐竹常陸介秀義がこの城に居住したと伝えられているそうだ。 佐竹氏は新羅三郎義光を祖とし、常陸国内で大きな勢力を築いた源氏である。秀義は義光から五代目、佐竹氏を名乗った昌義からは三代目にあたる。 その佐竹氏がなぜ美濃に城館を構えるに至ったのか。たしかに秀義の子等の子孫が美濃に定着して美濃佐竹氏を称してはいる。その間の経緯でこの城が築かれたのかもしれないが、詳細は分からない。 北方城:築城年代は定かではないが北方太郎左衛門光就によって築かれたと云われる。 西美濃三人衆の一人安藤伊賀守守就は、斎藤義興を見限って織田信長に仕え、姉川合戦などで功を挙げたが、天正8年(1580年)河渡城主であった実子安藤尚就が甲斐の武田氏に内通した嫌疑により、守就父子は武儀郡谷口村に蟄居し、その所領は稲葉一鉄に預けられた。 天正10年(1582年)織田信長が本能寺の変に倒れると、安藤守就は旧臣を集めて北方城に立て籠もり、稲葉一鉄・貞道父子と戦ったが敗れ自刃して果てた。 曽根城:築城年代は定かではないが永禄年間初期に稲葉良通によって築かれたと云われる。 稲葉氏は伊予国河野氏の一族で稲葉通貞の時に美濃にきて、土岐氏に仕えたと云われる。土岐氏が没落すると斎藤氏に仕え、さらに織田信長、豊臣秀吉に仕え天正16年(1588年)郡上八幡に四万石で移封となった。 稲葉氏のあと西尾光教が二万石で入封、関ヶ原合戦では東軍に属して大垣城攻めの功により揖斐城に三万石で転封となり、曽根城は廃城となった。 揖斐城:築城年代は定かではないが南北朝時代に土岐氏の一族によって築かれたと云われ、興国4年(1343年)に土岐頼清の子頼雄が築いて揖斐氏を称したのが始まりとも云われる。 代々揖斐氏の居城として続いていたが天文16年(1547年)揖斐光親が城主のとき斎藤道三によって攻められ落城したという。 その後、斎藤氏の武将堀池氏が城主となったが、天正11年(1583年)稲葉一鉄によって攻められ落城した。 菩提山城:永禄2年(1559年)一説に天文15年の説もあるが、竹中重元によって築かれた。 重元は羽柴秀吉に仕えて播磨国三木城攻略時に病没した竹中重治(半兵衛)の父である。 この地には岩手氏が勢力を張っていたが、竹中重元が岩手氏を攻め滅ぼして菩提山城を築いた。しかし、翌年には重元は病没し子重治が16歳で家督を継いだ。 重治は羽柴秀吉に仕えて播磨国三木城を攻略中に病没する。子重門は幼少であっだか成人した後、菩提山城を廃して麓の館を移し、竹中陣屋を築いた。 竹中氏陣屋:築城年代は定かではないが竹中重門によって築かれた。 重門は羽柴秀吉に仕えて播磨国三木城攻略時に病没した竹中重治(半兵衛)の子で、成人した後、菩提山城を廃して竹中館を築いた。 関ヶ原合戦後も所領を安堵され五千石を領して旗本として明治まで続いた。 西高木家陣屋:築城年代は定かではないが関一政によって築かれた多羅城がその前身である。 関一政は関盛信の二男で蒲生氏郷の与力として各地を転戦していたが、慶長5年(1600年)美濃国多良三万石の城主となり、信濃国飯山より移った。 関ヶ原合戦後、一政は父盛信が領した旧領の伊勢国亀山へ転封となった。 高木氏は源満仲を祖とする清和源氏で大和から伊勢に出て、斎藤道三に仕えて駒野城主となった。その後、織田信長、織田信孝に仕え今尾城主となったが信孝没後に駒野城へ戻った。小牧長久手合戦では織田信雄に従っていたが、天正18年(1590年)織田信雄が改易となると関東へ移った。その後、徳川家康によって貞利(貞久の二男で西高木家祖)、貞友(貞久の三男で東高木家祖)、貞家(貞久の長男貞家の子で北高木家祖)がそれぞれ召し出され関東に所領を与えられた。 江戸時代の高木家はこの多良に三家あり、いずれも大名格の交替寄合の旗本として江戸時代を過ごしたが、三家を区別する為に、陣屋の位置により西高木家、東高木家、北高木家となっている。 高木家は水奉行と呼ばれ、木曽川水系などの治水や巡見などが命ぜられている。宝暦治水と呼ばれる、宝永4年(1754年)から四年の歳月をかけて行われた木曽川流域の治水工事は薩摩藩主体で行われた難工事であったが、この治水にも高木氏は参加している。 慶長6年(1601年)高木権右衛門貞利が千石を与えられ、西高木家の祖となった。西高木家は貞利の後、貞盛のときに二千三百石に加増され、寛文8年(1668年)三代貞勝以降は三家が隔年で参勤交代するようになった。以後代々高木氏が続き、十代貞広のとき明治に至る。 16:00終了帰路に向かう。 今回の旅行、中部地方岐阜県に足を運び、岐阜県に点在する比較的マイナーなお城11か所をおとずれ楽しみました。 今回のお城、立派なお城が多く、資料館となっている模擬天守閣、城跡公園、立派な石垣、見るべきものがたくさんあり、感動しました。 今まで訪れた城跡巡り、ピカ一でした。 |
              |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百十四弾:三重県お城・城下町巡り観光 2017年11月18日-19日 東海地方で南北朝時代に大納言・北畠親房が伊勢国に向かい、南朝の勢力を強めるために奮闘し、南北朝の和議が成り立ったあとは、北畠氏をはじめ、長野氏、関氏のほか、北部の地侍北勢四十八家が戦いを繰り広げた三重県に足を運び、三重県に点在する比較的マイナーなお城7か所を訪れました。 18日16:00車で出発、第二京阪京滋バイパス新名神伊勢自動車道経由して松坂インター下車。 18:30松坂駅前のホテル到着後繫華街を散策し就寝。 19日7:00車で出発、お城巡り 赤木城:赤木城は赤木川の北岸にある標高230mの丘陵に築かれている。現在は国指定史跡となり、以前よりも更に良く整備されており、自然と石垣が織りなす絶景を堪能することができる。 比高30m程の丘陵に築かれた城で総石垣造りで、最高所の主郭を中心に南の谷間にある南郭を挟んで東西両尾根に東郭と西郭、北に北郭を設けている。 主郭はやや歪んだ方形で高石垣が巡り南東隅に枡形虎口を開く。南西隅と北端に張り出しがある。東郭は中央に虎口があり、伝鍛冶屋敷からの入口となる。北尾根は堀切が一条ある。 五ヶ所城:築城年代は定かではないが康永年間(1342年~1345年)頃に愛洲氏によって築かれたと云われる。 愛洲氏の出自については諸説あるが清和源氏武田氏の流れを汲むとされる。 南北朝時代愛洲氏は南朝方として北畠氏に属し、大永7年(1527年)愛洲弾正親忠は家督を国忠に譲って玉丸城へ移り、北朝方と戦った。 天正4年(1576年)田丸城主で北畠氏の養子となった織田信長の子信雄によって攻められ愛洲氏は滅亡したという。 波切城:貞治2年・正平18年(1363年)頃に九鬼隆良によって築かれたと云われる。 九鬼氏は隆良の時に波切の川面氏の養子となり紀伊国九鬼城より移ったという。 隆良には嫡子ができず、和具城主青山氏より養子を迎え隆基と名乗った。隆良より四代の九鬼泰隆の時に田城城へ移って居城としていた。隆良の孫にあたる九鬼嘉隆はこの波切城で生まれたと云いう。 九鬼氏は志摩十三地頭の一人であり、互いに盟約を結んでいたが不可侵条約の無視が次第に目立つようになり、伊勢国司北畠氏の助けを得た志摩七党が波切城に攻め寄せ、嘉隆は海路伊勢の安濃津へ逃れた。滝川一益を介して織田信長に接近した嘉隆は永禄12年(1569年)信長が北畠氏の居城伊勢国大河内城を攻めた時、志摩へ戻って志摩七党を敗って、田城城を取り戻して居城とした。 鳥羽城:中世に橘氏の居館があったとされ、永正年間(1504~1521年)橘忠宗の時に伊勢国司北畠材親に降り志摩国二郡を与えられ取手山砦に居城を移したという。 鳥羽城は文禄3年(1594年)九鬼嘉隆によって築かれた。 嘉隆は波切城主であったが、伊勢国司北畠氏の助けを得た志摩七党に攻められ、海路伊勢の安濃津へ逃れた。ここで滝川一益を介して織田信長に接近し、永禄11年(1568年)織田信長を後ろ盾として志摩の平定に乗り出し、小浜城主小浜久太郎、浦城主浦豊後守を攻め落とすと、鳥羽城主橘宗忠も娘を人質として降伏した。嘉隆はこの娘を妻に迎えている。 その後も和具城・越賀城などを攻略して志摩を平定した。 九鬼嘉隆は織田信長に属して水軍を率いて各地を転戦し、本願寺攻めでは毛利水軍を敗るなど活躍して、信長亡き後は豊臣秀吉に仕え、朝鮮の役にも出兵した。 慶長2年(1597年)嘉隆は家督を守隆に譲り隠居し、慶長5年(1600年)関ヶ原合戦では、守隆は東軍に属して桑名城攻めで戦功を挙げたが、父嘉隆は西軍に属して鳥羽城を占拠し立て籠った。西軍が敗れた後は鳥羽城を脱して和具の洞仙庵に入った。守隆は徳川家康に父嘉隆の助命を嘆願して許されたが、この使者が到着する前に嘉隆は自害して果てた。関ヶ原合戦の功によって加増を受けた守隆は五万五千石を所領となった。 田丸城:建部3年・延元元年(1336年)北畠親房によって築かれたと云われる。 南北朝時代は玉丸城と呼ばれ南朝方の北畠氏の愛州忠行が城主で養子政勝の時に玉丸と名乗った。 天正3年(1575年)北畠信雄は大河内城を廃し田丸城に本拠を移し三層の天守を上げたが、天正8年(1580年)放火により焼失し再建することなく、松ヶ島城を築いて移った。 天正12年(1584年)蒲生氏郷が松ヶ島城に入封すると、氏郷の妹婿となっていた玉丸直昌が再び田丸城主となった。 氏郷が会津若松城に移封となると直昌も三春城主として移った。 その後は稲葉道通が城主となったが元和元年(1615年)摂津国中島に転封となり、田丸城は津城主藤堂高虎の預るところとなったが、御三家の一つ紀伊国和歌山藩が興されるとその所領となり家老久野氏が城主となった。 大河内城:応永22年(1415年)北畠顕雅によって築かれたと云われる。 伊勢国司北畠満雅は弟顕雅をこの地に配して北朝方の攻撃に備えた。 永禄12年(1569年)織田信長が南伊勢に侵攻すると伊勢国司北畠具教がここを本拠として信長軍と対峙した。 具教は籠城の末、信長の次男信雄を養子に向かえ家督を譲ることで和議を結び、三瀬館に隠居した。 信雄は家督を嗣ぐとここを本拠としていたが、天正3年(1575年)田丸城を改修し本拠を移して大河内城は廃城となった。 阿坂城:築城年代は定かではないが応永年間(1394年~1428年)に北畠満雅によって築かれたと云われる。 正長元年(1428年)小倉宮聖承(小倉宮)は皇位継承に不満を抱き、伊勢国司北畠満雅を頼って嵯峨より伊勢に落ちると、北畠満雅は鎌倉公方足利持氏とともに挙兵した。 満雅は阿坂城を築いて足利将軍の軍勢を迎え撃つと、幕府軍は城を包囲して水の手を切った。このとき籠城軍は白米を馬の背に流して水があるように見せかけ、幕府軍を欺いたことから白米城とも呼ばれる。 永禄12年(1569年)織田信長が大河内城の北畠具教を攻めたさいには、重臣大宮入道含忍斎が阿坂城に籠もっていたが、織田の家臣木下藤吉郎らに攻められて落城した。 16:00終了帰路に向かう。 今回の旅行、東海地方の三重県に足を運び、比較的マイナーなお城7か所をおとずれ楽しみました。 今回の城跡、立派な城跡が多く、丘城ほとんどで、石垣がしっかり残っていました。 十分見る価値があります。 |
          |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百十三弾:静岡県お城・城下町巡り観光 2017年11月11日-12日 中部地方の東西に広く太平洋に面し、駿河、遠江の守護職となった今川氏の影響力が、南北朝時代からおおきかったエリア、残る伊豆は北条氏が治め、今川氏真が徳川家康の攻撃を受け困窮すると、駿河、遠江の支配をあきらめて北条氏を頼った静岡県に足を運び、静岡県に点在する比較的マイナーなお城10か所を訪れました。 11日16:00車で出発、第二京阪京滋バイパス、新名神高速道路経由して浜松下車。 19:30浜名湖西部のホテル到着後周辺を散策し食事を済ませて就寝。 12日7:00車で出発、お城巡り。 三岳城:築城年代は定かではないが南北朝時代に井伊道政によって築かれたと云われる。 暦応2年(1339年)井伊道政は後醍醐天皇の皇子宗良親王とともに三岳城に籠もり、南朝方の拠点となっていた。暦応3年(1340年)北朝方の高師泰・仁木義長らによって三岳城は落城し道政と宗良親王は大平城へ逃れて立て籠もったがこれも落城した。 永正11年(1514年)引馬城主大河内貞綱が尾張斯波義達と結んで反今川の兵を挙げたとき、井伊直盛はこれに呼応して三岳城に籠もったが、今川氏の武将朝比奈泰以の猛攻を受けて落城し奥山城へ逃れ後に今川氏に降った。 二俣城:築城年代は定かではないが文亀年間(1501年~1504年)二俣昌長によって築かれたと云われる。 桶狭間合戦で今川義元が敗死すると今川氏の勢力は衰え徳川氏の支城となる。 元亀3年(1572年)武田信玄は遠江に侵攻、武田勝頼を大将として二俣城を囲んだ。 武田氏は猛攻を仕掛けたが城は堅固で籠城兵もよく守っていた。しかし、城内の水之手が天竜川に井楼を組んでくみ上げていることを知った武田勢は、上流から筏を流してこれを破壊した。水之手を断たれた城内は水不足となり開城した。 天正3年(1575年)長篠の合戦で武田氏を敗った徳川家康は、武田氏の家臣依田信守・信蕃父子が守る二俣城攻略に懸かり鳥羽山城に本陣を構えて、その周囲に毘沙門堂砦、蜷原砦、和田ヶ島砦を築いて包囲した。 父信守が病死するなか信蕃が指揮して奮戦し、諏訪原城が攻略されても抵抗を続け、ついに武田勝頼の勧告により、全ての城兵を助けることを条件として開城、信蕃は堂々と城を出て高天神城へ退去した。 家康は家臣の大久保忠世を二俣城主とした。天正7年(1579年)家康の嫡男松平信康は、織田信長から武田氏に通じて謀叛の疑い有りとされ、家康に信康と生母築山殿の処罰を命じた。岡崎城から二俣城に幽閉されていた松平信康は、この地で自刃させられた。 天正18年(1590年)徳川家康の関東移封にともない、大久保忠世も相模国小田原四万石の城主として移り、替わって浜松城主となった堀尾吉晴の弟堀尾宗光が城主となり、関ヶ原合戦後、堀尾氏が出雲国広瀬へ転封となると廃城となった。 高根城:築城年代は定かではないが南北朝時代に奥山定則によって築かれたと云われる。 その後、奥山氏は今川氏に属して水巻城、大洞若子城、小川城を築いて一族で固め勢力を広げたが、桶狭間合戦後に今川氏が没落すると、今川・武田・松平のどこに属するかで一族は内部分裂となった。 元亀年間には遠江国に武田氏が侵攻し、高根城も武田氏の手に落ち、この頃に改修されたといわれるが、武田氏が没落すると廃城となった。 久野城:築城年代は定かではないが、明応年間(1492年~1501年)久野宗隆によって築かれたと云われる。 宗隆の子元宗は元禄3年(1560年)今川義元に従って桶狭間合戦に従軍して討死し、宗能が継いだ。その後徳川氏に属して、天正12年(1590年)徳川家康が関東へ転封となると下総国佐倉に一万三千石で転封となる。 その後、松下之綱が遠江国頭蛇寺城より一万六千石で入封したが、慶長8年子重綱の時に、幕府に無断で石垣を築いた罪によって常陸国小張に転封となる。 替わって久野宗能が万石未満の旗本として旧領へ戻ったが、元和5年(1619年)宗成の時、徳川頼宣の重臣となって和歌山へ移った。 替わって元和5年(1619年)下野国富田より北条氏重が一万石で入封したが、寛永17年(1640年)下総国関宿へ転封となり、廃藩となった。 横須賀城:天正6年(1578年)大須賀康高によって築かれた。 天正2年(1574年)武田勝頼に高天神城を奪われた徳川家康は、高天神城奪還のため、馬伏塚城の大須賀康高に命じて横須賀城を築かせ、康高を城主とした。 天正16年(1588年)康高は嗣子なく没した為、康高の娘を生母とする榊原康政の長男(一説に次男)忠政が大須賀家を継いだ。 天正18年(1590年)徳川家康の関東移封に伴い、忠政は上総国久留里へ転封となった。 代わって渡瀬繁詮が三万石で入封するが、文禄4年(1595年)豊臣秀次事件に連座して改易となると、家臣有馬豊氏が領地を継いだ。 高天神城:築城年代は定かではない。永正10年(1513年)頃に今川氏親の重臣福島正成が城将として高天神城に入城したことが初見とされる。 『高天神を制するものは遠州を制す』と称されるほど重要な城であり、武田氏と今川・徳川氏によって攻防が繰り広げられた。 今川氏没落後、高天神城主小笠原長忠は徳川氏に属していた。元亀2年(1571年)武田信玄は二万越える大軍で高天神城を包囲したが、これを落とすことができず撤退した。天正2年(1574年)信玄の跡を相続した武田勝頼は二万余の軍勢を率いて再び高天神城を包囲、力攻めと降伏勧告を繰り返し、小笠原長忠はついに支えきれず降伏開城した。高天神城を手に入れた勝頼は岡部真幸(元信)、横田甚五郎尹松らを城将として守らせた。 天正3年(1575年)武田勝頼は長篠・設楽原合戦で織田・徳川連合軍に大敗を喫してしまう。好機と見た家康は諏訪原城を攻略し、天正6年(1578年)横須賀城を築いて高天神城への備えとする。高天神城を攻略できない家康は小笠山砦など六つの砦を築いて付城としこれを包囲した。籠城する岡部氏らは武田勝頼に援軍を求めたものの、北条氏と対峙していた勝頼は援軍を送ることができず、天正9年(1581年)にはついに兵糧が尽きた。城将岡部真幸は籠城兵を従えて打って出ると大久保忠教によって討ち取られ、ついに高天神城は落城した。このとき横田甚五郎は秘かに城を脱して甲斐へ戻った。家康は高天神城を焼き払って廃城とし、以後は横須賀城を拠点とした。 諏訪原城:永禄12年(1569年)武田信玄が砦を築いたのが始まりとされるが定かではない。 本郭的な城が築かれたのは天正元年(1573年)武田勝頼によるもので、縄張りは馬場美濃守信房によるものである。 武田勝頼は翌天正2年に高天神城を攻め落とすなど遠江に勢力を伸ばしていくが、天正3年(1576年)に長篠・設楽原合戦で織田・徳川連合軍に大敗を喫してしまう。好機と見た徳川家康は諏訪原城を取り囲んで攻め立て、二ヶ月に及ぶ攻城戦の末、城兵は降伏開城して小山城へ退去した。 諏訪原城を奪った家康は改修して牧野城と改め、今川氏真、松平家忠、松平康親らを在城させ、遠江攻略の拠点とした。 天正10年(1582年)武田氏が滅亡すると諏訪原城の役目も終わり、天正18年(1590年)に徳川家康が関東へ転封となった頃には廃城となったと推測される。 小山城:築城年代は定かではない。 今川氏が没落し、大井川を国境に駿河国を武田氏、遠江国を徳川氏が領することとなったが、武田氏は大井川を越えて遠江国に侵攻し小山城を修築した。 元亀元年(1570年)徳川氏が小山城を落としたものの、元亀2年(1571年)再び武田氏によって奪還された。この時、武田氏は城を改修し大熊長秀を城主として守備させた。 信玄が没し勝頼の代になると高天神城などを落とし遠江国に勢力を伸ばしたが、天正3年(1575年)長篠の合戦で織田・徳川氏に大敗すると高天神城も奪還され小山城も徳川氏の手に落ちた。 丸子城:築城年代は定かではない応永年間に斉藤氏によって築かれたと云われる。 今川氏親の頃になると丸子城は府中館を守る城郭群の一つとして今川氏に接収され、福島安房守を城主とした。 永禄年間(1558年~1570年)に武田信玄が駿河に侵攻すると、山県昌景を丸子城に布陣して西側からの防御にあたらせた。 駿河国を手中に収めると、諸賀兵部大輔、関甚五兵衛、後には屋代勝永を城番として置いた。 久能山城:南北朝時代に南朝方に属した入江駿河守が中野掃部助とともに北朝方の今川氏と戦ったが敗れ、久能山城に退去したことが知られるが、当時は本格的な城郭ではなく、城郭寺院に着眼して代用したものと考えられている。 永禄12年(1569年)頃に武田信玄によって築かれた。永禄11年(1568年)駿河国に侵攻して今川氏真を破った武田信玄は久能山にある久能寺を移設して久能山城を築いた。 武田氏は今福閑斎・今福丹波守を守将として兵350、馬上40騎を与えて守らせた。 天正元年(1573年)今福丹波守は遠江国諏訪原城の城番を命ぜられたが、天正3年(1576年)徳川家康によって攻められ落城すると再び久能山城に籠もった。しかし、天正10年(1582年)2月27日に持舟城が徳川家康によって落城すると、久能山城も徳川軍によって包囲され今福丹波守は開城して甲斐国へ逃れた。 天正11年(1583年)松平源三郎勝俊が城主となったが天正18年(1590年)徳川家康の関東移封に伴い、駿府城主となった中村一氏の家臣松下吉綱が城主となった。慶長6年(1601年)大久保弥一郎忠政が入り、慶長11年(1606年)以降榊原清政・照久父子が在城したが、元和2年4月17日徳川家康が駿府城にて没するとその遺言により久能山城は廃城となり、愛宕曲輪に埋葬され久能山東照宮が造営された。 16:00帰路に向かう。 今回の旅行、静岡県に足を運び、静岡県に点在する比較的マイナーなお城10か所を訪れ楽しみました。 今回は城跡としては立派な建造物が多く、再建天守閣、石垣、なかなかの遺残で、整備され城跡公園と利用されているところが多く見られました。案内板もしっかりありスムーズに訪れることができました。 静岡県のお城、レベルが高い、感心しました。 |
                |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百十二弾:和歌山県お城・城下町巡り観光 2017年11月4日-5日 近畿地方の南に位置し太平洋に接し僧兵集団が力を持ったエリアで、戦国時代に入っても、織田信長、豊臣秀吉に反発し、やがて秀吉の奇襲征伐によって、有力な拠点が相次いで陥落、秀吉は和歌山城を築き、紀州での支配力を強化した和歌山県に足を運び、和歌山県に点在する比較的マイナーなお城11か所を訪れました。 4日16:00車で出発、17:30和歌山市駅前のホテル到着後繫華街を散策し食事を済ませて就寝。 5日7:00車で出発、お城巡り。 手取城:築城年代は定かではないが南北朝時代に玉置大宣によって築かれたと云われる。 玉置氏は大和国十津川地域の出身で、奥州岩城判官の後裔を称す。 南北朝時代に大和国から日高川の上流地域に鶴ヶ城を築き、さらに下流へ降って山崎城の川上兵衛則秋を攻略してこの地域を支配した。 その後は亀山城の湯川氏とともに日高地方を二分する勢力を築いて代々続いた。 天正13年(1585年)羽柴秀吉の紀州侵攻に対し、亀山城主湯川直春は娘婿である手取城主玉置直和に対して同調して秀吉と対決することを望んだが、玉置氏はこれに従わなかった。怒った直春は二百余名で手取城を攻め焼き払った。 亀山城:築城年代は定かではないが湯川氏によって築かれたと云われる。 湯川氏は甲斐源氏の武田三郎忠長が熊野の賊を平らげて芳養庄を賜り、内羽位に館を構え湯川(湯河)氏を称したことに始まる。 亀山城が築かれたのは貞和4年・正平3年(1348年)頃とも永享11年(1439年)頃とも云われ定かではないが、日高に進出した湯川光春によって築かれたと云われる。 その後代々湯川氏の居城であったが、十一代湯川直光は天文18年(1549年)頃に小松原館を築いた。これは単なる居館ではなく平城であったと云われる。移した理由については「亀山城は寒風の季節は住みにくい」というものであった。 天正13年(1585年)羽柴秀吉が紀州へ侵攻すると、湯川直春は娘婿の手取城主玉置直和に対して同調して秀吉と対決することを望んだが、玉置氏はこれに従わなかった。怒った直春は二百余名で手取城を攻め焼き払った。その後、秀吉の大軍に攻められた湯川氏は城を焼き払って退去し後に和睦する。しかし、天正14年(1586年)湯川直春は羽柴秀長の居城である大和郡山城で没した。一説に謀殺されたとも伝えられる。 入山城:築城年代は定かではない。 大永2年(1522年)阿波の三好義長が由良に上陸して小坊子城を築き、畠山氏と戦い勝利した。入山城はこの時に小坊子城の支城として築かれたと考えられる。義長は子息の三好義継を小坊子城に置いて阿波へ引き上げたが、畠山氏と湯川氏が結んで小坊子城を落としており、入山城は湯川氏の支配に置かれたと推測されている。 戦国時代には青木勘兵衛由定の居城となっており、秀吉に属して三好氏との戦いに功があったとも伝えられるが、不明な点も多い。入山城は北の城山と南の本丸という二つの城郭が同じ丘陵に存在していることから、歴史が混同されて伝えられているようである。 鹿ヶ瀬城: 湯浅城:康治2年(1143年)湯浅宗重によって築かれた。 湯浅氏は藤原鎌足の子孫で、平治の乱では熊野まいりから引き返す平清盛に兵30騎を率いて加勢した。 源平合戦では源氏に付き後に鎌倉幕府から阿て(氏に_)河荘・保田荘・田殿荘・石垣荘の地頭職に任ぜられた。 南北朝時代には南朝方となったが、南朝方が不利になるに従い湯浅衆も内部分裂し勢力は衰退した。 鳥屋城:築城年代は定かではないが鎌倉時代末期から南北朝時代初期頃に湯浅宗基によって築かれたと云われる。 湯浅宗基は湯浅氏の祖である湯浅宗重の孫で宗光の子である。石垣氏の祖となったことから石垣城とも呼ばれている。 応永7年(1399年)に紀伊国守護職として畠山基国が入国すると、その弟の畠山満国が城主となり外山城と改められた。その後、鳥屋城と改められ畠山氏の一族や守護代神保氏等が城主を務め、天正13年(1585年)畠山貞政が城主のとき羽柴秀吉に攻略され廃城となった。 大野城:築城年代は定かではない。建武年間(1334年~1338年)に紀伊国守護職に任ぜられた畠山基国がこの大野城に入城していたという。 その後、建武年間(1334年~1338年)には南朝方の浅間入道覚心、その子浅間忠成、保田氏、北朝方の細川氏が続いて大野城に入城した。 細川氏が南朝方の急襲によって敗走すると、紀伊守護職に任ぜられた山名義理が、永徳2年・弘和2年(1382年)に大野城を攻略して大野城主となった。しかし、六分の一殿と呼ばれるまでの勢力を持った山名氏を抑えようと、将軍足利義満が画策し明徳の乱が勃発する。山名義理は紀伊から兵を出さず動かなかったが、乱の平定の後に罰せられ、紀伊国と美作国を取り上げられた。紀伊を召し上げられた後も大野城から出なかった山名義理に対して、将軍は大内義弘を送って攻めせると、義理はこれに対応しようとしたが紀伊の国人衆はこれに従わず、義理は再起を図る為に城を脱して淡路国由良へ脱した。 応永6年(1399年)大内義弘が和泉国境で挙兵した応永の乱の後、紀伊国守護職に任ぜられた畠山基国が再び大野城に入城したが、基国は応永8年(1401年)に広城を築いて移り、大野城は二男の満則に守らせた。 雑賀城:妙見山城とも。天正五年(1577)織田信長の紀伊侵攻に備え、鈴木佐大夫が築いた本拠城といわれる。 佐大夫が妙見山北端に築き、中世城下町を形成。その子である孫一(重秀とも)の時に信長との雑賀合戦が勃発し、石山本願寺の顕如上人を死守しようとした。信長の軍勢は雑賀党の鉄砲に撃ちすくめられてあえなく撤退したとされる。巷説では織田信長10万の軍勢に対して、雑賀衆はわずが3千の兵であったともいう。その時に雑賀党の老若男女が勝利を祝って踊ったのが今でも残る「和歌祭り」の中の「雑賀踊り」であるとされている。 信長の歿後、天正十三年(1585)、豊臣秀吉が6万の大軍で紀伊に侵攻。根来寺・雑賀衆らが太田城に籠もる一方で雑賀城も雑賀孫六を主将として頑強に抵抗する。しかし顕如上人から降服すべき旨の書状が届き、開城に至ったと云われている。 千畳敷とよばれた広大な平地がかつての城跡で、城を中心に城下町が広がっていた。雑賀港の背後の階段状の斜面に家が建ち並ぶ奥和歌浦を見下ろす雑賀崎に本丸があったされる。しかし戦国時代の城址地は明確にはできず、一説にその後の江戸時代に城址へ紀州藩が海の見張りをするための番所を築いたとも云われている。現在、古城の面影は一切ない。 中野城:築城年代は定かではないが室町時代に雑賀党によって築かれたと云われる。 孝子峠越えと大川峠越えの道が交差する付近で、土入川沿いの微高地に位置する。 天正5年(1577年)織田信長の雑賀攻めでは、中野城は和泉国に近く前線となって攻められ落城、弥勒寺山城に本陣を構える雑賀党に対する織田方の陣として中野城は利用された。 太田城:延徳年間(1489年~1492年)第64代国造俊連が築城したとも云われる。 天正4年太田源太夫が築いた太田城は 天正5年織田信長は雑賀を攻めると太田衆はその先導を勤める。翌年雑賀衆は太田城を攻めるが、守りの堅い太田城を攻略できずに和議となった。 天正13年には羽柴秀吉の紀州侵攻軍が、根来寺などを次々と落とし太田城に来襲、三千の先陣が紀ノ川を渡岸しようとした所を弓・鉄砲で迎撃するなど抵抗する。 容易に落ちぬとみた秀吉は備中国高松城攻めでも見せた水攻めによる攻略を実行し、約一ヶ月の籠城戦で落とした 根来城:大治元年(1126年)に覚鑁上人(かくばん)が石手荘を寄進され、大治5年(1130年)に高野山に伝法院を建てたことに始まる。 戦国時代には根来衆と呼ばれる僧兵集団を持ち、雑賀衆(さいか)とともに石山本願寺の要請を受け、たびたび織田軍と戦った。 天正13年(1585年)羽柴秀吉により焼き打ちにあい、根来寺は壊滅的な打撃を受けたが、徳川家康の時代になると紀伊国徳川氏の庇護のもと復興された。 16:00終了、帰路に向かう。 今回の旅行、近畿圏の南に位置する和歌山県に足を運び、和歌山県に点在する比較的マイナーなお城11か所をおとずれ楽しみました。 なかなか地味な城跡が多く、案内板も不十分、見つけるのが一苦労、特に山城は大変苦労しました。 最後に訪れた根来字、霊場巡りで訪れたことがありましたが城跡であったこと驚きました。 次回は御坊から南、新宮までのエリアに点在する城跡を訪れたいと思います。 |
   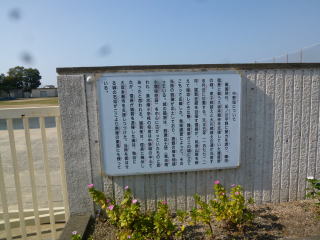 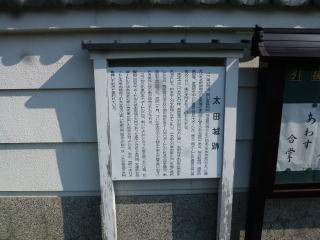   |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百十一弾:新潟県お城・城下町巡り観光 2017年10月14日-15日 甲信越地方の日本海に東西細長く位置し南北朝の内乱では、南朝の軍勢が力を持っていたが、足利尊氏は上杉憲顕を越後守護に投入し、南朝方を破った、やがて上杉謙信の登場で越後は統一され、関東や川中島など、各地へ勢力を広げようとする新潟県に足を運び、新潟県に点在する比較的マイナーなお城9か所を訪れました。 14日17:30伊丹空港出発。 18:30新潟空港到達、レンタカーで三条市内に向かう。 17:40三条駅前のホテル到着後繫華街を散策し食事を済ませて就寝。 15日6:30レンタカーで出発、お城巡り。 根知城:根知城(上城山城)は、姫川と根知川が合流する地点の南東に聳える、標高525.2mの城山山頂に築かれている。 山頂の主郭は東西二段で標柱が建っている。西に続く尾根には数条の堀切が設けられ、いずれも竪堀として南へ伸びている。東へ降りていくと、鞍部に空堀が設けられ、西側に土塁が付いている。空堀は南側が東へ曲がっている。空堀の東側はやや平坦な面が続いているが曲輪としては不明瞭で、その先は北東へ尾根が延びているが自然地形になっている。 勝山城:築城年代は定かではない。一説に天正10年(1582年)に上杉景勝による築城とも云われる。 城将は須賀盛能、秋山伊賀守定綱、荻田主馬などが務めた。また天正13年(1585年)羽柴秀吉と上杉景勝がこの城で会見したとも伝えられる。 上杉城:築城年代は定かではないが弘治年間(1555年~1558年)に上杉謙信によって築かれたと云われる。 天文21年(1552年)関東管領上杉憲政は上野国平井城から上杉謙信を頼って越後に逃れた。この憲政の住まいとして築造されたのが御館である。 天正6年(1578年)上杉謙信が急死すると上杉景勝と上杉三郎景虎との間で越後の諸将を二分した家督相続争いが起こる。これが「御館の乱」である。いち早く春日山城の本丸を占拠した景勝に対して、三郎景虎は春日山城を脱しこの御館に籠もって防戦する。天正7年には景勝軍の御館への猛攻撃が開始されると三郎景虎は支えきれず、和睦の使者として関東管領上杉憲政と三郎景虎の長男道満丸は景勝の元へ訪れようとしたが景勝軍に囲まれ討ち果たされた。三郎景虎は出自の小田原北条氏を頼って落ちる途中、鮫ヶ尾城に立ち寄ったが城主堀江宗親はすでに景勝方に内応しており、三郎景虎はここで自刃して果てた。しかし、御館の乱はこれで終結せず、本庄秀綱などは最後まで抵抗し天正8年(1580年)になってようやく終結した。 鮫ケ尾城:築城年代は定かではない。 鮫ヶ尾城の名が史料に現れるのは天正7年(1579年)の上杉景勝書状で、堀江宗親が城主であった。上杉謙信の急死によって跡目相続争いが起こり、謙信の養子であった上杉景勝と上杉三郎景虎によって越後を二分する争いとなり『御館の乱』と呼ばれた。 天正7年(1579年)三郎景虎は上杉景勝の攻撃によって御館を逃れ、生家の小田原北条氏を頼って落ち延びようとした。ようやく味方であった堀江宗親の鮫ヶ尾城に到着したが、このとき既に堀江宗親は景勝方へ靡いており、景虎は城内で自刃して果てた。 直峰城:南北朝時代に南朝方の風間信濃守信照によって築かれたのが始まりとも云われるが定かではない。 直峰城は上杉氏の番城で、吉田英忠、竹俣清綱、長尾伊賀守などが番将を勤めた。 天正6年(1578年)御館の乱が勃発した時には三郎景虎方の吉益伯耆守が守っていたが、上杉景勝に攻められ落城した。 その後は樋口惣右衛門が在城したが、慶長3年(1598年)上杉景勝が会津に転封となると、代わって福島城に入封した堀秀治の一族堀光親が城主となった。しかし、慶長15年(1610年)堀忠俊の時に改易となり直峰城も廃城となった。 箕冠城:築城年代は定かではない。城主は大熊氏で長尾為景の時代には大熊備前守政秀が段銭方などの要職を務め、上杉謙信の時代には大熊備前守朝秀が父同様に重用された。しかし、弘治2年(1556年)朝秀は上杉氏に叛いて武田氏に内通して挙兵、敗れた朝秀は越中へ逃れ、後に武田信玄に仕え、山県昌景の与力となって信濃国根古屋城主となった。 大熊氏が越後から去った後も春日山城の支城として存続したが、後に廃城となった。 荒戸城:天正6年(1578年)上杉景勝によって築かれた。 上杉謙信没後、景勝と景虎の間に「御館の乱」という相続争いが起こった。 景虎の父は北条氏康であるから、景勝は関東からの援軍を阻止する目的で三国街道を見下ろす要所に築城した。 天正6年(1578年)北条氏によって落城したものの、翌天正7年(1579年)景勝によって奪還された。 樺沢城:築城年代は定かではない。 はじめ坂戸城長尾氏の番城であったが、上杉謙信の越後平定により春日山城の番城となり、関東進出の宿城となった。 謙信没後「御館の乱」が勃発し上杉景勝と上杉景虎が相続を争うようになると、小田原北条氏が荒戸城と樺沢城を攻略した。 しかし北条氏は厳冬期を前に一部の将兵を残し、関東へ帰陣する。 翌年初旬に景勝方により攻められ落城した。 坂戸城:築城年代は定かではない。 室町時代に長尾宗景が上杉憲顕より上田荘を与えられ入部した。 上田長尾氏は長房、政景、景勝と続き、景勝は上杉謙信の養子となり春日山城に移ったので、栗原、登坂、深沢など景勝に近い武将が在城した。 謙信没後「御館の乱」が勃発し上杉景勝と上杉景虎が相続を争うようになると、小田原北条氏が荒戸城と樺沢城を攻略したが、その侵攻を坂戸城で食い止めた。 上杉氏が会津へ移封となると、堀秀政が福島城に入封となり、坂戸城には家臣堀直寄が三万石で入城した。 堀氏が改易となると、直寄は信濃国飯山へ移封となり、廃城となった。 16:00終了、新潟空港に向かう。 17:00新潟空港到達。 19:05新潟空港出発 20:05伊丹空港到達。 今回の旅行、甲信越地方の日本海に東西細長く位置する新潟県に足を運び、新潟県に点在する比較的マイナーなお城9か所をお城を訪れ楽しみましたました。 今回は比較的地味ですが案内板がしっかりあり迷うことなく訪れることができました。次回は新潟の東方面の訪れたいと思います。 |
         |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百十弾:島根県お城・城下町巡り観光 2017年9月30日-10月1日 中国地方の日本海に東西細長く位置し、室町時代に京極氏が守護になると、同族の尼子氏を守護代に据え、守護代を継いだ尼子経久は戦国大名になるべく野心を見せ、京極氏にいったん役目を解かれたが、やがて力を盛り返し出雲を手中に収めた島根県に足を運び、島根県に点在する比較的マイナーなお城9か所を訪れました。 9月30日17:10伊丹空港出発。 17:55出雲空港到達、レンタカーで出雲市内に向かう。 18:40西出雲駅前のホテル到着後繫華街を散策し食事を済ませて就寝。 10月7:30レンタカーで出発、お城巡り。 七尾城:築城年代は定かではないが鎌倉時代に益田兼高もしくは益田兼時によって築かれたと云われる。 益田氏は一般的に藤原氏の後裔とされるが、歌人柿本人麻呂の後裔とする系図も庶流の周布氏系図として残っている。初代は御神本兼高こと益田兼高で、元暦元年(1184年)源頼朝の呼びかけに応じて一の谷の合戦に参加し、翌年の壇の浦の合戦でも戦功を挙げた。この功によって鹿足郡を除く石見国五郡を与えられ、那賀郡上府から益田に移った。 兼高が益田に居住した所は諸説あるが、上久々茂土居、大谷土居そして三宅御土居へと益田川の上流から次第に下流へと移っていったと考えられている。そしてその詰城として築かれたのがこの七尾城で、慶長5年(1600年)関ヶ原合戦で敗れ防長二カ国に減封となった毛利氏に従い、長門国須佐へ移るまでの累代の居城であった。 益田氏城館:応永3年(1370年)頃に益田兼見によって築かれたと云う。 大谷土居屋敷が火災により全焼したことによって三宅の地に新たに土居が築かれた。七尾城を詰城とした平治の居館である。 浜田城:元和6年(1620年)古田重治によって築かれた。 元和5年(1619年)吉田重治が大坂の役の功によって五万四百石余を領し、伊勢国松坂より浜田へ加増転封となり元和6年(1620年)浜田城を築いて浜田藩となった。 慶安元年(1648年)浜田藩主二代古田重恒が嗣子なく没して古田氏は改易となり、播磨国山崎より(松井)松平康映が入封する。 (松井)松平氏は康映から康宦・康員・康豊・康福と五代続き、宝暦9年(1759年)松平康福のとき下総国古河へ転封となり、代わって下総国古河より本多忠敞が入封した。 本多氏は忠敞から忠盈・忠粛と三代続き、明和6年(1769年)本多忠粛のとき三河国岡崎へ転封となった。代わって三河国岡崎より(松井)松平康福が入封するが、この康福は 宝暦9年(1759年)に下総国古河へ転封となり三河国岡崎を経て再び浜田へ戻ってきている。 第二期(松井)松平氏は康福から康定・康任・康爵と四代続き、天保7年(1836年)松田康爵のとき、陸奥国棚倉へ転封となった。代わって上野国館林より(越智)松平武厚が六万一千石で入封した。 (越智)松平氏は武厚から武揚・武成・武聰と四代続いたが、慶応2年(1866年)第二次長州征伐のさい、浜田口を守備していた長州藩の大村益次郎に敗れ、浜田城を自ら焼き払って出雲国松江に逃れた。その後、武聰は飛領地であった美作国鶴田に陣屋を構えて鶴田藩として明治を迎えている。 二ツ山城:築城年代は定かではないが貞応2年(1223年)富永朝助(出羽朝祐)によって築かれたと云われる。記録に残る築城年代としては石見国では益田氏の七尾城に次ぐ古さである。 出羽氏(イズハ(ワと発音))は伴姓で祖富永祐純は近江国三上荘の荘官であったが治承4年(1180年)源頼朝の挙兵に呼応して木山義経に味方し平家に反旗を翻した。これによって石見国邑智郡久永荘に流罪となった。文治元年(1185年)壇ノ浦合戦で平家は滅亡し、佐々木定綱が石見国守護に補任されたこともあって荘園別当和田氏とともに瑞穂・石見町の支配することとなった。 南北朝時代には出羽氏は北朝方として各地を転戦した。康安元年・正平16年(1361年)阿須那の藤掛城主高橋師光・貞光父子は足利直冬の要請によって南朝方となり、北朝方の出羽氏を攻めた。高橋氏はもともと備中国高梁を領し、北朝方として高師直に従っていたが、高師直の失脚によって阿須那に転封となっていた。高橋氏の出羽侵攻は半年余り続き、出羽実祐は次第におされ二ツ山城に押し込められると高橋氏は火を放って山を焼き尽くしたという。実祐は火中で自刃して果てたが、嫡子祐忠は地頭所城に籠って佐波氏からの攻撃を退けた。 二ツ山城を落とした高橋氏は本城を築いて居城とし、その後、安芸国・備後国にも勢力を拡げている。出羽氏は横領された出羽郷の旧領回復を執拗に嘆願していたが、明徳3年(1392年)大内義弘によって南北朝の統一がなされ、高橋氏は出羽郷七百貫のうち二百五十貫の領地を出羽氏に返還することで和議が調い、出羽氏は出羽郷の宇山城に居城した。 戦国時代になると台頭してきた安芸国の毛利元就に接近し、享禄3年(1530年)高橋氏が毛利元就によって滅ぼされると出羽郷の旧領を回復した。この時、本城は破却されたが、宇山城から二ツ山城に居城を移したかどうかは定かではない。 出羽元祐(元実)は嗣子として毛利元就の六男鶴法師丸を迎え、元服して出羽元倶と名乗ったが、元亀2年(1571年)僅か十七歳で早世した。家督は元祐の実子元勝が継いだ。この元勝は天正17年(1589年)従五位下出雲守に叙任され豊臣姓を賜わっている。天正19年(1591年)出羽氏は出雲国頓原の由岐に転封となった。 慶長5年(1600年)毛利氏が関ヶ原合戦で防長二ヶ国に減封となると、出羽氏もそれに従って移り、御手廻組と大組(元勝の子元智を祖とする)の二家存続した。 福光城:築城年代は定かではない。はじめ福光氏の居城であったと云われる。 永禄2年(1559年)石見に侵攻して温湯城の小笠原長雄を降した毛利元就は、吉川経安に福光氏の所領を与えた。これを機に吉川経安は福光城を改修して殿村城から居城を移した。 永禄4年(1561年)本明城の福屋隆兼が毛利元就に叛いて挙兵し、福光城の吉川氏を攻めたが、これを撃退している。 天正9年(1581年)織田信長の家臣羽柴秀吉が因幡国鳥取城を攻めたとき、信長に降ろうとした城主の山名豊国を家臣の森下道誉と中村春続が追放した。森下と中村は吉川元春に支援を要請、これに応じて吉川経安の子、吉川経家が鳥取城へと派遣された。鳥取城に籠城した経家は兵糧がなくなるまで織田軍に抵抗し、最後は城兵の解放を条件として自身が切腹し開城した。 その後は経家の子経実が城主となったが、毛利氏が関ヶ原合戦に敗れ、防長二カ国に減封となると、経実は吉川広家の家老として周防国岩国へ移り廃城となった。 鵜の丸城:元亀2年(1571年)毛利元就によって築かれた。 山陰側の毛利水軍の拠点として築かれたもので、都野氏に在番を命じている。 山吹城:延慶2年(1309年)大内弘幸によって築かれたと云われる。 銀山争奪のため、大内・尼子・毛利氏によって激しく争奪戦が行われたが最終的には毛利氏の所有となっり、江戸時代には天領となって廃城となった。 高瀬城:築城年代は定かではない。 南北朝時代に建部伊賀が築いたとの伝承もあるが、今残る形状は戦国時代に米原氏によって築かれたものと思われる。尼子十旗の一つ。 米原氏は近江国坂田郡米原郷の発祥で、佐々木六角氏の支流といわれ、出雲国守護代となった尼子氏の被官として下向したものであるが、その年代については定かではない。 永禄5年(1562年)米原綱寛のとき毛利氏に降り、毛利氏に従って豊後大友氏との戦いに従軍していたが、永禄12年(1569年)尼子勝久が再興をはかり出雲に入国すると帰国し尼子方へ復帰した。 しかし毛利氏によって尼子再興軍も次第に勢力を削がれ、高瀬城と 真山城を残すのみとなったが、元亀2年(1571年)3月高瀬城は落城し、綱寛は真山城へと逃れその真山城も同年8月落城した。 この後は吉川元春が入城し尼子再興軍一掃の拠点となったが、尼子氏が滅亡すると廃城となった。 三刀屋城:築城年代は定かではないが三刀屋氏によって築かれた。尼子十旗の一つ。 三刀屋氏は清和源氏満快流で承久3年(1221年)諏訪部扶長が出雲国三刀屋郷の地頭職を得て、16代為扶の時に三刀屋氏を名乗った。 この時居城として築かれたのがじゃ山城(石丸城)であり、その支城として築かれたのが現在の三刀屋城(城山)で、戦国時代にじゃ山城(石丸城)から三刀屋城(城山)に本拠を移したといわれる。 天文11年(1542年)周防大内氏が出雲の国人衆を率いて出雲に侵攻すると、三刀屋氏もこれに降り、尼子氏の居城月山富田城へと侵攻する。 しかし出雲国人衆は尼子氏に再び寝返り大内氏は嫡子義房を水死させる大敗を喫した。 永禄5年(1562年)毛利氏が出雲に侵攻するとこれに降り、以後毛利氏に属して各地で転戦したが、天正16年(1588年)に上洛したさい徳川家康と面会したため毛利輝元から疑われ領地を没収される。 16:00終了、出雲空港に向かう。 16:30出雲空港到達。 18:25出雲空港出発 19:15伊丹空港到達。 今回の旅行、中国地方の日本海に面してに位置する島根県に足を運び、島根県に点在する比較的マイナーなお城9か所を訪れ楽しみました。 比較的案内板がしっかりしていてスムーズに訪れることができました。 今回は出雲より西に点在するお城を訪れました。次回は東方面を訪れたいと思います。 |
                |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百七弾:石川県お城・城下町巡り観光 2017年9月2-3日 室町時代に畠山基国が能登守護を任じられ、守護代には遊佐浩氏が就い、やがて応仁の乱を終えた畠山義統が下国し、戦国大名となり、一方、加賀では富樫氏が守護を務めていたが、一向一揆に悩まされた石川県に足を運び比較的マイナーなお城9か所を訪れました。 2日18:12大阪駅サンダーバードで出発 20:56金沢駅到達。駅前のホテル到着後繫華街を散策し食事を済ませて就寝。 3日8:00レンタカーで出発、お城巡り。 穴水城:築城年代は定かではないが南北朝時代に長氏によって築かれたのが始まりとされる。 当初は砦程度の規模であったものが、戦国時代に長氏十九代長続連の時に城として整備されたとされる。 天正4年(1576年)上杉謙信が能登に侵攻して七尾城に攻め入ると長氏は七尾城に籠城し、留守であった穴水城は上杉氏によって攻略され上杉家臣長沢筑前・白小田善兵衛が守将として置かれた。 天正6年(1578年)長沢筑前が主力を率いて珠洲郡正院の一揆鎮圧へ出向いた隙に、長連龍が穴水城を攻略して一時は奪還したものの、越後勢が大挙して押し寄せた為、城を脱して越中の神保氏を頼って落ちた。連龍は後に鹿島郡半郡の所領を織田信長より得て、能登に入部した前田利家に従った。 小丸山城:天正10年(1582年)前田利家によって築かれた。 天正9年(1581年)越前国府中より能登に入国した前田利家は羽咋郡菅原(菅原城か)に入り、その後能登一国を領して七尾城に入った。利家は山城である七尾城より港に近い所口村へ居城を移す為に築城に着手した。これが小丸山城である。しかし本能寺の変により織田信長が没すると天正11年(1583年)には加賀国で石川郡と河北郡を加増され、利家は加賀国尾上城(後の金沢城)へと移り、小丸山城には兄の前田安勝を置いた。その後、一国一城令により廃城となった。 石動山城:天正4年(1578年)上杉謙信によって築かれたと云われる。 天正4年(1578年)七尾城を攻めた際に、石動山城を築き直江大和守景綱を守将として置いたという。 石動山ははやくより山岳宗教の拠点として栄えており、天平寺の石動山衆徒が砦を構えていたと推測される。天正10年(1582年)には織田信長が本能寺の変で倒れた混乱をついて、能登畠山氏の旧臣が蜂起して石動山に籠ったが、これを前田利家や佐々盛政などの織田軍が攻め込んで焼き打ちにし全山焼失した。 その後、前田氏の寄進により復興をとげたが、明治の神仏分離政策で全ての院坊が破却され廃寺となった。 末森城:築城年代は定かではないが畠山氏によって築かれたと云われる。 天文19年(1550年)の城主は畠山義続の家臣土肥但馬であった。 天正5年(1577年)上杉謙信は七尾城を落とした後、末森城に侵攻してこれを落とし七尾城に援軍として来援した織田方と手取川で戦った。 前田利家が能登に入封となると、家臣奥村永福が城番となり、土肥但馬の一族が附属した。天正12年(1584年)越中国の佐々成政は能登を急襲して末森城を囲み、坪井山砦に本陣を構えて攻めかけた。土肥伊予などは吉田口で討死し、三の丸・二の丸も落ち、本丸を残すのみとなったが、奥村永福は頑強に防戦した。末森城の急襲を知った前田利家は、松任城の前田利勝に出陣を命じ、単身出撃して津幡城に入り、松任の軍勢と合流した。利家は末森城を包囲している佐々軍の背後に回り込んで攻撃したので、佐々軍は壊滅し、利家は末森城に入城して成政に備えた。成政は坪井山砦の本陣で体制を整えたが、利家が末森城に入って防備を整えた事を知ると攻撃を断念して越中に引き上げた。 津幡城:寿永2年(1183年)木曽義仲の軍を迎え撃つ為に平家軍によって築かれた砦がはじまりと云われる。その後、正平6年(1351年)富樫氏春が籠って桃井直常と戦った。 天正11年(1583年)前田秀継が築城し居城とした。翌天正12年(1584年)末森城合戦の時、ここで前田利家と秀継は末森城救済の軍議を開いた。翌天正13年(1585年)前田秀継は越中国今石動城の守将となり、後に越中国木舟城へ移ったが、地震により没した。 朝日山城:朝日山城は加賀朝日町と北千石町の間にあり東西に伸びた丘陵に築かれている。 「日本城郭大系」には開墾された曲輪の写真が掲載されているが、現在は南麓の部分は畑となっているものの、大半は薮に覆われている。 朝日山城は東西に三郭連ね一段下がった腰曲輪で繋ぐ縄張りで、東端部に堀切が残っている。 松根城:築城年代は定かではない。 応安2年・正平24年(1369年)越中の桃井直和が陣を構えていた所、能登の吉見左馬助がこれを攻略したという。 長享2年(1488年)には越智伯耆が布陣していた。 文明年間(1469年~1487年)には加賀一向一揆尾山坊の首領州崎兵庫(慶覚)の家臣青天小五郎(青山小五郎)が籠もっていた。 天正12年(1584年)前田利家と敵対した佐々成政が家臣杉山隆重を置いて、境目の城としていた。 鷹巣城:築城年代は定かではない。天正4年(1576年)には平野神右衛門が居城としていたが、翌天正5年(1577年)に越後の上杉謙信のもとへ走ったと伝えられる。 天正8年(1580年)佐久間盛政が金沢城へ入ると、その家臣柘植善左衛門、敦賀八矢、松本我摩久順次などが城番となった。また、一説に柴田勝家の家臣拝郷家嘉が在城したともいう。 天正13年(1585年)富山城主佐々成政が前田利家方の鷹巣城を攻めたが、前田利家はこれを撃退したという。 高尾城:築城年代は定かではないが長享2年(1488年)以前に富樫氏によって築かれたと云われる。 富樫政親は加賀国守護であったが、次第に強力になる一向一揆に危機感を募らせ、将軍足利義尚に支援を要請して一向一揆に対抗しようとした。一向一揆方は政親の家老山川三河守を介して和睦を伝えたが、政親はこれを固持し高尾城を修築して備えた。 一揆方は越前・越中からの政親方の援軍に対する備えを行い、富樫泰高を大将として大乗寺に本陣を据えて高尾城を大軍で包囲した。政親は城内より討って出て一揆勢と戦ったが打開することはできず、頼みの援軍も加賀国境で一揆軍に退けられ政親は城内で自刃して果てたという。一説に高尾城から脱出して鞍ヶ嶽城に入ったが、そこで敗れて討死したとも伝えられる。 16:30終了、金沢駅に向かう。 17:00金沢駅到達。 17:54金沢駅サンダーバードで出発 20:38大阪駅到達。 今回の旅行、北陸地方の石川県に足を運び、石川県に点在する比較的マイナーなお城9か所を訪れ楽しみました。 石川県は観光名所が多く、比較的マイナーなお城の案内板は少なく、特に山城は見つけるのに一苦労でした。 今回は金沢市から北のエリアに点在するお城を訪れました。 次回は金沢市から南のエリアに点在するお城を巡りたいと思います。 |
               |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百四弾:青森県お城・城下町巡り観光 2017年7月29-30日 奈良時代から平安時代に、地域の長が多くの館を築いたエリア、やがて、平泉・欧州藤原氏の支配力が及ぶが、源頼朝に討たれると、南部氏が定着し、戦国時代には南部氏が津軽統一を成し遂げた青森に足を運び青森に点在する比較的マイナーなお城10か所を訪れました。 29日16:15伊丹空港出発。 17:45青森空港到達、レンタカーで青森市内に向かう。 18:20青森市内のホテル到着後繫華街を散策し食事を済ませて就寝。 30日7:00レンタカーで出発、お城巡り。 七戸城:築城年代は定かではない。 建武元年(1334年)北畠顕家の国宜にみえる工藤右近将監がいたと考えられているが定かではない。 建武2年(1335年)南部師行の弟南部政長は新田義貞の鎌倉攻めに馳せ参じて功を挙げ、七戸は政長に与えられた。以後、七戸南部氏の代々の居城となった。 康正2年(1456年)蠣崎蔵人の乱、文明15年(1483年)三戸南部の御家騒動で落城したという。 天正19年(1591年)九戸城主九戸政実が宗家三戸南部信直に謀叛を起こした九戸の乱で、七戸南部家国は政実に味方した。南部信直は豊臣秀吉に援軍を要請し、秀吉が派遣した奥州仕置軍によって乱は平定され、七戸南部氏は滅亡し翌年には廃城となった。 七戸の重要性から浅水城主南直勝が七戸氏の名跡を継ぎ、慶長2年(1597年)にはその子直時が七戸二千石の城主となった。直時が没し、正保4年(1647年)南部利直の五男重信が七戸氏を継いだが、寛文4年(1664年)には南部宗家を継ぐこととなった為、南部直轄地となり、七戸代官所が設けられた。 芦名沢館: 八戸城:寛文4年(1664年)南部直房によって築かれた。寛文4年(1664年)盛岡藩南部重直が嗣子なく没した。通常嗣子なく没すると改易となる時代であったが、四代将軍徳川家綱の命によって新たに七戸重信(重直の弟)に盛岡八万石、中里直房(重直の庶子)に八戸二万石を与えられ、それぞれ立藩した。 初代南部直房は在任わずか数年の寛文8年(1668年)に没した。この死は盛岡藩南部氏による暗殺とも云われている。 天保9年(1838年)八代藩主南部信真のときに城主格に昇進した。九代藩主は薩摩藩の島津重濠から養子に迎えた信順が継ぎ明治に至る。 三戸城:築城年代は定ではないが永禄年間(1558年~1570年)頃に南部晴政によって築かれたと云われる。 三戸南部氏は甲斐国巨摩郡南部郷出身で、文治5年(1189年)奥州平泉の藤原氏討伐の戦功によって源頼朝より糠部の地を賜り、本三戸城を居城とした。 天文8年(1539年)24代南部晴政のとき、家臣の赤沼備中による放火で聖寿寺館は焼失する。これにより晴政は三戸城を新たに築いて居城を移し、聖寿寺館は本三戸城と呼ばれるようになった。 天正18年(1590年)26代南部信直は豊臣秀吉による小田原征伐に参陣した功によって、南部七郡(糠部・岩手・紫波・稗貫・和賀・閉伊・鹿角)の領有が認められ近世大名となった。 天正19年(1591年)かねて南部信直とは家督争いなどで不和であった九戸城主九戸政実が反乱を起こした。南部家中随一の精鋭と云われる九戸氏の反乱は南部氏内部では収めることができず、信直は豊臣秀吉に援軍を要請する。秀吉は豊臣秀次を総大将、軍監に浅野長政として奥州再仕置の軍勢を派遣し、九戸政実の乱を鎮圧した。 南部信直は蒲生氏郷が改修した九戸城を受け取ると、福岡城と命名して居城を移した。しかし、居城が所領の北に偏っていたため、新たに盛岡城を築きはじめ、寛永10年(1633年)利直の時代に完成し、以後南部氏は盛岡城を居城として明治まで続いた。 三戸南部氏の居城が福岡城から盛岡城へと移った後も三戸城は城代が置かれ維持されていた。貞享年間(1684年~1688年)頃までは城代が置かれていたが、その後は代官が支配している。 堀越城:建武3年・延元元年(1336年)曾我太郎貞光によって築かれたと云われる。 元亀2年(1571年)大浦城主大浦(津軽)為信は大仏ヶ鼻城主石川高信と和徳城主小山内讃岐を攻略、その後も津軽地方に勢力を伸ばし南部氏から独立した。 文禄3年(1594年)豊臣秀吉から四万五千石の所領を安堵されると大浦城から堀越城に居城を移し、慶長12年(1609年)二代藩主津軽信枚が弘前城を築いて移るまでの本城であった。 大光寺城:建武3年・延元元年(1336年)曾我太郎貞光によって築かれたと云われる。 元亀2年(1571年)大浦城主大浦(津軽)為信は大仏ヶ鼻城主石川高信と和徳城主小山内讃岐を攻略、その後も津軽地方に勢力を伸ばし南部氏から独立した。 文禄3年(1594年)豊臣秀吉から四万五千石の所領を安堵されると大浦城から堀越城に居城を移し、慶長12年(1609年)二代藩主津軽信枚が弘前城を築いて移るまでの本城であった。 黒石陣屋:建武3年・延元元年(1336年)曾我太郎貞光によって築かれたと云われる。 元亀2年(1571年)大浦城主大浦(津軽)為信は大仏ヶ鼻城主石川高信と和徳城主小山内讃岐を攻略、その後も津軽地方に勢力を伸ばし南部氏から独立した。 文禄3年(1594年)豊臣秀吉から四万五千石の所領を安堵されると大浦城から堀越城に居城を移し、慶長12年(1609年)二代藩主津軽信枚が弘前城を築いて移るまでの本城であった。 大浦城:文亀2年(1502年)南部光信(大浦)によって築かれた。 延徳3年(1491年)光信は安東氏の津軽回復を阻止するため本家三戸南部氏の命によって入部し、種里城を居城とした。 元亀2年(1571年)大浦(津軽)為信は大仏ヶ鼻城主南部高信と和徳城主小山内讃岐を攻略、その後も津軽地方に勢力を伸ばした。 文禄3年(1594年)豊臣秀吉から四万五千石の所領を安堵されると大浦城から堀越城に居城を移し、後に弘前城を築き津軽藩祖となった。 湯口茶臼館:青森県弘前市(旧中津軽郡相馬村)にあった中世の山城(やまじろ)。南北朝時代に、覚応院という寺院の南西にある独立峰の山頂にあった先住民の築いた館跡を利用して築かれ、南朝方の溝口左膳が居城としていた。現在、山上の曲輪(くるわ)のあったところは神社の境内になっているが、その西斜面には、4段の腰曲輪が築かれていた名残がある。◇蝦夷館とも呼ばれる。 浪岡城:築城年代は定かではない。南朝方として活躍した北畠顕家の末裔と云われる北畠氏が浪岡の地に移ったのは文中・応永年間(1372年~1428年)頃で北畠顕邦のときと考えられている。浪岡城が築かれたのはこの顕邦の子顕義の時代と考えられている。 北畠氏は浪岡氏を称して代々続いたが、永禄5年(1562年)川原御所を再興した北畠具信が浪岡具運を殺害するという内紛が起こり衰退、天正6年(1578年)浪岡顕村のとき、大浦(津軽)為信によって浪岡城が攻撃され顕村は捕らえられ、顕村は西根の寺で自害した。一説に舅の安東愛季を頼って檜山城近くの茶臼館に逃れたとも云われる。 浪岡氏の後は津軽氏の持城となったが後に廃城となった。 16:00終了、青森空港に向かう。 18:20青森空港出発。 19:55伊丹空港到達。 今回の旅行、本州の北端に位置する青森県に足を運び青森県に点在する比較的マイナーなお城10か所を訪れ楽しみました。 関西より気温が低く、涼みながら快適なドライブお城巡り満喫しました。 |
                 |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百三弾:福島県お城・城下町巡り観光 2017年7月8-9日 東北地方の相馬地方の相馬氏、会津地方の蘆名氏、県北の伊達氏などが力を誇り、さらに安積郡の伊東氏、岩瀬郡の二階堂氏と多数の勢力が覇権を争い、のちに伊達政宗がほぼ手中にした福島県に足を運び比較的マイナーなお城7か所を訪れました。 8日15:45伊丹空港出発 16:50福島空港到達、レンタカーで出発、須賀川方面に向かう。 17:30須賀川駅前のホテル到着後繫華街を散策し食事を済ませて就寝。 9日7:00レンタカーで出発、お城巡り。 猪苗代城:築城年代は定かではないが佐原経連によって築かれたと云う。 佐原氏は三浦氏の一族で黒川城の蘆名氏とは同族であり後に猪苗代氏を称した。佐原経連が最初に築いたのが八手山城と云われ、その後この猪苗代城を築いたという。 天正16年(1588年)鶴峯城に隠居した猪苗代盛国は当主盛胤が蘆名義広に伺候している隙を付いて猪苗代城を乗っ取り伊達氏に内通した。これを機に天正17年(1589年)伊達氏が猪苗代城に入城し、麿上原で蘆名義広を破り会津を手中に治めた。 しかし、伊達氏は小田原合戦後の奥州仕置によって会津を召し上げられ、会津は蒲生氏郷の治める所となり猪苗代氏は伊達氏に従いこの地を去った。 その後、猪苗代城は一国一城令の例外として会津若松の支城として存続し、各大名の城代が置かれ明治を迎える。 神指城:慶長5年(1600年)上杉景勝によって築かれた。 慶長3年(1598年)上杉景勝は越後国春日より会津に転封となり黒川城へと入ったが、ここは小田山に近く大砲による砲撃に弱い為、新城を築く事にしたと云う。この予見は正しく戊辰戦争では黒川城へ小田山より砲撃が行われた。 当初候補地として北田城が挙げられたが水害の危険性から神指城が築かれたという。 築城は直江兼続が担当し3月18日より本丸、5月10日より二の丸の工事が昼夜兼行で行われたが、完成を見る事無く工事は中断された。これは徳川家康による上杉討伐の機運が高まり、それに対する備えとして国境の城の整備を進める為とされる。 結局、徳川家康による上杉討伐軍は石田三成の挙兵により中止され、上方へ戻った徳川軍と石田軍によって関ヶ原の合戦がおこり、戦後上杉氏は米沢に転封となったため、景勝は神指城には一度も入城しないまま米沢へ移った。 向羽黒山城:永禄4年(1561年)葦名盛氏によって築かれた。 盛氏が隠居城として築いたもので、家督を盛興に譲った後、盛氏は一旦向羽黒山城へと移った。しかし、天正2年(1574年)盛興が26歳の若さで嗣子なく没すると、盛氏は盛興の正室(伊達氏)を自分の養女として、二階堂盛隆を養子に向かえて家督を継がせた。盛氏は後見人として黒川城へ再び移ることとなり廃城となったとされる。 しかしながら、現在の遺構は隠居城というには遙かに壮大で、また虎口などは非常に技巧的かつ規模が大きく、連続して存在するなど、蘆名氏の後に会津を領した、伊達、蒲生、上杉の各領主によって改修されたものと思われる。 鴨山城:築城年代は定かではないが南北朝時代に長沼氏によって築かれたと云われる築城年代は定かではないが南北朝時代に長沼氏によって築かれたと云われる。 長沼氏は下野国小山氏の一族で下野国芳賀郡長沼発祥、文治5年(1189年)源頼朝の奥州攻めのに参加して戦功を揚げ南会津に所領を得たものとされる。当初は長沼城を居城としていたが、応永年間(1394年~1428年)頃に鴫山城を本拠として移ったと見られている。 長禄3年(1459年)山中越中は白河結城勢を密かに導き、長沼氏を鴫山城より追だしたが、長沼氏は葦名氏の力を借りて鴫山城を取り戻したという。 天正17年(1589年)葦名氏が伊達政宗によって滅ぼされると伊達氏に帰属し、先陣として伊達氏に服属しない山内氏や河原田氏を攻めた。天正18年(1590年)豊臣秀吉による奥州仕置き伊達氏が会津から取り除かれると、長沼氏は伊達氏に従って退去した。 その後は会津に入封した蒲生氏郷の家臣小倉作左衛門、ついで上杉氏の家臣大国実頼が城代となり、この頃に大門付近の改修が行われた。再び蒲生氏が会津に入封した時には蒲生主計・蒲生内記が在城したが、寛政4年(1627年)加藤嘉明が会津に入封した後、元和の一国一城令により廃城となった。 久川城:天正17年(1589年)河原田盛次によって築かれたと云われる。 河原田氏は藤原北家秀郷流の下野国小山氏の庶流で下野国都賀郡河原田郷発祥とされる。 河原田盛光が源頼朝に従って奥州合戦で戦功を挙げ、その恩賞として伊南を与えられたのが会津河原田氏の始まりとされる。河原田氏は西館・東館を平治の居館として築き、南背後の駒寄城を詰城として築いたとされる。 天正17年(1589年)葦名義広は摺上原で伊達政宗と戦ったが敗れ、生家である佐竹氏を頼って常陸へ落ちた。政宗は居城を黒川城へと移して所領拡大を計るなか、河原田氏は伊達氏に対抗するために久川城を築いたと云われる。 伊達氏は新たに帰属した鴫山城主長沼氏などを先陣に久川城に攻め寄せたが、攻め落とすことはできず、天正19年(1591年)伊達氏は惣無事令に反したとして会津領は召し上げられ、奥州仕置きによって蒲生氏郷に与えられた。久川城を守りきった河原田氏ではあったが、奥州仕置きにより所領は没収となり、葦名義広を頼って常陸から出羽国角館へ移るもの、帰農して土着したものなど離散した。現在も出羽国角館の武家屋敷群の中に河原田家の武家屋敷があり、この子孫のものである。 会津に蒲生氏が入封すると蒲生郷可、上杉氏の時代には清野助次郎長範、再び蒲生領となると蒲生彦太夫が入城し、慶長15年(1610年)頃に廃城となった。 棚倉城:寛永2年(1625年)丹羽長重によって築かれた。 慶長8年(1603年)立花宗茂が棚倉一万石を領して大名に復帰し、居城としたのは赤館といわれ、宗茂は後に三万五千石に加増され、元和6年(1620年)宗茂は旧領の筑後国柳河へ転封となった。かわって元和8年(1622年)に入封したのが丹羽長重で、常陸国古渡より五万石で入封するとはじめ赤館を居城としていたが、棚倉城を築いて居城を移し赤館は廃城となった。 赤館城:築城年代は定かではない。 建武年間(1324年~1336年)には伊賀国より下った伊賀隆定の二男定澄が赤館城主となり、赤館氏を名乗り、以後代々赤館氏の居城となった。 永禄3年(1560年)寺山館まで勢力を北上させた佐竹氏に対抗するため、白河結城氏は葦名氏に支援を求め、葦名氏によって赤館が改修され、赤館氏は沢井へ領地替えし、上遠野盛秀を城代とした。 天正3年(1575年)佐竹氏は赤館を攻略し南郷を制圧し、赤館・寺山館・羽黒館・東館をもって南郷衆を組織した。 関ヶ原合戦後に佐竹氏が出羽国秋田へ転封となると一時天領となったが、慶長8年(1603年)立花宗茂が棚倉一万石を領して大名に復帰し、そのとき居城したのがこの赤館といわれる。宗茂は後に三万五千石に加増され、元和6年(1620年)宗茂は旧領の筑後国柳河へ転封となった。元和8年(1622年)丹羽長重が常陸国古渡より五万石で入封すると、新たに棚倉城を築いて居城を移し廃城となった。 16:30終了、帰路に向かう。 17:30福島空港到達。 18:10福島空港出発。 19:20伊丹空港到達。 今回の旅行、福島県に点在する比較的マイナーなお城7か所をおとずれ楽しみました。 城跡は現在公園として利用されているところが多く、気持ちよく散策することができました。 道も広く、車も少なく、信号も少なく、ストレスなく気持ちよくドライブお城巡り満喫しました。 |
     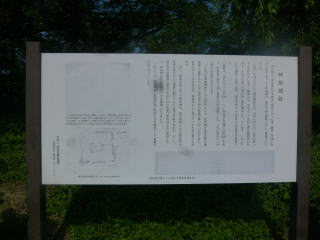                 |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百二弾:岩手県お城・城下町巡り観光 2017年7月1-2日 東北地方の世界遺産で有名な奥州藤原氏の支配した平泉があり、その他にも源氏の流れを汲む名門武家、南部氏の遺構が数多く残され、また陸奥土着のさまざまな武家の居城が点在している岩手県に足を運び比較的マイナーなお城9か所を訪れました。 1日17:05伊丹空港出発 18:25花巻空港到達、レンタカーで北上方面に向かう。 19:20北上駅付近のホテル到着後繫華街を散策し食事を済ませて就寝。 2日7:30レンタカーで出発、お城巡り。 九戸城:築城年代は定かではない。白鳥城との別名から安倍頼時の子則任が築城したとの伝承があるが、これを裏付ける史料はない。 九戸氏による築城としては、明応年間(1492年~1501年)九戸光政によって築かれたとする説や永禄年間(1558年~1570年)頃に九戸政実によって築かれたとする説などがある。 天正19年(1591年)九戸政実は三戸城主南部信直に対して挙兵する(九戸政実の乱)。政実の反乱は天正8年(1580年)南部晴政・晴継と南部家当主が相次いで没し、その家督を巡って田子信直(後の南部信直)と九戸政実の弟実親が争ったことや、信直が小田原城攻めに参陣して南部宗家の安泰を計るとともに、九戸氏らを家臣として組み込もうとしたことに対する反発などがその発端と考えられている。 九戸氏の反乱に荷担した櫛引城主櫛引清長は三戸方の苫米地館を攻めたがこれを落とせず九戸城に入った。また、久慈城主久慈直治・政則父子も九戸城に入り籠城した。 三戸城主南部信直は九戸氏の反乱を家中でおさめることができず、豊臣秀吉に援軍を求めた。秀吉は豊臣秀次を大将、浅野長政を軍監として奥州再仕置軍を派遣した。奥州再仕置軍が九戸方の姉帯城、根曽利城を攻め落とすと九戸方は全ての支城を捨てて九戸城に立て籠もった。仕置軍が九戸城の堀際まで攻め寄せて城を包囲すると、長興寺の和尚に説得された九戸政実は降伏開城した。 九戸氏が滅亡すると蒲生氏郷によって九戸城は近世城郭として改修され、南部信直に渡された。信直は九戸城を福岡城と改名して三戸城より移り居城とした。このとき松の丸を居所としたと伝えられる。しかし、居城が所領の北に偏っていたため、新たに盛岡城を築きはじめ、寛永10年(1633年)利直の時代に完成し、福岡城は廃城となった。 一戸城:築城年代は定かではないが建長年間(1249年~1256年)頃に一戸摂津守義実によっで築かれたと云われる。 一戸南部氏は南部光行の長子行朝を祖とする。妾腹のために本家を相続できず野田城を築いて一戸氏を名乗ったという。この行朝の子義実が一戸城を築き移ったと云われる。一戸南部氏の動向は詳らかではないが、周辺には分家を輩出しており、それなりの勢力を持っていたようである。南部晴政の死によって起こった家督相続争いは、三戸南部氏を二分する騒動となり、結局重臣北信愛の推す南部信直が家督を相続することとなったが、これに反発していた九戸政実は密に一戸城主一戸兵部大輔政連を誘って南部信直を亡き者にしようと画策するが政連に拒まれた。天正9年(1581年)九戸政実は政連の弟一戸信濃と謀って政連を暗殺し、政連の子出羽も後に討たれ一戸家は断絶となり、一戸城には政実の腹心一戸図書が入った。 これを知った南部信直はただちに一戸城を襲撃してこれを落とし、北信愛の二男北主馬介秀愛を城主とした。天正19年(1591年)九戸の乱で九戸政実は一戸城に夜襲をかけたが、北秀愛はいち早く南部信直に九戸の反乱を伝えた。乱の後は石井信助が城代となったが文禄元年(1592年)豊臣秀吉の命により廃城となった。 姉帯城:築城年代は定かではない。 城主は九戸南部氏一族の姉帯氏という。天正19年(1591年)九戸の乱で姉帯大学は弟の姉帯五郎兼信とともに姉帯城に籠もり、豊臣秀吉の軍勢と戦ったが大半が討死して落城したという。 浄法寺城:築城年代は定かではないが浄法寺氏によって築かれたと云われる。 浄法寺氏は鎌倉御家人畠山重忠の末裔を称し、重忠の三男重慶を祖とする。 浄法寺氏は十四代浄法寺重恒のときに南部守行の麾下となり、二十五代浄法寺重房のときに三戸南部氏の家臣となったと云われる。 天正19年(1591年)九戸城主九戸政実が反乱を起こしたとき、浄法寺修理は南部信直に従い、豊臣秀吉による奥州仕置き軍として浅野長政の先鋒として九戸城攻撃に布陣している。 浄法寺修理は五千石を領して南部家の重臣であったが、慶長5年(1600年)南部利直の岩崎城攻めで、これに従っていた浄法寺修理は不手際を犯して家名断絶となった。 昼沢城:工藤氏の末裔とされる葛巻氏の築城といわれるが詳細はわかっていない。三重空堀など防御遺構が独特である。 安部館:築城年代は定かではない。安倍館は古来厨川柵と見られ、前九年の役で安倍貞任ら安倍一族が籠城して源頼義・清原武則の連合軍に敗れた場所と考えられていた。しかし、近年の発掘調査によって嫗戸柵(うばと)であった可能性も指摘されているという。鎌倉時代には岩手郡一帯を所領とした工藤行光の居城であった。工藤氏は後に栗谷川氏(厨川氏)を名乗り、天正年間(1573年~1592年)頃、栗谷川仁右衛門は南部氏に属していた。 雫石城:南北朝時代に戸沢氏によって築かれた。 戸沢氏は南北朝時代に南朝方に属しており、暦応3年・興国元年(1340年)頃には雫石城が南朝方の拠点として築かれ北畠顕信が在城して南朝方を指揮した。 天文年間に入ると南部家への服従を拒否したため石川高信を大将とする南部勢によって攻撃され落城した。 座主城: 高水寺城:建武2年(1335年)斯波家長によって築かれたと云われるが定かではない。 斯波氏は足利泰氏の長男家氏が斯波郡に下向し斯波氏と改名したことに始まる。 戦国時代には南部氏と戦うようになり、天文6年(1537年)には岩手郡を攻略したが、天正年間(1573年~1592年)頃には南部氏に押され、南部の支族九戸政実の弟弥五郎が入り婿となって高田吉兵衛康実と名乗り高水寺城の出丸として吉兵衛館に住んだ。しかし、天正14年(1586年)高田康実が出奔して南部氏のもとに走ると再び南部と争うようになり、天正16年(1588年)には家臣の岩清水館主岩清水義教らが南部氏に内通するなどし斯波詮直は高水寺城を捨てて大崎氏の元に逃亡、高水寺斯波氏は滅亡した。 その後、南部信直は中野康実(高田康実改め)に高水寺城を与え、郡山城と改称して城主とした。郡山城は南部氏が盛岡城を築城する過程で一時南部氏の居城として利用されたが、寛文7年(1667年)廃城となり資材は盛岡城に転用されたという。 17:20終了、花巻空港に向かう。 18:00花巻空港到達。 18:55花巻空港出発。 20:25伊丹空港到達。 今回の旅行、東北地方の岩手県に足を運び岩手県に点在する比較的マイナーなお城9か所を訪れ楽しみました。 今回のお城巡り、案内板も少なく、見つけるのに一苦労、跡地が公園である地は比較的まし、こ辺の畑周辺が跡地のところも多くがっかりしたお城巡りでした。 |
         |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百一弾:長野県お城・城下町巡り観光 2017年6月17-18日 木曾義仲が拳兵した平安末期から、南北朝時代の混乱を経て、武田氏が勢力を拡大した戦国時代まで、幾度も戦いが繰り広げられた信濃、とくに戦国時代は築城技術が発展し、貴重な史跡を現在に伝えている長野県に足を運び、県内に点在する比較的マイナーなお城8か所を訪れました。 17日18:40新大阪新幹線のぞみで出発 19:31名古屋駅到達 19:40名古屋駅特急しなので出発 21:48松本駅到達、駅前のホテル到着後?華街を散策し食事を済ませて就寝。 18日8:00レンタカーで出発、お城巡り。 大島城:築城年代は定かではないが大島氏によって築かれたと云われる。 大島氏は船山城主片切為行の八男、八郎宗綱が大島郷を分知され大島氏を称したのが始まりとされる。 元亀2年(1571年)武田信玄は飯田城代であった秋山信友に命じて大島城を普請させ、高遠城とともに伊那の拠点とした。 天正10年(1582年)織田信忠率いる織田軍が飯田城を落とし大島城に迫ったが、城兵は戦わず城に火を放って逃亡し落城する。 飯田城:築城年代は定かではないが鎌倉時代に坂西氏によって築かれたと云われる。 坂西氏の出自については詳らかではないが、飯田城を築いて愛宕城から居城を移したと云われる。 戦国時代には武田信玄によって攻略されたが、天正10年(1582年)織田軍の侵攻により落城した。 織田氏の領地となった後は毛利秀頼が入封したが、本能寺の変の後は徳川氏の領地となり、菅沼定利が城主となった。 天正18年(1590年)徳川家康が関東へ転封となると、菅沼氏は上野国吉井へ移り、毛利秀頼が再度入封する。文禄2年(1593年)文禄の役で秀頼が病没すると京極高知が入部した。 松尾城:築城年代は定かではないが室町時代頃に小笠原氏によって築かれたと云われる。 小笠原氏は室町時代に府中、松尾そして鈴岡の小笠原三家に分かれ、信濃守護および小笠原惣領職の座を争った。隣接する鈴岡小笠原氏とは当初良好な関係であったが、やがて伊賀良荘の領有を巡って対立することとなった。明応2年(1493年)正月小笠原貞基は、鈴岡城主小笠原政秀・長貞父子を松尾城にて謀殺し鈴岡小笠原氏を滅亡させた。 小笠原貞基は政秀の養子であった府中の小笠原長朝と幾度となく戦ったが敗れて甲斐へ逃れた。その後、松尾城に戻ってきたが、天文3年(1534年)に貞基の子貞忠は小笠原長棟に攻められ再び甲斐へ逃れた。 天文23年(1554年)武田氏が伊那へ侵攻した際には、定基の子小笠原信貴が先鋒として伊那に攻め入り小笠原長時の弟小笠原信定の籠もる鈴岡城を攻め落とし、松尾城主に復帰した。 天正10年(1582年)織田信長が信濃に侵攻すると、信貴の子小笠原信嶺は織田氏に降伏し、その後の高遠攻めなどで道案内をした。信長が本能寺の変で倒れると信濃に侵攻した徳川家康に降り旧領を安堵された。天正18年(1590年)徳川家康が関東に移封となると小笠原氏もそれに従い武蔵国本庄へ移り廃城となった。 鈴岡城:築城年代は定かではないが、室町時代初期に小笠原貞宗の子宗政によって築かれたとも云われる。 小笠原氏は室町時代に府中、松尾そして鈴岡の小笠原三家に分かれ、信濃守護および小笠原惣領職の座を争った。文安3年(1446年)惣領の小笠原宗康は弟の光康とともに小笠原持長と漆田原で戦って討死した。その子政秀は鈴岡城を拠点として伊賀良荘を領して勢力を維持し、松尾小笠原氏とは良好な関係にあったが、やがて伊賀良荘の領有を巡って松尾小笠原氏と対立することとなった。政秀は文明12年(1480年)諏訪氏と結んで松尾の小笠原家長を討ったが、明応2年(1493年)正月に家長の子貞基によって松尾城で子の長貞とともに暗殺され、鈴岡小笠原氏は滅亡した。 政秀の養子であった府中の小笠原長朝は、松尾城の小笠原貞基と幾度となく戦って甲斐へ追いやった。その後、松尾城に戻ってきていた貞基であったが、天文3年(1534年)に小笠原長棟に攻められ再び甲斐へ逃れた。その後、長棟の子小笠原信定が鈴岡城主となった。 信定は武田信玄が信濃に侵攻し、府中の小笠原長時が敗れた後も抵抗したが、天文23年(1554年)武田氏が伊那に侵攻すると敗れて京へ逃れた。 妻籠城:築城時期、築城者は定かではありません。文永年間(1264~75年)に沼田右馬介あるいは木曽讃岐守家村が築いたとも伝えられます。室町中期には美濃遠山氏の所領であったとされ、その後の戦国期(1500年頃)からは木曽氏が支配しました。天正十二年(1584年)の小牧・長久手の戦いでは木曽義昌が秀吉方に付き、妻籠城には山村甚平衛良勝を入れましが、徳川方の菅沼大善定利、保科越前守正直、諏訪安芸守頼忠らが攻め寄せたが、良勝はこの城を死守しました。関が原の戦いの時には修復されましたが、元和二年(1616年)に廃城となりました。 高島城:文録元年(1592年)日根野高吉によって築かれた。 天正18年(1590年)豊臣秀吉による小田原征伐の功により日根野高吉が入封する。 高吉ははじめ諏訪古城に入ったが、文録元年(1592年)に諏訪湖に浮かぶ小島に築城を開始する。 慶長7年(1602年)吉明の時下野国壬生に転封となり、代わって諏訪頼水が上野国総社より二万七千石で入封、諏訪氏は10代続いて明治に至る。 桑原城:築城年代は定かではないが桑原氏によって築かれたと云われる。 天文11年(1542年)武田信玄が諏訪へ侵攻し、上原城の諏訪頼重を攻めると、頼重は上原城を焼き払って桑原城へと退いたが、これを退けることはできず降伏し甲斐へ連行された。 上原城:築城年代は定かではないが諏訪氏によって築かれた。 天文11年(1542年)武田信玄が侵攻すると、諏訪頼重は上原城を焼き払って桑原城へ退き降伏した。信玄は上原城に板垣信方を置いて代官としたが、天文17年(1548年)上田原合戦で討死した。 17:00終了松本駅に向かう。 18:15松本駅到達。 19:07松本駅特急しなので出発 21:21名古屋駅到達 21:30名古屋駅新幹線のぞみで出発 22:20新大阪駅到達。 今回の旅行、信州長野県に足を運び、県内に点在する比較的マイナーなお城8か所をおとずれ楽しみました。 今回もマイナーなお城であるが比較的、城址公園として整備さているところが多く満足できました。 次回松本から長野方面のお城を攻めたいと思います。 |
           |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第三百九十九弾:富山県お城・城下町巡り観光 2017年6月3-4日 雄大に聳える立山連峰と国内最深の富山湾、越中守護の畠山氏の家督争いをきっかけに、各地で群雄が基盤を築くようになり、その後、上杉謙信が越中を平定し、能登国も支配するが、織田信長の勢力に敗れ、江戸時代は富山藩として前田氏が治めた富山県に足を運び、富山県に点在する比較的マイナーなお城、7か所を訪れました。 3日大阪駅18:12サンダーバードで出発 20:56金沢駅到達 21:06金沢駅新幹線つるぎで出発 21:29富山駅到達、駅前のホテル到着後?華街を散策し食事を済ませて就寝。 4日7:30レンタカーで出発、お城巡り 宮崎城:築城年代は定かではないが寿永年間(1182年~1185年)に宮崎太郎長康によって築かれたと云われる。 寿永元年(1181年)源義仲は都落ちした北陸宮の御所を八幡山(城山)に築き奉じたといわれ、このとき在地豪族の宮崎太郎・南保二郎・入善小太郎などの名が見られる。 宮崎城の名が史料に現れるのは南北朝時代で、越後守護上杉憲顕の家臣長尾景忠が南朝方の籠もる宮崎要害で勝利を得たとあるのが唯一という。 越後との国境にある宮崎城はその後も重要視され、椎名氏の家臣や越後の上杉氏の家臣などが在城した。戦国時代末期になると越中へ侵攻した織田軍は松倉城や魚津城を落とし、越中に入国した佐々成政の家臣が在城した。成政の後は前田氏の家臣高畠織部が在城したが、後に廃城となった。 魚津城:築城年代は定かではないが、室町時代に守護畠山氏の守護職椎名氏により築かれたと云われる。 椎名氏は松倉城を居城としいるが、北陸道の押えとして築いたものと思われる。 椎名氏は上杉氏が越中に侵攻するとそれに降ったが、後に武田信玄と結び上杉氏に背いた。 これに対して上杉氏は越中に侵攻し、魚津城を落とし河田長親を置いた。 天正10年(1582年)柴田勝家を大将とした織田軍が侵攻し取り囲んだ、これに対して上杉氏は天神山城に後詰めとして着陣したが、これを救う事はできず中条景泰をはじめことごとく討ち取られた。 この後、本能寺の変の急報を聞いた織田軍は撤退、すぐさま上杉氏が奪還に成功し須田満親を守将として置いた。 天正11年(1583年)佐々成政が侵攻、満親は開城して退去した。 松倉城:築城年代は定かではないが南北朝時代に井上俊清によって築かれたと云われる。戦国時代には守護畠山氏の守護代椎名氏の居城であった。 椎名氏は上杉氏が越中に侵攻するとそれに降ったが、後に武田信玄と結び上杉氏に背いた。 永禄12年(1569年)上杉謙信によって攻められ落城、椎名康胤は逃亡した。 上杉氏は後に金山城にいた河田長親を移し拠点として重要視するが、天正10年織田氏に攻められ落城した。 弓庄城:築城年代は定かではないが土肥氏によって築かれたと云われる。 土肥氏は相模国土肥郷を本貫とする土肥実平を祖とするといわれ、南北朝時代頃に越中に入部し土着したという。弓庄系の土肥氏がいつ頃弓庄城を居城としたのかは定かではない。戦国時代にははじめ上杉謙信に属し、謙信没後は織田信長の勢力下に収まったが本能寺の変の後、再び上杉氏方となり、天正10年と天正11年の二度にわたって佐々成政の攻撃を受けたが落城しなかった。しかし越後の上杉景勝からの来援もなく孤立したため開城し、土肥氏は越後に去ったという。 猿倉城:飛騨の塩谷秋貞が元亀年間~天正初期に越中攻略のひとつの拠点として築城されたようです。塩谷氏は当初上杉方で謙信死後は織田方となりますが、天正十一年(1583年)に城生城を攻略中に上杉景勝の軍に攻められ討死し塩谷氏は断絶しているようです。 安田城:築城年代は定かではないが天正13年(1585年)頃に築かれたとみられている。天正13年(1585年)羽柴秀吉による佐々成政征伐で、秀吉が白鳥城に本陣を布いた際に、白鳥城にいた前田氏の家臣岡島一吉が安田城に移っており、築城もこの頃と見られている。岡島一吉が金沢へ退いた後は代官平野三郎左衛門が居城し、後に廃城となった。 白鳥城:築城年代は定かではない。古くは寿永2年(1183年)源義仲の部将今井兼平が御服山に陣を張るなど要害として活用されていた。 天正6年(1578年)には神保八郎左衛門が居城としていたとも云われるが定かではない。神保氏は越中国中央部に勢力を持った国人で、天文12年(1578年)頃に神通川を越えて富山城を築き、新川郡を支配していた椎名氏と対立していた。 永禄3年(1560年)頃から越後の上杉謙信は圧迫された椎名氏を援助して神保氏を攻め、永禄5年(1562年)神保長職は呉増山に立て籠もってこれに抵抗したが敗れて城を去った。 天正13年(1585年)羽柴秀吉の佐々成政征伐では、秀吉の本陣が白鳥城に置かれ、白鳥城に籠もっていた前田氏の部将岡島一吉は南麓の安田城に出城を築いて移った。 この頃に現在に残る縄張に改修されたと見られている。 佐々成政が降伏すると成政は新川一郡に減封となり、砺波・婦負・射水三郡が前田利家に加増された。利家は越中三郡を支配するため守山城に前田利長、木舟城に前田秀継、増山城に山崎長鏡、白鳥城に岡島一吉、城生城に青山佐渡を置き、佐々成政に備えた。天正15年(1587年)佐々成政は肥後に転封となると、慶長2年(1597年)には前田利長が守山城から富山城に移り、岡島一吉は白鳥城から安田城へ移ったという。 17:00終了、富山駅に向かう。 17:30富山駅到達 18:11富山駅新幹線つるぎで出発 18:33金沢駅到達 18:42金沢駅サンダーバードで出発 21:23大阪駅到達 今回の旅行、北陸地方の富山県に足を運び比較的マイナーなお城7か所を訪れ楽しみました。 今まで多くのマイナーなお城を訪れましたが、地味な城跡が多かったですが、今回の城跡、遺残が見るべきものが多く、感動いたしました。城跡も今回のような立派な遺残が あれば訪れた価値があります。 |
             |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第三百九十六弾:島根県中国三十三所観音巡礼観光 2017年4月1-20日 中国地方の島根県に足を運び山陽路から山陰路へとつづく中国三十三所観音霊場、島根県に点在する7か所を訪れました。 1日17:10伊丹空港出発 17:55出雲空港到達、レンタカーで出雲市内に向かう。 18:30西出雲駅前のホテル到着後周囲を散策し食事を済ませて就寝。 2日7:00レンタカーで出発、霊場巡り。 鰐淵寺:浮浪滝を中心とした修験信仰、持統天皇6年(692)に当たる壬辰年在銘の重文・青銅観音菩薩像が示すような観音信仰、ならびに智春上人の滝の行験に期待する薬師信仰の三つから生じた寺で、奈良時代に開創されましたが、平安に入り伝教大師が比叡山に天台宗を開かれますと、第三代天台座主慈覚大師が山陰に足跡を印された折、天台の教義の下に第一番にはせ参じ、天台宗最初の末寺となりました。 後、出雲大社や比叡山横川(よかわ)三昧院、無動寺との関係を深め、鎌倉時代には、武家との関係を密にし、出雲大社との習合を確立・推進し、別当寺を務めました。又、この頃、南院と北院との存在も伝わります。 頼源(らいげん)は後醍醐天皇に尽くし、栄芸は毛利元就との親交を深め、本堂再建を輝元の代に完成させました。又、有名な弁慶も当寺で修行し、いまも『弁慶まつり』『弁慶ウォ―ク』として残り、八百屋お七もねむっております。この他、寺との関係のある名僧・武将は数多くその名を残しております。 一畑薬師:出雲神話の国引きで名高い島根半島の中心部、標高三百メートルの一畑山上にあります。「目のお薬師様」として古くから全国的な信仰の広がりをもち、千三百段余りの石段(参道)も有名です。現在は車で簡単に上がれます。山上からの眺めは絶景で、宍道湖を眼下に、東に大山、西に三瓶山を始めとする中国山地の山々を一望できます。静かで眺めの良い宿泊施設(コテージ)もあります。 お寺の宗派は禅宗(臨済宗)、一畑薬師教団の総本山です。本尊の薬師如来は、平安時代894年に日本海から引き上げられ、眼病、諸病平癒、子供の無事成長はじめ、諸願に霊験あらたかとして篤く信仰されています。全国におよそ50の分霊所、年間数十万人余りの参拝があります。観音堂は、本堂の右側の大きなお堂です。瑠璃観世音菩薩をおまつりし、中国観音霊場の他出雲観音霊場の特別札所となっています。日々のご祈念、例月祭、坐禅会、団体研修、茶会、奉納音楽祭など年間を通じてさまざまな行事があります。 神門寺:出雲大社との係わりに於ても、又、中世時代、山陰地方随一の寺院であったことなど未知のロマンを今も秘めたままになっている。名残りらしきものは欅の巨木の森に囲まれた広大な寺域に垣間見ることができる。 開山が宋肇菩薩、二世は伝教大師、三世が弘法大師である。いかに当時隆盛していたことを物語るもので、弘法大師がこの神門寺から「いろは四十八文字」を四方に弘めたれたということから神門寺ではこの仮名文字の御真筆を現在も収蔵している。 御本尊は行基菩薩のご自作と伝えられる阿弥陀如来で、法嗣は永く密教を厳修していたが、三十八世良空上人が法然上人の専修念仏に帰依して上洛し、七条の袈裟と六字名号を授かって帰り、山陰地方の念仏弘通の霊場となった。観音堂には慈覚大師作と思われる平安初期の秘仏十一面観世音菩薩像が祀られている。 禅定寺:斐伊川堤から三刀屋町に入る道と国道九号線から宍道町より国道五十四号線を三刀屋に向かう何れかの道にしても三刀屋の町を過ぎて約3km入ったところに鍋山の集落があり、そこから出雲市へ出る道路を2km位入った所に参道入口がある。そして約5〇〇m馬場を登ると山門につく。峻しい山の自然が随所にあり登山は苦しい事もある。しかし、今では車で山門下まで入る事が出来て案ずる事はない。 山寺が創建された深遠な事は、密教思想の根本でもある、苦行修練の精心を説いたもので、苦難の道に菩提心を養う事が信仰の世界といえる。こうした聖地に建立された寺の山号・寺名についても四方の景観により慶びを迎える山であるというところから慶向山と号し、又禅定三昧に適した所であるところから禅定寺と名づけられた由。 庫裡の畳の上から中国山脈の連山を眺める時、数10kmの山並は静かに眠る「おろち」のようで四季にはそれぞれの姿を見せてくれる。雄大にして、繊細なその表情は、自然の豊かさを教えてくれる 多陀寺:奇岩と白砂が交互に繰り返し広がる山陰海岸・石見路、その中核の街が「浜田」であり、中世には大陸貿易の主要港として栄えた街である。その浜田、否、石見路を代表する屈指の古刹が多陀寺である。寺は県立自然公園の浜田海岸や天然記念物の石見畳ヶ浦の絶景が一望できる小高い山上に位置する。 多陀寺開山の流世上人は空海と相弟子で、共に唐に留学僧として渡り、恵果阿闍梨より密法の直伝を受け、空海より2年早く帰国(806年)、諸国を遊歴しながらの上洛の途次、この地での奇瑞を感得し、唐より持帰った金色観音像を安置したのが始まりと、縁起を伝える。 山陰海岸の落日風景は、えも言われぬ美しさ、荘厳さは定評があり、仏教信者には将に、夕陽の沈む大海原に西方浄土の光芒を見る想いであったろう。 参道は急な石段からと、山腹を迂回した自動車道がある。仁王門の傍には天然記念物の大楠が天に聳えるのが印象深い。また、珍しい流木仏60余体を蔵していることでも広く知られている。 清水寺:山陰唯一の多宝塔、中海圏の観光名勝古刹静かにうねる中海から南にわずか2km、海抜50m余りの小さな山の谷間にたたずむ清水寺は、東には霊峰大山を望み、西には八雲の峰峰が連なる景勝の地、安来節の故郷、安来市に位置する。 用命天皇2年の開基で、1400年の法灯を有する山陰随一の観音霊場である。 根本堂は明徳4年の建立で600余年の歳月を有し、御本尊は推古天皇感得の厄除けの観音様である。 初詣、厄年のお払い、節分の星祭り、春の還誕祭、夏の御開扉法要、秋の光明真言会、師走の大梵焼祭、そして、毎月17日の観音様御縁日には朝から香煙のたえ間ない、天台密教の祈願道場である。 又、境内の奥に高くそびえる三重塔は山陰唯一の多寶塔で、登ることができる塔は全国でも珍しい。更に光明閣の書院庭園、重文の佛像他寺宝を収めた宝蔵と、豊かな自然とよく調和した堂舎は中海圏の観光要所として、参拝者のたえることなし。 雲樹寺:中海に面した安来港は、伯太川の河口が発達し、地場産業の積み出し場所として賑わいました。また西回り航路の寄港地として古くから栄えていましたが、松江藩では東の入口に位置したことからも警備も厳しく、番所、制札場などが設けられていました。 その安来港から伯太川をさかのぼって千代富橋を過ぎ、堤を下ると、左側に臨済宗妙心寺派の名刹・雲樹寺の参道が見えます。拈華微笑仏を本尊とするこの寺は、後醍醐・後村上両朝の勅願寺でした。 松並木の参道に入ると辺りは水田で、中程にある四脚門を通り、石門を抜けると左に広がる境内に、山門、仏殿、方丈、と伽藍が一直線に並んでいます。禅宗様式と呼ばれる構えで、地方寺院には珍しい貴重なものです。大門から先の繁みには「酒だち地蔵」の祠があります。山門のすぐ脇にある観音堂には、親称「子授け観音」が祀られており、諸願成就と共に、古来より多くの信仰を集めています。 方丈の背面の山には枯山水形式の禅宗庭園があり、巡拝者の心を和ませてくれます。 16:00終了、出雲空港に向かう。 17:00出雲空港到達。 18:25出雲空港出発 19:15伊丹空港到達。 今回の旅行、中国地方の島根県に足を運び島根県に点在する中国三十三所観音の7か所を訪れ楽しみました。 いずれも立派な霊場で、門から建物までたどり着くのが遠くて時間がかかるところが多く、規模の大きい霊場が目白押しでした。 残るは広島県の霊場のみとなりました。次回訪れたいと思います。 |
           |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第三百九十四弾:栃木県お城・城下町巡り観光 2017年3月11-12日 北関東地方の源頼朝、木曾義仲、そして平家が争う渦中で、頼朝についた小山氏が力をつけ、下野守護となる。宇都宮氏、那須氏と領地を分け合うが、度重なる争いで衰退し、小規模な勢力が割拠する時代に突入した栃木県に足を運び比較的マイナーなお城10か所を訪れました。 11日13:50新大阪新幹線のぞみで出発 16:30東京駅到達、タクシーで帝国ホテルに向かう。 17:00帝国ホテルタクシーで虎ノ門ヒルズに向かう。 17:30講演会参加 21:00タクシーで帝国ホテルに向かう。 21:30帝国ホテル到達、就寝。 12日7:30帝国ホテルタクシーで八重洲に向かう。 8:00レンタカーで出発、栃木県佐野方面に向かう。 9:00佐野市到達、栃木県宇都宮から南エリアに点在する比較的マイナーなお城10か所を訪れる。 佐野城:慶長7年(1602年)佐野信吉によって築かれた。 信吉は新たに佐野城を築城して唐沢山城より城下町を移したが、城は完成を見る事無く、信吉の実兄の伊予国宇和島藩主富田信高の改易に連座して所領没収となった。 唐沢山城:天慶3年(940年)藤原秀郷によって築かれたのが始まりとされる。 秀郷は平将門が関東を制圧した天慶の乱を鎮圧した功によって、下野に勢力を張った。 延徳3年(1491年)佐野氏中興の祖といわれる佐野盛綱が城を修築した。 戦国時代には小田原北条氏と越後上杉氏の狭間にあって苦慮しながら、上杉謙信による攻撃を10回にわたって退けるなど堅城ぶりを発揮した。 しかし、天正13年(1585年)当主佐野宗綱が長尾顕長の足利に攻め入ろうとして、須花坂を越えようとしたとき、鉄砲に当たって討死した。その後家中は動揺し北条氏康の五男氏忠が佐野家の養子となって家督を継ぐことで北条氏と和解する。 天正18年(1590年)豊臣秀吉による小田原征伐では、先の当主宗綱の弟房綱は豊臣方となり唐沢山城の城代大貫氏を討って唐沢山城に入った。 これにより秀吉から所領三万九千石を安堵される。 その後、房綱は秀吉の家臣富田左近将監の次男信種を養子に迎え、信種は佐野信吉と改名した。 慶長7年(1602年)信吉は佐野城を築いて居城を移したため、唐沢山城は廃城となった。 皆川城:築城年代は定かではない。寛喜年間(1229年~1232年)に皆川宗員によって築かれたと云われるが、これは近くにある白山台であったとも考えられている。この先の皆川氏は元享3年(1323年)には断絶している。 永享12年(1440年)には長沼秀宗が皆川城を本拠にしてしたことから、この頃には築かれていたようである。 皆川広照は宇都宮氏に従っていたが、北条氏政・氏直父子が大軍を率いて北上してくるとそれに降った。天正18年(1590年)豊臣秀吉による小田原征伐で、皆川広照は小田原城に籠城したが、徳川家康を介して秀吉に降り助命された。 天正19年(1591年)皆川広照は栃木城を築いて居城としたが、家康の六男松平忠輝の家老となり、忠輝が信濃国川中島へ移るに従い信濃国飯山へ転封となっている。 多気城:康平6年(1063年)宇都宮宗円によって築かれたと云われるが定かではない。 「天正4年(1576年)の12月2日に着工して同月25日に落成した」との記載が残っているが、その期間からすると改修工事と思われる。 戦国時代末期の宇都宮国綱は北条氏の脅威から一時的に宇都宮城を離れ多気山城に居城を移し、天正18年(1590年)豊臣秀吉による小田原征伐の後に、宇都宮城に戻ったともいわれる。 石那田城:石那田館は田川と赤堀川に囲まれた平地に築かれている。長方形に近い館で北東側がやや斜めになった五角形の館であったようだが、現在北側は日光宇都宮道路によって消滅している。土塁は西側に残っており、南は田川に面した崖地になっている。詳細不明。在地豪族の小池氏の館と推測されている。 宇都宮城:築城年代は定かではないが宇都宮氏によって築かれた。 鎌倉時代には館として機能していたが南北朝時代に城郭として拡張されていく。 宇都宮氏は慶長2年(1597年)22代国綱の時、突然豊臣秀吉によって改易された。 改易の理由は諸説あり定かではないが、国綱の養子問題について、内乱を引き起こし秀吉の命に背いたことが要因とされる。 宇都宮氏の後は城代として浅野長政が入城するがすぐに会津若松から蒲生秀行が入封する。 蒲生秀行は4年後に会津若松に復帰して替わって大河内氏、奥平氏と替わる。 元和5年(1619年)本多正純が十五万石で入封し近世城郭へと大改修された。 元和8年(1622年)本多氏は有名な「宇都宮城釣天井事件」の俗説が巻き起こる程、突然の改易となり、正純は出羽国本荘に流された。その後は譜代大名が目まぐるしく入れ替わる。 元和8年(1622年)下総国古河より奥平忠昌が十一万石で入封、寛文8年(1668年)昌能の時、出羽国山形に転封。 寛文8年(1668年)出羽国山形より(奥平)松平忠弘が十五万石で入封、天和元年(1681年)陸奥国白河へ転封。 天和元年(1681年)陸奥国白河より本多忠平が十一万石で入封、貞享2年(1685年)大和国郡山へ転封。 貞享2年(1685年)出羽国山形より奥平昌章が十万石で入封、元禄10年(1697年)昌成の時、丹後国宮津へ転封。 元禄10年(1697年)丹後国宮津より阿部正邦が十万石で入封、宝永7年(1710年)備後国福山へ転封。 宝永7年(1710年)越後国高田より戸田忠真が七万八千石で入封、寛延2年(1749年)忠盈の時、肥前国島原へ転封。 寛延2年(1749年)肥前国島原より松平忠祗が六万六千石で入封、安永3年(1774年)忠恕の時、肥前国島原へ転封。 安永3年(1774年)肥前国島原より戸田忠盈が七万八千石で入封、以後明治に至る。 飛山城:築城年代は定かではないが永仁年間(1293年~1299年)に芳賀高俊によって築かれたと 云われる。 芳賀氏は下野国芳賀郡大内荘の発祥で、清原高澄の子高重が花山天皇の怒りに触れて寛和元年(975年)芳賀郡大内荘に配流となって居住したことに始まる。南北朝時代には宇都宮氏に従って北朝方として南朝方と対峙、暦応4年(1341年)南朝方の春日顕国によって攻められ、飛山城は落城、しかし康永年間(1342年~1345年)頃には再び芳賀氏の手に戻った。天正18年(1590年)の小田原征伐の後に廃城となった。 児山城:築城年代は定かではないが建武年間(1334年~1338年)に児山朝定によって築かれたと云われる。 多功朝定は宇都宮頼綱の四男で多功城主の多功宗朝の二男(または三男)で、児山郷を領して児山城を築き児山氏の祖となった。 永禄元年(1558年)上杉謙信が多功城を攻めた際、児山兼朝が上杉方の佐野豊綱と戦って討死し、児山城は廃城となった。 祇園城:築城年代は定かではない。一説に平安時代末期に小山政光によって築かれたとも云われるが確証はない。 小山氏(おやま)は藤原秀郷の末裔太田政光が下野国都賀郡小山を領し小山氏を名乗ったことに始まる。 南北朝時代には小山朝氏・氏政は北朝方に属す。康暦2年(1380年)小山義政の時には宇都宮氏との領地争いが起こり、鎌倉公方足利氏満の再三の制止しにもかかわらず、河内郡裳原で宇都宮基綱と戦い基綱は討ち死にした。これに対して鎌倉公方は義政を討つよう関八州に命を下し、義政は各地で応戦するも好転せず永徳2年(1382年)祇園城を焼き払って櫃沢城へと逃れるも更に攻められ義政は自害し、子の若犬丸は奥州へ逃れた。若犬丸も奥州で挙兵したが再興はかなわず応永4年(1397年)会津で自害し小山氏は滅亡した。この時代の小山氏の本城は祇園城ではなく鷲城であったという。 その後小山氏は同族の結城泰朝が継ぎ祇園城を本城として代々続く。戦国時代には北条氏に属していたが、豊臣秀吉による小田原征伐後に所領を没収され、所領は結城秀康に与えられた。 徳川家康が関東へ移封となると本多正純が三万三千石で入封したが、元和5年(1619年)宇都宮へ転封となり廃城となった。 鷲城:築城年代は定かではない。小山氏の居城で小山義政は祇園城、長福城、中久喜城などの支城を配して鎌倉公方足利氏満と戦った 17:30東京駅到達。 18:10東京駅新幹線のぞみで出発 20:30新大阪駅到達。 今回の旅行、北関東の栃木県に足を運び、宇都野宮から南のエリアに点在する比較的マイナーなお城10か所をおとずれ楽しみました。 土曜日は東京で講演会に出席し、翌日はレンタカーで栃木県に向かいました。 |
              |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第三百九十三弾:山口県お城・城下町巡り観光 2017年3月4-5日 中国地方の最西端、周防、長門からなり、周防の大内氏が力をつけ、防長両国に基盤を築き、大内氏の勢力拡大は北九州にまで及んだが、尼子氏との戦いで衰退し、やがて防長の支配は毛利氏に移り変わった山口県に足を運び、比較的マイナーなお城10か所を訪れました。 4日17:05新大阪新幹線のぞみで出発 18:57新山口駅到達、レンタカーで防府に向かう。 19:30防府駅前のホテル到着後繫華街を散策し食事を済ませて就寝。 5日7:00レンタカーで出発、反時計回りで山口県西エリアに点在するお城を巡る。 築山城:室町時代に大内教弘によって築かれたと云われる。 大内氏は守護大名として次第に勢力を伸ばすにつれ大殿大内氏館だけでは手狭となった為、別邸として築山館を築いた。 もともとは大石を積み上げた石垣で周囲を囲っていたが、江戸末期に毛利氏が長門国萩城から山口城に居城を移したときに大石を運び出した為、現在の土塁のようになったと云う。 大内氏館:正平15年(1360年)頃に大内弘世によって築かれたと云われる。 弘世は京に似た山に囲まれた盆地として山口を選地しここに館を築いた。大内義隆が重臣陶晴賢によって討たれ、その後、陶氏を滅ぼした毛利氏によってこの館跡に龍福寺が建立された。 山口藩庁:元治元年(1864年)毛利敬親によって築かれた。 防長二カ国三十六万石の大名であった萩藩毛利十三代敬親によって築かれた。 毛利敬親は文久3年(1863年)湯田温泉への日帰り湯治と称して萩城から山口へと拠点を移した。 これは保守派に取り囲まれた萩では攘夷を実行できないことと、北に偏った萩では交通の便、海からの防御の面で不都合があったためである。 幕府に対しては山口屋形として申請していたが、背後には中世大内氏の詰城であった高嶺城があり、表には水堀を配していた。 高嶺城:弘治3年(1557年)大内義長によって築かれた。 弘治元年(1555年)陶晴賢が厳島合戦で毛利元就に敗れると、義長は毛利氏に備えて急拠築城することとなったが毛利氏の侵攻が早く完成を見ないまま籠城することとなる。 大内氏に属してした諸将が毛利氏に寝返るなど次第に不利となり義長は城を捨てて長門国且山城に逃走し長福寺で自刃した。 その後毛利氏は市川経好等を城番として置き城を補修した。 永禄12年(1569年)毛利氏は豊後国大友氏と筑前国立花城にて対峙したが、大友氏は大内義興の弟高弘の子大内輝弘に兵を与えて山口に侵攻させた。このとき高嶺城は市川氏の留守兵がわずかに守るだけであったが、市川経好の正室市川局が籠城兵を指揮して毛利の援軍が来るまで持ちこたえた。 輝弘は茶臼山に退きそこで自刃して果てた。 荒滝城:築城年代は定かではない。大内氏の重臣で後に毛利家臣となった内藤隆春の居城と伝えられる。 内藤隆春の姉が毛利元就の嫡男毛利隆元の正室尾崎局であった。陶晴賢による大内義隆への謀叛には同調せず、厳島合戦の後は毛利氏に従って各地を転戦し、大内義長滅亡後は長門守護代となった。隆春には嫡子がいなかったことから宍戸元秀の二男元盛を養子に迎えている。この元盛が佐野道可と名乗って大坂城に籠城した人物である。 清末陣屋:万治2年(1659年)毛利元知によって築かれた。 長府藩毛利綱元は承応2年(1653年)毛利秀元の遺言により秀元の二男元知を一万石で分地し元知は万治2年(1659年)陣屋を築いた。 享保3年(1718年)元平の時、長府藩元矩が嗣子なく元平が匡広と改名して長府藩を継ぎ清末藩は長府藩と合併した。 享保14年(1729年)匡広の二男正苗に一万石が再分地され清末藩が再興した。 勝山城:築城年代は定かではないが永和4年(1378年)大内氏の家臣永富上総介嗣光が在城したのが始まりとされる。続いて応永15年(1408年)に相良民部少輔が在城したと云う。 大永7年(1527年)には内藤興盛の居城となり、この興盛の時に南の尾根続きにある青山城主高森内膳之助と「青山くずれ」と呼ばれる争いが起こった。(「青山くずれ」に関しては青山城を参照)。内藤興盛は後に長門国守護代となり櫛崎城へと移った。 陶晴賢を厳島合戦で敗った毛利元就はすぐさま周防国・長門国へ侵攻し、弘治3年(1557年)には周防国高嶺城に攻め寄ると、大内義長は内藤隆世(内藤興盛の孫)を頼って且山城へ逃れた。毛利氏の軍勢は且山城を取り囲んで攻め寄せ、外城を落とし本丸を残すのみとなったところで城内に矢文を放ち「内藤隆世は毛利父子に遺恨があるので自決すれば、義長のことは問わぬ」と伝えた。 隆世は切腹し義長は城を出て兄である大友義鎮を頼って九州を目指したが、叶わず長福院(現在の功山寺)にて自刃した。 その後は南条宗勝、山田重直が在城したという。 勝山御殿:勝山御殿は南を除く三方を山に囲まれた谷間の奥地に築かれている。 北に且山城、西に青山城、北東には四王司山城と中世城郭に囲まれた地である。 以前訪れたときは公園整備中であったが、現在は公園も完成しきれいに整備された御殿跡と案内板が設置されていた。 北から南にかけて本丸(奥)、本丸(表)、二ノ丸、三ノ丸と並び、西と南面が石垣となっている。 串崎城:天慶3年(940年)に藤原純友の配下稲村平六景家が在城していたと伝わるが定かではない。 戦国時代には大内義隆の家臣内藤隆春が在城していた。 関ヶ原合戦後、毛利輝元は防長二カ国に減封となり萩城を居城とした。これによって毛利秀元は六万石を分知されて櫛崎城を居城とし長府藩となった。 毛利秀元は毛利元就の四男穗井田元清の長子で、長らく嫡男に恵まれなかった毛利輝元の養子となった人物である。後に輝元に嫡男秀就が誕生したことから別家をたてた。 元和元年(1615年)幕府による一国一城令によって櫛崎城は廃城となり、長府藩は現在の豊浦高校の敷地に居館を構えて藩庁とした。元治元年(1864年)十三代毛利元周のとき勝山御殿を築いて居城を移している。 霜降城:治承3年(1179年)七代厚東武光によって築かれたと云われる。 厚東氏は物部氏の末裔を称し、初代厚東武忠が棚井の地に住んだことに始まるとされ厚東氏館を居館としていた。 十四代厚東武実は長門守護職となり勢力を拡げるが、その後大内氏と争うようになり、十七代厚東義武のとき延文3年・正平13年(1358年)大内弘世によって霜降城は攻め落とされ、厚東義武は城を逃れて九州へ落ちていった。 18:00終了。 18:46新山口駅新幹線のぞみで出発 20:38新大阪駅到達。 今回の旅行、山口県の西エリアに点在する比較的マイナーなお城10か所を巡り楽しみました。 山口県は道も広く、車も少なく、渋滞に絡まずスムーズに走ることができました。 次回は東エリアに点在するお城を巡りたいと思います。 |
             |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第三百九十二弾:佐賀県お城・城下町巡り観光 2017年2月18-19日 九州の小規模な国人に過ぎなかった龍造寺氏が、龍造寺家兼の時代に飛躍し、肥前で権力をふるう戦国大名となり、一時は島津氏、大友氏と並び九州の支配を分け合うが、龍造寺隆信の死後、配下の鍋島氏に実権が移る佐賀県に足を運び、比較的マイナーなお城8か所を訪れました。 18日17:30伊丹空港出発 18:50長崎空港到達、レンタカーで武雄方面に向かう。 20:00武雄駅前のホテル到着後繫華街を散策し食事を済ませて就寝。 19日7:30レンタカーで出発、お城巡り。 千葉城:築城年代は定かではないが南北朝時代頃に千葉氏によって築かれたと云われる。 千葉氏は桓武平氏で下総国に住し、代々千葉介を称して千葉氏を名乗った一族で、千葉常胤が源頼朝の挙兵や奥州合戦で戦功を挙げ、肥前国晴気荘を与えられた。千葉頼胤のとき、元寇で九州へ下向したが討死し嫡男の宗胤も下向した。この宗胤の次男千葉胤泰が肥前千葉氏の祖となった。 肥前千葉氏は小城・佐賀・杵島三郡に及ぶ勢力を振るったが、文明年間(1469年~1487年)頃には千葉氏は内訌により分裂、少弐氏に属した晴気城の千葉胤資と大内氏に属した千葉城の千葉興常が敵対した。明応6年(1497年)大内義興は少弐政資を攻めると筑前を破棄した政資は晴気城へ逃れたが、さらに追い立てられ政資と千葉胤資は滅亡した。これによって千葉興常は肥前守護代に任ぜられた。 大内義隆が討たれ、龍造寺隆信が台頭してくると千葉氏はその支配に組み込まれるようになる。龍造寺隆信が有馬・島津連合軍と戦って敗死すると鍋島直茂が執政となり、近世佐賀藩の家臣として千葉氏は続いた。 高木城:久安年間(1145年~1151年)に高木貞永によって築城された。 高木氏の祖は藤原氏で鎌足12代の後裔藤原隆家が大宰権師として赴任したことに始まる。 南北朝時代には足利氏に属して豪族として強大な勢力を持っていたが龍造寺氏との戦いに破れて衰退した。 姉川城:築城年代は定かではないが正平15年(1360年)に菊池武安によって築かれたと云われる。その後は菊池氏の庶流という姉川友安、姉川惟安、姉川信安などが城主であった。 蓮池城:応永34年(1429年)小田常陸介直光によって築かれた小曲城がその前身である。 小田氏は常陸国小田城主であった小田氏の庶流という。 永享6年(1434年)横武頼房が少弐の勢力を回復するために挙兵したときには、小田貞光もこれに参戦して渋川満直と戦った。永享3年(1530年)大内の軍勢を田手畷で敗った少弐氏であったが、家臣の龍造寺家兼が勢力を伸ばすと天文5年(1530年)少弐資元は大内義隆の家臣陶興房に攻められ自刃して果てた。資元の子冬尚が頼ったのが蓮池城主の小田資光である。 少弐冬尚が再興すると小田政光はこれに仕え、天文14年(1545年)には水ヶ江城、天文20年(1551年)には村中城を攻めている。しかし、天文22年(1553年)小田政光が城番を務めていた村中城が龍造寺隆信よって奪われると政光の居城である蓮池城も攻められ、政光は龍造寺氏に降った。 永禄元年(1558年)小田政光は龍造寺隆信の要請によって少弐冬尚の家臣江上武種を攻め長者林で戦った。苦戦した政光は隆信に増援を求めたが隆信は援軍を送らず、政光は討死してしまった。政光戦死の報を聞いた隆信は小田氏の居城である蓮池城を急襲して攻め落とした。 蓮池城を脱して落ちていた政光の子小田鎮光・朝光・増光はその後帰参が許され龍造寺氏に従ったが、永禄11年(1568年)小田鎮光は梶峰城へ移され、龍造寺長信が多久から蓮池城に移った。長信の後は龍造寺家晴、鍋島信生(後の直茂)、江上家種の居城となった。 江上家種は龍造寺隆信の次男で鍋島直茂の嫡男勝茂を養子に迎えていた。 家種は文禄2年(1593年)文禄の役で渡海し釜山で討死しており、その後は鍋島氏が城主となった。この時代の蓮池城には天守が存在し、一つ目は天正18年(1590年)に名護屋城に移している。その後天守が再建され、元和の一国一城令により廃城となったときに佐賀城へ移されたと云われる。 承応3年(1654年)鍋島直澄が蓮池城跡地に蓮池陣屋を構え蓮池藩となった。蓮池藩は 寛永16年(1639年)佐賀藩初代鍋島勝茂の三男鍋島直澄が三万五千石余りを分与され、その後に五万二千六百二十五石の所領を分与されたもので、蓮池陣屋を構えるまでは佐賀城三ノ丸に居住していた。 綾部城:宮山城、鷹取城、などこの地に固まる複数の城の総称。 勝尾城:応永30年(1423年)九州探題渋川義俊によって築かれたと云われる。渋川氏は大宰少弐武藤氏と争いに敗れ、その大宰少弐武藤氏も明応6年(1497年)筑前国の回復を目論んだが周防国大内氏に敗れた。その後、筑紫氏が勝尾城主となり、満門、惟門、広門と三代に渡って居城となった。 天正14年(1586年)筑紫広門は北侵する島津軍と戦ったが敗れ落城した。この戦いでは弟晴門が島津の部将川上忠堅と一騎討ちを演じて相討ちとなり、広門は捕らえられて幽閉の身となった。天正15年(1587年)豊臣秀吉による九州征伐で広門は幽閉先から脱出して再帰を計り、旧領を奪還する。戦後秀吉から賞され、筑後国上妻郡に一万八千石余りを賜り転封となった。 基肄城:天智4年(665年)築かれた。 天智2年(663年)に唐・新羅軍と対峙した日本と百済の連合軍は海戦において大敗した。大陸からの侵攻に備えて大宰府を置き九州の各所に城を築いた。そのうちの一つが基肄城で百済から亡命した貴族の指導のもとに築かれた朝鮮式山城である。 三瀬城:築城年代は定かではないが、享禄年間(1528年~1532年)に三瀬(野田)土佐守入道宗利によって築かれたと云われる。 もともとは在地領主の三瀬氏の居城であったが、天文元年(1532年)三瀬貞家のとき、神代勝利を招いて山内諸豪族の盟主とし、三瀬城を譲ったと云われる。 神代勝利は山内の盟主として勢力を拡げ、村中城主の龍造寺隆信と戦った。永禄7年(1564年)勝利は隠居して畑瀬城へ移り、家督は嫡男の長良が継いだ。神代長良は翌永禄8年に三瀬城を改修して家臣団を集め、龍造寺氏に備えた。また長良は千布城を拠点として平野部へも進出したが、同年嫡男と娘が疱瘡によって夭折すると、この混乱に乗じて龍造寺隆信に攻められ千布城から追われた。 元亀2年(1571年)神代長良は鍋島直茂の弟小川信俊の子を養子に迎えて家督を譲り、その神代家良は天正18年(1590年)に山内から芦刈・川久保へ領地替えとなり、三瀬城は廃城となった。 17:00長崎空港到達。 19:20長最空港出発 20:35伊丹空港到達。 今回の旅行、九州佐賀県に足を運び、佐賀県に点在する比較的マイナーなお城8か所を訪れ楽しみました。 佐賀県も観光地が少ない都道府県、比較的マイナーなお城は案内板も確りあり、容易にたどり着けることができました。 九州のお城巡り、残りは熊本県のみとなりました。震災でインフラがまだまだ不十分、年末を計画しています。 |
           |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第三百九十弾:大分県小京都&重要伝統的建造物群保存地区&お城・城下町巡り観光 2017年2月4-5日 九州の源頼朝に守護を任じられた大友氏が長く治め、南北朝の内乱が終息したころ、大内氏が九州に進出し豊前守護となり、両者は対立するが、大内氏が胸氏の謀反などで衰退し、大友氏が掌握した大分県に足を運び、比較的マイナーなお城5か所、重要伝統的建造物群保存地区5か所を訪れました。 4日15:00伊丹空港出発。 15:55大分空港到達、レンタカーで城めぐり。 国東半島巡る。 安岐城:築城年代は定かではないが応永年間(1394年~1428年)に飯塚城主の田原親幸によって築かれたと云われる。 室町時代の田原親宏は一時豊後から追放されており、大友宗麟のときに帰参が許されると国東郡安岐郷を与えられた。このとき安岐城が拠点として整備された。 天正8年(1580年)田原親宏の跡を巡る家督争いで、大友宗麟が次男親家に田原家の家督を継がせようと画策した。親宏の養子であった田原親貫は毛利氏などに援軍を求めてこれに対抗し、安岐城でも田原氏と大友氏で激戦が繰り広げられたが城は大友氏によって落城した。 文禄2年(1593年)豊臣秀吉によって大友義統は改易となり、一万五千石が熊谷直陳に与えられ安岐城主となった。この熊谷氏の時代に近世城郭に改修された。慶長5年(1600年)関ヶ原合戦では熊谷直陳に西軍に属して美濃国大垣城を守っていたが、内応によって落城し直陳は討たれた。 富来城:弘長元年(1261年)富来忠文あるいは正安元年(1299年)富来忠政によって築かれたと云われる。 富来氏は代々大友氏に仕えるが18代実直、実信父子は耳川合戦で戦死、19代鎮久は朝鮮の役で戦死するなど衰退した。 文禄2年(1593年)豊臣秀吉は大友義統を改易とすると、垣見家純に二万石を与えて城主とした。 慶長5年(1600年)関ヶ原合戦で垣見家純は西軍に属して美濃国大垣城を守っていた。このとき、豊後国では石垣原合戦で大友氏を下した黒田孝高がその勢いに乗じて富来城を包囲したが、留守を守る垣見理右衛門は城を固く守り落城しなかった。しかし、家純が守っていた大垣城は東軍に内応した諸将が出て落城、家純も討死した。この急報を聞いた理右衛門は開城降伏した。 田原城: 18:00豊後高田方面に向かう。 19:00豊後高田市内のホテル到着後繫華街を散策し食事を済ませて就寝。 5日7:30レンタカーで出発、城、重要伝統的建造物群保存地区巡る。 豊後高田:大分県豊後高田市は、古い時代が息づく町。 千年の時を越えて受け継がれてきた美しい自然、六郷満山(ろくごうまんざん)文化の歴史が織り成す豊かな風土、古い町並みや伝統行事など、古き良き時代を知り、触れることができる町です 高田城:建久7年(1196年)高田掃部介重定によって築かれたと云われる。 高田氏は大友氏の豊後下向に随従してきたという。 文禄2年(1593年)豊臣秀吉は大友義統を改易し、美濃国長松城主竹中重利(重隆)に一万三千石を与えて高田城主とした。重利は竹中半兵衛の従兄弟にあたり、この竹中氏の時代に城が拡張された。 慶長5年(1600年)関ヶ原合戦で重利は西軍に属して近江の瀬田橋の警固を務め、その後丹後国田辺城攻めに加わったが、黒田官兵衛の誘いに応じて東軍に寝返り、戦後所領を安堵された。 翌慶長6年(1601年)重利は三万五千石で府内に転封となり、寛永16年(1639年)豊前国龍王から松平重直が入封する。 正保2年(1645年)重直は木付に転封となり寛文9年(1669年)丹波国福知山の松平忠房が肥前国島原に転封となると飛領地として豊州陣屋が設けられた。 真玉城:文和2年・正平8年(1353年)真玉重実によって築かれたと云われる。 それ以前に在地豪族の大神系真玉氏が居たが、文和2年に大友氏一族の木付頼重が兄頼直より真玉荘七十町を譲られ大友系真玉氏の祖となった。 天正18年(1590年)真玉氏9代統寛は豊臣秀吉による小田原城攻めに参陣するため竹田津港に向かう途中で家臣山田兼佐の謀反により落命。これによって真玉氏は滅亡した。 中津に向かう。 中津:大分県の中津は歴史を感じることができる町である。江戸時代の城下町を再現した町並み、幼少の福沢諭吉が過ごした家などが存在する。 日田に向かう。 日田:日田市は、北部九州のほぼ中央、大分県の西部に位置し、福岡県と熊本県に隣接した地域です。また、周囲を阿蘇・くじゅう山系や英彦山系の美しい山々に囲まれ、これらの山系から流れ出る豊富な水が日田盆地で合流し、筑後・佐賀平野を貫流しながら、流域住民と福岡都市圏住民の生活や産業を潤しています。さらには、古くから北部九州の各地を結ぶ交通の要衝として栄え、江戸時代には幕府直轄地・天領として西国筋郡代が置かれるなど、九州の政治・経済・文化の中心地として繁栄し、当時の歴史的な町並みや伝統文化が、今なお脈々と受け継がれています。 別府に向かう。 鉄輪温泉:日本1位の湧出量を誇る別府では、408本のゆけむりが出ており、その大半を鉄輪がある鉄輪地区が占めています。 杵築に向かう。 杵築:大分県の北東部に位置する杵築市は杵築城や武家屋敷跡など、歴史的な景観を今も残している城下町で、南北の高台には武士が、その谷あいには商人が住んだという日本唯一の「サンドイッチ型城下町」ともいわれています。「 15:00大分空港に向かう。 15:30大分空港到達。 16:25大分空港出発。 17:20伊丹空港到達。 今回の旅行、九州大分県に足を運び、比較的マイナーなお城5か所、重要伝統的建造物群保存地区5か所を訪れ楽しみました。 お城に関しては今回も地味で際立ったものはなかったが重要伝統的建造物群保存地区はそれぞれ個性があり散策して楽しむことができました。 豊後高田は小さなレトロな商店街、中津は中津城を中心に周囲にお寺、武家屋敷が点在する城下町、日田はエリアも広く現在も活気があり観光客も多いビッグなレトロの商店街、鉄輪温泉は日本一温泉量の多い温泉町、杵築は杵築城を中心として二つの高台に武家屋敷が点在し、谷は商人の町、それぞれ特色があり個性的な重要伝統的建造物群保存地区巡り堪能しました。 |
           |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第三百八十九弾:宮崎県小京都&重要伝統的建造物群保存地区&お城・城下町巡り観光 2017年1月28-29日 九州の守護大名の伊東氏が権力を持つが、木崎原の戦いで島津氏に大敗を喫すると、豊後の大友氏を頼り、島津氏と大友氏は激しく争い、最終的には豊臣秀吉の九州統一によって争乱にピリオドが打たれた宮崎県に足を運び、比較的マイナーなお城2か所、小京都1か所、重要伝統的建造物群保存地区3か所を訪れました。 28日17:55伊丹空港出発 19:05宮崎空港到達、レンタカーで延岡方面に向かう。 21:05延岡駅前のホテル到着後繫華街を散策し食事を済ませて就寝。 29日8:00レンタカーで出発、歴史的建造物巡り。 延岡城:築城年代は定かではないが中世の縣城(あがた)がその前身である。 近世延岡城を築いたのは高橋元種で、豊臣秀吉による九州征伐により松尾城に封ぜられた豊臣大名である。元種は慶長6年(1601年)に延岡城の築城を開始し、慶長8年(1603年)に完成した。 松尾城:文安3年(1446年)土持宣綱によって築かれたと云われる。 縣庄を本拠として勢力を張った縣土持氏は宣綱の時、松尾城を築いて西階城より移り、康正2年(1456年)一族の財部土持氏とともに都於郡城の伊東氏と戦ったが敗れ、翌長禄元年(1457年)には財部城は伊東氏によって包囲され、開城して財部土持氏は滅亡する。 その後、縣土持氏は伊東氏と門川城、日知屋城などを争って度々戦うが、元亀3年(1572年)木崎原の戦いで島津氏に敗れた伊東氏は瞬く間に衰退し、天正5年(1577年)伊東義祐は都於郡城を捨てて大友氏を頼って落ち延びた。これによって島津氏と大友氏の巨大勢力の狭間に立つこととなった縣土持氏は、島津氏、大友両氏に通じて命脈を保とうとするも、天正6年(1578年)大友氏の大軍に攻撃され落城し滅亡した。 その後、耳川合戦で大友氏を敗った島津氏の所領となったが、天正15年(1587年)豊臣秀吉による九州征伐の後は高橋元種が入封し、慶長8年(1603年)延岡城を築いて移るまでの居城であった。 椎葉村:椎葉村(しいばそん)は、ちょっぴり悲しい平家落人伝説で全国に知られた宮崎県北西部にある東臼杵郡の村です。いまも各地からの観光客が絶えない日本三大秘境のひとつ平家落人伝説の郷。 美々津:江戸、明治時代の白壁土蔵の町並みが残る。昔から海の交易の拠点として歴史を刻み、関西との交流の主役となった廻船問屋の活躍がしのばれ、往時の文化的な遺産を大切にした町づくりが行われている。 飫肥:飫肥は、天正16年(1588)から明治初期までの280年間飫肥藩・伊東氏5万1千石の城下町として栄えたところです。武家屋敷を象徴する門構え、風情ある石垣、漆喰塀が残る町並みは、昭和52年に重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。 昭和53年に復元された大手門を中心に、松尾の丸や藩校振徳堂、伊東家の歴史を綴る貴重な資料が展示されている飫肥城歴史資料館があります。また、 商人町通りには樽を店頭に置いた商家や、格子に壁燈籠、番傘を飾った商家が軒を連ね、町を流れる堀割の清流など、江戸時代を彷彿とさせる町並みが楽しめます。 16:00終了、宮崎空港に向かう。 17:30宮崎空港到達。 19:30宮崎空港出発。 20:35伊丹空港到達。 今回の旅行、九州宮崎県に足を運び、比較的マイナーなお城2か所と小京都1か所、重要伝統的建造物群保存地区3か所を訪れ楽しみました。 今回から初の小京都、重要伝統的建造物群保存地区巡り、日本の中世の街並みの散策、癒されますね。 これから全国の中世の街並み散策、楽しみです。 |
       |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第三百八十八弾:香川県お城・城下町巡り観光 2017年1月21-22日 四国の室町時代に讃岐守護に任じられた細川氏の支配下にあり、ただ、守護代として東部を治めた安富氏、西部を治めた香川氏など、同地ゆかりの勢力も力を蓄え、やがて応仁の乱を経て割拠の時代に入る香川県に足を運び、比較的マイナーなお城13か所を訪れました。 21日13:00車で出発、阪神高速、神戸淡路鳴門、高松自動車道経由して引田インター下車、お城巡り。 引田城:築城年代定かではない。 永正年間(1504年~1521年)頃に昼寝城主寒川元政の家臣四宮右近が城主であった。 元亀3年(1572年)寒川氏は阿波国の三好長治によって大内郡を奪われ、長治の家臣矢野駿河守が引田城主となった。 天正10年(1582年)中富川合戦で長宗我部氏に敗れ、虎丸城に籠城した十河存保を救援するため、秀吉は仙石権兵衛秀久を引田城に派遣して守らせた。 羽柴秀吉の四国征伐によって讃岐国は仙石秀久に与えられ引田城主となったが、九州征伐での戸次川合戦での失態により秀久は改易、替わった尾藤知宣も九州征伐の失態によって改易となっている。 生駒親正が讃岐国を与えられると引田城に入ったが讃岐国の東に偏りすぎていたため、聖通寺城に移り廃城となった。 虎丸城:築城年代は定かではない。 初期の城主は寒川氏で太田郡、寒川郡、小豆島を領し東讃に勢力を張った豪族である。 元亀3年(1572年)寒川元政の時代に阿波国の三好長治によって虎丸城は奪われ、寒川氏は昼寝城へ退き、虎丸城へは三好氏の家臣雨滝城主安富氏が入る。 天正10年(1582年)中富川合戦で長宗我部氏に敗れた十河存保は虎丸城へ逃れる。天正12年(1584年)十河城は長宗我部氏によって落城したが、虎丸城も奮闘するが天正12年(1584年)末頃に落城したと考えられている。 雨滝城:築城年代は定かではないが長禄年間(1457年~1460年)安富盛長によって築かれたと云われる。 安富氏は播磨国三ケ月郷を領していたが応安年間(1368年~1375年)頃に細川頼之に従って讃岐国にきた。 元亀3年(1572年)安富盛定の時、三好長治の家臣篠原弾正入道紫雲の女を娶り三好と誼を結んだ。 元亀3年(1572年)東讃に勢力のあった寒川氏は三好氏によって虎丸城を追われ、昼寝城に退くと、虎丸城には盛定が移り雨滝城には家臣六車城主六車宗湛が移った。 十河城:築城年代は定かではない。 十河氏は山田郡を拠点とした植田氏の支流の一つであり西讃の香川氏、東讃の安富氏の二大勢力には及ばなかったが、阿波の三好一族との関係が深まったことでその勢力が大きくなった。 十河景滋の子が早世したため三好長慶の弟が養子となり家督を継いだ。これが十河一存である。一存は子の義継を長慶の養子にして三好を継がせ、義賢の子存保に十河家を継がせるなど三好と十河のつながりをより深めた。 織田信長の勢力が三好に及ぶようになると、三好長治と存保はそれに対抗したが最終的には信長に降った。 長宗我部氏が四国平定の兵を進めていた時、存保は阿波国勝瑞城にあり長宗我部氏の攻撃により落城し存保は虎丸城へと退いた。十河城には三好隼人佐があり良く戦ったが最後は開城し備前へ逃れた。 羽柴秀吉による四国征伐の後、仙石秀久が讃岐へ入り、存保は二万石が与えられ再び十河城主となったが、九州征伐において戸次川合戦で討死した。 喜岡城:建武2年(1335年)高松頼重によって築かれた。 建武3年(1336年)細川定禅との合戦に破れ落城するがその後、高松氏の居城となる。 天正13年(1585年)城主高松頼邑は長宗我部に属していたが豊臣秀吉の四国平定軍約二万に攻められ将兵約200ことごとく討死して落城した。 現在喜岡寺が建てられている所が本丸跡と言われ、その近くには城址碑が建てられいる。 このあたりは周りの地形より一段高くなっておりそれがわずかに城のあった名残と言えるかも知れない。 屋島城:屋嶋城は源平古戦場としても知られる屋島に築かれていた。 長らくその存在が不明であったが、平成10年に地元の研究家によって南嶺の南西斜面部に石積が発見され、それ以降発掘調査などによって北水門、南水門、城門、土塁などが発見されている。城壁は総延長7kmに及ぶとされるが、大半は自然の断崖を利用したもので、それが途切れる谷間に城壁を築いていたようである。南の城門地区の石垣の復元工事が完成して公開されている。窪んでいる部分が城門で下部には暗渠がある。城門へはハシゴを使って登る事を想定しているようで、入ると左へ折れて登っていく構造であった。 18:00高松市内のホテル到着後繫華街を散策し食事を済ませて就寝。 22日7:00車で出発、お城巡り。 勝賀城:前回ここを訪れた時は登山口がわからず撤退したのだが今回は勝賀城主の居館である佐料城の所から登山口への案内表示があり農道をたどって行くと登山口の駐車場にたどり着けた。 遠望からもわかる通り山頂はかなり広く本丸の周囲をぐるりと取り巻いた土塁が残ってる。 遺構は良く残っているようだが残念なことに本丸以外は草が生い茂っている。 聖通寺城:築城年代は定かではないが応仁年間(1467年~1469年)奈良元安によって築かれた。 奈良氏は武蔵国大里郡奈良を本貫としていたが元政が貞治元年・正平17年(1362年)の高屋合戦における功により鵜足郡と那珂郡を領した。 天正10年(1582年)長宗我部氏の侵攻により城を捨て阿波国勝瑞城へと敗走したが中富川合戦で討死した。 羽柴秀吉による四国征伐の後、讃岐国を領した仙石秀政が入城したが戸次川合戦の敗戦により失脚した。 その後、尾藤知宣、生駒親正と替わり生駒氏の時に高松城を築き廃城となった。 多度津陣屋:文政10年(1827年)京極高賢によって築かれた。 多度津藩は元禄7年(1694年)丸亀藩主京極高豊の子高通に一万石を分与して多度津藩が成立したが、当初は丸亀城下に藩庁を置いていた。 四代高賢の時、幕府に陣屋建設を願い出て許され、完成したのが多度津陣屋である。 宅間城:城址は埋め立ての為に土を取られたようである。 周りは畑や住宅地となり登ってみたものの矢竹が密集して群生しているため踏み入ることができない。 天霧城:貞治年間(1362年~1368年)香川氏によって築城された。 香川氏は守護の細川氏の四天王の一人として西讃岐一帯を領していたが長宗我部元親の侵攻により開城する。 その後羽柴秀吉の四国平定に長宗我部氏が降伏すると天霧城も開城し以後廃城となる。 城山城:築城年代は定かではないが屋嶋城と同様、七世紀後半頃に築かれた朝鮮式山城と考えられている。 『日本書紀』によれば天智天皇6年(667年)に高安城、対馬国金田城とともに屋嶋城が築かれたことが記されているが、この城山城については記されていない。東麓には古代讃岐国の国府があったとされ、それに関係するものと考えられている。 由佐城:現在は香南町歴史民族郷土館として櫓を模した建物が建つ。 16:00帰路に向かう。 今回の旅行、四国の讃岐うどん等で有名な香川県に足を運び、香川県に点在する比較的マイナーなお城13か所を訪れ楽しみました。 香川県も観光地で有名、観光名所がたくさんあるため、比較的マイナーなお城は案内板も少なくわかりにくいとことが多く、今回も見つけるのが苦労しました。 山城の天霧城訪れてからの下りの狭い右折の曲がり角で右後方車輪の脱輪を避けるため大回りしたら左前の車輪が溝に落ち脱輪しました。急いでバックしましたが車輪が空回りし動かず、車から出て状態を把握し考え込んでいました。 周りは人はおらず、JAFを呼んでも山の奥、時間がかかる。 もう一度運転席に乗って再度チャレンジ、バックしても動かず、逆にハンドルを右に回して前進を試みたら脱輪した左前方タイヤが溝から道に乗り上げ難なく復帰でき帰れることができました。 下り坂のためバックは車の重みで力が入らず、前進では逆に車の重みで力が入り溝を乗り越えることができました。いい経験勉強になりました。 一人での自動車運転気を付けましょう。 |
              |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第三百八十七弾:鹿児島県お城・城下町巡り観光 2017年1月14-15日 九州の南端、大隅、薩摩、そして日向の一部で構成され、古くから海外との交易が盛んで、大隅の肝付氏、日向の伊東氏がいち早く合戦に鉄砲を取り入れ、守護の島津氏が同地を支配し、九州全土を席巻した鹿児島県に足を運び比較的マイナーなお城10か所を訪れました。 14日16:25伊丹空港出発 17:40鹿児島空港到達、レンタカーで鹿屋方面に向かう。 19:30鹿屋市内のホテル到着後繫華街を散策し食事を済ませて就寝。 15日7:30レンタカーで出発、お城巡り。 高山城:築城年代は定かではく諸説あるが、 長元9年(1036年)兼俊が大隅国肝属郡の弁済使となって肝付氏を名乗り居城として築いたと云われる。 南北朝時代には北朝方の島津氏に対して、日向国伊東氏・肥後国菊地氏とともに南朝方となって転戦した。 肝付兼久は明応3年(1494年)島津忠昌による高山城攻めを退け、永正3年(1506年)再び柳井谷に陣を置いて攻めてきた島津忠昌を退けた。 戦国時代になると肝付兼続は大隅国一円に勢力を広げ戦国大名となっていったが、良兼・兼亮の時代に島津氏に降伏、高山は安堵されたが他の領地は没収された。 天正8年(1581年)肝付氏は薩摩国阿多へ移封となり廃城となった。 志布志城:築城年代は定かではない。南北朝時代には楡井氏が領していたが、畠山氏と禰寝氏によって攻められ落城し、頼仲は弟頼重とともに胡麻ヶ崎城へと退いたが、弟頼重は討死し頼仲も自害して楡井氏は滅亡した。 楡井氏を滅ぼした畠山直顕は延文3年(1358年)日向国穆佐城にて肥後の菊地氏に敗れて敗走し衰退、志布志城は島津元久が領して新納実久が城主となった。 新納忠続の時、伊東氏の備えとして飫肥城へと移されたが伊東氏に飫肥城を奪われ、改めて志布志城主となる。七代新納忠勝の時には勢力を拡大しようとしていたが都城城主北郷忠相、串間城主島津忠朝の怒りをかって攻められ忠勝は降伏した。新納氏の所領は北郷氏と豊州島津氏で分領となった。その後永禄5年(1562年)頃に肝付兼続が所領としたが、肝付氏が島津氏に降伏すると志布志城は鎌田政近の所領となり、元和の一国一城令によって廃城となった。 恒吉城:築城年代は定かではない。 鎌倉時代には恒吉大膳亮の所領であったといわれる。応永年間(1394年~1428年)の城主は山田忠道、永享年間(1429年~1441年)には忠道の兄山田忠尚が城主であった。その後は一時島津忠親の所領となっていたが概ね肝付氏の所領として続き、天正4年(1576年)からは都城の北郷氏の所領となった。北郷氏はその後祁答院へ移り、かわって伊集院氏の所領となった。慶長4年(1599年)庄内の乱で蜂起した伊集院忠真は、恒吉城に一族の伊集院惣右衛門を城主として守らせた。島津方は島津図書頭忠長、志布志地頭の樺山久高、松山地頭柏原左近将監有国の三名が恒吉城を攻め、樺山久高の策によって三日間の攻防で落城した。 その後は寺山四郎左衛門久兼が地頭となったという。 富隈城:築城年代は定かではないが文禄年間初期に島津義久によって築かれた。 島津義久は文禄4年(1595年)家督を譲って富隈城に隠居した形をとって鹿児島から移り、慶長9年(1604年)舞鶴城へ移るまで在城した。 加治木城:築城年代は定かではないが平安時代に大蔵氏によって築かれたと云われる。 大蔵氏は東漢霊帝の血を引く帰化人とされる。 数代目の当主大蔵良長のとき継嗣なく、流罪となってこの地へ流れてきた関白藤原頼忠の三男経平に娘を娶せて大蔵家を継がせ、経平は加治木氏と名乗ってこの地に住んだと云う。加治木氏は以後有力国人としてこの地を治めていたが、明応4年(1495年)加治木久平は帖佐へ侵攻し平山城の南城を占領したが、高尾城に籠った川上忠直に防がれ、加治木侵攻に怒った島津宗忠昌の大軍に攻められ加治木城に帰還した。翌明応5年(1496年)島津忠昌が加治木城に押し寄せ久平は敗れて謝罪し許されたが薩摩国阿多へ移され加治木氏は没落した。 加治木氏の後は伊地知重貞が地頭となったが後に重貞も島津氏に叛いた為、大永7年(1527年)島津忠良が加治木城に攻め寄せ伊地知重貞・重兼父子は城中で自刃して果て、肝付兼演に加治木城は与えられた。 天文23年(1554年)蒲生範清は渋谷一族とともに島津氏に反抗し加治木城に攻め寄せた。島津貴久は加治木城を救援する為、岩剱城の祁答院良重を攻め、加治木城を取り囲んでいた蒲生軍が岩剱城を取り囲んでいた島津氏を討ちに戻ってきた所を激戦の末に打ち破り加治木城を救った。 文禄4年(1595年)加治木・日当山・溝辺のうち一万石が豊臣家の蔵入地となり、肝付兼三は喜入に移封となった。しかし、文禄・慶長の役での島津氏の功によって加治木は島津氏の所領に戻り、島津義弘が平松城より加治木へ移ったが加治木館を新たに築城した為、加治木城は廃城となった。 長尾城:築城年代は定かではないが承久年間(1219年~1222年)頃に横川時信によって築かれたと云われる。 以後河内守種氏まで六代続いた。 永禄年間(1558年~1570年)頃には北原伊勢介が領していたが、永禄5年(1562年)北原氏に内乱があり、一族の多くが島津氏に属した為、伊勢介と子の新助は日向国飫肥の伊東氏に内応して横川城に籠った。島津氏は島津義弘・歳久兄弟が横川城を攻め、北原父子は城内で自刃して果てたと云う。 その後は菱刈重猛の所領となり、一族の菱刈中務が城主となったが、永禄10年(1567年)重猛の弟隆秋が島津氏に叛くと菱刈中務もそれに加わり、島津氏によって馬越城が落城すると横川城を棄てて大口城へ退いたという。 栗野城:天正15年(1587年)島津氏によって築かれたと云われる。天正18年(1590年)島津義弘は日向国飯野城より移って居城とした。 義弘は朝鮮の役にはここから出陣し、帰国後文禄4年(1595年)に帖佐館を築いて移り、城代として川上三河守が在城したという。 出水城:築城年代は定かではないが建久年間(1190年~1199年)に和泉兼保によって築かれた。 和泉氏は応永24年(1419年)川辺松野城の合戦で島津久豊方に組みしたが戦死し後継なく断絶した。 享徳2年(1453年)島津忠国の弟用久が薩州島津家を興しここを本拠とした。 平佐城:築城年代は定かではないが鎌倉時代末期に薩摩氏によって築かれたと云われる。 15世紀末には入来院氏の所領で12代重朝が一時居城としていた。 元亀元年(1570年)入来院、東郷氏が島津氏に降ると島津義久は直轄地として地頭を置き、天正8年(1580年)頃は桂忠あき(日方)が地頭であった。 清色城:築城年代は定かではないが入来院氏によって築かれた。 入来院氏は鎌倉時代中期に相模国渋谷庄司の渋谷光重が地頭職となり、その子定心が入来院地頭となって入来院を名乗ったことに始まる。 永禄年間(1558年~1570年)入来院氏は島津氏に降り以後島津氏に従った。文禄4年(1595年)入来院重時は代々所領とした入来院の地を離れ、大隅国湯尾へ転封となった。慶長5年(1600年)入来院重時は島津義弘に従って関ヶ原合戦に参加し討死した。重時には嫡男がいなかったことから島津義虎の子で頴娃家の養子となっていた久秀が重国(後に重高)と名を改め入来院家の家督を継いでいる。 江戸時代に入り、慶長18年(1613年)入来院重国は湯尾から旧領である入来院に転封となり、以後入来院地頭として入来麓に仮屋を構え代々続いた。 16:00終了、鹿児島空港に向かう。 17:00鹿児島空港到達。 18:10鹿児島空港出発。 19:20伊丹空港到達。 今回の旅行、九州南端の鹿児島県に足を運び比較的マイナーなお城10か所を訪れ楽しみました。 広範囲に点在するお城、道も広く、信号も少なく、渋滞もなく、スムーズに訪れることができました。 鹿屋市内の繁華街で夕食を済ませましたが、居酒屋、焼き鳥屋、どこもいっぱいで7件目でやっと席に着くことができました。食事のお店を苦労するは初めてで、人口はそんなに多くなく、観光名所も多くなく、観光客も少ないのに何故こんなに混んでいたのか、お店が少ないのでしょうね。 |
             |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第三百八十五弾:九州八十八箇所&佐賀県お城巡り観光 2016年12月10-11日 九州の小規模な国人に過ぎなかった龍造寺氏が、龍造寺家兼の時代に飛躍し、肥前で権力をふるう戦国大名となる、一時は島津氏、大友氏と並び九州の支配を分け合うが、龍造寺隆信の死後、配下の鍋島氏に実権が移る佐賀県に足を運び佐賀県に点在する九州八十八箇所霊場の12か所、比較的マイナーなお城8か所を訪れました。 10日17:30伊丹空港出発 18:50長崎空港到達、レンタカーで大城方面に向かう。 19:50大城市内のホテル到着後周辺を散策し食事を済ませて就寝。 11日7:30レンタカーで霊場・お城巡り。 獅子城:築城年代は定かではないが治承年間から文治年間(1177年~1190年)頃に源披によって築かれたと云われる。 源披は松浦党の祖源久の孫にあたり、この一帯を領して築城したが、子の源持の時代に平戸へ移った為、廃城となったという。その後、戦国時代に日在城主鶴田兵部大輔直(ただす)の弟、鶴田兵庫介前(すすむ)によって再築城された。 金剛寺:寺伝によれば、当山ご本尊は、上松浦の要として当山より南に半里の地に在りし獅子ヶ城に代々守り本尊として 伝えられていた尊像で、別名を厄除け千躰大師と称します。 城主鶴田氏衰退後、永年岩間に端座せしが、明治三十年三月。 縁あって当地に大師堂を建立し安置し奉るが当山の始めなり。 なお、厄除け千躰大師の名の由来は、一切衆生の願いの数だけ、その尊いおすがたを千にも万にも千々に分かち、 人々の災厄をしりぞけ、衆生を救わんとのお誓いによるものです。 岸岳城:築城年代は定かではないが、波多氏によって築かれたと云われる。 波多氏の居城としては八幡神社の裏山に波多城がある。 波多氏は、源久の次男特を祖とする松浦党の一族で波多氏を名乗った。 16代波多盛が嫡子なく没すると、後室の妹の子を17代波多親として迎えたが、これに不満を抱いた重臣日高氏は岸岳城を乗っ取った。後室は龍造寺氏に岸岳城の奪還を依頼、日高氏は松浦氏に援軍を依頼したが、松浦氏の到着前に龍造寺氏が攻め寄せ、日高氏は岸岩城を破棄したという。 波多氏はその後豊臣秀吉による九州征伐に参陣せず、秀吉の怒りに触れたが減封のみで存続、しかし文禄の役からの帰国途中で改易となり常陸国筑波山麓へ配流となった。 鶴林寺:九州の西北端に位置し、唐津・玄海灘を臨む、古くから大陸と日本を結ぶ海洋の要港であった。近くには、虹の松原の景勝があり、唐津くんちも全国に知られている町である。 ご本尊は薬師如来・子安弘法大師を安置し、安産、子育ての加持祈祷の寺として信者様に知られ、境内は不動明王、十三仏を配置し、地元では子安さんとして知られている寺であり、松井寳堂師が開基、ひたすら弘法大師の教えを実践。 吉原山の山号は、○信者に結縁している。この土地は吉原氏の所有で先祖の地を寺院に提供その功徳を称して山号にした。 大聖寺:唐津城、唐津焼、虹の松原で有名な唐津市。その中心部、駅より徒歩5分ほどの場合に大聖院は位置します。周りは寺町の名にふさわしく寺院が立ち並びます。もともとこの寺は秀吉の時代、北波多村というところにあり、岸岳城主波多三河守の祈願寺として名を大法寺と称した。岸岳城落城の後火災に会い、その後慶安元年に大僧都興玄大和尚により唐津に移転され名を大聖院と改号した。 山門を入れれば正面に入母屋造りの本堂がある。本尊は不動明王様で参拝の方々の願いを一身に受け止めてくださいます。また一緒にお祀りされているお大師様は、もともと讃岐の金比羅様の境内にありその後、明治初年に四国善通寺にお移りされ明治7年大聖院に御遷座なされました。 開運厄除け・道中安全に特にご利益ありといわれております。また、本堂には開運福徳大黒天、唐津神社本地佛十一面観世音菩薩(8月17日のみご開帳)・銅造如来坐像も安置されています。山門より右手屋上に大きな修行大師像がお祀りされております。昭和7年の御遠忌に建造されましたが戦国中に没収、昭和26年に再建されました。 徳川家康陣:徳川家康は文禄の役の時、武蔵国江戸城主二百四十万石の大名である。家康は名護屋で在陣しているが渡海はしていない。 徳川家康の陣は名護屋浦を挟んで東西にあり、こちらが西が本陣、東が別陣である。 その規模は西側の方が小さい。 住吉城:築城年代は定かではないが後藤氏によって築かれた。 後藤氏は塚崎城を居城としていたが、天正14年(1586年)20代家信の時に住吉城を居城とした。 しかし、慶長4年(1599年)火災により焼失したことで再び塚崎城へ居城を移し廃城となった。 宝光院:世界に名声高い有田焼の地に有って周りは県立公園の黒髪山と龍門峡を背にし、流れる水は百選の1つで、初夏にはホタルが舞うという背景に小さな寺が有ります。 御本尊は十一面観世音(秘仏)で、参拝者の願いや苦しみを取り除いて頂いています。 開山は修験者達がお参りされる人の願い事や、五穀豊穣を祈願したと言い伝えが有って、現在も引き継いで御本尊に祈念しております。境内には水子堂が建っていますが、各方面より多数の人達が供養に訪れています。各地でも、水子、子育て丈の(供養・祈願)お堂が有るのは大変珍しいと思います。 又、本堂の側には御大師様が安置されていて厄除大師としてお参りされています。寺全体が明るく、心が清らかになる寺です。どうぞお誘いあわせでお参りください。 西光密寺:古来より山岳信仰の霊山として名高く、 佐賀県立自然公園でもある黒髪山のほぼ頂上にあります。 弘法大師さまが入唐求法の途上で遣唐使船が平戸係留の間に、 無事の渡航を祈念して黒髪山にご登嶺され、 無事にご帰朝の後にはお礼参りに再びご登嶺あり、 不動明王を爪彫りされ安置されたのが寺の始まりと伝えられています。 (この不動明王は今は佐世保市の黒髪山大智院にお祭りされています) 現在の西光密寺のご本尊は、 黒髪三所権現の本地仏といわれる、薬師如来、 阿弥陀如来、千手観音の三体の掛け仏さま(秘仏)です。 多数ある山中の石造物等から、 往時の信仰の深さが偲ばれます。 無動院:室町時代創建の当山は、約600年もの間、黒髪山修験道とともに、繁栄してまいりました。境内には重要文化財指定の六地蔵尊石塔、近隣の人々に篤く信仰を受ける眼病平癒の黒髪眼不動尊、子供の安全発育を願う子育地蔵尊等心の安らぎが得られる静かな佇まいのお寺です。心を癒しにおいでください。 また、九州三十六不動霊場第二十六番札所としての信仰も受けております。 土曜日は住職による寺子屋書道教室も開講され、小学生の賑やかな声が聞こえ京都嵯峨書院九州支部にもなっています。 東光寺:佐賀県西部に位置する三間坂は長崎県境を塞ぐ神六山の裾野に拓けた盆地で、信仰の中心は黒髪山に縁起している。 東光寺は国道35号線から南に入ったところに在り、参道を分けて左側に幼稚園が営まれている。寺史には弘法大師が巡錫の砌り黒髪山に西光密寺(大智院)を創建されたとき、その末寺として建立されたと伝えられているが、阿忍僧正をもって中興開基としている。阿忍僧正は天文十六年(1547)、東光寺を再建して本尊に薬師如来を安置した。脇持は阿弥陀如来と聖観音を合祀し、後の明暦二年(1656)城主茂和の命により黒髪大権現を勧請して鎮守神と崇め、神仏合体の信仰を宣揚した。 脇持の阿弥陀如来は安阿弥の作と伝え、厨子に願文が書されている。それによると『曰奉造厨子一字信心。大檀那後藤藤原純明公。権少僧都阿忍。天文十六年卯月八日 東光坊』とある。その後、領主(後藤家)の崇信は篤く、元亀三年(1573)貴明は仏殿を造営し、寛文七年(1667)茂紀は仏像の修復に寄与するなど、代々料米を下附して外護につとめられた。しかし、明治三年の神仏分離令によって鎮守社は近くに独立移転し、東光寺も寺運の衰退気味になるも、法灯は継承され先代隆堅和尚により現在のように伽藍が整備された。 寺宝として現存する兼好法師撰、小倉山京極定家筆「真髪山紀事」の古文書は、弘法大師と黒髪山との関係を知る上での貴重な史料である。 身丈二十センチほどの観音像(制作年代不詳)に異国の信仰が偲ばれる。右手の結んだ印が親指と中指で十字の形をしており、隠れキリシタン観音と呼んでいる。美術品としてみる仏像の価値観より、祈りという信仰の心を覗くことができる。また、白く美しい正観音(ボーンチャイナ)も信仰を集めている。 塚崎城:築城年代は定かではないが元永年間(1180年~1120年)に後藤氏によって築かれたと云われる。 後藤氏は藤原北家利仁流で塚崎荘の地頭となり下向したと云われる。 天正14年(1586年)20代家信の時に住吉城へ居城を移したが慶長4年(1599年)火災により焼失したことで再び塚崎城を修復して居城を移した。 光明寺:武雄温泉は古くからの湯治場として多くの人々の癒しの場として親しまれて参りました。光明寺は「南無薬師諸病疾除の瑠璃の寺肥前湯の町尽きぬことなし」と詠歌に歌われている様に、温泉の守護として土地の人々に見守られながら今日に至っております。 また明治26年より武雄新四国発願所としてお彼岸等には、市内を中心に420カ所以上のお堂や寺院などを住職が先頭に立ち檀信徒の方々と巡拝し、広く信仰を集めております。また、境内や参道には多くの石仏が手作りの赤い胸当てを掛けてお参りの方々を暖かく迎えておられます。 高野寺:大同元年(西暦八〇六年)弘法大師さまが中国、当時の唐の国の都長安にて密教を学ばれ、九州博多に帰朝され九州各地を行脚しておられた折、この土地が紀州の高野山に似ておることからこの地を肥前の高野山と定められ、草の庵を結ばれたのがこの寺の始まりと伝えられる。その折、現在の穀倉地帯の佐賀平野は原野でこれを開墾するには、人口を増やさねばと、一体の観音さまを刻み、この観音さまに祈ると子供が授かり安産で元気に育つと申され現在も子宝観音として、子授け、安産、子育ての祈願が絶えない。 また、佐賀多久藩の祈祷寺として代々帰依を受け、残される古文書には、「いかなる咎人も高野寺の境内に走りそうらえばその罪を許される」と云う近世の駆け込み寺の役割もしていた罪障消滅の道場である。境内には平地に珍しい高山植物のシャクナゲが樹齢三百年以上を含めて千本以上あり、毎年四月初旬より開花し大勢の花見の客でにぎあう。平成十八年(西暦二千六年)、開創千二百年を記念として、焼失後百十八年ぶりに、新しく本堂、会館など建立し境内を整備し弘法大師の教えを今に伝えておる。 須古城:築城年代は定かではいが天文年間(1532年~1555年)に平井氏によって築かれたと云われる。平井氏は少弐氏の一族で少弐資頼の二男盛氏の子経氏が平井氏を称したのが始まりとされる。その後、千葉氏の家臣となり有馬氏に備えてこの地へ配されたという。 有馬氏に備えて杵島の地にいた平井氏は、大永5年(1525年)平井経則は有馬氏に寝返り、以後有馬氏に従って千葉氏と戦った。天文年間(1532年~1555年)に須古城を築いて居城とし、支城として男島城と杵島城を築き弟に守られた。 平井経治は永禄6年(1563年)から天正2年(1574年)までの間に、龍造寺隆信によって四度攻められ、天正2年(1574年)ついに落城し平井氏は滅亡した。 その後、須古城は龍造寺氏の属城となり、天正6年(1578年)(一説に天正9年)に龍造寺隆信が隠居すると須古城へ移り居城とした。しかし、天正12年(1584年)龍造寺隆信は有馬・島津連合軍との戦いで討死し、須古城は隆信の弟龍造寺信周の居城となり、須古鍋島家の祖となった。 潮見城:潮見城跡は橘氏が長嶋の庄の総地頭としてこの地に、潮見山の要害を利用して築城 鹿島城:文化4年(1807年)鍋島直彜(なおのり)によって築かれた。 鹿島藩ははじめ常広城にあったが、度重なる水害の為、幕府の許可を得て高津原に築城した。 誕生院:誕生院は、真言宗の中興の祖であり、新義真言宗の開祖である興教大師覚鑁聖人の誕生の地に建てられた祈願のお寺です。境内5200坪の中には、金堂、本堂、鐘楼堂などが建ち、桜、藤、つつじ、しゃくなげ、もくせいなど四季折々の花が咲き乱れる香煙縷々として絶えることなく今日に至ります。御本尊は、皆様の身代りになって下さる錐鑽身代不動明王さまです。 年間通じて、覚鑁聖人のご誕生になられた聖地として安産祈願や誕生祈願、又、涙を流す慈悲深き水子地蔵さまには多くの方々に参拝戴いております。皆様も、是非、ご気軽にご参拝戴き、私生活や仕事を忘れて、諸仏諸菩薩のご利益を受け、ひとときのやすらぎを求めてはいかがでしょうか。 蓮厳院: 祐徳稲荷神社の膝元。平安時代から続く古刹で、本堂と庫裡は藁葺き屋根。庫裡は県内では少なくなったクド造りとなっています。 一見寺とは思えないたたずまいです。 ご本尊阿弥陀如来2体と薬師如来1体は国の重要文化財で全国でも数少ない定朝様式の仏様として知られています。 平安時代から今日まで、人々は手を合わせ諸願成就と、ご先祖様の菩提を祈る寺でございます。 又、当山奥之院岩屋山興法寺は真儀真言宗の祖、覚鑁上人(興教大師)幼少の折の修行聖地であり、当山は上人13歳で仏門に入る時本山二利寺寛助大僧正の弟子になられた勝縁の寺としても知られています。 平安仏に手を合わせ、心身の平安をお祈り下さい。お参りをお 大定院:当山は慶長年間に、藩主 鍋島直澄公が開基となり、権大僧都 阿金和尚の開山と伝えられている。 永代 米穀数十石を毎年修繕費として下附され、鍋島藩の祈願寺として法燈隆昌をなす藩の厚い庇護を受けていたが、 明治4年の廃藩の際に寺領没収され、その後の資助が絶え堂宇荒廃する。 明治12年、嬉野町より当地に移転し、鍋島藩ゆかりの吉田焼陶業の繁栄と領民の福祉、また、鍋島直澄公の霊牌を安置し祈願所とされている。 16:30終了。 17:30長崎空港到達。 19:20長崎空港出発。 20:35伊丹空港到達。 今回の旅行、九州佐賀県に足を運び、佐賀県に点在する九州八十八箇所霊場12か所、比較的マイナーなお城8か所を訪れ楽しみました。 観光名所の少ない佐賀県、マイナーなお城にもかかわらず、整備され案内板もあり今回はすんなりと見つけることができました。 霊場の立派な寺院が多く満足いたしました。 今回で九州八十八箇所霊場は制覇いたしました。 |
               |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第三百八十四弾:九州八十八箇所&長崎県お城巡り観光 2016年12月3-4日 九州北西部に位置し、対馬や五島列島など島々が多く、様々な勢力があり、強力な水軍を擁する松浦党が発展し、大村氏も長く存在感を示したが、戦国時代が到来すると勢力地図は一新、秀吉の直轄地となる長崎県に足を運び、長崎に点在する九州八十八箇所霊場2か所、比較的マイナーなお城11か所を訪れました。 3日17:30伊丹空港出発 18:40長崎空港到達、レンタカーで佐世保方面に向かう。 20:10佐世保市内のホテル到着後周辺を散策し食事を済ませて就寝。 4日7:30レンタカーで出発、霊場、お城巡り。 最教寺奥の院:最教寺は、大同元年(806)弘法大師が唐から帰朝した時、初めて護摩を焚いたところといわれる。現在、奥の院には大師の護摩石と坐禅石があり、住時をしのぶことができる。慶長十二年(1607)平戸藩主松浦鎮信が高野山最教寺を復興、真言教学の学問所である談義所を合併し、大和国長谷寺の空盛上人を中興開山として招いた。 また、その二年後、奥の院を建立している。西の高野山と呼ばれるだけあって、広大な境内である。駐車場からは、脇より境内に入ることになるが、本来の参道は楠が並ぶすばらしい石段が続く。切妻造の山門を入った正面が入母屋造の本堂で、安永三年(1774)の建築である。本尊は虚空蔵菩薩を拝することができる。 開元寺:弘法大師空海は、密教の奥義を学ぶため、唐(中国)に渡ることを目指した。そして、延暦二十三年(804)三十一歳の時、留学生として第十六回遣唐使船で難波を出航。その時の大使は藤原葛野麻呂。伝教大師最澄や義心、橘逸勢なども、同じく入唐して いる。瀬戸内の各所に立ち寄りながら九州に至り、最後に日本を離れたのが、田ノ浦である。寺号の由来は、嵐など苦労の末、弘法大師が十二月の終わりに唐に上陸後、一ヵ月の間とどまった福州の寺院が開元寺で、近年にその寺号を称したものである。入唐山開元寺 というが、お寺であるわけではなく、顕彰碑と法要殿があり、顕彰碑には『弘法大師唐渡解纜之地』と刻まれている。石碑には、石造の厨子のなかに、弘法大師の石仏が安置されている。また、法要殿においては五月に『田ノ浦法要』が勤修される。弘法大師の時代と同じ風景を見、大師の心の内を垣間見ることのできる霊場である。 日の岳城:中世以来、平戸松浦氏の居城は御館をはじめとしていくつかの変遷をみるが、26代(初代藩主)鎮信(法印)が、それまでの白狐山城(勝尾岳城)を棄城して、現在平戸城のある亀岡に築城を着工するのは、慶応4年(1599)のことで松浦氏が戦国大名を脱して近世大名へと転換をはかる時期と符合する。ところが城は完成を待たずに鎮信みずからの手で焼き払われてしまう。オランダ商館設置に象徴される平戸城下の発展と領内のキリシタンの存在に向けられた幕府の猜疑と不信をとくことが理由であったと考えられるが、はっきりした理由は不明である。 以後、藩主は約100年間城を持たず御館に居住していたが、元禄16年(1703)、5代藩主棟(たかし)の再築願いが許可され、翌(宝永元)年着工、亨栄3年(1718),6代藩主篤信(あつのぶ)の代に完成する。焼却以前の平戸城を日の岳城とよび再築後は亀岡城、玄武城、朝日岳城の名でよばれた。現在の天守閣は昭和37年(1962)の築造である。 梶谷城:築城年代は諸説あるが松浦氏の始祖源久(みなもと ひさし)によって築城された。 直谷城:築城年代は定かではない。 城主は志佐氏で、松浦清の次男貞を初代としており、松浦氏の勢力拡大とともに志佐一帯に勢力を伸ばしここを居城とした。 八代志佐義の時代には壱岐の湯岳を領有して朝鮮貿易も行っている。 明応年間(1492年~1501年)志佐純勝のとき、大村氏と龍造寺氏の連合軍に攻められ落城、五島へ逃れたことにより直谷城は空城となった。 その後の平戸・田平合戦によって里城の峰氏は田平一帯を松浦氏に譲り直谷城に入り志佐の名跡を継いで志佐純元と名乗った。 寛永2年(1625年)志佐純昌のとき御厨に移封となり直谷城は廃城となった。 三城城:永録7年(1564年)大村純忠によって築かれたと云われる。 三城をめぐっては三城七騎籠(さんじょうななきごもり)が有名で、これは元亀3年(1572年)塚崎城主後藤貴明・平戸城主松浦隆信・高城城主西郷純尭の連合軍に囲まれたおり、城主大村純忠と主たる武将七騎(大村純盛,朝長純盛,朝長純基,今道純近,宮原純房,藤崎純久,渡辺純綱)で籠城し守り通した戦いである。 三城は慶長4年(1599年)に喜前が玖島城を築城し拠点を移すまでの本拠地であった。 玖島城:慶長4年(1599年)大村喜前によって築かれた。 大村氏は藤原純友の後裔を称し、純友の孫直澄が肥前国藤津郡・彼杵郡・高来郡の三郡を与えられ、彼杵郡大村郷に住んで大村氏を称したことに始まるとされる。 喜前の時、玖島城を築き三城より居城を移した。 大村純前は有馬晴純の次男純忠を養子に迎え家督を継がせた。これが初のキリシタン大名として知られる大村純忠である。純忠は永禄6年(1563年)洗礼を受けてバルトロメウの洗礼名を与えられた。天正15年(1587年)豊臣秀吉の九州征伐に従い所領を安堵され、純忠の後に家督を継いだ大村喜前は、関ヶ原合戦で東軍について小西行長の宇土城を攻め、二万八千石弱の所領を安堵された。 大村氏は家臣団を再編する機会がないまま大名となったため、藩主の経済力が極めて低く、これを解決するため「御一門払い」と呼ばれる家臣団の整理を断行し、庶家一門十五家の所領八千石余を没収し、領内の総検地を行った。 俵石城:築城年代は定かではないが室町時代に深堀氏によって築かれたと云われる。 深堀氏は相模国三浦荘発祥の三浦氏の一族で建長7年(1255年)八浦荘地頭職を得て能仲が下向して深堀氏を名乗った事に始まる。 鎌倉時代以降一貫してこの地を治め、江戸時代には佐賀藩鍋島氏の家老として深堀陣屋を築いている。 諫早城:築城年代は定かではないが文明6年(1474年)頃に西郷尚善によって築かれたと云われる。 西郷氏は尚善の時に伊佐早次郎入道を討って、宇木城から諫早へ進出して船越城に入り、高城を築いてこれに移ったという。 天正15年(1587年)豊臣秀吉の九州征伐に参陣しなかった西郷氏は所領を没収され、替わって龍造寺家晴が諫早に入部し一万石余を領した。家晴の子直孝の時、諫早氏を名乗り諫早家は独立した大名であったが、直孝が病身で江戸でのご奉公ができないとの理由で大名を破棄し佐賀藩の家老となった。諫早氏は高城城を居城として維持していたが、五代茂門の時、財政難によって城が維持できなくなり、東麓に諫早陣屋を構えて居城とした。 鶴亀城:築城年代は定かではない。神代氏代々の居城であったと考えられるが、神代氏の出自は詳らかではない。筑後や肥前にも神代(くましろ)氏がおり、龍造寺隆信と争った神代勝利などが著名であるが、この神代(こうじろ)氏は別系統である。 南北朝時代の神代式部貴益と戦国時代の神代兵部大輔貴茂が知られる。貴茂ははじめ日野江の有馬氏に属していたが、龍造寺隆信の勢力が及ぶとそれに従い、天正5年(1577年)には龍造寺軍が神代に着船すると神代貴茂は龍造寺隆信を饗応した。 天正12年(1584年)龍造寺隆信が有馬・島津連合軍と沖田畷で戦い討死すると、龍造寺方となっていた島原の豪族は有馬方へと寝返る中、神代貴茂は龍造寺方として踏みとどまり、有馬氏によって攻められた。しかし神代城は難攻不落であったため攻め落とされることはなかった。貴茂は有馬氏と和議を結ぶべく多比良城に招かれたが、その帰路謀殺されてしまった。当主を失った神代城も落城し神代氏は滅亡した。 深江城:応永年間に鎌倉幕府の引付奉行安富奉嗣が深江の地頭職となって以来、この地を領した。 天正5年、佐賀村中城主龍造寺隆信が高来郡の征討を企て、日之江城主有馬鎮貴と対決した際には、安富純治・純泰父子は有馬勢の主力として戦っている。 天正10年、有馬鎮貴が島津氏と手を組み、再度龍造寺隆信と戦った際には、龍造寺方となり深江城に籠城して戦っている。 その後、龍造寺隆信が沖田畷の合戦で敗死したため、安富純泰は佐賀に移り深江氏を称した。 原城:明応5年(1496年)有馬貴純によって築かれたと云われる。 日野江城を居城とした有馬氏八代有馬貴純によって支城として築かれたのが始まりと云われる。 慶長4年(1599年)有馬晴信は日野江城よりも住みやすくより堅固な城を築いているとイエズス会宣教使の報告書に記されており、これが原城と考えられている。慶長9年(1604年)にはほぼ完成し、三層の櫓や家臣の屋敷、教会も建設された。 慶長19年(1614年)有馬直純のとき日向国延岡に五万三千石で転封となり、元和2年(1616年)松倉重政が大和国五條より四万三千石で日野江に入封した。 松倉重政は新たに島原城を築いたため、原城の石垣や建物を島原城へ移し、原城は元和の一国一城令によって廃城となった。 寛永14年(1637年)島原の乱が勃発し、一揆側の総大将として天草四郎が農民二万数千とともに籠城する。天草四郎は小西行長の家臣益田甚兵衛好次の子と云われる。 これに対して幕府は板倉重昌を派遣し九州の諸大名を率いて原城を包囲した。幕府の討伐軍は幾度となく原城に攻め寄せたが、籠城していた一揆軍は城を固く守ってこれを寄せ付けなかった。一揆を鎮圧出来ない幕府は老中松平信綱を派遣して事態の収拾を図ろうとしたが、この知らせに焦った板倉重昌は原城に総攻撃を命じ、突撃して討死してしまった。老中松平信綱は十数万もの軍勢で原城を包囲すると兵糧攻めを行い、兵糧が尽きたころに総攻撃を仕掛け原城は落城、大将天草四郎時貞も討ち取られた。 この一揆の責任を問われ島原藩主松倉勝家は改易ののちに斬首刑となり、大名として唯一切腹ではなく斬首という厳しい処分が科せられた。 日野江城:建保年間(1213年~1218年)有馬経澄によって築かれたと云われる。 有馬氏の祖は藤原純友あるいは平直澄とも云われるが詳らかではなく、有間庄の開発領主で始め有間氏を称し、後に有馬と改めたと考えられている。 有馬氏が最盛期を迎えたのは天文年間(1532年~1555年)頃で有馬晴純の時である。 晴純は始め賢純と名乗っていたが、将軍足利義晴より晴の字を賜り晴純と名乗った。 島原半島から肥前東部を制しており、天正年間(1573年~1592年)に龍造寺隆信が台頭してくるまでは、肥前で最大の勢力であった。 晴純のあと家督を継いだ義貞は、永禄6年(1563年)百合野の戦いで龍造寺隆信に大敗を喫し、以後衰退していく。義貞の家督を継いだ義純は家督相続わずか一年で急逝したため、義純の弟鎮純が家督を継いだ。この鎮純が後にキリシタン大名となった有馬晴信である。 天正5年(1577年)佐嘉の龍造寺隆信の軍勢が島原半島を侵攻すると、有馬氏もこれに対抗できず降った。しかし、天正10年(1582年)晴信は龍造寺を離反して深堀城を攻め、天正12年(1584年)には島津氏の支援を受けて沖田畷の合戦で龍造寺軍を敗り、龍造寺隆信は討ち死にした。天正15年(1587年)豊臣秀吉による九州征伐で有馬氏は秀吉に従い所領を安堵された。 江戸時代に入り日野江藩四万石の大名となった有馬晴信は、慶長17年(1612年)岡本大八事によって所領没収の上甲斐国都留軍に配流となった。晴信の嫡男有馬直純は幼少の頃から家康の近習となって家康の養女国姫を娶っていたことなどから、父晴信の連座を免れ、家督相続のうえ日野江藩四万石を継承した。その後、幕府に転封を願い出て慶長19年(1614年)日向国縣五万三千石で加増転封となった。 有馬氏転封後、しばらく天領であったが、元和2年(1616年)大和国五條より松倉重政が四万石で入封した。重政は当初日野江城を居城としたが、島原城を築いて居城としたため廃城となった。 18:00長崎空港到達。 19:20長崎空港出発 20:35伊丹空港到達。 今回の旅行、九州北西部に位置する長崎県に足を運び、長崎県に点在する九州八十八箇所霊場2か所と比較的マイナーなお城11か所を訪れ楽しみました。 平戸から島原まで広範囲の霊場お城巡りでしたが、道も広く、車も少なく、スムーズに訪れることができました。 |
            |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第三百八十三弾:兵庫県お城巡り観光 2016年11月26-27日 摂津、但馬、丹波、播磨、淡路と、広大なエリアに多数の国を擁し、山名氏と赤松氏が勢力を誇っていたが、羽柴秀吉の前に屈し、国宝で世界遺産の姫路城は、城郭史において極めて重要な存在である兵庫県に足を運び、比較的マイナーなお城9か所を訪れました。 26日17:00車で出発、阪神中国山陽自動車道経由して赤穂インター下車。 19:30赤穂駅付近のホテル到着後周辺を散策し食事を済ませて就寝。 27日7:30車で出発。お城巡り。 白旗城:築城年代は定かではないが元弘3年(1333年)頃に赤松円心則村によって築かれたと云われる。 建武2年(1335年)新田義貞が大軍を率いて白旗城を包囲したが、50日あまりの籠城を耐え抜き落城しなかった。しかし、嘉吉元年(1441年)の嘉吉の乱では山名軍によって落城、赤松氏は城山城で一時滅亡した。 上月城:築城年代は定かではないが、鎌倉時代末期に上月景盛が大平山に上月城を築いたのが始まりとされる。上月氏は赤松氏の庶流で四代続いたが、嘉吉の乱によって滅亡した。天正5年(1577年)織田信長の部将羽柴秀吉が福原城を攻略して上月城を攻めた。上月城は赤松政範が籠もり宇喜多直家が救援に駆けつけたが、高倉山に本陣を構えていた羽柴秀吉によって上月城は落城し、政範は自刃して果てた。尼子勝久を担いで尼子家再興を願う山中鹿之介は織田信長に与し、この上月城を守ったが、天正6年(1578年)毛利の大軍によって落城し、尼子勝久は自刃、山中鹿之介は捕らえられて毛利の本陣へ護送される途中に討たれた。 利神城:貞和5年・正平4年(1349年)別所敦範によって築かれたのが始まりである。 別所氏は嘉吉元年(1441年)嘉吉の乱により赤松氏とともに滅亡したが応仁元年(1467年)別所治定が再興して城主となった。 しかし、天正6年(1578年)上月城の山中鹿之助によって攻められ落城した。 関ヶ原合戦後は播磨国を領した池田輝政の甥にあたる池田由之が城主となり佐用三万石を領した。 完成した城の威容を見た輝政は慶長12年(1607年)三層の天守の破却を命じ由之を退去させ長政を城主としたが期間は3年程であった。 佐用郡は続いて輝政の妻である良正院尼公(徳川家康の女)に化粧領として与えられ4年後には実子である輝興に城主を譲った。 寛永8年(1631年)輝興は赤穂に転封となり廃城となった。 城は山頂に"へ"の字のような形で石垣で固めた曲輪を配しているが、中央に三層の天守をあげた本丸を配し南に二之丸と馬場、西に三の丸を配している。 一般的には南から尾根伝いに登ることになるが尾根まで登るとすぐに幅2m程の道の両側を石垣で固め石段のある番所跡のような所がある。そこから尾根を進むと石垣で固めた空堀に木橋が掛けられ続いて天王社が祭られた横穴が現れる。 それを越えると三の丸まで何もないが三の丸手前の山上にたどり着いたときには山頂に見える崩れかけた石垣の異様な光景に暫し座り込んで見入っていた。 置塩城:文明元年(1469年)赤松政則によって築かれた。 赤松氏は嘉吉の乱によって一時没落していたが、南朝方から神璽を取り戻した功によって、政則の家督相続が認められ加賀半国の守護として復興した。 その後政則は、応仁の乱で細川勝元の命で播磨へ攻め込み、旧領の回復に努め、代々の居城であった白旗城から置塩城へ居城を移した。 天正5年(1577年)赤松則房は羽柴秀吉の播磨平定に従って、天正13年(1585年)の四国征伐に功があり、阿波国住吉に一万石の所領を得て阿波国住吉城に移り置塩城は廃城となった。 羽柴秀吉が姫路城を改修した際に、置塩城の用材を姫路城に転用したといわれる。 八木城:築城年代は定かではない。 八木城は石垣造りの石城と土塁造りの土城があり通常八木城とは石城を指す。 城主八木氏は「山名四天王」のひとりに数えられたが山名氏の勢力が衰えるとしだいに毛利氏に近付くが天正5年(1577年)と天正8年(1580年)の2度にわたる羽柴軍の但馬攻めによって15代八木豊信は降伏する。 降伏した豊信は天正8年(1580年)の羽柴秀吉による鳥取城攻めに従って因幡国若桜鬼ケ城の守備を命ぜられたが毛利氏の攻撃によって落城、豊信は後に日向国佐土原城主の島津家久に仕えた。 天正13年(1585年)別所重棟が一万二千石で入封するが子吉治は関ヶ原合戦で西軍に属した為に改易となった。 此隅山城:築城年代は定かではないが文中年間(1372年~1374年)に山名時義によって築かれたと云われる。山名氏はその全盛期において11ヶ国(山城・和泉・紀伊・丹波・丹後・但馬・因幡・伯耆・美作・隠岐・出雲)の守護を勤め「六分の一殿」と呼ばれる程の一大勢力を誇った。 応仁の乱では山名持豊(出家して宗全)は西軍の総大将として東軍の細川勝元と対峙した。しかし、戦国時代になるにつれ山名氏の守護としての地位は落ち、永禄12年(1569年)羽柴秀吉によって攻められ此隅山城は落城し、城主の山名祐豊は但馬から堺へ逃れた。その後、堺商人の力を借りて但馬に復帰し、天正2年(1574年)に有子山城を築いて居城とした。 このとき、此隅山城の別名子盗を嫌い有子と名付けたと云われる。 有子山城:天正2年(1574年)山名祐豊によって築かれた。 永禄12年(1569年)羽柴秀吉によってそれまでの居城であった此隅山城が落城し、山名祐豊は但馬から堺へ逃れた。その後、堺商人の力を借りて但馬に復帰し、天正2年(1574年)に有子山城を築いて居城とした。 このとき、此隅山城の別名子盗を嫌い有子と名付けたと云われる。 但馬へ復帰した山名祐豊であったが、天正8年(1580年)再び織田軍の羽柴秀長によって攻められ有子山城は戦うことなく開城、城主山名氏政は城を脱して因幡へ逃れ、城内に残った山名祐豊は五日後に病死したと云われる。 天正13年(1585年)前野長康が五万石で入封したが、関白豊臣秀次の処刑に連座して殺された。文禄4年(1595年)播磨国龍野から小出吉政が五万三千石で入封、慶長9年(1604年)小出吉英が山麓に出石城を築いて居城とし、山頂の有子山城は廃城となった。 黒井城:築城年代は定かではないが建武年間(1334年~1338年)に赤松貞範によって築かれたと云われる。 箱根竹ノ下の戦功によって足利尊氏より春日部荘を得た赤松貞範が築いたとされる。 その後、荻野氏の居城となり、荻野和泉守・荻野伊予守と替わった。荻野氏時代の大手口は東方面とされ、荻野伊予守秋清は留堀城を館城としていたといわれる。 天文11年(1542年)後屋城主赤井時家の次男才丸は朝日城の荻野一族に請われて荻野氏を継ぎ、朝日城主となった。これが丹波の赤鬼と称された荻野(赤井)直正で、天文23年(1554年)叔父の黒井城主荻野秋清を留堀城で殺害し黒井城主となった。 荻野直正は兄の後屋城主赤井家清が亡くなると、その子忠家の後見人として赤井家を取り込み、丹波国のみならず但馬国へも侵攻して勢力を広げ、八上城波多野氏とともに西丹波を支配した。 天正4年(1576年)織田信長の部将明智光秀が丹波攻略を命じられ黒井城を包囲したが、この時は八上城波多野秀治が背反して光秀は近江国坂本へ引き上げた。 天正6年(1578年)荻野直正が病没すると、その子正置(直義)は幼少の為、三尾城主赤井幸家が後見人となった。しかし、天正7年(1579年)明智光秀は八上城を落とし、さらに氷上郡の諸城を落として黒井城を孤立させ、8月9日攻め落とした。 黒井城を攻め落とした光秀は斎藤利三を城主とした。利三は南麓(現興禅寺)に館を構え、ここで春日局が誕生したといわれる。明智光秀が山崎合戦で羽柴秀吉に敗れると、黒井城主として堀尾吉晴が入部するが、天正13年(1585年)堀尾吉晴は近江国佐和山へ転封となり廃城となった。 岩尾城:永正13年(1516年)和田斉頼によって築かれたと云われる。 和田氏は文明3年(1471年)谷基綱が地頭として信濃国南和田より入部(一説にそれより三代前の谷頼綱が至徳年間(1384年~1387年)に入部した説もあり)したのが始まりとされる。 基綱の子頼衡は一族の斉頼を婿として迎えたが、斉頼は養父頼衡を殺害して和田日向守と名乗り、近隣を侵略して井原荘を和田荘と改名したという。斉頼は天文13年(1548年)病没し、師李が城主となったが、天正7年(1579年)丹波へ侵攻した明智光秀に攻められ落城した。天正14年(1586年)近江国木戸より佐野栄有が三千七百五十石で入封すると、岩尾城を近世城郭へと改修した。文禄4年(1595年)佐野栄有は近江国木戸へと移り、その後は前田玄以の属城となって慶長2年(1597年)廃城となった。 16:00終了、帰路に向かう。 今回の旅行、近場の兵庫県に足を運び、比較的マイナーなお城9か所を訪れ楽しみました。 比較的地味で目立った遺跡が少ないお城めぐりでした。 |
            |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第三百八十一弾:伊予大島八十八箇所&愛媛県お城巡り観光 2016年11月12-13日 開創二百年余りの歴史を有する島四国、のどかな瀬戸内の風景を心癒される伊予大島准四国霊場八十八箇所の16箇所と愛媛県のしまなみ海道に位置するお城三か所を訪れました。 12日17:25新大阪新幹線のぞみで出発 18:32福山駅到達、レンタカーで今治方面に向かう。 20:5今治港付近のホテル到着後周辺を散策し食事を済ませて就寝。 13日7:00レンタカーで出発、伊予大島に向かう。 8:00伊予大島霊場巡り 牛頭山: 昌清庵: 櫛野辺堂: 万性寺: 道場庵: 霊仙寺: 金剛院: 遍照坊: 般若庵: 大来庵: 普光寺: 五光庵: 福寿庵: 供養堂: 紫雲庵: 知足庵: 蓮台庵: 12:00しまなみ海道に位置する愛媛県のお城巡り。 甘崎城:天智天皇10年(671年)越智氏によって築かれたと云われ、最古の水軍城とされる。中世には村上水軍の水軍城として来島村上氏の部将村上吉継などが居た。慶長5年(1600年)今治に入封した藤堂高虎は弟の藤堂大輔を城主として城を改修、その死後は菅宇兵衛、桧垣五郎などが在城したという。慶長13年(1608年)藤堂高虎の伊勢国安濃津への転封により廃城となった。 能島城:応永26年(1419年)村上吉房によって築かれたと云われる。 村上吉房は村上義顕の三男で分家し築城した。 村上水軍三家のうち最も四国よりに拠点を構えた来島村上氏は主家河野氏の内紛に乗じて伊予本土にまで次第に勢力を拡大していく。 四代通康は河野通直が寵愛し後継者として指名した程であったが、これには河野家臣団の猛反発を喰らい反対派が来島を攻める第一次来島合戦が起こった。 天正10年(1582年)村上通総のとき、織田信長の部将羽柴秀吉の調略を受けて河野氏を離反し織田氏に付いた。河野氏は毛利氏とともに来島村上氏を攻め、通総は耐えきれずに来島城を脱して秀吉の元に逃れたが、鹿島城主で通総の兄である得居通幸は鹿島城を固く守って攻撃を退けた。 秀吉の元に逃れていた通総も羽柴氏と毛利氏が和睦したのち旧領に戻り、天正13年(1585年)秀吉による四国征伐では小早川隆景の指揮下で先鋒を務めた。この功により風早郡一万四千石が来島通総に与えられ、通総は来島城を廃して鹿島城を居城とした。 慶長2年(1597年)来島通総は慶長の役で討死し、家督は次男の長親が継いだ。 慶長5年(1600年)関ヶ原合戦で来島長親は西軍に属し、豊後国森一万四千石で転封となったが、三島村上氏で唯一江戸時代に大名となり、久留島氏と名を改め明治まで続いている。 来島城:応永26年(1419年)村上吉房によって築かれたと云われる。 村上吉房は村上義顕の三男で分家し築城した。 村上水軍三家のうち最も四国よりに拠点を構えた来島村上氏は主家河野氏の内紛に乗じて伊予本土にまで次第に勢力を拡大していく。 四代通康は河野通直が寵愛し後継者として指名した程であったが、これには河野家臣団の猛反発を喰らい反対派が来島を攻める第一次来島合戦が起こった。 天正10年(1582年)村上通総のとき、織田信長の部将羽柴秀吉の調略を受けて河野氏を離反し織田氏に付いた。河野氏は毛利氏とともに来島村上氏を攻め、通総は耐えきれずに来島城を脱して秀吉の元に逃れたが、鹿島城主で通総の兄である得居通幸は鹿島城を固く守って攻撃を退けた。 秀吉の元に逃れていた通総も羽柴氏と毛利氏が和睦したのち旧領に戻り、天正13年(1585年)秀吉による四国征伐では小早川隆景の指揮下で先鋒を務めた。この功により風早郡一万四千石が来島通総に与えられ、通総は来島城を廃して鹿島城を居城とした。 慶長2年(1597年)来島通総は慶長の役で討死し、家督は次男の長親が継いだ。 慶長5年(1600年)関ヶ原合戦で来島長親は西軍に属し、豊後国森一万四千石で転封となったが、三島村上氏で唯一江戸時代に大名となり、久留島氏と名を改め明治まで続いている。 18:00福山駅到達。 18:59福山駅新幹線のぞみで出発。 20:01新大阪駅到達。 今回の旅行、愛媛県しまなみ海道に足を運び、伊予大島に点在する八十八箇所霊場の16箇所と3個のお城を訪れ楽しみました。 伊予大島の八十八箇所霊場は初心者にはもってこい、険しい場所にはなく、距離も短く、四国八十八箇所霊場を訪れる前の練習の霊場巡りです。 今回3回目で伊予大島八十八箇所すべてを巡ることができました。 昼からは愛媛県のしまなみ海道に点在するお城を巡り、こちらも愛媛県のお城全てを終了いたしました。 |
           |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第三百七十九弾:愛媛県お城城下町巡り観光 2016年10月29-30日 源平合戦で源頼朝に味方した河野氏が、伊予で一大勢力を築く、応仁の乱以降は、周防の大内氏、豊後の大友氏が接近し、毛利氏も 争乱に絡んでくるが、最終的には土佐の長宗我部元親によつて制圧された愛媛県に足を運び比較的マイナーなお城6箇所を訪れました。 29日14:20伊丹空港出発 15:10松山空港到達、レンタカーで宇和島に向かう。 17:00宇和島駅前のホテル到着後繫華街を散策し食事を済ませて就寝。 30日7:00レンタカーで出発、お城巡り。 河後森城:築城年代は定かではない。 戦国末期の城主は河原淵教忠(渡辺)で土佐一条氏一族の東小路家から政忠の養子となった人物だが重臣芝氏に城を追われる。 芝氏は土佐を統一した長宗我部氏に通じ西園寺氏に敵対した。 豊臣秀吉による四国平定後は城番が置かれ、藤堂高虎が宇和島城を築城した際には河後森城の天守を月見矢倉に移築したと伝えられる。 慶長19年(1614年)伊達秀宗が宇和島に入部すると、付家老桑折氏が七千石をもって居城としたが、元和の一国一城令により廃城となったようである。 大森城:築城年代は定かではないが土居氏によって築かれた。 土居氏は紀伊国牟婁郡土居の鈴木党発祥と称しているが定かではない。 土居氏は西園寺十五将の一人に数えられる。 戦国時代の当主土居伊豆守清宗は天文15年(1546年)石城に籠って豊後の大友氏からの侵攻を防いだ。しかし、永禄3年(1560年)に再度大友氏の来攻を受け石城は落城して土居清宗・長子清定父子は自刃して果てた。 永禄5年(1562年)土佐国一条氏に人質となっていた土居式部大輔清良が大森城主としてこの地に戻った。清良は天正7年(1579年)長宗我部氏によって落城した岡本城の奪還に成功している。 吉田藩陣屋:明暦4年(1658年)伊達宗純によって築かれた。 宗純は初代宇和島城主伊達秀宗の五男で三万石を分地され吉田藩を立藩した。 石城のある御殿山の南麓の低湿地帯を埋め立てて築かれている。 現在は国安川沿いに石垣の一部、少し中に入った所に井戸が残っており御殿風の図書館がなんとなく当時をしのばせる。 黒瀬城:築城年代は定かではないが天文年間頃に西園寺実充によって築かれたと云われる。 西園寺氏ははじめ松葉城を本城としていたが豊後の大友氏や土佐の一条氏に備えるため、居城を移した。 天正12年(1584年)実充の跡を継いだ西園寺公広のとき長宗我部氏に降伏した。公広は豊臣秀吉による四国征伐の後に宇和地方の領主として大洲城へ入った戸田勝隆によって下城を命ぜられ、翌年謀殺された。 松葉城:築城年代は定かではないが西園寺氏によった築かれたと云われる。 西園寺氏は鎌倉時代中期に西園寺公経が宇和郡地頭職となり、南北朝時代に下向して松葉城を築き領国支配を行ったとこに始まるとされる。 築城当初は岩瀬城と呼ばれていたが、西園寺家の世継ぎの宴の際に、武将の杯の中に松の葉が落ちた。城主はこれをめでたいことだと喜び、松葉城と呼ばれるようになったと云われる。 西園寺氏は南予における最大の大名であったが、大洲の宇都宮氏、豊後の大友氏、土佐一条そして長宗我部氏などと争い、西園寺実充は天文年間(1532年~1555年)頃に黒瀬城を築いて居城を移した。 三滝城:築城年代は定かではない。 初代甲之森城主紀実定の時には七枝城の一つとして存在している。 2代紀実平によって本城を三滝城へ移すべく縄張りを行ったが病に倒れ、子実次によって永享年間(1429年~1441年)に築かれた。 戦国時代には西園寺氏に属し西園寺15将の一人に数えられたが、長宗我部氏によって攻められ落城した。 長宗我部氏による三滝城の攻撃は諸説あり定かではないが、そのうちの一つは天正9年(1581年)通安、天正11年(1583年)親安の時であったという。 17:00松山空港到達。 18:05松山空港出発 18:55伊丹空港到達。 今回の旅行、四国の愛媛県に足を運び、宇和島周辺の比較的マイナーなお城、6箇所を訪れ楽しみました。 お城は地味でしたが案内板がしっかりあり、今回は苦労せず見つけることができました。 愛媛のお城、あとは離島に位置するお城のみとなりました。次回訪れたいと思います。 |
       |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第三百七十八弾:山梨県お城城下町巡り観光 2016年10月22-23日 南アルプスをはじめ、多くの山々が自然の障壁となり、他国と交戦することは珍しく、安定した時代が長く続いたが、武田氏滅亡後に起きた天正壬午の乱では、甲斐も大規模な戦闘の舞台となった山梨県に足を運び、比較的マイナーなお城9か所を巡りました。 22日13:40新大阪駅新幹線ひかりで出発 15:55新三島駅到達、レンタカーで甲府に向かう。 18:30甲府駅前のホテル到着後繫華街を散策し食事を済ませて就寝。 23日7:30レンタカーで出発、お城巡り。 湯村山城:大永3年(1523年)武田信虎によって築かれた。 信虎は永正16年(1519年)石和から躑躅ヶ崎館に居城を移し、翌年詰の城として要害山城を築いたが、引続き湯村山城を築いた。 白山城:築城年代は定かではないが武田信義によって築かれたと云われる。 信義の武田信義館の要害城として築いたものだと云われる。 その後、この地は信義の子一条忠頼の遺領を継いで一条氏を名乗った信長の末裔である時光が青木氏を名乗り、さらに青木信種の次男信明が山寺氏を名乗って領地とした。 この山寺氏は武田氏滅亡後も徳川氏の家臣となって甲府城番を勤めたという。 新府城:天正9年(1580年)二月、武田勝頼は真田昌幸を普請奉行とし韮崎市にある七里岩と呼ぶ絶壁の上に築城を開始、同年九月にはほぼ完成し躑躅ヶ崎館を破棄して移った。 しかし、織田軍の進撃の前に在城わずか二ヵ月余りで、小山田信茂の進言により新府城に火をかけ、岩殿城を目指して退去した。 若神子城:築城年代は定かではない。 若神子城はこの古城と北の若神子北城(大城)、南の若神子南城らを総称した名称である。 武田氏の祖である新羅三郎義光あるいはその子源義清(武田義清)の居城であったとも伝えられるが定かではない。 天正10年(1582年)武田氏が滅亡し、織田信長が本能寺の変に倒れると旧武田領は北条氏と徳川氏によって争われた。この天正壬午の乱で北条氏の軍勢は信濃佐久から大門峠を越えて諏訪へ出て、新府へ退いた徳川軍を追って若神子周辺に布陣、本陣は若神子城に置かれたという。 獅子吼城:築城年代は定かではない。元応2年(1320年)に信田小右衛門実正・小太郎実高父子が討死した記録が見性寺の寺記に残っている。 永正6年(1509年)小尾弥十郎が江草城を乗っ取った記録が「高白斎記」に記されている。 応永年間(1394年~1428年)には武田信満の三男江草兵庫助信泰の居城で、見性寺に位牌と木像が安置されている。 天正10年(1582年)本能寺の変の後、旧武田領を巡って北条氏と徳川氏が争った天正壬午の乱では、北条軍が獅子吼城を占拠したが、服部半蔵率いる伊賀組と小尾衆など周囲の国人の夜襲によって落城した。 旭山砦:天正10年(1582年)北条氏によって築かれたと云われる。 武田氏の時代に烽火台があったとも伝えられるが、現在の遺構は武田氏滅亡後、その所領を徳川氏と北条氏が争った天正壬午の乱のときに北条氏が築いた陣城である。 北条氏は佐久から甲斐へ侵攻して若神子城を修築して本陣を構え、新府城に入った徳川氏の軍勢と対峙した。しかし、徳川氏の依田玄蕃が佐久で北条氏の兵道を断ったことから、信濃から撤退している。 深草城:詳細不明。「甲斐国志」によれば城主は堀内下総守とされ、元亀・天正年間(1570年~1572年)頃の武田家臣とされ、その子主税助の時に落城したという。 谷戸城:築城年代は定かではないが鎌倉時代に逸見清光によって築かれたと云われる。 清光は常陸国から大治5年(1130年)甲斐国巨摩郡市河荘に配流となり、逸見(へみ)に住んで逸見氏を名乗った。後に甲斐源氏武田氏となる系統はこの清光の次男で武田信義館に住んだ信清の系統である。 天正10年(1582年)武田勝頼が天目山で自刃して武田氏が滅亡すると、織田氏の勢力下となったが、織田信長が本能寺の変に倒れたことにより、徳川氏と北条氏が甲斐に侵攻して草苅り場となる。この天正壬午の乱で谷戸城は北条氏方の城となり、この北条氏によって城が改修されたとされる。 真篠城:詳細不明。『南巨摩郡誌』に原大隅守、後に真篠勇太夫が城主であったと伝えるが、何れの人物も不詳である。 17:00新三島駅到達 17:48新三島駅新幹線ひかりで出発 20:03新大阪駅到達。 今回の旅行、富士山をはじめ自然いっぱいの山梨県に足を運び、比較的マイナーなお城9箇所を訪れました。 自然の観光名所は多いが文化遺産は地味で今回も案内板が整備されておらず見つけるのが苦労いたしました。 |
       |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第三百七十七弾:群馬県お城城下町巡り観光 2016年10月15-16日 源義重を祖とする新田氏が、上野国で勢力を持つが、やがて南朝方として敗戦にまみれ、南北朝の内乱が収束しても、各地で戦いが発生し、幕府は関東管領として上杉氏憲を立てたが、混乱の時代が長く続いた群馬県に足を運び比較的マイナーなお城11か所を訪れました。 15日13:50新大阪新幹線のぞみで出発 16:23 東京駅到達 16:40東京駅新幹線Maxときで出発 17:30高崎駅到達、駅前のホテル到着後繁華街を散策し食事を済ませて就寝。 16日8:00レンタカーで出発、お城巡り 高崎城:高崎城の前身は和田城で正長元年(1428年)和田義信によって築かれた。 和田氏は関東管領上杉氏に従って永享の乱に従軍した。 戦国時代には上杉政虎、後に武田信玄に属し、長篠合戦にも従軍したが武田氏滅亡後は小田原北条氏に属した。天正18年(1590年)豊臣秀吉による小田原征伐で和田信業は小田原城に籠城したが、この時和田城も落城、小田原城も開城となり、信業は紀伊国へ逃れたと云う。 高崎城は慶長3年(1599年)和田城跡に新たに井伊直政によって築かれた。 小田原の役の後に関東に入部した徳川家康は、はじめ井伊直政を箕輪城に置いたが、後に和田城跡に新たに縄張した新城を築かせた。 直政はここを高崎と命名するが慶長5年(1600年)関ヶ原合戦後に近江国佐和山に転封となった。 以後目まぐるしく城主が入れ替わる。 ・慶長5年(1600年)井伊直政は近江国佐和山に転封。 ・慶長9年(1604年)下総国臼井より酒井家次が五万石で入封、元和2年(1616年)忠勝の時、越後国高田に転封。 ・元和2年(1616年)常陸国笠間より(戸田)松平康長が二万石で入封、元和3年(1617年)信濃国松本に転封。 ・元和3年(1617年)常陸国土浦より(藤井)松平信吉が五万石で入封、元和5年(1619年)丹波国篠山に転封。 ・元和5年(1619年)下総国小見川より安藤重信が五万六千五百石で入封、元禄8年(1695年)重治の時、備中国松山へ転封。 ・元禄8年(1695年)下野国壬生より(大河内)松平輝貞が五万二千石で入封、宝永7年(1710年)(大河内)越後国村上に転封。 ・宝永7年(1710年)相模国より間部詮房が五万石で入封、享保2年(1717年)詮言の時、越後国村上へ転封。 ・享保2年(1717年)越後国村上より(大河内)松平輝貞が七万二千石で入封、以後明治に至る。 倉賀野城:築城年代は定かではないが応永年間(1400年)頃に倉賀野頼行によって築かれたと云われる。 倉賀野氏は武蔵児玉党の一派で、関東管領上杉憲政に従っていたが、城主倉賀野行政が川越付近の戦で討死した。 その子尚行は永禄3年(1560年)上杉政虎の関東進出に従い、翌永禄4年には上杉政虎に従い相模国小田原城に侵攻した。この後、反撃に出た小田原北条氏は、武田氏とともに倉賀野城に攻め寄せたが、これを撃退した。 永禄6年(1563年)上野国に侵攻した武田氏は、木部城を落とし倉賀野城に攻め寄せたがこれも撃退する。 しかし、永禄8年(1565年)に武田氏の攻撃で落城し尚行は上杉謙信を頼って逃れた。 落城に先立って永禄2年(1559年)頃、武田氏に降っていた倉賀野十六騎の一人、金井秀景が元亀元年(1570年)城主となり、倉賀野氏を称した。 秀景は後に小田原北条氏に属し、小田原の役では小田原城に籠城し、降伏開城後に死去した。 平井城:永享10年(1438年)上杉憲実によって築かれたと云われる。 憲実は関東管領山内上杉氏五代当主である。 上杉憲実は室町将軍足利義教と鎌倉公方足利持氏との確執が生じていく中、平井城と金山城は総社城主長尾忠房に命じて密かに築城させていたものだという。永享の乱(1438年)で足利持氏は上杉憲実を討つ為、一色直兼・時家三千騎を派遣し自身も五千騎を率いて武蔵国高安寺に馬を進めた。 憲実は密かに鎌倉を脱し平井城へ逃がれ、室町幕府に急使を派遣して援軍を要請した。 急使を受けた将軍足利義教は上杉持房を将として今川・朝倉・小笠原・山名などに憲実の救援を命じ、越後国からも上杉教朝が三千五百騎の援軍が到着した。 幕府軍は早川尻で持氏方を敗り、持氏は鎌倉へ戻ろうとしたが叶わず幕府軍に降り相模国の弥名寺で剃髪し、上杉憲実は幕府に持氏の助命嘆願行ったが叶わず、持氏は永安寺で自刃した。 享徳3年(1454年)鎌倉公方足利成氏が関東管領上杉憲忠を暗殺すると、上杉房顕は平井城へ移り、以後関東管領山内上杉氏の本城となった。 天文年間(1532年~1555年)山内上杉氏は小田原北条氏と度々戦ったが、天文20年(1551年)上杉憲政は平井城を捨てて越後国の長尾景虎(後の上杉謙信)を頼って落ち延びた。その後、北条幻庵が平井城主となったが天文21年(1552年)長尾景虎の送った軍勢により攻め落とされ、平井城は破却された。 根小屋城:永禄13年(1570年)武田信玄によって築かれた。 箕輪城を攻略し西上野を手に入れた信玄は、山名城と鷹ノ巣城との間に新城を築き、信濃国から信頼のできる武将望月甚八郎・伴野助十郎を城主として、配下に治めた上野の諸将を見張らせた。 国峯城:築城年代は定かではないが小幡氏によって築かれたと云われる。 小幡氏は児玉党の一族で関東管領山内上杉氏に属しており、小幡憲重は箕輪城主長野業政の娘(妹とも)を室に迎えていた。 天文20年(1551年)関東管領上杉憲政が越後の長尾景虎を頼って越後へ落ちると、上杉氏に属していた諸豪族は越後の長尾氏、小田原の北条氏、甲斐の武田氏に別れ、小幡憲重・重定父子は天文22年(1533年)甲斐の武田氏に属した。これに対して長尾氏方へ付いた長野業政は留守中の国峯城を奪って一族の小幡景定を城主とした。 永禄3年(1560年)武田信玄は小幡氏に信濃国大日向で五千貫を与え市川馬之助兄弟などの南牧地衆を付けた。永禄4年(1561年)信玄は西上野に侵攻して国峯城を奪い返し、小幡氏を城主に復帰させた。 天正3年(1575年)長篠の合戦では小幡信真は赤備えの騎馬武者五百騎を率いて従軍している。この信真は小幡重定で、はじめ重定、武田晴信に仕えて信実、勝頼の代で重定、武田氏滅亡後に滝川一益に従って信貞、北条氏に従って信定と名乗りを改めている。 天正18年(1590年)豊臣秀吉による小田原征伐では、小幡信定父子は家臣庭谷左衛門大夫に庭谷城と国峯城の守備を命じて小田原城に詰めたが、国峯城は上杉景勝の武将藤田信吉によって攻められ落城した。 松井田城:築城年代は定かではない。永禄年間(1558年~1570年)初期に安中忠政によって築かれたと云われるが、それ以前に築城されていたという。安中忠政は甲斐の武田信玄に備えて松井田城を改修し、嫡子忠成を安中城へ置いて自身は松井田城に籠った。永禄2年(1559年)頃より武田信玄が西上野に侵攻し、度々松井田城を巡った争いがあったが落城しなかった。しかし永禄7年(1564年)安中城主の嫡子忠成は武田氏に降伏し、父忠政はそれでも松井田城に籠って防戦したが力尽きて開城した。 父忠政は自刃または切腹を申し渡されたが、嫡子忠成は所領を安堵され安中城主となり、松井田城は武田氏家臣市川国貞が城代となった。武田氏が滅亡すると織田信長の家臣滝川一益の所領となるが、織田信長が本能寺の変で没すると一益は伊勢へ逃れ、松井田城は北条氏重臣大道寺政繁が城主となる。 この大道寺氏時代天正15年頃に城は拡張され現在の縄張へとなったという。天正18年(1590年)豊臣秀吉による北条征伐では、前田利家率いる北陸勢によって攻められ、4月22日に政繁は降伏開城した。 安中城:永禄2年(1559年)安中忠政によって築かれたと云われる。 弘治年間頃より西上野に侵攻してきた武田信玄に備えるため、忠政は安中城を築いて嫡子忠成を置き、自身は松井田城を改修して籠った。 永禄2年(1559年)頃より武田信玄が西上野に侵攻し、永禄7年(1564年)安中城主の嫡子忠成は武田氏に降伏し、父忠政はそれでも松井田城に籠って防戦したが力尽きて開城した。 父忠政は自刃または切腹を申し渡されたが、嫡子忠成は所領を安堵され安中城主となった。 忠成改め安中景繁は天正3年(1575年)長篠の合戦に従軍し、景繁以下尽く討死して安中へ帰るものはなく廃城となって荒廃した。 慶長19年(1614年)井伊直勝が安中三万石を領して安中城を再築城した。直勝は井伊直政の長男で、彦根藩二代藩主となるはずであったが、病弱を理由に弟直孝が彦根藩を継ぎ、安中三万石を分与されて立藩した。 築城当初は陣屋程度の規模で、元禄15年(1702年)に内藤政森が入封し城主格が認められ城として改修している。 前橋城:天文3年(1534年)頃、長野賢忠によって築かれた。 天文3年(1534年)石倉城が利根川の氾濫によって崩れ去り残った三の丸を中心に築城したのが厩橋城の始まりと云われる。 永禄3年(1560年)上杉政虎(後の謙信)が越後から進出し厩橋城を関東進出の足掛かりとして関東管領の権限で兵を動員し北条氏の小田原城を攻めたが落城せず帰国した。 永禄5年上杉輝虎(政虎改め)は北条高広を城主として置いたが永禄9年箕輪城が武田信玄によって攻略されると高広は小田原北条氏に内通する。 武田信玄が駿河今川氏を攻めると上杉氏と北条氏は同盟を結び高広は許されて上杉氏に復帰した。 織田信長によって武田氏が滅亡すると関東管領に任ぜられた滝川一益が入城するが本能寺の変で信長が倒れると伊勢に戻った。 小田原の役の後は三万石で平岩親吉、続いて慶長6年酒井重忠が十五万石で入城、寛延2年(1749年)酒井忠恭が播磨国姫路に転封となり替わって松平朝矩が入封する。 明和5年(1768年)利根川の浸食によって前橋城は廃城となり川越城に移った。 文久3年(1863年)再び前橋城が築城され松平直克が入封して明治に至る。 大胡城:築城年代は定かではないが天文年間(1532年~1555年)大胡氏によって築かれたと云われる。 大胡氏は藤原秀郷の末裔といわれる。 天文10年(1541年)頃、金山城横瀬氏の勢力により圧迫され、大胡勝行は小田原北条氏を頼って武蔵国江戸の牛込に移り、弘治元年(1555年)牛込氏に改称した。 その後、金山城由良成繁の家臣増田繁政が城代を勤めたが、由良氏は後に上杉輝虎に叛き、輝虎は大胡城を奪って北条高広を置いて金山城を攻めた。 小田原の役の後、関東に入部した徳川家康は、牧野康成を三河国牛久保より二万石で入部させた。牧野氏は元和2年(1616年)五万石で越後国長峯に移封となり、大胡は前橋酒井氏の領地となり城代が置かれた。 しかし、寛延2年(1749年)酒井氏が播磨国姫路に転封となり廃城となった。 山上城:築城年代は定かではないが大永年間(1521年~1528年)に山上氏によって築かれたと云われる。 山上氏は藤原秀郷の後裔とする藤姓足利氏の一族で、足利俊綱の弟高綱が山上氏を称したことに始まる。山上道及のとき北条氏康によって山上城を追われて下野へ下り、山上城は北条氏の手に落ちたが、後に上杉謙信によって攻め落とされた。その後、大胡民部左衛門、木戸大炊頭などが置かれた。 桐生城:観応元年(1350年)桐生国綱によって築かれたと云われる。 桐生氏は「吾妻鏡」で足利俊綱を殺害した桐生六郎の名が知られる。桐生国綱は桐生氏中興の祖と云われ佐野氏から養子に入った人物である。 桐生氏は桐生助綱のときに全盛を迎える。天文13年(1544年)菱の細川内膳、善因幡守を敗って勢力を拡大し、永禄3年(1560年)には上杉政虎に奉じられて関東入りした上杉憲政の警固をしている。 助綱没すると、佐野氏から養子に迎えていた親綱が家督を継いだ。桐生親綱は家中をまとめることができず内紛状態となり、諫言した里見上総入道を討つなど家臣の離反を招いた。 元亀3年(1572年)由良成繁の軍勢が桐生城を急襲し落城、親綱は佐野氏を頼って落ちた。 由良成繁は桐生城代として横瀬長繁を置き、天正2年(1573年)由良成繁は隠居して金山城を国繁に譲ると、自身は桐生城を居城とした。天正6年(1577年)由良成繁が没すると、桐生親綱が桐生城の奪還を計ったが失敗している。 天正14年(1586年)由良国繁が金山城を追われると桐生城に本拠を移した。天正18年(1590年)豊臣秀吉による小田原征伐で国繁は小田原城に籠城させられたが、母妙印尼は嫡男貞繁を率いて松井田城の前田利家に従い各地を転戦した。この功によって戦後、由良国繁は常陸国牛久五千四百石余り、弟渡瀬繁詮は遠江国横須賀三万石が与えられた。 説明 18:22高崎駅新幹線はくたかで出発 19:12東京駅到達 19:20東京駅新幹線のぞみで出発 21:53新大阪駅到達 今回の旅行、関東地方の群馬県に足を運び、比較的マイナーなお城11箇所を訪れ楽しみました。 案内板もわかりにくく、見つけるのが一苦労、県が史跡に力をいれているところでは比較的案内板がわかりやすく、スムーズに訪れることができますが、都道府県によってはまちまちでわかりやすい都道府県、わかりにくい都道府県がはっきりしています。 観光に力を入れてる都道府県は城跡も案内板がしっかりしていてわかりやすくたどり着くのが容易いです。 |
   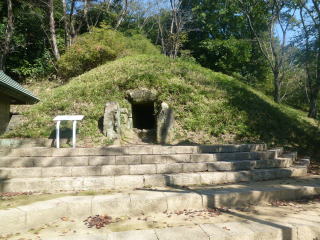                 |
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第三百七十弾:滋賀県お城・城下町巡り観光 2016年8月20-21日 肥沃な土地を持ち、幾内に向かう交通の面で重視され、古くから源平および僧兵勢力の争乱があり、源頼朝が鎌倉幕府を開いた際は、佐々木氏が近江の守護職となり、戦国時代は浅井氏が力をつけた滋賀県に足を運び、比較的マイナーなお城16か所を訪れました。 20日13:00車で出発、第二京阪、京滋バイパスを経由して石山インター下車、大津に向かう。 お城巡り。 膳所城:慶長6年(1601年)徳川家康によって築かれた。 築城においては藤堂高虎が縄張を行い天下普請で行われ完成後は戸田一西が三万石で入城した。 元和2年(1616年)戸田氏鉄は大坂夏の陣の功により摂津国尼崎に移封となり替わって三河国西尾から本多康俊が入封する。 元和7年(1621年)本多康俊になると旧領三河国西尾に移封され替わって伊勢長島から菅沼定好が入封する。 寛永11年(1634年)定好は丹波国亀山に移封となり替わって下総国佐倉から石川忠総が入封するが慶安4年(1651年)石川氏もまた伊勢国亀山に移封となる。 最後に以前三河国西尾に移封になって伊勢国亀山に移封されていた本多俊次が再入封し以後明治に至る。 大津城:天正14年(1586年)浅野長吉によって築かれた。築城に際しては坂本城の部材が転用され、坂本の住民も多くが大津へ移住したという。 その後立て続けに城主がかわったようで、天正17年には増田長盛、天正19年に新庄直頼、文禄4年に京極高次が城主となったようである。 慶長5年(1600年)関ヶ原合戦の直前に京極高次の籠る大津城を毛利元康が攻め、激しい戦いが繰り広げられ、あとは本丸を残すまで攻め込んだ所で大津城は開城した。 関ヶ原合戦後、大津城は廃城となって新たに膳所城が築かれ、大津城の部材は膳所城と彦根城に転用された。現存してる彦根城の天守はこの大津城の天守を移築したといわれ、もともと五層四重であった天守を移築に際して三重三階に切り詰めたという。 宇佐山城:元亀元年(1570年)森可成によって築かれた。 織田信長が家臣の森可成に命じて築かせた城で、近江国から京へ入る道筋を押さえる為に築いたものと云われる。 元亀元年(1570年)九月朝倉義景・浅井長政の連合軍が坂本へ押し寄せると、森可成は城を出て坂本で迎え撃ち討死した。連合軍は宇佐山城へ攻め寄せ放火したが、攻め落とすことはできなかった。摂津から急ぎ京へ戻った信長は宇佐山城へ入り連合軍と対峙したが、膠着状態となり和議となった。 信長は明智光秀を宇佐山城主とすると、延暦寺の焼き打ちなどを命じた。元亀2年(1571年)明智光秀は坂本の地に坂本城を築いて移り、宇佐山城は廃城となった。 坂本城:元亀2年(1571年)明智光秀によって築かれた。 元亀2年(1571年)織田信長は明智光秀に比叡山焼き打ちを命じ、その功によって近江国志賀郡五万石を与え坂本城の築城を命じた。 坂本城は琵琶湖に面した低地にあり、天主と小天守を備えた城郭であったと云われる。 天正10年(1582年)光秀は本能寺にて主君織田信長、二条御所では信長の嫡男織田信忠を急襲して自刃に追い込んだ。安土城を占拠して明智秀満に託し、光秀は天王山に羽柴秀吉と戦ったが敗れ、わずかな手勢を引き連れて坂本城へ戻る途中、山城国小栗栖にて落ち武者狩りの百姓に致命傷を受け、自刃して没した。 光秀の死を知った明智秀満は安土城から坂本城に移り、城に火を放ち坂本城は灰となった。 その後、坂本の地は丹羽長秀に与えられ天正11年(1583年)から坂本城の再建が行われたが、天正14年(1586年)に大津城の築城に際して坂本城は廃城となり、部材は大津城に移されたと云われる。 湖北に向かう。 大溝城:天正6年(1578年)織田信澄によって築かれたと云われる。 織田信澄は織田信長の実弟織田信行の子で、津田信澄とも称した。 元亀年間(1570年~1573年)に信長は浅井長政を滅ぼして高島七頭も降すと、高島郡には磯野丹波守員昌が入部し新庄城を居城とした。信澄はこの員昌の養子となっていたが、天正6年(1578年)員昌は信長の勘気を被って追放されると所領は信澄が継いだ。 天正10年(1582年)織田信長が本能寺の変で倒れた際、信澄は四国征伐軍の副将として織田信孝に従って大坂にいたが、信澄の正妻が明智光秀の娘であったことから内通が疑われ、織田信孝・丹羽長秀の軍勢に急襲され摂津国野田城にて討たれた。 信澄の後は丹羽長秀の所領となって代官として植田重安が在城した。 天正11年(1583年)賎ヶ岳合戦後に丹羽長秀が越前国府中城に移封となると、加藤光泰が入部した。天正13年(1585年)には加藤光泰は美濃国大垣城へ移り、代わって生駒親正が城主となるが、親正も翌天正14年(1586年)に伊勢国神戸城へ移封となった。 その後は再び秀吉の直轄領となっていたが、天正15年(1587年)京極高次が入部した。天正18年(1590年)には織田三四郎が城主となるが、再び秀吉の直轄領になって吉田修理が代官を務め、最後に文禄4年(1595年)岩崎掃部佐が城主となった。 慶長8年(1603年)に大溝城は破却され水口岡山城に部材が転用されていたと云われる。 江戸時代に入り元和5年(1619年)伊勢国上野より分部光信が二万石で入封し大溝藩となった。大溝藩は城主格ではなかったため、廃城となっていた大溝城の三の丸付近に大溝陣屋を構え、以後代々続いて明治に至る。 朽木城:築城年代は定かではないが江戸時代初期に朽木氏によって築かれた。 朽木氏は高島七頭の一人で宇多源氏佐々木信綱を祖とする。 信綱は近江守護で承久の乱の戦功により、高島郡朽木荘の地頭職を得て、信綱の曾孫である義綱の時、朽木氏を名乗った。 朽木氏は足利将軍が京での戦乱を避け、朽木谷へ逃れてきたのを度々もてなしている。 元亀元年(1570年)織田信長が越前朝倉氏を攻めたとき、浅井氏が朝倉氏と結んで信長の退路を断った際に、松永秀久の説得に応じて信長を応対し京へと案内した。 また、関ヶ原合戦においては当初西軍に付いていたが、途中で徳川方へ寝返り、その結果九千五百石を安堵され、一万石に満たないものの大名格の交代寄合として江戸に参勤した。 朽木氏は薩摩島津氏、肥後相良氏などと同じく中世から明治まで一貫して在地を治めた数少ない家である。 清水山城:麓にある西屋敷跡を散策しながら登る。 主郭は南側の頂部で北側の2条の竪堀は良く見えるが、東側の竪堀は草に覆われている。南西方向の尾根に土塁などが残る曲輪群がある。 北曲輪群には畝状竪堀群があり、ここは非常に良く残っている。 木ノ本方面に向かう。 賤ヶ岳砦:築城年代は定かではない。天正元年(1573年)に浅井・朝倉軍が賎ヶ岳に布陣していた記録が残されている。 天正11年(1583年)賤ヶ岳合戦では羽柴秀吉方の砦として利用された。 城将は但馬国竹田城主桑山重晴、羽田長門守、浅野弥兵衛であった。 羽柴秀吉が美濃の岐阜城主織田信孝を攻めにいって留守のとき、柴田勝家の武将佐久間盛政が秀吉方の大岩山砦を急襲して砦は陥落、守将中川清秀は討死、盛政はさらに高山右近の岩崎山砦も攻め落とした。勝家は盛政に撤退を命じたが盛政はこれを無視して大岩山砦に兵を置いて維持した。その後、賎ヶ岳砦の桑山重晴も砦を破棄して撤退しようとしたが、琵琶湖を渡って援軍に駆けつけた丹羽長秀と合流して砦を維持した。さらに翌日には急を聞きつけ美濃の大垣よりとって返した秀吉の本隊も合流して佐久間盛政を撃破し、さらに柴田勝家の本隊も切り崩し秀吉方の勝利となった。 山本山城:築城年代は定かではない。 平安時代末期に山下兵衛尉義経が籠った山下城がこの城であったと云われる。 その後京極氏の被官阿閉氏の居城となったが、永正年間(1504年~1521年)頃には浅見氏の居城となっていた。 浅見氏は一時期浅井亮政と対立したが後にその傘下に組み込まれ再び阿閉氏が城主となった。 織田信長による小谷城攻撃では、阿閉氏の籠る山本山城が天正元年羽柴秀吉謀略によって開城となり、小谷城は孤立し落城した。 18:30彦根方面に向かう。 19:30彦根市内のホテル到着後繁華街を散策し食事を済ませて就寝。 21日7:30車で出発、米原方面に向かう。 佐和山城:築城年代は定かではないが、佐々木定綱の六男佐保時綱が麓に屋敷を構え砦を築いたのが始まりと云われる。 六角氏と京極氏の争いでは境目に位置する佐和山城が標的となり、京極氏に替って勢力を伸ばした小谷城の浅井氏が奪うと、磯野員昌を城主とする。 織田信長が越前朝倉氏を攻ると、浅井氏は朝倉氏と結び、織田氏と敵対する。 危機を脱した織田信長は粘り強く佐和山城を攻め、天正10年(1582年)礒野員昌は降伏し城を明け渡した。 信長が本能寺の変で没すると、明智光秀を討った羽柴秀吉の所有となり、後に石田三成が城主となる。 石田三成が関ヶ原合戦で破れると井伊直政が入封するが、後に彦根城を築き廃城となった。 鎌刃城:築城年代は定かではない。 城主は土肥氏ともいわれるが、堀氏が有力視されいる。堀氏の出自は詳らかではないが藤原秀郷流と推測されている。 この城は観音寺城佐々木六角氏と上平寺城京極氏・小谷城浅井氏との間で幾度か争われ、堀氏はその狭間で度々主家を変えている。 織田信長が越前朝倉氏を攻めると、浅井氏は朝倉氏と通じ織田氏と対峙するようになる。 堀氏は織田方へついたため、浅井氏によって攻められるが織田氏の援軍によって辛うじて落城を免れている。天正2年(1574年)堀氏は織田氏によって粛正され滅亡した。 弥高寺跡:仁寿年間(851年~854年)に僧三修によって設けられた山岳寺院と伝えられる。 伊吹山寺の中心をなした寺院と推測され、地元では弥高百坊と呼ばれている。隣接する京極氏の上平寺城との関連性があり、この弥高寺も支城の一つとして城郭化された。 上平寺城:築城年代は定かではないが永正年間(1504年~1521年)頃に京極高清によって築かれたと云われる。 京極氏は佐々木氏の分家で京の京極高辻に屋敷を構えたことから京極を称し、宗家である佐々木六角と区別して佐々木京極氏とも呼ばれている。 京極氏は京極導誉のとき足利尊氏に従って力を付け、室町時代には四職家の一つとなり、北近江の守護職や出雲守護職、飛騨、隠岐などの守護職にも任ぜられた。 その後、京極氏の内訌などが続いたが永正2年(1505年)京極高清は正経の子京極材宗と和睦が成った。この後に高清の居城として上平寺城が築かれたと云われる。 大永3年(1523年)再び家督を巡る争いが起こり、浅見貞則を旗頭とする国人衆らによって上平寺城は落城し、京極高清らは尾張へ逃れた。その後、近江へ戻った高清であったが、小谷城主の浅井氏が台頭し、京極高清・高広父子は小谷城へ移り住むなど京極氏の居城としての上平寺城の役目は終わっていった。 元亀元年(1570年)織田信長が越前の朝倉氏を攻めたとき、浅井長政は背後から挙兵して織田軍と戦ったが、信長は九死に一生を得て岐阜へ戻った。信長を逃した長政は織田氏に備えるため、刈安城(上平寺城)と丈比城を改修して備えたが、鎌刃城主の堀秀村らが織田方に寝返ったため、この防衛戦も役に立たなかった。 余呉方面に向かう。 横山城:築城年代は定かではないが京極氏によって築かれたと云われ、 永正14年(1517年)浅井亮政によって攻め取られ、浅井氏によって改修されたものといわれる。 織田氏が越前朝倉氏を攻めると、浅井氏は朝倉氏と結び織田氏と決別、元亀元年(1570年)世に云う姉川合戦となり、織田・徳川連合軍と浅井・朝倉連合軍は姉川を挟んで対峙する。 この時、織田信長は横山城の北の尾根端、竜ヶ鼻砦に陣取り、柴田勝家・羽柴秀吉等に横山城を攻略させた。 信長は羽柴秀吉を横山城主とし天正元年(1573年)浅井氏滅亡まで小谷城を抑える拠点として重要な役目を担った。 虎御前山城:天正元年(1572年)織田信長によって築かれた。 元亀元年(1570年)鎌刃城の堀氏を調略した信長は虎御前山を本陣として小谷城を攻めたが、この時は本格的な築城には至らず兵を引いた。 天正元年(1572年)再び小谷城に侵攻した信長は虎御前山に築城し、元亀4年(1573年)小谷城が落城するまでの間、最前線の砦として利用された。 東野山城:築城年代は定かではないが東野氏によって築かれたと云われる。 東野氏は西麓に東野館があり、その詰城として東野山城が築かれたと云われる。現在の遺構は天正11年(1583年)賎ヶ岳合戦で羽柴秀吉方の砦として築かれたもので、堀久太郎秀政が布陣した。 14:00帰路に向かう。 今回の旅行、北海道の旭川方面のお城めぐりの予定でしたが、台風の影響もあり、旭川は大雨、河川氾濫に危険性有とのことで急遽変更、近場の滋賀県に足を運び、比較的マイナーなお城14か所を訪れ楽しみました。 歴史深い滋賀県、特に戦国時代は幾多の戦場の場でもあり、多くの歴史的建造物遺跡が多く興味深い地でもあります。 お城も多く、戦のための山城が多く、確認するのに苦労を要しました。 結局1泊2日で16か所のお城をめぐり堪能しました。 |
                   |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第三百六十八弾:宮城県お城・城下町巡り観光 2016年7月30-31日 東北の宮城県に足を運び、南北時代、奥州探題の?斯波氏が勢力を拡大し、南朝方の葛西氏と戦国の世まで対立した。のちに伊達氏が巨大勢力を作り上げ、同地では、土塁や空堀を備えた拠点を館とよぶのが特徴的な宮城県に点在する比較的マイナーなお城7か所を訪れました。 30日16:10伊丹空港出発 17:25仙台空港到達、レンタカーで仙台市内に向かう。 18:30仙台市内のホテル到着後周辺を散策し食事を済ませて就寝。 31日7:30レンタカーで出発、お城めぐり。 岩切城:築城年代は定かではないが南北朝時代に留守氏によって築かれたと云われる。 正平6年・観応2年(1351年)足利尊氏と直義の対立による観応の擾乱が東北にも波及し、奥州管領の吉良貞家と畠山国氏が対立した。尊氏方についた畠山氏・宮城氏・留守氏は岩切城に籠城し、これを直義方の吉良氏・和賀氏・結城氏が攻め落とし、畠山国氏ら百余名が討死あるいは切腹した。 この戦いで勢力を失った留守氏は、その後大崎氏に従って勢力の回復を計り、戦国時代に伊達氏の勢力が拡がると、大崎氏と伊達氏の狭間で留守氏の内部も分裂していく。永禄10年(1567年)には留守顕宗が伊達晴宗の三男政景を養子に迎える。 元亀年間(1570年~1573年)留守政景は利府城に居城を移し、岩切城は廃城となった。 若林城:寛永4年(1627年)伊達政宗によって築かれたが、それ以前には国分氏の城があったと云われる。 伊達政宗が隠居城として幕府に願い出て許可されたのが若林城で、寛永4年(1627年)に築城を開始して翌寛永5年に政宗が入城した。寛永13年(1636年)政宗が江戸の屋敷で没すると、若林城は一重の堀を残して廃城となった。 川崎城:築城年代は定かではないが慶長13年(1608年)頃に砂金右兵衛実常によって築かれたと云われる。伊達氏の家臣であった砂金氏が前川本城から川崎城を築いて移ってきた。 一国一城令のなか、川崎要害として存続し砂金氏が住んでいたが、元禄15年(1702年)砂金重常が嗣子なく没して砂金氏は断絶、その後は一時宮床の伊達氏が居たが、伊達村詮が川崎要害を与えられ、川崎伊達氏となり以後代々続いて明治に至る。 船岡城:築城年代は定かではない。正治2年(1200年)芝田次郎は鎌倉幕府からの召し出しに応ぜず、参上しなかったことから、幕府の命を受けた宮城四郎家業によって芝田館を攻撃され、滅亡したという。 天文年間(1532年~1555年)には伊達稙宗の家臣四保但馬守定朝が居た。定朝の子宗義のときに四保氏から柴田に改称し、文禄2年(1593年)志田郡桑折へ転封となった。柴田氏は慶長8年(1603年)に伊具郡金津、慶長12年(1607年)に胆沢郡水沢、元和2年(1616年)に登米郡米谷と転封したが、天和元年(1681年)の伊達騒動の後、柴田宗意のときに再び舟岡要害へ戻ってきた。 慶長年間(1596年~1615年)には伊達氏の重臣屋代勘解由景頼が二の丸に住んでいた。元和元年(1615年)原田宗資が桃生郡大瓜から転封となるが、その子宗輔のとき伊達騒動によって原田家は断絶、柴田宗意が舟岡要害に復帰して以降明治まで続く。 角田城:築城年代は定かではないが永禄年間(1558年~1570年)に田手宗光によって築かれたと云われる。田手氏は伊達崎城主の伊達氏一族で伊達朝宗の六男実綱を祖とする。はじめ伊達崎氏を称し、後に田手氏となり江戸時代は伊達一門となっている。 永禄9年(1566年)隣接する丸森・金山・小斎一帯が相馬氏に侵略されると、田手宗光は伊達氏を離反して相馬氏に従った。天正4年(1576年)以降、伊達氏と相馬氏の争いは激しくなり、天正12年(1584年)に伊達氏が再び支配するようになると、宗光の子で父に従わず伊達氏に従っていた田手宗時が角田城主となった。 その後しばらく城主が不在となっていたが、慶長3年(1598年)石川昭光が角田城主となり、一国一城令の後も角田要害として石川氏の居城として代々続き明治に至る。 |
        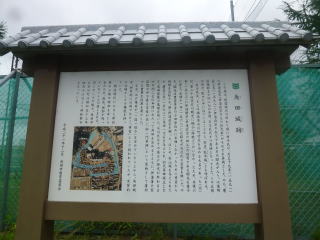     |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第三百六十五弾:北海道八十八箇所&三十三観音&お城・城下町巡り観光 2016年7月9-10日 北の北海道に足を運び、旭川から北部に点在する北海道八十八箇所10か所、三十三観音1か所、お城1か所を訪れました。 9日15:20伊丹空港出発 17:10新千歳空港到達、レンタカーで旭川に向かう。 20:05旭川駅前のホテル到着後繁華街を散策し食事を済ませて就寝。 10日6:30レンタカーで出発、霊場、お城めぐり。 大阿寺:小島秀元師が明治37年来道。石狩を経て、当地に錫を留め、翌38年教会を設立し布教活動を始めたのを当山の開創とします。大正4年霊光山大阿寺と寺号公称し、以来第二世秀澄師、第三世秀隆師、第四世真光尚如師と受け継がれ昭和59年より現住職真光昌雄師が就任しました。 市の区画整理で境内が削られた横長の境内に、庫裡と本堂(昭和54年建立)、納骨堂が一列に並びます。 門を入って右に大師堂があり、本尊子安大師(石像)は、近隣女性の信仰を集め、いつとはなしに花が奉られ、着物が掛けられています。また、当寺は北海道八十八ヶ所霊場札所のほか、朔北七福神霊場になっています。本尊は毘沙門天で、毎年7月7日に七福神まつりを行い多くの信者で賑わいます。 不動院:大正12年5月3日、故阿部昭忠師が現境内の霊水滝前に小堂宇を建立したのが始まりです。 師は不治の病におかされていたところ、明王突然枕辺に現れ「汝の病症は医師の治療のみにては全治するものに非ず、西方の小山の中腹に小滝あり、その水を服用せよ!必ず全治すべし、夢疑う可からず」と告げられたそうです。不思議に思いましたが、そのまま打ちすぎたところ再度同じ夢の示現があり、師は意を決して医師や看護婦の止めるのも聞かず4月7日退院し、友人の力をかり、ついに小滝を探しあて病気も平癒し、師は大いによろこびその霊験あらたかなるを感じ報恩の為小堂宇を建立しました。 実心寺・実心寺観音堂:当山は明治42年、種野憲如師がこの地に錫を留め観音信仰を広めるために開教に専念。大正13年には本堂、庫裡を建立し、知水山・実心寺と寺号を公称。開基憲如師、第二世暁如師、第三世憲暁師、現住職第四世秀憲師と法灯を継承。 昭和46年納骨堂、同53年現本堂、庫裡、同59年檀信徒会館を建立。 入所時には奈良県の吉野桜を移植し「さくら」の寺として永く親しまれていましたが、現在は10本程が春に彩りを見せ近隣の人々の心を癒しています。 境内庭園の中には、十一面観世音菩薩像と西国三十三ヶ所観音霊場があります。 観音堂は、中に十一面観世音菩薩像、弘法大師像を奉安し壇信徒信仰の道場となります。 法弘寺:人は生きていく上で、様々な煩悩や執着、それらから生ずる苦悩の中に生きておりますが、当霊場17番札所のご本尊のお薬師さまはそういった苦悩を癒すお力を持った仏様です。 また、27番札所の御本尊十一面観世音菩薩さまは、慈悲に満ちた相、衆生を仏道に導かんとする怒りの相などの十一のお顔をもたれる仏さまです。名寄市を含む道北は、冬はマイナス35度、夏は35度と1年の寒暖の差が70度近くになる自然の厳しい地域です。しかし、夏の猛暑、冬の酷寒・風雪に耐え、咲いた花はその強さゆえに美しいものです。 当山は開基住職以来、植物や庭園に造詣が深い住職が続いた事もあり、庭には四季折々・種々様々な花、高山植物が咲き誇り「花の寺」として、参詣者や道行く人々の目を楽しませております。ご参詣になられた際には、お薬師さま・観音さまに手を合わせた後、庭の花々の強さや美しさを堪能され、仏様のいのちの真中に生かされている喜びを感じていただきたく存じます。 第27番札所御本尊「十一面観世音菩薩」さまは、慈悲に満ちた相、衆生を仏道に導かんとする怒りの相などの十一のお顔を持たれる仏さまです。 観音さまの慈悲・怒りなどの様々なお顔は、自然と同じであるといえましょう。植物が秋に花や葉を落とすのはやがて来る冬の寒さに耐えんとするものであり、また次の世代に「いのち」をつながんとするためであります。 当山は植物や庭園に造詣が深い住職が続き、庭には多数の石仏・石塔のそばに種々様々な山野草が咲く「花の寺」であります。 観音さまに手を合わせた後、庭の花々に目と心を癒され、また仏さまの世界をお大師さまとともに歩む喜びとしていただければ幸いです。 光願寺:光願寺の前身は通称真言宗説教所です。 堂内に不動明王像並びに弘法大師像を奉安し、町内の信仰を集めていたようです。 昭和25年此の地に新本堂を建立。 真言宗豊山派真珠山光願寺と公称。 「朔北七福神 寿老人霊場」 「北海道三十六不動尊霊場第八番札所」 弘法寺:弘法寺のある美深町は人口6千人ほどの町で地名の由来はアイヌ語の「ピウカ」(石の多い河床)からつけられました。弘法寺は明治39年徳島県地蔵寺第24世服部智信により創立されました。 本尊の弘法大師像は江戸初期の寛文6年、仏師藤原源衛門作が鎮座され、脇仏は平成18年開創の北海道八十八ヶ所霊場本尊薬師如来像と大正2年徳島県出身の女性、山本ラクが観音像奉納により開創した北海道三十三観音霊場第28番札所として本尊聖観世音菩薩像が奉安されています。 また、本堂左側には文化2年京都大仏師塩釜浄而法橋作の精巧な造りの十一面千手観世音菩薩像も祀られている。 観音寺奥之院:明治33年にお山の山頂に、人の姿をした木のこぶが発見され、留萌に逗留していた修行僧の夢枕に立ち「我、観世音の化身なり」と言われました。 そのころ、病に伏せっていた尾作修妙師が同じような夢を見、「我を信仰すれば必ず病が完治するだろう」といわれて以来信仰する様になりました。またその修行僧により入佛開眼されて開基住職となり、尾作修妙尼は悩める人々を救い、現在は孫に当たる康勝師が住職を務めています。本尊天然佛聖観世音菩薩(奥の院)の右横に13番、14番の御本尊を奉安、平成11年に開基百年法要を厳修。 毎年、6月18日当山山頂護摩道場にて火渡り、2月4日節分豆まき法要を行っています。 札所が山頂にある為、火気の使用はおことわりしています。また、お堂に入ることは出来ません。山頂まで約115段の石段があります。 浜益毛陣屋:浜益村(現石狩市浜益区)は石狩湾の北部、北海道の日本海側沿岸のほぼ中央に位置します。かつてはマシケと呼ばれ、松前藩独特の場所請負制度による益毛場所がありましたが、のちにこの場所を二分し、北方を増毛(現増毛町)、従来の益毛を浜益毛(のちに浜益)としました。 安政6年(1859)年に荘内藩は幕府に西蝦夷地警備を命じられ、秋田藩領の増毛を除く浜益から天塩までを領地として与えられハママシケに陣屋を作って総奉行をおきました。 この陣屋は浜益川を天然の堀とし、海岸から500mほど東に入った丘陵部に大手門を設け、5haほどの土地を開いて本陣とし、千両堀といわれる物資輸送のための運河を掘ったそうですが現在は残っていません。 荘内藩は土地開墾に力を入れ、藩内から1300人余の農民のほか、日常生活に必要な大工・鍛冶・味噌・醤油などの職人に至るまで移住させました。しかし明治維新の際には全員帰国し、田畑は荒れ果ててしまったそうです。 15:00新千歳空港に向かう。 16:30新千歳空港到達。 17:55新千歳空港出発。 19:45伊丹空港到達。 今回の旅行、北の北海道に足を運び、霊場11か所、お城1か所をドライブかねて訪れ楽しみました。 今回も広大な北海道のドライブ巡り、広いまっすぐな道、車が少なく、信号も少ない、ストレスを感じない、爽快なドライブ走行満喫いたしました。 |
    
    |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第三百六十四弾:秋田県お城・城下町巡り観光 2016年7月2-3日 北の東北に足を運び、戦国時代に突入するころ、秋田氏(安東氏)が勢力を拡大したエリア、関ヶ原の戦いが終わり、常盤から佐竹氏が国替えで送り込まれると、秋田氏、戸沢氏、本堂氏など、周辺の大名は反対に常盤へと転封された秋田県訪れ、秋田県の南部に点在する比較的マイナーなお城・城下町9か所をめぐりました。 2日16:55伊丹空港出発 18:15秋田空港到達、レンタカーで秋田市方面に向かう。 18:40秋田市のホテル到着後繁華街を散策し食事を済ませて就寝。 3日7:00レンタカーで出発、秋田県の南部の点在するお城をめぐる。 豊島館:永正3年(1504年)豊島玄蕃頭によって築かれたと云われる。 豊島氏は畠山重忠の末裔と云われ、永正3年(1504年)飛騨国より一門十二家二百人を率いて豊島荘に入ったという。 玄蕃頭の子次郎重村は仁賀保氏から妻を迎えていた。元亀元年(1570年)玄蕃頭は周辺の国人と同調して湊城主安東茂季に謀反を起こした。湊騒動とも呼ばれる内乱であったが檜山安東愛季の援軍もあって玄蕃は敗れ、山根館の仁賀保氏を頼って落ちたが、後に許されて豊島館に復帰したという。 天正16年(1588年)湊城主安東高季が脇本城主秋田実季に謀反した湊合戦では、湊安東氏に従って秋田氏に対したが敗れ、その後は由利十二頭のひとり羽川館赤津尾九郎の弟新内が豊島館に入って豊島殿と呼ばれたという。 一説に湊安東氏を継いだ安東茂季は湊城ではなく、この豊島館にいたとされる。 山根館:築城年代は定かではないが由利氏によって築かれたと云われる。 その後仁賀保氏祖である大井伯耆守友挙が修築して居城とした。 大井氏は信濃国大井城主大井朝光の後裔大井友光の子友挙が応仁元年(1467年)仁賀保に下向し、はじめ待居館に住んだが、翌年山根館を修築して居城としたといい、仁賀保氏は友挙の子挙政が名乗った事に始まるとされる。 仁賀保氏は由利十二頭の一人とされ、矢島氏などと争った。 仁賀保氏は友挙・挙政・挙久・挙長・重挙・挙晴・挙誠と七代に渡り山根城を居城とし、豊臣秀吉からも所領安堵を受けたが、慶長7年(1601年)関ヶ原合戦の恩賞により由利一円が最上氏の所領となったため、仁賀保氏は常陸国武田に五千石で移った。 元和9年(1623年)仁賀保挙誠は由利に戻り塩越城を居城として一万石を領した。 西馬音内城:建治3年(1277年)小野寺道直によって築かれたと云われる。 鎌倉時代初期に雄勝郡に入部した小野寺経道の二男道直が由利方面に対する備えとして西馬音内に配され、その後西馬音内氏を名乗った。 天正14年(1586年)最上氏に属した鮭延地方の奪還を目指した有屋峠の合戦では西馬音内茂道も参陣した。 文禄元年(1592年)西馬音内茂道の女を娶って婚姻関係であった由利十二頭の一人八森城主矢島満安が、同じく由利十二頭の一人山根館の仁賀保氏によって八森城を追われ、西馬音内へと逃れてきたが、このことが宗家との間にあらぬ疑いを招き西馬音内氏は満安を自刃させた。このような内紛の中、山形城主最上義光は雄勝郡へ侵攻し文禄4年(1595年)頃には西馬音内氏・柳田氏・松岡氏・深堀氏などが最上方に属した。 慶長3年(1598年)横手城主小野寺氏が湯沢城奪還を目指すと西馬音内氏は再び小野寺氏に属して立ちあがった。慶長5年(1600年)関ヶ原合戦では上杉氏に呼応して東軍となり、上杉氏が最上領から撤退した後は孤立し、最上氏が雄勝郡へ侵攻すると西馬音内氏は城を焼き払って庄内へ逃れ、横手城主小野寺氏は改易となって石見国へ流罪となった。 八口内城:築城年代は定かではないが八口内氏によって築かれたと云われる。 八口内氏は平将門の後裔を称する。 暦応2年(1339年)小野寺氏に攻められ落城したと云われる。 天正14年(1585年)越後の上杉氏が最上の庄内へ出兵することを知った小野寺義道は、鮭延氏が最上に降って以降失った地を奪い返すべく、山北より最上へ侵攻することを計画し、一族郎党に八口内城へ集結するよう陣触を出した。これを知った最上氏は最上義光自ら軍勢を率いて出陣した。両軍は山北と最上を結ぶ要衝にある有屋峠で八日間にわたり激しく戦い、両軍とも多数の戦死者を出した。(有屋峠の合戦) 文禄2年(1593年)豊臣秀吉による奥州仕置きとして検地を行うため、最上の家臣鮭延秀綱が先導して有屋峠を越え雄勝郡へ侵攻した。八口内城主八口内尾張守貞冬(定冬)は横手城の小野寺氏に注進するものの軍勢は集まらず、貞冬は有屋峠の道を堀切り、大木を切り倒し、逆茂木を引て待ち構え、武者三騎にて敵軍に討ち入り討死した。 稲庭城:築城年代は定かではないが小野寺氏によって築かれたと云われる。 小野寺氏は下野国都賀郡小野寺郷発祥で藤原秀郷流を称す。小野寺道綱・重道父子は文治5年(1189年)の奥州合戦の功により出羽国雄勝郡の地頭職となった。 小野寺氏の雄勝郡入部に関しては詳らかではなく、建久4年(1193年)頃に小野寺重道、または建長年間(1249年~1256年)の小野寺経道など諸説ある。 小野寺氏はこの稲庭を拠点として大館、西馬音内城、湯沢城などに一族を配して勢力を拡げ、戦国時代には沼館城へ居城を移したが、その後も稲庭城には小野寺氏の一族が居城した。 文禄4年(1595年)雄勝郡に侵攻した最上氏は湯沢城を落とし、岩崎城を占拠した。翌文禄5年(1596年)にはこの稲庭城も最上氏に攻められ落城した。 横手城:築城年代は定かではない。鎌倉時代から城があったとする説もあるが、天文年間(1532年~1555年)頃に小野寺輝道によって築かれたともいわれる。 小野寺氏は関ヶ原合戦で西軍に属したとみなされ改易となり、小野寺義道は石見国津和野の坂崎出羽守に御預けとなった。 慶長7年(1602年)佐竹氏が秋田に入部すると最上氏より城を受け取り伊達盛重が城代となった。慶長8年(1603年)には須田盛秀が城代となり、寛永2年(1625年)盛秀の子須田盛久が城代となる。 寛文12年(1672年)常陸国戸村城主であった戸村義連が城代となり、以後戸村家が城代として続いて明治に至る。 大森城:文明年間(1469~1487年)、標高120mの山頂に横手城主小野寺泰道の四男小野寺道高が築いたと云う。1580年頃、小野寺康道が入り、「大森城」と称して、3万石で平鹿西部一帯を支配した。1590年太閤検地の際、上杉景勝が入城し、一時、太閤蔵入地の収納所となる。1591年再び小野寺康道が入り、最上氏との対立で大攻防戦となったが、和睦した。1600年「関ヶ原の戦い」の後、最上氏家臣伊良子将監の居城となる。現在は大森公園、大森神社に変わり、曲輪、土塁などが残る。 本堂城:築城年代は定かではないが天文4年(1535年)頃に本堂氏によって築かれたと云われる。 本堂氏は陸奥国和賀郡に勢力をもった和賀氏の一族で、南北朝時代の頃に本堂に土着し元本堂城を築いて居城としたことに始まる。 天文年間(1532年~1555年)に本堂城を築いて山城である元本堂城より移ったとされる。戦国時代の本堂氏の系譜は義親・頼親・朝親・忠親・茂親で、義親は戸沢氏と戦って鴬野で戦死、頼親は金沢城主と戦って野口で戦死、朝親も戦死したという。 天正年間(1573年~1592年)の当主は本堂忠親で豊臣秀吉にの小田原征伐に参陣し、藤田信吉の検地に協力して八千九百八十三石余を領した。 関ヶ原合戦の後、本堂茂親は常陸国志筑八千五百石に転封となり廃城となった。本堂氏は以後交代寄合として明治まで続いた。 角館城:築城年代は定かではない。 応永30年(1423年)角館能登守利邦が小野寺氏に通じて謀反を起こしたため、門屋城主戸沢家盛に攻められ落城、応永31年(1424年)家盛は居城を門屋城より移し、以後代々戸沢氏の居城となったという。 戸沢氏は小野寺氏や安東氏(秋田氏)などと戦って勢力を維持し、天正18年(1590年)豊臣秀吉による小田原征伐に参陣して本領を安堵され、同年藤田信吉による検地が行われ四万四千三百五十石余となった。 慶長6年(1601年)関ヶ原合戦では東軍に属して上杉氏を攻撃した。戸沢氏は慶長7年(1602年)常陸国小河城に四万石で転封、慶長11年(1606年)常陸国松岡へ移り、元和8年(1622年)出羽国新庄へ移り明治まで続いている。 戸沢氏が角館を去ると秋田へ入部した佐竹氏の家臣葦名盛重(義広)が常陸国江戸崎より一万五千石で入部し角館城主となったが、元和6年(1620年)一国一城令によって廃城となった。 葦名氏は三代で断絶し、明暦2年(1656年)佐竹北家の佐竹義隣が出羽国紫島城より角館に入り、「みちのくの小京都」と呼ばれる町並みを整備した。 16:00秋田空港に向かう。 17:00秋田空港到達。 18:45秋田空港出発 20:10伊丹空港到達。 今回の旅行、北の東北地方に足を運び、秋田県の南部に点在する比較的マイナーなお城9か所をめぐり楽しみました。 今回も田園風景を望みながらのドライブお城めぐり、車が少なく、信号も少ない、渋滞なく、ストレスを感じさせないドライブ走行満喫しました。 比較的地味なお城が多かったが、2つのお城だけ、派手できれいすぎるような景観で歴史を感じさせない人工的な建造物に思われ残念でした。 快適な東北・北海道のドライブお城めぐり、もうすぐ制覇ですね、頑張ります。 |
             |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第三百六十三弾:岩手県奥州三十三観音&お城・城下町巡り観光 2016年6月26-27日 東北地方の世界遺産で有名な奥州藤原氏の支配した平泉、その他にも源氏の流れを汲む名門武家、南部氏の遺構が数多く残され、また陸奥土着のさまざまな武家の居城が点在している岩手県に足を運び奥州三十三観音5か所、お城7か所を訪れました。 26日17:00伊丹空港出発 18:25花巻空港到達、レンタカーで北上方面に向かう。 19:10北上駅前のホテル到着後周辺を散策し食事を済ませて就寝。 27日7:00レンタカーで出発、霊場、お城めぐり。 二子城:築城年代は定かではないが和賀氏によって築かれたと云われる。 和賀氏の出自は定かではないか武蔵七党の一つ横山党の中条氏の後裔とも源頼朝の落胤とも云われる。二子城は和賀郡一帯に勢力を持ち天正18年(1590年)の奥州仕置によって滅亡した和賀氏の本城である。 岩谷堂城:築城年代は諸説あり定かではないが、鎌倉時代に千葉胤道によって築かれたと云われる。南北朝時代以降江刺氏が勢力を伸ばした為、葛西氏との争いが多くなり度々合戦が行われた。 明応4年(1495年)の合戦で江刺氏が敗れると岩谷堂城には葛西政信の孫重胤が城主となる。天正18年(1590年)豊臣秀吉による小田原征伐に参陣しなかった葛西氏は、奥州仕置きによって改易となり、岩谷堂城には木村吉清の家臣溝口外記が入った。しかし、葛西大崎一揆との戦いで外記は討死、一揆鎮圧後は伊達政宗の所領となり、家臣の桑折摂津守が入った。万治2年(1659年)伊達宗規(岩城宗規とも)が岩谷堂要害五千石で転封となり、岩谷堂伊達氏となった。この宗規の時代に大手の移転など大規模な改修があった。その後は岩谷堂伊達氏が代々続いて明治に至る。 柳の御所:奥州藤原氏の「平泉館(ひらいずみのたち)」に比定され、政務の場であったと考えられている。 中尊寺:中尊寺は嘉祥3年(850)慈覚大師円仁を開創とする天台宗の古刹です。昭和33年別格大寺に昇格、天台宗東北大本山の称号が許されています。奥州三十三観音巡りの特別霊場(番外札所)でもあります。その後、12世紀のはいめに奥州藤原氏初代清衡によって大規模な堂塔の造営が行われました。藤原氏滅亡後、度重なる火災によって、多くの堂塔が焼失したなか金色堂だけが当初のまま残り、その堂内には奥州藤原氏のご遺体が納置されています。 毛越寺:岩手県平泉町に天台宗 医王山 毛越寺があります。特別史跡・特別名勝に指定されていますが、奥州三十三観音 特別霊場でもあります。毛越寺は慈覚大師円仁が開山し、二代基衡から三代秀衡の時代に多くの伽藍が造営されました。往時には堂塔40僧坊500を数え、中尊寺をしのぐほどの規模と華麗さであったといわれています。奥州藤原氏滅亡後、度重なる災禍に遭いすべての建物が焼失したが、現在大泉が池を中心とする浄土庭園と平安時代の伽藍遺構がほぼ完全な状態で保存されています。 長泉寺:曹洞宗。元は天台宗のお寺であったが、衰退していたのを大原城主の大原広英が再興し、曹洞宗の寺となる。 普門寺:曹洞宗。草創は本山・永平寺より2年古い。開山した記外和尚は三度宗に渡航し、帰国の際に皇帝より宝物を賜り、現在も寺宝として残る。本尊の聖観音もその一つで県有形文化財。 大善寺蛸浦観音:別名「蛸浦観音」。ご本尊は本村小向の佐々木家にて寄贈したものという。尾崎山の麓の海岸にあり神社に祀られている。 大槌城:大槌城(おおつちじょう)とは、岩手県上閉伊郡大槌町にかつて存在した日本の城(山城)。代々、大槌氏が城主を担当した。室町時代に大槌次郎によって築造されたといわれている[1]。浜崎城とも呼称されていた。規模は東西が700m、南北が100mに及ぶ。 鍋倉城:築城年代は定かではないが天正年間(1573年~1592年)に阿曽沼広郷によって築かれたと云われる。 阿曽沼広郷は代々遠野保を領し横田城を居城としていたが、猿ヶ石川の度々の反乱に川向かいに住んでいる諸士の往来に不都合であったため、鍋倉山に新城を築いてた。この新城も横田城と称していたが、南部氏の治世となって鍋倉城と改称された。慶長5年(1600年)広郷の子広長のとき、南部利直に従って山形に出陣中に一族で鱒沢城主である鱒沢広勝の謀叛によって遠野を乗っ取られ、以後南部領となった。寛永4年(1627年)八戸から南部直義が遠野に約一万石で転封となり、城を改修して城下町を整備した。このとき横田城から鍋倉城へと改称した。直義は南部家の重臣として盛岡に居ることが多かったため、先代で養母である清心尼が遠野の政治に関わることが多かったようである。以降、八戸南部氏(遠野南部氏)が代々続いて明治に至る。 土沢城:慶長17年(1612年)南部氏によって築かれ、縄張は南部家臣野田内匠頭直盛が行ったという。最初の城主は新堀城主江刺隆直で二千石を与えて移駐させたという。南部氏は度々伊達氏と国境を巡って小競り合いがあり、伊達氏が築いた浮牛城に対する備えとして国境に近いこの地に拠点となる土沢城を築いた。江刺氏は葛西氏の重臣であり、奥州仕置きにより改易された葛西氏の旧臣を操る伊達氏を牽制する役目も担っていたとされる。 寛文10年(1670年)の総検地に際して廃城となり、その後も城内小路を統治所として七代続いたが江刺氏は天明元年(1781年)お家騒動によって断絶した。 花巻城:築城年代は定かではない。古くは前九年の役の安倍頼時の磐基駅に擬定されている。花巻城の前身は鳥谷ヶ崎城といい稗貫氏の居城であった。稗貫氏の出自は諸説あるが、鎌倉時代頃に稗貫郡に入部し、はじめ小瀬川館(あるいは瀬川館)を居城とし、ついで本館(十八ヶ城とも)、最後に鳥谷ヶ崎城を居城とした。永享8年(1436年)南部を支援した薄衣氏が稗貫氏の十八ヶ城を攻めた際にここに陣を構えていることから、鳥谷ヶ崎城の築城はそれ以後という。天正18年(1590年)豊臣秀吉による小田原征伐に参陣しなかったため、稗貫広忠は奥州仕置で領地を没収され、鳥谷ヶ崎城には浅野長吉が滞在し、長吉は浅野重吉を目代として置いた。稗貫広忠は和賀義忠が浅野家臣後藤半七の籠る二子城を攻めた際、これに呼応して鳥谷ヶ崎城を攻め落とし奪還に成功した。しかし、天正19年(1591年)には一揆を平定する秀吉の軍勢に二子城・鳥谷ヶ崎城ともに落城し、稗貫広忠は大崎氏を頼って落ちたという。一揆平定後、南部家臣北秀愛が八千石を領して花巻城代となり近世城郭へと改修された。慶長3年(1598年)秀愛が死去すると替わって父北信愛が城代となる。 慶長5年(1600年)南部氏が山形に出陣中のときを狙って和賀忠親が一揆を起こし花巻城へ押し寄せた。一揆軍は本丸まで攻めよせたが、信愛は城内にいた13名の士卒と婦女子だけで持ちこたえ、北十左衛門の援軍が駆けつけ一揆軍を退けた。慶長18年(1613年)信愛が没すると南部利直の次男政直が二万石で城主となった。 政直没後は嗣子なく城代が置かれ、以後明治に至る。 17:00終了。花巻空港に向かう。 17:30花巻空港到達。 18:55花巻空港出発。 20:25伊丹空港到達。 今回の旅行、東北の岩手県に足を運び、点在する奥州三十三観音5か所、お城7箇所をめぐり楽しみました。 藤原家やその他の武家で歴史的に深い岩手県、立派な霊場、立派なお城が目白押しでした。 ほとんどの城跡は城跡公園と変化し規模の大きさを物語っていました。 世界遺産の平泉は何回か訪れたことがありましたが整備ができすぎ、道路も広く、きれいに仕上げており、観光に力を入れすぎて逆に歴史を感じないような景観のような気がします。 整備しすぎてきれいすぎる、古さを感じない歴史を感じない、改築した建造物がほとんどで現存する歴的建造物は数少ないのは残念です。 |
             |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第三百六十二弾:神奈川県お城・城下町巡り観光 2016年6月18日ー19日 関東地方の相模国と武蔵国という「歴史的に極めて重要な土地を含み、鎌倉幕府はもとより、戦国時代も小田原の北条氏が強烈な存在感を示し、古都鎌倉、小田原城など、歴史散策の見どころが多数ある神奈川県に足を運び、点在するお城・城跡10か所を訪れました。 18日13:50新大阪駅新幹線のぞみで出発 16:40東京駅到達、タクシーで赤坂のホテルに向かう。 17:00赤坂のホテル到達 17:30品川の新高輪プリンスホテルに向かう。 17:50新高輪プリンスホテル到着 18:00講演会出席 20:00講演会終了、懇親会。 21:00赤坂のホテルに向かう。就寝。 19日8:00レンタカーで神奈川県内お城を巡る。 衣笠城:衣笠城(きぬがさ★★神奈川県横須賀市衣笠町、標高102m、比高80m。)は大谷戸川と深山川に挟まれた半島状の丘陵に位置する。 康平年間(1058-1064)三浦為通によって築城されたといわれ、以後為継・義継・義明の四代にわたり三浦半島経営の中心地であった。 治承四年(1180)八月源頼朝の旗揚げに呼応して、この城に平家側の大軍を迎えての攻防戦は、いわゆる衣笠合戦として名高い。この位置は衣笠城の大手口で、坂を登って滝不動に達する。居館はその附近にあったかと推定され、一段上に不動堂と別当大善寺がある。さらに、その裏山に金峯山蔵王権現を祀った社が存在した。また、その西方の最も高い場所が、この城の詰の場所であったと伝えられている(『横須賀市資料』)。 宝治元年(1247)北条氏によって三浦泰村一族が滅亡し、佐原氏が継承した以後廃城になったとみられている(『日本城郭大系』)。 現在の遺構は削平地以外に明確ではないが、なるほど城郭に適した立地、地形をなしている。 物見に使われたという巨石があり、その下から武器などが出土したという。城址は「衣笠山公園」ではないので注意したい。横浜横須賀道路衣笠ICを出て、坂口集落に進み、大善寺を目指すとよい。 新井城:三浦一族滅亡の地で、面積約128ヘクタール。相模湾に突き出た小半島に位置し、小綱代湾と油壺湾に挟まれて、三方をいずれも海で囲まれ、切り立った断崖である。陸地に通ずる路は、北方約3キロの大手の引き橋で、この橋を切って落とせばどこからも攻め込まれないようになっていた。引き橋は後に地名になったが、ここで北条軍は橋を引かれて渡ることが出来ず、三浦勢に時を稼がれたという。現在は関東大地震による隆起で、往時の面影は薄らいでいるが、当時としては大軍をもっても攻めがたく、わずかの手兵で三年間も持ちこたえた。いずれにしても室町期の居館としての新井城の名残りは、本丸を中心にめぐらされている空堀に往時を偲ぶことができる(『三浦市・現地説明板』)。 築城年代は不明だが、衣笠城を本拠とした三浦氏が滅亡すると、それを継承した佐原氏の拠点として築かれたようである(『三浦半島城郭史』)。明応三年(1494)には、城主・三浦時高と養子・三浦義同の内訌で落城して三浦義同が奪取、彼は一時大田道灌に従ったが、その後、山内上杉氏に属している。戦国期に至った永正九年(1512)から同十三年に亘って、北条早雲と三浦氏はこの城で攻防を繰り広げている。早雲は新井城を力攻めで落とすことができず、持久戦となり、玉縄城を築いて武蔵方面の援軍を断ち切った。兵糧尽きた三浦義同は子・義意と共に城門を開いて打って出て、華々しく討死を遂げ、一族は滅亡した 城址は、ほとんどが東京大学の敷地になり関係者以外は立ち入ることができないが、ハイキングコースから傍観することができ、大規模な空堀と土塁を確認できる。おそらく後北条氏時代の遺構であろうが、周辺は断崖で、その要害ぶりを垣間見る。また近く「内の引き橋」と呼ばれる堀切が配され、さらに3㎞離れた所に「引き橋」という地名がある。ここまで城域なのかは躊躇するが、三浦半島の城址としては最も優れた史跡であろう。なお「油壺」の由来は滅亡時に三浦一族が投身し、湾が血で覆われたことによるという。 鎌倉城:鎌倉時代、源頼朝の築城。彼が鎌倉に幕府を開いたのは、源氏ゆかりの地であり、三方を馬蹄形の連丘に囲まれた理想的な都城の地形であったことによる。鎌倉城の範囲は広大で、稲村ヶ崎から飯島崎までに連なる丘陵に囲まれ、南は相模湾に面している。また、七ヶ所の切通しを作って出入口とし、防御度を増させている。 鎌倉城での戦いは3回あり、正慶二年(1333)新田義貞によって攻められ、北条高時以下は自刃して幕府は滅亡している。建武(1337)北畠顕家らが攻め込み、杉本城とともに落城。最後は、文和元年(1351)新田義興らが初代鎌倉公方・足利基氏を攻め込み、落城している。 以上の合戦ではいずれも守備側の敗北に終わり、その後、南北朝時代に至ると要害性が失われ、鎌倉城をめぐる攻防戦は行われなくなった(『日本城郭大系』)。 永禄四年(1561)長尾景虎が、上杉憲政から、鶴岡八幡宮にて上杉姓と関東管領職を譲られたのは有名な話である。 玉縄城:甘縄城とも。標高71m、比高45m。 永正九年(1512)北条早雲(伊勢新九郎長氏)築城。当時小田原城にいた早雲は、関八州制覇の過程で、三浦半島の新井城を本拠とする三浦義同と衝突、三浦半島の基部であり交通の要衝であったこの地に向城を築いた。永正十三(1516)新井城に兵糧を送ろうとした上杉朝興の軍勢を早雲は玉縄城の北方に陣取って対抗、まもなく新井城は落城した(『北条五代記』)。 大永六年(1526)二代当主・北条氏綱の弟・氏時が城主となり、房州国・里見氏が鎌倉に乱入した際、彼は玉縄城を背に、戸部川(現・柏尾川)で防戦した。氏時歿後は猛将・北条綱成が城主になる。 永禄四年(1561)上杉景虎(謙信)の小田原城攻撃の帰路、鶴岡八幡宮へ拝賀し管領就任を披露すべく鎌倉へ立ち寄った際に玉縄城は囲まれたが、城主・綱成は不在だったもののその長子・氏繁がよく守ったので越後へ引き上げた。 永禄十二年(1569)武田信玄の小田原攻めの時は、藤沢のおんべ山砦(大谷城)を落としたものの玉縄城は素通りしている(『北条記』)。これは上杉謙信でも落とせなかった堅城ぶりを信玄がよく理解していたからだとされる(『日本城郭大系』)。 綱成の引退後は氏繁が城主となり、天正六年(1578)氏繁が歿するとその子・氏勝が城主となった。天正十八年(1590)豊臣秀吉の小田原攻めのとき、氏勝は山中城へ援軍したが、大軍の前に落城。恥辱を感じた氏勝は、当主・氏政が小田原城に篭城するよう命じたが、「玉縄城を枕にして討死すべし」と答えて玉縄城に籠城。頑強に抵抗したが、徳川家康の策によって、氏勝の叔父である大応寺住職・了達を通して説得し、開城となった。その後、本多正信、水野正忠などが入城したが、元録十六年(1703)に廃城(『日本城郭大系』)。 城は大規模な山城で、後北条氏系城郭有数の堅牢ぶりであったが、本丸跡には清泉女学院が建ち、また周囲も新興住宅地と変貌した。「諏訪壇」など、ところどころに遺構が残ってはいるようだが、細かく散策できない状況である。昭和三十年代の航空写真を見るに、本当に残念なことである。 大庭城:標高42.8mの大規模な平山城。東方を引地川、西方を小糸川に挟まれた要害の地にある。 成立年代は不明で、室町時代後半に相模国で威勢を誇った扇谷上杉氏の拠点されている。明応八年(1499)には、「一人大庭堅其塁、大庭氏館、此去不遠」と記され(『玉隠和尚語録』)、扇谷上杉氏の「一人」が大庭城で守りを固め、大庭氏の居館はその近くにあったことが分かる。(大庭氏館は大庭城址南西の城(たて)にあったと考えられている。)また、その家宰・太田道灌の勢力が及んでいたようでもある。 戦国時代、永正九年(1512)に北条早雲は鎌倉入りしており(『快元僧都記』)、すでに藤沢一帯も後北条氏が領していたとされる。しかし、戦国期の史料も少なく、福島左衛門という人物が城主であったらしい(『小田原衆所領役帳』)ことを知るのみである。 従来、大庭城は玉縄城の支城とされ、後北条氏時代には廃城になっていたともされるが、出土した遺構や城の規模から、後北条氏によって改修された可能性が高い(『日本城郭大系』)。 城址は、かつて約南北800m、東西250の台地の全域を城域とし、北に駒寄・二番構、東に門先、西に裏門・城下などの地名が残ることから、周辺にも城に関連する施設や大規模な城下が存在していたとされる。 しかし1970年代ニュータウン化で北側が宅地化され、現在は南部の450mほどが城址公園として名残りをとどめている。 広大な大庭城址公園だが、意外にも良好に遺構が残存している。現在四つの大郭に、馬出しのような小郭、腰郭、大規模な空堀、土塁などが散見され、城好きには是非とも藪の中に進入して確認されたい。 深見城:境川に面した台地上に築かれている。北側から東側は切り立った急崖となっており、境川との比高は15m程度で、天然の要害を形成している。西側は天竺坂の大規模な掘割り、そして南側は平坦地形を加工して曲折を多用した二重の堀と、土塁構造が密接に連携した東西2つの虎口(門・出入り口)などを構築し、要害地形を形成している。その縄張りは構造は歴史遺構上、高い価値を持つもので、発掘調査の成果から、利用は14世紀末頃より16世紀末頃までの年代幅の中にあることが分かっている。一方、現存する城址の構造をみると、軍学による城制に整合することから、16世紀戦国時代の遺構であると思われ。 一説に、享徳四年(1452)頃、山田伊賀守経光が城主であったという(『新編相模国風土記稿』)が、この人物の詳しいことは分かっていない。 ほとんど手付かずで保存されたようで、遺構がよく確認できる。また、戦国末期の後北条氏の改修と思われ、屈折した空堀を多用した注目に値する城郭である。主郭にふたつの虎口があるのは珍しい。その分、防御力は下がるだろう。また、主郭を巻く二重の空堀の外には、これといった城塞設備が見られない。したがって南側の防御力が薄くなっているが、これは軍事的な城郭として構築されたのではなく、武将の居館を主な目的とされたからではないだろうか。 桝形山城:室町時代の築城で比高57mの山城。その起源は源頼朝の重臣である稲毛氏が枡形山山腹の居館の詰め城として築城したものであったという。鎌倉の北方を防御する山城として重要視された。 その後、北条早雲が関東進出中の永正元年(1504)、今川氏親とともに扇谷上杉朝良に味方した際、この枡形山に布陣した。また後北条氏が関東に勢力を拡大し、江戸城を包囲した時にもこの枡形山が改修されたようである。一説に、永禄12年(1569)、甲斐の武田信玄が後北条氏の小田原城を攻撃した際にこの近くを通過したが、この際にも後北条氏の一拠点として横山弘成という武将が守っていたという。 現在は生田緑地の一角としてハイキングコースにもなっている。城址である頂上部は非常に広大で、展望も抜群である。城としての遺構は認められないものの、すこぶる築城に向いた都心に稀有な地形であり、周囲は切り立った地形であることから特段の防御施設はもともと無かったのかもしれない。 茅ヶ崎城:標高32m、比高20m。200m×100mの山城で、郭・土塁・空堀・虎口が良好に残る。 室町中期以前の上杉氏か、上杉氏に替わって相模を支配した後北条氏による築城でないかという。小机城から約4キロほどの近距離であり、戦国時代にはその支城として重要な役割を果たしていたとされる。。 小机衆のひとりでこの周辺を領していた座間氏が城代に入ったといわれる。後北条氏の勢力が鶴見川流域から早淵川周辺に拡大する中で利用・改修されたと思われる。相模統治が確立し、その勢力が関東一帯に広がるにつれ茅ヶ崎城の重要性は薄れ、大きな改造がなされないまま廃城を迎えたとされている。よって現在残る遺構は後北条時代中期のままなのであろう。 遺構は大変保存度が良い。ただ、小机城と比較すると、空堀はやや小さく、本格的な虎口も見られないことから、小机城よりも早い時期(後北条氏前期)に築城され、その後、大きな改築もなかったものとされている(『日本城郭大系』)。 城址は小高い山全体が要塞化されたもの。しかし、近く公園化の計画もあるようで、重機が荒らした痕跡も見られた。今後の行方が心配である。 小机城:飯田城、根古屋城とも。標高42m、比高22m。築城年代築城者不明だが、室町時代・豪族小机氏が築いた館が発祥ともいう。 城郭としての初見は文明八年(1476)長尾景春の乱で、城主・矢野兵庫助は景春方に味方した。一方、上杉氏配下の太田道灌は、豊島泰経を江古田原の合戦で破り、平塚城、石神井城を落とし豊島氏残党と笠原、小机、矢島氏が籠城する小机城を文明十年(1478)一月に攻撃する。この時、泰経は小机城に逃れていたという。この合戦で道灌としては珍しく2ヶ月という長い期間をかけたらしいが、鶴見川を挟んだ対岸に亀之甲山陣城を敷いて攻め落としたという(『太田道灌状』)。また道灌は「小机はまず手習いの初めにて、いろはにほへとちりぢりとなる」と詠じて士気を鼓舞したとの伝説もある。 その後廃城となっていたが、戦国時代・後北条氏時代には小机城が重視され、「小机衆」という軍団が組織し、城代に笠原信為を入れて大改修を実施した。また氏康の子である三郎氏秀が城主になるなど関東進出の前線拠点であった。 天正十八年(1590)豊臣秀吉との小田原城合戦では、小机城は笠原虎千代が守備していたが、豊臣軍の攻撃を受けることなく後北条氏が降伏したので、実際に戦いはなかった。徳川家康の関東入封によって小机城は廃城となった。 遺構保存度の芳しくない神奈川県にあっては、全国に誇れる中世城郭である。このような本格的な城郭が新横浜のスタジアムが望める都会に残っているとは驚き。 神奈川台場:慶長十五年(1610)造立。寛永十一年(1633)守殿造営(『新編武蔵国風土記稿』『日本城郭大系』)。 神奈川県には、徳川将軍が鷹狩りや遠出の際に宿泊する施設として、いくつかの御殿が築かれた。(他に中原御殿、藤沢御殿、小杉御殿など) 神奈川御殿も周辺には土塁や空掘を設けて要塞化し、家臣屋敷などが立ち並んでいたと思われる。伝承によれば、「成仏寺」の敷地を徳川家が召し上げて御殿を造営したという。 横浜市神奈川区神奈川本町、「成仏寺」の北側、JR横浜線と京急本線の間の地域が跡地とされるが、他の御殿と同様に遺構は何ら残っていない。近く「仲木戸」という駅名が城塞のあったことをわずかに偲ばせる。 17:00東京駅に向かう。 18:00東京駅到達。 18:10東京駅新幹線のぞみで出発 20:35新大阪駅到達。 今回の旅行、神奈川県に点在するお城10か所をめぐり楽しみました。 大都会の神奈川県、信号・踏切・車の多く渋滞に何度も巻き込まれ移動に時間かかりましたが何とか10か所のお城をめぐることができました。 今回の城跡、数か所の城址公園に変貌している箇所以外はめだった城跡は存在せず、大半が地味なものであり見つけるのが苦労を要しました。 |
           |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第三百六十一弾:北海道八十八箇所霊場&北海道三十三観音霊場&お城巡り観光第5弾 2016年6月11日ー12日 北の北海道の道南に足を運び、点在する北海道八十八箇所11か所、北海道三十三観音4か所、お城2か所を巡りました。 11日15:45伊丹空港出発 17:10新千歳空港到達、レンタカーで苫小牧方面に向かう。 望洋寺:当山は大正13年開基住職吉田守賢師が、この地に来錫し開教を始めた事に濫觴します。昭和2年幸町に不動院教会所を設立し認可を受け、その折、総本山智積院より下付された不動明王(二童子付)が、現本堂に安置の御本尊です。 昭和10年ころ、当初から目標でした寺号公称を目指し寺域創りに奔走します。昭和12年遂に現在地に移転しました。本堂を落成して望洋寺と寺号公称し、爾来、各行事を通じて教化活動も活発に展開し、檀信徒の安らぎの道場として基盤が確立されました。その後、納骨堂、大師堂、護摩堂、客殿等の諸堂が落成し伽藍の輪奐も整ってきました。20数年前より毎月写経会、大師講、護摩供、詠歌講を開催し、また毎年全国の霊場に巡拝し共に感動を味わっています。 白老陣屋:安政3年(1856),幕命により仙台藩が築いた陣屋跡。当時植えた松,土塁,堀がそのまま残されている。 18:30室蘭方面に向かう。 19:00室蘭駅前のホテル到着後周辺を散策し食事を済ませて就寝。 12日6:30レンタカーで出発、日高方面に向かう。 日高寺:明治四十三年香川県(三郷郡三野町旧吉津村)出身の琢磨宥文がこの地に説教所を建立したことをもって開山としています。 宥文は明治四十一年四十歳のときに、北海道開教をすすめられ、香川県からやってきました。おそらく笠谷霊海(亮昌寺)、原田智巌(高野時)らのすすめがあったと思われる。 (北海道三十三観音よみがえった霊場 資延憲英著参照) 大正十五年に建立された八十八ヶ所霊場が、裏山に有り約一時間で巡ってくることができる。 当初は軟石作りの為、痛みも激しくなったので、平成五年九月に新しく八十八ヶ所を御影石にて建立をしました。 龍徳寺:高野山真言宗の末寺で、明治三十六年、旅の僧侶が説教所を建てる。明治四十一年大阪の宝珠院住職少僧都、仙田梁応が布教をはじめ説教所の設置を出願し、翌四十二年許可になった。寺号公称は大正十三年十一月認可となった。 明治四十五年本堂新築、昭和三十二年開創五十周年法会を営む。同四十三年納骨堂新築、五十一年庫裏、会館新築、六十二年山門新築、十五年本堂新築、開創百周年法会を営む。御本尊金大日如来、脇仏は馬頭観音、弘法大師尊像、平成二十六年現在寺歴百十一年である。 シベチャリチャシ:全道のアイヌを率い、和人と戦ったアイヌ民族の英雄シャクシャイン。銅像の建つ真歌公園は、そのシャクシャインが寛文9年(1669)、「寛文九年蝦夷の戦い(シャクシャインの乱)」で最後の砦とした場所である。 シャクシャインの乱とは、交易時の不平等に怒りを募らせたアイヌの長シャクシャインが、全道のアイヌに呼びかけ一斉に蜂起した争い。一時は道南地方(現長万部町国縫)まで攻め寄ったものの、松前藩の鉄砲隊に徐々に後退。最期は和議の申し出という口実のもとに謀殺され、砦も焼き払われたと伝えられている。 円昌寺:明治30年、開基龍長和尚は、神奈川県大磯町西小磯に在った白岩山円昌寺(東寺派)を現在地に移転し、寺号公証。 三石山円昌寺(本尊金剛界大日如来)創立。 明治42年本堂、庫裏新築。 明治45年裏山に、巡路三千米の新四国八十八ヶ所完成。真言宗各宗派連合長者土宜法龍師を導師として開眼法要。 大正4年龍神堂建立。 大正5年北海道三十三観音霊場 三十一番聖観世音像安置。(現在祀られている観音像は昭和53年再安置された聖観世音像である。) 大正15年鐘楼堂完成(現存)。昭和19年大梵鐘供出させられる。 昭和6年三石観音堂入佛開眼(優駿豊平号大印の等身像上に馬頭観音を安置)。 昭和30年堂宇祝融。昭和33年三世住職小笹典之師晋山。 昭和39年本堂再建落慶。昭和47年現梵鐘開眼供養奉修。 平成3年当山開基百年記念慶讃大法会執行。 年中行事:3月10日涅槃会、4月20日正御影供会、7月15日弘法大師降誕会お砂踏み、11月8日十夜法会。 山内のツツジの見頃は五月下旬から六月上旬です。 妙龍寺:妙龍寺は北海道小樽市にある寺院です。 明治15年に開山して以来、北海道の開拓とともに歩んできました。お寺の前には地獄坂という坂があります。 この坂の上には高校・大学があるのですが、その昔は建物が少なく、 山からの吹雪が容赦なく学生達に襲いかかっていました。 その様子を見て、誰が名付けたか地獄坂と呼ばれるようになりました。 地蔵寺:当山は昭和3年4月40歳にて仏門を志した細川智隆和尚にて昭和5年10月24日高野山真言宗広尾教会を設立。16年10月8日遷化、同年11月千葉憲應師晋山、檀家強化に勤めましたが18年、室蘭市に転寺します。同年林賢修師晋山し、昭和21年5月岩手県に転寺しました。その後昭和21年5月宮下栄厳師が晋山する。27年には宗教法人地蔵寺と寺号公称し、昭和32年広尾新四国八十八ケ所開創のため21日間水だけの苦行断食し寺裏の丸山に開創しました。 春季大祭4月24日、秋季大祭は11月10日に厳修しています。 先代栄厳僧正は42年本堂、52年回向殿納骨堂を建立、境内整備にも努力し、昭和60年11月1日遷化。その後現住栄隆晋山、現在に至ります。祈祷を重点にし各種お払い、特に2月11日の星祭厄払いは盛大です 高野山寺(金剛閣)、高野山寺:雄大な日高山脈のふもと、江戸時代から純度の高い砂金を産出する清流「歴舟川」が沃野を潤す大樹町。 当山は昭和の大仏師「松久宗琳」入魂の大日如来と不動・愛染両明王が、鎌倉様式を忠実に再現した本堂に鎮座する古刹です。 開基は大正6年、初代住持佐藤密道が、明治の末、遠くインド、ミャンマーを遍歴し、ミャンマーの名刹シェダゴンパゴダで五粒の仏舎利を授かり、当山に奉安したのを濫觴とします。また、開基がその師、高野山奥の院維那、八王子金剛院主「田和諦観大和尚」から伝えられた古佛十一面観世音及び弁財天をも奉安します。 境内には樹齢二百年にも及ぶ松(一位)と桐が仲良くたたずんでいます 帯広方面に向かう。 新正寺:明治末、伊藤キク37歳が、受戒し「栄心」と名のり、教会所設立、その後、新正寺となります。 現本堂は御堂作りで大正2年、竹田忠三郎の寄進にて建立されました。 古くから、加持、祈祷の寺である44番札所御本尊は、十一面観世音菩薩です。 五穀豊穣の願いが込められています 真隆寺:明治39年真言宗説教所として開山。大正15年に北海道開教を志した長谷川真隆和尚が当山説教所主任として着任、日夜真言密教の教えを広め加持祈祷などによる人々の救済に力を注ぎ、またその霊験あらたかでした。 現在はスキー場のある明野の山に四国八十八ケ所霊場本尊の石仏を奉安し日増しに信徒が増加し永続維持の基盤ができ昭和6年寺号公称の認可を受けて第一世住職を拝命しました。 真隆和尚遷化後は昭和26年英隆和尚が第二世住職を拝命し本堂、納骨堂など境内整備等は英隆和尚によってなされ、英隆和尚遷化後は隆憲和尚が第三世住職を拝命し現在の庫裏納骨堂、弘真閣は隆憲和尚によってなされました。現在、四国八十八ケ所霊場本尊の石仏は境内の北側に奉安されています。 松光寺:境内は観音。八十八ヶ所石仏があり四季をとおしてありがたい思いをいたします。 高野寺:大正3年中富良野弘照寺開基住職岩田實乗師により高野山説教所として開基。昭和3年末富山県出身高野山で修学を積み釧路西端寺から来帯した大多賀清洞師夫妻が借地に建てた12坪の大師堂に定住して大師信仰の宣揚に勤めました。 昭和11年本堂新築、同18年高野寺公称、十勝川温泉協会設立糠平八十八ケ所開創、糠平寺創立。更に昭和46年現在地に移転新築し同58年82歳で遷化の間、生涯を寺門興隆と教化に専念し、二代住職実忍に至ります。 堂内には、日本唯一英霊馬頭観世音菩薩、子安弘法大師、宇賀大明神、タイ国御請来仏舎利と降魔釈迦如来、本堂内に八十八ケ所御尊像が奉安されています。 弘真寺:当山は大正10年、帯広近郊の川西村美栄に薬師如来を本尊とする利生寺の開基から始まります。 昭和4年には十勝四国八十八ケ所霊場を開創。昭和30年帯広市富士町に本堂を移転改築、昭和34年寺号を日月山 弘真寺に改め、昭和58年帯広市西24条南2丁目(西帯広)に伽藍を移転建立し現在に至っています。 祈願寺・供養寺として地域に根ざし熱心に手を合わせる参詣者がみられます。 十勝四国八十八ケ所霊場の他に、十勝管内6ケ寺院で干支の石を奉安している十勝北斗十二支めぐりでは、「寅」と「卯」を奉安しています 照覺寺、照覺寺(三味堂):当寺は、昭和10年清水町御影の照明寺住職山本祐澄により当町に大師教会光明支部設置の許可を受け、大師信者である広瀬ヨノ宅にて教線を張ったのに始まり、その後、山本師の弟子前川光榮が引継ぎ高野山芽室教会となりました。 昭和17年東2条5丁目に本堂を設立、昭和19年、西沼行貫が教会主管代務者となり、同24年寺号公称し開基住職に。 師は寺門興隆と布教に心血を注ぎ寺院を整え、同45年行貫遷化後、師の妻行基尼は同47年行眞が晋山するまで寺を守りました。行眞は住職就任直後、足掛け6年かけ寺を現在地に移転し普請します。 当山には行貫の弟子勇弘道が謹刻した千体の地蔵菩薩をおまつりしている御堂があり「北海道十勝北斗十二支 福徳神めぐり」の霊場(全六ケ寺)になっています。そのなかで、「申」と「酉」の守本尊とエトの霊石を奉安しています。 三昧堂は、当寺の施設の中にあるもので、住職が専ら修法する道場で、一般の檀信徒の入堂はできません。 ここの本尊は不動明王でその他、歓喜天、ダキニ天、龍神、聖徳太子などが奉安されています。 15:30新千歳空港に向かう。 17:00新千歳空港到達 17:55新千歳空港出発 20:10伊丹空港到達。 今回の旅行、北の北海道に足を運び、道南に点在する北海道八十八箇所11か所、北海道三十三観音4か所、お城2か所を巡り楽しみました。 広々とした真っ直ぐな道、地平線を見ながらのドライブ、本州では味わえない風景、最高!、何回訪れても素晴らしい、癒されるドライブ霊場巡りでした。 札幌、旭川に点在する寺院は小規模の物が多かったですが、道南に点在する寺院は立派な建物が多く感動いたしました。何らかの歴史的背景によるものなのでしょうか。 何回も訪れたいドライブ観光、爽快で、癒されて、楽しめた北海道道南ドライブ霊場お城巡りでした。 |
                |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第三百五十七弾:埼玉県お城・城下町巡り観光 2016年5月14日ー15日 武蔵国は古くから武士団の力が強く、平安後期以降の館が多く残る。鎌倉幕府の成立に尽力した武士たちは、館からより強固な城に拠点を移したが、やがて関東に転封された徳川家康によって多くが廃城となった埼玉県のお城10か所を訪れました。 5月14日13:50新大阪新幹線のぞみで出発 16:25東京駅到達、タクシーでパークタワープリンスホテルに向かう。 16:45パークタワープリンスホテル到達 17:30講演会出席 20:00講演会終了後懇親会 22:00就寝。 15日8:00レンタカーで埼玉県に向かう。 お城・城下町めぐり。 赤山城:1600年 初代伊奈忠次は家康の関東入国とともに伊奈町に関東郡代として関八州.江戸幕府の直轄地 として治めたが、1629年寛永5年三代忠治tadaharu の時に八千石で赤山領に移り、 赤山城を創建10代163年間居城とした。 広さは2万4千坪の陣屋を構え外堀は水が、内堀は空堀で内側には土塁が築かれていた。 本丸、二の丸だけで11万平方メートルからなる小さな城下町であった。 伊奈家は家康入国以来関東全域の治水を負い、「坂東太郎の利根川」と「暴れ荒川」の洪水を農民らと抑え、用水を引き農地を開き、すぐれた土木技術により治水灌漑.新田開発を民と共に行い、民の中から指導者を育て苦楽を共にし信頼を勝ち得た。江戸時代の治水、新田開発に大きく貢献、初代忠次.三代忠治 は利根川.荒川から関東平野に新しい水路を作り諸国からの水運を計り、江戸の繁栄をもたらし、初代忠次から三代忠治に至る60年間で徳川家の禄高を60万石から120万石にした。 そして、関東入国以来50年江戸の町は爆発的な人口増加により緊急に江戸80万の民の水を確保するため、1653年 保科正之らにより三代忠治が奉行を命じられ多摩川の水を引いてくる上水道.玉川上水事業が行われた。 しかし偏見を持った知恵伊豆松平信綱に国策である玉川上水事業を川越藩の野火止用水事業に利用され、追求した忠治は疎んじられ閑職に追われた。 岩槻城:長禄元年(1457年)太田道真・道灌父子によって築かれた。 関東管領扇谷上杉持朝は古河公方足利成氏に対抗するため、太田父子に命じて築かせた。大永4年(1524年)小田原の北条氏綱は扇谷上杉朝興の居城である江戸城を攻め落とし、翌5年には岩槻城に侵攻、家臣渋江三郎が北条氏綱に内応したため落城、北条氏は渋江三郎を守将とした。 石戸城へ逃れた太田資頼は、享禄3年(1530年)岩槻城を奪い返した。資頼の子資正が継いだ後、扇谷上杉氏が滅び、山内上杉氏も越後国長尾氏を頼って落ち延びると、資正は上杉政虎(謙信)と結び、北条氏に対抗する。 しかし、永禄7年(1564年)里見氏等とともに北条氏と戦ったが破れ、北条氏の謀略により長子氏資が寝返り、資正は佐竹氏を頼って落ちた。天正18年(1590年)豊臣秀吉による小田原征伐では、浅野長政等が攻め寄せ落城した。 徳川家康が関東に入部すると、高力清長が二万石で入封するが、江戸時代を通じて激しく城主が替わっている。 伊奈氏陣屋:天正18年(1590年)伊奈忠次によって築かれた。 天正18年(1590年)徳川家康の関東入部に従い三河国小島から移り、一万三千石(一説に一万石)を知行した。伊奈忠次は家康の関東入部により関東代官頭(関東郡代)に任ぜられ、検地や治水、新田開発などに手腕を発揮した。慶長15年(1610年)忠次が没すると嫡男伊奈忠政が家督を継ぎ、関東代官頭も引き継がれたが、元和4年(1618年)に没した。忠政の家督は嫡男伊奈忠勝が継いだが、幼小であったことから関東代官頭は忠政の弟で旗本として赤山陣屋を構えていた伊奈忠治が継いだ。小室藩の家督を継いだ伊奈忠勝であったが、翌元和5年(1619年)わずか九歳で没し、小室藩は嗣子なく改易となった。しかし、伊奈家の過去の功績から忠勝の弟忠隆が旧領のうち小室郷など千百八十六石が与えられ旗本として存続、以後明治まで続いた。 足利政氏館:永正15年(1518年)足利政氏によって築かれたと云われる。 足利政氏は足利成氏の嫡男で二代目古河公方である。 永正3年(1506年)頃から政氏と嫡男高基は対立しはじめ、いったんは和解となったが永正10年(1513年)に上杉顕定の後継者問題で再び対立し、政氏は下総国古河城を出て下野国小山城主小山成長を頼った。しかし、永正13年(1516年)頃になると高基を支持する小山政長の影響で小山氏も高基に味方するようになり、政氏も隠居を余儀なくされ、この久喜の館へ移ったという。 永正16年(1519年)に永安山甘棠院を建立し、開山は政氏の子貞巌和尚である。 永正17年(1520年)政氏は古河城の足利高基を訪ねて和解し、享禄4年(1531年)にこの地で没した。 源経基館:築城年代は定かではない。伝承に依れば、承平8年(938年)武蔵介に任ぜられ下向した源経基が館を構えた所という。 松山城:築城年代は定かではないが、応永6年(1399年)上田友直により築かれたと云われる。 それ以前にも正慶2年・元弘3年(1333年)新田義貞が鎌倉の北条高時を攻めたおり、要害を構えたという。 天文6年(1537年)川越城を落とし勢いに乗る北条氏綱は上田正広の籠る松山城に侵攻したが落とすことはできず撤退した。 扇谷上杉氏は川越城奪回を目指して攻めるが、逆に北条氏康の夜襲により撃退され、さらに松山城をも奪われた。 しかし、上田朝直はすぐさま岩槻城主太田資正の協力を得て松山城を奪還。この時、本丸は太田資正の家臣広沢尾張守が守り朝直は二の丸に入った。 再度北条氏は松山城を攻め、この時朝直が北条方へと寝返り城は落城した。 永禄4年(1561年)上杉政虎が大軍を率いて攻め攻略し太田資正に預けた。政虎が関東から退くと再び北条氏が来襲するが、太田氏はこれを退ける。 しかし翌永禄5年(1562年)北条氏が侵攻、甲斐武田氏にも援軍を求め大軍で押し寄せた。 北条・武田連合軍は大軍をもって攻撃したが容易に落城せず、武田氏は金山衆を用いて地下に穴を掘る作戦にでるも失敗。連合軍は完全包囲で兵糧攻めし、なんとかこれを落とし再び上田朝直の居城となった。 天正18年(1590年)豊臣秀吉による小田原征伐では前田利家、上杉景勝等の大軍に囲まれ落城した。 徳川家康が関東に入部すると、三河国桜井城より(桜井)松平家広が一万石で入封するが、慶長6年(1601年)松平忠頼の時、遠江国浜松に転封となり、以後廃城となった。 大築城:築城年代は定かではない。応永年間(1394年~1428年)に吾野左衛門尉憲光が築いたとも伝えられる。『新編武蔵国風土記稿』では天正年間(1573年~1592年)に松山城主の上田能登守朝直が慈光寺を攻めるために築いたとする。 河越氏館:築城年代は定かではないが平安時代末期に河越氏によって築かれたと云われる。 河越氏は桓武平氏秩父氏の一族で、秩父重隆が河越へ移り河越氏の祖となった。治承4年(1180年)源頼朝が伊豆で挙兵すると、はじめは平家方として頼朝と敵対するが、のちに畠山氏などとともに頼朝に従い平家討伐軍に参加した。 河越重頼の娘は頼朝の弟源義経の正室となるなど重用されたが、義経と頼朝の仲違いから重頼・重房父子は誅殺され、武蔵国留守所総検校職の地位も畠山重忠に奪われ河越氏は衰退する。元久2年(1205年)畠山重忠の乱で、北条義時率いる重忠討伐軍に河越重時・重員兄弟が従軍する。嘉禄2年(1226年)には畠山重忠に奪われていた武蔵国留守所総検校職の地位が鎌倉幕府より河越重時に与えられた。応安元年(1368年)河越氏は「平一揆」を組織して鎌倉幕府と対立し、河越館に立て籠もったが敗れ、伊勢に落ちて没落した。明応6年(1497年)山内上杉顕定は河越城の扇谷上杉氏を攻める為に河越氏館跡に上戸の陣を構えている。その後、小田原北条氏が河越城一帯を勢力下におさめると、重臣大道寺政繁がこの辺りを整備したという。 難波田城:難波田城は中世に富士見市内を本拠として活躍した難波田氏の居城跡で、昭和36年に埼玉県旧跡に指定されました。城は荒川低地の一角に築かれた平城で、規模は5万平方m以上と推定されています。 園内には難波田城資料館や城跡を復元した「城跡ゾーン」、市内の古民家を移築した「古民家ゾーン」があり、富士見市の歴史や文化を感じることができます。 山口城:築城年代は定かではないが平安時代末期に山口家継によって築かれたと云われる。 山口氏は武蔵七党の一つ村山党の出自で、村山頼家の子家継が武蔵国入間郡山口に住んで山口氏を名乗ったことに始まる。家継は平安時代末期に山口に館を構え、後に城郭として整備されたと考えられ、戦国時代には根古屋城を築いて居城を移したといわれる。 今回の旅行、関東地方の埼玉県に足を運び、埼玉県に点在する比較的マイナーなお城10か所をめぐり楽しみました。 |
      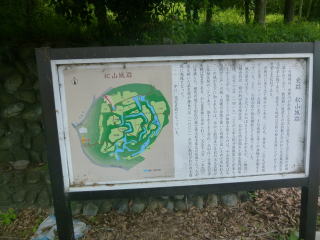     |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第三百五十五弾:茨城県お城・城下町巡り 2016年4月16ー17日 関東地方の南北朝の内乱で、常陸国も2つの勢力に分かれ、激しく火花を散らし、この争乱で北朝方の佐竹氏が発展し、文禄4年の常陸統一につながっていく、関ヶ原後、石田三成に協力した佐竹氏は秋田の国替となる茨城県に足を運び点在する比較的マイナーなお城10箇所を訪れました。 16日13:50新大阪新幹線のぞみで出発 16:16品川駅到達 16:44品川駅特急ひたちで出発 18:07水戸駅到達、駅前のホテル到着後繁華街を散策し食事を済ませて就寝。 17日8:00レンタカーで出発、お城巡り 那珂西城:藤原秀郷流那珂氏の居城と考えられていたが、現在では大中臣姓(おおなかとみせい)那珂氏の居城とする説が有力となっている。大中臣姓那珂氏の祖は賴継の子宗経で、実経、実久と続く。実久は御家人として常陸国那珂東郡・那珂西郡などの地頭職を得て那珂中左衛門尉を称し、その子時久は那珂三郎左衛門を称している。那珂氏はその後、丹波国天田郡金山郷へと移って行くがその時期は明確ではない。那珂宗泰が足利尊氏に従って丹波へ移った説が有力ではあるが、その祖父経久の時代とも云われる。いずれにしても那珂氏は古くより丹波の地に所領を得ていたようである。 石神城:延徳2年(1490年)小野崎通老によって築かれたと云われる。 延徳元年(1489年)陸奥の伊達・葦名・結城の軍勢が常陸へ侵攻してきたさい、主君の佐竹義治の身代わりとなって小野崎通綱は討死した。この功によって通綱の子通老は河合350貫、石神350貫の地を与えられ、石神城を築いて石神氏を称したという。 天文5年(1536年)石神通長のとき領地の境界を巡って争いとなり、同族の額田城主小野崎額田就通に攻められ石神城は落城した。その後、石神氏は帰城を許され、天正5年(1577年)には石神通実が三百六十騎を率いて佐竹義重に従い結城晴朝を授けた。天正12年(1584年)石神通信は佐竹義重に従って府中を攻め討死、通信の子石神通広のとき、佐竹氏に従って秋田へ移り廃城となった。 太田城:築城年代は定かではないが天仁2年(1109年)に小野崎通延によって築かれたと云われる。 小野崎氏は藤原秀郷流を称し、太田大夫公通が下野国佐野郷より常陸国大田郷にきて初代小野崎氏となり、その子通延も太田大夫を称している。太田城築城に関しては、この通延あるいはその子通成によるものとする説もある。 長承2年(1133年)には佐竹氏初代佐竹義昌が佐竹郷八ヶ村を領して馬坂城主となり、二代佐竹隆義は久安年間(1145年~1151年)頃に太田城主小野崎通成に圧力をかけ、通成は太田城を明け渡して小野崎城を築いて退き佐竹氏の家臣となった。以後、佐竹氏はこの太田城を居城とし、天正18(1590年)に江戸氏の水戸城を奪い居城を移すまで代々の居城であった。 助川海防城:天保7年(1836年)水戸藩主徳川斉昭によって築かれた。 水戸藩主徳川斉昭は家老の山野辺義観を海防総司に任命し、太平洋を見渡せる高台であるこの地に海防のための城を築かせた。 本丸、二の丸、三の丸を備えた本郭的な城郭であったが、元治元年(1864年)山野辺義芸のとき、天狗党の乱によって落城し焼失した。 龍子山城:築城年代は定かではない。応永年間(1394年~1428年)に大塚氏がこの辺りを支配して龍子山城を居城としたと云われる。 大塚氏の出自は詳らかではないが佐竹氏の一族あるいは小野崎氏の一族とする説もある。多賀郡大塚郷を発祥とし菅股城主であったが、龍子山城を築いて移ったという。 大塚氏ははじめ佐竹氏に従っていたが、文明17年(1485年)岩城常隆が侵攻して車城を攻め落とすと岩城氏に従った。その後は代々岩城氏に従っていたが、戦国時代末期に佐竹氏の勢力が拡大すると佐竹氏に従った。慶長元年(1596年)大塚隆通のとき、陸奥国楢葉郡折木へ転封となる。慶長7年(1602年)岩城貞隆が所領を没収されると、大塚氏は伊達氏の家臣で陸奥国角田城主の石川昭光を頼って家臣となった。 慶長7年(1602年)佐竹氏が秋田へ転封となると出羽国角館から戸沢政盛が四万石を領して小川城へ入り、慶長11年(1606年)龍子山城を改修して松岡城と改称して居城とし、松岡藩となった。元和8年(1622年)出羽国山形の最上氏改易により出羽国新庄へ六万石で転封となった。 戸沢氏の後は水戸藩領となり、付家老中山氏の所領となった。宝永4年(1707年)中山氏の所領が太田へ移されると太田へ移ったが、享和3年(1803年)再び高萩地方を知行することとなり、松岡館が再建された。 笠間城:元久2年(1202年)笠間時朝によって築かれたと云われる。 笠間氏は常陸国茨城郡笠間発祥で、下野国宇都宮氏の支流塩谷朝業の次男時朝が笠間に住み、笠間氏を名乗ったことに始まる。 天正18年(1590年)豊臣秀吉による小田原征伐で、笠間綱家は宗家の意に反して小田原北条氏に味方した為、秀吉は宇都宮国綱に命じて笠間氏を滅ぼした。 その後、宇都宮氏の支配下に置かれたが慶長2年(1597年)宇都宮氏が改易となった後は、下野国宇都宮に入封した蒲生氏郷の家老蒲生氏成が三万石で笠間に入封した。 慶長6年(1601年)武蔵国私市より(松井)松平康重が三万石で入封、慶長13年(1608年)丹波国篠山へ転封。 慶長13年(1608年)下総国佐倉より小笠原吉次が三万石で入封、慶長14年(1609年)改易。 慶長17年(1612年)下総国古河より(戸田)松平康長が三万石で入封、元和2年(1616年)上野国高崎へ転封。 元和3年(1617年)上野国小幡より永井直勝が三万二千石で入封、元和8年(1622年)下総国古河に転封。 元和8年(1622年)常陸国真壁より浅野長重が五万三千石で入封、正保2年(1645年)長直の時、播磨国赤穂に転封。 正保2年(1645年)遠江国横須賀より井上正利が五万石で入封、元禄5年(1692年)正任の時、美濃国八幡に転封。 元禄5年(1692年)下野国足利より(本庄)松平宗資が四万石で入封、元禄15年(1702年)資俊の時、遠江国浜松へ転封。 元禄15年(1702年)常陸国下館より井上正岑が五万石で入封、延享4年(1747年)正経の時、陸奥国磐城平へ転封。 延享4年(1747年)日向国延岡より牧野貞通が八万石で入封、以後明治に至る。 宍戸城:建仁3年(1203年)宍戸家政によって築かれたのが始まりとされる。 宍戸氏は八田知家の四男家政が常陸国宍戸荘地頭職となり、宍戸氏を称したことに始まる。 小田城の小田氏、下野国茂木城の茂木氏などは同族である。 元弘3年(1333年)宍戸知時の子朝家は足利尊氏に従って六波羅を攻め、その功によって安芸国甲立荘を賜わり、建武元年(1334年)甲立に下向し、はじめ柳ヶ城を居城としたが、後に五龍城を築いて移った。この家系が毛利元就の長女五龍局を正室に迎えて一門となった安芸宍戸氏で、江戸時代は一門筆頭として長州藩家老となっている。 宍戸氏は当初小田氏に従っていたが、佐竹氏の勢力が拡大し、小田氏が衰退すると佐竹氏に属していくこととなる。天正18年(1590年)小田原征伐に参陣した佐竹氏は、秀吉より常陸大半の領有権を安堵された。これにより水戸城の江戸氏を攻めると、宍戸義綱は江戸氏に荷担して佐竹氏と戦い討死した。義綱の子義長は鹿島へ逃亡、宍戸宗家は佐竹氏と親密な関係にあった義利が継ぎ、文禄4年(1595年)には海老ヶ島城へ転封となった。 義利が没すると宍戸義長が家督を継いだが、関ヶ原合戦後に佐竹氏は出羽国秋田へ転封となる。しかし宍戸義長は秋田へは従わず土着している。宍戸氏の一族のうち秋田へ移ったものもおり、茂木氏とともに出羽国十二所城に配された。 慶長7年(1602年)出羽国秋田より(安東)秋田実李が五万石に減封され宍戸城に移された。この実季によって近世宍戸城が築かれたものと考えられている。 秋田氏は正保2年(1645年)秋田俊季のとき、陸奥国三春へ五万五千石で転封となり、幕府直轄領となった。 天和2年(1682年)徳川光圀の弟松平頼雄が一万石を与えられて諸侯に列し、宍戸に陣屋を設けて支配した。以後、松平氏が代々続いて明治に至る。 難台山城:この城は、南北朝時代の南朝の勢力が失われようとしていた元中4年(1387)小田第8代孝朝の子、五郎藤綱が小山隆政若犬丸に加担して挙兵したところである。足利方は、上杉朝宗を将として攻めたが、小田五郎はよく奮闘し南朝のため気を吐いした。朝宗は攻撃に手を焼き、近くの舘岸城に拠って持久戦法をとった。一方佐竹氏に真壁方面からの糧道を絶たれるにおよんで万策つき、自らは部下と共に自刃した。この戦を機に、南朝方はその勢力を失った。城跡は、難台山頂近くにあり、雑木林の中にわずかに石を組んだ跡がのこっている。 真壁城:承安2年(1172年)真壁長幹によって築かれたと云われる。 真壁氏は大掾氏の支流で多気直幹の四男長幹が常陸国真壁郡真壁郷を領して真壁氏を名乗ったことに始まる。 真壁氏は初代長幹以後400年余り真壁城を居城として続くが、小田氏・江戸氏・結城氏など諸豪族の狭間にあって領地の維持に奔走している。戦国時代になると常陸国守護佐竹氏が国内統一へ向けて勢力を拡大し、また小田原北条氏が関東へ進出するなど巨大勢力が迫る中、真壁久幹は長男に北条氏政より氏の字受け氏幹、次男には佐竹義昭より義の字を受け義幹と名乗らせている。最終的には佐竹氏に属し、関ヶ原合戦後佐竹氏に従って出羽国秋田へ移り出羽国角館城へと移った。 浅野長政が五万石で入封し長重が継いだが、元和8年(1622年)笠間へ転封となり、寛永元年(1624年)には稲葉正勝が一万石で入封したが、正勝は寛永5年(1628年)に下野国真岡を継ぎ廃藩となり、その後は天領となって廃城となった。 小幡城:築城年代は定かではない。応永24年(1417年)頃に大掾詮幹の三男義幹による築城、あるいは鎌倉時代に小田知重の三男光重が築いたという説などがあるが、いずれも確証はない。 戦国時代には小幡氏がいたが水戸城の江戸氏の支配下に置かれ、府中城の大掾氏との領地境に位置する小幡城は、重要な支城と位置づけられていた。 天正18年(1590年)小田原征伐に参陣しなかった江戸氏は、常陸の大半を安堵された佐竹氏によって瞬く間に滅ぼされ、この小幡城もその役目を終えたと推測される。 18:27水戸駅特急ひたちで出発 19:43東京駅到達 20:00東京駅新幹線のぞみで出発 22:33新大阪駅到達。 今回の旅行、関東地方の茨城県に足を運び、点在するお城10箇所を訪れて楽しみました。 遺残の少ない城跡が多く、又城址公園に変化しているところも多く見受けられました。 |
             |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第三百五十三弾:徳島県お城・城下町巡り観光第二弾 2016年3月26ー27日 瀬戸内海・紀伊水道・太平洋に面している一方で、山地も多く、県全体面積の約8割を占めているという自然に恵まれた地域です。また、阿波人形浄瑠璃や情緒あふれるうだつの町並み、そして四国八十八ヶ所霊場などの歴史や文化が今も多く残る町の徳島県に足を運び紀伊水道沿いに点在する比較的マイナーなお城・城下町の4箇所を巡りました。 26日14:30車で阪神淡路鳴門自動車道経由して徳島に向かう。 16:25徳島市内のホテル到着後周囲を散策し食事を済ませて就寝。 27日7:00車で出発、紀伊水道沿いに点在するお城・城下町を巡る。 平島館:築城年代は定かではないが藤原清兼によって築かれた平島塁がその前身である。天文3年(1534年)室町幕府11代将軍足利義澄の二男足利義維(後の義冬)が阿波国守護職細川持隆に招かれ、三千貫の所領を与えられて阿波へ移り、平島塁を修築して住んだのが平島館である。 平島館に代々住んだ足利氏は阿波公方あるいは平島公方と呼ばれた。足利義冬の長男が永禄11年(1568年)に三好三人衆に奉じられて第十四代室町幕府将軍となった足利義栄である。江戸時代になって蜂須賀氏が支配するようになると平島公方の所領は減らされ、わずか百石となった。四代義次のときには足利から平島に改めるように命じられ、以後平島氏を称するようになる。文化2年(1805年)九代義根のとき阿波から脱出して紀州経由で京へ上った。これにより平島館は廃城となった。 牛岐城:築城年代は定かではない。 観応2年・正平6年(1351年)足利義詮の家臣で淡路国由良城主である安宅備後守頼藤と、同族で紀伊国周参見見氏が竹原庄を知行したとき、牛牧庄を預かっている。 延文3年・正平13年(1358年)に安宅氏は南朝方に与したが、貞治元年・正平17年(1362年)頃には阿波国の南朝勢力は一掃され、安宅氏も阿波を追われた。 その後、阿波国守護職細川氏の家臣新開氏(しんがい)が入部した。この新開氏は武蔵国新戒を出自とする豪族である。 天正3年(1575年)土佐の長宗我部元親が阿波への侵攻を開始すると、天正8年(1580年)には牛岐城主の新開遠江守実綱入道道善も降伏した。 天正10年(1582年)中富川の戦いでは長宗我部方として戦ったが、同年10月に丈六寺に招かれて謀殺された。その後、元親は弟の香宗我部親泰を海部城から牛岐城へ移し、阿波の拠点としている。 天正13年(1585年)豊臣秀吉による四国征伐で、木津城が落城したことから香宗我部親泰も牛岐城を破棄して土佐へ退いた。その後、阿波へ入部した蜂須賀家政は家臣の細山帯刀(後に賀島主水正と改名)が一万石で城主となり、阿波九城の一つとなった。 賀島氏が入城した後、牛岐から富岡に改称され富岡城と呼ばれたが、寛永15年(1638年)一国一城令によって廃城となった。 日和佐城:築城年代は定かではないが元亀年間(1570年~1573年)日和佐肥前守によって築かれたと云われる。天正5年(1577年)(一説に天正3年)日和佐氏は長宗我部元親に降った。 海部城:築城年代は定かではないが永禄年間(1558年~1570年)頃に海部左近将監友光によって築かれたと云われる。 海部川流域に勢力を持った海部氏が戦国時代末期に海部川下流の鞆浦に築城したのが始まりであった。海部氏は三好氏に従っていたが、長宗我部元親が土佐国を統一すると阿波国の最前線となっていた。 元亀2年(1571年)長宗我部元親の末弟である島弥九郎親益は、病気療養の為に土佐国から海路有馬温泉に療養に赴く途中、強風によって那佐湾に停泊した。この知らせを聞いた海部友光は手勢を率いて島弥九郎を討ち取った。これを期に長宗我部元親は阿波国へ侵攻することとなる。 天正3年(1575年)大軍を率いて海部城を攻めると、海部方の武将で鉄砲の名手栗原伊賀右衛門は攻め寄せる敵兵を尽く打ち落としていた。しかし長宗我部方の武将で槍の名手である黒岩治左衛門によって討たれてしまい、ついに海部城も落城した。一説にこの戦いは宍喰城での戦いで、海部城では主力が三好氏に従軍して留守であったため、抵抗する間もなく開城したとも云われる。 海部城を攻め落とした元親は弟の香宗我部親泰を海部城に入れて阿波国の拠点としたが、その後に牛岐城へ移っている。 天正13年(1585年)豊臣秀吉の四国征伐によって蜂須賀家政が阿波国へ入封すると、阿波九城の一つとして大多和長右衛門正之を入れ改修された。その後、城番は中村右近大夫重友、益田宮内一政そして一政の子、益田豊後守行長へと替わった。この行長は藩の掟を破り、木材を切り出して江戸で売り払い私腹を肥やして謀叛を企て処刑された。 寛永15年(1638年)海部城は廃城となり、かわって東麓に御陣屋が築かれた。 12:30終了、帰路に向かう。 今回の旅行、徳島県に足を運び、紀伊水道沿いに点在する比較的マイナーなお城・城下町4箇所を訪れて楽しみました。 徳島のお城巡り第二弾で今回で徳島のお城をほぼ制覇しました。
|
        |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第三百五十一弾:宮崎県お城・城下町巡り観光 2016年3月12ー13日 九州に足を運び、守護大名の伊東氏が権力を持つが、木崎原の戦いで島津氏に大敗を喫すると、豊後の大友氏を頼り、島津氏と大友氏が激しく戦い、最終的には豊臣秀吉の九州統一によって争乱にピリオドが打たれた宮崎県を訪れ、宮崎県に点在する比較的マイナーなお城・城下町を17箇所巡りました。 12日14:45伊丹空港出発 15:50宮崎空港到達、レンタカーでお城巡り 清武城:築城年代は定かではないが文和年間(1352年~1356年)清武氏によって築かれた。 清武氏は伊東氏の支族である。 伊東氏四十八城の一つ であったが天正5年(1577年)伊東氏が豊後に逃亡後は島津氏の領地となり伊集院久宣が城主となった。 豊臣秀吉による九州征伐の後は伊東氏の所領となり稲津氏が城主となった。 関ヶ原合戦では稲津氏は宮崎城を攻め落とし佐土原城にも攻め寄せた。 穆佐城:築城年代は定かではないが元弘年間(1331年~1334年)足利尊氏によって築かれた。尊氏は妻の出である赤橋氏の所領とした。この後、伊東氏、土持氏など南北朝の武将が争った。 応永年間(1394年~1428年)には薩摩国の島津元久が侵攻し周辺諸城を落として子豊久(後の8代当主)に守らせた。 文安2年(1445年)伊東氏が攻め取り落合治部少輔を置き以後伊東氏が豊後に逃れるまで伊東氏48支城の一つとなった。 綾城:築城年代は定かではないが元弘年間(1331年~1334年)頃に綾氏によって築かれたと云われる。綾氏は足利尊氏の家臣細川小四郎義門がこの地を領し、その子義遠が収納使として下向、綾氏を称した。綾氏ははじめ内屋敷城を築いて居館とし、後に詰城として綾城を築いたという。 綾氏は義遠以降、義勝、義廉、義郷、義佐、義範、義継、義義と八代続き、伊東氏に従った。その後は伊東氏48城の一つとなり、長倉若狭守、稲津越前守、佐土原遠江守が城主を務めたが、天正5年(1577年)伊東氏は島津氏によって日向を追われ、島津の所領となった。 島津氏の時代になると新納久時、上井秀秋、蒲生清宣、本田新平、新納久時、大野将監と城主が続き元和の一国一城令によって廃城となった。 宮崎城:築城年代は定かではない。建武2年(1335年)に図師随円・慈円父子がこの城を拠点に南朝方として兵を挙げたことが知られる。 慈円は北朝方の縣城主土持宣栄に攻められ落城した。 戦国時代は伊東氏の城で一族の伊東県氏が居たが、文安3年(1446年)島津に内応したことから伊東祐堯がこれを奪い取り、家臣の落合彦左衛門を置いた。 天文3年(1534年)伊東家の家督を継いだ伊東祐吉が宮崎城を居城としたが、天文5年に病没。祐吉の兄義祐が還俗して家督を継ぎ、佐土原城から宮崎城へ一時居城を移したが、都於郡城へ移り、宮崎城には肥田木越前守が守将となり伊東氏48城の一つとなった。 天正6年(1578年)伊東氏が没落すると島津豊後守忠朝、天正8年には上井覚兼が城主となった。 天正15年(1587年)豊臣秀吉の九州征伐の後は延岡の高橋元種の所領となり、家臣の権藤種盛が置かれた。。慶長5年(1600年)関ヶ原合戦で、東軍に属していた飫肥の伊東祐兵の部将稲津掃部助は西軍に属した高橋元種の宮崎城を攻め落としたが、高橋氏は東軍に寝返っていたことから宮崎城は高橋氏に返還されるという「稲津騒動」の舞台となった。 19:30宮崎駅前のホテル到着後繁華街を散策し食事を済ませて就寝。 13日7:00レンタカーで出発、お城巡り 日南方面に向かう。 南郷城:慶長6年(1601年)伊東祐慶によって築かれたと云われる。 慶長5年(1600年)関ヶ原合戦で、伊東祐慶は清武城主稲津重政に命じて西軍の大垣城に籠城していた縣城主高橋元種の支城宮崎城を攻め落とさせた。しかし、高橋元種は東軍に寝返って本領安堵となっていたため、宮崎城は高橋氏に返還され、稲津重政は責任を負わされる形で粛正された。 翌慶長6年(1601年)島津氏に対する備えとして築いたのが、この南郷城だと云われる。 しかし、元和元年(1615年)一国一城令によって廃城となった。 目井城:築城年代は定かではないが天文年間(1532年~1555年)に島津忠広によって築かれたと云われる。 飫肥城主であった島津忠広が支城として築き、家臣の日高源左衛門に守らせたが、源左衛門は伊東氏に降り、その後は度々島津氏と伊東氏によって争われた。永禄11年(1568年)伊東氏が飫肥城を奪取した後はその家臣川崎駿河守が入り伊東氏四十八城の一つに数えられた。 串間方面に向かう。 櫛間城:建武2年(1336年)に野辺盛忠によって築かれたと云われる。 野辺久盛の子盛忠が南朝方に属して櫛間城を居城とした。野辺氏は盛忠のあと、盛房、盛久、盛在、盛仁と続くが、嘉吉元年(1441年)盛仁は足利義満の子の大覚寺義有(義昭)を匿った罪で罰せられ、野辺氏は滅亡する。 野辺氏の後は伊作久逸が城主となった。久逸は飫肥城主の新納忠続と争いとなって伊東氏と結ぶなど島津氏に反旗を翻したが、その後降伏して伊作の地に戻り、櫛間は飫肥城主となった島津忠廉の管理となった。 天正15年(1587年)豊臣秀吉による九州征伐の後、筑前国古処山城より秋月種実・種長が高鍋三万石に転封となり高鍋城へ移った。慶長4年(1597)には櫛間城へ移り居城としたが、慶長9(1604年)に再び高鍋城を居城としたため廃城となった。以後、串間は高鍋藩の飛領地となった。 都城方面に向かう。 都城城:永和元年・天授元年(1375年)北郷義久によって築かれた。 北郷氏(ほんごう)は島津忠宗の六男資忠が戦功をあげ、北郷を所領し北郷氏を称した事に始まる。 北郷氏は2代義久の時、都之城を築き居城として以来、天正15年(1587年)から慶長5年(1600年)までの間に一時伊集院氏の領地となったが、元和の一国一城令で廃城となった後は、都城麓で明治まで続いた。 豊臣秀吉によって九州が統一されると、伊集院忠棟が都之城に入封するが、主家島津氏の転覆を画策した忠棟は伏見の島津邸で成敗された。これを知った子忠真は都之城をはじめ、月山日和城・山ノ口城・勝岡城・梶山城・安永城・志和池城・山田城・野々美谷城・梅北城・財部城・末吉城・恒吉城に兵を入れ徹底抗戦に出た。しかし慶長5年(1600年)徳川家康の仲介で忠真は降り庄内の乱は幕を閉じた。 祝吉館:築城年代は定かではない。 島津氏発祥の地として知られる。 島津忠久は惟宗広言の子で文治元年(1185年)伊勢国須可荘の地頭職と島津荘の下司を得た。さらに薩摩国・大隅国・日向国の守護職を得て鎌倉から下向した。 島津家は多数の分家を排出したが、薩州家は実久の時に相州家忠良に破れ、その子貴久によって一族が統一され、義久の代には九州の大半を制圧するに至ったが、天正15年(1587年)豊臣秀吉に破れ、薩摩国・大隅国と日向国の一部の所領となった。 梶山城:築城年代は定かではないが応永年間(1394年~1428年)高木氏によって築かれたと云われる。 嘉吉元年(1441年)島津忠朝の所領となったが、明応4年(1495年)伊東氏の所領となった。 大永2年(1522年)山田城主北郷久家が攻め寄せたが、伊東氏が待ち構え久家を討ち取った。 豊臣秀吉によって九州が統一された後は伊集院氏の所領となった。 勝岡城:築城年代は定かではないが文保年間(1317年~1319年)島津資久によって築かれたと云われる。 資久は島津忠宗の五男で文保2年(1318年)樺山地方三百町を譲られ樺山氏を称した。 明応4年(1495年)には伊東氏の所領となり加江田氏を城主とし、後永正17年(1520年)荒武藤兵衛を城主として改修させ、北郷氏の侵攻を破った。 しかし、天文元年(1532年)には北郷氏に破れ、豊臣秀吉の九州統一後は伊集院氏の所領となったが、庄内の乱の後、元和の一国一城令により廃城となった。 えびの方面に向かう。 加久藤城:築城年代は定かではないが応永年間(1394年~1428年)に北原氏によって築かれたと云われる。 飯野城主の北原氏の城で、徳満城の支城であったが、北原氏に代わって島津義弘が飯野城主となったとき、久藤城に新城と中城を拡張し加久藤城と名付けた。加久藤城には広瀬夫人と長子鶴寿丸を住まわせ川上忠智を城代とした。 元亀3年(1572年)伊東氏が加久藤城の鑰掛口を攻めた「木崎原合戦」の舞台となり、島津軍に敗れ壊滅的打撃を被った伊東氏はその後衰退の道をたどっていくこととなる。 日向方面に向かう。 都於郡城:建武4年・延元2年(1337年)伊東祐持によって築かれたと云われる。 伊東氏は源頼朝の家臣工藤祐経が日向の地頭職を得てその子祐時が伊東氏を称したことに始まる。祐持のとき日向に下って都於郡城を築いたが、その後京都で没し、祐持の子祐重が貞和4年(1348年)に日向に下向、一族の守永祐氏に奪われていた都於郡城を回復して居城とした。 その後、伊東氏代々の居城として続いたが、永正元年(1504年)火災によって焼失し、その後は宮崎城や佐土原城などを居城とすることもあった。伊東義祐は嫡男義益を都於郡城に置いて自身は宮崎城や佐土原城を居城とした。家督を継いだ義益が没すると、その嫡男義賢も都於郡城主となった。 日向一円に勢力を拡げ伊東氏四十八城と呼ばれる勢力を持った伊東氏も、天正5年(1577年)島津氏に敗れ、豊後の大友宗麟を頼って落ちていった。 島津氏の所領となると鎌田政親が城主となり、天正15年(1587年)豊臣秀吉による九州征伐の後は佐土原領となった。 佐土原城:築城年代は定かではないが建武年間(1334年~1338年)田島氏によって築かれたと云われる。 田島氏は伊東祐時の子祐明が田島庄の代官として居住したため田島氏を名乗ったことに始まる。 伊東義祐は天文21年(1552年)京都金閣寺に模した金柏寺を建立するなどその栄華を誇ったが元亀3年(1572年)木崎原合戦で島津氏に大敗すると天正5年(1577年)一族を率いて豊後国大友氏を頼り落ち延びた。 その後、佐土原城は島津義久の弟家久が城主となったが九州征伐の後に急死した。 家久の子豊久が継いだものの関ヶ原合戦に参戦し義弘の退却戦で殿を勤め戦死、一時天領となった。 慶長8年(1603年)島津以久が三万石で垂水から入封し2代忠興の時、山下に二の丸を移して御殿が建てられた。 高鍋城:築城年代は定かではないが斉衡年間(854年~857年)財部土持氏によって築かれたと云われる。 財部土持氏は日向一円に広がった土持七頭の一つであったが、長禄元年(1457年)景綱の時、伊東祐尭に小浪川合戦で敗れ滅亡した。 伊東氏は落合民部少輔を城主とし伊東氏48城のうちの一つとなった。 豊臣秀吉による九州統一後は秋月種実の所領となり、慶長9年(1604年)種長の時、串間城から財部城に居城を移した後、明治まで秋月氏の治政が続いた。 慶長12年(1607年)からは城改修を行い、山上に三重櫓が設けられるなど近世城郭へと変貌した。また地名も延宝元年(1673年)三代種信の時、高鍋と改めた。 高城:建武2年(1335年)新納時久によって築かれたと云われる。 新納氏は島津忠宗の四男時久が足利尊氏から新納院を与えられ新納氏を称したことに始まる。新納氏が上京中に富山国長に城を奪われ、後に新納土持氏の所領となったが、長禄元年(1457年)土持景綱が伊東祐尭に敗れると伊東氏の所領となった。伊東氏は野村蔵人佐を城主として伊東氏四十八城の一つに数えられたが、天正5年(157年)伊東氏は島津に敗れて豊後に逃走し、島津氏は山田有信を城主とした。天正6年(1578年)大友宗麟の大軍は松山塁などに布陣して高城を包囲したが、城主山田有信はわずかな兵で島津の援軍がくるまで耐えた。島津義久も軍勢を率いて駆け付け、両軍は高城川で激突し、緒戦は大友軍が押し込んでいたが、次第に島津軍が優勢となり大友軍は敗走、島津の追撃にあい耳川に追い詰められ大敗した。天正15年(1587年)豊臣秀吉の九州征伐では、羽柴秀長率いる二十万の大軍に攻められた。山田有信はわずかに千五百の兵で籠城して耐えたが、援軍に駆け付けた島津義久の軍勢は白根坂で秀長軍と戦い敗れ撤退、その後島津義久は秀長を経由して秀吉に降伏した。高城が開城したのは義久の降伏であった。 松山塁:天正6年(1578年)佐伯宗天によって築かれたと云われる。 天正6年(1578年)豊後の大友宗麟の軍勢は日向へ侵攻し、高城を攻めるため野久尾陣、松山陣(惣陣)、田間陣、河原陣、松原陣の五箇所に陣を構えた。この松山陣には佐伯宗天が布陣した。この高城合戦で敗れた大友軍は敗走する中でさらに多くの将兵を失い、以降衰退していく。天正15年(1587年)豊臣秀吉による九州征伐では羽柴秀長の軍勢が高城を攻めたときにも活用された。 18:00宮崎空港到達 19:30宮崎空港出発 20:35伊丹空港到達。 今回の旅行、九州宮崎県に足を運び、宮崎に点在する比較的マイナーなお城17箇所を巡りました。 城跡は際立った遺残が少ないところが多いが、今回は櫓有り、石垣有り、石碑ありと城跡を想像できる歴史的建造物が多く確認できました。又位置を見つけるのも容易でした。 宮崎北部の延岡方面以外の城を制覇出来た宮崎県ドライブ城跡巡りでした。 |
                |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第三百四十八弾:大分県お城・城下町巡り観光 2016年2月20ー21日 九州に足を運び、豊後は源頼朝に守護を任じられた大友氏が長く治め、南北朝の内乱が終息した頃、大内氏が九州に進出し豊前守護となり、両者は対立するが、大内氏が陶氏の陰謀などで衰退し、大友氏が掌握した大分県を訪れ、比較的マイナーなお城12箇所を巡りました。 20日18:00伊丹空港出発 19:00大分空港到達、レンタカーで別府に向かう。 18:05別府駅前のホテル到着後周辺を散策し食事を済ませて就寝。 21日7:00レンタカーで出発、お城巡り。 高崎城:築城年代は定かではない。建久2年(1191年)大友能直が豊後国守護職に任ぜられ、その先発隊が豊後へ入国しようとした所、在地豪族の阿南惟家が高崎山に陣取ってこれに抵抗したことが知られ、高崎山城の初見とされる。 正平14年・延元4年(1359年)には大友氏時によって本郭的な城が築かれており、南朝方勢力と戦った。これ以降、大友氏の詰城として利用された。 永正15年(1518年)朽網親満が反乱を起こして高崎山城に立て籠もったが、大友義長によって鎮圧された。 天正14年(1586年)大友義統が戸次川の戦いで島津軍に敗れると、一旦高崎山城に入城したが、ここからさらに豊前国龍王城へ退いている。 大友館:築城年代は定かではないが大友氏によって築かれたと云われる。 大友氏は相模国大友荘を本貫地とする一族で初代は大友能直である。大友氏が豊後に下向したのは三代大友頼康の頃と云われ、その後豊後に勢力を拡げていく。第二十代大友義鑑は嫡男義鎮を廃嫡して側室の子塩市丸を寵愛したため、天文19年(1550年)大友館にて家臣に殺された。大友館の二階で就寝中に襲撃されたことから「二階崩れの変」と呼ばれている。家督を継いだのがキリシタン大名として著名な大友宗麟となる義鎮で、豊後を中心に豊前・筑後・肥後など九州に勢力を拡げた。 天正6年(1578年)島津の侵攻に耐えきれず、豊後の大友氏を頼ってきた日向の伊東義祐の嘆願を受け、大友軍は日向へ侵攻する。日向の高城攻め、そして耳川合戦で島津氏に大敗を喫した大友氏はこの戦いで多くの家臣を失い、その後は勢力を失う。天正14年(1586年)には島津氏に豊後へ攻め込まれて焼き打ちにあい、宗麟は豊臣秀吉に支援を要請することとなる。天正15年(1587年)豊臣秀吉による九州征伐により島津氏は降伏し、大友義統は豊後一国を安堵された。しかし義統は文禄の役で鳳山城を破棄して敵前逃亡した罪により改易された。 佐伯方面に向かう。 栂牟礼城:築城年代は定かではないが大永年間(1521年~1528年)に佐伯惟治によって築かれたと云われる。 豊後の佐伯氏は豊後大神氏の一族で平安時代から続く名族である。 佐伯氏十代当主が佐伯惟治で、大永7年(1527年)大友義鑑から謀叛の嫌疑を掛けられ討伐軍を送られた。大友氏の討伐軍は臼杵近江守長景を大将とした二万余りの軍勢で、惟治は栂牟礼城に籠もってこれに応戦した。堅城であった栂牟礼城を攻め落とせなかった長景は一計を案じ、惟治に一時日向へ立ち退いた後、大友義鑑に申し開きをして許しを得るのが得策と説得、惟治はこの案に乗ってわずかな手勢を率いて日向へ落ちる途中、長景に通じていた土民によって討ち取られてしまった。 天正6年(1578年)耳川の合戦で大友氏は島津軍に大敗を喫し、佐伯惟教、惟真、鎮忠などが討死し、家督は惟真の子の佐伯惟定が継いだ。惟定は、天正14年(1586年)豊後に侵攻してきた島津軍を堅田合戦で退けると、朝日嶽城の守将で島津方に寝返っていた柴田紹安の居城である星河城を攻め落としてその妻子を捕縛し、翌天正15年(1587年)には島津方の土持親信が守る朝日嶽城の奪還に成功している。 文禄の役の後、主家である大友義統が除封となると、佐伯惟定もまた所領を失いこの地を去った。惟定は後に藤堂高虎に仕え、子孫は伊勢国津藩藤堂家に仕えて代々続いた。 日田方面に向かう。 森陣屋:慶長6年(1601年)来島長親(康親)によって築かれた。 関ヶ原合戦の後、長親は伊予国来島城から豊後国森に転封となり、2代通春の時、久留島と改めた。 森藩は一万四千石で城主格ではなかったため、角牟礼城を廃し南麓に陣屋を築いた。 天保8年(1837年)通嘉の時、三島神社の改築として陣屋を城郭風に改修し天守の代用とも云われる茶亭の栖鳳楼を建て現在の状態になった。 角牟礼城:築城年代は定かではない。史料に最初に登場するのは『志賀家文書』の文明7年(1475年)であることから、これ以前に築かれていた。 角牟礼城は玖珠郡衆の一人森氏の詰城として築かれたものであるが、後に玖珠郡衆の番城となった。天正15年(1587年)島津軍の北上に対して玖珠郡衆は角牟礼城に籠城して戦い島津の攻撃を防いで落城しなかった。 文禄2年(1593年)大友義統が改易となると毛利高政が入封した。この毛利時代に石垣造りの近世城郭へと改修されていった。 関ヶ原合戦後、毛利高政は佐伯に転封となり、黒田氏を経て慶長6年(1601年)来島長親が伊予国来島から入封すると、久留島陣屋を築き廃城となった。 日隈城:文禄3年(1594年)宮城豊盛(宮木長次郎)によって築かれたと云われる。 豊後の大友義統が改易となった後、豊臣秀吉の蔵入地となった豊後の日田郡と玖珠郡の管理を宮城豊盛が支配し、五千石を賜った。このとき、築いたのが日隈城である。 慶長元年(1596年)毛利高政が二万石の所領を賜って日隈城に入り、五重の天守を備えるなど城を改修した。関ヶ原合戦後、毛利高政は二万石で佐伯に移ったが、引き続き蔵入地の管理を任され毛利隼人佐が代官として在地した。寛永16年(1639年)天領となった日田地区の代官所は月隈城へと移り廃城となった。 月隈城:慶長6年(1601年)小川光氏によって築かれた。 関ヶ原合戦後、光氏が入封し古城を改修して丸山城と改め居城とした。 元和2年(1616年)美濃国大垣より石川忠総が六万石で入封すると永山城と改称したが、寛永10年(1633年)下総国佐倉に転封となり、豊前国中津藩小笠原長次と豊後国杵築藩小笠原忠俊に分割して預けられ、寛永16年(1639年)再び天領となった。 天和2年(1682年)播磨国姫路から(越前家)松平直矩が七万石で入封、このとき山上は破棄され麓に館を築いたが、完成を待たず出羽国山形に移封となった。 その後は再び天領となり小川氏が代官となった。 耶馬溪方面に向かう。 長岩城:建久9年(1198年)野仲重房によって築かれたと云われる。 重房は豊前国守護宇都宮信房の弟で、下毛郡野仲郷を分与され野仲氏を名乗った。 南北朝時代に野仲道棟・道春父子は北朝方として高勝寺城を攻め、永正5年(1508年)野仲興道は周防国大内氏とともに上洛し、船岡山合戦に参陣した。 戦国時代には大内氏に属すが、大内義隆が陶晴賢に討たれ大友宗鱗の弟晴英が大内義長と改名して大内氏を継ぐと、大友宗鱗が豊前に勢力を伸ばす。 この時野仲重兼は籠城して大友氏と対したが降伏、大友宗鱗はその武勇を賞して"鎮"の字を与え、野仲鎮兼と称した。 黒田氏が中津城に入封すると、野仲氏はこれに従わず、後藤又兵衛を先陣とした黒田長政に攻められ落城、野中氏は滅亡した。 中津方面に向かう。 光岡城:貞和6年・正平5年(1350年)赤尾次郎左衛門種綱によって築かれたと云われる。 赤尾氏は筑前の原田氏の一族で、足利尊氏から吉田村の地頭職に補任された。 代々大内氏に属しており、文明年間(1469年~1487年)に吉田村を赤尾村に改めたという。 弘治2年(1556年)大友氏に降り、永禄9年(1566年)高尾城を落とし麻生氏を滅ぼした。 しかし、大内に属する土井城の佐野親重と時枝城の時枝平大夫によって攻撃され、赤尾統秀の次男行種は豊後へ逃れたが、それ以外の一族は討ち取られた。 立石方面に向かう。 立石陣屋:寛永19年(1642年)日出藩初代木下延俊が没し二代俊治が家督を相続すると、父延俊の遺言により弟延次(延由)に五千石が分与され旗本となった。 日出藩初代木下延俊の父家定は豊臣秀吉の正室ねね(高台院)の兄である。 本来の遺言は一万石を分与であったものの、家老長沢市之亟が五千石にしたと伝えられる。 日出藩はわずか三万石で、このうち一万石を分与するのは過分であることなどから、延次が豊臣秀頼の遺児豊臣国松ではないかという説もある。 日出藩分家立石木下家は寛文4年(1664年)正式に旗本交代寄合と認められ、十一代続いて明治に至る。 杵築方面に向かう。 日出城:慶長6年(1601年)木下延俊によって築かれた。縄張は義理兄である豊前国小倉藩細川忠興によるものである。 木下延俊の父は備中国足守藩主となった木下家定で豊臣秀吉の正室高台院の兄にあたる。家定の三男が延俊で関ヶ原合戦の時の所領はわずか五百石であった。関ヶ原合戦で正室加賀の兄細川忠興に従って東軍として丹波国福知山城攻めに加わり、速見郡内にて三万石余が与えられ日出藩となった。 寛永19年(1642年)二代俊治が家督を相続すると、父延俊の遺言により弟延次(延由)に立石領五千石が分与され、日出藩は二万五千石となり、以後十六代続いて明治に至る。 17:30大分空港に向かう。 18:00大分空港到達。 19:30大分空港出発。 20:25伊丹空港到達。 今回の旅行、九州に足を運び、温泉、観光名所、盛りたくさんの大分県を訪れ、車で12箇所の比較的マイナーなお城を巡り楽しみました。 自然有り、歴史的建造物あり、多くの観光名所を身近に車で走行してのお城巡り堪能しました。 |
          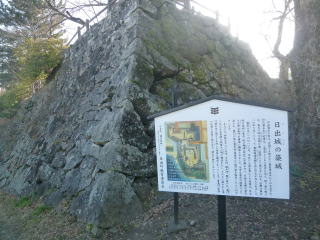  |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第三百四十六弾:熊本県九州八十八ヶ所巡り&お城・城下町巡り観光 2016年2月10ー11日 室町時代に、古くから同地で力を持っていた菊池氏が守護となり、阿蘇氏、名和氏、相良氏などが各地を支配するが、争乱が絶えなく、やがて大友氏が肥後に進出し、龍造寺氏、島津氏と対立することになる九州熊本県に足を運び、九州八十八ヶ所13箇所、お城・城下町6箇所を巡りました。 10日17:40伊丹空港出発 18:50熊本空港到達、レンタカーで熊本駅に向かう。 19:30熊本駅付近のホテル到着後周囲を散策し食事を済ませて就寝。 11日7:00レンタカーで出発、霊場巡り。 本蔵院:歴史は、阿蘇山から始まります。阿蘇山は本来、阿蘇神社の別当所として隆盛した西巌殿寺(天台宗・最栄読師開創)に総括された修験の山です。 有名な草千里には、かつて西巌殿寺の子院三十七坊が並び、修験の拠点となっていました。 しかし、明治の廃仏毀釈と修験道禁止令で、阿蘇修験は壊滅状態になりました。 西巌殿寺は山麓と山上にそれぞれ本堂を存続させていますが、子院三十七坊はいずれも廃されてしまいました。 後に、三十七坊の一院が熊本市迎町に移転し、真言宗に改宗したのが、満念寺本蔵院です。 さらに、昭和2年(1927)現在の本荘に移りました。 本尊は珍しい北向き不動明王。また、同じく本堂に祀られている弘法大師像は、人形師安本亀八の作です。 金剛寺:市街の中に在り、人々から中将姫の愛称で呼ばれている。創建は慶長年間(1596)斉藤又右門と称する人が開基したと伝えられている。 当初は熊本城の裏鬼門にあたる所にあって、加藤神社の別当を兼ねていたが、明治維新の廃仏毀釈に寺門は衰退していた。 明治25年(1892)増本法秀が現在の地に法灯をかかげ、由緒ある金剛寺を復興して維新の世情に弘法大師の教えを広めた。 しかし、昭和の戦火に焼失したが、寺門の再建に仏心をたぎらせ、新たな法灯を継承した。 以来、昭和58年に現在の秀和尼が本堂を再建して、祈りの道場を構えた。 中将姫の由来は、開基の斉藤又右門が霊示のお告げをうけて勧請したという。 中将姫といえば、奈良の当麻寺で出家した姫は、法如尼と改め阿弥陀如来に祈願していたところ、比丘尼が現れ、当麻曼荼羅を織り上げたと言う伝説がある。 蓮華院誕生寺:ここでお生まれの「皇円大菩薩様」をおまつりする真言律宗の「九州別格本山」です。 皇円大菩薩様(皇円上人様)は、浄土宗御開祖の法然上人様のお師匠様で、約900年前、肥後の守、藤原重房公の嫡孫として、ここ熊本県玉名市築地に御誕生されました。 幼くして比叡山で修行された皇円上人様は学徳にすぐれ日本三大歴史書の一つ『扶桑略記』を編述されました。 ご入定から六年後の治承元年(1177年)に平重盛が「蓮華院」を建立。そして60年後、法孫、恵空上人が、ご誕生の地に蓮華院浄光寺を再興、関白塔などを建立されましたが、天正十年(1582年)戦乱のあおりを受けて焼失してしまいました。 昭和に入り、川原是信大僧正様がご霊告により昭和5年に蓮華院を再興し、53年に奥之院を建立され、現在に至ります。 金剛寺:荒尾市は、熊本県の北西部に位置する。東に小岱山をいただき、西に不知火で名高い有明海に面し、彼方に雲仙岳を望む。県境の大牟田市とは共に炭鉱で栄えた。 昭和9年赤星精秀和尚が四国八十八ヶ所霊場遍路の後、真言宗寺院のなかった荒尾に、弘法大師御入定千百年御遠忌の記念事業として法雲院を開創した。法燈を継いだ善弘師が昭和35年入山して、法雲院を山号に改め、法雲山金剛寺と改称した。 参道には番号の刻まれた敷石がある。左側が四国八十八ヶ所霊場、右側が西国三十三ヶ所霊場の御砂が収められている。本堂前の観音立像の前には坂東秩父の観音霊場の御砂が収められ合せて百観音の結願となる。 弘法大師入唐1200年、御帰朝1200年それぞれの記念の石塔があり、中には中国赤岸鎮と青龍寺の石砂が収められている。殊に御帰朝記念の石塔には、中国で刻まれた黒御影石の金剛五鈷杵が蓮台の上に安置されている。 大勝寺:当山は千葉県成田市の成田山新勝寺が本山であり、その大本山成田山新勝寺の御本尊南無大日大聖不動明王(弘法大師一刀三礼謹刻開眼)のご分身が当成田山のご本尊であります。 1972年、九州のほぼ中央に位置し眼下に有明海が広がり、雲仙普賢岳、県立公園小岱山を望む自然ゆたかな地と、山門前には、西日本最大のテーマパーク「グリーンランド」を中心にアミューズメント施設等『遊・食・住』を兼ね備えた一大リゾート地が存在するこの有明の地を聖地と定め、本山より成田山の山号を戴き、寺号大勝寺を賜わり交通安全、厄除け現世利益、済世利人の成田山祈願道場として、九州一円熱誠信徒の心の寄り処となっている。 護国山仏性院金剛乗寺:825年弘法大師御開基にて「西の高野」と称される真言の大伽藍なり。 お大師様九日間談義され、この地を九日町、当山を談義所と呼ぶ。後鳥羽院御勅願寺。 中興の祖恵鏡法印より34世。菊池・細川家など祈祷本坊、多くの信者の当病平癒・所願成弁の 祈願寺として現在に至る。 1473年山鹿の温泉涸渇の折、当山中興八世宥明法印が硫礦山浄瑠璃寺(現在の薬師堂)を建立、 不借身命の大祈祷により温泉を復活させたのを祝って、山鹿の温泉祭が始められた。 また、法印供養法要の際山鹿庶民の献じた紙灯篭が灯篭祭の始まりとある。 お手植えの弁財天所縁の[童子椿]は法印の再来を待ち、花を開かず蕾のまま散るので有名。 八代方面に向かう。 医王寺:平安中期に創建されたと伝えられ、江戸時代寛文5年(1655)に、現在地に再興されました。歴代、八代城の安全と城主並びに城下、家内の除病息災・子孫繁栄を祈願して以来、八代城主 松井家の祈願寺だったお寺です。 ご本尊は、薬師如来立像で、平安中期~室町時代の作で桧の一木造り、高さ63.7cm、明治39年に国の文化財指定を受けました。聖観音は、鎌倉時代の作で桧の寄木造り、県指定重要文化財です。境内には、手足を病気、ケガから御守りいただける、青面金剛を祭神とする足手荒神、約300年も立ち続けた仁王様(石造の仁王像 高さ2m50cm)沢山の仏、神をおまつりしています。 八代城:元和8年(1622年)加藤正方によって築かれた。 熊本城に入封した加藤氏は元和の一国一城令の例外として熊本城と麦島城を残していたが、元和5年(1619年)麦島城は地震によって崩壊した。 熊本城主加藤忠広は幕府に麦島城を廃し新たに八代城を築くことを願い出て許された。 寛永9年(1632年)加藤忠広が改易となると替わって豊前国小倉から細川忠利が入封し、城代として弟立孝を本丸に父忠興を二の丸に置いた。 忠興が亡くなると家老の松井氏が城代となり以後明治に至る。 古麓城・鷹峰城:築城年代は定かではないが内河義真によって築かれたと云われる。 隠岐を脱した後醍醐天皇を伯耆国船上山に迎え、倒幕の兵を挙げた名和長年は、鎌倉幕府が滅亡すると、その功により嫡男義高に肥後国八代庄の地頭職が与えられた。 翌建武2年(1335年)一族の内河義真が代官として八代に下向し、南北朝初期の争乱により城を築いた。これが八代城で現在古麓城と呼ばれている。 「太平記」には建武3年(1336年)に北朝方の一色範氏が内河の城(八代城)を攻めたことが記されている。 長禄3年(1459年)名和義興が十六才のときに殺害されると、幸松丸は元服して名和顕忠と名乗った。文明年間(1469年~1487年)になると名和氏は相良氏と敵対するようになる。文明14年(1482年)名和顕忠が高田に侵攻するが相良為続に撃退され、翌15年には相良為続が逆に八代へ攻め入り古麓城は落城した。相良氏は一度退いたが文明16年に再び八代に侵攻してくると名和顕忠は古麓城を捨てて逃れた。 明応8年(1499年)相良氏は豊福で菊池能運と戦って敗れると、勢いに乗じて八代へ侵攻した菊池軍に追われ、八代の地は再び名和氏が復帰した。 文亀4年(1504年)相良長毎が八代へ侵攻すると、名和顕忠は古麓城を明け渡し、木原城を経て宇土古城へ移った。天文3年(1534年)には相良義滋(長唯)によって城の拡張と城下町の整備が行われ、自ら移って居城とした。 豊臣秀吉の九州征伐の後、肥後に入封した佐々成政は肥後国人一揆により改易となり、代わって加藤清正と小西行長が入封する。八代は小西行長の所領となり、古麓城は廃され麦島城が築かれた。 人吉方面に向かう。 願成寺:当寺はおよそ770年前、四条天皇天福元年(1233)人吉城主初代相良三郎藤原長頼公の創建で、開山弘秀上人は建久9年遠州常福寺より来られました。 金堂は鎌倉の長勝寿院の大御堂を模造し、1345畳敷と伝わっています。本尊は阿弥陀如来です。 文禄元年、当山13世勢辰上人は大いに功あって、寺録を300石増加され、慶長16年(1611)当山は後陽成天皇の勅願所となりました。塔頭六院を設け諸堂伽藍を経営していましたが、永録15年と更には西南戦争で、古の諸堂伽藍は悉く焼失しました。しかし、国指定重要文化財の阿弥陀如来・県指定重要文化財の不動明王・両界曼荼羅・七重の石塔・相良家の墓地・古文書数千点他安泰を待所蔵。 高寺院:球磨地方は、かつて平家一門の荘園がありました。平家滅亡後、平重盛の家人だった平貞能が、追善菩提のため重盛の念持仏の金造毘沙門天を胎内に納めた尊像を刻み、堂宇を建立したのが高寺院の始まりとされています。また、一説には、永享5年(1433)に快親という僧が開山して、本尊に毘沙門天を安置したとも言われています。江戸時代には、かなりの諸堂が軒を連ねていました。庫裏を兼ねた本堂は、寄棟造の葦葺きで、山村の農家のような感じの建物。外観からはお寺とは思えないが、日本人のふるさとといった雰囲気があります。 本堂の裏手にある入母屋造の収蔵庫に、本尊などの諸仏が安置されています。内部に並ぶ三体の毘沙門天像は、まさに壮観であり威風堂々と立っています。このうち、二体が国指定の重要文化財であります。 観蓮寺:元は観琳寺といい、治承年間(1177~1181)平重盛菩提のため、矢瀬主馬佑が建立したと伝えられています。その当時は禅宗の一派だったそうですが、大永6年(1526年)当地の内乱「瑞堅の乱」に依り堂宇も焼失してしまいました。慶長年間(1596~1615)再興しその時から千福寺 観蓮寺と改称し真言宗に改められました。途中数回の無住の時を経て現在に至っています。 青井山高野寺:熊本県南部、清流「球磨川」の流れる街「人吉市」の中心部、国宝「青井阿蘇神社」 門前にお寺を構えます。 大正十五年、初代良戒大和尚により開山せられました。その当時から“お大師さん”や“こうやさん”と 呼ばれ、皆様に親しまれております。 山門を入りまして左手すぐのところに『新四国八十八ヵ所霊場』の八十八体の佛様が御鎮座されておられます。 四季折々の花を見る事が出来る参道を歩けば、正面に『御身堂(おんみどう)』と呼ばれる、当山本尊 「高祖弘法大師(おだいしさま)」のおられます蓮華の花を模した八角堂(本堂)がございます。 本堂入り口の手前右手には、小さな子供たちを抱いた愛らしい「水子地蔵」さまがおられます。 勘代寺:日本三代急流 球磨川の上流 奥球磨 美しい田園風景の中にございます多良木町に勘代寺はあります。寺暦は鎌倉時代中期からの歴史を有し、諸代相良家の祈願所とし栄え現在は地域の方々の心のよりどころとして、日々お香のたえることのないお寺です。ご本尊様は、秘仏十一面観世音菩薩さま 内陣には、等身大以上のお大師様 薬師如来 孔雀明王 不動明王 をおまつりしておりまた 境内には、修行大師 弥勒菩薩を中心に石像十二支守護本尊八体佛 疳封じ地蔵 水子地蔵 子安観音裏門からは 厄払いの男坂四十二段・女坂三十三段をのぼると、厄除け不動尊をおまつりしており、毎月のお大師様報恩日(21日)には、たくさんのお参りのかたがたに大数珠まわしをしていただき、護摩祈祷を修しております。 生善院:寛永2年(1625年)に創建され、熊本県南部に位置する真言宗智山派の寺院です。 謀反の疑いで非業の死をとげた普門寺第5代住職盛譽法印と後を追って死んだその母玖月善女を 祀るために人吉藩主相良長毎公により建立されました。本堂には盛譽法印の影像である阿弥陀如来が、 観音堂には母玖月善女の影像である千手観音がそれぞれ納められています。 言い伝えでは、盛譽法印の母玖月善女は、その息子の死を怨み相良氏を呪いその愛猫「玉垂」とともに、 茂間ヶ崎淵(湯山ごしんさん)に身を投じました。その後、この猫が相良氏のもとに化けて出たため、 この猫の供養も兼ねて生善院が建てられたと伝えられており、この化け猫の伝説により生善院は 通称「猫寺」と呼ばれています。 鍋城:築城年代は定かではないが鎌倉時代に上相良氏によって築かれたと云われ、 以後代々上相良氏の居城となった。 南北朝時代には上相良氏は南朝方となり、人吉の下相良氏は北朝方として対立するようになる。その後南朝方に属した上相良氏は形勢が不利となって下相良氏に帰順し、相良氏惣領の座は下相良氏へと移った。 熊本市方面に戻る。 御船城:築城年代は定かではない。 阿蘇惟長によって日向国に追われた阿蘇惟豊は、甲斐親直(宗運)の助けで惟長を追って復帰する。その後、阿蘇惟豊の命で御船城主御船房行を討った甲斐宗運は、御船城主となった。宗運は御船城を居城として勢力を持ち、大友氏と阿蘇氏の間に立って重要な役目を果たしたが、耳川の合戦で大友氏の勢力が衰えると、島津氏の命で攻め寄せた相良義陽を響ヶ原で討ち取るなどの戦功をあげた。宗運が亡くなると島津氏が北上して益城郡の諸城を落とし、御船城主甲斐親乗は城を捨てて退散した。 岩尾城:築城年代は定かではないが貞応年間(1222年~1224年)頃に阿蘇惟次によって築かれたと云われる。 阿蘇氏の浜の館の詰城として築かれたものである。 天文21年(1552年)に岩尾城で火事があったことが「八代日記」に記されているという。 18:10熊本空港到達。 19:20熊本空港出発。 20:25伊丹空港到達。 今回の旅行、九州熊本県に足を運び、九州八十八ヶ所13箇所、お城・城下町6箇所を巡り楽しみました。 天候快晴、久々のドライブ日和、気温も比較的暖かく、気持よく、霊場・お城を回るこtが出きました。 九州の八十八ヶ所、お城巡り、徐々に制覇し続けています。明後日は長崎の霊場、お城巡りを予定しています。 |
                 |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第三百四十五弾:広島県お城・城下町巡り観光 2016年2月6ー7日 毛利元就が厳島の戦いで陶晴賢を破ったことをきっかけに、中国地方に巨大な勢力が展開され、山陰を抑えた吉川元春、山陽を治めた小早川隆景による毛利両川体制が支配の拡大に大きく寄与した広島県に足を運び、比較的マイナーなお城・城下町を巡りました。 6日18:20新大阪新幹線のぞみで出発 19:28福山駅到達、駅前のホテル到着後繁華街を散策し食事を済ませて就寝。 7日:8:00レンタカーで出発、城跡巡り。 神辺城:神辺城は、建武2年に朝山景連によって築城され、嘉吉の変の時に赤松氏討伐のため山名丈休が修築した。 戦国時代の天文17年に杉原忠興が城主であったが、忠興が大内氏から尼子氏へ属したため、大内義隆の重臣陶隆房によって攻められ落城した。 その後、杉原忠興は毛利元就に従い城主に返り咲くが、永禄7年には毛利元就の7男元康が城主となった。 慶長5年、関ヶ原の戦功により広島城主となった福島正則の持城となり城代が置かれた。 元和5年に福島氏改易の後、大和郡山から水野勝成が入城するが、福山城築城に伴い廃城となった。 桜山城:桜山城は、築城年代や築城者は定かでないが、文応~文永年間に山名氏正が居城していたが、弟山名備中に殺され、その後備中を氏正の子が討って再び桜山城に居城したと伝えられている。 遺構には中世後半の特徴が見られることから、戦国時代の永禄10年に小早川隆景が三原城を築城するが、この時期に背後の桜山城を三原城の詰の城として修築したと考えられている。 相方城:相方城は、永禄6年に毛利の武将で宮一族の有地元重が、宮氏の本城亀寿山城と相対するようにこの城を築城した。 天正初年、元重が出雲富田月山城主尼子氏に従うと、毛利方の神辺城主杉原盛重が攻めたが容易に落ちず、毛利の援軍が到来して開城した。 有地元盛は、備中猿掛城の合戦、大坂石山の木津川口での海戦、播磨上月城攻めに参陣・奮戦している。 天正15年、豊臣秀吉による山城禁止令によって相方城は廃城となった。 尚、相方城の城門が戸手天王社に移築されている。 鞆城:鞆の浦には、古くから大可島城が村上水軍の拠点としてあった。 鞆城の築城年代には諸説が在るが、天正3年、織田信長によって京を追放された足利義昭はを毛利輝元は鞆城に迎えている。 慶長5年、関ヶ原の戦功により安芸・備後の太守として福島正則が広島城に入城すると、鞆城には重臣大崎玄蕃を入れて、天守の建築などの城の修築を行った。 元和の一国一城令により鞆城は廃城となった。 しかし、廃城後も大手門等は存在し、城としての機能は残った。 福山城主となった水野勝成は、鞆城に嫡男勝俊を居住させている。 その後、福山藩の鞆奉行所となった。 鷲羽山城:建武3年・延元元年(1336年)杉原信平・為平兄弟によって築かれたと云われる。 杉原(椙原)氏は丹波国椙原発祥で桓武平氏。平貞盛を祖としているが、平清盛の四代孫秀衡の子恒平を養子に迎えていることから平秀衡の後裔とも称している。 椙原胤平の子、信平・為平兄弟は再興をかけて九州へ落ちた足利尊氏にしたがって九州の多々良浜の戦いで功を挙げ、木梨十三か村(尾道・後地・栗原・吉和・久山田・木原・猪子迫・白江・三成・市原・木梨・小原・梶山田)を領し鷲尾山城を築いたという。 鷲尾山城主は信平・光守・元盛・元直・光恒と続いたが、天文12年(1543年)尼子晴久の軍勢によって攻められ鷲尾山城は落城、杉原光恒は自刃して果てた。 光恒の子隆盛(始め高盛・元清とも)は大内義隆の助力を得て鷲尾山城主となり釈迦ヶ峰城と改められた。 元亀3年(1572年)石原忠直に攻められ落城。高盛も討死してその子元恒は本郷城主古志豊長を頼り、後に小早川隆景の助力で石原氏を討って釈迦ヶ峰城を取り戻した。 天正12年(1584年)元恒は千光寺山城を築いて移り廃城となった。 三原城:三原城は、永禄10年に毛利両川の小早川隆景によって築かれた。 隆景は、それまでの新高山城から三原城へと移したが、その後も逐次増改築が繰り返され、天正10年まで完成したと言われている。 天正15年、小早川隆景は豊臣秀吉から筑前国を加増されて名島城に居城を移す。 文禄4年、隆景は養子秀秋に家督を譲り、三原城に隠居、慶長2年に没した。 慶長5年に関ヶ原の戦功で福島正則が安芸広島城に入ると、三原城には福島正之が入った。 元和5年、福島正則が改易となった後、紀伊和歌山から浅野長晟が広島城へ入封する。 三原へは、浅野家筆頭家老浅野長吉が紀伊新宮より入り、代々相続し明治に至った。 高山城:高山城は、建永元年に源平合戦の時、源頼朝に仕えた土肥実平の子孫小早川茂平が東国から沼田荘に本拠を移して高山城を築城した。 小早川氏は、一族を各所に配して土着させ勢力の拡大を図った。 分家の木村城主竹原小早川氏と嫡流家とは不和になり、応仁の乱の時には、東軍に与した嫡流家を西軍に与した竹原家が2度に渡って高山城を攻めることもあった。 戦国時代の天文19年、沼田の小早川嫡流家の当主繁平は、盲目であったため、繁平の妹婿に分家竹原小早川隆景がなり、嫡流家の養子となって沼田・竹原両小早川氏が合体した。 天文20年に隆景は、竹原小早川氏の居城木村城から高山城へ移る。 そして、翌年に隆景は、中世城郭の縄張りであった高山城を廃し、戦国時代の乱世に適した新城を沼田川を挟んで対岸にある砦を大修築して築いた。 これが新高山城でる。 新高山城:小早川隆景は、天文2年に吉田郡山城主毛利元就の三男に生まれた。 天正10年、13代小早川興景が銀山城(広島市)攻めに出陣中に病死すると、興景夫人が元就の姪であった関係から、天正13年に養子に迎えられ、竹原小早川氏14代を相続した。 隆景は、天正19年に沼田小早川繁平の養子となり、小早川本家をも相続して高山城へと移り、天正21年に新高山城を築いて居城を移した。 隆景の晩年、養子秀秋に筑前名島城と家督を譲ると、慶長元年に三原城を隠居城と定め、新高山城の石垣の巨石を残らず三原城へと運んだと云われている。 頭崎城:頭崎城は標高504.3mの頭崎山に築かれている。城域は広く東西約700m、南北約500mと安芸国でも有数の規模を誇る。主郭部は山頂にあり、石垣の残る「甲の丸(本丸)」の南に「二の丸」、南東下の頭崎神社のある所が「三の丸」、その南の高台が南北二段の「太鼓の段」、南西に伸びた尾根にあるのが「煙硝の段」、主郭の北西下に「西の丸」、以上が主郭部の曲輪で看板の建っているものである。他に確認した看板は三の丸から南へ降りた所にある鳥居の段、北西から続く林道側にある「大将の陣」である。西の丸から東へ回り込んだ所には連続竪堀、さらに北東下に降りていくと畝状竪堀群が残っている。南西側の谷間一帯には屋敷跡のような平段遺構が数多く残されており、一部に石積を伴っている。「大将の陣」と呼ばれる所は最高所が林道によって切通されているが、北と南に平段遺構が連なっている。 鏡山城:鏡山城は、長禄・寛正年間に大内氏によって築かれたと云われている。西条盆地は、室町時代には安芸の中心地で、安芸に進出した大内氏の拠点が鏡山城であった。 応仁の乱から戦国時代にかけて、この城の争奪戦がくり広げられた。 大永3年、出雲富田城主尼子経久の芸備進出に対抗して、大内義興は鏡山城に蔵田房信を置いた。 しかし、尼子経久は、毛利元就ら芸備の諸将らを先鋒に城を囲み、城将房信の奮戦もむなしく落城した。 府中出張城:築城年代は定かではないが応永年間(1394年~1428年)白井胤時によって築かれたと云われる。 白井氏は千葉上総介忠常の後裔義胤が上野国白井山田荘を領して白井氏と名乗り、その子胤時が下向して出張城を築いて居城としたと云う。 白井氏ははじめ安芸国守護の銀山城武田氏に属し、明応4年(1495年)武田元信より「安芸国仁保島海上諸公事」が認められ、仁保島付近を航行する所船からの勘過料を徴収する権利を得ている。 白井氏は主に水軍を持って勢力を張っていたようで、大永7年間(1527年)には周防国大内氏に属し、天文8年(1539年)には武田氏の川内警固衆を敗っている。 陶晴賢が大内義隆を討つと、その後、台頭してきた毛利元就によって追われ、白井氏は大内氏の宇賀島水軍と合流する。弘治元年(1555年)には矢野保木城にて大内方として毛利に抵抗していた野間隆実を援護するため、呉浦や仁保島、海田などを襲撃する。 しかし、陶晴賢が厳島合戦において毛利元就に敗れると、後に白井氏は小早川隆景に降った。 銀山城:城は北から張り出した尾根の先端にあり、主郭から南の尾根と東の尾根に曲輪を配している。城への登城路は両尾根の谷を北西から南東へと落ちる竪堀とされる。この竪堀は谷の奥で主郭側から落ちる数条の竪堀群と合流するようになっている。主郭部は南から北へ伸びた尾根にあり、三段の曲輪がある。北側が主郭と思われる。 主郭は北側を堀切で断ち、北と西側に土塁があるとされるが、わずかに高くなっている程度である。西側の南端隅部に石積がわずかに残されている。 一番南側の曲輪の北東隅に虎口があり、両側が土塁となっている。この虎口は外側に空間があり、そこから東面を北側へと通路が走り登城路とされる竪堀へと通じる。この南の曲輪の西側面には畝状竪堀があるとされるが薮が深く見付からなかった。東尾根に配された曲輪群は北側に土塁が残り、南側は石垣が部分的に残っている。ここから登城路とされる竪堀を狙うのは容易である。 桜尾城:桜尾城の築城年代は定かではないが、鎌倉時代には厳島神社神主佐伯氏の本拠となっていた。 室町時代には、安芸の守護武田氏は佐西郡の領有をめぐって、佐伯氏としばしば戦っている。 厳島の合戦の前年、天文23年に毛利元就は桜尾城を占拠して、重臣桂元澄に守らせている。 元澄没後、元就の四男穂田元清が城主となり、慶長5年の関ヶ原の合戦後毛利氏が防長に転封するまで、西方の政治・軍事の要衝であった。 亀居城:慶長5年、関ヶ原で西軍に与した毛利輝元は防長2ヶ国に減封され長門萩に移った。 替わって、福島正則が尾張清洲から安芸・備後2ヶ国の領主として広島城に入城した。 正則は、領国に6支城(三原・三次・神辺・鞆・東城・亀居)を構えることにし、小方の地には甥の福島伯耆を配した。 亀居城は、慶長8年から築城を開始し、慶長13年に完成する。 しかし、完成間もない慶長16年に、幕府の圧力により廃城となった。 また、元和5年には、福島正則もまた広島城無届け修築を理由に改易となった。 18:05広島駅に向かう。 18:45広島駅到達。 18:57広島駅新幹線のぞみで出発 20:18新大阪到達。 今回の旅行、広島県に足を運び、福山からスタートし大竹までのお城14箇所を巡り楽しみました。 山城、平城、平山城とタイプの違ったお城を14箇所、時間かけて探し出して訪れました。 今回は遺残の多い城跡が多く、歴史を感じ取ることが出きました。 |
  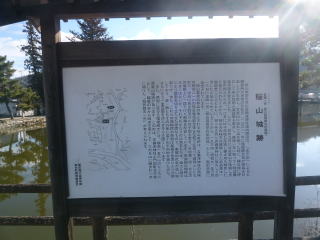     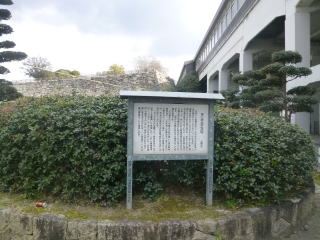  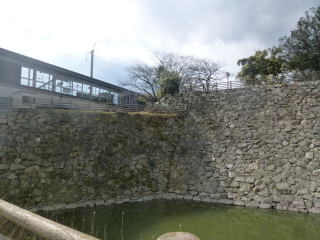    |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第三百四十四弾:鹿児島県九州八十八ヶ所巡り&お城・城下町巡り観光 2016年1月30日ー31日 大隈、薩摩、そして日向の一部で構成され、古くから海外との交易が盛んで、大隈の肝付氏、日向の伊東氏がいち早く合戦に鉄砲を取り入れ、守護の島津氏が同地を支配し、九州全土を席巻した鹿児島県に足を運び、九州八十八ヶ所の8箇所、比較的マイナーなお城11箇所を訪れました。 1月30日16:20伊丹空港出発 17:35鹿児島空港到達、レンタカーで鹿児島市内に向かう。 18:20鹿児島市内のホテル到着後繁華街を散策し食事を済ませて就寝。 31日7:00レンタカーで巡る。 不動寺: 美し風景で知られる鹿児島の名所、磯庭園。庭園の目の前には桜島と錦江湾が広がります。その近く、鹿児島市十号線沿いに稲荷町という町があり。この町に不動寺があります。 このお寺のある場所は、かつて真言宗大乗院というお寺が存在した地でありました。不動寺はそのような仏縁の深い場所に築かれています。由来を語ると、大隅半島にある西大寺の鮫島弘明住職が薩摩の地に祈祷道場を求めて行脚していた時、夢に不動明王の霊示を受けたという。急いでこの地を訪ねてみると茂みの中に石仏が放置されていた。鮫島住職はこの石仏を仮に安置し、後の昭和35年に仮道場を興された、これが不動寺の始まりであります。現在は真言密教を広める道場とし、平成8年5月26日に本堂を落慶法要し、寺院として今にいたります。 大歓寺:大歓寺は、昭和45年に建立されたお寺です。御本尊様はお不動さまで、病気平癒、災害除け福徳や煩悩を滅ぼしたり、大変霊験あらたかな仏さまで、これまでもたくさんの信者さんからお不動さまのおかげを授かっておられます例えば鹿児島市で過去あった大水害にみまわれた時もお寺でご祈祷したお不動さまのお札を授かった方の中には、倒壊した道路を通行していたが、お不動さまのおかげで間一髪の所を救われたという方や、床下浸水で畳が浮き上がり、次々と家具が倒れる中、お不動さまのお札を納めたお仏壇だけは微動だにしなかったという信者さんもおられます、霊験談は数えあげるときりがないほどある。 また大歓寺のご利益といえば、安産祈願が有名である。この安産祈願の安産お守りは護摩を焚き、祈りを込めた手づくりのお守りで、このお守りを授かりにくる方も多い。また老若男女の心のより所として開かれたお寺ですので、大いなる活気に満ち溢れています。 東福寺城:暦応4年・興国2年(1341年)島津貞久によって築かれた。 貞久は南朝方の矢上氏と肝付氏の籠る浜崎城(一説に東福寺城の一曲輪とも云われる)を攻め落とし薩摩の拠点とした。 嘉慶元年・元中4年(1387年)島津氏は勢力を伸ばし新たに清水山城を築いて拠点を移した。 清水城:嘉慶元年・元中4年(1387年)島津元久によって築かれた。 島津氏は東福寺城を居城としていたが勢力が拡大するにつれ手狭となり清水城を築いて本拠を移した。 元久が没すると長子犬千代を推す伊集院頼久と元久の腹違いの弟久豊の間で相続争いがあり頼久によって清水城が焼き払われた。 指宿方面に向かう。 光明寺:薩摩半島の一角、縁に囲まれ全国に知られる温泉の里指宿天然砂蒸しは特に有名であります。この地に光明寺があります寺周辺には、そら豆、おくら等畑が多く季節を感じます境内に目を向けますと前面を駐車スペースとして広く取り高齢者の方、身体に障害のある方が安心して御参りができるように設計してあります。又、参拝者の皆様の健康を祈って、観音菩薩蔵を平成18年に建立しました。 堂内に地蔵菩薩を本尊として安置しその側に寺宝で大師ゆかりの密教法具の一つ香炉と如意棒が島津家祖霊の願文とともに奉納してあり年に1回元旦の日にご縁にあう事が出来ます。 当寺は修行はもとより悩みのある方が“笑顔で帰っていただきたい“これを心より望むてらです。『今日を大切に、出会いを大切に、明日を元気よく』 指宿城:指宿市西方外城市字城ヶ崎にある松尾城は、鎌倉時代から江戸時代初期までの約400年間、山城、海城の両方の性格を持つ城でした。指宿五郎忠村(ただむら)が城を建てて以来、歴代の城主は、阿多氏、奈良氏、紀氏、相州島津氏、祢寝氏、薩州島津氏、田代氏などにうつり変わりました。元和(げんな)元年(1615年)の江戸幕府の一国一城令で廃城になるまで、指宿の歴史は、この城を中心に動いていたのです。防御のための空堀(からぼり)や本丸跡などが現在も残っており古城からの眺めはすばらしいものがあります。 頴娃城:応永27年(1420年)頴娃兼政によって築かれた。 頴娃氏には頴娃古城を居城とし、開聞宮下司職と頴娃郡の郡司を兼任した平氏系の土豪の頴娃氏と、それが滅びた後に頴娃氏を称した肝付一族の頴娃氏があり、兼政は後者の初代である。 頴娃城はポルトガル商人J・アルヴァレスによってヨーロッパで紹介された最初の日本の城だという。 知覧方面に向かう。 知覧城:築城年代は定かではない。 島津忠久が入国したとき、頴娃忠信が知覧院郡司職に任ぜられた。その後北朝方の島津氏によって薩摩・大隅・日向が平定されると、島津忠宗の三男佐多忠光が領した。 応永年間(1394年~1428年)城主佐多親久の留守中に、南朝方として島津氏に反抗していた伊集院頼久の一族によって、攻られ落城したが、応永27年(1420年)頼久が島津氏に降ると佐多氏が再び城主となった。 枕崎方面に向かう。 大国寺:昭和42年に住職によって開山され市民の悩みは台風だったので、百日間の願いをかけ禅をくんだ、すると国見岳が浮かび、観音菩薩の姿が現れた。さっそく手作りで御堂を建て、台風が一番やってくる方向に高さ8mの大日観音菩薩を造立した、すると不思議に大きな台風はあまり来なくなり枕崎市では、お大師様のお力と有名になった。 平成14年11月に佐賀県の七山村に如意輪観音庵を設立し、平成18年3月9日、金剛界大日如来様を建立した所、上空より大日如来の誕生の姿が現れた、写真に撮れた。 またこの大国寺に参拝すると、お茶の代わりに水を勧められる。かつてはこの山には水がなく山下から桶で運んでいた。それが平成5年になって、弘法大師のお陰で湧き出した、この大師の恵みの水も参拝された方々には有り難くいただいてほしい。 薩摩半島を北上する。 剣山寺:鹿児島県の南にあり、東支那海の見える静かな町の小さなお寺です。廻りの人達はとても人情厚く笑いのたえない所です、お寺の後ろには熊野神社があります。本尊不動明王様は参拝のみなさまのお話しをいつも“ニコニコ”して聞いて下さいます、「あわてるな、急ぐな、あなたはあなたのままでよい」といつも、話かけてくださる様な気がします。境内には慶長九年(約400年前)の三重の塔があります。気軽にどなたでも参拝出来るそんな寺にしたいと思います。 加世田城:治承元年(1177年)別府忠明によって築かれた。 別府氏は桓武平氏良文流で忠明の時に別府を名乗り別府城を居城として代々続いたが、応永27年(1420年)島津久豊に降った。島津宗家勝久の跡目をねらった島津実久は嫡子貴久を勝久の養子として宗家を継がせた島津忠良と激しく対立するが、天文7年(1538年)島津忠良が猛攻を加えて攻め落とした。 伊作城:築城年代は定かではないが南北朝時代に伊作島津氏によって築かれた。 伊作島津氏は久長を祖とし、忠良(日新)の時代に勢力を広げ、子貴久は本家を継いで戦国大名と成長した。義久の時代には九州北部まで進出したが、豊臣秀吉による九州討伐に敗れた。 峰浄寺:境内に足を踏み入れると、坂村真民先生の「念ずれば花ひらく」の真言碑と大きな修行大師さまが優しく出迎えてくれる。本堂奥には緑の散策路が広がり、八十八ヶ所の札所があり、入口には十二支えと地蔵、水子地蔵、弁財天堂、紺髪観音、子安観音などあり四季折々の花が咲き、親子や若い人たちのお参りが絶えない峰浄寺です。 一宇治城:築城年代は定かではないが建久年間(1190年~1199年)伊集院時清によって築かれたと云われる。 伊集院氏は時清から4代で血脈が絶え島津氏の一族伊集院久親がこれに代わった。 南北朝時代には島津一族で唯一南朝方に属したが島津貞久に破れた。 天文の初めには島津実久の勢力下であったが天文5年(1536年)島津忠良・貴久父子によって攻略された。 忠良・貴久父子はここを拠点として薩摩を統一し天文19年(1550年)貴久は内城を築いて移った。 薩摩薬師寺:奥薩摩の小さな集落の中にある当寺は新寺建立したまだ新しい寺ですが、のどかな環境に囲まれ、故郷に里帰りしたような気軽さでお参りができます。 本尊薬師如来立像は、御身の丈十三センチと小さいながらも、高野山よりお迎えした大変霊験あらたかな仏さまで脇仏の不動明王は、男女の縁はもとより、あらゆる不思議な縁結びの仏様です。 境内奥の八幡神と御神木の梛の木は永年に渡り、世の平和を見守っています。 これから歴史を刻んでいくお寺ですが、たくさんの方々の悩みや病がお薬師さまのお徳により救われることを願い、心のよりどころとなれば有り難いです。 法城寺:桜島が浮かぶ錦江湾の一番奥。美しい景色に囲まれた加治木町に法城院はあります。街中の国道沿いということもあり小さなお寺ですが、御参拝者のお線香の煙が絶えることなくたなびいています。御本尊は、参拝者の願いを叶え、苦しみを取り除いてくださる不動明王(秘仏)です。また、境内では無病息災・長寿祈願の「延命地蔵菩薩」、子供の安全・発育を願う「子安地蔵菩薩」などたくさんの仏様をお参りいただけます。現在、地元では「加治木の高野山」として皆様に親しまれておりますが、はじめてお参りされる方でも気軽に本堂に上がって手を合わすことが出来る、ちょっとした悩みでも話せる、そんなお寺でありたいと願っております。 加治木城:築城年代は定かではないが平安時代に大蔵氏によって築かれたと云われる。 大蔵氏は東漢霊帝の血を引く帰化人とされる。数代目の当主大蔵良長のとき継嗣なく、流罪となってこの地へ流れてきた関白藤原頼忠の三男経平に娘を娶せて大蔵家を継がせ、経平は加治木氏と名乗ってこの地に住んだと云う。加治木氏は以後有力国人としてこの地を治めていたが、明応4年(1495年)加治木久平は帖佐へ侵攻し平山城の南城を占領したが、高尾城に籠った川上忠直に防がれ、加治木侵攻に怒った島津宗忠昌の大軍に攻められ加治木城に帰還した。翌明応5年(1496年)島津忠昌が加治木城に押し寄せ久平は敗れて謝罪し許されたが薩摩国阿多へ移され加治木氏は没落した。 加治木氏の後は伊地知重貞が地頭となったが後に重貞も島津氏に叛いた為、大永7年(1527年)島津忠良が加治木城に攻め寄せ伊地知重貞・重兼父子は城中で自刃して果て、肝付兼演に加治木城は与えられた。 天文23年(1554年)蒲生範清は渋谷一族とともに島津氏に反抗し加治木城に攻め寄せた。島津貴久は加治木城を救援する為、岩剱城の祁答院良重を攻め、加治木城を取り囲んでいた蒲生軍が岩剱城を取り囲んでいた島津氏を討ちに戻ってきた所を激戦の末に打ち破り加治木城を救った。 文禄4年(1595年)加治木・日当山・溝辺のうち一万石が豊臣家の蔵入地となり、肝付兼三は喜入に移封となった。しかし、文禄・慶長の役での島津氏の功によって加治木は島津氏の所領に戻り、島津義弘が平松城より加治木へ移ったが加治木館を新たに築城した為、加治木城は廃城となった。 建昌城:築城年代は定かではないが享徳3年(1455年)頃に島津李久によって築かれたと云われる。 李久は島津忠国の弟で島津氏が平山氏を制した後、帖佐は李久に与えられ瓜生野城を築いたという。 李久の子忠廉は文明18年(1486年)島津忠昌の日向国伊東氏攻めに従軍し、日向国飫肥へ移った為、瓜生野城は廃城となった。 関ヶ原合戦後には徳川家康が加藤清正を先鋒として薩摩に攻め入るとの風聞があり、島津義弘が改修したともいわれ、また島津家久(忠恒)は鶴丸城にかわってこの建昌城を本城にしようとしたという。建昌城の名は明人頴川三官が中国の建昌城に似ているといったことから建昌城「けんしょうじょう」または「たてまさじょう」と呼ばれている。 蒲生城:保安4年(1123年)蒲生舜清によって築かれたと云われる。 蒲生氏(かもう)は、豊前国宇佐神宮の留守職藤原教清と宇佐大宮司の女との間に生まれた舜清が、神領管理のために大隅国垂水を訪れ、保安4年に蒲生・吉田の惣領職に転じて蒲生城を築いて蒲生氏を名乗ったことに始まる。蒲生氏は代々蒲生城を居城として続いたが、十八代蒲生範清のとき、渋谷祁答院良重と結んで島津貴久と戦った。弘治2年(1556年)島津貴久は蒲生氏の家臣中村氏の籠もる松坂城を攻め落とし、蒲生城に軍勢を推し進めた。蒲生氏の援軍として菱刈重豊が大軍を率いて駆けつけ北村に陣取り持久戦となったが、島津義弘が陣頭に立って奮戦するなど激闘となり、菱刈重豊が自刃して菱刈軍は壊滅、籠城していた蒲生氏も城に火を放って祁答院氏を頼って落ちた。蒲生氏の後は比志島美濃守が地頭として入部したという。 17:30鹿児島空港に向かう。 18:10鹿児島空港到達。 18:45鹿児島空港出発 20:05伊丹空港到達。 今回の旅行、九州の南、鹿児島県に足を運び、九州八十八ヶ所の8箇所、お城11箇所を車で巡り楽しみました。 戦いの場が点在する鹿児島県、今は大きな建造物は見受けられないが、昔は大きな建造物が存在していたと思われる、城跡の遺残で想像できる立派な城跡が点在していました。 九州八十八ヶ所の8箇所、お城11箇所、合計19箇所を車で回り堪能した歴史めぐり観光旅行でした。 |
                  |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第三百四十三弾:高知県お城・城下町巡り第二弾 2016年1月16日ー17日 鎌倉時代に地頭を任じられた長宗我部氏が、戦国の世になって、一条氏、香宗我部氏、本山氏、吉良氏、大平氏、津野氏などと競い合った。長宗我部元親の代に土佐を統一し、四国制覇の偉業に乗り出す四国高知県に足を運び、第二弾10箇所のお城・城下町を巡りました。 16日15:35伊丹空港出発 16:20高知空港到達、レンタカーで市内に向かう。 17:35市内のホテルに到着後繁華街を散策し食事を済ませて就寝。 17日7:00レンタカーで出発、お城巡り。 浦戸城:元となる城は鎌倉時代?室町時代初期に既に砦として存在しており、天文年間(1532年?1554年)には、土佐の豪族・本山氏の支配下にあった。永禄3年(1560年)に長宗我部国親が、本山氏から攻略し、その支配下となる。その後、戦国時代末期、岡豊城を主城としていた国親の子・長宗我部元親は、天正16年(1588年)大高坂山(現在の高知城がある辺り)に城を移したが水害が多く、3年後の天正19年(1591年)、浦戸城をそれまでの海からの防衛を主とした山城であったものから、水陸両面からの防衛を重視した本格的な城郭に改築し、その居城とした。三層の天守を設け、本丸・二の丸・三の丸・出丸で構成されていた。丘陵北部の浦戸湾岸に城下町を置いた。 朝倉城:築城年代は定かではないが大永年間(1521年~1527年)本山清茂によって築城されたと云われる。 本山城主の本山清茂は岡豊城の長宗我部兼序を攻めてこれを討ち、長浜・浦戸など土佐中央部に領土を拡張し、その拠点として朝倉城を築城した。 永禄3年(1560年)長宗我部国親は本山茂辰の長浜城を急襲して攻め落とし、さらに追撃して浦戸城も落城したが国親が病に倒れ撤退した。国親が没して元親が家督を継ぐと、永禄5年(1562年)には朝倉城に攻め寄せ包囲した。周辺の諸豪族が長宗我部方に降っていったため、 永禄6年(1563年)本山氏は朝倉城を焼き払い本山城へと退いた。 吉良城:築城年代は定かではないが吉良氏によって築かれたと云われる。 吉良氏は源頼朝の弟源希義の後裔と伝えられる。希義は源頼朝の挙兵に呼応して平家打倒の兵を挙げたが、平家の家臣蓮池城主蓮池家綱と平田俊遠によって襲われ年越山で殺された。 吉良氏は土佐七守護の一人に数えられる。吉良宣経は南村梅軒を招いて土佐南学の礎を築いたことで著明である。 天文9年(1540年)吉良宣直が城を明けて仁淀川へ狩猟に出かけた隙に、朝倉城まで進出していた本山茂辰は吉良城に奇襲を仕掛け落城。吉良宣直も本山氏に討たれ吉良氏は滅亡した。本山茂辰は吉良式部小輔茂辰と吉良氏を名乗っている。 永禄3年(1560年)本山茂辰は長宗我部元親と争うようになると次第に不利となり、永禄6年(1563年)拠点であった朝倉城を脱して本山城へ敗走した。このとき吉良城も破棄された。長宗我部元親は弟親貞を吉良城主とし、吉良左京進親貞と名乗らせた。 蓮池城:築城年代は定かではないが嘉応2年(1170年)頃に蓮池家綱によって築かれたと云われる。 蓮池氏は平重家の家臣近藤家綱が蓮池の地に居城を構え蓮池氏を名乗ったことに始まる。 寿永元年(1182年)蓮池家綱は平田俊遠とともに、平家打倒の兵を挙げた源頼朝の弟源希義を年越山で討ちとったが、まもなく伊豆右衛門有綱と夜須行宗によって攻められ討たれた。 建久3年(1192年)藤原国信が蓮池城を居城として大平氏を名乗り、以降大平氏の代々の居城となった。永正5年(1508年)大平元国は本山氏・吉良氏・山田氏などと岡豊城の長宗我部兼序を攻め敗死させた。天文年間(1532年~1555年)になると一条氏が津野氏に攻め込み天文12年(1543年)一条房基は津野基高を戦った。大平氏は本山氏とともに津野氏に援軍を送ったが敗れ、天文15年(1546年)大平氏は一条氏に降った。 弘治3年(1557年)南土佐に進出してきた本山茂辰は森山城・秋山城を攻略して仁淀川を渡り蓮池城をも奪った。永禄3年(1560年)本山茂辰は長宗我部元親と争うとその隙を付いて一条氏が蓮池城を取り戻したが、永禄12年(1569年)吉良城主吉良親貞が計略をもって蓮池城を奪い、戸波城へ逃れた城兵を追って戸波城をも落とした。 蓮池城は吉良親貞に与えられ、子の吉良親実が城主となった。吉良親実は戸次川合戦で討死した長宗我部信親の後継争いで盛親の家督相続に反対し、元親の怒りをかって比江山親興とともに自刃させられた。 戸波城:この辺りは、土佐中村の一条氏の家臣が治めていました。その後、長宗我部氏が侵攻、長宗我部一族がこの城に入り、戸波氏を名乗りました。この戸波氏は、大坂の陣の後に藤堂藩に仕えて、鍵屋の辻の決闘で有名な剣豪・荒木又右衛門を指導したそうです。 波川城:築城年代は定かではないが天正年間(1573年~1592年)始めに波川玄蕃頭清宗によって築かれたと云われる。波川玄蕃は長宗我部氏に降伏したのちは重用され、長宗我部元親の妹を妻に迎え、一条氏滅亡後は幡多郡山路城主となった。しかし、伊予国大洲に軍勢を進めた際に伊予河野氏の来援に駆けつけた小早川隆景と和睦を結んで引き上げたことから元親の怒りを買い、山路城を没収され波川城へ戻された。天正8年(1580年)波川玄蕃は秘かに謀叛を企てたが露呈し、阿波国へ逃れたが、阿波国海部で自刃させられた。 姫野々城:築城年代は定かではないが津野氏によって築かれたと云われる。 津野氏は藤原仲平の子山内蔵人経高が伊予より土佐に入り津野山を本拠として津野氏を名乗ったことに始まると云う。津野氏は土佐七雄の一人に数えられる勢力を誇っていたが、永正14年(1517年)津野元実は一条氏の家臣戸波城の福井玄蕃を攻めて敗れ討死した。これによって津野氏の勢力は衰退し、天文年間(1532年~1555年)には一条氏に降った。元亀2年(1571年)頃になると勢力を拡大していた長宗我部元親の三男親忠を養子に迎えその支配化に入った。津野親忠は長宗我部元親が豊臣秀吉の四国征伐により降伏し、土佐一国を安堵されると秀吉の元に人質となって大坂に送られた。豊臣秀吉による九州征伐で元親の嫡子信親が討死すると、家督相続争いに巻き込まれ、慶長4年(1599年)には元親によって岩村に幽閉された。長宗我部盛親が関ヶ原合戦で西軍について敗れると、親忠は親しかった藤堂高虎を通じて徳川家康に長宗我部家の存続を願い出ていたが、盛親によって殺害された。 久礼城:築城年代は定かではない。 城主は佐竹氏で承久の乱の時、佐竹信濃守と後藤基之が入部したことにはじまる。 南北朝時代には北朝方として戦った。 戦国時代に入ると一条氏に属したが元亀2年(1571年)長宗我部氏の軍門に下り、以後久武氏等とともに転戦した。 四万十方面に向かう。 中村城:築城年代は定かではないが、為松氏の為松城がその始まりといわれる。 応仁2年(1468年)前関白一条教房は、応仁の乱の戦火を逃れるため一条氏の荘園であった幡多庄に下向した。 教房は加久見城主加久見土佐守宗孝の娘を娶り生まれたのが一条房家である。この房家が実質的な土佐一条家の初代である。 戦国時代の土佐は一条氏を別格として、津野氏、大比良氏、吉良氏、本山氏、安芸氏、香宗我部氏、長宗我部氏の七人守護といわれた。 諫言した重臣土居宗珊(宗三とも)を成敗するなどした一条兼定は、天正2年(1574年)羽生、安並、為松の三老臣によって幽閉され、豊後に追放された。これにより一条氏は兼定の嫡男内政(ただまさ)が擁立され、長宗我部元親に後見を頼み大津御所に送られた。元親は中村城主に実弟である吉良親貞を置いて幡多郡を支配させた。 天正3年(1575年)一条兼定は中村城奪還のために、伊予の法華津播磨守らの助勢を得て栗本城に要害を構えて拠点とした。兼定と元親の軍勢は渡川(四万十川)を挟んで戦ったが兼定の軍勢は敗れ、伊予に退き奪還は果たせなかった。 宿毛城:築城年代は定かではない。もとは松田城と呼ばれ松田兵庫の居城であったが、後に依岡伯耆守が城主となり、天正3年(1575年)長宗我部氏によって攻められ落城した。 慶長6年(1601年)長宗我部氏に代わって山内氏が土佐に入部すると、山内一豊の甥山内可氏が六千石で入部し改修したが、一国一城令により廃城となった。 14:30高知空港に向かう。 17:30高知空港到達。 19:10高知空港出発。 19:55伊丹空港到達。 今回の旅行、四国の高知県に足を運び、高知のお城巡り第二弾、10箇所を車で巡り楽しみました。 今回は平城が多く比較的見つけやすく、2箇所の山城のみ時間がかかりました。 高知市から宿毛までの広範囲に点在する10箇所のお城、400kmのドライブ巡り堪能しました。 |
         |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第三百四十弾:四国福岡お城・城下町巡り観光第二弾 2015年12月19ー20日 九州に足を運び九州北部に位置し、古くから中国や朝鮮との貿易を通じて、本州に物資を送り込む拠点、室町時代に大内氏が勢力を拡大するが、やがて大友宗麟が北九州を平定、島津氏の北上に対抗した福岡を訪れ比較的マイナーな10箇所のお城をめぐりました。 19日18:59新大阪新幹線さくらで出発 21:17小倉駅到達、駅前のホテル到着後繁華街散策し食事を済ませて就寝。 20日8:00レンタカーで出発、お城巡り。 門司城:亀城とも。元暦二年(1185)平知盛が源氏との合戦に備え、長門国目代紀井通資が築城の起源との説がある。寛元二年(1244)下総前司親房が平家残党鎮圧の下知奉行として、鎌倉幕府より豊前国代官職に任じられて下向し、門司六ヶ郷と筑前国香椎院内などを拝領した。親房の子孫は地名により門司氏を称し、門司城を本城に領内に足立・吉志・若王子・三角山・金山の5支城を構えてそれぞれ一族が配置された。門司氏はその後およそ350年にわたって北九州の地に続いたものの、南北朝時代には二派に分かれ、門司城には北朝武家方の吉志系門司左近将監親尚が拠り、一方、南朝宮方の伊川系門司若狭守親頼は猿喰城に籠もり内乱の時期を送る(『日本の名城・古城事典』)。 松山城:古記によれば、天平十二年(740)に藤原広嗣によって築城されたと言われ、その後数回の戦乱にみまわれ、何度も城主が変わり、慶長十一年(1606)に廃城になったと伝えられている。 山頂には主郭が、主郭の北側には石垣と石段に続く腰曲輪、二ノ郭との間には石段と石垣が、南には虎口と推測される門の跡がある。三ノ郭からさらに東側には、かつて小城と呼ばれた遺跡があったが、今は土取りのため消滅した。主郭には発掘調査の結果、基壇と礎石をそなえた建物が屋根瓦を葺いて建っていたと推測される。山頂の側面には横堀や竪堀が複雑に確認でき、山頂の遺構から続く土塁が広範囲に広がっている。 松山城跡の全体の構図は主に山頂部の屋根瓦を持つ各郭と門を石段・石垣・横堀が複雑に取り囲んで、さらにその外側には土塁と竪堀が巡らしてあり、まるで松山の半島全体を難攻不落の要塞として造り上げた様子がうかがえる貴重な山城である(『城址案内板』)。 馬ヶ岳城:京都平野を眼下に一望する豊前の要衝、馬ヶ岳に城が築かれたのは、一説に天慶五年(942)ともいわれるが史料に乏しくはっきりしない。本格的な城の構えができたのは、おそらくもう少し時代が下ってのことであろう。 城の遺構は東西二つの峰を中心に郭が形成され、この西側の峰の平坦地が最も広く本丸跡と考えられる。また東側の峰から北に下る尾根には約500mにわたる土塁も確認された。 江戸時代に著された軍記物語などには、十四世紀半ばから十五世紀前半にかけて義基、義氏、義高の新田氏三代が在城したことが記されている。南北朝から室町時代を経て豊臣秀吉による九州平定までの動乱の時代、豊前地域をめぐって小弐氏、大友氏、大内氏、毛利氏などの群雄が覇を競った。この時代に馬ヶ岳城は香春岳城、苅田町の松山城、添田町の岩石城などとともに戦略上の重要拠点として攻防の舞台となった。 天正十四年(1586)豊臣秀吉が島津氏征討を決めると、馬ヶ岳城主・長野三郎左衛門は秀吉に降った。翌年、遠征軍を率いて自ら九州に上陸した秀吉は小倉城を経て、この城に逗留している。九州平定後、馬ヶ岳城は豊前六郡を与えられた黒田孝高が、拠点を中津に移すまでの居城となった。慶長五年(1600)黒田氏は筑前に移り、豊前は細川忠興の所領となった。このころ馬ヶ岳城も役割を終え長い歴史を閉じた(『城址案内板』)。 城井谷城:城井谷城(きいだに・★福岡県築上郡築上町大字寒田)は、宇都宮氏が城井谷渓谷の奥に築いて代々居城した。建久七年(1196)、豊前国に地頭職を与えられて下野から宇都宮信房が下向。戦国時代、その子孫の鎮房のころ築かれた。 豊臣秀吉の九州平定のとき、鎮房は秀吉軍として戦功をあげたが、四国への移封を拒否し、一時城を明け渡して他へ移った。その後、城井城代となっていた黒田氏の家臣を追い払って立て籠もった。秀吉は黒田長政らに攻撃させたが敗北する。そこで偽りの講和を結び、当主鎮房を謀殺してしまった。ついで長政は城井谷に攻めよせ、当主を失った城井谷城は落城した。孝高はこの勇将・城井鎮房を殺害したことを悔いて(中津城に城井鎮房の亡霊が出たためとも)、中津城に城井神社を創建し、その霊を祀ったという。 岩石城:保元3年(1158年)大宰大弐となった平清盛が大庭平三景親に築かせたのが始まりとされる。応保元年(1161年)豊後の日田陸奥守次男の日田判官宗道が在城。文治2年(1186年)からは筑紫三郎種有、筑紫弥平治種因の居城であった。種有は承久の乱で官軍に従って所領を没収され、大友氏の持城となった。暦応元年(1338年)からは大庭十郎左衛門景道、正平19年・貞治3年(1364年)には岩石城に籠もっていた城井出羽守が菊池勢に攻められ落城した。応安元年(1368年)豊前国守護大内氏の任命により熊井右近将監が守った。永徳元年(1381年)頃より大庭平太景忠が城主となったが、この頃より大内氏と大友氏によって争奪戦が繰り広げられたようであるが、景忠以降、景行、景種、景則、景尚と五代続いたとされる。天正6年(1578年)大友氏が耳川合戦で島津氏に大敗を喫すると、天正13年(1585年)秋月種実によって攻められ、坂本栄仙は奮闘むなしく討死して落城した。 天正15年(1587年)4月豊臣秀吉の九州征伐で前田利長・蒲生氏郷が攻め寄せ、わずか一日にして落城。秋月氏の城将熊井越中守は討死した。九州征伐の後、小倉城に入った毛利勝信は毛利九郎右衛門高頼を城将として岩石城に置いた。関ヶ原合戦後に豊前に入封した細川忠興は、長岡肥後守忠尚を城将として置き、元和の一国一城令によって廃城となった。 香春岳城:保元二年(1157)、平清盛が太宰大弐になると、家臣越中次郎兵衛盛次に命じて香春岳山王宮の東に新たな城を築き、鬼岳城(香春岳中腹)と名づけた。平治二年(1160)、清盛が帰任の後は豊後の人緒方惟義・惟時が居城とした。治承二年(1178)には香春庄司孝義、建長年間(1249~56)には香春判官友義が居城し、弘安年間(1278~88)の頃には中尾兵部丞が居城した。建武年間(1334~38)からは、小弐頼尚、その子刑部少輔頼長、その子右馬頭頼光と三代在城している。応永三年(1396)には千手信濃守興房が少弐頼光を滅ぼして居城したが、同五年に至り、大内盛見に攻められ、城を枕に討死した。 その後原田氏が在城したが、天文年間(1532~55)、原田五郎義種が大友氏に滅ぼされ、高橋九郎重種が居城した。天正十四年(1587)までは高橋三河守元種が居城したが、豊臣秀吉の先鋒黒田・小早川氏に囲まれ降伏した。慶長年間(1596~1615)の頃は、細川兵部大輔藤孝の次男中務少輔が居城し、元和元年(1615)の一国一城令により廃城となった。 障子ヶ岳城:障子ヶ岳城(☆ 福岡県京都郡みやこ町勝山松田)の創建は、建武三年に足利尊氏の命を受けて一族の足利駿河守統氏が築き、豊前の守護となった。応安元年(1368)、千葉上総介光胤が統氏を討ち居城とした。同六年元旦、千葉氏は、慶賀の宴の最中に大内氏の大軍によって攻撃されて落城し、その後、大内氏の抱城となった。一時、千葉氏が奪還したが、長くは続かず滅亡した。天正年間(1573~92)の初めには小早川隆景の抱城であったが、天正十五年(1587)の九州征伐に際しては豊臣秀吉の宿舎となった。のち、宇都宮氏が叛旗を翻した時、障子ヶ岳城に居城した添田雅楽介一族は宇都宮方についたため、同十七年に廃城となり破却された。 城址は北の味見峠と南の七曲峠との間に位置し、展望がひらけている。
|
            |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第三百三十九弾:四国徳島お城・城下町巡り観光 2015年12月12ー13日 四国の徳島に足を運び、阿波細川氏の勢力が強かったエリア、家臣の三好義賢が反逆し、阿波を手中に収め、細川氏と三好氏は以後も争うが、それが長宗我部元親の介入を呼び、天正13年の長宗我部氏による四国制覇につながった徳島県のお城・城下町13箇所を訪れました。 12日12:30車で出発、阪神神戸淡路鳴門自動車道経由して徳島到達、城巡り。 撫養城:築城年代は不明である。 古くは小笠原氏の居城であったが天正10年(1582年)長宗我部元親によって攻略され真下飛騨守が城番として置かれた。 しかし、天正13年(1585年)豊臣秀吉による四国平定で阿波一国は蜂須賀家政の領するところとなり阿波9城の一つとして益田氏を置いたが一国一城令により廃城となった。 現在は櫓跡に天守を模した鳥居記念館が建ち、本丸には妙見神社が建つがその本殿の裏には布積みの石垣が残っている。 木津城:築城年代は定かではないが永禄年間(1558年~1570年)に篠原肥前守自遁によって築かれたと云われる。 篠原自遁は三好氏の家臣で篠原長房の弟である。 天正5年(1577年)三好長治は荒田野で細川真之と戦って敗死すると、長治の実弟で讃岐国十河城主となっていた十河存保が勝瑞城に入ることとなった。自遁はこれを歓迎せず抵抗したが敗れ、勝瑞城入城の先導役を務めた。 天正10年(1582年)中富川合戦で三好氏は長宗我部氏に敗れ勝瑞城は落城、十河存保は讃岐国虎丸へ退いた。自遁はこの戦いには参加せず城に籠もっていたが、本能寺の変により織田信長が倒れると城を捨てて淡路へ逃れたという。 長宗我部元親は木津城に桑野城主東条関之兵衛を置いて守らせた。 天正13年(1585年)羽柴秀吉による四国征伐では、羽柴秀長・秀次を大将とする大軍が押し寄せた。籠城方も奮戦して良く防いだが、水の手を切られ落城したという。 勝瑞城:板野郡井隅荘は承久の乱(1221)の時阿波国守護になった小笠原氏は、この地に守護所を設け、阿波一国の軍事・警察の任に当った。南北朝内乱期に細川家の三代守護詮春は、守護所を秋月城(土成町)からここに移し、勝瑞城と称した。歴代守護細川氏は京都の管領家を支援し、たびたびこの城から大軍を畿内に送って活躍した。また城下に五十ほどの寺院があるなど、四国最大の守護町が形成され、大井に賑わった。 天文二十一年(1552)に守護の細川持隆は、執事の三好義賢と対立して謀殺され、その後は戦国大名三好氏の居城として栄えた。天正十年(1582)に阿波へ侵攻した土佐の長宗我部元親との間に攻防がくりひろげられ、城主十河存保は敗れて讃岐に退去した。当地に三好三代の墓もある。 天正十三年(1585)に入部した蜂須賀家政は、徳島城の早期築城をすすめるため、廃城となた勝瑞城から石材や建造物の一部を持ち去ったという。 城跡は旧本丸の部分といわれ、いまは三好家の菩提寺である見性寺が下克上の舞台竜音寺を吸収し、その境内となっている。 中世城郭は、山城が圧倒的に多い中で、中富川の水運を利用した平城の勝瑞城は、全国的に貴重な城郭として注目されている。なお見性寺に伝わる三好長輝と長基の画像も県有形文化財に、また徳島藩の儒員で四国正学といわれた那波魯堂の撰になる勝瑞義家碑は町の参考資料に選定されている。 勝瑞城は、室町時代の阿波国守護細川氏及び、その後三好氏が本拠とした城で、県内に残る中世城郭の中では珍しい平城である。十五世紀中頃に細川氏が守護所を土成町の秋月から勝瑞に移したとされ、その後、勝瑞城を中心として形成された守護町勝瑞は、阿波の政治・文化の中心として栄えた。勝瑞城は、京都の管領屋形に対して阿波屋形または下屋形とも呼ばれた。応仁の乱では東軍の後方拠点となり、また両細川の乱では細川澄元党、次いでその子晴元党の拠点となった。 天文二年(1553)、家臣の三好義賢(後に実休と号する)が守護細川持隆を殺害し、その実権を奪った。このころ三好長慶らは度々畿内に出兵し、三好の名を天下に轟かせた。 勝瑞は、吉野川の本支流に囲まれ、水運の便に恵まれた土地で、畿内で活躍した細川・三好両氏は、畿内から多くの物資や文化をもたらせ、畿内と直結した文化都市としても全盛を誇った。そのことは発掘調査で出土した遺物からもうかがえる。また、城下には多くの寺院が立ち並び、市が賑わい、かなりの城下町が形成されていた。本丸の周辺には寺院跡をはじめ各種の遺跡や伝承が残されている。 天正十年(1582)、土佐の長宗我部元親は十河存保の守る勝瑞城に大挙して押し寄せた。八月二十八日、存保は中富川の合戦で大敗を喫し、勝瑞城に篭城したが九月二十一日、讃岐に退き、ここに勝瑞城は歴史の幕を下ろすこととなった。 その後、天正十三年(1585)の蜂須賀家氏の阿波国入部により、城下の寺院の多くは徳島城下に移転され、町は衰退した。 周囲を濠に囲まれた当地は本丸跡で、昭和三十年二月七日に徳島県の史跡に指定されている。城内にある見性寺は、三好氏の菩提寺であり、当時は城の西方にあったが、江戸時代の中期にこの地へ移転してきた。境内には、之長・元長・義賢・長治らの墓が並んでいる。また、見性寺が所蔵する絹本着色の三好長輝(之長)・長基(元長)の肖像画は徳島県の有形文化財に指定されている。 西条城:西条東城は一条神社の近くにある天守台と呼ばれる小高い丘のあたりが城跡らしいといわれている。築城したのははっきりしていないが、三木左近将監備前守春之が秋月城の支城として築城したという記録がのこっている。 天文年間には岡本美作守清宗が居城し、勝瑞城の主君細川持隆に仕えていた。清宗の娘は持隆の側室となったが、傾国の美女として長宗我部元親の侵略を招いたといわれているほどである。その後天正十年(1582)八月、元親により落城した。 天正十四年(1586)、蜂須賀家政がこの城を阿波九城の一つとして修築し、家臣森監物に守らせたが、のちの元和元年(1615)の一国一城の令により寛永十五年(1638)に阿波九城は廃城となった。 17:00徳島市内のホテル到着後繁華街を散策し食事を済ませて就寝。 13日8:00車で出発。 一宮城:一宮城は延元三年小笠原長宗が構築したもので自然の地形を利用した城として知られる。また、阿波山岳武士の根拠地として、さらには戦国時代の一宮氏の拠点として活躍した名城であった。 今月残っている本丸の城壁・明神丸等の跡はこの頃のものであろう。その後長宗我部氏の侵入・豊臣秀吉の四国統平の際の攻防場となり、天正十三年、元和元年一国一城の制により廃城となっている。 一宮城は、前方に鮎喰川、後方に険しい山々がそびえ立つ自然の要害に築かれた大規模な山城であった。 現在では、標高百四十四メートルの本丸跡に石塁が残っており、その他、明神丸、才蔵丸、水手丸、小倉丸、倉庫跡の遺構も明らかで、貯水池といわれるくぼ地もその跡をとどめている。 この城は、南北朝時代、南朝に味方していた山岳武士の拠点であり、一宮氏が長年居城としていたが、成裕のとき土佐の長宗我部氏に占拠された。 その後、豊臣秀吉が四国を平定し、天正十三年(1585)、蜂須賀氏が最初入城したのが、一宮城であった。翌年、蜂須賀氏が徳島城に移ってからは、その支城として有力家臣を置いて守らせたが、元和元年(1615)の一国一城令により、廃城となった。 なお、一宮城跡は県指定史跡となっている。 また、一宮城跡周辺には、本拠が国の重要文化財に指定されている一宮神社、四国八十八ヶ所第13番札所の大日寺などの観光名所がある。 上桜城:築城年代は定かではないが戦国時代末期に篠原長房によって築かれたと云われる。 篠原長房は三好義賢に仕え、永禄5年(1562年)和泉国久米田の戦いで先鋒を務めたが、大将三好義賢が討死して大敗した。義賢亡き後、長房は紫雲と号して剃髪したが、義賢の遺児長治を補佐して「新加制式」という法令を制定して領内を治めた。 しかし元亀3年(1572年)長房の弟という木津城主篠原自遁の讒言により、三好長治は讃岐国十河城主十河存保、切幡城主森飛騨守、伊沢城主伊沢右近らを大将とする七千の軍勢を動員して長房の籠もる上桜城を攻め、両軍合わせて三千余人の戦死者を出し、長房・大和守父子も討死して落城した。 川島城:天正十三年(1585)蜂須賀の重臣、林道感が阿波九城の一つとしてここに川島城を築き兵300余名を置いた。しかし、元和元年十一月、一国一城令が出て廃城となる。岩の鼻に立てば阿北の山々と吉野川の清流が一望に収まり、道感原には、林道感の碑、朝鮮女の墓、また真福寺境内には板碑があり、史跡の床しい景勝地である。 秋月城:この地は古代秋月郷と呼ばれ、土豪秋月氏がここに居館を構えた。文永年間守護小笠原氏から世継ぎを迎えたと伝えられている。 細川阿波守和氏らは秋月氏に迎えられ、秋月に居館を構え四国全域に号令、四国管領として大きな勢力を誇っていた。 秋月城は南北朝から室町時代にかけて、細川氏の拠点として枢要の地歩をしめていた。 その後、細川詮春が勝瑞城に移った後、秋月中司大輔(森飛騨守)が守ったと伝えられている。 天正七年(1579)、土佐の長宗我部軍の兵火にあって落城したといわれている。 この城跡の周辺には、秋月城の名残りとして御原の泉・的場の跡・竈跡等が残っている。 岩倉城:築城年代は定かではない。文永4年(1267年)三好郡領平右馬頭盛隆が叛乱したとき、阿波国守護小笠原長房はここに城を築いて盛隆を平定したという。 永禄年間(1558年~1570年)には三好康長が岩倉城を築いて嫡子三好徳太郎康俊が城主となった。天正7年(1578年)康俊は脇城主武田信顕とともに長宗我部元親に降り、脇城外に三好方をおびき寄せ奇襲して勝利した。天正10年(1582年)三好方の説得に応じて再び三好氏に従ったが、同年阿波を攻略した長宗我部氏は脇城も攻略して岩倉城にも攻め寄せ、康俊は降伏開城して逃れたとも討死したとも云われる。 重清城: 小笠原家は清和源氏の裔にして小笠原左京大夫信濃守源長時阿波国守護職となる四代長房の孫長親が重清に築城したといわれている。この城は本丸の東方と南方に土盛で二条の空堀を設け北と西は城ヶ谷川と呼ばれる深い切り込みのある絶壁で守られ北は讃岐山脈の南斜面に守られ天然の要害をなしていた。また山脈の中腹には狼煙小屋を置き常時番人がつめていたといわれている。室町期に入り、新守護細川氏が阿波に入るにともない、小笠原一族はこれに抵抗、戦うが、重清城は早くその支配下に入り、正平十八年一の宮城の小笠原宮内大輔成宗も服従し、ここ重清城に退隠している。当時の重清城の貫高は二百貫といわれ、吉野川中流平野部の緒さえの拠点であた。 ついで動乱の戦国時代に入り、土佐の長宗我部元親は四国制覇の野望のもと、大挙して南北から阿波に侵入する。土佐軍は池田の大西城を落とし、ここ重清城に迫るが、難攻不落の城を攻めあぐみ、天正六年、大西上野介(白地城主大西覚養の弟)、その従兄弟の中島城主久米刑馬の二人を手先に使い、降伏を勧告する。その話し合いの途中、城主小笠原豊後守長政とその子弟を謀殺し、重清城は落ちる。その後、大西覚養が城主となったが、讃岐の十河存保に反撃され、城は一旦小笠原氏にもどる。同年夏、長宗我部軍再度の来攻で敗退し、再び長宗我部軍に奪われ、天正十三年、豊臣秀吉の四国攻めごろまでは存続したものと推定されるが、その後は廃城となった。 現在城跡南の台地に、大正十五年作られた、従五位小笠原豊後長政公蒋土英魂の石碑がある。 東山城:築城年代は定かではない。南北朝時代に南朝方の新田一族によって築かれ、八ツ石城とともに新田氏一族の拠点となったとも考えられているが、詳らかではない。 戦国時代には白地主大西出雲守頼武の弟(あるいは三男)で、伊予国轟城主でもあった大西備中守元武の城となっていたが、天正5年(1577年)長宗我部元親との戦いで落城し、元武は伊予国宇摩郡妻鳥村で逆徒に襲われ憤死したという。 その後の動向は定かではないが、現在残る遺構から長宗我部氏によって改修されたものと考えられている。 大西城:池田大西城は承久三年(1221)阿波の守護として信濃の深志(現在の長野県)から来た小笠原長清によって築かれ、400年に余って繁栄したが、寛永十五年(1638)江戸幕府の一国一城制により廃城になった。 この石垣の積み方は野づら積みと言われるもので、昭和五十四年幼稚園改築の際、北側に埋蔵して保存し、東側はコンクリートの下から一部観察できるようにしている。 白地城:白地城は、南北朝時代に近藤京帝が築城した。 その後、子孫は大西氏を称した。 天正4年に大西覚養は、土佐の長宗我部元親に追われてしまう。 白地城は、元親の四国統一の拠点として大修築された。 天正13年、豊臣秀吉の四国平定により、白地城は廃城となった。 15:00帰路に向かう。 今回の旅行、四国徳島県に足を運び、13箇所のお城巡り楽しみました。 毎度のことですが見つけるのが苦労するお城がいくつか有りました。特に山城は今回も見つけるのに苦労しました。 |
                 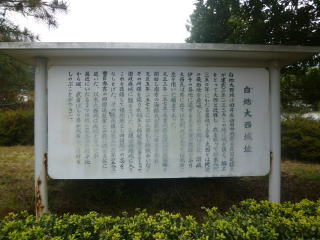 |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第三百三十八弾:四国別格二十霊場&四国三十六不動霊場&お城・城下町巡り観光 2015年11月29ー30日 四国の高知県に足を運び四国別格二十霊場、四国三十六不動霊場4箇所、鎌倉時代に地頭を任じられた長宗我部氏が、戦国の世になって一条氏、香宗我部氏、本山氏、津野氏などと競いあい、長宗我部元親の代に土佐を統一し、四国制覇の偉業に乗り出す高知のお城・城下町7箇所を巡りました。 29日15:35伊丹空港出発 16:20高知空港到達、レンタカーで市内に向かう。 17:30高知駅前のホテル到着後繁華街を散策し、食事を済ませて就寝。 30日7:30レンタカーで出発 極楽寺:弘法大師霊跡に先住僧師が民衆の幸福、とりわけ航海安全、病気平癒、家内安全などの祈願のため水行の後、一願不動尊として安置したのが由来である。 安芸城:延慶2年(1309年)安芸親氏によって築かれたと云われる。 安芸氏は蘇我赤兄の子孫といわれ、行経のとき安芸氏を名乗った。 戦国時代に入ると土佐七人守護の一人に数えられた。永禄6年(1563年)長宗我部氏が本山氏を攻めに出陣した隙を突いて、一条氏の援助を受けて長宗我部氏の居城岡豊城を攻めたが失敗した。 その後一旦和睦となったものの、永禄12年(1569年)長宗我部氏に岡豊城に招待された国虎はこれを謀略と考え拒否、長宗我部氏に攻められ落城し滅ぼされた。 安芸氏を滅ぼした元親は香宗我部親泰を城主として、後の阿波国への侵攻の拠点となった。 慶長6年(1601年)関ヶ原合戦で長宗我部盛親に代わり山内一豊が土佐に入国すると重臣五島為重を配した。 香宗我部城:築城年代は定かではないが中原秋家によって築かれたと云われる。 秋家は楠目城山田氏の祖となった人物で、香宗我部氏の祖である一条忠頼の子中原秋通の後見人であった。 大永6年(1526年)香宗我部親秀が安芸氏との戦いで敗れ、嫡子秀義が戦死すると弟秀通を養子として家を継がせたが、長宗我部氏が台頭すると長宗我部国親の三男親泰を養子として迎えようと画策する。既に秀通には嫡子がおり、これを拒否したが親秀は秀通を殺して親泰を養子に迎えた。 長宗我部氏が安芸氏を滅ぼすと親泰は安芸城主となり、後に阿波国方面の軍代として活躍する。 豊臣秀吉による朝鮮の役では嫡男親氏が出陣したが戦死し、代わって親泰が出征したものの長門国で病死する。このため親氏の子親和が幼少の身で家督を継いだ。 慶長6年(1601年)長宗我部氏が改易となると親和は肥前国唐津の寺沢氏に仕官した。 山田城:築城年代は定かではない。鎌倉時代に中原秋家による築城とも云われるが、現在残る遺構は戦国時代のものと思われる。 山田氏は中原秋家の後裔で鎌倉時代に香美郡宗我郷・深淵郷の地頭として入部したと云われる。山田氏は後に土佐の七守護の一人に数えられる程の勢力を持った。しかし、天文年間(1532年~1555年)の当主山田元義(基道とも)は猿楽を好んで武道を好まず、政治を疎かにしていた。重臣である烏ヶ森城主西内常陸・雪ヶ峰城主山田監物はこれを諌めたが、元義はかえってこれを遠ざけてしまった。 岡豊城主長宗我部国親の家臣吉田重俊は謀略を持ってまず西内常陸を討ち、大軍をもって山田城に攻め寄せた。山田監物が江村小備後によって討ち取られると、山田元義は韮生へ逃れ山田氏は滅亡した。 極楽寺:本尊不動明王は、開山喜道和尚感得した霊像にして、身代わり不動尊として信者の崇拝を受けている。境内には、西日本一の霊峰山石鎚山の行場第二の鎖を模した行場を形成。また行の滝もある。 大津城:築城年代は定かではないが天竺氏によって築かれたと云われる。 天竺氏の出自は詳らかではないが、守護職細川氏の一族と考えられている。天竺氏の後は津野氏の城となり、天文15年(1546年)津野基高が一条氏に降って一条氏の家臣が在城した。天文16年(1547年)頃に長宗我部国親が大津城を攻め取り、以降は長宗我部氏の持ち城となった。天正2年(1574年)一条兼定が豊後へ追放されると、長宗我部元親は一条内政を大津城へ迎え大津御所と呼ばれた。 岡豊城:岡豊城跡は、四国を平定した長宗我部氏の居城として知られる中世の城跡です。長宗我部氏は鎌倉時代に地頭として土佐へ入国したと伝えられており、それ以後、長岡郡を中心に勢力を広げ、戦国大名へと成長していきました。 岡豊城の築城は発掘調査の結果、13~14世紀ころと考えられています。「土佐物語」によると16世紀の初頭に一度落城したと伝えられており、その後、国親により1516(永正十三)年に再興され、1588(天正十六)年に元親が大高坂城(現在の高知城)へ移転するまでの、約70年間にわたり居城として使われていたといわれています。 岡豊山は、香長平野に突き出した丘陵であり、標高97mの頂上部(詰)に立てば、眼下に香長平野をおさめ、遠く太平洋も望むことができます。南には国分川が流れ、自然の要害の地でありました。 城跡は、詰を中心とする本城といわれる部分と西の伝厩跡曲輪、南斜面の伝家老屋敷曲輪の二つの出城からなる連郭式の構造となっています。本城は、詰と掘切によりへだてられた二の段、詰の南から西にかけて周囲を取り巻く三の段、四の段からなり、虎口(城の中心となる出入口)は西部に造られています。 発掘調査の結果、詰・詰下段・三の段では礎石建物跡や土塁の内側に石積みが発見されています。また、多量の土師質土器とともに青磁、白磁、染付と呼ばれる輸入陶磁器、瀬戸、備前、常滑などの国産陶器、渡来銭、小刀、また武器として火縄銃の部品(火鋏)や弾丸などの遺物が出土しています。 岡豊城の整備にあたっては、発掘調査の成果をもとに詰、詰下段、二の段、三の段の土塁や礎石建物跡などを復元しています。 本山城:築城年代は定かではないが本山氏によって築かれたと云われる。 本山氏の出自は詳らかではなく、清和源氏吉良流の八木氏、平氏、但馬国造八木氏など諸説あり定かではない。 戦国時代土佐七雄の一人に数えられた本山氏は、天文年間(1532年~1555年)本山茂宗の頃には高知平野へ進出し、朝倉城を拠点として一大勢力を築くまでに至った。しかし、茂宗の子本山茂辰の代になると一条氏の庇護を受けて岡豊城主に復帰した長宗我部国親との争いが本格化し、永禄6年(1563年)には高知平野の拠点である朝倉城を破棄して本山へ退くまでに圧迫された。その後も長宗我部元親によって攻め込まれ、本山城も破棄して瓜生野に逃れたが最後は長宗我部氏の軍門に降った。 宗安禅寺:当不動尊は鏡川上流領家郷から洪水で流され、現在地の大藤に掛り、安置された伝承から川上不動の名がある。弘法大師の木像で、彩色持国天、増長天の二天像とともに、国の重要文化財に指定されている。 泰泉寺城:築城年代は定かではないが鎌倉時代に吉松播磨守光義によって築かれたと云われる。 吉松氏は源義賢の子淡路冠者義久らが平教経と戦って戦死した功により、義久の子松若が源頼朝によって秦泉寺の領主となり、播磨守光義と名乗ったことにはじまるという。 その後、吉松氏は高知平野に進出した本山城主本山氏に属していたが、弘治2年(1556年)に長宗我部国親、永禄3年(1560年)には長宗我部元親の攻撃を受けて城主吉松掃部頭茂景は降伏した。 茂景は万々城へ移され、替わって中島大和が城主となり、秦泉寺大和と称した。「土佐軍記」によればこの秦泉寺大和は天正16年(1588年)に農民の私闘のことから元親の怒りに触れ、秦泉寺大和・掃部父子はともに滅ぼされたという。一方「古城伝承記」には秦泉寺城は天正16年には「荒城」と記されている。 大善寺:弘法大師四国八十八カ所御開創の砌、須崎の入海はきわめて広く、今の大師堂の地点は海に突き出た岬とっていた。当時は山越しに行くのを常としたが干潮の時はこの二つ石岬の端を廻って行くことができた。ところが同地は波浪いつも岩をかみ「土佐の親しらず」といわれ、波にさらわれて海の藻屑となるものも多く海難が多発し、そのうえ同地点は伊予石鎚山の末端に当たるので身に不浄あるものは時々怪異に出会うといっておそれられていた。 大師は、そのことを聞いて海岸にたつ大岩の上で海難横死者の菩提のため、海上・陸上の往来安全を祈願して祈祷を行い、一寺を建立したのが今の大師堂の起源である。それ以来難儀も軽減したので、誰言うともなく「二つ石のお大師さん」と呼ばれるようになったという。 二つの大岩は長年波荒く打ち寄せる波の力で磯になり丘になり、遂に昭和の初め防潮堤ができ、今はその姿を留めていない。寺伝によれば宝永四年(1707年)の大変までは古市町にあり八幡山明星院大善寺といい、法印職の住する中本寺格として八幡神社の別当職として末寺十七カ所寺を擁していたが(寺地境内は六反十二畝三歩・寺は三間に二十四間だったという記録がある)津波で流失し古城山のふもとに移ったものらしい。 後に明治の廃仏毀釈により廃寺となり、明治二十九年(1896年)大師の霊跡を惜しむ里人の手で再興され現在地に移転し寺の再建を計って今日に至っている。 尚、本堂前境内よりのながめは太平洋を眼下に一望でき「二つ石の上でお大師様」が今もみなさま方の幸せをとこしえに御祈願されております。 16:00高知空港に向かう。 17:00高知空港到達。 19:10高知空港出発 19:55伊丹空港到達。 今回の旅行、四国の高知県に足を運び、点在する霊場4箇所、お城7箇所を巡り楽しみました。 |
             |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第三百三十ニ弾:山形県東北三十六不動霊場&お城・城下町巡り観光 2015年10月17-18日 東北山形県に足を運び東北三十六不動霊場3箇所、南北朝時代の内乱の際、北朝方の欺波兼頼によって、一定の基盤が築かれ、兼頼の子孫は最上氏を名乗り、庄内地方の武藤氏、陸奥国伊達郡の伊達氏と争う。又江戸時代になって入った上杉氏ゆかりの城もあるお城・城下町6箇所をめぐりました。 17日16:15伊丹空港出発 17:30山形空港到達、レンタカーで新庄方面に向かう。 18:20新庄駅前のホテル到着後周辺を散策し食事を済ませて就寝。 18日7:30レンタカーで出発、鶴岡、酒田方面に向かう。 松山城:天明元年(1781年)酒井忠休によって築かれた。 慶安2年(1649年)中山支藩として陣所が置かれていたが三代忠休のとき築城が許可され松山城を築いた。 現在も大手門が現存し土塁と堀の一部が残る。 新田目城:築城年代は定かではない。 十一世紀後半に出羽留守所職に任ぜられた須藤氏が築いたのが始まりとされる。 平形舘:築城年代は定かではない。この辺りには出羽国府および国分寺が置かれていたと考えられてたが、発掘調査によっても奈良時代まで遡る遺物は発見されていない。 平形館は平賀館、金野館とも呼ばれ、天正18年(1590年)上杉景勝が太閤検地を実施したとき、これに抵抗して藤島城に立て籠もった平賀善可が館主と推測されている。 |
 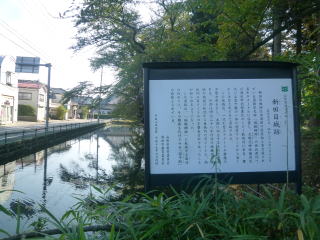          |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第三百二十四弾:秋田県東北三十六不動霊場&お城・城下町巡り観光 2015年8月22-23日 東北の秋田県に足を運び東北三十六不動霊場6箇所、お城・城下町9箇所をめぐりました。 22日16:55伊丹空港出発 18:15秋田空港到達、レンタカーで本荘に向かう。 19:00本庄駅前のホテル到着後周辺を散策し食事を済ませて就寝。 23日6:00レンタカーで出発、秋田市内に向かう。霊場、お城巡り。 普傳寺:普傳寺の開基は不明だが、初代、普光上人から数えて、現在義佑和尚まで十三代というが、この場合の初代は中興と考えられる。何故なら天和二年(1682年)尊慶なる僧、大館遍照院六代に赴く、とあり、江戸中期の所在を明らかにし、更に不動明王像は鎌倉期の運慶作という文化的価値を考慮すると、初代の事蹟は中興ということになる。秘宝、不動明王、弘法大師坐像は運慶の作風を伝え、秋田市の指定文化財である。 秋田城・出羽柵:天平5年(733年)の築城と云う。 東北地方における蝦夷への対策として庄内地方に出羽柵が築かれ、これを高清水岡に移し秋田城と改称した。 湊城:築城年代は定かではないが永享8年(1436年)安倍康季が築いたとも云われる。 属にいう安東三城(檜山城・脇本城・湊城)の一つ。その後、湊安東氏の居城として続いたが、天文20年(1551年)安東尭季が没すると、檜山安東氏の安東愛季の弟茂季が湊安東氏の家督を継いだ。元亀元年(1570年)豊島城主豊島玄蕃らが謀反を起こし湊騒動と呼ばれる内乱となると、檜山安東氏の援軍もあってこれを鎮圧した。天正7年(1579年)に茂季が没すると家督を継いだ嫡子高季が幼少であったこともあり、後見人となった安東愛李が事実上湊安東を併合する形となった。天正15年(1587)(秋田)安東愛李が没すると、翌天正16年(1588年)湊安東高李が戸沢・小野寺氏を味方にして謀反を起こした。家督を継いだ秋田実李はいまだ13歳と幼少で脇本城を棄てて檜山城へ逃れて籠城し劣勢であったが、由利十二頭の赤尾津・羽川氏の援助を得て形成は逆転し湊城は秋田実季によって落とされた。秋田氏は湊城を居城として豊臣秀吉に臣従し五万七千石を領していたが、関ヶ原合戦での不手際があり、慶長7年(1602年)安東実李は常陸国宍戸へ転封となり、替わって佐竹氏が秋田に入部すると久保田城を築いて居城としたため廃城となった。 嶺梅院:嶺梅院の縁起は定かではないが、一部に伝わる古文書に次のように記されていた。永福山嶺梅院は無等良雄禅師(南朝の忠臣萬里小路藤房卿と伝えられる)の閑居寺にして、現在の松原・補陀寺の場所に創建した。その後、寺風は荒廃して一宇を残していたが、寛延年中(1748年)蒼龍寺の桂岩極芳和尚が現在地に再興し、後地に補陀寺を移して曹洞禅の教化につとめたということである。 多聞院:多聞院の開山は、慈覚大師・安慧。一説には元禄年間(1688年)の創建ともいう。羽黒山系天台宗から発展した寺院という説もある。松前船・辰悦丸が航路の安全を祈願し、階の石段を寄進している。また、同船の錨は寄進され、境内に置かれている。 男鹿半島方面に向かう。 脇本城:築城年代は定かではないが、一説に元亀・天正年間(15701573年~1592年)頃に染川城主安東鹿季が築城したと伝えられる。属にいう安東三城(檜山城・脇本城・湊城)の一つ。元亀・天正年間初期の城主は安東修季で湊城主安東友季の後見人であった。天正5年(1577年)檜山城主安東愛季は湊安東氏を併合し、檜山城を長男業季に譲り脇本城を居城とした。安東氏は愛季の時に安東から秋田と改名している。愛季は天正15年(1587年)小野寺氏・戸沢氏と唐松山合戦の後、淀川の陣中で病没すると家督は嫡子実季が継ぐ。しかし、この時12歳と幼少であったためか、脇本城主修季は湊城主安東高季を扇動して謀反を起こした。この湊合戦と呼ばれる戦いで実季は脇本城を棄てて檜山城へ逃れて籠城する苦戦を強いられたが、由利十二頭などが檜山安東氏方となったことで形成は逆転し、湊城を落として終結した。 吉祥院:男鹿は仏教の発祥地、本山、真山、毛無山の三山がそびる、慈覚大師開祖の赤神山日積寺永禅院の信仰の地である。永禅院代五世覚運(953-1007)開基の塔頭寺院で叡山中興の祖、良源の高僧弟子で天台宗であった。明徳2(1392)年の頃、日積寺29世頼叶が高野山龍光院の感化をうけ真言宗に改宗された。幕末の頃、寺門の衰退に加え明治初年の廃仏棄釈で無住となり、幾度となく廃寺を免れ、再度の移転で昭和18年に現在地にその法燈を継承す。文応元(1260)年からの歴史をもつ、岡山県の福泉寺所蔵本奥書日書写、高野山で伝授の開運星祭り北斗護摩祈祷会と、聖天浴油供祈祷会などの行事がある。 玉蔵院:現在、真言宗智山派に属し、その昔、男鹿にあった日積寺永禅院の塔頭の一ヶ寺として創建され、天台宗の寺院であった。南北朝時代の頃に日積寺は真言宗に改宗するが、玉蔵寺も、その時改宗したものと思われる。今から約300年前、元禄の頃と思われるが、鮎川の寺畑(現在地より北方、高台の山林)へ移転、さらに200年前頃、現在地へ移転した。今の本堂は昭和58年に建立。本堂内陣の丸柱は、神代欅を使用。数千年、土の中に埋もれていた欅の丸柱が、神々しい光を放っている。 能代方面に向かう。 檜山城:築城年代は定かではないが14世紀中頃に安東忠季によって築かれと云われる。 安藤氏は安倍貞任の子高星丸が津軽に逃れ、後に藤崎城を居城としたことに始まる。安藤氏はその後十三湊へ移ったが、南部氏によって一時滅亡、南部氏に捕らわれていた師季(政季)が田名部の地を与えられ、安藤氏を再興した。政季は田名部から蝦夷ヶ島へ渡り、康正2年(1456年)に湊安藤堯季の支援を受けて小鹿島へ渡った。忠季のとき檜山へ移り、檜山城の前身となる檜山屋形を築いたという。檜山安藤氏(安東)は愛季のとき、湊城主湊安藤氏を併せて勢力を拡大していく。愛季の子実季のとき秋田氏に改称し、慶長7年(1602年)実李は常陸国宍戸へ転封となった。慶長7年(1602年)佐竹氏が秋田に入部すると小場義成や多賀谷氏の居城となったが元和6年(1620年)一国一城令によって廃城となり、多賀谷氏は麓に居館を築いて移った。 大館方面に向かう。 遍照院:大館盆地に位置する遍照院の開基は、小場義成(後に佐竹姓を名乗った)であるという。「大館城と関係社寺」から由来を抜粋すると、『常陸国那珂小場県遍照院開山は至徳三年(1386年)小場大炊助義躬が小場城外に一宇建立。本尊に薬師如来を安置する故に医王山長久寺遍照院と号す』とある。小場氏に随いて秋田に下向し、慶長十五年(1610年)大館に移建して三十石を付与されたという。 十狐城:築城年代は定かではないが永正年間(1504年~1521年)に浅利則頼によって築かれたと云われる。 浅利氏は甲斐国浅利郷を発祥とする甲斐源氏で文治5年(1189年)源頼朝による奥州藤原討伐に参陣し比内の地頭職を得た。南北朝時代には北朝方に属し南朝方であった南部氏の鹿角の諸城を津軽の曽我義氏らと攻めている。その後の動向は詳らかではないが、永正年間(1504年~1521年)に浅利則頼が十狐城を築き、小大名ながら一勢力を築いた。この則頼の出自は定かではなく「浅利軍記」などによれば甲斐国より比内に下向したとある。天文19年(1550年)浅利則頼が没すると長子則祐が家督を継いだ。浅利則祐は安東氏に属し、永禄年間(1558年~1570年)はじめには南部氏の長牛館を攻撃したが、永禄5年(1562年)則祐は安東氏との不和により攻められ長岡城で自刃して果てた。則祐の跡を継いだのは弟勝頼で、中野城より十狐城に移り、さらに長岡城に移っている。天正2年(1575年)浅利勝頼は独立を計り、田代町山田で安東愛季と戦い(山田合戦)花岡城主浅利定頼が討死するなど大敗を喫した。しかし、その後も浅利氏は安東氏とたびたび戦っている。天正11年(1583年)安東愛季は和睦交渉と偽って勝頼を呼び寄せ謀殺させた。勝頼の子頼平は津軽為信を頼って比内より逃れ、比内は安東氏の所領となった。天正17年(1589年)大館城代五十目兵庫秀兼が南部氏に内通して比内が南部氏に奪われると、翌年秋田実季は津軽為信と結んで比内を奪還する。このとき津軽氏に身を寄せていた浅利頼平は為信の斡旋により再び比内に戻り秋田氏に従って太閤蔵入地となった大館一帯を支配した。しかし蔵入米や文禄の役での金子の未納などの問題で再び浅利氏と秋田氏は対立し、慶長3年(1598年)浅利頼平は上洛中に大坂にて没し、浅利氏の残党は秋田氏に討たれ十狐城は破却され浅利氏は滅亡した。 大湯館:築城時期は不明。館主は鎌倉中期、地頭職として鹿角に入部した武蔵武士団横山党奈良氏の嫡流大湯氏とされます。入部以降、大湯氏は大湯川流域に勢力を扶植し、庶子家(小枝指氏・新斗米氏等)を各地に分知して惣領支配していたと思われますが、詳細な事績は不明。永禄9(1566)年、檜山城主安東愛季の鹿角侵攻が開始されると大湯四郎左衛門昌次は安保衆とともにこれに加担したとされ、また天正19(1591)年 「九戸の乱」が勃発すると四郎左衛門は九戸政実方に加担して鹿倉館に籠りましたが、大光寺正親勢の攻撃を受けたため鹿倉館をあきらめ九戸城に遁れました。しかし九戸城は奥州仕置軍の攻撃を受けて降伏し、四郎左衛門は九戸政実等とともに捕縛され、栗原郡三迫で処刑されました。乱後、大湯氏の所領は信直方に加担した四郎左衛門の兄五兵衛(彦六)昌忠に宛がわれましたが、天保年間(1644-48年) 昌忠のあとを継いだ門之助昌邦が死去したため大湯氏は改易となり、代わって毛馬内靭負範氏が大湯に入部しました。明暦3(1657)年、範氏が死去すると赤尾又兵衛が大湯代官に任ぜられ、寛文5(1665)年 赤尾氏が南部家を退去すると北九兵衛宣継が小軽米から所替で大湯に入封し、北氏が明治維新まで大湯館に在城しました。 小枝指館:小枝指館は七ツ館とも呼ばれるように七つの曲輪で構成された館である。 日本城郭体系に掲載されている縄張図には第一館から第七館として名称をふり、個々の名称は不明となっているのだが、たまたま畑仕事をしていた方と話した所、ここは○○、あっちは××と館の名称を呼んでいたようである。空堀の一部は道路などに転用されているものの、多くの空堀と曲輪群は良好に残っているようである。 石鳥谷館: 大里館: 15:00秋田空港に向かう。 16:50秋田空港到達。 18:50秋田空港出発。 20:10伊丹空港到達。 今回の旅行、東北の秋田県に足を運び東北三十六不動霊場6箇所、お城・城下町9箇所をめぐり楽しみましたました。 今回も東北の霊場、立派な寺院が多く、素晴らしかった。広く、真っ直ぐな道が多く、人も車も少なく、ドライブ気分で楽しむことが出来ました。 お城は、館と名のつくお城は、確認が難しく、広く田園風景に位置するのが多かったです。 東北秋田県に位置する霊場、お城ドライブ観光巡りでした。 |
              |
||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第三百二十ニ弾:北海道八十八箇所・北海道三十三観音&お城・城下町巡り観光 2015年7月25-26日 北の北海道に足を運び、夜景や教会群、赤レンガで有名な道南の函館エリアの北海道八十八箇所の2箇所、北海道三十三箇所観音2箇所、比較的マイナーなお城・城下町8箇所を巡りました。 25日15:30関西国際空港出発 17:10函館空港到達、レンタカーで霊場めぐり。 高野寺:明寺初年に函館港の発展に伴って本州からの移住が日を追って増加し、随って真言宗を信仰する人も増え、檀信徒の間に寺院設立の声が高まり明治16年に真言僧が布教来函の時に後に総代になる遠藤吉平氏が主となって相談して一寺建立の義纏まり、同年9月に大塔再建勧奨の為に本道を巡教されていた高野山真言管長獅岳快猛大僧正に新寺建立の願いを申し述べて、新寺建立の許可を得て、翌17年東川町に本山より下付された大日如来を本尊として一宇を建立したのが本寺の創りです。後青柳町に移転、大正3年の大火に類焼のため現在地住吉町に移転するも、昭和9年の大火で再び類焼、当時の第9世原田智厳師はその時代の寺院建設には考えられなかった鉄筋コンクリート建本堂(現在の本堂)を昭和12年に落成する。 本尊大日如来は2度の大火とも運び出して難を逃れ、昭和42年国指定重要文化財に指定される。 善導院:当院は昭和六十二年に開山主恵晃師が大聖不動明王を御本尊とし、当地、山の手の高台に本堂を建立しました。 以来、宗祖弘法大師の御教えを伝燈すると共に、真言密教の護摩修法により、災厄、霊障に悩まれる方々をお救いし今日に至っております。又、平成十九年には、北海道八十八ヶ所霊場第六十四番札所として、霊場御本尊「阿弥陀如来」を奉安し、菩提の道場として多くの巡礼者が参拝されております。 神山教会:明治33年、篤親家室本幾太郎翁が神山村の山中に四国八十八ヶ所の石仏を安置する。 明治36年、室本翁より境内地の寄進を受け小山智道僧正「真言宗神山説教所」開山。 昭和17年、「真言宗神山教曾」と改称。 昭和29年、開山50年にあたり、中興丸山哲應僧正堂宇を現在地に移転改築する。 昭和63年、弘法大師御入定1,150年と開山88年を記念して堂宇を新築する。 平成14年、開山100年記念法要厳修 大宝寺: 18:30江差方面に向かう。 19:40江差市内のホテル到着後周辺を散策し食事を済ませて就寝。 25日7:30レンタカーで出発、お城巡り 舘城:明治元年(1868年)、箱館戦争の直前に松前藩により渡島国檜山郡の館(現在の厚沢部町)に建造された日本の城である。従来の本拠である松前城に対し、新城とも言う。完成直後に旧幕府軍の攻撃を受け、落城した。国の史跡に指定されている。 蝦夷地を支配する松前藩は松前城を本拠としていたが、明治元年7月に起こった正義隊のクーデターにより尊王派に転じた後、旧幕府軍の攻撃に備えて、内陸部に新城を建設することとし、9月1日、箱館府に築城を願い出るとともに、工事に着手した[2]。 松前城は艦砲射撃を受けるおそれがあること、従来の漁業・交易経済からの転換を図るため厚沢部川流域開墾の拠点とすること、が館城築城の目的であった。工事を突貫で進めた結果、10月末には一応の完成を見た。 花沢館:源頼朝は、文治5年(1189)に奥州藤原氏を滅ぼすと、津軽に東北北部や北海道の「蝦夷」を支配する「蝦夷管領」を設置し、俘囚安倍氏の系譜を引く安藤氏を配した。 安藤氏は、十三湊を拠点に北方との交易を行なうが、15世紀半ばに南部氏との争いに敗れ、道南へ逃れた。その後も、本州最北部では豪族間の争いが続き、享徳3年(1454)には、下北半島田名部の安東(藤)政季が、内紛で若狭武田氏を出奔した武田信広らを伴い渡島半島に渡った。 こうした状況を反映して、当時の渡島半島には、和人、和人系渡党、アイヌ系渡党、アイヌなど多様な人々が住んでおり、その中から交易などで富を得た小豪族らが館(たて)を築いていった。 花沢館もそうした館の一つであり、道南には東の志苔館から西の花沢館まで12の館が築かれた 勝山館:築城年代は不明だが、館北端にある館神社の創建が文明5年(1473年)と伝えられているため、この頃の築城と推定されている。蠣崎信広あるいはその子光広以降、蠣崎氏の本拠地とされていたが、光広の時代の永正11年(1514年)に松前の徳山館に本拠を移転して以降は、主要な副城として脇館転じて「和喜の館」と称され一族を配した。 夷王山の中腹、南から北へと伸びる斜面を利用して長さ270メートル、幅100メートルで総面積20.9万平方メートルの規模を有する。さらに城の背後から山頂に向かって中世和人の墳墓群(夷王山墳墓群)が存在する。 戦後、夷王山墳墓群の調査が先行され、館そのものの本格的調査は昭和52年(1977年)の史跡指定後の昭和54年(1979年)になってからである。その結果、15世紀後期から16世紀後期にかけての陶磁器・金属器・漆器・骨角器など7万点におよぶ遺物が出土しており、主要な遺物921点が国の重要文化財に指定されている[2]。 松前方面に向かう。 松前大館:松前大館はもともとは津軽を本拠として蝦夷地もその領有下としていた安東氏の蝦夷地の拠点として作られたようです。コシャマインの戦いの時も、安東氏の同族である下国定季と相原政胤が守将となっていましたが、アイヌの攻撃に抗しきれず陥落しました。しかしすぐ回復し、下国氏が守護していましたが、定季の子恒季は非法が多く、秋田安東氏によって滅ぼされ、相原季胤・村上政儀が守将となりました。 永正9年(1512)、アイヌの攻撃により陥落、両守将は戦死しましたが、これは蠣崎氏二代光廣の策謀によるものと言われています。そして同11年(1514)光廣は上ノ国から大館に移り、徳山館と名を改め安東氏の代官として蝦夷地支配をを進めました。その後もアイヌの攻撃がありましたが、慶長11年(1606)に福山館(松前城)に移るまで蠣崎氏政権の拠点でした。その後は万一の場合の隠し砦としてそのまま保存され、現在に至っています。 大館跡は発掘調査が行われておらず謎がまだ多いようですが、天然の要害を利用した大規模な山城だったようです。 函館方面に向かう。 茂別館:鎌倉時代から室町時代中期にかけて、道南地方には和人の館が12あり、茂別館(もべつだて)も、そのうちの1つであった(*道南12館)。 嘉吉3年(1443)津軽十三湊城主・安東太郎盛季が館を造ったのに始まるといわれ、南の大館と北の小館から成っている。 大館は、西は茂辺地川岸に面し、南と北は自然の沢で切られ、東は空濠を巡らしている。 また、小館は、西は茂辺地川左岸の崖地で、他の三方は、自然の沢を利用し、更に土塁を設けている。 康正2年(1456)のアイヌ人の蜂起(*コシャマインの乱)があった時も、花沢館とこの茂別館の2つだけが最後まで落城しなかった。 松前藩戸切地陣屋:北斗の町から北西に4kmほど、大野平野の西の外れに松前藩戸切地陣屋跡がある。箱館開港に伴う外国船渡来による不測の変に備えて幕府は松前藩に七重浜から木古内までの守備を命じ、1855年にこの戸切地陣屋が構築された。陣地は蘭学の築城書による四稜堡で広さは4.3ヘクタール。東南部の稜堡に6門の砲座を配置した。郭内には17棟の建物があり約120人で守備していたが、1868年の箱館戦争時、榎本武揚率いる旧幕府残党に追われて相手方に陣屋が使われないよう建物に火をつけ焼払って敗走した。この陣屋は建物こそ焼失しているが保存状態が極めてよく、幕末における北辺の国際情勢や西欧風の影響を知る資料として築城史上価値ある史跡である。表御門跡と裏御門跡には大手門と搦手門が復元され、門から入ると広い郭内には大砲入跡、筒入跡、蔵跡、備頭・目付詰所跡、足軽長屋跡、武器庫跡などがあり、石で基礎を再現して跡地を表示している。1904年に日露戦争を記念して陣屋跡までの800mの一本道に585本の桜の木が植えられた。以後この松前藩戸切地陣屋跡は桜の名所として知られるようになり、5月上旬~5月中旬にかけて桜並木が見頃を迎える。 四稜郭:箱館戦争の際に蝦夷共和国(箱館政権)が、明治2年(1869年)に現在の北海道函館市に築城した堡塁。新台場、神山台場、新五稜郭などとも呼ばれる。四稜郭の名称は4つの突起を持つ事に由来する。幅2.7m、深さ0.9mの空堀に囲まれ、土塁の規模は東西約100m、南北約70m、幅5.4m、高さ3mである。土塁の四隅には砲座が配置されている。南西側に門口があり、その後方に幅0.9mほどの通路が設けられている。郭内には建物は建設されなかったと考えられている。面積は約2万1,500平方メートルを有する。 五稜郭を援護する支城として、また東照宮を守護する為に北東約3キロメートル離れた丘陵上に洋式築城法により築かれた。建設を指揮したのは大鳥圭介あるいはブリュネ大尉といわれている。建設には旧幕府兵卒200人および近隣住民100人が徴用され、昼夜兼行の突貫工事で造り上げたと言われる。しかし、堡塁としては脆弱であり、立て篭もるには手狭で井戸等の設備も存在しなかった。星形要塞であるものの、実際には野戦築城に近いものである。四稜郭以外に当時造られた要塞としては七飯町の峠下台場がある。こちらは漫画の吹き出しのような七稜形(Tenaille:欧米では星形要塞とは区別される形態の築城方式)である。 昭和9年(1934年)国の史跡に指定された[1]。当時は周囲が耕作地になるなどして土塁が一部崩されていたが、昭和48年(1973年)に元の形に修復された。 志苔館:北海道函館市に所在する中世城館跡(日本の城)。小林氏によって築かれたとされる道南十二館のひとつ。国の史跡に指定されている。館跡は、自然地形を活かし、四方に土塁と薬研(やげん)または箱薬研状の空堀が巡らされ、全体でほぼ長方形の形状を呈している。内部は東西約70-80メートル、南北約50-65メートルで、約4,100平方メートルの広さがあり、曲輪の内部では掘立柱建物跡や井戸が確認されている。土塁の高さは、北側で約4.0-4.5メートル、南側で約1.0-1.5メートルであり、土塁の外側にあたる北側と西側には幅約5-10メートルの空堀が設けられ、最も深い所で約3.5メートルの深さをもつ。 発掘調査では、15世紀前半ごろを主体とする青磁・白磁・珠洲焼・越前焼・古瀬戸などの陶磁器が出土している。これらの遺物の年代は『新羅之記録』に記された長禄元年のコシャマインの戦いにおける志苔館陥落の時期(1457年)と矛盾しない。 15:20函館空港に向かう。 17:45函館空港出発。 19:40関西国際空港到達。 今回の旅行、北海道の道南地方に点在する、北海道八十八箇所の2箇所、北海道三十三箇所観音2箇所、比較的マイナーなお城・城下町8箇所を巡り楽しみました。 霊場は前回と同様に寺院に似つかない建物も有りましたが、立派な寺院風の建物も多く見られました。 一方お城は北海道らしく公園のような広々とした敷地面積の広いお城後が殆どでゆっくり散策することがで来ました。 今回感じたことは函館では外人さんにはあまり出会いませんでしたが(マイナーな霊場、お城のためか)、関西空港に向かうはるか、関西国際空港内、帰りの空港バスには多くの外人を見かけ、外国観光客が急速に増えているのがわかります。日本も観光大国になったのでしょうか。 |
               |
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第三百二十弾:青森県東北三十六不動霊場&お城・城下町巡り 2015年7月11-12日 本州の最北端、十和田湖、奥入瀬、白神山地で有名な青森県に足を運び、反時計回りで青森市、津軽、深浦、弘前に点在する東北三十六不動霊場6箇所、比較的マイナーなお城・城下町6箇所を訪れました。 11日16:20伊丹空港出発 17:50青森空港到達、レンタカーで青森市方面に向かう。 18:00青森市内のホテル到着後周囲を散策し食事を済ませて就寝。 12日7:00レンタカーで出発、青森市内の霊場を巡る。 青龍寺:青森市郊外の東寄りに位置した桑原地区は、武兵衛川が北流して平野部を潤す農圃地帯で、山崎の山林に戸崎館趾がある。館主、壘砦の年代は不明とされているが、近年、この近くに日本一を誇る昭和大仏が開眼された。昭和大仏は大日如来で、無限の智恵、無限の慈悲、無限の能力を象徴している。 青森寺:当山の開基は、明治21年9月。ご本尊は大慈大悲のご利益厚き、大聖不動明王である。千葉の成田不動尊詣での為に組織されていた成田講の人々が、青柳に不動堂を建立したのが始まりである。その后年々隆盛を極め明治41年、現在地に本堂を建立、信徒も市内のみならず、八戸、十和田、鰺ヶ沢など県下全域に及ぶに至った。しかしながら、昭和20年7月の空襲で堂宇本尊悉く灰燼に帰した。堂宇再建の為、県内はもとより東北各地のご信者より志納を募り、ついに昭和32年7月、輪奐旧に倍し立派に本堂再建が成った。ついで35年、不動明王ご本尊も目出度く開眼、奉安された。以後鎮守稲荷堂、清瀧権現堂、を建立。更には昭和60年本坊客殿建立。平成2年、生れ年1代尊並びに仁王尊像造立し現在に至る。当山の年中行事で代表的なものは、2月の節分会と7月の灯籠流しである。節分の豆撒きには、厄除祈願の善男善女が多数参集し、その規模は県下一である。又夏の灯籠流しは、川面を幻想的な光で彩り、誠に叙情的で短い青森の夏には欠かせぬ風物詩となっている。 津軽半島に向かう。 尻八館:築城年代は定かではないが安東氏によって築かれたと云われる。暦応2年(1339年)の「曽我貞光申状」に曽我貞光が「尻八楯」の安東四郎道貞(潮潟道貞)を攻めた記録があり、この尻八館に比定する説がある。現地の案内板によれば、寛喜2年(1230年)安東一族がアイヌのチャシを土台として尻八館を築き、貞永元年(1232年)安倍三郎成季が治領代頭役に任ぜられた。正安2年(1300年)安東孫次郎が尻八館城主となり、明徳4年(1393年)安東四郎道貞が尻八館城主となって潮潟四郎と名乗った。応永32年(1425年)道貞の長男重季が鉢巻館より移り、重季は南部義政の女を妻とした。永享7年(1435年)尻八館は南部義政に攻められ落城し、このとき重季の子政季が捕らえられたが義政の女の子であるので八戸で育てられ、成人して旧安東家の知行を継いだ。 中里城:中里城の創建は明らかではないが、発掘調査の結果、遺構は縄文時代前期(約5500年前)まで遡れるという。 城主に関しては、建武元年(1334)の『津軽降人交名注進状』に新関又二郎の名が見える。 他には津軽氏に追われて南部八戸へ逃れた中里半四郎や、また城の西下には高坂修理の居館があったとされる。 福島城:築城年代は定かではないが正和年間(1312年~1317年)頃に安倍貞李(安藤貞李)によって築かれたと云われる。 藤崎城を拠点として津軽に根付いた安藤氏は鎌倉時代後期頃に十三湊へ移り、蝦夷との公益で栄えていた。永享4年(1432年)安藤康李のとき南部守行・義政父子によって攻められ福島城と唐川城は落城、康李は柴崎城へ逃れた。この戦いは室町将軍足利義教の命によって康李の妹が南部義政に嫁ぐことで和睦がなされたが、嘉吉2年(1442年)再び南部氏に攻められ、安藤氏は津軽を離れて蝦夷島へ逃れた。 十三湊安藤氏は、その後南部氏に捕らわれていた安藤師李(後の政李)が南部氏から田名部を賜り、十三湊安藤氏を相続した。しかし政李は享徳3年(1454年)に田名部から蝦夷ヶ島へ渡り、二年間滞在したのち小鹿島へ上陸、その末裔が檜山安東氏となっていく。 唐川城:築城年代は定かではない。一般的には鎌倉時代末頃に安藤貞李によって築かれてたと云われているが、発掘調査によってそれ以前の平安時代後期に築城されていたことが判明している。 安藤氏は福島城を居館、この唐川城を詰城として築いたが、永享4年(1432年)と嘉吉2年(1442年)に南部氏によって攻められて落城し、安藤氏は蝦夷島へ落ちていった。 弘法寺:津軽半島の中程にある木造町の開拓は比較的遅く、当山の縁起についても、開創等は記録がなく不明な点が多い。 唯一現存する七代目住職の位牌が六〇〇余年前の物ということである。一時洪水等の天災で寺が消失した時期があったらしく、明治に入ってから再興された。再興後は九十九森寺と呼ばれていたが、昭和に入り、弘法寺と改称された。 種里城:延徳3年(1491年)南部光信(大浦)によって築かれたと云われる。 津軽藩初代津軽為信の祖とされる光信は、延徳3年(1491年)九戸郡下久慈より入部した南部一族と云われる。 文亀2年(1502年)光信は大浦城を築き、子の大浦盛信を置いた。光信は大永6年(1526年)種里城にて没し、以後、大浦氏は大浦城を本城として五代為信の代に至る。この為信は久慈城主久慈信義の弟十郎が津軽郡代の石川高信を頼り後に大浦氏の養子となったという説がある。 深浦に向かう。 深浦城:深浦港の南方500mの沢に挟まれた丘陵端に位置する。南方に5本の空堀があり、他の三方は沢に続く急斜面となっている。曲輪は2つあり、北側の一段高い位置に東西33m、南北88mの主郭がある。二の郭は東西80m、南北100mほどの規模だった。 南部氏によって所領を失った安東氏が当地に来て再起を図り、当城を築いた。その後、葛西頼清が本拠とした。最後の城主は千葉弾正で、戦国時代まで使用されていたものと推測される。 弘前方面に向かう。 最勝寺:東北地方で五重塔のある名刹として知られる金剛山光明寺最勝院は、常陸国桜川の弘信法印開基である。天文元年(1532年)津軽に下向し平賀郡堀越城外の北、荻野という処に伽藍を造営した。 これが最初とされるが、それ以前の古文書に最勝院という文字が見えることから、創立年代はもっと古いという。 大圓寺:大鰐温泉郷の中にある大円寺は、もと阿闍羅山千坊と称された高伯寺に由来する。寺伝に依ると、奈良時代、聖武天皇の国分寺建立に始まり、本尊大日如来を阿闍羅山の大安国寺に安置されたことに起こる。 その後、大安国寺は荒廃し、鎌倉時代建久二年、神岡山の高伯寺に移奉された。のち慶安三年(1650年)津軽三代信義公が高伯寺と本尊を現在の場所に移し、以来津軽家代々の崇敬を受けてきた。 ところが明治四年、弘前にあった大円寺(現在の最勝院)の寺号を以て高伯寺を大円寺とした。 本尊大日如来は大正九年に国宝の指定をうけ、昭和二十七年には国定重要文化財となった。 國上寺:当山は人皇第三十四代推古天皇御宇十八年(610年)国家北門鎮護のため、聖徳太子の命を受け泰川勝公が開基。建長六年(1254年)北条時頼公本尊並びに法具を現在地に奉移し、三森山不動院古懸寺とし、鎌倉将軍数代の祈願所とした。 天正十六年(1588年)津軽右京亮為信公国上山不動院古懸寺と改め鎮護国家、津軽家領域安泰のため、更に仏殿、山門、護摩堂、大師堂などを造営し、寺領地二百町歩、寺録百石を贈り、津軽家歴代の祈願所とした。 明治二十六年(1893年)旧正月七日火災のため本堂並びに仏堂を焼失、消失をまぬがれた護摩堂を本堂として、昭和五十四年現本堂建立まで寺務を執行した。 16:30青森空港に向かう。 17:10青森空港到達。 18:20青森空港出発 19:55伊丹空港到達。 今回の旅行、本州最北端の青森に足を運び反時計回りで青森市、津軽、深浦、弘前に点在する東北三十六不動霊場6箇所、比較的マイナーなお城・城下町6箇所を訪れ楽しみました。 前回の北海道旅行と同様に、天候晴れ、絶好のドライブ日和、ドライブ兼ねての霊場、お城巡り堪能しました。 やはり東北の霊場、立派な寺院が多いですね。歴史の深さを感じます。 特に青龍寺の巨大な大仏は圧巻でした。日本一大きな大仏でしょうね。 好天に恵まれたドライブを兼ねた霊場、お城巡り観光でした。 |
          |
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第三百十八弾:山形県東北三十六不動尊霊場&城・城下町巡り観光 2015年6月27-28日 サクランボ、蔵王で有名な東北の山形県に足を運び、山形県内の秋田・青森・岩手・宮城・福島の東北6県をそれぞれ六波羅蜜の道場に見立て、各県で6つの札所を巡る東北三十六不動霊場3箇所、城・城下町12箇所を訪れました。 27日16:15伊丹空港出発 17:30山形空港到達、レンタカーで天童方面に向かう。霊場巡り。 大樹院:山形盆地の東端に位置した青野郷は、大岡山から南に広がる農業地域で、丘陵には果樹園が営まれている。大樹院はこうした中に在り、裏山一帯ではリンゴの栽培が行われている。本尊不動明王には、このような話しが伝わっている。「請雨瀧不動尊は、往古、弘法大師湯殿山を開基し給いしのち下山の砌り、最上荘大早魃に罹れ、雨を乞うとて諸俗あつまり西根より東根に至るまで其の趣き成る故、悉くそれを憐み給い、弘法大師辰己の方につき、山に下りて雲を発し候故に此処に山篭し玉いて雨を乞うに、則ち雷不動尊あらわれ給い、弘法大師、請雨瀧に勧請せらる」と。 光明院:温泉と将棋の駒で有名な天童市で、光明院は上山口村に伽藍を鎮め、高瀧不動尊の本坊として、土地の信仰を集めている。 不動尊利益和譛から縁起を見ると、「聖武天皇の御宇、行基菩薩が開眼した景勝無双の霊地にて、その霊験は世々に赫灼なり」と記す。不動尊の影現は滝の魔崖仏である。峻厳な山の気を分けて千仞の谷に降りると、幽邃境に瀑布がひびき、屏風岩に不動明王と阿弥陀仏の影向を拝することが出来る。 慈恩寺:寒河江市は最上川と支流の寒河江川に挟まれた農畝地帯で、慈恩寺の文化を中心に発展してきた地域である。 草創は神亀元年(724)に遡り、行基菩薩が諸国遊錫に訪れ、都に帰った折り、この地の景勝を奏上された。時に天平18年(746)印度の波羅門僧上が勅宣を以って開山し、勅願寺と定められたのが始まりと伝えられている。 往古は天台宗・真言宗の二宗兼学によって護られてきた。近年に山内を統一し、最上院、華厳院、宝蔵院とこれに属した十七坊で一山組織を形成し独立した。 17:00天童駅前のホテル到着後周辺を散策し食事を済ませて就寝。 28日7:00レンタカーで出発、お城巡り。 天童城:天童城は、天授元年に天童頼直によって築かれた。 南北朝時代に北畠天童丸が築いたとも云われているが、定かでない。 天童頼直は、山形城主斯波(最上)直家の二男で里見氏の跡を受けて天童に入り、天童氏を称した。 天童氏は、『最上八楯(天童・延沢・飯田・尾花沢・楯岡・長瀞・六田)』と呼ばれる村山地方の館主の盟主として、惣領家最上氏に匹敵する勢力を誇った。 天正12年、天童頼久は最上義光に天童城を攻められ落城し、城は廃城となった。 尚、天童頼久は、国分氏を頼って逃れ、のち伊達氏に仕えた。 寒河江城:寒河江城は、嘉禄年間に大江親広によって築かれた。 親広は、鎌倉幕府創世記の重臣大江広元の嫡男で、建久3年に父より寒河江荘地頭職を譲られ、承久の乱で敗れた後に寒河江に逃れて土着する。 8代時氏から寒河江氏を称した。 寒河江氏は、戦国時代になると最上氏の勢力拡大により都度攻防を繰り返したが、天正12年最上義光によって寒河江高基は滅ぼされた。 山形方面に向かう。 畑谷城:築城年代は定かではない。 城主は江口五兵衛光清で、上杉領との境に位置する要所の為、武勇の誉れ高かった江口氏が長岡城より八千石を領して移封されたという。 慶長5年(1600年)関ヶ原合戦前、上杉討伐のため北上中の徳川家康は石田三成の挙兵により西へ引き返す。最上氏は南部氏などの諸将を最上へ集結し米沢口より会津領へ押し寄せる予定であったが、石田三成の挙兵を聞いた諸将は領内の安定をはかるために領国へ退いてしまう。上杉氏は周辺大名の動向を見たうえで、直江兼続を主将とする大軍を最上領へ侵攻させる。これに対して最上軍は各出城を破棄して兵力を集中させることを目指すが、畑谷城主江口光清は、敵を目の前にして城を明け渡すのは武士として末代までの名折れとして上杉軍を迎え撃った。義光は飯田播磨守・谷柏相模守などを援軍として派遣したが、到着する前に落城、勝ちに乗じた上杉軍は軍勢を二手に分け長谷堂城・上山城へと向かった。 長谷堂城:長谷堂城は、築城年代や築城者については定かでない。 永正11年に伊達氏が最上方の長谷堂城を落としたとの記録があり、この頃には既に最上氏の城として機能していた。 慶長5年、直江兼続に率いられた上杉軍2万が米沢から東軍に与した山形城の最上義光を討つべく北上して、長谷堂城を囲んだ。 城主志村光安は上杉の猛攻から長谷堂城を守り通し、上杉勢の山形盆地進入を阻止した。 翌年、志村光安はこの戦功により東禅寺城3万石の城主となった。 その後坂紀伊守が城主となったが、元和8年に最上義俊改易となり、長谷堂城も廃城となった。 上山城:上山城は、天文4年に武衛義忠によって築かれた。 羽州街道の要衝の地である上山城は、慶長5年に西軍に与した直江兼続率いる上杉の大軍に攻められたが、城主里見民部以下の奮戦により撃退した。 関ヶ原以後、城主は里見・坂氏、次いで最上義光の五男義直(上山光弘)が城主となり、21,000石を領した。 元和8年、最上義俊改易になり、義直も筑前黒田氏へお預けとなった。 同年上山へは遠江横須賀より松平重忠が入封し4万石を領した。 松平-蒲生-土岐と城主が変遷したが、元禄5年に土岐頼殷が越前野岡へ移った後、上山城は幕命により破却された。 その後、金森頼時、元禄10年には備中庭瀬から松平信通が3万石で入り、以後松平(藤井)氏が10代続いて明治に至った。 中山城:中山城は、戦国時代の永禄から元亀年間に米沢城主伊達輝宗の家臣中山弥太郎によって築かれた。 天正18年、蒲生氏郷が会津若松に入ると、中山城は蒲生領となり、氏郷は、重臣蒲生郷可に13,000石を与え城主とした。 この蒲生時代に城の修築と拡張がなされたと考えられている。 慶長3年、上杉景勝が越後春日山から会津へと移封され、中山城へは横田旨俊が城代として入った。 慶長5年に関ヶ原の役後、中山城は廃城となったが、その後も山麓には御役屋陣屋が置かれた。 米沢方面に向かう。 館山城:築城年代は諸説あるが天正15年(1587年)頃に伊達政宗によって築かれたとの説が一般的である。 天正12年(1584年)伊達輝宗が隠居所として館山へ移つり、隠居所の普請が完了するまで家臣鮎貝宗重宅に住み、翌13年に移ったという。天正15年(1587年)には政宗自身が地取・縄張して築城を開始、しかし天正19年(1591年)には領地替えで岩出山城へ居城を移し廃城となった。また一説には、伊達氏が米沢を居城としていたのは米沢城ではなく、この館山城という説があり、政宗の普請はそれを改修したとする説がある 最上方面に向かう。 延沢城:天文16年(1547年)野辺沢(延沢)薩摩守満重によって築かれたと云われる。 野辺沢氏の出自は詳らかではないが天童氏に従っており、満重のときに野辺沢城を築いて本町館より移ったとされる。 満重の子が野辺沢(延沢)能登守満延で、天正12年(1584年)嫡男又五郎(後の光昌)に最上義光の娘松尾姫を迎え、最上氏に従ったことから天童氏は滅亡した。天正19年(1591年)満延が没すると光昌が家督を継いだ。 野辺沢(延沢)遠江守光昌は長谷堂城の戦いや庄内退治などに参加し、二万石を領したが、元和8年(1622年)最上氏が改易となると肥後国熊本藩加藤氏にお預けの身となり、熊本にて病没した。 最上氏に代わって鳥居氏が山形へ入部すると家臣の戸田玄蕃が城番として延沢城に入ったが、寛永7年(1667年)に廃城となった。 小国城:築城年代は定かではないが、細川氏が岩部館(小国城)を築いて富沢館より移ったのが始まりとされる。 細川摂津守直元は天童城主天童頼澄に娘を嫁がせるなど天童氏と結んで最上氏に対抗する。 天正12年(1584年)天童城は最上義光によって落城、城主天童頼澄は陸奥へ逃れ天童氏は滅亡する。この勢いに乗じて最上軍は山刀伐峠を越えて小国郷へ侵攻し、細川直元はこれを馬騎原で迎え撃ったが敗れ滅亡した。この戦いで格別の功があった蔵増城主倉津安房守は小国郷八千石を得て、嫡子が小国日向守光基と名乗って小国城を改修し居城とした。 元和8年(1622年)最上氏が改易となると陸奥国仙台伊達氏によって城は接収され破却、廃城となった。小国光基は肥前国佐賀鍋島氏にお預けとなり、小国郷は新庄藩の所領となって、小国城の麓に代官所が設けられた。 新庄方面に向かう。 新庄城:天正8年、日野有祐によって築かれたと言われている。 日野氏は山形城の最上氏に臣従して、「最上四十八館」の一つに数えられている。 しかし、元和八年に最上義俊の改易と共に廃城となった。 同年、常陸松岡より戸沢政盛が六万石で新庄の北方真室城に入封した。 政盛は、寛永2年に新田分を加え67,000石を領し、翌年に新庄城を再築した。 戸沢氏は、明治まで11代この地を動くことなく明治に至った。 鮭延城:築城年代は定かではないが佐々木綱村によって築かれたと云われる。 佐々木氏は近江源氏佐々木の一族と云われ、佐々木綱村のとき近江国より出羽国へ下向し、仙北の小野寺氏の客将となったという。 鮭延城の築城に関しては諸説あり定かではないが、佐々木氏は当初岩鼻館を居城としていた。しかし、庄内の大宝寺氏との戦いで敗れ、当時幼小であった秀綱は大宝寺氏に捕らわれて庄内へ連れ去られ、岩鼻館周辺の所領を失った。その後、佐々木氏は真室郷へ退き鮭延城を築き居城としたと云われる。 天正9年(1581年)鮭延秀綱のとき最上義光の攻撃を受けて降伏、その後は最上氏に従った。鮭延秀綱は以後、最上氏北方の拠点として小野寺氏などとの戦いで戦功を挙げた。 慶長5年(1600年)上杉景勝が最上領に侵攻した長谷堂城の戦いで、鮭延秀綱はその武勇を大いに知らしめ、重臣として一万一千五百石を領した。 しかし、元和8年(1622年)最上氏は改易となり、秀綱は下総国佐倉藩主土井利勝にお預けとなった。その後、秀綱は客分として五千石を領し、土井氏の古河転封にも従い天保3年(1646年)に没した。 その後、常陸国松岡より戸沢政盛が六万石を領して入封すると、当初は鮭延城を居城としたが、寛永元年(1624年)新たに新庄城を築いて移り廃城となった。 清水城:築城年代は定かではないが文明10年(1478年)頃に清水満久によって築かれたと云われる。 清水満久は最上の祖である斯波(最上)兼頼の曾孫で、鳴沢城主鳴沢兼義の次男である。 最上氏は北方の守りを固める為に鳴沢満久をこの地に封じ、清水氏を称した。 満久は当初白須賀の元館を築いて居城としていたが、文明10年(1478年)頃に清水城を築き、以後代々清水氏の居城となった。 長年にわたり庄内の大宝寺氏と争っていたが、永禄10年(1567年)頃には大宝寺氏によって清水城は落城した。 六代清水義氏には嫡子なく、最上義光の三男義親を養子に迎えた。この頃には清水氏は二万七千石余りの所領を持っていたという。 最上義光には三男の男子がいたが、嫡男義康は山形城に置いたものの、次男家親は徳川家、三男義親は豊臣家に近侍として奉公させていた。嫡男義康は義光より早く没し、家督は次男家親が継いだ。徳川家康の諱を受けた家親と、豊臣家に仕えた過去を持つ清水義親は氏第に対立が深まり、慶長19年(1614年)家親の命を受けた延沢遠江守光昌らが清水城を急襲し落城、清水氏は滅亡した。 14:30山形空港に向かう。 15:25山形空港到達。 18:00山形空港出発 19:45伊丹空港到達。 今回の旅行、東北の山形県に足を運び、山形県内の東北三十六不動霊場3箇所、城・城下町12箇所を訪れ楽しみました。 霊場は歴史深く立派な歴史的建造物でした。一方お城は、戦国時代戦いのために築かれた山城が多く、山頂にこじんまりした城跡を確認できました。 平城は権力者の住まいとして立派住まいを想像できる城跡でした。 比較的マイナーな城跡めぐり、見つけるのが一苦労要しますが、どんな城跡か、歴史的意味はなにか、楽しみなお城巡り満喫しました。 |
                 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第二百九十四弾:愛媛県お城・城下町巡り観光 2014年12月20-21日 四国の中心地愛媛県に足を運び比較的マイナーなお城7箇所(荏原城、港山城、恵良城、鷺森城、西条藩陣屋、川之江城、新谷藩陣屋)を訪れました。 20日14:20伊丹空港出発 15:15松山空港到達、レンタカーで城めぐり。 荏原城:この城跡は、室町時代から戦国期、伊予の豪族河野家十八将の首位であった平岡氏代々の居城跡である。高さ五メートルほどの土塁を周囲に築き、方形の平地で、長さは約東西130メートル、南北120メートル、堀の幅は北側20メートル、西と東は14メートル、南は10メートルで、南側で外とつながっている。四隅に櫓があったらしく西南の隅に石積みがある。矢竹が植えられているのは、この期の城塁に共通する特色である。建武二年(1335)、怱那氏が「会原城」で戦ったという記録が『怱那一族軍忠次第』にあり、築城は、それ以前である。土佐からの侵入を防ぐ拠点であったが、天正十三(1585)年平岡通倚の時、秀吉の四国統一により、道後湯築城とともに落城した。 17:30松山駅付近のホテル到着後繁華街を散策し食事を済ませて就寝。 21日7:00レンタカーで出発、お城をめぐる。 港山城:築城年代は定かではないが建武年間(1334年~1338年)に河野通盛によって築かれたと云われる。 湯築城を居城とした通盛が海辺を防御するために築いたと城だと云われる。河野本家と予州家による内紛では、予州家の河野通春が拠点としていたが、通春が病没すると攻め落とされた。天正13年(1585年)豊臣秀吉による四国征伐で落城し廃城となった。 恵良城:築城年代は定かではないが治承5年(1181年)以前に河野氏によって築かれたと云われる。治承5年(1181年)河野通清が源氏に味方して高縄山城に挙兵するに及んで、備後国の奴可入道西寂が大軍をもって押し寄せたので、通清は日高・高穴・恵亮(恵良)の砦を守らせて防戦するも賓兵敵せず落城すると「河野家譜」に記されているという。暦応4年(1341年)伊予宮方の土居通世が恵良城に籠って武家方の河野通盛と戦った。室町時代には得能氏の支族得居氏の居城となるが、天文年間(1532年~1555年)頃より来島村上氏の勢力が伸び、得居氏は村上通康の子通久を養子に向かえた。元亀3年(1572年)毛利氏の攻撃によって落城したが、豊臣秀吉による四国征伐の後も得居通久が三千石を領して居城した。しかし、関ヶ原合戦で来島氏は西軍に属して豊後国森へ転封となったため廃城となった。 鷺森城:水壕で囲む「浮城」・鷺森城は、応永元年(1394年)伊予国守護職河野氏の一族である桑原摂津守通興が築城した。壬生川の入江沼地を利用し、東と南に堀をめぐらし、北は入り江を切り開いて海水を導き、航路を兼ねた堀川を造る。大手口は西側に置き、壕に橋を架け(一ツ橋)、後方に大手門を造った。現在は、城跡の1/3が神社境内で、2/3が住宅地になっている。南西の国道沿いに「森岡さん」と呼ばれる小祠があり、城主の墓所であったと伝えられている。「鷺森城跡記念碑」「鷺森城跡校歌の碑」「松山藩年貢米倉庫跡碑」「壬生川村公会堂跡碑」などがある。 西条藩陣屋: 寛永十三年伊勢神戸城主一柳直盛は、郷国西条へ転封になったが、赴任の途次大阪で病没したため、長男直重が後を継ぎ西条に赴任し、西条陣屋を築造し城下町を開いた。直重の後を継いだ直興は、寛文五年改易となり一柳氏の治政は、三十年間で終った。そのあと、寛文十年紀州から徳川頼宣の次男松平頼純が就封され、その後十代二百年間松平頼英が明治二年版籍を奉還するまで、西条は城下町として繁栄した。現在陣屋跡は、西条高等学校となっているが、校門となっている大手門、門脇の堤、前濠の石崖、お矢来、濠等に昔の面影が偲ばれる。 川之江城:南北朝動乱の頃(約650年前)南朝方、河野氏の砦として土肥義昌が延元二年(1337)鷲尾山(城山)に川之江城を築いた。興国三年(1342)北朝方、細川頼春が讃岐より七千の兵を率いて攻めてきた。義昌は出城の畠山城主由良吉里と共に防戦したが破れ、城を落ちのびて各地を転戦した末、武蔵国矢口の渡で戦死している。細川氏の領有後、河野氏に返され城主は妻鳥友春になった。元亀三年(1572)阿波の三好長治が攻め入ったが、撃退している。こちらは川之江城模擬櫓門 土佐の長宗我部氏の四国平定の力に抗しきれなかった友春は、河野氏に背いて長宗我部氏に通じた。怒った河野氏は河上但馬守安勝氏に命じて城を攻めとらせた。天正七年(1579)前後のことと思われる。河上但馬守は轟城の大西備中守と戦い、打たれたという話も残っているが、天正十年(1582)長宗我部氏の再度の攻撃に破れ、戦死落城している。その時、姫ヶ嶽より年姫が飛び込んで自殺したという悲話伝説も残っている。天正十三年(1585)豊臣秀吉の四国平定に破れ、小早川、福島、池田、小川と目まぐるしく領主が替り、加藤嘉明の時最終的に廃城になった。数々の攻防は川之江が地理的に重要な位置にあった為の悲劇ともいえる。戦国の世も終った寛永十三年(1636)一柳直家が川之江藩28600石の領主になり城山に城を築こうとしたが寛永十九年(1642)病没。領地は没収されて幕領となり、明治に至ったため、わずか六年の「うたかたの川之江藩」で終った。 新谷藩陣屋:寛永十九年(1642)、新谷藩初代藩主となった加藤直泰は、大久保川を付け替えて、藩主や家臣の屋敷・町人住区等の区割りを行い、庭園からの水を防火用にするなど、陣屋の体制を整えた。新谷藩は、武術とともに学問を奨励し、中江藤樹の教えや和算の普及に勤め、廃藩置県(明治四年)まで続いた。この陣屋跡に、学制頒布(明治五年)によって、新谷小学校の前身である「令教小学校」が設立された。「令」の字は、九代藩主加藤泰令の徳をしたってその一字が付けられた。この藩から、和算学者別宮猶重、蘭医鎌田明澄、産業の発展に尽くした岡丈四郎(岡大明神)、儒学者児王輝山・宇都宮龍山、国学者平田(翠川)銕胤(かねたね)、明治維新に活躍した香渡晋(こうどすすむ)、宮脇通赫(みちてる)等を輩出し、学問を重んずる気風が藩の伝統となった。 16:00松山空港に向かう。 17:10松山空港到達 21日19:40松山空港出発 20:35伊丹空港到達 今回の旅行、四国の中心地愛媛県に足を運び比較的マイナーなお城7箇所(荏原城、港山城、恵良城、鷺森城、西条藩陣屋、川之江城、新谷藩陣屋)を訪れ楽しみました。 マイナーな城跡、見つけるのは 一苦労、学校とか市役所に城跡が位置することが多いが、これは平城で見つけやすい、山城はなかなか見つけにくい、案内板があれば容易ですがない場合が多いです。 苦労して巡った愛媛県お城巡り観光でした。 尚長浜港からフェリーで青島に行く予定でしたが悪天候のためフェリーが欠航、次回持ち越しとなりました。 |
        |
|||||||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第二百九十三弾:鳥取県お城・城下町巡り観光 2014年11月29-30日 鳥取県に足を運び、比較的マイナーで地味なお城・城下町18箇所(若桜城、景石城、山崎城、太閤ケ平砦、二上山城、桐山城、道竹城、天神山城、防己尾城、鹿野城、羽衣石城、打吹城、岩倉城、由良台城、船上山城、尾高城、米子城、江美城)を訪れました。 29日12:30車で出発、近畿中国自動車道経由して山崎インター下車しお城めぐる。 若桜城:若桜鬼ヶ城は応安二年(1369)矢部若狭守が築城したと言われています。その後矢部氏は矢部山城守まで十六代まで続きました。永録年間(1558-1569)に矢部兄弟が跡目争いをしている隙に、尼子勝久、山中鹿之介幸盛らが襲撃し、城を奪い取りました。これに対して吉川元春がさらに奪い取りましたが、天正六年(1578)には播磨から因幡に攻め入った羽柴秀吉が攻略し、荒木平太夫、木下備中守重賢に守らせました。同九年、鳥取城落城にあわせて重賢は八東、智頭二郡二万石の領主となりましたが、のちの関ヶ原の戦いに西軍に属したがために天王寺にて自刃しました。その後は山崎左馬允が二万五千石で入城しましたが、元和三年(1617)には移封され、一国一城令によって廃城となりました。 景石城:この城が何年頃築かれたかは明らかでないが、太平記に延文の頃(1360年頃)既にあったと記されている。その後、山名の城となったが天正八年(1580)豊臣秀吉の鳥取城攻略の重要な拠点として磯部兵部大輔にこの城を攻めさせ、山名勢を追い払い、磯部を城主として鳥取城への備えとした。ところが磯部が若桜鬼ヶ城に所用のため不在の折、鳥取山名に攻め落されたが、翌天正九年、秀吉再度の鳥取城攻略により、鳥取城は落城この際磯部は許されて再度景石城主となった。以来城下町として用瀬宿を発展させたが、関ヶ原の戦いに西軍に味方したため咎を受け、この城を去らなければならなかった。替って智頭八東二郡の領主となった山崎左馬介の持ち城となった。ところが元和元年(1615)一国一城の端城御禁制の令が出され、この城は廃城となった。今に昔を物語るものとして、下城・馬洗場などの地名が残っており又、本丸・二の丸・物見櫓などの広場と石垣又矢竹の群生が見られる。 山崎城:山城(242m/100m)天文年間(1532年~1555年)頃毛利氏によって築城された。毛利氏は大江広元の末裔とあるので安芸の毛利氏と同族と思われる。現在、殿町でダムを建設中のようだった。もしかしたら埋もれてしまうのか? 17:30鳥取駅前のホテル到着後繁華街を散策し食事を済ませて就寝。 30日7:00車で出発、お城をめぐる。 太閤ケ平砦:天正九年(1581)の羽柴秀吉の包囲作戦と吉川経家の籠城とによる対陣は、鳥取城の歴史の中で最大の攻防戦であった。この戦いは、天下統一をめざして中国地方を征討しようとする織田信長と、これを阻止しようとする中国地方の雄毛利氏との対立の中で展開されたものである。信長の派遣した部将羽柴秀吉は、姫路から但馬口を経て天正九年七月十二日鳥取に到着し鳥取城背後の東北の山頂(太閤ヶ平)のこの位置に本陣を置き、左右両翼と前面の袋川沿いに各陣を布いて、二万余の軍勢により兵糧を絶つ鳥取城包囲作戦を展開した。太閤ヶ平(本陣山)は、西方前方に鳥取城を望み、左方に芳心寺に至る一帯の山々をひかえ、右方にははるかに円護寺・覚寺・浜坂・賀露に至る一帯を見下し、総本陣としては最も適した場所であった。これを迎え撃つ鳥取城は、毛利氏の一族で石見国福光城主吉川経安の嫡男経家が城将として守備しており、その兵力は芸州毛利氏よりの加番衆四百と因幡国方衆千余であった。案内板にある太閤ヶ平の縄張り 毛利氏からの援軍・食糧の補給が阻止されて、包囲後三ヶ月過ぎるころには、「籠城兵糧つき、牛馬人等喰い候」という状況となった。ついに十月二十五日、吉川経家は城兵を助けるために開城し、自身は城中広間で切腹した。時に三十五歳であった。死の前日、十月二十四日に本家吉川広家にあてた遺言状に、「日本二つの御弓矢境において忰腹に及び候事、末代の名誉たるべく存じ候」と、経家は記している。織田信長と毛利氏という「日本二つの御弓矢」の正面対決による鳥取城攻防戦での切腹を、大きな名誉と感じていたのである。この太閤ヶ平には、当時の鳥取城攻防の歴史を物語るかのように、土塁と空濠を廻らした曲輪の跡が厳然として残されている。また、この一帯は鳥取自然休養林であり、摩尼寺に至る中国自然歩道も整備され、広く市民の憩いの場として親しまれている。 二上山城:ニ上山城の位置するニ上山は標高三四六・六メートル、所々に位置する巨岩と、標高ニ〇〇メートル前後からの急勾配をもつ、きわめて険阻な山です。城は山頂部の一の平帯曲輪を中心とし、北東方向へ向かってニの平、そして大小八ヵ所の削平地からなる三の曲輪と続く主要部からなっています。このほぼ一直線にならんだ城の状況を見ると、ニ上山城は北側からの寄せ手を意識して築城されていたようです。東西両斜面はかなり険しく、この方面からの攻撃は不可能と思われます。一方で、他の斜面に比べゆるやかな南側の尾根づたいのルートは非常時の逃げ道となっていたようで、こちらからの攻撃は少ないものと考えられていた様子がうかがわれます。 桐山城:桐山城跡は標高203メートルの日本海を一望できる桐山頂上に有り、郭が頂上と南東尾根に四カ所、東の谷に七ヶ所残っています。古くから浦富には因但国境海上交通の要所の港町でした。築城年代は不明ですが、塩冶周防守が桐山の攻め難く守り易く、かつ眺望の良い地形と、田後・岩本・網代の三村にも尾根が続く独立した山であるため、ここに城を築いたと伝えられています。そして、元亀三年(1572)尼子の勇者、山中 鹿之介が入城。その後は垣屋光成(一万石、子の恒総まで二十年間)、池田政虎(五千石、十五年間)さらに、鵜殿氏(五千石)が幕末まで浦富を領しました。この頂上までの散策道は地権者の方々のご厚意により出来ています。気象条件が良ければ遠く大山や隠岐ノ島が見えます。 道竹城:『因幡誌』によれば、文正元年(1466)因幡国守護である山名勝豊は、巨濃郡岩常の二上山城から高草郡布施にある天神山城へ移り住んだ。そのため山下の治安が乱れたために、天文の頃に地元の要請があり、但馬山名家から三上兵庫が迎えられ、二上山城へ入った。しかし二上山城は高い山の上にあり、不便であったため新井村に新しく道竹城が築かれたのであった。永禄の世になると、次第に尼子の勢力が衰え、毛利の勢力が因幡に及ぶようになると、三上兵庫(山名豊弘)は武田高信や毛利氏と結ぶようになった。しかし永禄七年、因幡守護山名豊数の軍勢に攻められた三上兵庫はあえなく討死、道竹城は以後廃城となってしまった。 天神山城:この小山は、天神山と呼ばれ、室町時代の因幡守護山名氏の居城、天神山城があった。江戸時代の地誌「因幡志」には、文正元年(1466)山名勝豊によって築城されたと書かれている。築城の経緯は不明な点もあるが、天神山城は、山名豊国が天正元年(1573)鳥取城に本拠を移すまで、十五世紀後半から約100年間にわたって、因幡国支配の政治的拠点であった。天神山城は、かつて内堀・外堀を備えており、内堀は天神山を囲んで南北400メートル、東西300メートルの長方形に掘られていた。外堀は布施卯山をも取り込み、湖山池に通じる総延長2.6キロメートルに及ぶものであった。外堀の内側には城下町が形成されていたと考えられ、壮大な規模を誇る城郭であった。発掘調査で土器・中国製の陶磁器・備前焼・古銭・下駄・曲物(まげもの)などが見つかっており、現在も井戸・櫓跡や濠の跡などが残っており、往時をしのばせている。 防己尾城:吉岡将監定勝が築城したといわれる。城跡は本丸・二の丸・三の丸とそれに取り囲まれた町屋とから構成されており、北側には船着場が設けられていた。天正九年(1581)羽柴(豊臣)秀吉鳥取城攻略の時、将監は奇襲によって、たびたび秀吉勢を悩ませた。また、将監の弟右近は秀吉の千生瓢箪の馬印を奪い取ったという。しかし、この城はその後亀井茲矩により落城した。 鹿野城:鹿野城主亀井武蔵守茲矩は1557年に出雲国(島根県玉湯町)に生まれた。茲矩は山中鹿介らと結託し、尼子氏再興を目指し山陰各地で毛利氏と戦う。後に豊臣秀吉の鳥取城攻めに参加し、その功によって鹿野城主となる。茲矩は大変豪壮な武将で、秀吉が「もはや出雲をやることはできなくなった。他に欲しい所はないか。」と尋ねたのに対し、「琉球を下さい」と言い、その大胆な発想を褒め讃えて「亀井琉球守」と軍扇に書いて与えたという。また茲矩は狭い日本には飽き足らず、朱印船貿易により大きな利益を得て、領内の開発を行った。同時期に、茲矩は秀吉の海外大陸進出計画の朝鮮遠征に加えられた。秀吉の朝鮮遠征は順調に成果を上げていった。しかし朝鮮救国の全羅左道水使・李舜臣が亀甲船を率いて戦陣に加わると情勢が一変した。李舜臣は朝鮮半島の唐浦に茲矩の軍が駐泊しているところに奇襲攻撃をかけ、その攻撃を受けた茲矩の水軍は全艦焼失し全員陸へ逃れた。この時、茲矩は秀吉から貰い受けた軍扇を失った。その軍扇は朝鮮救国の虞侯・李夢亀が拾ったと言われている。茲矩はその後、陸上に逃れて各地を転戦する。その道中に虎を生け捕りにし、秀吉にその虎を献上して大変な評判となった。また、茲矩は鹿野城の改築にあたり、朝鮮櫓、オランダ櫓を城内に建立し、懐かしの地の風物を偲んだ。この戦を日本では文禄・慶長の役と呼び、朝鮮半島では倭乱と呼んでいる。1578年羽柴秀吉が亀井茲矩等を先駆として、毛利氏の支城となっていた鹿野城を攻めおとし、羽柴軍山陰攻めの前線基地の役割を持ちました。亀井茲矩は鹿野城の城番を命ぜられ、翌年の秀吉の再出陣までの間、鹿野城を守るのみでなく、近くの諸城を攻め落し、これらの功により城主に任命されました。関ヶ原の戦いの後、世の中がおちつくと、茲矩は城の大拡張を行いました。古い鹿野城は山頂に近い部分だけの山城でしたが、山麓を中心に本丸・周囲に薬研堀、内堀、その外側に外堀をつくり近世の城として面目を一新しました。その一方でまえからの山城を整備しました。城は、仏教思想にもとづく「王舎城」の名が、また、櫓には南蛮貿易を物語る「朝鮮櫓」「オランダ櫓」の名が残っている。 羽衣石城:羽衣石城は東伯耆の国人、南条氏の居城として貞治五年(1366)から慶長五年(1600)まで約二三四年間使用された城であるが、城主の南条氏をはじめ羽衣石に関する記録は「羽衣石南條記」などの少数のものしか伝えられていない。また、これらの諸本の成立年代は南条氏が滅んだ後、百数十年たった江戸時代の中頃のものであり、どこまで事実を伝えているかは疑問であるが南条氏を知る一つの手がかりである。さて、これらの諸本によると南条氏の始祖は南条伯耆守貞宗とし、この貞宗は塩治高貞の二男で高貞が滅亡した時越前国南条郡に逃れた。貞宗は成長後、将軍足利尊氏、義詮の父子に仕えて功績をあげ義詮より伯耆守に任ぜられて貞治五年(1366)に羽衣石城を築いたという。この南条氏の活動が盛んになるのは応仁の乱以後である。明徳の乱(1291)応仁の乱(1467~1477)の為に伯耆国守護山名氏の権力が衰退するに乗じて南条氏は在地支配の拡大を目指して独立領主化をはかり、第八代南条宗勝の時には守護山名澄之の権力をうわまわる武力を保持するに至った。大永四年(1524)隣国出雲の尼子経久は伯耆国へ本格的な侵攻を行い、西伯耆の尾高城、天満城、不動ヶ城、淀江城並びに東伯耆の八城城、堤城、岩倉城、河口城、打吹城の諸城を次々に攻略し同年、五月中頃までにはこれらの諸城は降伏してしまった。南条氏の羽衣石城も落城し、城主の南条宗勝は因幡へ逃亡した。これを「大永の五月崩れ」といい、この乱後、伯耆国は尼子氏の支配するところとなり、羽衣石城には尼子経久の子国久が入城した。しかし尼子氏の伯耆支配も長く続かず、毛利氏の台頭とともに永録年間(1558~1569)には支配権を失った。南条宗勝は永録五年(1562)に毛利氏の援助により羽衣石城を回復している。以後伯耆国は毛利氏の支配下に入り、南条氏はこのもとで東伯耆三郡を支配した。 天正七年(1579)織田氏の山陰進出が本格的になると南条元続は毛利氏を離反して織田氏についた。毛利氏は羽衣石城を攻撃し、元続は因幡に進出していた羽柴秀吉の援助などによりこれに対処したが天正十年(1582)羽柴秀吉の撤兵とともにら落城し、城主元続は京都に逃走した。 天正十三年(1585)秀吉と毛利氏との間で領土の確定が行われ、東伯耆八橋城を残して秀吉が支配するところとなり、再び南条氏に与えられた。しかし慶長五年(1600)に起こった関ヶ原の役で西軍に属した南条元忠は役後改易され羽衣石城は廃城となった。 打吹城:打吹城は、延文年間(1356~61)に山名師義が田内城より移ってきた際に築城されたとされる。その後応仁の乱(1467~1477)を迎えると次第に山名氏の勢いは衰え、代わりに羽衣石城の南条氏、尾高城の行待氏が勢力をの伸ばしていった。大永四年(1524)に、出雲の尼子経久が伯耆国に侵入、山名氏の諸城を攻略していった。この打吹城も周辺の城と同様に陥落した。世にいう「大永の五月崩れ」であった。その後毛利氏の援助によって城を奪還できたものの、それは同時に毛利氏の配下となることであった。天正八年(1580)に吉川元春が打吹城に入ったが、秀吉による鳥取城攻めの後に和睦が成立すると打吹城は羽衣石城の支配下となった。慶長五年(1600)の関ヶ原の合戦ののちには中村一忠が伯耆国に入ると打吹城には入番が置かれるようになった。しかし同十四年には一忠の病死によって幕府の直轄領となる。さらに一国一城令によって伯耆国は米子城を残して他の城は破却されることとなったため、当城は廃城となった。 岩倉城:小鴨氏は、律令時代-奈良・平安時代-すでに名があり、伯耆国庁につとめた在庁官人の家柄と考えられている。平安時代の末期に、寿永元年(282)小鴨基保が西伯耆の豪族紀成盛と戦った記録がある。鎌倉時代に、小鴨氏は岩倉山(海抜247メートル)の山上に砦を築き、ここを代々の居城とした。元弘三年(1333)後醍醐天皇が船上山に潜幸の際、名和氏の軍勢により小鴨城が攻略されたという記事もあるが、よくわからない。応仁の乱(1467~1477)には、伯耆守護山名教之に従い、小鴨安芸守之基は主人に変わって防戦し、船岡山の戦いで討死した。大永四年(1524)五月、尼子経久が出雲より伯耆へ侵攻し、伯耆のすべての城が陥落し、小鴨氏の岩倉城も落城の浮目にあった。二の丸下の石垣 永禄四年(1561)西国より起こった毛利氏が強くなり、羽衣石城の南条氏と共に毛利氏に加担して尼子氏に反攻。永禄九年(1566)尼子氏は毛利氏に降伏し、小鴨氏は南条氏と共に吉川元春の配下となった。元亀元年(1570)、山中鹿之助の配下に一時奪われたが、因幡の湯原氏の応援を得て奪還した。天正七年(1579)小鴨元満は南条元続と共に毛利氏から離れ、織田氏に帰属するようになった。毛利氏は吉川元長を長として、圧倒的な軍勢ともって、岩倉城に猛烈な攻撃をしかけて来た。天正十年(1582)五月のことである。忠勇十二勇士の誓願盟約による奮戦も空しく、遂に落城した。城主小鴨元清は南条氏を頼って羽衣石に逃れ、ここに岩倉城の歴史は幕を閉じた。 由良台城:江戸時代末期、外国船がしきりに日本の近海に出没し沿岸をおかした。幕府は各藩に命じていっそう海防を厳重にするよう通達した。鳥取藩主池田慶徳は海防上砲台場築造の必要を認めその建設を砲術家武宮丹治に命じた。丹治は文久三年(1863)瀬戸村の武信佐五衛門の宅に来て相談、六尾反射炉をつくった武信潤太郎の建議をもとに由良川の河口に建設することにした。潤太郎はフランス式の築城法をもとに自ら設計し由良藩倉二十一ヶ部落の農民を集め指導監督して建設した。土塁の基礎は東隣の畑の砂を積み上げてつくり、土はかじ山(自動車運転免許試験場)と清水山(元大栄中グランド北隅)より、芝は干目野(県園芸試験場)から運んだといわれる。西側から見た由良台場 由良台場、南側土塁です。 由良お台場は六角形で、東西125メートル、南北83メートル、周囲約400メートル、面積約11913平方メートルである。大砲は七門配置され、この守備には農兵があたり、郷土の護りを固めた。数年後明治維新となり、大砲は廃棄改鋳され、台場は大正十四年八月、由良町(現大栄町)に払い下げられ今日に至っている。この台場はその規模が大きく形の整っていること、原型を完全にとどめている点などから、県内はもちろん全国的にも貴重な存在であり、永久に保存すべきものとして各方面から注目されている。 船上山城:鳥取県東伯郡琴浦町にあった山城(やまじろ)。南北朝時代初期に後醍醐天皇が行在し、寺院を城郭化した城。1333年(元弘3)閏(うるう)2月から5月下旬までの約80日間、天皇が京へ還御するまで行在した、いわゆる船上山行宮跡(せんじょうさんあんぐうあと)である。船上山は標高616m、断崖絶壁の要害で、古くから大山、三徳山と並ぶ山岳仏教の聖地であった。鎌倉幕府によって隠岐に配流されていた後醍醐天皇は、1333年(元弘3)隠岐を脱出して伯耆(現鳥取県)に入り、豪族名和長年(なわながとし)らに守られて船上山山頂の寺院にたてこもった。鎌倉幕府方の佐々木清高らの軍との間で激しい戦いが繰り広げられたが、天皇方が勝利し、これによって反鎌倉幕府勢力を決起させ、鎌倉幕府はほどなく崩壊した。山頂一帯は行宮跡として、また古戦場として、国の史跡に指定されている。 尾高城:米子勤労総合福祉センター(現在米子ハイツ)は、尾高城跡を中心とした約9万平方メートルの敷地内に建設されています。この尾高城は室町、戦国時代には行松氏累代の居城でしたが、1524年(大永4年)尼子方武将吉田光輪が変わって城主となり、その後伯耆因幡制覇をめざす毛利の勇将杉原播磨守盛重が備後から転城し伯耆守護の要害とされました。尼子方の武将で「我に七難八苦を与えたまえ」と三日月に祈った山中鹿之介幸盛は、幾度の戦後、この城の虜因となり、数十度の厠通いで城兵の油断を誘い、汲取口から脱出したとの史実があります。関ヶ原の戦いの後、伯耆十八万石の領主となって入府した中村一忠は、現米子市城山の久米城が完成するまで尾高に在城しました。また、土塁と堀に囲まれ、方形館跡と、北から二の丸、本丸、中の丸、天神丸と続くこの城跡は、中世の城の威容が忍ばれます。現在、城跡は米子市の文化財に指定されています。米子ハイツは、背後に大山を控え、前面には日本海が迫った風光明媚な尾高の地に、城跡の地形を十分に生かして梅園、桜の園、あじさい園、武家屋敷跡基礎復元、日本庭園、自由広場等を整備し四季とりどりの草花木を植え、自然に親しむ憩いの場として、また体育館、テニスコート、ゲートボール場などの体育施設も設け、勤労者の総合的な福祉の向上に寄与することを目的として昭和51年6月建設開業されたものです。ここは、中世の東西交通路をおさえる西伯耆の軍事上の中心地であった。城郭は、鎌倉時代から築かれたようであり、室町時代山名氏支配下では城主は行松氏が、尼子氏が進出すると城主は吉田氏が、16世紀後半になって毛利氏支配下時代には杉原盛重が城主であった。江戸時代初期、米子城築城によってこの城は廃城となった。城跡は、北から二の丸、本丸、中の丸、天神丸、後方の館跡など八つの郭があって掘りや土塁で守られ、平常の生活を営む館と城とがつながっている中世の城郭遺跡である。尼子回復戦のおり、尼子の勇将山中鹿之介が捕らわれ、この城にいたとき、腰痛といつわって汲取り口から脱出したという物語は有名である。行松正盛の居城であったが大永四年(1524)尼子経久に一旦は攻め落とされるが、その後毛利氏の援助で奪回する。その後杉原盛重が城をまかされたが、天正十一年(1583)、後を継いだ元盛は、弟景盛との抗争で殺害され、景盛も直後に自刃させられてしまう。その後は吉川元春が入り、西伯耆地方の要衝を守るようになった。 米子城:米子城のおこりは十五世紀の後半であろうとされているが、それは国道9号線の左の飯山につくられた砦であった。国道右手の湊山を中心とする米子城は16世紀末頃に、出雲東部と伯耆西部を領した吉川広家によってまず四重の天守を中心に城地の築構が始まった。関ヶ原役後、吉川氏は周防岩国に転封され、米子には静岡から中村一忠が伯耆18万石の領主として入部した。中村一忠は四重天守の横に五重天守を建て、城地の縄張りを完成した。約90メートルの湊山山頂の二つの天守を中心に米子城は本丸、二の丸(城主邸宅、武器庫などのある一郭)内膳丸(出丸)、三の丸、采女丸(飯山)などに区画し、周囲と西は海面、他の三面は延約1100メートルの内堀で囲んだ。四重天守は高さ約17メートル、五重天守は約20メートルであった。三の丸には厩舎、作事小屋、米蔵、役人詰所などがあり、城の裏手海岸は深浦と称して船手小屋などをもつ曲輪になっていた。城郭内の総面積は30ヘクタール余、櫓の数20余、内堀を超えて外堀との間は郭内といわれ侍屋敷の並ぶ区域であった。城郭は幕末まで数回の修理で維持したが、明治12年頃天守は売却されて壊された。城主は中村一忠の後、加藤貞泰、池田由之と変わり、寛永9年(1632)池田光仲が因幡・伯耆の領主に封ぜられると家老荒尾成利が米子城を預かり、以後荒尾氏の自分手政治が明治維新まで十一代続いた。 江美城:江美城跡は、だいせん火砕流台地を造成して、築かれた中世の山城で文明年間(15世紀後半)に蜂塚安房守によって築城され、二代・三河守、三代・丹波守、四代・右衛門尉と四代にわたってこの地を治めました。永禄七年(1564)八月六日、尼子氏を攻略する為に山陰へ侵攻してきた毛利氏により江美城は攻略され、蜂塚氏は滅亡しました。その後、美後・備中・美作方面に対する戦略的見地から、毛利氏により、蜂塚時代の中世的城郭から近世城郭へと大幅な改造がなされています。1997年12月の発掘調査により、多数の瓦片に混じって金箔装飾のある鯱瓦が発見されました。このことから安土桃山時代の後期、江美城には金箔装飾を施した鯱瓦を載せた立派な櫓があったことがわかりました。 今回の旅行、鳥取県に足を運び、比較的マイナーで地味なお城・城下町18箇所(若桜城、景石城、山崎城、太閤ケ平砦、二上山城、桐山城、道竹城、天神山城、防己尾城、鹿野城、羽衣石城、打吹城、岩倉城、由良台城、船上山城、尾高城、米子城、江美城)を訪れ、楽しめました。 |
                     |
|||||||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第二百九十弾:東海・関東・甲信越圏お城・城下町巡り観光 2014年11月1-3日 東海・関東・甲信越圏の広い範囲に足を運び、点在するお城・城下町13か所(長篠城、岩村城、高遠城、武田氏館、山中城、八王子城、水戸城、足利氏城、金山城、鉢形城、箕輪城、小諸城、春日山城)を訪れました。 1日12:30車で出発、第二京阪、京滋バイバス、名神、新名神、東名自動車道を経由して愛知県東部方面に向かう。 長篠城:三河設楽郡長篠(愛知県新城市長篠)にあった城(平城)。現在は国の史跡に指定され、城跡として整備されている。1575年(天正3年)5月の長篠の戦いに先立つ長篠城をめぐる激しい攻防戦で知られる。 岐阜県恵那方面に向かう。 岩村城:岐阜県恵那市岩村町にある中世の山城跡で、江戸時代には岩村藩の藩庁であった。 付近は霧が多く発生するため、別名・霧ヶ城とも呼ばれる。「女城主」悲哀の物語が残る。 長野県伊那方面に向かう。 17:05伊那駅前のホテル到着後周辺を散策し食事を済ませて就寝。 高遠城:長野県伊那市高遠町にある城。兜山城の別名をもつ。桜の名所としても有名である。国の史跡に指定されている。 2日7:00車で出発、山梨方面に向かう。 武田氏館:甲斐国守護武田氏の本拠である甲府に築かれた館で、守護所が所在した。現在、跡地には武田神社があり、また、「武田氏館跡」として国の史跡に指定されており、県内では甲州市(旧勝沼町)の勝沼氏館と並んで資料価値の高い中世の城館跡である 静岡県三島方面に向かう。 山中城:北条氏によって築城され、小田原城の支城として位置づけられる。箱根十城のひとつ。三島市によって当時を反映した整備改修がなされ、堀や土塁などの遺構は風化を避けるため、盛土による被履の上芝を張って保護し、畝堀や障子堀の構造が明確に把握できるように整備されており北条氏の築城方法を良く知ることのできる城跡となっている。 八王子方面に向かう。 八王子城:北条氏の本城、小田原城の支城であり、関東の西に位置する軍事上の拠点であった。延喜13年(913年)に華厳菩薩妙行が山頂で修行中に牛頭天王と8人の王子が現れた因縁で延喜16年(916年)、この城の山頂に八王子権現を祀ったことから、八王子城と名付けられた。 水戸方面に向かう。 水戸城:現在の茨城県水戸市三の丸にあった城である。徳川御三家の一つ「水戸徳川家」の居城である。茨城県指定史跡。三の丸にある藩校・弘道館は国指定特別史跡。 栃木県足利方面に向かう。 16:20足利駅付近のホテル到着後周辺を散策し食事を済ませて就寝。 3日7:00車で出発。 足利氏館:鑁阿寺(ばんなじ)は、栃木県足利市家富町にある真言宗大日派の本山である。「足利氏宅跡(鑁阿寺)」(あしかがしたくあと(ばんなじ))として国の史跡に指定されている。 金山城:群馬県太田市のほぼ中央にそびえる標高235.8メートルの独立峰、全山アカマツに覆われた金山に築かれた山城である。別名「太田金山城」、「金山城」。 埼玉県秩父方面に向かう。 鉢形城:埼玉県大里郡寄居町大字鉢形にある戦国時代の平山城跡で、東国における戦国時代の代表的な城跡のひとつである。 高崎方面に向かう。 箕輪城:榛名白川によって削られた河岸段丘に梯郭式に曲輪が配された平山城である。城の西には榛名白川、南には榛名沼があり、両者が天然の堀を形成していた。城地は東西約500メートル、南北約1,100メートル、面積約47ヘクタールにおよぶ広大なものであった。現在にのこる遺構として、石垣・土塁・空堀の跡が認められる。 長野方面に向かう。 小諸城:長野県小諸市にある城跡。別名、酔月城、穴城、白鶴城。 上越方面に向かう。 春日山城:現在の新潟県上越市にあった中世の山城。主に長尾氏の居城で、戦国武将上杉謙信の城として知られる。春日山城跡は国の史跡に指定されている。 14:40帰路に向かう。 今回の旅行、東海・関東・甲信越圏の広い範囲に点在するお城・城下町13か所を巡り楽しみ堪能しました。 山城から平山城、平城と種々のタイプのお城を巡りスケールの大きな建造物を再確認できました。 今回で日本の100名城をすべて訪れる事ができました。 |
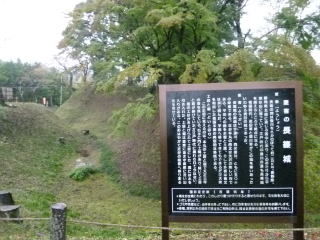           |
|||||||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第二百八十七弾:福井県お城・城下町巡り観光 2014年10月11136日 中部地方西部に位置する県。本州の屈曲部に位置し、日本海に面する。北は石川県、東は岐阜県、南西は滋賀県・京都府に隣接する。西部はリアス式海岸の若狭湾で観光・漁業地域。原子力発電所が多い。古くから北陸道の入り口にあたる要衝の地で、現在も京阪神地方・中京地方との結びつきが強い福井県に足を運び、比較的マイナーなお城・城下町16か所を訪れました。 11日12:30車で出発、第二京阪京滋名神北陸自動車道経由して小浜インター下車 15:00小浜到達 小浜城:年(1601)京極高次が着工し、その忠高にいたる33年間に城の大半を造り、寛永十一(1634)酒井忠勝が藩主となり、寛永十五年三層の天守閣を築いた。城域は東西156間(284メートル)、南北145間(264メートル)総地坪数18,937坪(62,492メートル)外濠を除く。 本丸 3,3130坪(10,329メートル)内堀3,755坪(12,391メートル)二の丸 藩主の家族の住宅屋敷 2、249坪(7,422メートル)三の丸 軍用食糧、兵器の倉庫 3,806坪(12,560メートル)北の丸 2,584坪(8,527メートル)西の丸 3,413坪(11,263メートル)在りし日の小浜城 特色は、海と河川とを取合せた要害の海岸城で、平地城としては慶長初期であり古く、石垣の慶長積みは特色である。京極氏の後は寛永十一年から明治四年(1871)まで、酒井氏十五代260年間の居城であった。明治四年十二月この城に大阪鎮台第一分営を設置すべく改造工事中二の丸櫓の工事場から失火し、城の大部分を焼失した。現況は左図のように河川拡張のため旧城地がけずられて縮小され往昔の面影がない。 後瀬山城:後瀬山城は大永二年(1522)戦国争乱の防備として若狭守護武田大膳大夫元光が築城した中世の山城である。城郭は海抜168メートルの山頂に主郭を配置しそれより北側八幡神社の裏山まで400メートルの間に16段の小郭を階段状につくっている。主郭の西南枝峰にも同じく小郭が18段あって、その山麓に武田氏館があった。現在の小浜小学校、空印寺がその跡地。さらに主郭の西側には巾広い空堀を隔てて西郭がある。ここは城の御殿と推定され築山など庭園らしい跡も残されている。城は戦国時代各地につくられたものと大差はないが、西側には斜面にそって四本の竪堀がつくられており、ゆるやかな斜面の守りを固めている。東側は急斜面のため部分的に竪堀をつくるが集中されていない。そのかわり元光は発心寺を造営し北東の城砦的役割を持たせたと思われる。石垣もよく残っています。 城主は元光、信豊、義統、元明と四代続いたが、永禄十一年(1568)越前守護、朝倉義景が、この城を攻め元明は敗れ、越前へ連れ去られた。天正元年(1573)朝倉氏滅亡後、丹羽長秀が国主としてこの城に入り、石垣を積むなどして補修した。現在の石垣はそのときのものである。そののち、浅野長吉、木下勝俊などと豊臣秀吉の家臣が若狭国主としてこの城を利用したが、慶長五年(1600)関ヶ原の攻で京極高次が国主となり、翌六年より小浜城を築城。後瀬山城は廃城となった。 美浜方面に向かう。 国吉城:美浜町指定史跡国吉城址は、若狭国守護大名武田氏の重臣であった粟屋越中勝久によって弘治二年(1556)に築かれた中世の山城である。通称”城山”の最高所(標高197.3メートル)を本丸とし、北西に延びる尾根上には段々の削平地(曲輪)が連続し、その先端に丹後街道が通る椿峠があった。尾根の斜面は切り立って急であり、守り易く攻め難い城であった。実際に、永禄六年(1563)から数年におよぶ勝久と越前朝倉氏との戦いにおいては、城を守り通して名声を内外に轟かせ、その活躍は『若州三潟郡国吉籠城記』などの軍記物にまとめられた。元亀元年(1570)越前攻めのために木下藤吉郎(後の豊臣秀吉)や徳川家康らを伴って国吉城に入城した織田信長は、城を守った勝久を褒め称えたと伝わる。その後、天正十一年(1583)に入城した木村常陸之介定光は、椿峠を越えた丹後街道が集落の中を通るように道筋を付け替えて町割りを行い、佐柿の町を興した。江戸時代に入ると国吉城は廃され、寛永十一年(1634)に若狭国の領主となった酒井忠勝は、町奉行所と藩主休息所として御茶屋屋敷を置いた。以降、佐柿は三方郡の中心、丹後街道の宿場町として繁栄し、現在も当時の景観を色濃く残した古い町家や寺社が現存している。 敦賀に向かう。 敦賀城: 天正十一年(1583)、蜂屋頼隆が五万石の敦賀領主となり、旧笙ノ川河口の左岸に敦賀で初めての平城を築いたが、同十七年に頼隆が病死すると、領主は豊臣秀吉配下の大谷吉継と交代した。吉継はこの城を整備拡充するとともに町も整えていった。三層の天守閣をもつこの城は現在の結城町と三島町一丁目にまたがるものであった。慶長五年(1600)年、関ヶ原の合戦で西軍に属した吉継は敗れて自刃した。元和元年(1615)の一国一城令によって城は破却された。寛永元年(1624)、小浜城主の京極忠高が敦賀郡を加増され、同十一年には酒井忠勝が小浜藩主となり敦賀の支配にあたった。そのため旧敦賀城の中心部に藩主の宿泊休憩所となるお茶屋(陣屋)町の支配や警察・裁判を行う南北の町奉行所、農村から年貢を取り立てる南北の代官所を設け、目付一名、町奉行二名、代官二名が常駐し、配下の足軽や同心とともにその任務にあたった。 明治四年(1871)、廃藩置県によって、若狭一国と当時の敦賀・南条・今立三郡を県域とする敦賀県が誕生し、その県庁を旧陣屋に置いた。同六年に足羽県を統合すると庁舎が手狭となり、庁舎を旧奉行所跡に新築移転した。同九年八月に敦賀県が廃止されて滋賀県と石川県とに分割されると、敦賀は滋賀県に属した。同十四年に旧敦賀県を管轄地域とする福井県が誕生するが、県庁が敦賀に戻ることはなかった。その後この地には警察署・裁判所・敦賀病院などがかわるがわる建てられ、結局明治四十二年に敦賀尋常高等小学校が神楽町から新築移転して現在の敦賀西小学校に引き継がれ、今に至っている。 金ヶ崎城:金ヶ崎城は「太平記」に「かの城の有様、三方は海によって岸高く、巌なめらかなり」とあり、この城が天然の要害の地であったことがわかる。南北朝時代の延元元年(1336)十月、後醍醐天皇の命を受けた新田義貞が尊良親王・恒良親王を奉じて当時気比氏冶の居城であったここ金ヶ崎城に入城。約半年間足利勢と戦い翌二年三月六日遂に落城、尊良親王、新田義顕(義貞嫡子)以下将士300余名が亡くなったと伝えられる。戦国時代の元亀元年(1570)四月には、織田信長が朝倉義景討伐の軍を起こして徳川家康、木下藤吉郎(豊臣秀吉)等が敦賀に進軍、天筒城、金ヶ崎城を落とし越前に攻め入ろうとした時、近江浅井氏が朝倉氏に味方するとの報告、信長は朝倉氏と浅井氏との間に挟まれ窮地に陥り急遽総退却、この時金ヶ崎城に残り殿を務めてこの難関を救ったのが秀吉で、その活躍で無事帰京できたと伝えられる。またこの殿での危機を救ったのは家康で、後の天正十四年(1586)家康上洛にあたり、秀吉は金ヶ崎城での戦いの救援に謝意を表したとされている。すでに十五、六年前のことで、天下人に一歩近づいた秀吉からすると、金ヶ崎の戦いはその後の二人の関係に大きな影響を与えたといえる。焼米が出土した郭。激戦の跡が伺えます 現在は三つの城戸跡などを残し、急峻な斜面は当時の面影を偲ばせる。また、最高地(標高86メートル)を月見御殿といい、近くには金ヶ崎古城跡の碑があり、この辺り一帯の平地が本丸の跡といわれる。ここからの眺めは素晴らしく天候がよければ越前海岸まで望むことができる 17:30敦賀駅前のホテル到着後繁華街を散策し食事を済ませて就寝。 12日7:30車で出発、 玄蕃尾城:滋賀県と福井県の県境内中尾山の山頂に築かれた玄蕃尾城は、天正11年(1583)に柴田勝家と羽柴秀吉が、信長亡き後の織田軍団の指導権を争って戦った賤ヶ岳の戦いの際に柴田勝家が本陣を構えた所です。曲輪は全部で8つあり、山頂に主曲輪を構え、各曲輪をなだらかな斜面に配しています。 曲輪周囲には空堀を巡らし、曲輪と曲輪の間は土橋で連絡されて、曲輪から空堀を見下ろすと、一見山中城(静岡県)の畝堀を思わせます。主曲輪(約40m×40m)の南北に設けられた虎口には、枡形虎口、あるいは馬出しなどを配して、織豊系城郭技術がこの時期にほぼ完成されていたことを窺い知ることが出来ます。遺構もほぼ完全な形で残っており、滋賀県あるいは福井県に数ある城郭の中でも屈指のものだと思います。また、主曲輪の東側には櫓台(10m×10m)が設けられており天守のようなものが築かれていたと考えられています。この玄蕃尾城の築城時期は天正10年~11年と特定することが出来、天正期における織豊系城郭の築城技術を考察する上でも非常に意義深い城といえます。 今庄方面に向かう。 杣山城:一帯に築かれた中世の山城。北の比叡山とも呼ばれ、鎌倉末期には瓜生一族の居城となり、その後延元元年(1336)から三年間新田義貞が籠城した南軍の拠点。北朝方との葉原の合戦で破れると、落城した。戦国時代には朝倉氏の家臣・河合宗清が城主になったものの、織田信長の朝倉・浅井討伐の際に落城し、廃城に帰したと思われる。その後、織田氏に抵抗する一向一揆勢が天正二年(1576)にここに籠もったとされる(『現地説明板』『日本の名城・古城事典』等)が、明確な記録は残っておらず、本格的な城郭としての機能は失っていたと思われる。西御殿、東御殿と伝わる平場や、姫穴、袿掛岩などの伝説の地形に、堀切、水場などの遺構も山全体に散在しているが、いずれも城郭の縄張としては極めて簡素である。少なくとも戦国時代に大規模な改修が為されたとは考えられない。 武生方面に向かう。 府中城:藩政時代府中邑主本多氏の館址である。往時の邸地は約八千坪で東邊と北邊を堀で囲みその東一帯に長さ二百八十余間の外堀があり館は南面し、大手門が馬場に通じていた。城の起源は文明の頃越前国守護朝倉氏の府中奉行所の構築に創まると云われ天正年間前田利家が城濠を修築拡張した。前田氏移封の後に丹羽・木村・堀尾の諸氏が相次いで在城したが慶長六年本多富正が居館を定めてから維新廃藩に至るまで本多氏が歴代在城した。明治五年城址に進脩小学校が建てられ後に武生東小学校と改称した。輓近市街の発達と学量増加のため中北府町へ移転すると共に市庁舎が建設された。創学以来十四年である。 小丸城:天正三年(1575)に越前一向一揆を平定した織田信長は、越前の抑えとして柴田勝家を置いた。勝家は北ノ庄に築城すると、その補佐役として付けられていた府中三人衆もそれぞれ前田利家が府中城に、不破光治が竜門寺城に、そして佐々成政は小丸城を築城して居城とした。小丸城の石垣には野々宮廃寺の礎石と見られるものが転用されていることが知られているが本丸周辺が工事により破壊されたこともあり詳しくは不明である。また成政が同七年に越中砥山城に転封となったため、わずか4年での廃城となった。そのことから小丸城は未完成な状態であった可能性も考えられている。現在残る城の遺構から考えられる城の規模は、味真野の扇状台地末端に本丸、二の丸、三の丸と環郭式の構造を持つ。高さ約7メートル、50メートル四方の本丸を中心に、基底幅20メートルほどの土塁、幅20メートルの堀などが見られる。また北西の乾櫓からは成政が一揆を成敗した際の様子を刻んだと言われる文字瓦も出土している。 東郷槇山城:東郷槇山城は一乗谷城の北西約3km、足羽川の左岸にあって三峰城,成願寺城,中山城と共に、一乗谷城の支城の一つである。一乗谷の西峰の御茸山とは尾根続きで、下城戸のちょうど真西に位置しており一乗谷の出城的な役割を担っていたと考えられる。東郷槇山城は通称城山と称する槇山に築城されており、槇山の西側から車で二の丸まで登ることができる。城台と称される主曲輪と南に位置する二の丸、および千畳敷は公園として整備され手軽に中世山城を見学することができるが、公園整備が優先され、山城としての魅力は半減してしまっている。唯一、千畳敷に残る土塁と南側の堀切がかろうじて原型を止めているのが救いである。 越前大野方面に向かう。 大野城:越前大野城跡は、大野盆地の西側に位置する標高約250メートルの亀山と、その東側に縄張りを持つ平山城跡です。織田信長の武将、金森長近により天正年間(1573~1593)の前半に築城されました。越前大野城は亀山を利用し、外堀・内堀をめぐらし石垣を組み、天守閣を構えるという中世の山城にはみられなかった新しい方式の城でした。江戸時代の絵図には、本丸に望楼付き2層3階の大天主と2層2階の小天主・天狗櫓などが描かれています。本丸の石垣は、自然石をほとんど加工しないで積み上げる「野面積み」といわれるものです。江戸時代には町の大火により、城も幾度か類焼し、安永四年(1775)には本丸も焼失しましたが、寛政七年(1795)に再建されました。廃藩後、城の建造物は取り壊され、石垣のみが残されました。 勝山方面に向かう。 勝山城:勝山城の名が歴史に登場するのは、天正8年(1580)柴田勝家の一族、柴田勝安が、加賀の一向一揆を討伐し袋田村に城を築き、村岡山の別名勝山にちなみ、勝山城と名付けたのが最初である。 その後天正11年には、丹羽長秀の老臣成田弥左衛門重政、慶長5年(1600)には、結城秀康の家臣林長門定正、寛永元年(1624)には、結城秀康の六男直基、同12年には七男直良とそれぞれ入封するが、いつの時点まで城が存在していたかは不明である。正保元年(1644)勝山は、福井藩領となったが、江戸幕府への上知石高を支配する為代官が派遣され、旧勝山城の池に陣屋が建てられた。元禄4年(1691)小笠原貞信が美濃国高須から2万2777石をもって勝山に入り、幕府代官の残した陣屋跡に居を構えた。貞信は幕府に築城を願出て宝永5年(1708)ようやく許された。設計者は江戸の軍学者、山鹿藤介であった。築城工事は、多額の出費と人夫の徴発に苦しんで容易に進まず、加えて文政5年(1822)城内から出火して建物のほとんどを焼失し、勝山城は未完成のまま廃藩を迎え、廃城となった。廃城後、城地は、町役場、成器男子小学校、西方寺、三の丸製糸場などに判明され、明治22年(1889)本丸跡に最後の城主小笠原長守の筆による「勝山城址之碑」が立てられた。現在は勝山市役所、市民会館、教育福祉会館が建ち並び、中央公園も造成されている。最後まで残っていた天守閣跡、石垣内堀の一部が取り壊されたのは昭和42年市民会館を建てた時である。その後勝山市民の間に勝山城再建の願いが年毎に高まり、ここ幸いにも適地を得て、めでたく天守閣の建設を果たすことができた。 三国方面に向かう。 丸岡藩砲台跡:江戸時代末期の1852年に、丸岡藩が沿岸警備のために築いたという砲台。海に突き出た海岸線上に、弓状に築かれた高さ1.8mの土塁に5つの砲眼が4.5m間隔で設けられている。原形をこれだけしっかり留めた砲台跡は全国でも珍しく貴重らしく、国指定史跡になっている。 朝倉山城:はその名のとおり朝倉氏一族の朝倉景連がいた城だという。景連は一乗谷奉行衆の1人だった。三国に近い鶉地区の173mの朝倉山の山頂に主郭を置き、周囲に郭がめぐる形の城だった。朝倉氏が滅びた後に一向一揆が越前を支配し、織田信長の侵攻を招いた時、この城にも一揆軍が立て籠もった。詳しくは解からないがこの一揆軍はどうなったのだろうか。1561年4月に、この城の近くの棗庄大窪の浜において朝倉義景が犬追物を開催した。義景は伝統行事を復興させることに熱中しており、これもその一環だった。この犬追物は盛大に催され、鎌倉時代源頼朝の由良が浜の犬追物も及ばないものと賞賛されたという。現在は近くの小学校の手作りによる登山表示のある登り易い山だった。また山頂には戦時中の防空監視哨跡もあり、防空壕跡らしき穴もあった。山頂の櫓からの眺めが良く、三国方面から福井市方面まで眺め渡せる。 福井方面に向かう。 黒丸城:日野川と九頭竜川の合流点付近に位置し、三方を川で囲まれた地形を利用して築城され、唯一開いた南東側は深田であったという。現在小黒丸城の石碑の建てられている場所は、河川工事もすすみ、地形的にはなんの変哲もない平地に変わり、遺構はおろか当時を偲ぶ地形すら残っていない。なお、現地の案内板によれば、城址碑は現在地より北方約50mの田んぼの中に建てられていたが、県営圃場整備に伴い現在の位置に移されたとある。 小黒丸城は、大黒丸城と併せて黒丸城と総称される場合と、勝虎城、藤島城、波羅蜜城、安居城、江守城、北庄城と共に大黒丸城の支城である足羽7城のひとつであるとする説がある。 北庄城:織田信長は、一向一揆を壊滅させた直後の天正三年(1575)八月に越前49万石を柴田勝家に与えた。勝家は足羽川と吉野川との合流点に北ノ庄城を構築した。現在の柴田神社付近が本丸と伝えられる。天正九年(1581)四月、北ノ庄を訪れて来た、ポルトガルの宣教師ルイス・フロイスは、本国あての書簡の中に『此の城は甚だ立派で、今、大きな工事をして居り、予が城内に進みながら見て、最も喜んだのは、城および他の家の屋根がことごとく立派な石で葺いてあって、その色により一層城の美観を増したことである・・・・・』と報告している。また、羽柴秀吉が勝家を攻めたときに、その戦況を小早川隆景に報じた天正十一年五月十五日付の書簡の中では、北ノ庄城について『城中に石蔵を高く築き、天守を九重に上げ候・・・・』と記しており、九層の天守閣であったことが知られる。勝家はまちづくりにも創意を施し、城下の繁栄のために一乗谷から社寺・民家等を北ノ庄へ移転させるなどに努めた。足羽川に架かる橋(九十九橋)を半石半木の橋に架橋したと言われる。柴田勝家は今日の福井市の基礎を築いた人である。 15:00福井駅前のホテル到着 18:00福井駅前の繁華街散策し食事を済ませて就寝。 13日8:00帰路に向かう。 今回の旅行、福井県に点在する比較的マイナーなお城・城下町16か所を巡り楽しみました。 越前大野に位置する大野城は立派な天守閣があり聳え立っていました。あまり知られていないのは不思議なぐらい素晴らしいお城でした。 又驚いた事に最近福井県の山間部にくまが頻繁に出現、ところどころにくま防御の電気線の囲いが見られました。山城のほとんどがこの防御柵が見られ訪れにくい状態でした。 |
                    |
|||||||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第二百八十三弾:東北圏お城・城下町巡り観光 2014年9月13-15日 東北圏に点在するお城・城下町12か所のお城・城下町(新発田城、村上城、鶴ヶ岡城、山形城、米沢城、仙台城、多賀城、白石城、二本松城、三春城、白河小峰城、若松城)を訪れました。 13日14:00伊丹空港出発 15:05新潟空港到達、レンタカーで新発田方面に向かう。 新発田城:後、戦国期の勇将新発田重家が、上杉景勝との7年間の抗争の末、天正15年(1587)落城した。江戸時代には、その後を古丸(ふるまる)と言っていた。慶長3年(1598)秀吉の命により、溝口秀勝が加賀大聖寺から6万石で入封し、古丸を取り込んで慶長7年(1602)から本格的な築城にとりかかり、3代宣直の承応3年(1654)に一応完成している。実に秀勝入封から56年後のことであった。 村上方面に向かう。 村上城:村上城は、標高135mの臥牛山(がぎゅうさん)に築かれた城で、築城年代は不明ですが、16世紀前期には城が存在していたものと考えられます。戦国時代には本庄氏の本拠地として、永禄11年(1568年)の上杉謙信との篭城戦(ろうじょうせん)など、幾たびも戦いが繰り広げられました。江戸時代に入ると、村上氏・堀氏・松平氏らの城主によって城の改造と城下町の建設が行われ、村上城は北越後(きたえちご)の中心拠点として整備されました。その後も、たびたび城主が交代しますが、享保5年(1720年)以後は内藤氏が代々城主を務め、明治維新を迎えます。 中条方面に戻り、中条駅付近のホテル到着後周辺を散策し食事を済ませて就寝。 14日7:00レンタカーで出発、酒田方面に向かう。 鶴ヶ丘城:難攻不落の名城とうたわれた鶴ヶ城は、戊辰の戦役で新政府軍の猛攻の前に籠城一ヵ月、城は落ちなかった。石垣だけを残して取り壊されたのは明治7年のことである。至徳元年(1384)葦名直盛がはじめて館を築き、改修を経て天下の名城となった。 山形方面に向かう。 山形城:形城は南北朝騒乱の中、足利政権下に奥州探題が成立し、 斯波(しば)家兼の次子兼頼によりその居所として築かれたことに始まる。兼頼の子孫は最上氏を称し、十一代目の義光は強力な在地支配を確立して、今の山形県のほとんどを手中にした戦国大名となる。 関ヶ原の合戦後は五十七万石の雄藩となり、本丸・二の丸・三の丸を同心円に重ねた標準的な縄張で、東北地方では屈指の本格的な平城を築城する。櫓は十三棟あったようだが、天守は築かれじまいである。 米沢方面に向かう。 米沢城:米沢城は、江戸時代に上杉氏が城主だったお城として知られています。越後の守護代だった長尾景虎が関東管領を譲り受け上杉氏を名乗り、武田信玄との激闘を経て、越後から能登・加賀に至る地域を平定しました。その人が戦国の名将と言われた、上杉謙信です。謙信の後継・上杉景勝は、豊臣秀吉が天下人となると、120万石の大大名として会津に移封されるのですが、関ヶ原の戦いで西軍に組した為、30万石に減封されこの米沢城に入城しています。 米沢城の起源は1238年(暦仁元年)に長井氏が築城したと伝わっています。その長井氏が1380年(天授6年)に伊達氏に滅ぼされると、上杉氏が会津に移封される1598年(慶長3年)までの200年間は伊達氏の居城だったそうです。 仙台方面に向かう。 仙台城:慶長五年(1600)、関ヶ原合戦において東軍に与した伊達政宗は、幕府の許可を得て居城を岩出山城から青葉山に移した。これが仙台城である。政宗は翌同六年(1601)四月には未完成の仙台城に移っており、新城にたいする熱い思いが感じられる。 政宗時代の仙台城は現在の本丸部分である。この地は南方には深い龍の口峡谷が、東から南にかけては広瀬川の河岸段丘に守られた天然の要害であった。唯一青葉山との尾根続きであった西側には掘切が設けられたいた。この周辺の崖は急峻な絶壁であり、そこから攻めることは不可能である。こうした選地について、『正保城絵図』の「奥州仙台城絵図」ははっきりと「本丸山城」と記している。 本丸には豪華な本丸御殿が建造され、政宗は山上で生活していた。本丸周辺は急峻な崖であるので、ほとんど石垣が築かれず、正面である北面にのみ象徴的に築かれたようである。南西隅には天守台も構えられるが、土塁であり、天守も建造されなかった。本丸は政宗以後用いられず、二代忠宗は山麓に二の丸を構えた。以後、二の丸は幕末に至るまで仙台城の中心として、政庁および藩主の私邸として機能した。 多賀方面に向かう。 多賀城:多賀城は神亀元年(じんきがんねん)(724)に大野東人(おおの あずまびと)によって創建され、陸奥国府(むつこくふ)と鎮守府(ちんじゅふ)が置かれました。 約900メートル四方という広大な城内の中央には、重要な政務や儀式を行う政庁がありました。 発掘調査成果をもとに環境整備が行われており、平城宮跡(奈良県)、太宰府跡(福岡県)とともに日本三大史跡に数えられています。 白石方面に向かう。 白石城:天正十九年(1591)豊臣秀吉は、伊達氏の支配下にあったこの地方を没収し、会津若松城とともに蒲生氏郷に与えた。蒲生氏家臣浦生源左衛門郷成は、白石城を築城し城主となった。慶長三年(1598)上杉領となるや上杉氏家臣甘糟備後守清長は白石城の再構築を行い居城した。 慶長五年(1600)関ヶ原合戦の直前、伊達政宗は白石城を攻略し、この地方は再び伊達領となり、伊達氏家臣片倉小十郎によって大改築がなされ、以後明治維新まで二百六十余年間片倉氏の居城となった。 福島方面に向かう。 福島駅付近のホテル到着後繁華街を散策し食事を済ませて就寝。 15日7:00レンタカーで出発、二本松方面に向かう。 二本松城: 二本松といえば、毎年秋の菊人形がつくられる舞台として名高い。菊祭り以外の時期に観光客を呼ぼうと考えた行政が、誤った歴史認識を市民に与えてしまった。昭和五十六年(1981)度に復興した箕輪門と二重櫓である。共に史実をまったく無視したもので、古絵図に描かれている箕輪門の姿ではない。しかし左右の石垣は、さすがに安土城の総普請奉行をつとめた丹羽長秀の嫡孫光重が築いたことだけあって、みごとの一言に尽きる。 箕輪門左右の石垣を見たなら、ぜひとも背後の山城に登ってもらいたい。平成十四年度までに全面発掘及び復元整備を完了した、山城域をぐるりとめぐる天守台石垣と本丸の石垣が見学できる。この標高三百四十五メートルの山城域こそ、足利政権が奥州の鎮守府として畠山氏を配して築いた二本松城のあった所、すなわち中世の二本松城のあった所で、麓の城とは異なるのだ。今、発掘で出土、復元整備された石垣は、畠山氏時代ののち、会津を領した蒲生氏郷・上杉景勝時代に積まれ、丹羽氏時代には詰の城として補強されたもの。 三春方面に向かう。 三春城:案内板によると三春城は「永世元(1504)年田村義顕が築城したと伝えられ、以後田村氏、松下氏等の居城となる。正保2(1645)年、秋田俊季が5万5千石で入城し、明治維新を迎えた。近世の城は、本丸、二の丸、三の丸を中心に形成され本丸には表門、裏門、三階櫓などの建造物が置かれていた。藩主は現三春小学校の場所に屋敷を構え、そこで政治を行った。明治初年廃城となり、建造物、石垣のほとんどを失ったが遺構の保存状態は良く、また県内で中世から近世にかけて同じ場所に城が築かれた例も少ないため、貴重な史跡といえる。 三春町教育委員会」とあります。三春城は当時はかなり高い石垣などをもっていたようですが、現在はその一部しか見ることが出来ません。郭や登城の道などは比較的残り、土塁や空掘り、建物の礎石の一部も確認する事が出来ます。三春城本体としては山城の為、大手門から本丸まではかなりきつい坂を登る事になり、近世に入ると城下町に近い現三春小学校の場所で政務が行われていました。藩校の表門が現在でも残っており三春小学校の表門として移築保存され三春町指定有形文化財に指定されています。 白河方面に向かう。 白河小峰城:白河小峰城は南北朝時代、結城親朝が興国元年(1340)小峰ヶ岡に城をかまえて小峰城と名付けたのがはじめといわれている。 寛永四年(1627)丹羽長重が十万石の城主として棚倉藩より移封され、幕命により同六年城郭の大改築に着手、四年の歳月を費やして同九年に完成。江戸時代における代表的な梯郭式の平山城である。その後、榊原、本多、奥平松平、結城松平、久松松平、阿部と七家二十一代の城主の交代があったが、慶応三年(1867)最後の阿部氏が棚倉藩に移封された後、白河は幕府領となって城郭は二本松藩丹羽氏のあずかるところとなり、同四年五月、戊辰の役の攻防で落城した。 会津若松方面に向かう。 若松城:会津若松城は蘆名(あしな)氏七代直盛によって至徳元年(1384)につくられた館が始まりといわれる。その後、蘆名氏は会津をはじめ中通り地方まで勢力を振るったが、天正十七年(1589)、摺上原(すりあげはら)の戦いで伊達政宗に敗れ滅亡した。しかし、伊達市も奥羽仕置で豊臣秀吉に会津を召し上げられ、蒲生氏郷が奥州の押さえとして会津に入った。氏郷は文禄元年(1592)から七重の天守を上げるなど大改修を施すとともに城下町を整備し、町の名を黒川から若松に改めた。氏郷が亡くなった後は上杉景勝が入った。景勝は大大名の主城として別に大きな平城である神指城(福島県)を築き始めるが、関ヶ原の戦いで未完成に終わった。 上杉氏の後は再び蒲生氏が入るが、現在見られるような城の姿につくりかえたのは伊予松山から入った加藤嘉明の子明成である。明成は寛永十六年(1639)に起工し、天守を五重に改めるなど大改修を行った。加藤氏改易の後は三代将軍家光の異母弟保科正之が入り、会津松平氏の祖となる。戊辰戦争では1か月の攻囲に耐え、官軍を一兵たりとも城内に進入させなかった。 新潟に向かう。 15:05新潟空港到達。 15:35新潟空港出発 16:45伊丹空港到達。 今回の旅行:東北に足を運び、東北圏に点在する12か所のお城・城下町(新発田城、村上城、鶴ヶ岡城、山形城、米沢城、仙台城、多賀城、白石城、二本松城、三春城、白河城、若松城)をレンタカーで巡り訪れ楽しめました。 以前に1度は訪れたことのあるお城(三春城は初めて)でしたが残念ながら白河小峰城は震災の影響で石垣が崩れ工事中であり中に入れず外からの景観を望むのみとなりました。 東北地方の観光地は震災後は観光客も少なく寂れていましたが、今回な多くの観光客が押し寄せ、賑わい、活気満ちていました。完全に観光地が復活したように思われる東北圏お城・城下町巡りでした。 |
              |
|||||||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第二百七十三弾:近畿圏お城・城下町巡り 2014年5月17-18日 近畿圏の日本100名城である6つのお城(千早城・高取城・竹田城・安土城・観音寺城・小谷城)を巡りました。 17日12:30車で出発、大阪の南河内方面に向かう。 千早城:南北朝時代、後醍醐天皇(南朝)の功臣として有名な楠木正成が鎌倉幕府との戦いの為、赤坂城の詰めの城として1332年に築城されました。四方を絶壁に囲まれた要害で、巧みな戦術を用いて北条(鎌倉幕府)の大軍を翻弄しました。正成の死後も楠一族により保持されていましたが、1392年には北朝方の畠山基国に破れ落城してしまい、現在は一部、空堀や曲輪を遺稿に残すのみとなっています。 奈良の高市方面に向かう。 高取城:1332年、南朝方の武将であった越智邦澄によって築城されました。江戸時代は高取藩の藩庁が置かれ、当時は曲輪が連格式に連なっていましたが明治に入り1873年には廃城になり、建物は払い下げられるか自然倒壊してしまいました。日本最大規模の山城で、現在は石垣や堀、井戸などの遺稿があり、三大山城の一つに数えられています。 兵庫の和田山方面に向かう。 16:30和田山市内のホテル到着後近場の居酒屋で食事を済ませて就寝。 18日7:30車で出発、竹田城に向かう。 竹田城:築城に関しては定かでありませんが1431年、応仁の乱の起因となった一人である山名宗全によって築城されたと伝えられる山城です。室町以降、畿内への要衝として多くの戦で攻防が繰り広げられましたが、関ヶ原の戦いの後、1600年には廃城となっています。城下から見上げる山頂に位置し、しばしば霞がかかることから「天空の城」とも呼ばれています。石垣がほぼ往時のままの状態で残っており、現存の山城の中では最大級の規模を誇ります。 8:40車で滋賀の安土方面に向かう。 安土城:1576年、織田信長によって築かれた最初の大規模近世城郭です。それまでの居城である岐阜よりも京都に近く、琵琶湖の水運も利用出来、北陸への向えるなど交通の要所でもあったことが理由とされています。1582年に本能寺の変によって信長が倒れると、時を置かず天守は原因不明の焼失をしてしまいまい、1585年には廃城となります。これまでに例を見ない壮大な造りでしたが、その姿を後世に伝える文献も少なく「幻の名城」と言われています。城跡は特別史跡に指定され石垣、大手石道、門跡などの遺構が残っています。 観音寺城:築城年は不明ですが近江源氏佐々木氏の居館があり、その後支族である守護大名の六角氏の居城として築かれたと言われ、応仁の乱では三度の攻防戦が繰り広げられました。1568年に上洛を目指す織田信長が支城である箕作城を落城させると、六角義賢、義治親子は逃亡し観音寺城も無血開城し廃城になりました。城跡には本丸や曲輪、石垣、土塁、堀、門跡などの数多くの遺構が残されています。 湖北方面に向かう。 小谷城:戦国期に近江北部を治めていた戦国大名浅井氏の代々の居城です。その築城は浅井亮政の時代、1516年頃ではないかと言われています。多くの支城の守られた堅固な山城で織田信長も何度も攻めあぐねましたが1573年、ついに落城。その後、小谷城近隣は信長により羽柴(後の豊臣)秀吉の所領とされましたが、1575年に長浜城が築城され、小谷城は廃城となりました。日本五大山城の一つで城址には土塁や曲輪、石垣が遺構として残っています。 16:30帰路に向かう。 今回の旅行、近畿圏内の日本百名城の比較的マイナーなお城6か所を巡り楽しめました。 6つのお城はすべて山城でたどり着くのが困難、かなり歩かされました。 竹田城は5年前訪れたことがありますが、すんなりお城の手前で車をとめてたどり着けましたが、今は竹田城ブーム、かなりの観光客が訪れるようになり、整備され、駐車場からは2km歩かないとたどり着けなくなりました。「天空の城」人気があるのですね。 全般にお城ブームか?、どのお城も賑会ってましたね。 |
       |
|||||||||||||
| 奈良県お城・城下町巡り 2014年4月6日 日本の歴史の源、世界遺産の宝庫、奈良県に足を運び、比較的マイナーなお城16か所をおとずれました。 7:00車で出発。 多聞城:永禄三年(1560年)に松永久秀が築城したとされます。安土城以前に天守を持ち、長屋状の櫓を巡らし、これが後にいろんな城郭で多用され、これを多聞櫓と呼ばれるようになりました。天正元年(1573年)に久秀は織田信長に離反し、多聞城は天正四年(1576年)に信長の命で筒井順慶が破却し、用材は筒井城、大和郡山城に使用されたようです。久秀は翌天正五年(1577年)に再び信長から離反し信貴山城で自刀しました。 柳生城:築城時期は不明です。天文十三年(1544年)筒井順昭に攻められ落城しています。その後、筒井氏、松永氏に従いますが、元亀二年(1571年)、宗巌は松永久秀に味方し筒井順慶と戦いました。天正13年に宗巌は豊臣秀吉から隠田発覚により所領没収となりますが、宗厳は柳生新陰流の祖、石舟斎となり、文禄三年(1594年)に石舟斎宗厳は家康の召しだされました。慶長五年(1600年)の関ヶ原の戦功により宗巌の五男宗矩が柳生家再興を果たしました。 福住井之市城:元々は福住氏を攻めた越智氏・十市氏の砦として築城されたようですが、その後は福住氏の詰めの城として機能したようです。 椿尾上城:築城年代は定かではありませんが、天文年間(1532~55年)の筒井順興・順昭が当主の時代に 平野の筒井城に対して、山ノ城として、筒井氏の拠点して築かれた城のようです。史料では天文十年(1541年)に山ノ城の記事があるようです。天文十九年(1550年)に順昭が死去し、幼い順慶が後を継ぎますが、永禄二年(1559年)に松永久秀に攻められ筒井城は落城し、椿尾(上)城を拠点に反抗したと伝わります。天正五年(1577年)に松永久秀が滅び、天正八年(1580年)に織田信長の大和一城令の命で、順慶は郡山城を居城としたため、椿尾(上)城も廃城になったと考えられます。 豊田城:築城時期は定かではありませんが、豊田氏の本拠として築城されました。豊田頼英が城主の頃が全盛期だったようで、豊田氏は応仁の乱までは越智方明応七年(1467年)に越智氏が没落時には筒井氏に攻められ落城、その後も豊田氏は筒井氏に対抗しますが、永正二年(1505年)の大和国人一揆以降筒井氏に従ったようです。永禄十一年(1568年)に松永久秀に攻められ落城し、以後、豊田城は松永氏によって現在の形に改修されたと考えられます。城の廃城はは松永氏の滅亡した天正五年(1577年)頃でしょうか? 龍王山城:南北朝期に小さな砦が構築されていたようです。戦国期に入り、十市遠忠が永正三年(1506年)の大和国人一揆以降に本格築城を開始したとされます。天文年間(1532~55年)に完成したようです。十市氏は遠忠の時が全盛期でしたが、天文十一年(1545年)に遠忠が死去し、急速に衰えました。遠忠の嫡男の遠勝の代になり、永禄十一年(1568年)に松永氏方の秋山氏に攻められ落城、遠勝は十市城に退きました。その後は、松永派の十市氏一族が守備、天正五年(1577年)、松永久秀が信貴山城で滅亡した後、翌年にこの城も織田信長の命で廃城になったとされます。 宇陀松山城:宇陀三将と呼ばれた秋山氏の本城として南北朝期に築城されたとされます。天正十三年(1585年)に豊臣秀長が大和郡山城に入り、秋山氏は伊賀に追放されたとされます。秋山城には伊藤氏、加藤氏などの居城となりました。慶長五年(1600年)の関が原の戦いでは、その時の城主の多賀秀種は西軍に付いたため改易され、変わって福島正則の弟の福島高晴(孝治)が入りました。この時に城は大改修され、名前も松山城と呼ばれるようになったようです。元和元年(1615年)に、大阪夏の陣で高晴が大阪方に内通したとして改易され、城は小堀遠州によって破城されました。同年に織田信長の次男の織田信雄が宇陀三万石と上州甘楽郡二万石を与えられ、麓に陣屋を築きました。元和三年(1617年)に信雄の四男の信良に甘楽郡が分与され小幡藩となりました。宇陀松山藩は信雄ー高長ー長頼ー信武と続きますが、元禄八年(1695年)、信武が家臣を殺害し自殺したため、信休は丹波柏原に減封され二万石で移封となり、宇陀松山はその後は天領となりました。 沢城:南北朝期に築城された沢氏の居城とされます。沢氏は南朝方としてこの地方に勢力を競いました。永禄三年(1560年)に松永氏に攻められ落城し、城には松永氏方の高山友照(飛騨守・図書)が入りました。永禄十一年(1568年)頃に高山氏は和田惟政に属し、さらに、元亀四年(1573年)に高山氏は高槻城の城主になっています。高山氏が沢城を離れてから沢氏が復帰していましたが、天正四年(1576年)頃には筒井氏に攻められ没落し、天正八年(1580年)の織田信長の破却令によって廃城になったようです。高山友照は高山右近(重友)の父であり、右近は天文二十一年(1552年)生まれであり、幼少期にこの城におり、洗礼を受けたと伝わります。 十市城:築城時期は定かでは無いようですが、筒井氏、越智氏に次ぐ国人の十市氏の本城でした。永正二年(1505年)からの大和国人一揆では国判衆として活躍しました。十市遠忠は筒井氏(順興・順昭・順慶)に従い、天文十年(1541年)頃に龍王山城を築城し、十市氏の全盛期であったとされます。天文十四年(1545年)に遠忠が九死し、十市遠勝の代になると松永氏と筒井氏の間で急速に衰えました。永禄十一年(1568年)には松永氏方の秋山氏に攻められ龍王山城が落城、十市城に拠るも、永禄十二年(1569年)に遠勝が急死し、嫡流は断絶しました。この後、家臣は跡継ぎ養子問題で松永派と筒井派で争い、さらに衰退し、遠忠の次男の十市常陸介遠長は筒井氏に従いますが、天正三年(1575年)には松永久通に攻められ落城し城を失いました。天正十三年(1585年)、筒井定次の伊賀転封後は豊臣秀長に仕えたとされますが、天正十九年(1591年)、秀長家断絶後は没落したようです。 高田城:永享四年(1432年)に高田当麻為貞が築城しました。當麻為長の代に天正八年(1580年)み織田信長の命で筒井順慶によって所領を没収されました。 二上山城:築城年代は定かではない。楠氏七城の一つとして楠木正成によって築かれたと伝えられるが定かではない。明応8年(1499年)赤沢朝経が二上山城を拠点として大和を制圧したが、永正4年(1507年)細川政元が永正の錯乱によって暗殺されると赤沢氏の勢力も削がれた。天文10年(1541年)木沢長政が二上山城や信貴山城を整備し拠点としたが、翌天文11年に木沢長政が敗死すると二上山城も攻め落とされた。 片岡城:明応7年4月5日(1498年5月5日)に畠山尚順配下の筒井氏が「片岡」を攻め落とした記録があるが、これが当城かは不明である。この時に片岡利持が自害した思われている。また『片岡系図』によると片岡城は16世紀初頭に片岡国春によって築かれたとされる。その後片岡春利の代になり、永禄12年(1569年)4月8日に松永久秀に攻められ、片岡城が乗っ取られ、数日駐留した後に越智氏征伐のため南進していった。その後『大和軍師』によれば、片岡春利は片岡城で抗戦しているところから、再奪取に成功したものと思われる。春利は翌元亀元年(1570年)3月5日、片岡城にて36歳で病死したようである。その後11月19日から20日に松永軍により片岡一帯が制圧し、片岡城も落城したのではないかと推察されている。天正5年(1577年)8月、松永久秀が織田信長に反旗を翻したため、信貴山城の戦いに先立つ同年10月1日(1577年11月20日)に、明智光秀・筒井順慶・長岡藤孝ら約5千兵で攻城、これに対して松永軍は海老名友清、森正友らが率いる約1千兵で防御したが激戦の末に落城した。ちなみに藤孝の息子である細川忠興・興元兄弟は、この戦いでの働きにより信長から直筆の感状をもらっている。廃城年代は不明。 信貴山城:築城年代は定かではない。河内国との国境に近い要衝にあることから南北朝時代頃から砦や陣が設けられたと云われている。本格的な城郭を築いたのは木沢長政で天文5年(1536年)の頃と云われる。木沢長政は河内国守護職畠山氏の家臣で飯盛山城主となるなど重用されたが、主君畠山義堯を裏切って細川晴元に接近した。天文11年(1542年)河内太平寺合戦で長政は討死し、二上山城とともに信貴山城も落城した。永禄2年(1559年)松永弾正久秀が大和へ入国すると、多聞山城とともに信貴山城も改修して拠点とした。永禄7年(1564年)三好長慶が飯盛山城で病没すると、松永久秀は三好三人衆と将軍足利義輝の暗殺するなど畿内での勢力を増したが、三好三人衆と仲違いしたことにより、大和より追い出した筒井順慶が三好三人衆と結んで筒井城の奪還を計る。三好家中で孤立した久秀は高屋城主の畠山高政と結んでこれに対抗しようとしたが、上芝での戦いに敗れた。 その後、三好三人衆の陣があった東大寺の奇襲に成功した久秀であったが、信貴山城は三好・筒井軍によって攻め落とされた。永禄11年(1568年)足利義昭を奉じて上洛した織田信長に久秀はいち早く降り、その加勢を得ると信貴山城を取り戻した。元亀元年(1570年)筒井順慶の勢力が盛り返すと、翌元亀2年には辰市城合戦で大敗を喫した。その後、筒井順慶も織田信長に帰順し、その斡旋もあって和睦となった。その後、将軍足利義昭が画策した信長包囲網に加わり反旗を翻したが、天正元年(1573年)甲斐の武田信玄が没すると包囲網も破綻し、久秀は多聞山城を明け渡すことで信長に降り、信貴山城へ退いた。天正5年(1577年)久秀は佐久間盛信に従って本願寺攻めに加勢していたが、再び毛利輝元や上杉謙信、本願寺など反信長勢力に荷担し信貴山城に籠城した。信長は筒井順慶などを主力とする大軍を送り込み、久秀が所有している名器・平蜘蛛茶釜を差し出せば助命すると勧告するが久秀はこれを拒否。久秀は天守に籠もって自爆して果てた。 小泉城:築城年代は定かではないが室町時代に小泉氏によって築かれた。 小泉氏は大乗院方衆徒で、康正元年(1455年)畠山政長方の筒井氏が没落した後、官符衆徒につき、その後越智方について筒井氏と対立した。 長禄3年(1459年)筒井順永の攻撃をうけ落城した。天正8年(1580年)以後、羽田長門守が陣屋を置いていたが、慶長6年(1601年)片桐且元の弟貞隆が一万五千石を領して小泉に入部し陣屋を構えた。 筒井城:永享元年(1429年)筒井順覚によって築かれた。 筒井氏は天児屋根命の子孫ともいわれるが定かではない。 興福寺一乗院の衆徒である。嘉吉元年(1441年)に家督を継いだ順永の代に勢力を広げるが、その後は越智氏などと抗争が繰り広げられた。 永禄2年(1559年)松永久秀が大和に入国すると松永氏と対立し筒井城を奪われた。松永氏の滅亡後多聞城の石を転用して城郭の拡張を行ったが、織田信長の大和一国破城命令によって破却となり、郡山城を居城とした。 稗田環濠:室町時代頃に形成された環濠集落と考えられている。 文安元年(1444年)古市胤仙が稗田を奪って城として使ったということから、この頃には城郭として一時機能していたと考えられている。 今回の旅行、近場の歴史ある奈良県に足を運び、16か所の比較的マイナーなお城を巡り楽しめました。 今回も見つけるのが一苦労で城山のみとか、石碑のみとか、案内板のみとか、地味な城跡がほとんどでした。 天候も生憎悪く、大雨が降ったり、雹が降ったり結構大変な城めぐりでした。 |
              |
|||||||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第二百六十八弾:大阪府お城&城下町巡り 2014年3月19日21日 奈良や京都に近く、交通の要所として栄え、南北朝の内乱では、各地で激しい戦闘が行われ、数々の城砦が築かれ、以後、細川氏、畠山氏が守護となるが動乱が絶えず、築城、廃城された城も多い大阪に足を運び、大阪府に位置する比較的マイナーなお城18か所(飯盛山城・交野城・津田城・守口城・茨木城・高槻城・芥川城・地黄陣屋・池田城・真田丸出城・若江城・恩智城・八尾城・高屋城・丹南陣屋・狭山陣屋・上赤坂城・根福寺城)を巡りました。 19日12:30車で出発、三か所の北河内のお城を巡る。 飯盛山城:飯盛山城は、建武年間に佐々目憲法によって築かれたと云われているが、南北朝時代の争乱期に臨戦的な陣城であったというのが実態である。戦国時代、畠山氏家臣木沢長政が飯盛山城を居城し、守護畠山義宣にとって替わり河内守護代となり将軍家直臣にまでなるほどの勢力を誇ったが、天文11年に細川晴元・三好長慶と河内太平寺で合戦して敗れ滅亡した。木沢氏滅亡後、交野城主安見直政が城主となり、守護畠山高政より河内守護代に任じられた。 永禄2年、三好長慶は畠山高政の居城高屋城を囲み、救援に向かった安見直政を敗走させ、永禄3年に長慶は高屋・飯盛山城を手に入れ、飯盛山城へと入った。三好長慶は、飯盛山城・高屋城・芥川城を拠点に河内を支配したが、永禄7年病没する。永禄11年、織田信長が入洛すると三好三人衆も信長に臣従し、飯盛山城は畠山昭高の持城となった。 天正4年、昭高の家臣遊佐信教が守備したが、信長に攻められ落城、その後廃城となった。 交野城:交野城は、私部城とも呼ばれ南北朝時代の文和元年頃に南朝方に与していた安見清儀によって築かれた。その後安見氏は北朝方に移り、正平年間に畠山義深が河内守護となった時から、代々畠山家の重臣となり、のち遊佐・木沢両氏とならんで河内守護代となったこともあった。戦国時代の安見直政は、守護畠山氏に替わって河内守護と称し勢力を誇ったが、三好長慶に攻められ一時大和へ逃れた。永禄12年、織田信長は河内統一後、安見直政は所領を回復し私部城に居城した。 安見直政が病没後、大和筒井氏に私部城は攻められ落城。 その後、天正3年に織田信長の命により廃城となった。 津田城:津田城は、今からおよそ500年前の延徳2年(1490)に、津田周防守正信が築いた城です。正信は楠木氏の一族につながると言われ、その子孫は根来寺の僧兵長だった津田算長(杉之坊算長)とも言われています。算長は種子島の領主から鉄砲を買い求め、畿内に持ち帰り広めた事で知られ、津田流砲術の祖としても有名です。畿内が三好長慶によって掌握された時、三好氏に従った津田氏でしたが、やがて織田信長が畿内に侵攻すると、津田氏も攻撃対象となり、津田城は落城しました。当時の城主津田正時は城を追われ浪人となりました。後に許された正時は、国見山の西麓に本丸山城を築きそこに入城しました。本能寺の変後、羽柴秀吉と明智光秀が争った山崎の戦いでは、明智方として戦いました。明智光秀が敗れ、正時は再び城を追われ、再度浪々の身となりました。しかし再び許され、秀吉からわずかな領地を与えられていたようです。昭和30年代に発掘調査が行われた際、地表から30cmのところに土が焼けているのが発見されました。これは信長に焼き討ちにあった時の跡と言われています。 17:00終了。 21日7:00車で出発、15か所のお城を巡りました。 守口城:守口城は、築城者は定かでないが室町時代に築かれ、大内義弘麾下の杉九郎が在城している。 応仁の乱や石山合戦においても度々戦場となっている。 茨木城:茨木城の築城年代は定かではない。 天正5年、中川清秀が7万石で入城している。 清秀は、賤ヶ岳の合戦で大岩山砦を柴田方の佐久間盛政に奇襲され戦死し、子の中川秀政は播磨三木に移る。 慶長6年、片桐且元が12,000石で城主となった。 且元は、元和元年の大坂の陣の後、茨木と大和龍田4万石を領して茨木城を居城としたが同年没する。 後を嗣いだ孝利は大和龍田へ、且元の弟貞隆は大和小泉に移り、茨木城は廃城となった。 高槻城:永禄12年、織田信長が芥川山城を落とし、高槻城は和田惟政(近江和田城が本貫の地)に与えられた。 元亀2年、惟政は白井河原の合戦で戦死し、後を嗣いだ惟長もまた、家臣高山右近父子によって元亀4年に城を追われる。 高山飛弾・右近父子は切利支丹大名と知られている。大坂の陣の後、元和元年に近江長浜より内藤信正が4万石で入城する。 内藤氏以後、土岐・松平・岡部・松平氏と目まぐるしく城主が替わる。慶安2年、永井直清が山城勝竜寺より36,000石で入城して安定する。 永井氏は、13代に渡って居城し明治に至った。 芥川城:芥川城の築城年代は定かではないが、鎌倉時代後期に芥川宿を根拠とした芥川氏によって築かれた。 応仁の乱では、芥川氏は三宅・吹田・茨木氏らと共に東軍に属して戦ったが、応仁元年に大内政弘の軍門に降った。延徳3年、細川政元が芥川城を再建して重臣能勢頼則を城主とした。 永正12年頃には芥川山城が築かれれ、その後芥川城はどのようになったかは定かではない。 地黄陣屋:地黄陣屋は、慶長7年に能勢頼次によって築かれた。 能勢氏は、代々陣屋北西の丸山城を居城としていた。 能勢氏は山崎の合戦では明智光秀に組みし、秀吉の丸山城来襲によりこの地を離れた。能勢頼次は、浪々の末徳川家康に仕え、慶長5年、関ヶ原の戦功により旧領を回復した。 元和元年、家臣山田彦右衛門を普請奉行にして、陣屋を築城し、同時に城下町も形成された。 能勢氏は、江戸時代を通じてこの地を領して11代頼富の時に明治を迎えた。 池田城:鎌倉時代に築かれて、室町時代初に池田教依によって城としての形態が整った。嘉吉3年には、池田充正が三の丸を拡張するなど城の規模拡大を行っている。 この頃に城下町池田が形成 された。永正5年に、池田貞正は細川高国と戦い城は落城。 その後、貞正の子、池田久宗が池田城を奪回している。 永禄11年に織田信長が摂津に出陣したとき、池田勝正は信長に降伏し、摂津三守護に任じられている。 天正7年(1579年)に、伊丹有岡城主荒木村重が信長に謀反を起こした時、池田重成は荒木氏に従い、運命を共にした。 天正8年(1580年)に信長が、筒井順慶に摂津・河内・和泉の破城 を命じた時に廃城となった。 真田丸出城:慶長十九年、大阪城の南面の防御が弱いことを見ぬいた真田幸村は自ら大阪城を出て、笹山という小丘陵に出城を築いた。真田丸出城である。この出丸は東西二つの郭からなっており、東側の郭は東南部を水堀で囲まれ、南部には空堀がつくられている。また北門からは大阪城内へと通じている。一方、西側の郭は南面を半月状に頑丈な柵で固められており、真田丸出丸の別名である「偃月」の通り、三日月状の出城であった。 遺構は餌差町の円珠庵の北方の高台がその遺跡である。 若江城:若江城は、南北朝時代に高屋城主河内守護畠山基国によって築かれ、守護代遊佐氏が城主となった。 宝暦2年に畠山持国の相続をめぐって実子義就と養子政長が争い、これが応仁の乱へと発展した。若江城は、若江氏・堀江氏・山田氏と城主が変遷し、その後三好氏の持城となっていた。 永禄11年に畿内平定を果たした織田信長は、河内北半国を三好義継に安堵し若江城主とした。 天正元年、足利義昭を追放した信長は義昭に与した三好義継を若江城に攻め、義継を自刃させた。天正4年から始まる信長による石山本願寺攻めの拠点として若江城は使用されたが、本願寺開城・退去後の天正8年頃に廃城となった。 恩智城:恩智城は、建武年間に恩智左近満一によって築かれた。 左近は、恩智神社社家の後裔で、南北朝期には楠木正成に従い楠公八臣の一人に数えられ、千早城の籠城戦や飯盛山城攻めにも参陣して活躍した。貞和4年、左近は楠木正行に従って四条畷で討ち死にした。 恩地城は、左近の討ち死に共に落城したと伝えられている。 八尾城:八尾城は、南北朝時代に八尾別当顕幸によって築かれた。 顕幸は、八尾一帯に勢力を誇った土豪で、正慶2年に南朝方として赤坂へ移った。戦国時代、池田紀正が八尾城に居城した。 紀正は、三好義継の老臣であったが、天正元年に織田信長が三好氏を攻めたとき、野間・多羅尾氏と共に信長に内応した。 その後、紀正は若江城を預かり、石山本願寺攻めが終わると若江城から八尾城へ移り、天正12年に長久手の合戦後美濃へ移った。 高屋城:応永年間に畠山基国が管領兼河内守護なり、古墳を利用して築城して、守護代遊佐氏が城代となった。 応仁の乱以後、守護畠山氏の居城として、畠山氏の相続争いの舞台となった。戦国期には、畠山高政・安見直政・三好長慶の三勢力により、高屋城争奪戦が繰り返され、目まぐるしく城主が入れ替わった。 天正3年、最後の城主となった三好康長が、織田信長に攻められ落城。 その後、高屋城は廃城となった。 丹南陣屋:元和9年、高木正次が大坂城定番となり、河内丹南1万石を与えられ、陣屋を築いた。 丹南藩は、河内にあった1万石クラスの4つの藩(大井・狭山・西代・丹南)の一つで、初代正次以後、代々居城して11代正担の時に明治を迎えた。 狭山陣屋:天正18年、秀吉の小田原征伐後に伊豆韮山城主北条氏規は河内の地に若干の領地を得た。北条氏直が高野山に蟄居して没した後、北条氏規の子氏盛は、氏直遺領4,000石余、父氏規遺領6,900石を併せて領し、狭山11,000石で大名に列する。陣屋は、狭山2代氏信が築いている。 制度上は陣屋であるが、城としての機能は十分備えた構えであった。 戦国関東の雄、北条氏は1万石ながら河内の地で明治まで存続している。 上赤坂城:上赤阪城は、元弘年間に楠木正成によって築かれた。 この上赤阪城が本城、詰の城が千早城、出城が下赤阪城だ。この地は、楠木氏の本拠地(千早赤阪村)で下赤阪城も含めて広義の赤阪城とも云われている。元弘3年、鎌倉幕府に反旗を翻した楠木正成を討つため、鎌倉幕府は大軍を派遣してこの城を攻めた。 周囲に配置した砦群を落とされ、防戦10日で城は落城した。 根福寺城:根福寺城は、天文4年に松浦守(まもる)によって築かれ、当初、野田山城と呼ばれていた。 松浦守は、細川晴元・細川元常の将として名を挙げたが、晴元が三好長慶と対立するに及んで長慶方となり、根来寺勢力とも敵対することになった。天文12年より根来寺領となり根福寺城と改称した。 その後、天正13年の羽柴秀吉の紀州征伐により根来寺降伏後は、秀吉の支配下に入った。 18:05終了、帰路に向かう。 今回の旅行、大阪府の比較的マイナーなお城18か所を巡り歴史の勉強してきました。 石碑のみとか、案内看板のみとかで探し出すのが一苦労の大阪のマイナーなお城巡り結構楽しめました。 |
              |
|||||||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第二百六十七弾:福岡県お城&城下町巡り第一弾 2014年3月15-16日 九州北部に位置し、古くから中国や朝鮮との貿易を通して、本州に物資を送り込む拠点で、室町時代に大内氏が勢力を拡大するが、やがて大友宗麟が北九州を平定、島津氏の北上に対抗した福岡県に足を運び、福岡県内のお城&城下町(11か所)を巡りました。 15日13:45新大阪新幹線のぞみで出発 16:14博多駅到達、レンタカーでお城めぐり。 名島城:天文年間(1532年~1555年)立花鑑載によって築かれた。 天正15年(1587年)小早川隆景が筑前一国と筑後、肥前の一部で五十二万数千石を領すると新しく改修した。改修に際しては豊臣秀吉も設計に関わったと言われる。 関ヶ原合戦の後に筑前一国で入部した黒田長政が慶長5年に入城したが慶長7年福岡城を築いて移り廃城となった。 三方を海で囲まれたこの地は水軍を重要視する小早川隆景には優れた土地であったが一国の中心として城下を築くには手狭であった。 立花城:築城年代は定かではないが建武年間(1334年~1336年)大友貞範によって築かれたと云われる。 大友貞範は豊後国大友氏6代貞宗の子で立花に入部して立花氏を名乗った。永禄11年(1568年)立花鑑範は安芸国毛利氏に通じて大友氏に反旗を翻した。これに対して大友宗麟は戸次鑑連(立花道雪)を将として大軍を送り、三ヶ月に及ぶ攻防の末に落とし、立花鑑範は自刃した。 その後も大友氏と毛利氏の間で争奪戦が繰り広げられたが元亀元年(1570年)大友氏の支配となり、翌2年に戸次鑑連が立花山城主となった。戸次鑑連の養子なった立花宗茂は島津氏の大軍に対して立花山城を守り抜き、天正15年(1587年)筑後国柳河に移封となった。 替わって入部した小早川隆景は名島城を居城とし、浦宗勝を城代として置いた。 慶長5年(1600年)関ヶ原合戦の後に黒田長政が豊前国中津から入部すると廃城となった。 18:30博多駅付近のホテル到着後繁華街を散策し食事を済ませて就寝。 16日6:15レンタカーで出発、お城めぐり。 元寇防塁:建治2年(1276年)鎌倉幕府が九州の御家人に命じて築かれた。 文永11年(1274年)元によって侵攻された鎌倉幕府が、元の再侵攻に備え海岸線に石の防塁を築かせた。現在元寇防塁と呼ばれる防塁は当時は『石築地(いしついじ)』と呼ばれていた。 弘安4年(1281年)に再侵攻してきた元軍は防塁の築かれた博多湾からは上陸することができなかった。九州の御家人は各国ごとに割り当てられた区画があり、所領に応じて防塁を築く長さが決められていた。今宿の元寇防塁は今山の麓から長垂山の麓まで約2.2kmに渡って築かれ、豊前国の御家人が分担した。 柑子ヶ岳城:築城年代は定かではないが天文年間(1532年~1555年)頃に大友宗麟によって築かれたと云われる。豊後の大友氏が筑前の志摩地方の拠点として築いたのが柑子岳城で、大友氏一族の臼杵新助鎮続が志摩郡代を兼ねて柑子岳城に入った。永禄11年(1568年)鎮続が宝満山城の高橋鑑種を攻めて大宰府へ出陣した隙に、高祖山城主の原田隆種に攻められ柑子岳城は奪われたが、急遽引き返した鎮続は激戦の末に取り戻している。元亀2年(1571年)鎮続は城代を辞して豊後へ戻ると、後任として臼杵鎮氏が城代となった。元亀3年(1572年)臼杵鎮氏は今津毘沙門天を参拝した原田了栄を待ち伏せして襲撃したが失敗した。同年原田氏と臼杵鎮氏は池田河原で戦い、臼杵氏は敗れて鎮氏は泊城へ逃れる途中、平等寺で自刃した。その後、再び臼杵鎮続と木付鑑実が城代として柑子岳城へ入った。天正7年(1579年)原田氏の攻撃を受けた木付鑑実は柑子岳城に籠城して立花山城に援軍を求めたが、支えきれずに立花山城へ逃れ、柑子岳城は原田氏の手に落ちた。天正14年(1586年)豊臣秀吉の九州征伐の後、原田氏は加藤清正に従って肥後へ移り、柑子岳城は廃城となった 高祖山城:建長元年(1249年)に原田種継によって築かれた。 高祖山城は怡土城の一部を利用して築かれている。 原田氏の祖は古処山城秋月氏と同じく藤原純友の乱で名を馳せた大蔵春実であり、大蔵氏は漢の高祖の子孫で阿知使主の末裔と伝わる。 原田氏ははじめ大内氏、陶晴賢謀反後は毛利氏、ついで島津氏と結び反大友勢力としてこの地に根付いていた。 しかし、豊臣秀吉の九州征伐によって落城し廃城となった。 原田氏はその後、加藤清正や寺沢広高らに仕えたが最終的には保科正之に仕えた。 岩屋城:築城年代は定かではないが天文年間(1532年~1555年)に高橋鑑種によって築かれたと云われる。高橋鑑種は豊後の大友氏の庶流一萬田氏より筑前国高橋氏の家督を継いだ武将で、筑前国守護代として宝満山城と岩屋城の城督を務めた。高橋鑑種は武勇に優れた武将であったが、永禄年間(1558年~1570年)に大友氏を離反して毛利氏に付いた。しかし、永禄12年(1569年)毛利氏は山陰で尼子残党が挙兵したこともあって九州から撤退する。これにより後ろ盾を失った高橋鑑種は大友氏に降り、鑑種は高橋家の家督を剥奪された。替わって吉弘鑑理の子の高橋鎮種(のちの高橋紹運)が家督を継いだ。天正14年(1586年)薩摩の島津氏が北上してくると、岩屋城には高橋紹運、宝満山城には紹運の次男で筑紫広門の娘婿である高橋統増が筑紫氏の家臣とともに籠城した。 岩屋城では壮絶な戦いの末に、高橋紹運以下籠城兵数百がことごとく討死した。その後、秀吉の援軍が九州に来襲した報を受けた島津氏は城を秋月氏に預けたが、立花山城の立花統虎によって奪いかえされ、天正15年(1587年)破却された。 水城城:天智天皇3年(664年)に築かれた水城は大宰府の入口、大野城の南西の麓に築かれている。 水城のある場所は現在でも国道3号線、鹿児島本線、九州自動車道など九州の主要幹線が集まる要衝の地である。水城は基底部の幅80m最高13mの土塁、その北側に幅60m深さ4mの濠を設け、この濠へ流し込む水は南側の大宰府方面から木樋と呼ばれる水路を通して送られていた。 久留米城:築城年代は定かではないが永正年間(1504年~1521年)に在地の土豪によって築かれた篠原城がはじまりと云われる。本郭的な築城は天正15年(1587年)豊臣秀吉による九州征伐の後、筑後国御井・上妻・三潴三郡を七万五千石を与えられた小早川秀包によるものである。秀包は安芸の毛利元就の九男で、兄である小早川隆景の養子となって小早川秀包とも名乗っていたが、文禄3年(1594年)小早川隆景が豊臣秀吉の養子である木下秀俊(後の小早川秀秋)を養子に迎えたことにより別家をたてることになり、後に毛利姓に復姓している。慶長5年(1600年)関ヶ原合戦で毛利秀包は西軍に属して戦ったが敗れ、わずかな兵力しかいなかった久留米城は黒田孝高や鍋島直茂などに攻められ開城勧告に応じて開城された。毛利秀包は戦後改易となり、代わって三河国岡崎から田中吉政が筑後一国で柳河城に入封し、久留米城は支城として嫡子吉信が入った。元和6年(1620年)田中忠政が嫡子なく除封されると丹波国福知山から有馬豊氏が二十一万六千石で入封し以後明治に至る。 発心城:天正5年(1577年)草野家清によって築かれた。草野氏は筑後国の国司として勢力を持っており戦国期には大友氏に属していたが天正5年(1577年)大友氏が耳川合戦に敗北すると龍造寺氏に寝返り発心城を築き大友氏の攻撃に耐えた。天正15年(1587年)豊臣秀吉による九州征伐で清家は秀吉に誘殺され草野氏は滅びた。 猫尾城:築城年代は諸説あるが仁安2年(1167年)大蔵大輔源助能によって築かれた説が有力とされる。 助能は徳大寺家の請いによって瀬高荘を管理する為、大隅国根智目(根占)から筑後国上妻郡黒木郷に移り築城したという。この末裔が黒木氏を称し大友氏に属していたが、家永の時に龍造寺氏に従った為、天正12年(1584年)大友宗鱗によって攻められ落城、黒木氏は滅ぼされた。柳河城に田中吉政が入封すると家臣辻勘兵衛が城代となったが元和の一国一城令によって廃城となったという。 益富城:築城年代は定かではないが永享年間(1429年~1441年)初頭に大内盛見によって築かれたと云われる。その後は大内氏・大友氏などによって争奪戦が繰り広げられた。天正15年(1587年)豊臣秀吉の九州征伐では豊臣軍がわずか一日で岩石城を落とすと、益富城に籠もっていた秋月種実は益富城を破却して古処山城に逃れた。秀吉は付近の人々に命じてかがり火を焚き、さらに障子や戸板を集めて城を修復したように見せかけ、いわゆる「一夜城」を築いて古処山城に籠もる秋月父子を驚かせた。これを見た秋月種実は剃髪して家督を種長に譲り「楢柴」の茶器を秀吉に献上して降伏した。秀吉は村人に華文刺縫陣羽織と佩刀を与え永代貢税を免除したという。関ヶ原合戦後に筑前に入封した黒田長政は六端城の一つとして後藤又兵衛基次に一万六千石を与えて城主としたが、慶長11年(1606年)に基次が逐電すると、鷹取山城より母里太兵衛友信が移った。元和の一国一城令によって廃城となった。 18:00博多駅到着。 18:55博多駅新幹線のぞみで出発 21:17新大阪駅到達。 今回の旅行、九州福岡県に足を運び、比較的マイナーなお城11か所巡り散策してきました。 皆が城跡で位置を確認するのが一苦労しました。 次回残り10か所の福岡県のお城を巡る予定です。 |
            |
|||||||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第二百六十弾:沖縄本土お城・城下町巡り 2014年1月18-19日 按司(豪族)が地方を治めた時代から、琉球王国の成立まで、グスクと呼ばれる城が多く築かれ、首里城をはじめ、複数の史跡が琉球王国のグスク及び関連遺産群として世界遺産になった沖縄県に足を運び、18か所のグスク(今帰仁城、名護城・座喜味城、伊波城、安慶名城、勝連城、中城城、浦添城、伊祖城、首里城、大里城、大城、糸数城、知念城、垣花城、玉城、南山城、具志川城)を訪れました。 18日14:55関西国際空港出発 17:15那覇空港到達、レンタカーで名護方面に向かう。 18:30名護市内のホテル到着、近くの居酒屋で食事を済ませて就寝。 19日7:00レンタカーで出発、お城めぐりする。 今帰仁城:琉球に統一王朝が樹立(1429年)される直前の(北山、中山、南山)の北山を治めた国王の居城。1416年に北山が中山に滅ぼされた後には、琉球王府から派遣された北山監 守の居城となった。 名護城:桜(ヒカンザクラ)の名所として全国的に有名になった名護グシクは、名護市の歴史の中で重要な位置をしめる遺跡のひとつです。このグシクに、いつの頃から人が住みはじめたのか定かではありませんが、これまでに採集された中国製磁器類・類須恵器・高麗系瓦・土器などのさまざまな遺物からすると、少なくても今から約600年前(14世紀)のことだと考えられ、名護按司の居城として伝えられています。その頃は「グスク時代」と呼ばれ、奄美諸島から八重山諸島にいたるまで、人々は「グスク(グシク・スク)」と呼ばれる小高い丘の上に暮らしていたようです。また、それまでの数千年にわたる海や山の自然物の採集・狩獣による生活から、農業を中心にした生活に転換した時代でもあります。このグシクには、石垣をめぐらした防御の施設はありませんが、丘陵の尾根の緩やかな尾根を、一つは約3m、もう一つは約8mの深さに削り取った「二重の堀切」で敵の侵入を防いでいます。近年、沖縄島の数ヶ所の「グスク」で「堀切」が発見されましたが、特に、この「二重の堀切は」保存がよく注目を集めています。また、グシク内には、祝女殿内・根神屋・掟神屋・フスミ屋・神アサギなど、城区の拝所があり、大切な信仰の場となっています。 座喜味城:1420年代に有力な按司(アジ)であった護佐丸によって築かれた 城。北山が滅びた後も、その旧勢力見張る目的で造営され琉球王国成立の初期に国家権力の安定に重要な役割を果たした。 伊波城:石川市街地を北東側に見下ろす標高87mの丘陵に位置し、東西45m、南北52mの範囲に一重の石垣をめぐらせた単郭式の城で面積は3712㎡の比較的小型のグスクといえます。城壁は自然の地形を巧みにとりこみながら石垣をS字状にくねらせ、自然石をほとんど加工せずに積み上げていく野面積という技法で作られています。平成元年(1989年)の発掘調査によって城内の地表下50cmから数回の立替をしたと思われる無数の柱穴跡が発見され、掘っ立て柱建物の存在が確認されました。また大量の地元産土器や外国産土器中国産の青磁や白磁、三彩陶器・褐釉陶器・染付・南島産の須恵器なども出土しており、伊波按司の交易の広さと力を知る事ができます。また当時の人々の食べ残した貝殻や魚や猪の骨なども出土しています。これらの遺物は13世紀後半から15世紀のものが多く出土していますが、同時に貝塚時代の土器も多数出土しており、約二千八百年前の貝塚が伊波グスクを含めたこの全体にあったことがうかがわれ、この地域が古代から人々の重要な居住地であったことを改めて教えてくれます。 安慶名城:安慶名城は、14世紀の頃、安慶名大川按司によって築城されたと伝えられ一名大川城とも呼称されています。城跡は天願川畔の平地に屹立する琉球石灰岩の山全体を占め自然の断崖を巧みに利用して城壁とし、さらに山の柱腹部から野面積手法によって城壁を築き上げています。中心部は山頂大地であり、これを泡護するように外郭をめぐらした輪郭式の構造をもっています。内郭南側に開口する城門までは、東側下方から斜面に沿って石造りの階段がとりつけられていています。城門は自然の岩盤の裂け目を利用して、これを一部掘削し、さらに切石を組み合わせて、アーチ状に建造したものとなっています。城門の間隔は約1.0mと比較的狭くしてあり、内部中央付近の上下両脇には扉をとりつけるための敷居・鴨居穴が見られます。城内からは中国製の陶磁器やグスク時代の土器等が出土しています。 勝連城:琉球王国の王権が安定していく過程で、国王に最後まで抵抗した有力按司、阿麻和利の居城。阿麻和利は、1458年に国王の重臣で中城に居城した護佐丸を滅ぼし、さらに王権の奪取をめざして国王の居城である首里城を 攻めたが大敗して滅びた。これにより首里城を中心とする中山の王権は安定した。 中城城:琉球王国の王権が安定していく過程で、国王に最後まで抵抗した有力按司、阿麻和利の居城。阿麻和利は、1458年に国王の重臣で中城に居城した護佐丸を滅ぼし、さらに王権の奪取をめざして国王の居城である首里城を攻めたが大敗して滅びた。これにより首里城を中心とする中山の王権は安定した。 浦添城:首里城以前の中山王城として知られています。発掘調査から十四世紀頃の浦添グスクは、高麗系瓦ぶきの正殿を中心に、堀や石積み城壁で囲まれた巨大なグスクで、周辺には王陵・寺院・大きな池・有力者の屋敷・集落などがあったと考えられています。のちの王都首里の原形がここでできあがっていたようです。王都が首里に移された後、浦添グスクは荒廃しますが、一五二四年頃から一六〇九年の薩摩藩の侵攻までは浦添家の居館となりました。去る沖縄戦では、日米両軍の激しい戦闘により、戦前まで残っていた城壁も大部分が破壊されましたが、これまでの発掘調査によって、石積み城壁に基礎や、敷石遺構、建物跡などが良好に残っていることが確認されています。 伊祖城:伊祖部落の北東方に位置し、東西に延びる標高五〇㍍~七〇㍍の琉球石灰岩の丘陵上に築かれた城である。眼下に沖縄最古の貿易港牧港をはじめ宜野湾、北谷の海岸、読谷の残波岬、南西には慶良間諸島を望む雄大な景観を呈し、要害の地になっている。伝承によると伊祖城は英祖王(一二二九~一二九九年)の父祖代々の居城といわれ、英祖王もこの城で生まれたという。比較的規模の小さな城であるが、 丘陵を取り囲む形で石垣が巡らされている。石積みは切石積みと野面積みの両積石の技法が用いられ、東北向きの城門付近から本丸後(現伊祖神社付近)にかけては切石積み、南西側の断崖上の崖縁は野面積みとなっている。伊祖城跡の考古学的な調査はまだ実施されていないが、城内外からはグスク系土器や須恵器、中国陶器等が採取されている。 首里城:首里城は、三山時代は中山国王の居城であったが、1429年の琉球王国統一後は1879年に至るまで、琉球国王の居城として王国の政治・外交・文化の中心的役割を果たした。 大里城:大里村字西原の北側、標高約150メートルの琉球石灰岩の丘陵に形成されている。北側から西側にかけて急峻な崖状をなし、崖を背に堅固な城壁と天然の地形を巧みに利用したグスクである。この城跡は別称「島添大里グスク」とも呼ばれ、当主であった南山王・島添大里按司によって築城されたと「中山世鑑」の中に記されている。また尚巴志が最初に攻略した城でもあり、後に三山統一のきっかけともなり歴史的に重要なところである。城の規模は東西に長く延び、北側の最奥部の本丸跡を取り巻く形で南側、東側に広く連郭式の城壁が連なり、石積みは野面積みが大半である。1991年の村内遺跡分布調査の際試掘した結果、本丸跡から褐袖陶器、中国青磁、グスク土器、青銅製の飾り金具、丸玉、鉄釘などが出土し14世紀から16世紀の資料となっている。 大城:四面の崖に囲まれた城、初代琉球国王、大城真武按司が築城したと伝えられる。ウフグスクの別名を持つ。 糸数城:現在の糸数村落南側の断崖上に築かれた古城で、築城年代は不明ですが、玉城按司が二男を大城按司に、三男を糸数按司に任したという伝説があり、おそらく「三山分立時代」の初期14世紀前半の築城であろうと思われます。城壁は野面積みと切石積みと両方用いられ、切石積の部分が最も高く約6メートルで、この上に立つと太平洋と東支那海が眼下に望めます。構造的には比較的単純な城で、西側は断崖を利用し、東北東に城門をひらいています。城内の随所には遺物包含層がみられ、そこからは土器に混じって中国製品の陶磁器類が発見されます。また、「琉球国由来記」にも記載された「糸数城之殿」も城内の一角にあります。 知念城:知念按司の居城であると伝えられ、17世紀末に改築され、後に知念番所(役所)として使われていました。知念城跡の周りには、古屋敷跡、ノロ屋敷跡、古屋敷跡、知念按司墓、受水走水とともに稲作発祥の地があります。 垣花城:沖縄県の指定史跡になっているこの垣花城が作られた年代は明らかではありませんが、同じ南部にある糸数城などとと同じ14世紀前半頃ではないかと言われています。道路沿いにある少し広い所に車を停めて細い山道を登っていくと、すぐにいくつかの石垣が現れます。自然の形のままの琉球石灰岩を積み上げた野面積みという方法で、石をそれぞれうまく組み合わさるような形に加工した後に積み上げられる相方積みなどと比べると古い形式のものだという事が解ります。 玉城:別名アマツヅ城とも称され、築城年代や歴代の城主についてはさだかでない。「島尻郡誌」では、「アマミキヨが築いた城であるとの伝説があって、城主は、一の郭、二の郭、三の郭の三つの郭からなる階段状の山城で天然の要害の地に築かれている。城壁は一の郭のみよく原型をとどめていて、二の郭と三の郭の城壁は、戦後、米軍基地建設の骨材料として持ち去られ、現在根石がかろうじて残っているにすぎない。一の郭は、東北東に自然岩をくり抜いた城門を構え、城内には「天つぎあまつぎの御嶽」(神名「アガル御イベ、ツルベ御イベ」)が祀られている。 南山城:琉球三山分立時代(14世紀頃)に栄えたグスクです。南山は明国と交易を盛んに行い、財源を得たり、明文化を移入したりして城を中心に南山文化を築いていました。15世紀になって中山王尚巴志に滅ぼされるまでの朝貢回数は22回を数えます。一九八四年、発掘調査が市教育委員会によって行われ、中国製陶磁器やグスク系土器の他、備前焼きスリ鉢、鉄鏃、ガラス製勾玉などが出土しています。これらの遺物から南山城は13世紀頃に築かれ、14~15世紀前半が特に栄えていたことが分かりました。南山の東方には水量豊かな「カデンガー」、北方には源為朝と王の妹との逢引場所だと伝わる「和解森」(わだきなー)があります。 具志川城:断崖の付け根のところに城門があり、そこから一段下がって二の丸、さらに一段下がって本丸が海に突き出ています。石垣は珊瑚性石灰岩の野面積みですが、門の部分には、切石を用いた痕跡が残っています。城の規模は、長さが東西82~3メートル、南北の巾は二の丸で33メートル、本丸で16~7メートルです。二の丸には穴(俗に「火吹き穴」)があって海に通じています。久米島の伝説によれば、この城は久米島の具志川城主真金声(まかねくい)按司が伊敷索(いしきなわ)按司の二男真仁古樽(まにくたる)に攻められて落城し、島を脱出して本島に逃れ、故郷と同じ名の具志川城を築いたと言われています。その真偽は不明ですが双方の立地や規模、構造はよく似ています。 19日19:30那覇空港出発 21:15関西国際空港到達。 今回の旅行、沖縄本土に足を運び18か所のお城グスクを訪れました。 琉球王国のグスク及び関連遺産群として世界遺産に指定され、結構見るべきものがあり、琉球王国成立までの歴史を学ぶことができました。 一泊二日の旅でしたが18箇所のグスクをゆっくり巡ることができました。 |
                 |
|||||||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第二百四十五弾:中国圏城・城下町巡り 2013年9月21日ー9月23日 中国圏のお城・城下町(津山城、鳥取城、月山富田城、松江城、郡山城、萩城、津和野城、岩国城、広島城、福山城、岡山城、鬼ノ城、備中松山城)を巡りました。 21日13:00車で出発、近畿・中国道経由して津山インター下車 16:00津山城到達、散策。 1604年(慶長9)、初代藩主・森忠政が築いた津山城。現在は、本丸跡や高さ45mの石垣が残る。一帯は鶴山公園として整備。西日本有数の桜の名所として知られ、桜の名所・歴史公園・名城100選にも選ばれている津山城(鶴山公園)を散策する。 16:30鳥取に向かう。 17:45鳥取城到達、散策。 鳥取市北東に位置する久松山(標高263m)。鳥取城は、久松山の山頂と山麓に城郭が築かれ、山頂の戦国時代の山城(山上の丸)と、麓の近世城郭の平城(山下の丸)からなる城。山上の丸にはかって天守があったが、現在は天守台が残るだけで、遺構はほとんど失っている。 山下)の丸は久松公園として整備され、石垣が整然と並び、仁風閣・県立博物館などが建つ。 18:15米子に向かう。 20:15米子到達、米子駅前のホテル到着後繁華街を散策し食事を済ませて就寝。 22日6:00車で出発、 7:00月山富田城到達、散策。 標高184mの月山の地形を利用した山城跡(史跡)。主に尼子氏の居城として知られ、戦国時代には中国地方の中枢となる城であった。現在、往時を偲ぶ建物は一つも残っておらず、中腹の山中御殿から山頂の本丸にかけて石垣が保存されているのみ。当時の母屋と侍所が復元された花の壇、桜の名所である太鼓壇などがある月山富田城を訪れる。 7:30松江に向かう。 8:10松江城到達、散策。 慶長16年(1611)、堀尾吉晴[ほりおよしはる]が築城した。5層6階で高さ30m。桃山初期の城郭の特徴を残し、黒塗り下見板張りの外壁に簡素な美しさが漂う。各層に設けられた銃眼、地階の井戸など、実戦的な側面を色濃く残しているのが興味深い。展示物は武具甲冑の類や古文書など。最上階は望楼になっており、市街と宍道湖を一望できる松江城(千鳥城)[松江城山公園]を訪れる。 鬼城山の頂上付近に築かれた古代山城の遺跡。鬼(温羅)の砦だったという伝説も。西門と角楼が復元されている鬼ノ城を散策する。 |
             |
|||||||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第二百三十七弾:北海道南部(函館)東北北部(青森、秋田、岩手)城、城下町めぐり 2013年7月13ー15日 北海道南部、東北北部に足を運び、北海道北部函館(五稜郭、松前城)、東北北部青森秋田岩手(弘前城、根城、久保田城、角館城、盛岡城)を訪れました。 13日15:05関西国際空港出発 16:45函館空港到着、レンタカーで五稜郭に向かう。 北方防備の目的で造られた、日本初のフランス築城方式の星型要塞で国の特別史跡に指定されている。幕軍と官軍の最期の戦いである箱館戦争の舞台となったことでも有名。4月下旬から園内のソメイヨシノが一勢に咲き誇り、市民でにぎわいを見せる花見の名所でもある五稜郭を訪れる。 18:00レンタカーで木古内方面に向かう。 19:10木古内のホテル到着後繁華街を散策し食事を済ませて就寝。 14日6:00レンタカーで松前城に向かう。 7:00松前城到着。 1854年(安政元)に完成した、わが国最後の日本式城郭。復元された天守閣の内部は資料館になっており、松前藩の御用船・長者丸に関する資料や、往時の様子が描かれた松前屏風など、松前の歴史を物語る貴重な資料が多く展示されている。本丸御門(重要文化財)は必見の松前城を訪れる。 7:30レンタカーで函館に向かう。 9:05函館駅到着。 9:19函館駅特急スーパー白鳥で出発、青森に向かう。 11:19青森駅到着、レンタカーで弘前城に向かう。 12:35藩政時代、津軽家の居城であった弘前城は、現在、弘前公園として多くの市民や観光客に親しまれています。また、藩政時代から引き継がれてきた貴重な文化財が多数存在する史跡でもあります弘前城を訪れる。 13:20弘前城レンタカーで出発、秋田久保田城に向かう。 18:00久保田城到達、 秋田藩佐竹氏二十万石のお城・久保田城跡。春の桜とツツジ、初夏のハスは特に美しく街行く人々を楽しませてくれる。 また、二の丸から本丸にかけては十二代藩主義堯の像、茶室、大手水鉢、与次郎稲荷など歴史をしのばせる光景に出会えるはずの久保田城を散策する。 18:45秋田駅付近のホテル到着後、繁華街を散策し食事を済ませて就寝。 15日7:00レンタカーで出発、角館に向かう。 8:00角館到達 8:30角館レンタカーで出発、田沢湖に向かう。 9:30田沢湖到達。 瑠璃色の湖面とたつこ姫伝説に彩られる田沢湖は、周囲約20キロメートルのほぼ円形の湖です。水深423.4メートル、日本一の深さを誇っています。神秘的な雰囲気をたたえた湖は、四季折々に表情豊かで、訪れる人々を楽しませてくれます田沢湖を散策する。 |
         |
|||||||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第二百二十弾:九州圏城・城下町巡り 2013年1月12ー14日 九州に足を運び九州圏の16か所の城・城下町(小倉城、中津城、杵築城、府内城、臼杵城、岡城、飫肥城、鹿児島城、人吉城、熊本城、柳川城、佐賀城、吉野ケ里、秋月城、大野城、福岡城)を巡りました。 12日13:45新大阪新幹線のぞみで出発 15:56小倉到着、小倉城に歩いて向かう。 16:30 1602年(慶長7)細川忠興により築城されたが、戦乱により焼失した。現在の天守閣は1959年(昭和34)に復元されたもの。内部は、1500体の和紙人形を使った城下町のジオラマや、からくりシアターなどハイテクを駆使した資料館。隣に小倉城庭園がある小倉城散策。 17:30レンタカーで中津に向かう。 18:30中津駅前のホテル到着、繁華街を散策し食事を済ませて就寝。 13日7:00レンタカーで中津城に向かう。 1588年、黒田官兵衛孝高(如水)が、山国川河口の地に築城し、その後、細川家、小笠原家と続き、1717年から奥平家の居城となり、廃藩置県まで統治した。奥平家は産業振興、蘭学振興等を行い、前野良沢や福沢諭吉等を輩出する土壌となった。現在の城は、昭和39年に奥平家が中心となって中津市民の協力のもと、再建したもので、五層の天守閣と二層の櫓からなっている。内部は歴史資料館となっており、徳川家康拝領の白鳥鞘の鑓や歴代当主の甲冑や古文書等数多くの奥平家所蔵の品々を展示している中津城(奥平家歴史資料館)を訪れる。 杵築に向かう。 市街の東端、守江湾に臨んで立つ。1394年(応永元年)、木付氏4代頼直が築城、江戸時代は松平氏が城主となった。3層の天守閣は1970年(昭和45)に復元されたものだが、本丸跡、二の丸跡などは往時のまま。城内には鎧兜などが展示されている杵築城を訪れる。 大分に向かう。 1597年(慶長2)、石田三成の妹婿である福原直高が築いた荷揚城が始まり。その後、竹中重利が未完成だった城内に4層の天守閣や楼閣などを建築し、名を府内城と改めた。現在は城址公園になっており、戦後復興された櫓や城門、城内には大分文化会館や復元された廊下橋がある。桜の名所としても有名な府内城跡を訪れる。 竹田に向かう。 185(文治元)、緒方三郎惟宋が源義経を迎えるために築城した。四方を断崖絶壁の深い谷に囲まれた難攻不落の城として知られ、1586年(天正14)には4万人近い島津軍を1000人で守ったといわれる。名曲『荒城の月』のモデルとなった城でもある岡城阯を訪れる。 日南に向かう。 かつて伊東氏五万一千石の城下町として栄え、九州の小京都ともよばれる飫肥。碁盤の目状に整備された町中に、古い石垣や武家屋敷が見られる。観光の中心となるのは、伊東氏14代の居城・飫肥城。当時は、松尾の丸、中の城、本丸など9つの城を配した平山城だった。難攻不落の城としても知られ、1484年(文明16)から始まった島津氏との城争奪戦は、日本史上最長の84年間にも及んだ。城跡には、石垣や大手門前の石段などが1693年(元禄6)の改築時のまま残っている。1978年(昭和53)には現在の大手門、1979年(昭和54)には松尾の丸が、樹齢100年以上の飫肥杉を使って復元された飫肥城跡を訪れる。 鹿児島に向かう。 19:00鹿児島市内のホテル到着後市街地を散策し食事を済ませて就寝。 14日7:00レンタカーで出発、 慶長7年(1602)に、島津家18代家久が築いた平城です。「人をもって城と成す」という精神に基づいてつくった天守閣のない質素な屋形でした。天然の要塞で、その地形から鶴丸城と呼ばれるようになりました鹿児島城(鶴丸城)を訪れる。 人吉に向かう。 1199年(正治元)改修後、相良氏700年の居住だった城跡。かつては繊月城と呼ばれた。現在は石垣を残すのみだが、石垣の上に長塀、角櫓、多聞櫓を復元。多聞櫓の中には天保時代の絵図(複製)等が展示されている。高台に立つ城跡からは、球磨川や人吉の町並みを一望。隣接して、地下遺構を保存・展示する人吉城歴史館もある。日本百名城の一つの人吉城跡を訪れる。 熊本に向かう。 日本三名城のひとつといわれ、国の特別史跡に指定されている。加藤清正が1601年(慶長6)から7年の歳月をかけて築城。城郭は広さ約98万平方m、周囲5.3kmにも及ぶ。1877年(明治10)の西南戦争の際、大部分を焼失したが、石垣や宇土櫓(重要文化財)をはじめとする各櫓が往時を伝える。今の3層6階の天守閣は1960年(昭和35)に再建され、加藤清正や細川氏らの歴代藩主や西南戦争に関する史料や遺品を展示している。周辺には、県立美術館・熊本博物館・県伝統工芸館などの文化施設がある熊本城を訪れる。 柳川に向かう。 福岡県柳川市本城町にあった城で、江戸時代には柳川藩の藩庁が置かれた。本丸は国の史跡に指定されている。城は、蒲池治久により築城されたもので、並郭式に本丸と下段の二の丸を並べ、三の丸の代わりに中堀を廻らす広大な内郭と市街地を総構えとする平城であった。掘割に包まれた天然の要害をなし、城内、市街には無数の堀が縦横に交わり、今も柳川の堀川として現存する。蒲池氏の城主時代に「柳川三年肥後三月、肥前、筑前朝飯前」と大友氏陣中で歌われた戯歌にもあるように、攻略には3年かかるという難攻不落の城と謳われた柳川城を訪れる。 佐賀に向かう。 鍋島三十六万石の拠点だった佐賀城。周囲に幅70mもの濠を巡らし、5層の天守閣を誇る名城とされたが、明治初頭の佐賀の役でほとんどを焼失。今も残る鯱の門と続櫓は国指定の重要文化財だ。また本丸跡には 、幕末期の佐賀城本丸御殿の一部を忠実に再現した県立佐賀城本丸歴史館が立つ佐賀城を訪れる。 弥生時代最大規模の環壕集落跡を復元整備した公園。神埼市・吉野ケ里町にまたがり、多数の竪穴住居跡や高床倉庫跡、甕棺墓などが出土。集落の様子が、『魏志倭人伝』に記述された邪馬台国に似ているので話題になった。見学できるのは、北内郭・倉と市、北墳丘墓、出土品の展示室など。高さ10m以上の物見櫓、直径40~50cmの柱を使った巨大な主祭殿など、その規模に驚かされる野ケ里歴史公園を訪れる。 秋月に向かう。 1624(寛永元)年に黒田長政の三男長興が秋月五万石を与えられて築城した。現在は秋月中学校の敷地となり、大手門として使われた黒門や石垣、長屋門が当時の栄華を物語る。県指定史跡の秋月城址を訪れる。 博多に向かう。 大宰府の北の守りとして築かれた大野城跡。665年(天智4)、朝鮮から渡来した技術者の指導で約8kmにわたる土塁や石垣で山や谷を囲み、その中に建物を造ったとされる。現在、倉庫跡と思われる約70棟分の礎石が点在している大野城跡を訪れる。 初代福岡藩主・黒田長政が1601年(慶長6)から7年がかりで築城した福岡城は、大中小の天守台と47の櫓を配した壮大な平山城だった。現在は多門櫓(重要文化財)と大手門、潮見櫓などが当時の面影をとどめている。周辺は舞鶴公園として整備。高台には展望台が設置され、福岡タワーや福岡ドームまで見渡せる福岡城を訪れる。 18:00博多駅到達。 18:30博多駅新幹線のぞみで出発 20:58新大阪駅到達。 今回の旅行、九州に足を運び、時計回りで九州圏の16か所の城・城下町(小倉城、中津城、杵築城、府内城、臼杵城、岡城、飫肥城、鹿児島城、人吉城、熊本城、柳川城、佐賀城、吉野ケ里、秋月城、大野城、福岡城)を巡りました。 残念ながら時間の都合で長崎県の城は巡れず、次回持ち越しとなりました。 広い九州、二泊三日のドライブ城めぐり観光楽しめました。 尚走行距離は1056kmでした。 |
                |
|||||||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第二百十八弾:四国圏城・城下町巡り 2012年12月22ー24日 四国の9か所の城・城下町(徳島城・高知城・宇和島城・大洲城・松山城・湯築城・今治城・丸亀城・高松城を巡りました。 22日13:00車で出発、阪神淡路自動車道経由して徳島に向かう。 15:30徳島到達。 徳島駅北東に広がる公園で、明治維新まで阿波の領主・蜂須賀家の居城だった。往時の建物はないが、石垣と桃山様式の旧徳島城表御殿庭園がかつての面影を伝える。2006年1月、徳島城跡が国の史跡に指定された徳島中央公園を散策する。 徳島中央公園内の徳島城御殿跡にあり、徳島藩と藩主・蜂須賀家に関する美術工芸品や歴史資料を中心に収蔵・展示している博物館。現存する最古の和船、徳島藩御召鯨船(重要文化財)をはじめとする徳島藩水軍についての貴重な資料、徳島城御殿の精巧な復元模型や城下町の暮らしぶりなども常設展示する徳島市立徳島城博物館[徳島中央公園]を見学。 徳島中央公園の徳島市立徳島城博物館に隣接。茶人武将・上田宗箇が関ケ原合戦後に作庭したとされる回遊式の大名庭園。枯山水庭と築山泉水庭からなり、阿波特産の青石(緑色片岩)を大胆に用いた豪壮なつくりが特徴。全長10mを超える大石橋や池畔の石組みは鮮やかで一見の価値がある旧徳島城表御殿庭園[徳島中央公園]を訪れる。 16:30高松高知自動車道経由して高知に向かう。 18:30高知到着、市街地のホテル到着後繁華街を散策し食事を済ませて就寝。 23日7:00車で高知城に向かう。 三層6階の天守閣をもつ平山城。初代土佐藩主・山内一豊が1601年(慶長6)に築城を開始。1611年(慶長16)、二代藩主・忠義の時に完成した。その後焼失したが、1753年(宝暦3)に再建。天守閣をはじめ、詰門[つめもん]や東西の多聞櫓、黒鉄門は、いずれも重要文化財に指定されている。天守閣のある本丸は、全国で唯一天守・御殿などの建造物がセットで残る。追手門そばの板垣退助像や山内一豊像、その妻の千代像も見逃せない高知城を散策する。 8:30宇和島に向かう。 10:30宇和島到達。 リアス式海岸の続く海に面し、四国百名山に数えられる1000m級の山々を背に、海抜80mの緑深い城山に白亜の天守がそびえる姿から鶴島城の別称を持つ優美な城。1601年(慶長6)に藤堂高虎が築城し、1615年以降伊達家9代の居城だった。10haの城山は国史跡、天守は現存12天守の1つで国重要文化財に指定されている。400種の草木が繁茂する照葉の森に、苔むす石垣が佇む幽玄の美が楽しめる宇和島城を散策する。 宇和島の中心部の緑深い城山の頂にそびえる。国の重要文化財で現存12天守の一つ宇和島城天守を訪れる。 大洲に向かう。 慶長年間(1596~1615)の築城とされ、後に大洲藩主・加藤氏が13代居城した。町の西の高台にあり、天守閣は1888年(明治21)に取り壊されたが、高欄櫓、台所櫓が残る。市内の芋綿櫓、南隅櫓とともに重要文化財に指定する大洲城を訪れる。 松山に向かう。 標高132mの勝山山頂に立つ松山城(史跡)は、大天守に複数の小天守が連結する連立式天守をもつ平山城。1627年(寛永4)、加藤嘉明によって完成。乾櫓、野原櫓、隠門など築城当時から残るものはすべて重要文化財に指定されている。1854年(安政元)に再建された天守(重要文化財)からは、石鎚山から伊予灘までが一望。小天守内部には松山城の歴史を展示している松山城を散策する。 湯築城を訪れる。二重の掘と土塁を巡らせ、その中に居住空間を持つ先駆的な「平山城」の形態をなす。中世伊予国(現在の愛媛県)の守護河野氏の居城として、約二五〇年間存続しました。南北朝時代の初め頃(十四世紀前半)、河野通盛によって築かれたといわれています。通盛の祖先には、十二世紀末の源平合戦の際、水軍を率いて活躍した通信。十三世紀後半の蒙古襲来の際活躍した通有がいます。通盛は、それまでの河野氏の拠点であった風早郡河野郷(現在の北條市)からこの道後の地に移りました。河野氏は、その後讃岐から攻め入った細川氏との戦いに敗れ、湯築城は一時占拠されましたが、守護職とともに湯築城を奪い返しました。しかし、近隣諸国から幾度となく攻撃を受けたり、お家騒動(惣領職の継承をめぐる分裂)や内紛(家臣の反乱)を繰り返し、その地位は決して安泰ではありませんでした。天正十三年(1585年)、全国統一を目指す羽柴(豊臣)秀吉の命を受けた小早川隆景に湯築城は包囲され、河野通直は降伏し、やがて湯築城は廃城となりました。 今治に向かう。 1602年(慶長7)藤堂高虎が着工し、2年後に完成。海水を引き入れた三重の堀をもつ海岸平城は、全国でも珍しい。当時のまま残るのは城塁や内堀だけだが、明治維新前までの規模は現在の10倍と記録に残る。5層6階建ての天守閣は、1980年(昭和55)に市制60周年を記念し再建。2~5階は展示室で、武具・甲冑・刀剣など約250点を常設展示。御金櫓、山里櫓は美術品の展示館になっている。2007年(平成19)には鉄御門を再建。築城当時の雄姿を再現している今治城を訪れる。 丸亀に向かう。 丸亀市内のホテル到着後近くの居酒屋で食事を済ませて就寝。 24日8:30車で出発。 亀山に築かれた平山城。内堀から天守閣へ幾重にも積み上げられた石垣は、扇の勾配と呼ばれる美しい曲線を描く。現在の城の大部分は、1641年(寛永18)に丸亀藩主になった山崎家治[やまざきいえはる]が造営。その後、明治維新まで城主だった京極家に受け継がれた。天守、大手一の門は国指定文化財、二の門と東西の土塀は重要文化財。天守は全国に現存する12の木造天守のうちの一つの丸亀城を訪れる。 高松に向かう。 潮の香りが漂っている。城の北側は海に面し、残り三方の堀には海水を引き入れた日本三大水城の一つ。堀が海とつながっているため、潮の干満による水位調整のための水門があるのも、海城ならではの遺構。高松城の天守台にかつて「南蛮造り」と呼ばれる三層四階の天守があった。高松市ではこの天守の復元を計画している。松平氏によって東の丸が増築された時に築かれた三層の月見櫓・続櫓・水手門・渡櫓が高松港のすぐ側に残っている。 かつては石垣が海の波に洗われていた。今は太鼓櫓の跡に均整のとれた三層三階の艮櫓が移築されている。 東の丸の石垣が、県民ホールから歴史博物館にかけて残っていて、ここに艮櫓の櫓台も残っていた高松城(玉藻公園)を訪れる。 帰路に向かう。 今回の旅行、中国圏の城めぐりを予定していましたが、西高東低の冬型の気圧配置、日本海沿いは雪とのことで急遽、四国圏の城めぐりに変更いたしました。 寒波厳しく、寒さと強風に耐え凌ぎながら9つの城と城下町を巡りました。 四国には現存する天守閣のある城が多く歴史を感じさせられました。 歴史学習できた四国の城・城下町巡りドライブ観光でした。 |
               |
|||||||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第二百十三弾:関東圏の城と城下町巡り 2012年11月3ー4日 関東圏の城と城下町(駿府城・小田原城・江戸城・佐倉城・川越城下・甲府城・松本城・上田城・松代城下・高田城)を巡りました。 3日6:00車で第二京阪新名神・東名自動車道経由して静岡インター下車 家康の居城として造られた、駿府城跡を整備した市民公園。堀に囲まれた広い園内には、家康の銅像や家康の手植えといわれるミカンの木などがあり、城の面影を伝える東御門、木造2層3階建ての巽櫓も復元(内部見学可)。4つの回遊式庭園が美しい紅葉山庭園は、県内各所の名勝をイメージしたものだ。庭園に面した立礼席では、静岡茶も楽しめる駿府公園を訪れる。 小田原方面に向かう。 小田原城址公園にあり、1960年(昭和35)に復興。3層4階建ての内部には、鎧や刀剣、小田原提灯などが並ぶ展示室と、三浦半島などを望む展望室がある小田原城天守閣[小田原城址公園]を訪れる。 東京方面に向かう。 皇居東御苑の東側にある。旧江戸城の正門として、1620年(元和6)に築造されたが、明暦の大火で類焼。1659年(万治元)に再建された。しかしその後、地震などで修理を繰り返し、1967年(昭和42)に復元工事が完成した大手門[皇居東御苑]を訪れる。 皇居東御苑と北の丸公園を結ぶ北桔橋門の近くにある。1607年(慶長12)に完成。44m四方、高さ18mの石積みに金色のシャチをいただく5層の天守がそびえていたという。1657年(明暦3)の大火で焼失したまま、現在は基礎の石積みが残っている天守閣跡[皇居東御苑]を訪れる。 佐倉方面に向かう。 江戸時代に堀田氏の居城であった佐倉城の城跡一帯を整備した公園。城の建物は明治初期にすべて取り壊されたが、土塁や空堀跡などが残り、往時の面影をとどめている。樹木の茂る園内には芝生広場や散策路、姥ケ池が配され、桜や初夏の花菖蒲が美しい佐倉城址公園を訪れる。 川越方面に向かう。 長禄元年(1457)に、上杉持朝の命により、家臣の太田道真・道灌親子が築いたといわれています。 江戸時代には江戸の北の守りとして重要視され、代々幕府の重臣が城主となっていました。現存する建物は嘉永元年(1848)に建てられたもので、本丸御殿の一部として玄関・大広間・家老詰所が残り、川越藩17万石の風格をしのばせています川越城を訪れる。 甲府方面に向かう。 甲府駅付近のホテル到着後繁華街を散策し食事を済ませて就寝。 4日6:00車で出発。 武田氏滅亡後、豊臣秀吉の命により築城されました。関東の徳川家康に対抗するための重要な戦略拠点として築かれたといわれ、徳川体制になってからは西側への備えとしての重要性を保ち続けたといわれています。かつては20haほどの広大な城郭でした。現在は、城跡の一部が「舞鶴城公園」「甲府市歴史公園」として開放されています甲府城を訪れる。 中央自動車道を経由して松本方面に向かう。 北アルプスや美ケ原高原の山並みを背景に立つ松本市のシンボル。現存する天守としては、犬山城、彦根城、姫路城とともに国宝に指定されている名城。石川数正、康長父子が1593年(文禄2)ころ建てたと推定され、戦闘に有利な山城が多く築かれた戦国時代の中で、松本城は異色の平城。敵の侵入を防ぐ石落や鉄砲狭間などが見どころ。中町通りの北を流れる女鳥羽[めとば]川は、侍町と町人町を分けた川で、堀の役割も果たした。4月中旬は桜に包まれ、5月上旬には月見櫓前にボタンが咲く松本城を訪れる。 長野方面に向かう。 天正11年(1583)に真田昌幸が築城した実戦用の堅固な平城で知られる。関ケ原の合戦後、徳川方に接収され、本丸の櫓などが破壊されたが、その後、上田に移封になった仙石忠政によって再建。近世後期には松平氏の居城となった。現在は上田城跡公園として整備され、隅櫓と石垣などが往時の面影を伝える上田城を訪れる。 戦国時代、武田信玄によって築城されたといわれる城。1622(元和8)年に真田信之が上田から移封されて以来、10代約250年にわたって真田氏が城主をつとめた。明治の廃城後、建物は取り壊されたが、櫓門や橋などが復元され一般公開されている松代城を訪れる。 高田方面に向かう。 松平忠輝が築いた高田城跡を利用した都市公園。4月中旬は桜、8月上旬には外堀一面にハスの花が咲く。園内の高田城三重櫓、石垣ではなく土塁を巡らせた外堀などは、高田城図間尺などに基づいて再現。三重櫓内の展示室には高田城略年譜、甲冑や陣笠などを展示している高田公園(高田城跡)を訪れる。 北陸自動車道を経由して帰路に向かう。 今回の旅行、車で関東に向かい1600km走行し関東圏の城と城下町(駿府城・小田原城・江戸城・佐倉城・川越城下・甲府城・松本城・上田城・松代城下・高田城)を巡りました。 何回か訪れた城と城下町ですが江戸城は初めて、大阪城に匹敵する広大な敷地、大きな天守台が印象で、、天守閣の再建を願いますが隣接地は皇居、天守閣が完成すれば展望台から皇居が丸見え、残念ながら再建は不可能でしょうね。 |
           |
|||||||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第二百九弾:中部圏城と城下町巡り 2012年10月6ー8日 中部圏の18城と城下町(大垣城、岐阜城、犬山城、掛川城、浜松城、吉田城、岡崎城、名古屋城、郡上八幡城、高山城、富山城、高岡城、金沢城、大聖寺城、丸岡譲、福井城、一乗谷城、越前大野城)を訪れました。 6日12:30車で第二京阪京滋バイパス名神を経由して大垣に向かう。 1535年(天文4)に築城。関ケ原合戦では西軍の本拠地となった。4層4階建て総塗りごめ様式の優美な天守閣からは大垣市内を一望できる大垣城を訪れる。 岐阜の向う。 戦国時代、斎藤道三の居城だった稲葉山城が、織田信長の占領によって岐阜城と名を変えたのは1567年(永禄10)。その後、関ケ原の合戦の前哨戦で落城。金華山に現在立つ岐阜城は、1956年(昭和31)に再建されたものだ。三層四階構造で、内部には甲冑や文献を展示。最上階は展望台になっている岐阜城[金華山]を訪れる。 犬山に向かう。 1537年(天文6)、織田信康により築城。天守閣の美しさは荻生徂徠が李白の詩を引用し、「白帝城」と讃えたほど。展望台からは濃尾平野を一望できる国宝・犬山城を訪れる。 東名高速を経由して掛川に向かう。 掛川駅の南のホテルに到着後繁華街を散策し食事を済ませて就寝。 7日7:00車で出発。 1994年、全国初の木造天守閣として復元された3層4階建ての城。戦国時代に今川氏の家臣・朝比奈泰熈によって築城され、天守閣は山内一豊の時代に築かれた。城内では鎧兜や装身具などを展示。最上階の天守台からは周囲が一望できる掛川城(雲霧城)を訪れる。 浜松に向かう。 1570年(元亀元)、徳川家康が遠州攻略の拠点に築城。徳川の治世はここから始まったともいえ、その後代々の譜代大名が居城としたことから別名「出世城」とも呼ばれる。城跡は浜松城公園として整備。築城当時の姿を残す石垣の上には、1958年(昭和33)再建の天守閣がそびえる。天守閣内部では鎧や刀剣などを展示。最上階の展望回廊は浜松市内が一望できるビュースポット。桜の名所でもある浜松城を訪れる。 豊橋に向かう。 吉田城は、永正2年に牧野成時(古白)によって築かれ今橋城と称した。 その後松平氏と戸田氏の争奪戦が続くが、天文15年に今川義元が攻略して城代を置いた。永禄3年、桶狭間で今川義元が織田信長に討たれると、徳川家康は永禄7年には吉田城を攻略して、酒井忠次を城主にしている。今は豊橋公園となっている。 本の丸には復興隅櫓(鉄櫓)が建ち、この城のシンボルとなっている吉田城を訪れる。 岡崎に向かう。 岡崎公園内にある、徳川家康出生の城として知られる名城。1531年(亨禄4)に家康の祖父・松平清康が入城して以来岡崎城と称されるようになり、家康の天下統一の拠点となった。明治時代に取り壊された天守閣は1959年(昭和34)に復元され、歴史資料館になっている岡崎城[岡崎公園]を訪れる。 名古屋に向かう。 金鯱で有名な城。1612年(慶長17)、徳川家康が築城。天守閣と本丸御殿が隅櫓・多聞櫓で囲まれた豪壮堅固な造りで、尾張徳川家約六十二万石として栄えた。1945年(昭和20)の空襲で大部分が焼失し、1959年(昭和34)に天守閣と正門を再建。三つの隅櫓(重要文化財)と表二之門(重要文化財)・石垣は、ほぼ原型を残している。再建された天守閣は、1~5階が旧本丸御殿の障壁画などを観賞できる展示室で、最上階は展望室がある名古屋城を訪れる。 郡上八幡に向かう。 標高354mの八幡山山頂に立つ、4層5階の城。1559年(永禄2)、遠藤盛数により築城。現在の城は、1933年(昭和8)に再建されたものだ。木造再建城としては、全国で最も古い。天守閣からは郡上八幡の町並みを一望。貴重な収蔵品も展示されている郡上八幡城を訪れる。 高山に向かう。 1588年(天正16)、金森長近がこの地に築城して城下町を開き、107年間にわたって支配。6代目の頼時が出羽国(現在の山形県)に転封となり、1695年(元禄8)に取り壊された。当時全国でも有数の規模を誇る山城だったが、今は2万平方mの敷地に三の丸堀、二の丸石垣、天守閣跡が昔の面影を残している。園内の広場からは市街の眺め、金竜ケ丘からは乗鞍岳など北アルプスの眺望がすばらしい。春は桜、秋は紅葉の名所で、遊歩道を散歩しながら森林浴やバードウォッチングも楽しめる高山城跡を訪れる。 東海北陸道を経由して富山に向かう。 富山駅付近のホテルに到着後繁華街を散策し食事を済ませて就寝。 8日6:00車で出発。 佐々成政、そして富山前田家230年間の居城だった富山の必見スポット。戦国時代には佐々成政の居城であり、江戸時代には富山前田家の居城として、富山藩政の中心であった。この城跡が「富山城址公園」として整備され、市民の憩いの場となっています富山城を訪れる。 高岡に向かう。 第2代藩主前田利長の隠居城で日本100名城に選ばれています。城は、高岡市のほぼ中心部にあり、その総面積は約21万㎡。前田支藩の一つである富山前田家居城(10万石)の富山城の22万㎡に匹敵する大きさの高岡城を訪れる。 金沢に向かう。 天文15(1546)年、本願寺による金沢御堂の創建に始まります。天正11(1583)年に前田利家が入城し、本格的な城づくりが始まり、加賀藩前田家百万石の居城として発展しました。 明治以後は陸軍の拠点として、終戦から平成7(1995)年までは金沢大学のキャンパスとして利用され、金沢大学の移転後、平成13(2001)年9月に「金沢城公園」として、金沢御堂の創建から450余年を経て、一般に開放されました金沢城を訪れる。 |
       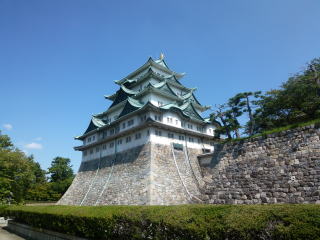        |
|||||||||||||
| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第二百六弾:近畿圏城と城下町巡り 2012年9月15ー17日 近畿圏の22城と城下町(和歌山城、岸和田城、大阪城、明石城、姫路城、龍野城、赤穂城、出石城、田辺城、小浜城、福知山城、篠山城、伏見城、二条城、彦根城、長浜城、桑名城、松坂城、津城、亀山城、上野城、郡山城)を訪れました。 15日12:30車で和歌山に向かう。 1585年(天正13)、豊臣秀吉が藤堂高虎に命じて築城し、弟の秀長に与えたのが始まり。桑山重晴、浅野幸長の時代を経て1619年(元和5)、徳川家康の第10子・頼宣が入城。明治の廃藩置県まで徳川御三家の一つ、紀州徳川家の居城として使われた。岡口門(重要文化財)と特産の青石を使った野面積の石垣などは当時のもの。戦後復元された天守閣は鬼瓦や鎧の展示室を備え、紀ノ川の眺めがすばらしい。城内西の丸の紅葉渓庭園(名勝)は、紀州藩祖徳川頼宣が西之丸御殿に築造したもので、戦後復元した池泉観賞式庭園の和歌山城を訪れる。 大阪に戻る。 1334年(建武元)、当時の代表的武将であった楠木正成が、一族の和田高家に、岸と呼ばれていたこの地に築城させたのが始まり。和泉地方の岸の和田氏が転じて「岸和田」の地名となったという。その後、1585年(天正13)に小出秀政が入城し天守閣を築造。徳川政権下では1640年(寛永17)に岡部家が入封、13代にわたり支配したが、1827年(文政10)に五層の天守閣が落雷で焼失。1954年(昭和29)、鉄筋コンクリート造りの三層の天守閣が、1969年(昭和44)に城壁と櫓が再建された岸和田城を訪れる。 1583年(天正11)、石山本願寺の跡に豊臣秀吉が天下統一の拠点として築城を始めたのが大坂城。大坂夏の陣で落城し、徳川政権下で再築されたが落雷で天守閣を焼失、1931年(昭和6)築の現在の天守閣は3代目だ。内部は歴史資料や、ジオラマ、ビデオなどでさまざまな角度から大阪城を楽しめる。巨石を組み込んだ壮大な石垣、大手門やいくつもの櫓など、城内のみどころは多い大阪城天守閣[大阪城公園]を訪れる。 16日6:00車で出発、明石に向かう。 1619年(元和5)、徳川家康の曾孫にあたる小笠原忠真[おがさわらたださね]が築城。明治維新で大半は取り壊されたが、白亜の巽櫓(重要文化財)と坤櫓(重要文化財)が残されている。2000年春には両櫓を結ぶ土塀を100年ぶりに復元、美しい姿が蘇った。一帯は桜や紅葉も美しく、野球場やテニスコートなどもあり、市民の憩いの場として親しまれている明石城[明石公園]を訪れる。 姫路に向かう。 1993年(平成5)、法隆寺とともに日本初の世界文化遺産に登録された、日本を代表する名城。白鷺が羽を広げて舞っているように見えることから、白鷺城の別名がある。羽柴秀吉が中国毛利攻めの拠点として築いた3層の城を、関ケ原の合戦後に入城した池田輝政が1601年(慶長6)から8年の歳月を費やし改築。5層7階の大天守と3つの小天守を渡櫓で結んだ独特の連立式天守閣(国宝)は、石垣や白漆喰総塗籠造の外観とともによく保存されている。櫓・門など、城内74棟の建物が重要文化財。美しい造形の中に、敵の侵入を防ぎ攪乱する仕組みを潜ませているのも興味深い姫路城(白鷺城)を訪れる。 龍野に向かう。 町を見下ろす鶏籠山の麓に立つ。1672年(寛文12)に脇坂安政が築城した平城を復元した本丸御殿、隅櫓、多聞櫓、埋門が往時を偲ばせる。優美な大屋根を持つ本丸御殿は一般的な城のイメージと違って、入母屋造、瓦葺の平屋建ての造りが特徴で内部の見学もできる。鶏籠山山頂に室町末期の山城跡が残り、かつてそちらを朝霧城、麓の城を霞城と呼んだ龍野城(霞城)を訪れる。 赤穂に向かう。 常陸国笠間から入封した浅野長直が13年の歳月を費やし、1661年(寛文元)に完成。播磨灘に面して築かれた海城(平城)で、天守台はあるが天守閣はない。縄張は、本丸を中心に二之丸が同心円状に囲む輪郭式だが、三之丸が二之丸の北に張り出した変形輪郭式。浅野家断絶後、城は永井家、森家に引き継がれた。明治の廃藩置県後に取り壊されたが、1955年(昭和30)に大手門の一部と大手隅櫓が復元。大手門から入った道筋に大石良雄宅跡があるのは、当時藩邸や家老、藩重臣の屋敷を城内に置いたための赤穂城跡を訪れる。 出石に向かう。 1604年(慶長9)、有子山の麓に小出吉英が築いた平山城の城跡。江戸時代には出石藩の本城として約260年間利用された。現在は本丸跡に隅櫓が復元されている。その横に延びる157段の石段には37基の鳥居が並ぶ。ここは城山稲荷と呼ばれ、信仰の対象としても親しまれてきた。春には桜の名所として多くの人が訪れる出石城跡を訪れる。 出石皿そばで有名な町には、道が碁盤の目状になっており、但馬の小京都ともよばれる。出石城跡や時を告げた辰鼓楼など、風情ある町並みが今も残る出石城下町を訪れる。 舞鶴に向かう。 天正6年、織田信長の命により細川藤孝と明智光秀は丹後に侵攻し、建部山城主一色義通を滅ぼして丹後を平定した。 その功により細川藤孝は丹後一国12万石の領主となった。天正7年、藤孝は宮津城を本城として築き、同時に加佐郡の押さえとして田辺城を築城した。 天正10年に本能寺の変の際、藤孝は隠居して田辺城を居城とした。慶長5年、関ヶ原の戦功により細川藤孝・忠興父子は、豊前中津に移り、替わって京極高知が信州飯田から123,200石で入封する。 元和8年、高知が死去後、嫡男高広は宮津城に移り、次男高三が加佐郡35,000石を分知され、田辺城に居城した。寛文8年、京極高盛が但馬豊岡に移り、牧野親成が35,000石で入封、以後牧野氏が代々居城して明治に至った田辺城を訪れる。 小浜に向かう。 1601年(慶長6)、京極高次が築城に着手し、小浜藩祖・酒井忠勝が1636年(寛永13)に完成させた。以後は小浜藩の居城となったが、1871年(明治4)の出火のため、現在は本丸や天守閣の石塁だけが残る。本丸跡には小浜神社が立つ小浜城を訪れる。 福知山に向かう。 明智光秀が織田信長の命を受けて、1579年(天正7)に築城した。現在の天守閣は1985年(昭和61)に再建されたもので、内部は明智光秀や福知山城、城下町に関する資料を展示する郷土資料館になっている。野面積みの石垣は、築城当時のまま。近隣寺院からかき集めた五輪塔なども転用されている福知山城を訪れる。 丹波篠山に向かう。 1609年(慶長14)に徳川家康が築城の名手・藤堂高虎を縄張りとし、わずか6カ月で築かせた平山城。明治の廃城令で建物の大半が取り壊されたが、城跡二の丸に本格木造建築の大書院が復元され、狩野派の屏風絵を転用した障壁画などを展示。雄大な石垣を囲む外濠の周辺は桜の名所でもある篠山城跡を訪れる。 17日6:00車で伏見に向かう。 そもそも伏見という地は大阪と京都の中間に位置していて、豊臣秀吉が秀次に関白の位と聚楽第を譲ったあとの隠居所として屋敷を作ったそうです。その後、豊臣秀頼が生まれて、彼に大坂城をあげることにしたので、秀吉自身の居城としてこの伏見屋敷を改修して城を作ったと。この頃の伏見城を「指月山伏見城」と呼びます。大阪と京都の両方を支配するのに好都合な立地だった伏見城を訪れる。 京都に向かう。 関ケ原の戦いで勝利した徳川家康が、上洛の際の宿泊所として1603年(慶長8)に築城。後に3代将軍家光が大改修し、現在のような規模となった。堀を巡らし石垣に囲まれた広大な城内は、二の丸御殿(国宝)、本丸御殿(重要文化財)、二の丸庭園(特別名勝)などからなり、豪壮な外観に反して内部はきらびやかさに満ちている。二の丸御殿の障壁画(重要文化財)は狩野派の作で、松鷹図などがよく知られる。本丸御殿は京都御苑内にあった旧桂宮家の御殿を移築した元離宮二条城を訪れる。 彦根に向かう。 彦根藩・井伊家30万石の居城。1622年(元和8)、井伊直継・直孝によって、約20年の歳月をかけ完成。琵琶湖から直接引き込んだ堀をめぐらし、小高い山に立つ。3重3層の天守(国宝)を中心に、長浜城から移築された天秤櫓(重要文化財)、城内の合図のための太鼓が置かれていた太鼓門櫓(重要文化財)、近江八景を模した庭園の玄宮園など見どころが数多く残る。天守の最上層からは琵琶湖が一望の下に見渡せる彦根城を訪れる。 長浜に向かう。 1574年(天正2)、豊臣秀吉が初めて一国一城の主となった城。大坂の陣の後に廃城となったが、1983年(昭和58)に天守閣を再興。現在は長浜市長浜城歴史博物館として公開されている。館内では琵琶湖の湖底遺跡などから発見された縄文土器や、「賤ケ岳合戦図屏風」などの資料を交えて湖北地方の歴史を紹介。周辺は桜が名所の豊[ほう]公園として整備されている長浜市長浜城歴史博物館を訪れる。 桑名に向かう。 1601年(慶長6)、本多忠勝が城主になり、城下町割とともに城郭の拡張整備を行った。城郭は現存しないが、城跡は九華公園として整備され、桜やツツジ、菖蒲などが美しく、市民の憩いの場として親しまれている桑名城跡・九華公園を訪れる。 松坂に向かう。 戦国武将、蒲生氏郷によって1588年(天正16)に築かれた。かつては本丸とニノ丸に石垣を築き、3層の天守閣に敵見、金の間、月見などの櫓が配されていた堅城だった。今はそそり立つ石垣を残し、公園として整備されている。桜、イチョウなどが美しく、市民の憩いの場の松阪城跡を訪れる。 津に向かう。 1580年(天正8)に織田信長の弟・信包によって築かれ、藤堂高虎の入城によって大改修が行われ、明治維新まで藤堂氏の居城となった。現在は堀や櫓などが残り、庭園も造られている津城跡を訪れる。 亀山に向かう。 1590年(天正18)に岡本良勝が築いた城。かつては5つの曲輪があり、櫓や門が立ち並んでいた。現在は石垣の上に多門櫓を残すのみだが、美しい石垣に往時の姿が偲ばれる。多門櫓は県の史跡に指定されている。近年、城内門の1つであった石坂門の石垣が発掘され、亀山市歴史博物館の玄関前に一部を移築・復元されている亀山城跡を訪れる。 伊賀上野に向かう。 1585年(天正13)、筒井定次が築城。関ケ原の合戦以降、築城の名手である藤堂高虎が大改修を行ったが、天守閣は竣工直前の1612年(慶長17)に暴風雨で倒壊した。現在の城は1935年(昭和10)の再建で、城跡は国の史跡の指定を受けている。日本一の高さを誇る石垣は高虎時代のものの伊賀上野城を訪れる。 郡山に向かう。 大和郡山のシンボルとして親しまれる。1580年(天正8)に筒井順慶が築城。豊臣秀長時代の大増築に際し紀州根来寺の大門を城門として移築、平城京羅城門の礎石や石仏、墓石までかき集めて豪壮な石垣が築かれた。今も天守台の後ろで逆さまに積まれた地蔵が見られる。江戸時代には、水野、松平、本多と城主が替わり、1724年(享保9)以降は柳沢藩十五万石の城下町として栄えた。明治時代に城郭は壊されたが内堀と外堀の一部が残り、追手門、東隅櫓、多聞櫓などが復元されている。桜の季節にはお城祭りで賑わう郡山城跡を訪れる。 今回の旅行、韓国釜山観光を予定していましたが台風の影響で断念、急遽、近畿圏の城と城下町22か所を訪れました。 何回か訪れたことのある近畿圏の城と城下町、城と城下町の専門雑誌を読みながら散策し、歴史学習できました。 |
                  |
|||||||||||||